[32]お茶室の恋~イケメン茶道男子の正座姿に魅せられて~
 タイトル:お茶室の恋~イケメン茶道男子の正座姿に魅せられて~
タイトル:お茶室の恋~イケメン茶道男子の正座姿に魅せられて~
分類:電子書籍
発売日:2018/03/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:88
定価:200円+税
著者:江原 里奈
イラスト:江原 里奈
内容
海外大好きOLの石田優香は、会社の先輩が通う茶道教室のお茶会に出席し、綾小路君という着物が似合うイケメンに一目惚れ!
それをきっかけに茶道を始めたが、足がすぐ痺れて失敗ばかりしていた。
そんな時、憧れの綾小路君から正座特訓法を教えてもらい、二人の距離は少しずつ縮まっていくが……。
お茶室を舞台にした外資系OLとイケメン茶道男子のピュアなラブストーリー。
生まれも育ちも正反対。そんな二人の恋の行方は……?
販売サイト
販売は終了しました。

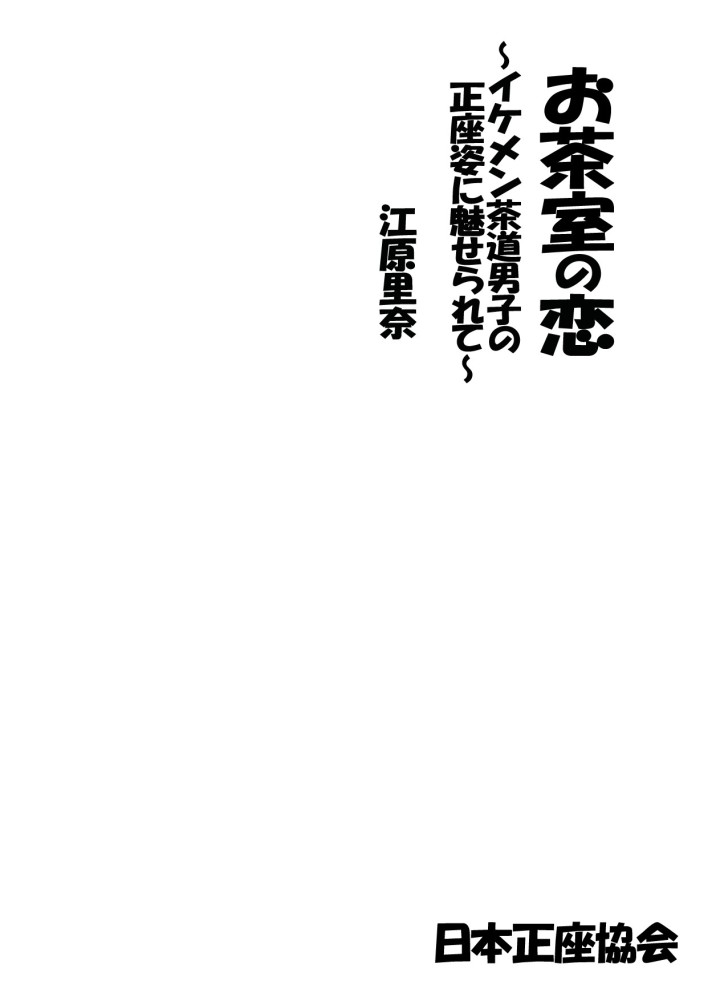
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1.日本文化は私の天敵!
「体グラグラさせないっ! 静かにお点前して!」
「は、はいっ、すみません!」
静けさに包まれていた茶室は、緊張感あふれたやり取りに空気がピンと張りつめる。
(そ、そんなこと言っても……足が、しびれちゃって……)
優香は、泣きそうになりながら心の中でぼやいた。
先生と一対一だったらまだいいが、タイミング悪くこれからお稽古を待っている生徒がすでに三人もいる。赤の他人に先生に怒られるところを観察される状況は、何よりも優香のプライドをズタズタにした。
彼女――石田優香は、これまで挫折を知らない人生を送ってきた。
昔から優等生で、大学を出た後に入った外資系企業でバリバリ働いている。しかも、見た目だって華やかな美人。要は、これまでずっと光の当たる場所を歩いてきたタイプだ。
そんな優香が、
(私って、もしかしてすごくダメ人間なのかしら……?)
と、自信喪失するのは、この茶道教室の空間以外にはありえない。
この教室では、ふつうの個人指導のお稽古に入る前に三ヶ月間の入門コースという集団レッスンを受ける。
そこで基本的な挨拶、お茶の飲み方、袱紗さばきなどの割り稽古をマスターし、盆略点前の基本的な流れまでを終わらせる……が、優香はそれさえもあやふやなまま、ここに来てしまっている。
他の人と比べて、物覚えはけっして悪くないはず。なのに、小さな所作や手順が覚えられないのには、大きな原因があった。
そう――彼女は、正座が大の苦手。
生まれ育った家には洋室しかないし、通っていたのはインターナショナルスクール。正座をする機会が、学校生活でもあるわけがない。
それでも、入門クラスはまだ我慢できた。つらそうにしていると、「足崩していいですよー」と頻繁に言ってもらえたから、その苦行を乗り越えることができた。
しかし、個人指導はそんなに甘くない。入門クラスでは、若めの先生が担当してくれたが、今回は指導歴何十年のベテラン、すごく情熱的な指導をして下さると有名な松木先生だ。
先生の厳しい視線、生徒たちの「早くして」という催促の視線、足のしびれという三重苦に耐えながら何とかお茶を点てていく。
正客にお茶を出す頃には、優香の目尻にうっすらと涙が滲んでいた。
「どうしたの、優香。浮かないカオしちゃって」
給湯コーナーのエスプレッソマシンでコーヒーを淹れていると、資料を片手に東条先輩が話しかけてきた。
彼女はアメリカの大学を卒業した才女で、優香より二つ年上のイケてる女性だ。
「……昨日、お茶のお稽古いったんですけど、松木先生にめっちゃ怒られちゃって」
「ああ、松木先生ねー。お茶への情熱がすごいから、最初のうちは仕方ないわよ」
と、肩をすくめて見せた。
「先輩みたいに、お茶を楽しめるようになれるか心配だなぁ」
「そうねぇ……あッ!! そういえば、あなたがお気に入りの綾小路君、お稽古に復活してたわよ」
その名に、優香の胸がドキッと高鳴った。
優香が茶道を習い始めたのは、二十八歳の誕生日を迎えてからだ。
それまで、彼女はずっと外国の文化に憧れていて、外人っぽく見せるためにいつも髪色を明るくしていた。花の都・パリに憧れて、フランス語を勉強して大学時代にフランスに交換留学をしたほどだ。
――が、現地に行くと事情が違った。外国かぶれの日本人よりも、日本文化をよく知る日本人が尊敬されているのに気づいてしまった。
優香と同じクラスの日本人留学生に、着物を自分で着られる子がいた。語学はできないのに、その子はフランス人からやたらと人気があった。なぜなら、きちんと日本文化を説明できるからだった。
(キー、くやしい!!)
と、優香は地団太を踏んだ。
しかし、彼女は反省した――日本人なのに、自国の文化や歴史を何も知らないのは恥ずかしい、と。
その時は、帰国したら色々と習ってリベンジしたいという野望を抱いた。実際は、卒論や就職活動が忙しくて、すっかりそんなことは忘れてしまっていた。
優香が、日本文化に注目したのはそれから六年後。付き合っていたイケメンのアメリカ人が、浮気したことがきっかけだ。
その浮気相手の女が、日本人形のような黒髪ストレートで日本舞踊が趣味とかいう古風な和風美人だ、と聞いて優香の怒りは爆発した。
「あー、なんで外人ってああいう古臭い女が好きなのよ!」
失恋直後で自暴自棄になっている優香を、自分が通う茶道教室のお茶会に誘ったのが東条先輩である。
「日本文化を知るのも、悪くないと思うよ。やってみたら楽しいかもしれないじゃん」
「……じゃあ、行くだけ行ってみます」
当初は気乗りがしなかったお茶会も、行ってみれば新たな発見の連続だった。
外人が茶道や着物に不思議な魅力を感じるのと同じような、何とも言えないカルチャーショックを受けた。東条先輩が隣でアドバイスしてくれても、お茶のいただき方すら覚束ない状態が、面白すぎて優香は泣きそうになった。
和服姿の超美形男性が現れたのは、まさにそんな時だった。
――その男性……綾小路君は、優香の憧れの人。
サラサラした黒髪、色白で端正な面立ち、伏せた睫毛は長く、お茶を点てる時の真摯な瞳が眩しかった。
これがお茶会のお点前デビューとは思えないほど、凛として涼やかな立ち居振る舞い、長時間の正座をものともしない涼しげな佇まい……そのすべてが、優香の心に日本文化の素晴らしさを印象づけた。
(日本って……よくわからないけど、奥深いのね!)
自国へのカルチャーショックとほのかな恋心から、優香は茶道教室に通うことになったのだ。
上場企業の経理部所属の綾小路君は決算期で忙しく、しばらくお茶のお稽古を休んでいたようだ。仕事の状況が落ち着いてきたので、また通い始めたらしい。
東条先輩はたまにお稽古が一緒になるようで、彼の情報を教えてくれる。
「この前、金曜の夜に来てたわよ。優香は水曜に行ってるみたいだけど、曜日ずらしてみたら?」
「金曜ですか……! 松木先生に、相談してみます!」
「そうよ。彼、マジメな好青年だから、意外と合うかもしれないわよ。この前、帰り一緒になったから色々聞いたけど、独身で彼女もいないって言ってたし」
「えッ、あんなにイケメンなのに!?」
「優香が美人なのに、彼氏がいないっていうのも不思議よ。まぁ、どうしても国際結婚したいっていうならオススメしないけど」
と、言い残すと、先輩は彼女の前を立ち去った。
一人残された優香は、淹れたコーヒーが冷めるのも気にせず、スマホを出して松木先生に曜日変更の電話をした。
2.イケメン茶道男子との再会
次の金曜日、優香はドキドキしながらお稽古に行った。
数人の先客がいたが、その中に目的の人物はいない。お稽古の受付は、午後八時半まで。優香がお点前を始める頃には、すでに八時を過ぎていた。
(綾小路君、欠席なのかなぁ……?)
残念に思いながら、お盆を炉の前にセットして一呼吸する。
すると、教室の戸が開く音……次いで、板の間を進む足音が聞こえた。
「松木先生、皆様、ごきげんよろしゅうございます」
その涼やかな声に、袱紗をさばきながら戸口の方をちらっと見る。
待ち人来たる――優香は、一瞬自分のお点前のことをすっかり忘れて見惚れてしまっていた。
端正な顔立ち、柔らかな表情。茶会と違って和服ではなくスーツ姿だが、数ヵ月ぶりに顔を合わせる綾小路君は、イケメンぶりをさらに増したようだった。
「ごきげんよろしゅうございます、綾小路さん。さぁ、早く中に。お客様、やってあげてちょうだい」
「わかりました」
と、微笑んで彼が茶室へと入ってきた。
(えッ……私がたてたお茶、綾小路さんが飲むの!?)
そのことに気づいて、変な緊張感が優香の顔を強張らせた。
憧れの人に会えただけで十分満足で、本日の目標達成だ。なのに、自分の無様なお稽古風景を見られ、微妙なお茶を彼に飲まれるだなんて……!
それに気づいたせいか、正座したばかりなのに足が途端にしびれ始めてしまう。
(あー、正座さえなければ、もうちょっと集中できるのにー!!)
お稽古が終わるまでの間、優香の試練の時間は続くのだった――。
(……今日も、たくさん怒られちゃった……)
ガックリと肩を落としながら、優香は盆と建水を下げにいく。
(しかも、あんなマズそうなお茶飲ませちゃって、私ってば……)
さっきのお稽古での失態の数々に、とてつもない自己嫌悪に陥ってしまう。一応、入門コースのテキストを読み直し、割り稽古や盆略点前の動画を見て、自分なりにおさらいをがんばっているが、今日は全然ダメだった。
斜め前から先生に凝視される緊張感と足のしびれ、そして、憧れの人がお客様だということで、いつもよりもさらにあがってしまった。
金曜日にお稽古の曜日を変えたのは、少し早すぎたかもしれない、と後悔する。
物思いに耽っていたせいで、優香は水屋に綾小路君がいるのを失念していた。次のお稽古の人が、水屋でお支度をするのは当然のことなのに……。
「あッ、すみません! お邪魔ですよね……!」
綾小路君は、優香が水屋の入口でモゾモゾしているのに気づいて、申し訳なさそうに頭を下げた。
「そんなこと……! お待ちしますので、大丈夫です」
「申し訳ありません。すぐに準備を終えますので」
と、言いながら彼はテキパキと柄杓や建水などを茶室へと運んでいく。
(すごいなー。柄杓なんて、私に使えるような日がくるのかなぁ……?)
そんなことを思いながら、ぼーっと彼を見つめる。
やっぱり、カッコいい。まるで、ジャニーズのアイドルのようなさわやかな笑顔がいい。
「すみませんでした。どうぞ、お使いください」
と、にこやかに会釈をすると、綾小路君は袱紗ばさみを抱えて茶室へ去っていく。
自分が使い終わったお道具を清め始める優香は、心を落ち着かせるどころか、微妙に浮かれていた。
(綾小路君ってカッコいいだけじゃなくて、性格も良さそう!)
これまで彼女がデートしたことのある男性たちは、自信満々で女性の扱いに慣れたマッチョなプレイボーイタイプ。そうした肉食系男子にはない、すがすがしさが綾小路君から感じられた。
(恋愛うんぬんは、しばらく置いておいて……)
と、優香はこっそり茶室のほうを窺った。綾小路君が、茶道口でお辞儀をする様子が見える。
今日は、お客様役も自分のお稽古も終わった。もう帰っていいわけだが、せっかく再会できたのにそれだけじゃもったいない。
お茶を点てるのは苦手だが、諸先輩方のお点前を見るのは面白かった。
(ちょっとだけ、見学させてもらおう!)
基本的に、お稽古の見学は奨励されているから、先生が怒ることはないだろう。
向学の意味一割、憧れの人への興味九割で、優香は片づけが終わると再び茶室に向かった。
毎週金曜にお稽古に通い続けるうち、優香は綾小路君と少しずつ仲良くなっていった。
彼女は人見知りしないから、人と友達になるのはけっこう早い方だ――ただ、それはドキドキする相手以外の話。
綾小路君があまりにも奥ゆかしいから、最初のうちは調子が狂っていたけれど、慣れてしまえば距離を詰めるのは早かった。
「どうしても、足がしびれちゃうんですよね。それもあって、お点前が全然覚えられないんですよ」
「正座は、慣れないとキツいですよね」
「綾小路さんは、得意そうですよね。何か、特訓でもしたんですか?」
「僕も、最初は三分ももたなかったです。でも、母が華道の師範をしていて、僕も中学から花を始めたんです。基本は椅子でのお稽古ですけど、正座をする機会もあるので少しずつ慣れましたね」
「へぇー! 男性が活けるお花なんて、素敵ですよね!」
そう褒めると、綾小路君はお道具を清めながら、俯いて頬を赤らめる。
「そうですか……? 男が華道だなんて、変わり者だって思われがちで……」
「お花もお茶もできるなんて、スゴイと思います! 私はどっちもできないから、憧れます!」
屈託のない笑みを浮かべる優香と反対に、綾小路君は気恥ずかしそうにモジモジしている。
そんな二人の背後に、松木先生の声が聞こえた。
「ちょっとー、二人とも! そろそろ、お教室閉めるからさっさと片づけ終わらせて!」
「は、ハイッ!」
「はい! スミマセン!!」
二人は慌てて、すっかり中断していた片づけを再開するのだった。
――それから一ヶ月。
外資系はノー残業が基本なので、金曜日の茶道教室には欠かさず出席していた。
だからと言って、すぐに上達するわけではない。正座も十分ももたずにしびれてしまうけれど、ようやく袱紗さばきはマスターした。
その原動力は、言うまでもなく綾小路君の存在だ。
ところが、五月には毎週教室に来ていた彼の姿が、六月に入ると突然見られなくなった。
「綾小路さんはお花が忙しいみたいで、しばらくお休みするって」
と、松木先生が何も聞いていないのに教えてくれた。
「そうなんですか……!?」
「この時期、大きな花展が控えているからねぇ。綾小路さんの作品、素敵なのよ。去年、チケットいただいて鑑賞させていただいたわ」
優香は、紫陽花をモチーフにした和菓子を食べ終わり、自分が淹れたお抹茶を作法通りに飲み始めた。
綾小路君のお点前とは、雲泥の差だ。彼のお茶は、湯の量や茶の濃さが適度で、表面の泡立ち方がクリーミーでカフェ・ラ・テのようだ。
(それに比べて、私は……)
いやに水っぽいお茶を飲み干す頃には、優香の表情が歪んでいた。
いつも、こんなお点前をニコニコしながら飲んでくれる綾小路君は、天使……いや、それを通り越して神様のような存在である。
褒めるとすぐ照れる素直さも、忙しい仕事の合間をぬって茶道に通うところも、お茶ばかりではなくお花も続けている日本文化を愛する心も……綾小路君に関するものなら、何もかもが愛しく感じられた。
毎回少しずつだが仲良くなっていくのを感じて、優香はすごくうれしかった。
(しばらく、会えないだなんて……そんなのつらすぎるよ)
と、泣きそうになる。
「ちょっと……石田さんってば、なに悲しいカオしてるの? そんなに、自分のお茶がマズかった? それとも、綾小路君と会えないのがさびしい?」
「えッ! そんなことないですよー!」
どっちを否定しているのかわからないままに、優香は頭を横に振った。
松木先生はにっこり微笑みながら、
「あら、そう? 綾小路さんの花展のチケットあるのよ。他の生徒さんにお渡しする前に、綾小路さんと仲のいい石田さんに一枚、って思ったんですけど……要らないかしら?」
「ぜひ、その貴重な一枚をわたくしに……!」
「初日の夕方には会場にいる、って言ってたかしらねぇ」
「初日の夕方……! ぜひ、行かせていただきます!!」
言うまでもなく、優香の表情は一瞬のうちに晴れ渡っていた。
3.彼からのアドバイス
花展は、六本木の美術館で開催されていた。
閉会時間に近いためか、駅方向に帰ろうとしている人々が多い。その流れに逆らうように、優香はウキウキしながらゆるやかな坂道をのぼっていく。
花展の会場になっているギャラリーは一階にあったが、他の美術展に遜色なくそれなりに盛況のようだ。出入口に、人がたむろしている。
(美術館なんて、留学した時以来だなぁ……)
基本的に、美術鑑賞の類は好きではない。美味しいものを食べたり誰かとしゃべったり、ウィンドーショッピングしたりするほうが楽しい。
当然、花を愛でるような趣味もないが、綾小路君の力作ならば、いくらでも時間を割くつもりだ。久しぶりに訪れた美術館の文化的な香りを楽しみつつ、優香は松木先生にもらったチケットで会場内に入った。
(生け花って、こんなに大きな作品もあるんだ)
華道に対する先入観が、花展の最初の作品から覆された。
洋風に近いアレンジのものもたくさんあった。木の枝をうまく利用して、花を大きく見せているオブジェのような作品も多く、思わず立ち止まって見入ってしまう。
華やかで独創的なものは、師範などの免許を持っている人の作品のようだ。
もともとは野に咲くただの花が、こうしてアレンジを加えることで多様なスタイルに変化するのは興味深かった。
(……で、綾小路君の作品はどこかな?)
と、プログラムを見ると、最後のほうに『綾小路ケイ』という文字が目に入った。一番奥の展示室にあるのを確認すると、他の生徒の作品はさっと見るだけにとどめて、優香は綾小路君の作品がある一画へと急いだ。
そこはかなり大きな部屋になっており、中央にゆっくりと作品を鑑賞するためのソファーが配され、小休憩できる簡易なテーブルセットがあった。
その部屋に入って、優香は目的の作品を探す。
「あれかしら?」
優香の視線の先には、一メートルほどありそうな華やいだ作品があった。白と黄色の花を白木の枝にあしらった、見事な作品である。
和のテイストを残しながらも、古さを感じさせないのが素晴らしい。
作者の説明書きを見ると、『一級師範 綾小路ケイ』と書かれている。
(えー、綾小路君! 師範って……きっと、エラいのね!!)
作品に圧倒され、綾小路君の経歴にも驚いた優香は、作品をスマホのカメラで角度を変えて何枚も撮影した。
写真を撮り終えると、その前で惚けたように立ち尽くした。
(ステキなお花……! 上品で、和の良さが引き立ってる……)
そう思った瞬間、背後に人の気配を感じた。
「お花、お好きなんですか?」
と、後ろから男性が声を掛けてきる。
こんな場所でナンパか、とうんざりした優香だが一応知人の花展だから作り笑いをした。
「ええ……とてもステキな作品なので、つい……」
そう答えながら、振り返るとそこには――。
「綾小路さん!」
当の本人の登場に驚く優香に、彼はニッコリ微笑んだ。
黒のポロシャツにチノパンというカジュアルな格好をしているせいか、茶道のお稽古の時よりもずっと若々しく見える。
(スーツもカッコいいけど、こういうカッコもさわやかー!)
と、思わず目がハートマークになりそうだった。
「お褒めいただいてうれしいです、石田さん。わざわざ、お休みの日にありがとうございます」
と、うやうやしく会釈してきた。
久しぶりに見る彼の礼儀正しい様子に、優香の心臓はよろこびに高鳴った。
花展が終了間際だったので、二人は帰りにお茶をすることになった。
しかも、誘ってくれたのは、なんと綾小路君だ。華道の仲間がいる手前、誘っていいものかとモジモジしていたから、彼から言い出してくれてホッとした。
ミッドタウン近くのカフェに入って席に着くと、窓の外はすっかり日が暮れていた。外苑通りに車のヘッドライトが行き来するのさえ、浮ついた心持ちの優香にとってはアート作品のように感じられる。
「茶道教室の方も来てくださるんですけど、あまり時間帯が合わなくて……こんな風に、会場でお会いするのって実は初めてなんですよ」
と、はにかんだ笑みを浮かべる綾小路君。
「綾小路さんって、師範なんですね。お花のことって、よくわからないけどすごい!」
「いえ……そんなこと。華道歴は長いですが、途中で休み休みやっているから、なかなか上達しなくて、お恥ずかしい限りです。仕事が落ち着いた一昨年あたりから、花展に出るようになったんですよ」
「そうなんですか! 仕事が忙しいと趣味まで手が回らないですよねー。私もようやくひと息ついたんですよね」
優香の場合、ひと息ついたのは仕事じゃなくて恋愛だが、適当に話を合わせている。
「ああ……それで、茶道を始められたんですね。石田さんは、たしか外資系ですよね」
「ええ、東条先輩と同じフロアです」
「すごいなぁ! 僕、昔から英語が苦手で……僕こそ、英語ができるお二人を尊敬しますよ」
「そんな! 私、語学しか取り柄がないんです。正座だって、これまでほとんどしたことがなくて、始めてから半年経った今でもお稽古の時にすぐしびれちゃって……日本生まれの日本人なのに、本当にお恥ずかしい限りです」
表情を曇らせる優香に、綾小路君はふと何かを思いついたように瞳を輝かせた。
「もしよろしければ、僕が中学時代にやっていた正座特訓法、お教えしましょうか?」
「特訓法? 何ですか、ソレ!?」
「毎日、少しだけでも正座を続けるんです。最初は五分だけでもいいし……特に、お風呂の中でやると最初は楽ですね」
「お風呂……?」
「湯船の中で、正座するんですよ。浮力があるからふつうにするよりも、長時間できるんです。正座ってストレッチ効果があるんで、続けるうちに足腰の筋肉も柔らかくなってくるんですよね。体罰とか悪いことがクローズアップされがちですけど、正座は健康にもいい座り方なんですよ」
たしかに、彼の言うことは的を射ている。
正座をすると、背筋が伸びて猫背が治る。すぐに足がしびれてしまうけれど――。
「そうなんですか……知らなかった! じゃあ、今晩から試してみますね!」
「ぜひ、そうしてください」
……というわけで、綾小路君のアドバイスによって、その日の夜から優香の正座トレーニングが始まった。
綾小路君のアドバイス通り、優香はスポーツジムのジャグジーや湯船に入る時はずっと正座で過ごすようになった。
会社でも、椅子の上で正座してみた。すると、デスクワークが多くてむくみがちだった足が、続けるうちにスッキリしたような気がする。
「あれー? どうしちゃったのよ、優香ってば」
ミーティング帰りに通りかかった東条先輩が、椅子の上で正座している優香に目を丸くした。
「ユーカはトレーニング中なんだよ。足が細くなるんだって」
と、優香の隣の席のコンサルタントのジェフが教えてくれた。
「トレーニング?」
「ホントかどうかわからないけど、うちのワイフも正座すると姿勢がよくなるって言ってるよ」
「言われてみれば、私も茶道やってから姿勢がよくなった気がするわ」
「そうですよ、先輩。私、気合い入ってます!」
そのやり取りを横目に、優香はすごいスピードでプレゼン資料を作成中だ。
よい姿勢で作業しているせいか、前よりも能率が上がった気がする。正座をしている時とふつうに座っている時で、椅子の高さは変えなければいけないけれど大した手間ではないから続けられる。
足のむくみが減って、デスクワークからくる腰痛や肩こりも軽くなった。多少の面倒や周りの好奇の視線はあっても、正座の特訓はメリットが大きかった。
「地味な努力続けるタイプ? 意外ね!」
「そうですよー、一途ですよ、私!」
「そのエクササイズ、もしかして綾小路君のためかしら? そう言えば先週末、花展に行ったとか言ってたわね?」
そう言われて、ギクッとする。
昨日のランチで、綾小路君の花展に行ったことは先輩には伝えたが、そのあとで二人きりでイタリアンで食事したことは内緒にしていた。
綾小路君は、優香にとってアイドルだった。ところが、今は尊敬する友人のような距離感になってきている。恋愛に発展するかしないかは別として、周りに吹聴しても問題がない時期は過ぎていた。
業務時間内というのもあってか、先輩はそれ以上追及してこなかった。
「ま、努力はいいことよね。私も優香みたいな脚線美目指して、正座エクササイズしようかしら?」
意気揚々と自分のデスクに戻っていく先輩を見送りながら、優香はため息混じりに呟いた。
「私の場合、エクササイズじゃなくて特訓なんですけどねー」
地味な努力を積み重ねていると、ゆっくりだが確実に効果が現れてきた。
茶道のお稽古のたびに、しびれるまでの時間が少しずつ長くなっていく。それは、自分自身が一番実感できる部分だ。
正座から引き起こされていた苦痛が軽くなったおかげで、一生懸命インプットしているお点前の順序を覚えていられるようになり、スピードアップした気がする。
「石田さん、最近いいじゃない。袱紗さばくのも早くなったし、所作もキレイになってきたわ」
松木先生にお褒めの言葉をいただくのは、これが初めて。
優香は、うれしさのあまり頬を赤らめた。
「わぁ、本当ですか……!」
「本当よ。おいしそうなお茶を点てられるようになったし……ねぇ、綾小路さん?」
と、松木先生は、花展を終えて久しぶりにお稽古にきた綾小路君に話をふった。
彼は茶器の拝見をしているところだったが、顔をあげてにっこりと微笑んだ。
「ええ。とても飲みやすいお茶でしたよ。適量で泡立ちもよかったし」
「もしかして、正座が苦じゃなくなったのかしら? いいことだわ」
「少し、我慢できるようになってきました。家でちょっとずつやってます」
「そうそう。その努力、ずっと続けてちょうだい。正座は、アンチエイジングにもいいのよ」
「そうなんですか……?」
「茶道始めてもう半世紀ですけどね、背筋がシャンとしているから、実年齢言うと驚かれるわよ」
そう聞いて、松木先生や年配の先生方の背中が年の割に全然曲がっていないことに気づく。前に綾小路君から聞いた正座によるストレッチ効果も、老化防止にいいのかもしれない。
(そうなんだ。日本文化、奥が深いわ)
と、優香が認識を新たにしているところに、松木先生がある提案をしてきた。
「石田さん、盆略も足の運びもできるようになったし、次回からは柄杓の使い方を覚えましょうか」
「え、ひしゃく……ですか!? この私が!?」
「この私が、って他に誰がいるっていうの? 最初はどうなるかと思ったけど、がんばるタイプみたいだから、少しずつ覚えていってほしいわ」
「わかりました……! どうぞ、これからもよろしくお願いしますっ」
真のお辞儀をする優香を、綾小路君はやさしい微笑みを浮かべながら見つめていた。
4.和風美人のライバルあらわる!
金曜日の夜は、お稽古にくる社会人はさほど多くない。
週末を使って旅行に出たり友人と遊んだりするために、他の曜日にお稽古を変更する人が続いたらしい。そのせいで、意外と生徒は少なかった。
一番人気は、多くの企業が「ノー残業デー」に設定している水曜日。
だから、優香は松木先生の情熱的な指導をじっくり受けられるし、遅めの時間に行けば綾小路君とペアでお稽古ができる。週に一度のお稽古タイムは、優香にとって一週間仕事をがんばったご褒美タイムになっていた。
柄杓の使い方はまだまだ慣れないけれど、もっとがんばって先生や綾小路君に褒めてもらえるようになりたい、と意気込む優香だった。
(綾小路君、もう来てるかな?)
ドキドキしながら、お教室に入ると男性物の革靴があった。
しかし、その隣には見慣れない赤いミュールが……。
(……あれ? この時間に、めずらしい)
そう思いながら、身支度を整える。
白い靴下に履き替え、袱紗ばさみを持って茶室入口に行くと、そこには見たことがない女性がいた――しかも、お点前の最中である。
初心者の優香が見たことがない棚を使ったお点前。どう考えても、何年か経験がありそうな案じだった。
「先生、皆様、ごきげんよろしゅうございます」
「あら、石田さん、ごきげんよろしゅうございます」
「石田さん、ごきげんよろしゅうございます」
動揺を隠して、挨拶すると正客の席にいた綾小路君も挨拶を返してくれた。
「あなたも次客席に来て、お稽古見るといいわ。こちらの方、綾小路さんのご紹介でいらしたの。ブランクがあるけど、いいお点前なさるわ」
「五上美紗と申します。綾小路君と華道でご一緒させていただいております」
と、名乗ってこちらに振り向いた五上さんは、いかにもな和風美女だった。
髪はロングストレートの黒髪、日本人形のような切れ長の奥二重の瞳に、色白の肌、ぽってりとした赤い唇は男心をくすぐりそうだ。全体的にほっそりとした体型で、男性の庇護欲を掻き立てそうな感じがした。
そうした彼女の印象は、優香の元彼の浮気相手にソックリで、思わず背筋が寒くなった。
(いるのね、こういう女……! この人、綾小路君の何!?)
と、瞬時に初対面の五上さんをライバル扱いする。
内心、嫉妬心がメラメラと燃え上がったものの、ここは神聖なるお茶室である。松木先生と憧れの人の手前、そんな見苦しいところを見せるわけにはいかない。
「石田優香です。どうぞ、よろしくお願いいたします」
茶道で大事なのは、一期一会の精神。優香はニッコリ微笑み、イヤミなほどに恭しく真のお辞儀をしたのだった。
――翌週月曜日のランチタイム。
優香と東条先輩は、オフィスの近隣にある一流レストランのブッフェにいた。毎回、季節ごとにメニューが変わるとランチしにくるのが恒例になっている。
シャンデリアが下がった吹き抜けのロビーは開放感があり、オープンキッチンで調理される料理はどれもが美味だった。今日は「ピーチ&マンゴースイーツフェア」だからか、あちこちでランチ女子会が催されている。
しかし、美味しそうな料理を目の前にしても、優香の顔は浮かなかった。
「へぇ、綾小路君の花仲間かー! ライバル出現、手ごわい相手がきたもんだね!」
先週の茶道教室の出来事を聞いた東条先輩は、わざと焚きつけるようなことを言ってくる。
「やめてくださいよー。ライバルとか……」
取り皿に載った冷製パスタをスプーンの上でくるくる巻きながら、優香はゲッソリした様子で溜息を漏らす。
「私のライバルって、なんでみんな和風美人なんでしょう……同じタイプなら、売られたケンカは買いますけど、和に関してはからっきしダメだからなぁ……」
「えッ、そんなの優香らしくないよ」
「先輩にとって、私ってどういうキャラなんですか……!?」
「仕事にも、男にも肉食系」
先輩にそう言われて、これまでの恋愛を思い返してみる。
たしかに、優香は昔からモテていて常にデートする相手がいた。
外人は気に入った子にすぐアプローチするから、その中からいいなと思った相手と付き合ってきただけ。これまで、優香から主体的に行動を起こしたことはなかった気がする。
(……これまでは、相手が肉食系だからモテてただけかなぁ……)
と、優香は冷静に自己分析した。
相手がグイグイくるなら、それに乗ればいいだけ。恋愛の進展は、すこぶる早い。
それが、日本人で物静かな茶道男子だとしたら――?
「あー、無理よねぇー」
と、食事の途中で頭を抱え込んでしまう。
東条先輩はすでに一皿たいらげて、二皿目に突入しようとしている。不思議なのは、先輩が自分の大好物のステーキを食べているのに、なんの羨ましさも感じないことだ。
そんな優香を見て、東条先輩が呆れたように忠告した。
「ちょっとー、昼休み終わっちゃうじゃない! 二千円以上出して、デザートにいきつかなかったらコスパ悪いわよ。悩んでないで、さっさと食べなさいって!」
「だってー」
「だって、じゃない! そんなに好きだったら、自分から言っちゃえばいいのよ」
――ドキッ。
ビックリして、心臓が飛び跳ねる。
(……こ、告白ッ!? この私が……?)
先輩に言われて、初めて現実味が湧いた。
たしかに、思い悩んでも無意味で時間の無駄だ。これまで何人かと付き合ったのは、相手が積極的にアプローチしてくれたから。物静かな綾小路君を待っていても、何も起こるわけがない。
これまでは少し話ができるだけで満足だったけれど、五上さんが出現してからというものの、それだけじゃいけないような気になっている。
(やっぱり、嫉妬してるんだよな……私)
と、優香は溜息を漏らす。
あの日――金曜日のお稽古の時、五上さんと綾小路君はお点前とお客様とを交互でやった。だから、優香のお点前の前に二人は先に帰ったのだ。
水屋で楽しそうにしゃべりながら茶器を片づける様子を見て、優香は胸が張り裂けそうな不快感を覚えた。
それは、やるせない感覚。これまでの恋愛で、こんな思いをしたことはなかった。むしろ、元彼の浮気よりも精神的につらい。
そのあとのお稽古も散々で、柄杓の使い方をなかなか覚えられないのもキツかった。
相変わらず自分の点てたお茶は果てしなくマズくて、優香は思わず茶器をもどすためににじりながら泣き出しそうになった。
「どうしたの、石田さん? 具合でも悪いの?」
「い、いえ……今日のお茶、イマイチだったもので……」
松木先生に、優香は咄嗟に言い訳をした。
すると、
「ああ……お湯多く入れすぎたかもね。盆略と違うから、少しずつ加減を覚えていってちょうだいな」
と、やさしく微笑んでくれた。
そう――壊滅的にダメな子じゃないのは、自分でもわかっている。
お湯の入れすぎなんて、よくあるプチ失敗だ。たぶん、さっき見た五上さんのお点前があざやかすぎて、より自分がミジメに感じるだけなのだろう。
美しい黒髪と、すっと伸びた背筋、袱紗でなつめを清める動作も流れるようで、無駄な動きは何一つなかった。
お茶尺やなつめの拝見の問答を綾小路君としていたのも、羨望の念を起こさせた。優雅なやり取りを傍らで聞いていた優香は、無人島に一人取り残されたような悲しい気分に陥った。
(和風美人は、みんな私の敵だわ……!)
と、燃え上がるライバル心をおくびにも出さず、これから帰ろうという彼女に声を掛けた。
「五上さんって、すごく所作がキレイですねー!」
「ホントですか!? ありがとうございます。綾小路君が茶道教室のこと、楽しそうに話していたから、試しに来てみたんですけど……先生のご指導もよかったし、石田さんみたいな先輩もいるなら、私も通ってみようかなぁ」
どうやら彼女は今回、体験レッスンだったようだ――墓穴を掘ってしまったことに気づいて、優香は一瞬真顔になった。
(この人がきたら、綾小路君と二人きりになるチャンスが……!)
とは言っても、綾小路君が見ている前で怒ったら逆効果。
その辺りは意外と合理的な優香は、満面の笑みを浮かべてこう言った。
「ぜひ! また、お点前見せてくださいね!」
つくづく思い返しても、二人は美男美女でお似合いだった。腹立たしくなるほどに――。
今週末、また二人揃って教室に来るかもしれないと考えると、ご馳走を目の前にしても食欲が湧かない。
「マンゴー&ピーチフェアなんだから、デザートは食べておきなさいよ?」
東条先輩は物思いに耽っている優香の前に、彼女の分のデザートも持ってきてくれた。
完熟マンゴーがたっぷりのタルトにピーチの薄切りが載ったピーチゼリー、そして抹茶のティラミス――。
優香の視線は、小さなカップに入った緑色のデザートに釘付けになる。
「ありがとうございます! これ、いただいていいですか?」
「なんで、抹茶ティラミス? さっきから、マンゴー&ピーチフェアだって言ってるのに……あんたって意外と一途ねぇ」
呆れ顔の先輩に、優香は苦笑した。
(私、やっぱり、綾小路君のことをあきらめられない……)
抹茶ティラミスを一口食べると、ほろ苦い抹茶味が口の中に広がっていく。
追う恋をはじめて体験している優香にとって、その味は自分が今感じている気持ちそのものだった。
5.恋する乙女の決断
季節が廻り、年に一回の茶会のシーズンがやってきた。
優香が通っている茶道教室で、これはかなりの大イベント。関東に何件かある教室の生徒が東京の本部茶室に一堂に会するため、土日の二日間で多くの茶席が用意される。
去年の優香のように茶会をきっかけに茶道を始める生徒も多いため、直前の一ヵ月間はお点前をする生徒にとっては特に緊張感溢れる時期になる。
「今度のお茶会、出席なさるんですか?」
待合いにあった茶会の参加用紙を見ていたら、綾小路君が来たので話し掛けた。
「ええ。前回、お点前やらせていただいたので今回はお客様だけにしようか、と思っています。松木先生から茶花を頼まれているので、運営の協力もさせていただきますが」
「え、お花を……? 綾小路さんの作品、また見られるなんて楽しみです!」
そう言うと、綾小路君はうれしそうに頬を赤らめた。
「ありがとうございます……! 今回はお茶会用なので、小振りなものにしますよ」
「存在感がありすぎても、主役はどっち?みたいになっちゃいますもんねー」
「茶も花もおもてなしの一部ですからね。とにかく調和が大事なんです……ところで、石田さんは、当日はいらっしゃるんですか?」
「ええ。お客様で参加させていただこうかと思っています」
「せっかくですから、お点前されたらいいのに。薄茶はまだ空きがあるって聞いています」
「え、私が……!?」
「もちろん。初めて一年くらいの方だと、モチベーションアップのためにお点前披露するみたいです。先生に相談してみたら、いかがでしょう?」
優香は「そうですね」と曖昧に答えると、水屋に去っていく綾小路君の後ろ姿を見送った。
わからないことだらけで、人前でお点前をするような度胸も自信もあるわけがない。それでも、憧れの人に言われると、なんだかチャレンジしてもいいような気になってくるのが不思議だった。
たまに他の生徒が振替でくることはあっても、松木先生の金曜夜のこの時間帯の指導を受けるのは彼と優香の二人と、あと五上さんだけだ。
今日は、彼女は用事があるようで、久しぶりに二人きりになった。
結局、五上さんも華道と仕事が忙しく、茶道教室にくるのは月二回らしい。彼女がいる日は、綾小路君と彼女の仲睦まじい様子を見せられるので、優香はとにかくイヤな気分になる。
精神衛生上、毎回来られるととても困るのだ。
綾小路君のことはすごく好きだし、日本文化を学ぶ先輩として尊敬している。
それだけなら他の子と仲良くしていて、イラッとくるわけがない。どう考えても、今、自分が抱いている想いは『恋』と呼ばれる独占欲の現れだ。
(……綾小路君は、私のこと、どう思ってるんだろう……)
そんな風に思い悩んだ夜は数知れず。
いつも合理的にテキパキ事を進めるタイプの優香にとって、人の心をあれこれ考えるのは、とてつもない苦痛である。
さっさと、自分のことどう思っているか、ストレートに聞いてしまいたかった。
ただし、駄目だった場合のリスクもある。綾小路君にとって優香が恋愛対象外ならば、お互い顔を合わせるのが気まずくなるだろう。
ようやく苦手だったことを克服して、茶道を気長に続けようと思い始めた矢先だ。告白する度胸がないとかではないけれど、優香がそれをためらうには十分な理由があった。
隠し事がキライな優香は、悩みがあると真っ先に東条先輩に相談する。
二人は仕事が終わってから、オフィスの近くのオイスターバーで蒸し牡蠣を肴に白ワインを味わっていた。
「ふーん……けっこう悩んじゃってるんだ」
「そうですよ。先輩みたいに、仕事も恋も絶好調とかじゃないんで」
彼氏と順調な交際っぷりを見せる東条先輩がうらやましい。ただ、彼が来年アメリカ本社に転勤になるらしく、遠距離になるか結婚するかという岐路に立たされている。
(いいよなー。私なんて、スタートラインに立てるかどうかもわからないのに)
と、むくれながら、殻を持って牡蠣をツルリと口に入れた。
「長くなれば長くなったで色々あるのよ。優香の悩みなんて、カワイイもんだわ」
「えーなんか、二つしか違わないのにムカつくー」
「あはは、ゴメン! でも、綾小路君と優香、イイ感じに見えるけどなー。ライバルがいる時楽しそうっていうのは、彼なりの気遣いじゃない?」
「まぁ……五上さんは、お母さんのお弟子さんらしいですしね」
「そうよ。松木先生に紹介したのも自分でしょ。それが関係悪くなったら、彼は母親にも松木先生にも顔向けできないわよ」
「たしかに、そうですね」
「でもさー、優香には何のしがらみもないじゃない。それで、やさしくしてくれるんでしょー? キライじゃないと思うよ。むしろ、好きっていうか……」
「ええッ!」
慌てて顔を赤らめる優香に、東条先輩はニヤッと笑った。
「いいわね、その反応! 優香ってば、肉食っぽく見えてそういうとこピュアじゃん。そのギャップ、いいよねー」
「先輩! からかわないでください!」
「ゴメン。綾小路君は、彼女いないらしいしアタックしてみればー? いかにも草食男子じゃん。優香のこと気に入っていても、あっちから言い出さないわよ」
「うーん……でも、私のこと好きじゃなかったら……?」
「高校生じゃないんだからさー、気まずければ茶道教室を辞めるか、曜日ずらすかすればいいだけの話じゃん」
「まぁ、そうですね」
「フラれたらって思うと、プライドが許さないのかもしれないけどさ、何事も勉強だからやってみれば? とりあえず、今度のお茶会でお点前してみるとかさー」
「お点前……!」
「そうそう。それが無事に終わったら、綾小路君に告白するのよ」
言われてみれば、確かにそれはアリだ。
お茶会でお点前をすれば、茶道教室にがんばって通った意味がある。最悪、綾小路君にフラれたとしても、気持ちの区切りになるだろう。
「そうですね……! それまでは、とにかくお点前をがんばって、むっちゃがんばって……ベストなお点前をお茶会で披露できたら……私、彼に告白します……!」
「そうよ、その意気よ! それくらいのテンションなら、恋愛はうまくいくわよ」
「そうですかねー」
「だって、どー考えても緊張度はお茶会が上でしょ? 私も一年目でお点前披露したけどけっこう大変よ。あの妙な緊張感に比べたら、告白なんてハナクソみたいなもんよ!」
と、笑って東条先輩は大皿に一つ残っていた蒸し牡蠣に手を伸ばした。
「隙あり! これは、相談料としていただくわ!」
「どうぞ、どうぞ」
白ワインを傾けながら、優香はぼんやりと妄想してみた。
何人ものお客様に見守られながら、お点前を披露する緊張感――それを考えただけで、ワインの酔いが変にまわってしまいそうだ。
お茶会でお点前をするということは、一人ですべてやらねばならないということ。松木先生がアドバイスしてくれるわけでもなく、綾小路君が正客に座っているとも限らない……。
(……私にとって、綾小路君は日本文化の王子様なんだ)
彼の所作の美しさや、お茶を飲む優雅な手つき、正座姿の凛とした佇まい――そうしたものに惹かれたことが、優香が茶道を始めるきっかけになった。
ただの憧れだったのが、言葉を交わせる関係になった。それだけで十分だった。
なのに、今は変な嫉妬心にイライラして自分を見失っている。
(一度、恋も嫉妬もリセットしよう。初心に戻って、お茶会までがんばろう)
優香は、グラスに残った美酒を飲み干しながら決意を固めた。
次のお稽古の日、優香は松木先生に薄茶平点前で参加したいと申し出た。
先生は、満面の笑みを浮かべて頷いた。
「よかったわ。私の生徒さん、今回は誰もお点前出ないかと思ってヒヤヒヤしていたのよ。あなたは真面目に毎回来てくれるから大丈夫だと思うわ。緊張するかもしれないけれど、当日までがんばりましょう」
「ありがとうございます、先生! 未熟者ですが、がんばります!」
深々とお辞儀をしたところに、入口に綾小路君が現れた。
「松木先生、石田さん、ごきげんよろしゅうございます」
「綾小路さん、ごきげんよろしゅうございます」
「ごきげんよろしゅうございます」
礼をし終えてから、松木先生が嬉々としてニュースを伝える。
「綾小路さん、聞いてくれる? 今度のお茶会、石田さんがお点前してくださるって!」
「本当ですか!?」
「は、はい……」
二人の期待の視線が集中してくると、なんだかとんでもない決断をしたのではないか、と不安になる。ただ、自分ががんばることで二人が満足してくれるなら、これほど素晴らしいことはないと思った。
「私、がんばります……! 先生にも、先輩である綾小路さんにもご指導いただきますが、どうぞよろしくお願いいたします!」
「そうですか……! 僕にできることがあれば、ぜひおっしゃってくださいね。応援しています」
「ありがとうございます!」
優香は頬を赤らめて、綾小路君にお辞儀をした。
6.初めてのお茶会、初めての告白
――ついに、茶会の日がやってきた。
準備は、かなり大変だった。起きてすぐに母に着つけをしてもらい、自身でヘアメイクを施した。慣れない和装に苦労しながら、さっき茶道教室に到着したばかりだ。
十時から始まる茶席に向けて、先生やお点前をする生徒たちや運営スタッフがすでに設営作業をしたり、水屋で準備をしたりしているところだった。
「あらー、優香ってばステキじゃない! 意外と着物も似合うのね!」
と、東条先輩が声を掛けてくる。
今日の優香は、小さな桔梗柄があしらわれた藤色の訪問着を着ている。母から借りものだが、着丈もちょうどよくて助かった。茶席の亭主役として恥ずかしくないように、茶色にカラーリングした髪は黒にトーンダウンして、落ち着いたまとめ髪にしている。
「ありがとうございます。先輩もこのワンピース、いいデザインですね!」
「サンキュ! あっちに、綾小路君、いるわよ。挨拶してきなさいよ」
「はい」
「……お点前も告白も、がんばってね!」
優香の耳元でエールを送ると、先輩は颯爽と茶室へと去っていった。
残された優香は、着物姿で他の男子生徒と談笑する綾小路君を見つめた。
(……あなたがいてくれたお陰で、私この日を迎えることができました)
心の中で、優香は彼の存在そのものに感謝した。
涙ぐみそうになった瞬間、名を呼ばれて振り向くと五上さんがニッコリ笑っている。
「石田さん、今日はお点前なんですってね」
「五上さん……!」
「綾小路君から、お花の時にお噂は聞いていますよ。お点前なんて緊張しますけど、石田さんならきっと大丈夫だわ」
「ありがとうございます」
いつも綾小路君を独占する五上さんにはいつも嫉妬心しかなかったけれど、なぜか今日は戦友になったような気がした。
(そうよね……綾小路君の反応によっては、会うのが最後になるかもしれないんだ)
優香は五上さんの手をガシッと握り、感極まったように囁いた。
「ありがとう……五上さん。あなたのためにも、がんばります……!」
意味が分かりかねる、とでもいうように曖昧な笑みを浮かべる五上さんを置いて、優香はお支度を始めた。
(とにかく、集中しなきゃ……! 恋も嫉妬も、全部お茶席の後で!)
「いつも通り、平常心でやってくださいね!」
松木先生に肩をポンと叩かれ、優香は黙ってうなずいた。
この半年、散々練習を重ねてきたのだから、薄茶平点前は完全にマスターしているはず。直前には、週一回のお稽古を二回に増やしてがんばった。柄杓の使い方がより美しく見えるように、と心を砕くまでになった。
深呼吸して、優香は水指を持って茶道口に向かった。
正座をして総礼をする直前に、茶室にいる面々をさっと見回す。
正客に坐しているのは、予定通りで綾小路君だったからホッとした。それ以外には、見知った人はいない……と、思ったら綾小路君の隣の次客に、五上さんがいるではないか!
優香の視線に気づくと、艶然と微笑んでくる。その余裕が、今はなんだか腹立たしい。
(気にしない……! 嫉妬はとりあえず封印!)
と、心の中で自分に言い聞かせた――。
五上さんがいたことで、気が動転しそうになった優香だが、何とかお点前は問題なく済ませることができた。
茶会では人数が多いため、正客と次客だけに亭主がお茶を点てる。他の客には、それぞれの担当の先生が点てて、お手伝いのスタッフが運んでくれるのだ。
しかしながら、通常のお稽古の時間よりも正座をしている時間は長い。そのため、優香は暇さえあれば、綾小路君に教えてもらった正座特訓法をしていた。
茶道教室に通い始めた頃は五分もたずに痺れ始めていた足も、最近ではどうだろう? お茶会で涼しい顔でお点前をできるようにまで成長を見せていたのだ。
「えらいわ! がんばったわね!!」
水屋に下がると、一番最初に東条先輩がねぎらってくれた。
「ありがとうございます……どうなることかと思いましたけど、お陰様でなんとかなりました」
「残る試練は、例の件だけね! このあと、誘うんでしょ? がんばって!」
と言われて、緊張が過ぎたところに新たな緊張が押し寄せてきた。
(でもなぁ……今日は、五上さんいるしなぁ……)
緊張のあまり、いつもライバル視している五上さんを理由に告白を先送りしようとする自分に優香は呆れてしまう。
ふと待合いの方に視線をやると、仲良さそうに話している二人が見えた。
それを見ると、これまで封じていた嫉妬心がメラメラと燃え上がった。
(いや、やっぱ誘おう! そのために、ここまでがんばってきたんだもん!)
初心忘れるべからず――優香は拳を握りしめて、そう心に誓った。
つかつかと、綾小路君と五上さんのところに近づいていく。
「あ、石田さん!」
五上さんが優香に気づいて、いち早く声を掛けてきた。
それをほぼ無視して、優香は綾小路君に話し掛ける。
「綾小路さん! お正客役、いてくださってよかったです。ありがとうございました」
「石田さん、お疲れ様でした! すごくいいお点前だったと思いますよ」
「ホントですか? そう言われると、うれしいです」
と言うや否や、優香は五上さんに向き合った。
「五上さん、ごめんなさい! 私、綾小路さんにお話がありまして……!」
『申し訳ないけど席を外して』と、ほのめかすと五上さんが途端に無表情になった。
しかし、彼女に気を遣ってばかりもいられない。五上さんが無言のままでその場を立ち去ると、優香は綾小路君に向き直った。
彼は、突然のことに緊張した面持ちになっている。
「石田さん……?」
「すみません、綾小路さん。たぶん片づけで遅くまでいらっしゃるかと思うんですが、その後お時間あれば……」
「え……」
「私、綾小路さんのおかげで茶会まで辿り着けました。お礼に、お茶でもご馳走させてください」
「えッ、僕は何もしていないですが……石田さんがそうおっしゃるんなら……!」
綾小路君もまんざらでもなさそうなのが、表情で読み取れた。
優香は、心の中でガッツポーズする。
「六時くらいになるかもしれないですが、それでもよろしいでしょうか……?」
「大丈夫です! 私も、お客様として茶席に参加させていただくと思いますし」
「時間的に食事がいいですかね。この近くに気軽な感じのおばんざい屋さんがあるので、もしよろしければそちらに……」
「はい! じゃあ、そこでお待ちしています!」
お茶席が先に終わった優香は、一足先に松木先生にお礼をしてから、待ち合わせ場所の店に入った。
和風の店をイメージしていたが、実際はオーガニックカフェのような感じだった。ヘルシーなおばんざいを盛った定食がウリである。
(こういうお店が、好きなのかしら……東条先輩とだとワインバーとか行くけど、こういうのもいいかも)
考えるうちに緊張してきたので先にビールを注文して、一足先にテラス席で飲み始める。
綾小路君が店に到着したのは、それから三十分後のことだった。
「お待たせして、すみません!」
着替えを済ませ、着物ではなくカジュアルな格好でやってきた彼は、優香が飲み物を頼んでいるのを見て申し訳なさそうに頭を下げた。
「いえ、私こそ五上さんがいらっしゃるのに、空気読まないでスミマセン。しかも、フライングして飲んでます……」
「彼女のことは気にしないでください。あの人は、ちょっとむずかしいところがあるので……」
早い時間に入ったので、窓際の席に二人は陣取っている。並木道や通りの景色を楽しめるよう、席が斜めに配置されているので彼が隣に座ると距離が近くてドキッとする。
とりあえず、おつまみ程度におばんざい六種盛りを頼んでビールで乾杯すると、優香の緊張感が多少は和らいだ気がした。
「ホントに、お疲れさまでした。正直、最初に石田さんのお点前拝見した時はすぐにやめちゃうんじゃないかって思ったんです。よくここまで、がんばりましたね」
「綾小路さん……」
「あ、上から目線だったらスミマセン」
「いえ、そんなことありませんよ! 私こそ、正座訓練法を教えてもらって助かりました」
「あ! いつの間にか、大丈夫になったみたいですよね。努力の人だなーって、本当に感心しました……石田さん、昔からそうですよね。なんでも卒なくこなしちゃうタイプに見えて、すごく努力してそう」
「昔からって……?」
綾小路君は、失言してしたかのように気まずそうに視線を外す。
(どこかで、会ったことあるのかしら……?)
と、優香の頭の中に疑問符が飛び交う。
「どういうことです? 綾小路さんって、私のこと茶道でご一緒する前からご存じだった……?」
「え、あの……」
「気になって、眠れなくなっちゃうから教えてください!」
優香の勢いに、綾小路君はおずおずと切り出した。
「実は……新橋で開催された『経営力を身につける』セミナーで、お見かけしたことがありまして……」
言われてみれば、そんなセミナー出席あったかもしれない。たしか、二年ほど前だ。
管理職を目指すのに必要な経営学を若年層社員に解説し、グループ討議やプレゼンも盛り込んだ実践的な内容の研修である。
優香は東条先輩に誘われて、参加したからイマイチ印象が薄い。セミナーよりも、先輩と行ったホテルランチのことしか覚えていない。
「あのセミナー、外人講師もいたでしょう? 僕なんて緊張しちゃって日本語で議論するのもままならないのに、石田さんは流暢な英語でやり取りしていて……ネイティブ並みに英語もしゃべれて、しかも美人だったから忘れられなくて……」
優香は、その場に綾小路君がいたことすら覚えていない。
基本的に一途なので、彼氏がいる時はそれ以外の男はまったく目に入らない。その時は外人のイケメン彼氏がいたから、日本人のイケメンがどんなにたくさんいても、優香にとっては道の石ころと同じ程度の存在でしかなかった。
「石田さんと同じ会社の東条さんが、たまたま同じグループだったんです。ディスカッションの合間に、会社のこととか趣味のこととか色々お話していたら、茶道に興味を持っていただいたようで……」
「あー、だからいきなり先輩が茶道始めたんですね!」
「そうなんです。それで、教室で顔を合わせるようになりまして、思い切って石田さんのことを尋ねてみたんです。そしたら東条さん、石田さんのことお茶会に誘ってみるっておっしゃって。いつの間にか、石田さんも茶道教室に通い始めたって聞いて……なんだか、すごく不思議な縁を感じました」
要するに、東条先輩は失恋したばかりで傷心の優香と綾小路君を結びつけたキューピットということになる。
優香の恋を最初からずっと観察してきたわけだから、さぞかし本人も楽しかっただろう。
(先輩ってば、趣味悪いわ……!)
と、優香は溜息を漏らす。
たぶん、綾小路君が優香に好意を抱いているのを知っていたからこそ、彼女の告白作戦を後押ししてくれたのだろう。
優香が嫉妬していた五上さんについても、綾小路君は説明してくれた。
「あの方とは母の華道教室で顔見知りになりまして、それ以来、好意を持ってくれているのか……なぜか、ずっと僕を追いかけてくるんですよね」
「ああいう和風美人に好かれたら、男性はうれしいものじゃないんですか?」
「まぁ……世間的には美人なのかもしれませんが、母の教室の生徒さんというのもありますし、残念ながら全然そういう感情は持てなくて……」
言われてみれば、母親絡みの知り合いというのは彼も息苦しいのかもしれない。
「だから茶道のこと、ずっと秘密にしていたんです。茶道教室にまでついてこられたら、さすがにちょっと」
「なんでバレちゃったんですか?」
尋ねると、綾小路君はうんざりしたように表情を曇らせると、グラスに残っていたビールをぐいっと飲み干した。
「……この前の花展、終わったあとに石田さんと食事に行ったじゃないですか。あれを、彼女に見られていて」
「なんだか、探偵みたいですね」
「そうなんです! 昔、アイドルの追っかけやってたとかで情報網も機動力もハンパないんですよ。それで、お花の時に詰め寄られて……僕も嘘つくのイヤだから、言っちゃったんです。『好きな人がいる』って……そしたら、茶道についてきちゃって……僕も、母の教室の生徒さんだから無下にはできなくて……」
「え?」
優香は、すぐには彼の話が理解できずにいた。
(花展のあとに、食事したのは私……で、五上さんが嫉妬して茶道教室に? ってことは、綾小路君の好きな人って……)
一巡してようやく、彼の想い人が自分であることに気づく。
頬を赤らめる優香に、綾小路君は慌ててフォローを入れてきた。
「あ、スミマセン! 石田さんが、僕にそういう興味がなくても全然かまわないんです! 僕は、五上さんみたいにストーカーになったりしませんから!」
「えっ、それは、つまり……」
「あの……さっきからずっと同じことばかりで恐縮ですが、一目見た時からずっとステキだと思っていまして……茶道でご一緒させていただいて、お話もすごく面白くて……苦手だった正座とか袱紗さばきとか、一生懸命練習されていたのを見て……僕、すごく感動したんです」
「あ、ありがとうございます……!」
「すごくひたむきで、なんにでも一途なあなたのこと、いつの間にか忘れられなくなって……ただの興味じゃないんです。もう少し、きちんと石田さんと向き合いたいな、と思い始めて……」
しどろもどろになっている綾小路君は、やけに可愛い。
顔が真っ赤になのは、酔いのせいというわけではなさそうだ。
(……私、告白されてるの……!?)
優香は、自分がするはずだったことを相手から先にされたことに、かなり動揺していた。
(だって、綾小路君は私の日本文化のプリンスで……そんな馬鹿な!)
「それで、本題なんですが……友達としてでもいいので、一緒に休日に出かけたり、こんな風にお食事したりしていただけないでしょうか……? もし、ご迷惑じゃなければ……ですが」
律儀な人ゆえに、彼は居住まいを正してお辞儀をしてくる。
「え、友達って……?」
優香はそれまでかなり浮かれていたが、その言葉を聞いた瞬間、モヤッとした。
外人と付き合ってきた優香にとっての『友達』は、数多くの中の一人であって、日本で言うところの恋人でもなければ彼氏でもない。友達以上恋人未満のような微妙な関係も指すことから、優香はきっぱり首を横に振った。
「綾小路さん。私、友達じゃイヤです」
「え」
「友達じゃ、今とあまり変わらないじゃないですか? 私、もっと綾小路さんの色々なこと知りたいんです」
「色々なことって……?」
「恋人じゃないとしないことを色々と、です」
艶やかな笑みと意味深な言葉に、綾小路君は茹で蛸のように顔を真っ赤にした。
「あ、あの……それは、その……しかるべき順を追って、ですね……」
これまで付き合った男性にはない初々しさに、優香は苦笑いした。
(これは、リードしなきゃダメだ! このままじゃ、先に進まない!)
と、変な使命感に駆られる。
「わかりました! じゃあ、とりあえずレストラン出たらチューして、手をつないで、駅の改札で別れる前にまたチューしましょう!」
「え……! い……石田さんがそうしたいとおっしゃるなら、僕に異存はありません……というか、うれしいです……ハイ」
「じゃあ、決まりですね! 私は綾小路さんの彼女で、綾小路さんは私の彼氏。五上さんにお会いしたら、綾小路さんのストーカーは卒業してもらいます!」
綾小路君が自分を好きだという事実――まだ、両想いになったばかりで現実味が湧かない。
けれど、優香は基本的に一途なタイプ。自分の想いが一方通行ではないことを知った瞬間から、恋する乙女は大事な恋人を守る女戦士に変身していた。
「石田さんってば、大胆なんですね……! でも、すごく頼もしいです……! 僕、一生あなたについて行きます!」
キラキラした瞳で見つめてくる茶道男子・綾小路君に、なぜかこれまでに感じたことがない母性本能を刺激されてしまう優香だった。
ここは、青山にあるエステサロン。二人用の個室があるから、マッサージしながらおしゃべりできるのがお気に入りの理由だった。
優香と東条先輩は、寝椅子にくつろぎながら台湾式リフレクソロジーを受けていた。
「へー、男前じゃん、優香。あの草食系の綾小路君と、付き合うことになったんだー」
「まぁ……、まだチューしただけですけどね」
「自分からしたんでしょ? やっぱ肉食女子よね、アンタ」
呆れられたが、そのことを思い出すだけで優香はしあわせだった。
あの清純そのものの綾小路君が、優香を抱き寄せてキスをしてくれたのだ。その時のドキドキを思い出しただけで、おかずなしでご飯三杯いけそうである。
ニヤニヤしている彼女を見ながら、東条先輩が聞いてくる。
「……で? 今後のデートプランは?」
「ああ! 今度の連休に、京都にでも行こうって言ってくれて」
「いいわねー、いきなり京都でデート! オトナじゃん!」
「神社仏閣とか美術館、私あまり行ったことなくて……それを言ったら、あっちから誘ってくれたんですよね」
「いいんじゃない。優香も綾小路君が知らないこといっぱい知ってるでしょう?」
「そうですね。この前、外国の方にお花の説明をする機会があって、すごく大変だったらしくて。ぜひ、英語でのプレゼンとか教えてほしいって」
「よかったじゃん! お互い得意なことを教え合えるっていいねー……あぅ、イタタッ!」
東条先輩は、エステシャンの指先が弱っている内臓のツボに直撃したらしく、隣のベッドで悶え始めた。
――日本人なのに、ずっと目を向けずにこれまで知ろうとしなかった日本文化。
お点前や作法を覚え、背筋を伸ばしてきちんと正座してお点前すること、そのすべてが日本の文化を尊重することにつながっている。
海外文化大好きの優香にとって、最初は試練の連続だったけれど、振り返ってみて努力してよかった、と心から思う。
お茶室から始まった恋は、優香に色々なことを教えてくれた。心を落ち着けることも、目標に向かってがんばることも……そして、好きな人の価値観を理解し、共に尊重し合える深い愛情も。
(お茶も、綾小路君とのことも……これからも、全力でがんばろうっと!)
優香は目を閉じて、前よりも少したくましくなった自分の精神ににそう誓うのだった。








