[55]正座の私と、正座のボクは
 タイトル:正座の私と、正座のボクは
タイトル:正座の私と、正座のボクは
分類:電子書籍
発売日:2019/06/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:76
定価:200円+税
著者:笹川 チエ
イラスト:時雨エイプリル
内容
「アンタ、さくらのことが好きなんじゃないの?」
正座してお茶菓子を頬張る「お茶菓子部」の部長である私・西園寺智弥子は、後輩の桜庭さくらくんを目の前にすると不思議な気持ちに襲われていた。その正体に悩んでいたある日、弟の一言によって、私は唯一の特技であった「正座」をすることが出来なくなってしまい……。
卒業まであと少し。私だって―――背筋を伸ばして、正しく座って。あなたに伝えたいことがあるんだ。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1396256

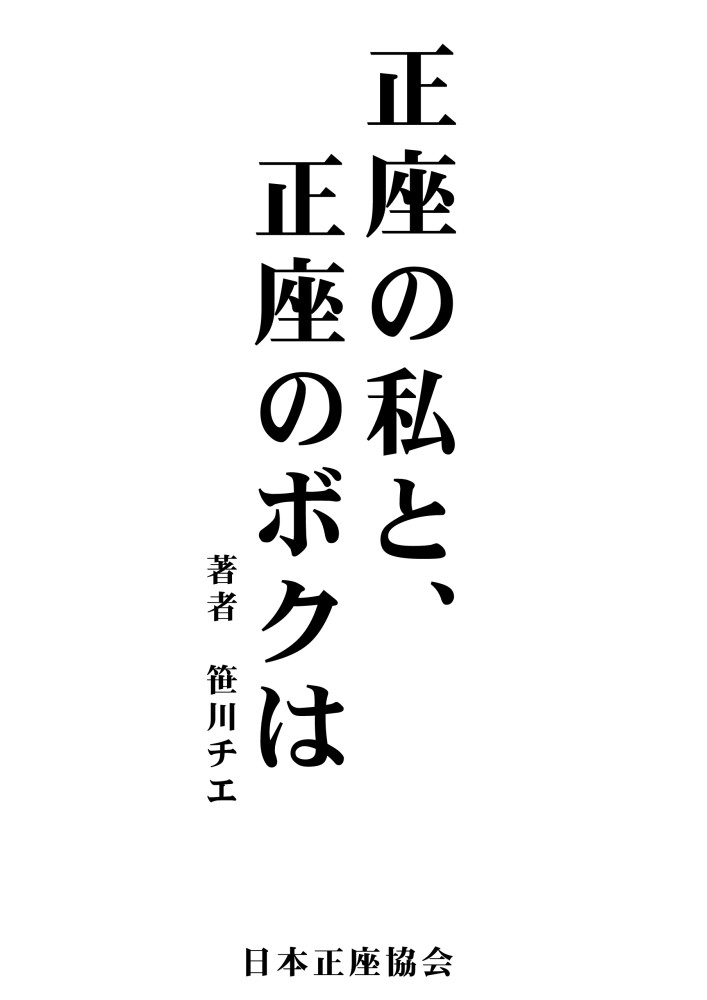
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
前を向くことが苦手だった。
いつも自信がなくて、何の取り柄もない自分が嫌いだった。そんな私の後ろを一生懸命ついてくる弟に、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。
気づけば、私は俯くことが多くなって。
だけど。
背筋を伸ばして、足を揃えて。
正しく座る、そのときだけは。
自分が「正しい自分」だって、思えるんだ。
2
「け、結婚っ?」
茶室に響いた素っ頓狂な声に、私―――西園寺智弥子は顔を上げた。それは隣にいたた東原千歳も同じのようで、私たちは、二人揃って彼を見つめることになる。
「そうなの。私たちに茶道を教えてくれてた先生、外国人のダーリンと結婚して、アメリカに行っちゃうんだって」
「怪我して入院してたっていうのに、何でそんな展開になるんだろうな」
「きっとロマンティックなドラマがあったんだよ」
「ろ、ロマンティック……」
「サクちゃんも欲しい? ロマンティックなドラマ」
「ひえっ」
またもや素っ頓狂な声。そのとき―――私と同じ三年生である秋山まどかと新垣陽一くん、そして千歳までもが、何故か私を見た。きょとんと瞬いている内に、三人の視線は再び彼の元へ戻る。
そう。素っ頓狂な声の主、桜庭さくらくんへ。
彼だけは私の方を見ず、ただひたすらに俯いて畳を凝視している。それでも背筋が伸びたままなのは、器用と言っていいものか。
「いいいいえっ、ぼ、ぼ、僕はっ、そんな!」
「動揺しすぎだってサク太郎」
「そうだよ気づけばもう私たちが卒業するからって」
「うっ」
「そうだぞ、さくら。気づけば何も進展できずにもう二月だからって」
「うう……っ!」
三人からのよくわからない畳み掛けを受け、彼の顔がどんどん赤くなっていく。頬から耳まで、おでこまで。
茹で蛸のようなその顔が嫌いじゃないことを、何故か私は誰にも言えない。
「まあまあ、落ち込むなって。俺のシュークリームやるから」
「た、食べかけ……」
「千歳、行儀が悪い」
「冗談だっつの」
窘めると、千歳―――私の弟は、むくれたようにそっぽを向く。
両親の離婚により今は名字が違うけれど、私たちが血の繋がった姉弟であることは変わらない。しかし、偉そうにされるのが気に食わないのだろう。私が何か言うたび、千歳は必ずむくれるか、拗ねる。
「しかめっ面するなよ千歳。本当はお姉ちゃんに叱ってもらえて嬉しいくせに」
「新垣先輩うるさい」
「チーちゃんそういうところあるよね」
「どういうところだよ一から説明してみろ!」
「けっ、喧嘩しないで……!」
……センチメンタルというのは、きっと今、この気持ちのことなんだろう。
胸が暖かくなって、楽して。でも、もう少しでこの時間は終わってしまう。その事実がとても寂しくて、切なくて。
……それでも。
今この瞬間、皆が正座をして。
お茶菓子を頬張って笑う皆が、私は何よりも大切だと、心の底から思える。
3
「お茶菓子部」と始めに呼んだのは誰だったのだろう。
正式な部活名は「茶道部」。茶道の先生がいる間、私とまどか、新垣くんは立派に茶道をしていた。
しかし足を骨折して入院した先生がいなくなると、私たち三名だけで立てるお茶は至極不味かった。とどのつまり、私たちは茶道部を続行することが出来なくなった。
そこで先生が帰ってくるまではお茶を立てることはやめて、代わりにお茶菓子だけはきちんと頂くことにした。もちろん背筋を伸ばし、足を揃え―――きちんと、正座をして。
決して、私が毎日お茶菓子を食べるための口実にしたわけではない。……決して。
そうしていると、春に桜庭さくらくんがやってきて。
彼が、東原千歳を連れてきて。
五人で正座をして、お茶菓子を食べて。
彼が背筋を伸ばして笑うことが、多くなって。
―――気づけば、終わりの春がやってくる。
「じゃあ、お茶菓子部は廃部?」
「えっ」
まどかのあっけらかんとした口調に、さくらくんは目を瞬かせた。一方、千歳は動じる様子もなく桜餅を頬張っている。右頬の方だけで噛んで食べる癖は治っていないらしい。
「だって、私たちが卒業したら、サクちゃんとチーちゃんの二人だよ?」
「部活として成り立つには三人必要だから、同好会になっちまうな」
固まったままのさくらくんをよそに、「『お茶菓子同好会』かあ」と千歳は関心が無さそうな声で言う。
「さ、『茶道同好会』じゃないかな……」
「サクちゃんとチーちゃんは、茶道一回もやったことないけどね」
「うっ」
「なんなら俺たちも出来ないし」
「そもそも、この茶室を使わせてもらってただけでありがたいもんねぇ。部活ちゃんとしてないのに」
「み、身もふたもない……」
そこで、さくらくんが私の方を見た。
見た、という表現は少し事実と違うかもしれない。ちらりと視線を向けるというか、こちらの様子を伺うというか。なんにせよ、私と目が合ったことに変わりはない。
そして、いつもの「不思議な気持ち」がやってくる。
正座をした足先が、じんと痺れるような、無性にかゆいような。背筋が必要以上にピンと伸びてしまうような。今すぐ目を逸らしてしまいたくなるような、でも、彼の目をずっと見ていたいような。
でも、いつだって目を逸らすのは彼の方からだ。
「ち、ちやっ」
真っ赤な頬と耳。彼は人と話すとき、いつも恥ずかしそうにする。私の前では、それ以上に。
「ち、ちゃっ、ちゃこ先輩、は」
下の名前で呼び合うようになったのは、夏が始まる少し前。だけど未だに彼は私の名前を呼ぶのが苦手らしい。「智弥子先輩」と呼びたいらしいけど、舌が滑って「ちゃこ先輩」になっている。最後に「智弥子先輩」ときちんと呼べたのは、十一月八日、私の誕生日のときだった。
「嫌、ですか」
「え」
ぼおっとしていて、さくらくんの話の意図を掴めなかった。彼は泳がせていた視線を、おずおずと私に向ける。気遣う瞳の色だと、私はようやく気づく。
「ちゃこ先輩は、この部が無くなったら、嫌ですか」
どうしてだろう。
どうして彼が優しくしてくれると、背中までむず痒くなるんだろう。他の女の子にもこんなに優しいのかと、聞いてしまいたくなるんだろう。
残ったシュークリームを頬張る。甘いクリームが口いっぱいに広がる。
「……私は……」
彼の問いにきちんと答えられるように、私は考える。彼に誠実でありたい。嘘でありたい。
いつだって正しく座って、応えたい。
「私は部活だろうと何だろうと、さくらくんと千歳が楽しく笑ってくれれば、それでいい」
ぽかん、という音が聞こえたような気がした。もちろんそれは幻聴で、皆が小さく口を開けてこちらを見ているだけだ。
「……なに? 皆して」
「いやあ。西園寺のことだから、『お茶菓子の文化を絶やしてはならない』とか言うかなと思って」
「シュークリームはお茶菓子か?」
「そこはもう突っ込まなくていいんじゃないかな、チーちゃん」
まどか達が再び賑やかに話し始める中、彼は呆けた顔のまま私を見つめていた。
足先の痺れがじれったい。やっぱりおかしいなと思う。正座はもう何年も続けている。正しく座れていれば、足が痺れることなんてないはずなのに。
首を横に傾げると、さくらくんは慌てたように私から目を逸らした。その赤い顔も、卒業したら見られなくなってしまう。
ああ、そうか。
もうすぐ彼と、お別れなのか。
―――そう思うだけで、どうして胸が痛いんだろう。
4
「俺はどっちだっていいよ」と、あっけらかんに千歳は言った。
「さくらが『お茶菓子部続けたい』って言うなら手伝うつもりだけど、言わないなら俺は何もしない」
「……そう」
部活が終わって、空が橙色に染まる時間。私と千歳は、同じ帰路を歩いていた。今日は私と千歳、父の三人で食事をすることになっているからだ。
「久しぶりに弟と食事できて嬉しいだろう」と笑う父が、一番嬉しそうに見えたのを覚えている。
「そもそも俺がお茶菓子部にいるのは、さくらや姉ちゃんがいるからだし」
「……そうなの?」
「『そうなの?』ってアンタ……。あ、ちゃんと秋山先輩たちも好きだよ? でも、先輩たちだっていなくなるわけだし。俺としては、皆いなくなるのに部活続ける意味を感じないかな」
「……そう」
「さくらとは、四月からも一緒に昼飯食べられるし。まあ今年度みたいに同じクラスになれるかは、わかんないけど……どっちにしろ、放課後だって遊びに行けるし」
……何故かニヤニヤしながら視線を向けられた。
千歳はこうやって、たまにさくらくんに関することで優越性を見せつけてくる。そして私は決まって、そんな千歳の頬をぐりぐりと押さえつけたくなる。
でも、もうそんなことは出来ない。私たちはもう高校生になった。千歳の背は、あっという間に私を追い越した。
つい自分の手で高さを測っていると、千歳がいぶしんだ顔をする。
「……なに?」
「千歳、大きくなったなと思って」
「……今更かよ」
「昔は、ちょうど頭を撫でやすい高さだったのに」
「いつの話だっつの」
少し前まで、私は千歳の気持ちがわからなかった。
千歳は私のことが嫌いなんだと思っていた。それだけのことをしたのだと、私もわかっていた。
でも、そうじゃないって。そう思って何も言わないのは、とても、悲しいことだって。
さくらくんが、私たちに教えてくれた。
今はときどき、千歳の気持ちがわかるようになった。拗ねたように口を尖らせているけれど、これはおそらく、照れている。
「ふふ……」
「なに笑ってんだよ」
「別に」
「なんだよ、言えよ」
「言わない」
「ケチ」
例えば、千歳が歩いているときも背を曲げなくなったこととか。あの茶室で隣同士、一緒に正座をできることとか。
そういうことが、とても嬉しい。千歳という弟の存在を、私は諦めようとしていた。だけど今、この子は私の隣を歩いてくれている。
それも全部、彼の……。
「……千歳は……」
「なんだよ」
「さくらくんを見ると、どんな気持ちになる?」
「……は?」
きょとんとした目。なんだかあどけなくて、ランドセルを始めて背負ったときの千歳を思い出す。
「どんな気持ちって何だよ」
「質問してるのは私なのに」
「意味がわかんねぇって言ってんの」
「……こう……不思議な気持ちになったりする?」
「はあ?」
「だから……」
いざ口にしようとすると、どう表現するのが正しいのかわからなくなってしまう。更に言えば、何故か気恥ずかしさが込み上げてきている。一体どうしてだろう。この話はやめた方がいい? でも、本当に何故か、千歳に聞いてほしい気持ちもあって。
「さくらくんのことを考えると、正座していても足が痺れるような感覚になったり」
「……正座がヘタになったってこと?」
「……落ち着かなかったり」
「……ほお」
「そわそわしたり……」
「『落ち着かない』と『そわそわ』は大体一緒だ」
「……胸がぎゅっとしたり……」
「…………」
「目を合わせるのがやけに恥ずかしがったり……」
「…………」
「……千歳?」
黙り込んだ千歳の顔を覗き込む。「近い」と身体を軽く押される。
はあ、と千歳は大きな溜め息を吐いた。
「なんなの姉ちゃん。俺がさくらに、自分と同じ気持ち抱いてるとか思ってんの?」
「……同じ気持ち?」
「さくらは俺の親友だけど、それ以上は女の人が良いし、好みのタイプは姉ちゃんみたいな人だし」
「……そうなの?」
「さすがに冗談だよ突っ込んでくれ」
「……千歳、話の意図がわからない」
千歳が再び黙り込む。ジッと怪しむように私を見て、だけど数秒しないうちに二度目の溜め息を吐く。
「……マジで気づいてなかったのか。秋山先輩と新垣先輩の言う通りかよ。隠してるつもりなんだと思ってた……」
「……?」
「あのさあ」
塞きとめる何かが外れたように、千歳は言う。投げやりにも、懸命に言っているようにも聞こえて。
「俺だって二人のこと応援してるつもりなんだよ。でもしゃしゃり出るのもアレだから、黙って見守ってたわけ」
「だから、話の意図が……」
「でももう無理だ。このままじゃアンタたち、二進も三進もいかないし。アンタが卒業してから、さくらがめちゃくちゃ落ち込むの見たくないし」
「あの、千歳?」
「その俺の想いを含めて、今から質問に答えるんだけど」
質問。そうだ。私は聞いた。
さくらくんを見ると、どんな気持ちになる? 不思議な気持ちにならない?
「―――アンタ、さくらのことが好きなんじゃないの?」
5
好き。
……とは、一体なんだろう。
「おーい、チャコちゃん?」
お茶菓子はもちろん好き。大好きに決まってる。私のライフワークと言っていい。今日も厳選に厳選を重ね、ご用達の和菓子屋さんで桜餅を買ってきた。もちろん美味しい。帰りもまた寄ろうと思う。
「おーい、西園寺?」
お茶菓子部の皆も好き。まどかは私と正反対で、「天真爛漫」という言葉が似合ってる。いつも笑顔で私たちを明るくさせてくれる。新垣くんはサバサバしていて、いつも正直に言葉を返してくれる。「でも褒められると超照れて否定するんだよ。超可愛いよね」とまどかが言ってた。
「……ねえ、ヨーちゃんどうしよう。チャコちゃん、部室に来てからただ黙々と桜餅を食べてる」
「まぁ、西園寺が桜餅を買ってくるときは、サク太郎のこと考えてるときだからな。大方原因は予想がつく」
「それはそうだけどー。もう桜餅五個も食べちゃってるんだよ? いつもよりハイスピードすぎるよ。どうしてチャコちゃんはこんなに痩せてるんだろう。羨ましい」
「お前はもうちょっと太っていいぐらいだぞ。健康でいてくれ」
「ありがとうヨーちゃん! 優しくて好き!」
「はいはい。俺も単純なまどかが好きだぞ」
好き、という単語に私は顔を上げる。勢いよく上げたものだから、二人がぎょっと目を見開く。
そうだ、この二人なら教えてくれるはず。千歳が私に言った言葉の意味を、知っているはず。だって二人は……。
「二人とも、教えてほしいことが」
「ど、どうしたのチャコちゃん」
「顔が怖いぞ西園寺」
「好きって、どういう―――」
「お、遅れました……っ!」
ガラガラと横開きの扉を開けて、彼は前のめりに部室へ入ってくる。続いていつも通りのんびりと千歳が入る。走って来たのか、彼はぜぇはぁと肩で息をし、顔がすこぶる赤い。
「遅れるも何も、お茶菓子部はいつだって自由参加だよサクちゃん」
「なんだ、走って来たのか? 廊下は走ったら駄目だぞ」
「ちゃんと早歩きして来ましたよ。さくらが顔赤いのは―――」
彼と、目が合う。
真っ赤な頬。自信なさげに揺れる瞳。もう何度も見合わせた表情。
―――アンタ、さくらのことが好きなんじゃないの?
「…………」
「……? チャコちゃん?」
……どうしよう。
どうしよう。どうしてしまったと言うんだろう。昨日と何も変わってない。千歳と話しただけだ。彼と話したわけじゃない。今も目が合っているだけ。鼓動がうるさいだけ。足がビリビリと痺れるだけ。
ああ、私は今、酷い顔をしているのではないだろうか。そんな顔を彼に―――さくらくんに見られるなんて、そんなの。
「……えっ」
さくらくんの驚く声が聞こえる、続いて他の三人も「えっ」と言う。どうしたんだろう。私は俯いてしまって、誰の表情も見れない。食い入るような視線だけ強く感じる。どうか今の私を見ないでほしいというのに。
「ちゃ、チャコちゃん……」
「あの、皆、あまり凝視しないで……」
「チャコちゃんの背中が、曲がってる」
えっ、と今度は私が声を上げる。曲がった背中。痺れて耐えきれなくなり、崩した両足。
そんな私を、皆が信じられないと言った目をして。
彼が一番、誰よりも目を見開いていて。
「チャコちゃんが、正座できなくなってる!」
まどかの言葉を、私はお茶菓子のようにすぐ噛みしめることが出来なかった。
6
背筋を伸ばして、と母は優しく言った。
家には畳の部屋があって、お茶菓子を食べる場所は必ずその部屋だった。私の座布団は花柄で、千歳の分は戦隊物のキャラクター柄。母の座布団は紺色の文字で、大人だなあ、格好いいなあ、と幼い私は思っていた。
母は和菓子が好きで、豆大福をよく買ってきてくれた。甘い餡子と豆の風味が口いっぱいに広がるのが楽しくて、私もすぐ好きになった。それを言葉にすると、母は嬉しそうに笑ってくれた。
ただ、母は優しいけれど、行儀だけにはとても厳しかった。お箸や茶碗の持ち方。内股になってはいけない。椅子に座ったとき、足をブラブラさせてはいけない。優しい口調でありながら、私と千歳は何度も姿勢を正された。きちんと出来ないと、お茶菓子は母が独り占めした。
特に正座になると辛かった。足が痺れるのに、足を崩しちゃいけないと言われる。背筋を伸ばしていたら辛いのに、背中を曲げたらいけないと言われる。私は正座が嫌いで、体育座りが好きだった。
どうして正座をしなきゃいけないの、私は母に聞いたことがある。すると、母は豆大福を飲み込んで、柔らかく微笑んだ。
「正座をすると、自分が正しいことをしてるって信じられるからよ」
まさかぁ、とそのときの私は思った。正座をしたぐらいで何故そうなるか、私にはさっぱりわからなかった。
―――だけど。
お茶菓子を食べるために、正しく座るよう頑張った。背筋を伸ばして足を揃えた。すると、だんだん足が痺れなくなった。
ちゃぶ台越しには母がいて、隣には千歳がいて。
私は、きちんと正座をして。
ああ、私は今。
この人たちの前で、正しくいられているんだと、思った。
7
「ち、ちゃこ先輩、背中が曲がってます」
「うん」
「あ、えっと、足の親指が離れてるので、重ねるかくっつけるか……」
「うん」
「せ、背中がまた曲がって……」
「うん」
「う、後ろにそり過ぎてしまってるので、あ、足に負担がかかるんだと、思います。重心は少し前に……」
「うん……」
「あの、背中……背中が……背筋は伸ばして、顎を引いて……」
「はい……」
「ごめんなさい生きててごめんなさい……」
「何でさくらくんが謝るの……?」
……背中が曲がってしまった、あの日以来。
私は、正座が上手に出来なくなってしまった。
最初は出来たように思えても、時間が経てば足が痺れてくる。ここ数年、正座をしてきて足が痺れたことは一度もなかった。どこかの姿勢が崩れている証拠だ。だけど、私はそれに気づけない。ハッとしたときには足がビリビリして、無理矢理立とうとした日には涙が出てしまいそうになる。
「特訓だね」と、まどかは言った。
「チャコちゃんがサクちゃんにしたように、特訓してもらえばいいんだよ」
「……誰に?」
「この流れで、サク太郎じゃないと思うか?」
えっ、と私とさくらくんは顔を合わせた。しかしすぐに逸らす。はぁと千歳の深い溜息が聞こえたのを、よく覚えている。
「ま、頑張れさくら。色んな方面から応援してる」
「い、色んな方面とは……?」
千歳の言葉に戸惑いつつも、さくらくんは承諾してくれた。そして、さくらくん以外の部員は何故か茶室からいなくなり、マンツーマンでの特訓が始まったのである。
結果はご覧の通り。二人きりだと考えると、ますます背中が縮こまる。顔が俯いてしまう。足が痺れてしまう。さくらくんが懇切丁寧に教えてくれても、そのこと自体がくすぐったくなってしまうのだ。
そんな状況が、既に二週間も続いている。
「ご、ごめんなさい。僕、教え方が下手で……」
「違う」と私は顔を上げる。ぱっちりと目が合って、互いに逸らしてしまう。
「さくらくんは、ちっとも悪くない。私が……」
私が、こんな風になってしまったから。
はっきりそう言えない自分がいることに気づき、私は驚く。そうか、私は今、正座を出来なくなってしまったことにショックを受けているのか。
たった一つの特技を、私は失ってしまった。
「あ、あの、ちょっと休憩しましょうか。ぼ僕、あの、コンビニで豆大福買ってきて……」
……さくらくんは、とても優しい。突然こんな状況になった私に、呆れることもなく付き合ってくれる。
優しいと同時に、不思議な人だな、とも思う。
初めて出会った去年の春。さくらくんは、人と話すのが得意じゃないようだった。いつも目が合わないし、背中が曲がっているし、俯いている。何度も言葉に詰まり、言葉尻は必ず萎んで小さくなる。
その反面で、人の話をきちんと聞いてくれる。その言葉を噛み締めて、考えて、自分なりに還元する。相手のためを、考えられる人なのだと、私は知った。
私と千歳のこともそうだ。距離が離れていた私たちのことを、「悲しい」と言ってくれた。私たちのためを思って泣いてくれた。私も千歳も、それが嬉しくて……とても、嬉しくて。
「……ち、ちゃこ先輩?」
「え、あ、はい」
「やっぱり、た、体調悪いですか」
「やっぱり?」
「え、ええと、顔が……その、ずっと赤い、から」
―――アンタ、さくらのことが好きなんじゃないの?
千歳の言葉が、ずっと頭の中で繰り返されている。
「(……わからない)」
さくらくんのことは、もちろん好きだ。でも、それは千歳のいう「好き」とは違う。それぐらい、私にだって理解できる。
まどかと新垣くんが思い合っているような「好き」を、私は経験したことがない。手を繋ぐとか、抱きしめるとか……好き同士の人たちは、そういうことをするらしい。それを、さくらくんとしたいかと言うと……。
「せ、先輩、また背中が……」
「ごめんなさい……」
「こ、こちらこそごめんなさい……」
熱い頬を抑えながら、私はどうにか背筋を伸ばそうとする。だけど、どうしても縮こまってしまう。
……さくらくんは、私のことをどう思っているのだろう。
この人は恥ずかしがり屋だから、基本的に誰の前でも顔が赤い。今だってそうだ。まどかの前でも、新垣くんや千歳の前でも……いや、千歳の前では、緊張しなくなっているように見える。やっぱり同じクラスだと一緒に過ごす時間も多いだろうし、話す時間だって私よりも多いんだろうし……。
「せ、先輩……?」
正体不明のモヤモヤが渦巻いていることに気がつき、かぶりを振った。何をひとりで考え込んでしまってるんだろう。さくらくんがいるというのに。
「……ごめんね、さくらくん。こんなことに付き合わせてしまって」
「え、い、いえっ、そんな……」
「……私には正座しか取り柄がないのに、恥ずかしい」
何の気なしに出た言葉だった。それは事実であり、私にとってごく普通のことのつもりだった。
―――それなのに。
「そんなことないです」
はっとする。顔を上げると、さくらくんと目が合う。だけど、今度は逸らされない。
まっすぐな声が、私の身体中に響く。
「そんなこと、絶対にないです」
眩しくて、目を細めた。
さくらくんといると、ときどきそういうことがある。本当に眩しいわけじゃないのに、ぱっと目の前が明るくなって。
だけど突然、彼は我に返ったように肩を震わせた。そしていつものように頭をペコペコと下げてくる。
「す、すすすみません、僕、偉そうなこと」
「……ううん。ありがとう」
首を横に振ると、さくらくんはホッと息を吐いた。気弱な表情は見慣れた彼のもので、私は何故か胸の中がふわふわと浮き上がる。
「ええと……あ、豆大福、食べますか?」
「……ごめんなさい。買って来てくれたのに申し訳ないけれど……正座が出来るようになるまで、お茶菓子を食べるのは我慢することにしたの」
「えっ!?」
「……そんなに驚くこと?」
「だだだ、だって、先輩がお茶菓子を食べないなんて……せ、先輩死んじゃう……」
「……さすがに死なない」
「で、でも」
「お茶菓子部は、正座をしてお茶菓子を食べる部活だから。正座ができないと食べる権利はない」
「そ、そんな厳しい部活でしたっけ……」
「家では食べてるから大丈夫」
「家では食べてるんですか……」
「……だって家は部活じゃないから……」
「そ、そんな拗ねた顔しないでください……」
……もうすぐ、こんな時間も来なくなってしまう。あと一ヶ月もすれば私は卒業し、さくらくんと話すどころか、会うこともなくなるだろう。もちろんときどきお茶菓子部のメンバーで集まることはあるかもしれない。だけど、こうして毎日のように、さくらくんと言葉を交わすことはできなくなる。
想像するだけで、とても悲しいと私は思う。そんなのは嫌だと、言いたくなる。
でも、私は正座が出来なくなってしまった。彼に正座を教えてきた、私が。
情けない。申し訳ない。恥ずかしい。でも、こうして一緒にいてくれて嬉しい。矛盾した気持ちばかりが、ずっと胸に渦巻いてる。
「(私は……)」
俯いて、スカートの裾を握る。
「………………」
自分のことにせいいっぱいで、私はさくらくんの揺れる視線に気づかないのだった。
8
「……さくらくん、背伸びた?」
「えっ」
結局正座が出来ないまま夕方になり、私たちは帰路に着いていた。肩を横に並べ、私とさくらくんは二人で歩いている。
私は手の平をかざし、自分と彼の背丈の差を図ってみた。さくらくんは落ち着かない様子で目をウロウロさせている。
「昨日よりも大きくなった気がする」
「き、昨日とはそんなに大差ないかと思います……」
「でも、去年よりは大きくなってるはず」
「そ、そう、ですか? 自分ではよく……」
「うん、あとは、多分……」
「多分?」
「背筋が伸びた」
「あっ」
そういえば、この間も千歳と同じようなやりとりをしたなあと思う。それこそ、あの言葉を言われたときだ。……また頭がこんがらがりそうで、私は頭を振る。
一方さくらくんは、小さく俯いた。だけど、それは悪い感情のせいではないようだった。
「……そっか」
呟いた彼の笑みに、私は目を奪われる。
満面というわけじゃない。小さく、柔らかく、とても嬉しそうな笑顔。
そうだ。初めて出会った彼の背筋は、いつも曲がっていた。笑うことも滅多になかった。
自分のことが嫌いだと、彼は言った。
今は、どうなんだろう。背筋が伸びた。背も伸びた。正座も、きちんと出来るようになった。
さくらくんは、さくらくんのことを好きになってくれただろうか。
「さくらくん」
「は、はいっ」
「……お茶菓子部に入って、よかった?」
「…………え」
「この一年間、私たちと一緒にいて、楽しかった?」
そんなことを聞くつもりじゃなかったのに、気づけば口に出ていた。
歩いていた足が止まる。彼と目が合う。
もうすぐ三月だというのに、日が沈むのは早い。既に橙色が隠れ始め、夜が訪れようとしている。
「……僕は……」
彼が、自分の服の裾を握る。言葉を、真剣に選んでいるのだとわかる。
「僕は、お茶菓子部に入ってよかった」
さくらくんは、いつだって真剣に私たちと向き合ってくれる。
「皆と一緒にいて、すごく、すごく楽しかった」
せいいっぱいの気持ちで、踏み出してくれる。
「皆と……」
背筋を伸ばして、伝えてくれる。
「あなたに、出会えてよかった」
優しい声が、胸の奥に響く。足先までやってきて、じんと痺れる。
さくらくんは、「ごめんなさい偉そうなことを」と言わなかった。頬を真っ赤にして、我慢するように唇を噛みしめていた。
その意味を、私はちゃんと汲み取らなければいけない。
「わ……」
私も、あなたと―――。
そのとき、トラックが傍の車道を通った。ブオオオンと大きな音を上げるものだから、私もさくらくんも肩を盛大に震わせた。
……トラックが見えなくなって辺りが静かになると、急に目を合わせていることが気恥ずかしくなった。二人して、慌てて視線を逸らす。
「か、か……帰りましょうか」
「……うん」
さくらくんの顔は、その日別れるまでずっと赤かった。きっと、私も同じようなものだったのだろう。
9
『つまりチャコちゃんは、サクちゃんが好きかもしれない! ってなって、どうしよう! ってなって、心も身体もパニックになってるから正座が出来なくなっちゃったわけだよね』
さくらくんとの正座の特訓が始まってから、私は毎夜、まどかと携帯で電話するようになった。
特訓の間、まどかと新垣くん、そして千歳は何故か部室に来ないようにするという話になり、放課後は会わない日々が続いている。その代わり、毎日のようにまどかから電話をくれるようになった。特訓のことや、新しいお菓子のことをよく話す。
「……大体そんな感じ、かな」
『サクちゃんも情けない男だよね。それなりに察して、チャコちゃんに応えてくれたらいいのに』
「応えてって……さくらくんは私のこと、そういう風には見てないと思うけど」
そこで不自然な沈黙があった。この間、千歳と二人で帰ったときの空気にとても似ている。
『そもそもさあ、チャコちゃんはどういうことだと思ってたの?』
「……何が?」
『私とヨーちゃんって、サクちゃんのことよくからかってたでしょ? チャコちゃんに見惚れてるーとか、好きなくせにーとか』
「……うん」
「その時点で、チャコちゃんは何か感じるところはなかったの?」
「……小粋なジョークかと思って……」
『小粋なジョーク!』
まどかはゲラゲラと笑った。彼女の素直な笑い方が好きだなあと思う。
私は笑うのが下手だ。というか、表情を動かすことが得意じゃない。「西園寺さんって無愛想に見えるけど、ただ天然なだけだよね」とよく言われる。……天然と言われる理由は、あまりわかっていない。
携帯を耳につけたまま、自分のベッドに寝転がる。すると寝巻きのシャツがめくれて、おへそが丸見えになった。こういう姿を、さくらくんには絶対見せられないなと思う。
『チャコちゃんって、そういうところあるよね』
「そういう?」
『サクちゃんに似てるところ』
「……私と、さくらくんが?」
初めてそんなことを言われた。さくらくんはとても良い子だ。優しくて真面目で、正座だってちゃんと出来るようになった。私なんかと似ているところは無いと思うのだけれど……。
と、ありのままを伝えたら、まどかは苦く笑った。
『そういう、自分に無駄に自信が無いところが似てる』
「……無駄に……」
『チャコちゃん綺麗し、可愛いし、面白いし。お茶菓子のことになると誰よりも知ってるのにさ。自分には正座しか誇れるところがない、とか言うし』
「……私ぐらいのお茶菓子の知識なんて、誰でも」
『似たもの同士だから、惹かれるのかも』
まどかの自分のペースで喋り倒すスタイルは嫌いじゃない。いつも私が思いもよらないことに気づかせてくれる。
『二人ともさ、自信はないけど、人に嫌われたくないでしょ?』
「……、うん」
パジャマの裾を引っ張り、おへそを隠す。
『チャコちゃんは今、サクちゃんに特別な気持ちを持っちゃった。それで「サクちゃんに嫌われたくない」って思いが、バンバンに膨れ上がっちゃった。だから緊張して正座が上手く出来ないんじゃないかな』
「………………」
『チャコちゃん?』
「まどかはすごい」
『なんで?』
「私が延々と考えていた原因を、いとも簡単に見つけ出した」
『不器用なのは間違いないからねぇ、チャコちゃん』
それもチャームポイントなんだよ、とまどかは笑う。だけど、私はやはりそう思えない。
今でさえ、さくらくんを困らせている。嫌われたくないはずなのに、こんなことになっている。もしこのまま正座が出来ず、卒業式を迎えたら……。
「……どうしたらいいんだろう」
弱々しい自分の声に呆れてしまう。こんな私は、やっぱり好きじゃない。さくらくんだって、正座すら出来なくなった私なんか―――。
『素直になればいいんだよ』
まどかは、きっぱりと言う。
『なんにも怖いことなんてないんだよ。俯く必要なんてない。チャコちゃんは、チャコちゃんのままでいいんだよ』
大丈夫と、まっすぐに言ってくれる。私はまどかと出会えてよかったと思う。
『私ね、お茶菓子部にいてよかったもん。正座して、皆でお茶菓子食べて、たくさんお喋りして……ヨーちゃんと喧嘩したときもあったけど、皆が背中を押してくれた。そういうの全部、チャコちゃんがお茶菓子部として、あの場所を作ってくれたおかげ』
『そんなめちゃくちゃすごい私の親友が、自分を信じちゃいけないわけないんだよ』
10
その夜、「卒業式まで特訓は中止」という連絡が新垣くんから来た。
「……なんで新垣くんから?」
『いろいろ係が決まってるんだよ』
「係……?」
電話越しの新垣くんの声は、いつもより優しい感じがした。もしかすると、私の前にまどかと電話していたのかもしれない。
でも、私は困った。特訓が中止になると、正座もできない私はあの茶室に行く資格がなくなってしまう。そう言うと、「お前、無駄に真面目だよなあ」と新垣くんは朗らかに笑った。
『特訓はもういらないって、まどかが言ってたからさ』
「……よくわからない」
『ま、俺も西園寺には感謝してるからさ。良いお立ち台を用意するよ』
やはりよくわからない。素直にそう言うと、新垣くんは「嘘つけ」と笑う。
『西園寺は不器用だけど、頭がいいよ。だからいつだってお前は、正しい言葉を見つけられるんだ』
「……正しい、言葉」
大丈夫だよ、と言う新垣くんの声は、とびきり優しい。
『だからあとは、西園寺が決めるだけなんだよ』
11
自分で決めるということを、あまりしたことがない。
何事にも不器用であることは自覚していたから、自ら積極的に何かを行うことをしなかった。その反面お茶菓子という自分の好きなものに情熱をかけているけれど、あくまで趣味の範囲だ。
そんな人生の中で、自ら決めたことがある。
私は、自分の弟を突き放すことを決めた。「一緒にいたい」と言ってくれたのに、離婚する母に弟を任せ、私は父について行った。
本当に正しい選択だったのか、私は何度も考えた。弟の泣きじゃくる顔を思い出すたびに、俯いてしまいそうになった。
それでも、背筋を伸ばした。
足を揃えて、膝を合わせた。顎を引いて、正しく、まっすぐに座った。
「正座をすると、自分が正しいことをしてるって信じられるからよ」
ただ、それだけで。前を向くだけで。
私は、私を。
12
「卒業おめでと」
式は滞りなく終わり、廊下や校庭で皆が泣きながら抱きしめ合う時間。
一年生は卒業式に参加しなくていいはずなのに、千歳は制服姿で現れた。そして無骨に私へ花束を突きつけてくる。ピンクと白の薔薇だ。千歳が選んでくれたのだろうか。
「……こんなの、わざわざいいのに」
「素直にお礼言って」
「……ありがとう」
「……どういたしまして。それじゃ行くぞ」
「えっ」
どこに? と聞く隙もなく、千歳は私の手首を握った。数年前なら、きっと私の手を取ったのだろう。でも私たちはもう高校生で、私は高校すら卒業した。昔のようにはいられない。
千歳を突き放したあのときは、もう二度と、触れることさえ出来ない覚悟した。だけど、彼が千歳くんをつれて来てくれた。
私の手首を引っ張りながら歩き出した千歳の背中を見る。大きくなったなあと思う。
「……千歳、一体どこに」
「あのさ、言っておきたいことがあるんだけど」
「……なに?」
「オレ、あんまり正座好きじゃなかったんだよね」
「えっ」
露骨に驚いてしまう。千歳が正座をどう思っているかなんて聞いたこともなかったが、お茶菓子部にいる以上、正座が好きなのだろうと勝手に思っていた。
「背筋まっすぐにするのシンドイし、疲れるし。オレは寝転がりながら、だらだら菓子食うのが好きだったし」
「……それは……」
「でもさ」
千歳は私へ振り向かない。優しい声だけが、私にやってくる。
「オレがちゃんと正座したら、姉ちゃん喜んだし、嬉しそうに笑ってくれたじゃん。同じ姿勢で、一緒にお茶菓子食べてくれたじゃん」
「…………」
「オレは姉ちゃんの前で正しくいられてるんだなあって、嬉しかった。だから正座が好きになったし、自分のことも好きになれた」
千歳が立ち止まる。
いつもの茶室―――私たちの、部室の前で。
「だから姉ちゃんも、自分が正しいと思うままでいてよ」
「……千歳」
「姉ちゃんは、きっと、何も間違ってなったんだからさ」
13
茶室に入ると、彼は正座をしていた。
「……さくらくん」
「ご、ご卒業、おめでとうございますっ」
さくらくんが、床に頭がぶつかりそうな勢いでお辞儀する。
正座をして、背筋を伸ばそうとする。だけど肩に力が入り、背中が曲がってしまう。誤魔化すように私もお辞儀した。
「ありがとう。……それ言うために来てくれたの?」
「あ、いえっ、あの、その、それだけじゃ、なくて、あの」
彼の目が左右上下にウロウロする。なんだか、出会ったばかりの頃みたいだ。懐かしくて思わず頬が緩む。そしてすぐに気づく。
彼とこうして向き合うのは、きっと最後になる。
「……さくらくん、今までありが―――」
「ずっと」
大きな、さくらくんの声が、茶室に響く。
正しく座る彼の背筋は、まっすぐに伸びている。
「ずっと、言いたいことが、伝えたいことが、あったんです」
初めて出会ったときのことを、覚えてる。
さくらくんは俯いてばかりで、おどおどしていて、自分のことが苦手だと言った。
その彼が今、私をまっすぐに見つめている。
「先輩は、先輩のことがあまり好きじゃないように見えます」
「………………」
「自分のことを『正座しか取り柄がない』って、よく、言いますよね」
「……だって、その通りだから」
思わず言うと、さくらくんは眉を下げる。そうだ。私が後ろ向きのときだと、彼はいつも悲しい顔する。
「……先輩は、優しくて、頭が良くて……」
「……さくらくん?」
「お茶菓子に詳しくて、好きなことに一直線になれる人で……」
言葉ひとつひとつが、ゆっくり私の耳に響いていく。
「『自分を好きになってほしい』と、僕に言ってくれた」
「……………」
「僕は僕が苦手だった。口下手で、俯いてばかりの僕なんて、好きになれるわけないと思ってた。だけど、先輩がそう言ってくれた。いっぱい優しくしてくれた。正しく座ることを、教えてくれた」
彼の言葉を、ちゃんと受け止めたくて。
背筋が、ぴんと伸びる。足を揃える。
「僕はずっと、ずっと、あなたに憧れていました。あなたのようになりたいと思いました。お茶菓子部に入って、皆とたくさん話して、笑って、泣いて、お茶菓子食べて……」
手は太ももあたりに。
「背筋を伸ばして、正しく座って、俯かなくなって」
顎を少し引いて。
「あなたの前で正しくいられる僕を、僕は好きになれた」
彼の目を見て。
「だから僕は」
私も、あなたの前で正しくいられるように。
「僕が好きな人を、悪く思わないでほしい」
恥ずかしくない、正しい自分でありたい。
「あなたに、あなたのことを好きになってほしい」
緊張した。逃げ出したかった。踏み出す勇気が、今までなかった。
―――だけど、私は。
「……いつも……」
声が震えた。
「いつだって、あなたは一生懸命だった。一緒に正座して、お茶菓子を食べてくれた。私のために怒ったり、泣いたりしてくれた」
それでも正しく座って、あなたに伝えなきゃいけなかった。何よりも伝えたいことがあった。
「それがすごく、すごく嬉しかった」
まどかと新垣くんの言う通りだ。私はただ、怖かっただけだ。自分で決めて、彼との関係が崩れてしまうのが不安だっただけだ。だから正しいことから目を背けて俯いた。
本当は、彼も同じ気持ちかもしれないと期待していたくせに。
「私は、あなたが好きだと言ってくれた私を、好きになりたい」
そうあってほしいと願うだけなのは、正しくない。
「私……」
彼が好きだと言ってくれた私は、正しく座る私だから。
「あなたと離れたくない」
さくらくんの頬が、赤く染まる。泣きそうな目が私を見ている。
「こうして、ずっと一緒にいたい。一緒にお茶菓子を食べたい。あなたの前で、正しい自分でありたい」
「せ、先輩」
「私はあなたのことを好きでいたいし、あなたにも、私を好きでいてほしい」
「す―――」
「だから……」
……だから?
そこで言葉が止まる。ふつふつと、自分の頬が熱くなるのを自覚する。
「……さくらくん」
「は、はい」
「状況を整理しましょう」
「はい」
二人で改めて背筋を伸ばす。それでもむずがゆい感覚は抜けない。
「さくらくんは、私を好きだと言ってくれました」
「あ、は、はい」
「私もあなたが好きだと言いました」
「は、あう、はい」
「つまり……」
「つ、つまり……?」
「つまりですね……」
―――そこで、ガラガラと扉の開く音がした。
「つまり二人は今から恋人同士ってことです!!」
「ひゃあっ!!」
まどかの大声とさくらくんの悲鳴が響き渡る。私も声なき悲鳴を上げつつ肩を震わせた。
状況を整理できないまま、茶室へまどかや新垣くん、そして千歳が入ってくる。もしかして、ずっと茶室の前にいたのだろうか。それってつまり。……つまり?
「ぬ、ぬ、盗み聞き……」
「言い方が悪いぞ、さくら。オレたちは二人を見守っていただけで」
「見てはないから、聞き守っていたって感じだ」
「こっそりだよ、こっそり。えへへ」
「それを盗み聞きっていうのよ……」
なんだか脱力してしまいそうになったところに、まどかがギュッと抱き着いてくる。彼女の頬も赤いことに、そのときようやく気づく。
「やったね、チャコちゃん。また正座できるようになったね」
「……うん。ありがとう」
「俺たちのおかげだな」
「そうだそうだ。礼を言ってくれ義理の兄ちゃん」
「義理の兄ちゃん……!?」
「だってオレの姉ちゃんの恋人になるんだから、さくらは義理の兄ちゃんだろ」
「い、いいいいいいえいえいえい、そんな!!」
「ノリいいなあ、さくら」
「その返し久しぶりに聞いたなあ」
まどかも新垣くんも、千歳も、笑っている。
私たちのことを、喜んでくれている。
……自然と背筋が伸びる。足を揃える。
皆が誇ってくれる、私であれるように。
「それでは、私たちの最後の部活動をしましょー!」
三人がぞろぞろと正座し始める。皆で円を囲むように座り、まどかは持っていた紙袋を突き出した。
「二人には内緒で、お茶菓子買っておいたの。桜餅と豆大福」
「ひえ」
さくらくんの顔が真っ赤っかになる。私の顔も多分同じくらい真っ赤っかだ。
「チャコちゃんチャコちゃん、どっちがいい?」
「…………」
「素直に桜餅って言え」
「千歳少し喋らないで……」
「俺は豆大福もらいな」
「じゃあ私もヨーちゃんと一緒!」
「オレは桜餅」
「ぼ、ぼ、僕は……」
「あと桜餅しか残ってないよサクちゃん」
「選択肢!」
私とさくらくんの前に桜餅がやってくる。彼と目が合い、つい逸らし、また互いを見る。どちらからでもなく、頬が緩んで笑い合う。
好きだと伝えられた。自分が信じた言葉が、彼に届いた。
きっとそれは、これからも私の背筋を伸ばしてくれるだろう。
「これでお茶菓子部も終わりかあ。寂しいなあ」
「え、サク太郎が部長じゃねえの?」
「そうなの?」
「……続けたい、です。とても、大切な場所だから」
「ま、さくらがそう言うなら、オレは手伝うけど」
「……そっか」
「姉ちゃん嬉しそうにすんな。顔がだらしない」
「これからはダブルデートができるね! あ、チーちゃんに恋人ができたらトリプルデートもできるよ!」
「早く姉ちゃん似の恋人作れよな千歳」
「新垣先輩ちょっと黙って」
……あまりにいつも通りの会話で、雰囲気で。私は吹き出して笑う。
この場所が大好きだった。思い出すたびに私は温かい気持ちになるし、寂しくもなるんだろう。
思いを馳せるたび、私は正しく座れる。そう信じられる。
「じゃあ、掛け声は次期部長に」
「えっ」
「頼むぞ、次期部長」
「オレは副部長頑張るから」
「え、ええと……」
「……お願いします、さくらくん」
さくらくんが私を見る。三人を見回す。
彼は俯かず、きゅっと唇を結んだ。手の平同士を合わせると、私たちも真似して手を合わせる。
「僕は……」
優しい、さくらくんの声。
「秋山先輩に、新垣先輩に、千歳に」
ゆっくりで、まっすぐな声。
「智弥子、先輩に」
一生懸命、伝えてくれる声。
「皆に出会えて、本当によかった」
背筋を伸ばした。皆が正しく座っていた。
それだけで私たちは、私たちが誇らしくて、大好きになる。
「―――いただきます」
五人の声と、正座が揃う。
身体中に温もりを感じながら、私は桜餅を頬張った。








