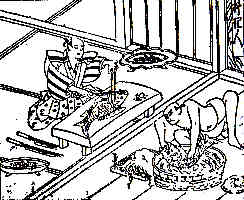――今では、私たちの“常識”になっていることも、
時代を少し遡れば、常識どころか、
逆に非常識だったことも珍しくありません――
文頭で、著者はこう語り、そして、
「反対に今、非常識とおもわれていることも、昔は常識だったことが沢山あるでしょう」
と述べた。
常識になるとほとんど意識をすることはなくなるが、少し考えてみれば出てくる、出てくる。
例えば、運動時の水分補給。
一昔前は、多くの人が、体力づくりという意味で水分を取ってはいけないと教えられて練習をしていた。
……と綴る私も、学生時代にこのような体験をしたことがある。
真夏の炎天下、熱を帯びた運動場は、ただ立っているだけで汗が出るほどだった。
そんな中、真っ黒の長袖・長ズボンのジャージを着こみ、“ひたすら体から水分を出すべく、運動を続ける”よう、先生に言われた。
水分補給は禁止。
とにかく“汗をかかなくなるための訓練”だからだそうだ……。
だが、それで汗をかかなくなったら、熱中症のできあがりだ。いや、これでは病院へ搬送されても、無事かどうか……。
……自分で書いておきながらゾッとする。
実際問題、これで命を落とした人間は、何人もいるのだ。(当然、現在は減少している)
でも、当時は仕方ない。
……いや、仕方ないというより、疑問にも思わなかったのだ。
「当たり前じゃないか、誰もがやっていることだ」と自信満々に言われたら、「そんなもんか」と、とりあえず納得してしまうのが人の性。(さらに、十代の学生時であったため、大人の一言には信頼性があった。)
とまぁ、以上は、現代だから分かる常識であり、当時は、現代の非常識が常識だったのだ。
他にも現在進行形で変わってきているケースがある。
例えば、ストレスで引き起こされる疾患の類が、「根性なしの病」などと言われていることだ。
確かに、昔はそう呼ばれていたのかもしれない。だが、この昔の常識(?)は、近年、医学によっても非常識と断定されつつある。
と、身の回りの常識・非常識の話はここまでにして、正座の話に移りたいと思う。
今回、本書の著者は、「正座」における常識・非常識の歴史を、教えてくれる。
沢山あるので、順番に紹介していきたいと思う。
まず最初は、脇息(きょうそく)の話である。
「『昔の日本人』が座るときに用いた補助具に脇息、つまり肘かけがあります。“肘かけに寄りかかる人”というと、江戸時代のお殿様を思い浮かべる人が多いかもしれません。――脇息には、贅沢な気分とリラックスできる両面があります」
この姿勢について、著者は、正座と比較して次のように述べている。
「脇息に寄りかかっているわけですから、自律的な姿勢ともいえる正座とは異なり、見るからに緊張感に欠ける姿勢ということもできます」
確かに、これでは緊張感は伝わってこない。むしろ、私には、この脇息を使うことによって、贅沢の極みのような雰囲気をかもしだいているように見える。姿勢1つで、人の印象とはずいぶんと変わるものだ……関心さえしてしまう。
著者は、そんな脇息の絵について、こう述べている。
「実は、脇息にもたれている肖像画は意外に多く、それはすべて公家などの身分の高い人です。室町時代中期の公家出身の連歌師で歌人の牡丹花肖柏(ぼたんかしょうはく)の肖像画も、脇息に肘をついて寄りかかり、右ひざは立てて座っています。――室町時代の身分の高さを示すステータスシンボル的な姿勢だったのではないでしょうか」
なるほど。どうやら、明治前後では正座がステータスシンボルのようであったが、この時代は脇息に立て膝のようだ。
やはり、後々形として残るものだけに、肖像画や写真はできるだけ美化して残しておきたいものだ……なんて思った。
私自身、脇息という言葉は初耳であった。
時代劇などにはよく使われていた気がするのでなんとなく想像がつくが、絵に描けと言われたら描けないほどのあやふやな記憶である。
そこで、実際に見て納得してもらうべく、イラスト登場。
脇息とは、このような肘置きなのだそうだ。
越後屋:「ささっ、お代官様、つまらないお茶菓子ではございますが、これからもごひいきに……」
悪代官:「ぐっふぁふぁふぁ……うまそうな山吹きじゃ。……越後屋、そちも悪よのぉ」
……という定番の会話が聞こえてきそうである。
いわずもがな、この悪そうなお代官の肘の下にあるのが、脇息である。やはり、これがあるのとないのとでは、贅沢さの迫力も違ってくるだろう。
次に、仏教と神道の姿勢の話がある。
ご存じだとは思うが、仏教はお坊さんで神道は神主さんである。
著者いわく、そのどちらもが正座をしていなかったのだという。
今では、お坊さんや神主さんが正座をしていないと、
「まぁ……仏(神)前ですのに……」
とか思ってしまう気もするものだが……主に私が、であるが。
だが、その理由を著者はこう述べている。
「江戸時代まではお坊さんはアグラ(楽座)か、立ってお経をあげることが多かったからです。念仏踊りに代表されるように、立ったり、時には踊ったりしながら説教しました。また、座ってお経をあげる場合も、正式には結跏趺坐の姿勢でした」
そういうことなのだそうだ。
お坊さんというと、いかなるときにも走らず、乱れず、座るとなれば正座をしているような気がしてしまう私であるが、少し前の時代では、そもそも正座ではなかったようだ。
一方、神道はどのような姿勢だったのだろうか。
「祝詞をあげる際、神主は瞬間的ないしはごく短時間、正座をすることはあったかもしれませんが、長時間にわたって正座をすることはなかったはずです。なぜそういえるのかというと、それはたとえば、神主の衣服を見るとわかります。袍(ほう)と呼ばれる神主が着る衣服は大きくて、ゆったりしています。これはアグラをかくことを前提にしていると考えられます。また、お祓いを受ける側も、基本的には正座をしていませんでした」
仏教はともかく、日本古来の神道も正座をしていなかったとなると、本当に正座の扱い方は、現在とはまったく異なることが分かる。
しかし、この服装
 |
| (袍。『写真譜・鶴岡八幡宮』鎌倉祭りより) |
を見る限り、私も正座というよりはアグラの方が適していると思える。
そして、かっこうがつく気がする。
更に、著者は正座の取り入れられた経緯をこう記している。
「寺院は伝統的に板間です。――しかし僧侶たちは、修身や神道の国教化改革に対抗するために仏事に伝統的な礼法を積極的に取り入れ、明治中期以降、板間に正座をするようになったと私は考えています。ちなみに僧侶の白足袋も、このころ普及し始めたものです」
これには少し驚いた。
板間であるのに正座を取り入れるとは、一種の修行も兼ねていたのだろうか。
心頭滅却!……とまではいかないだろうが、何やらそんな匂いがする気がするのだ。
こうして考えてみると、
「正座って、大まかにいえば、儀礼のためだけに我慢する姿勢なのかなぁ」
などという考えが浮かんできたりする。
……私同様、そんな思考をした方も、少なからずおられることだろう。
だが、本書記載の曹洞宗の開祖・道元が説いた結跏趺坐や半跏趺坐の話を読めば、少し変わってくるかもしれない。
道元は、結跏趺坐や半跏趺坐に関して、こう記したそうだ。
「尋常(よのつね)の坐処、厚く坐物を敷き、上に蒲団を用ゐる。或いは結跏趺坐、或いは半跏趺坐。謂(いわ)く、結跏趺坐は、先ず右の足を以て左のももの上に安(お)き、左の足を右のももの上に安く。半跏趺坐は、但(ただ)左の足を以て右のもも圧すなり」
著者いわく、「道元は降魔坐を説いているといえる」だそうだ。
だが、ポイントはそこではない。
著者は、この道元の前段の文に、興味深いところがあるという。
その文章は、次のことであった。
「座禅をするところには、まず厚い敷物を敷き、その上に蒲団を用いる」
これについて、著者は、以下のように解説をしている。
「坐物を厚く敷くのですから、文字どおり、かなり厚くなります。その上にさらに布団(これは今でいう座布団より硬い敷物)を敷くと、半ば椅子のようになります。そうした椅子に近い座の上で結跏趺坐ないし半跏趺坐をすると、足は下に少し垂れるような形になります。――すると、(結跏趺坐などは)かなり楽な姿勢になり、膝と股関節、腰への負担が減ります。お尻も楽だし、足がしびれることもほとんどありません」
そこで、それはいったいどのような姿勢になるのかと、適当な座布団で実際に行ってみたところ、確かに楽な姿勢であることが判明した。
少し前かがみになるような、座布団からずり落ちたような位置にお尻を乗せて、半跏趺坐などをするのである。
これは本当に楽に半跏趺坐をできる方法であるが、同時に
「ぇえー、こんなんでいいの?」
と、多少ごまかしているような気持ちも湧いてきた。
結跏趺坐の大仏像や僧侶が修行をしている様子を思い浮かべると、なおさらである。
この姿勢について、著者はこう述べている。
「医学的には、腰椎(ようつい)の第3番目を中心に、上半身が安定した楽な状態になります。これは、抗重力筋(頸椎(けいつい)や背中の筋肉)が最も自然に働く姿勢です。下肢もまったくしびれないため、不要な交感神経の高ぶりがなく、ゆっくりと瞑想することができます。道元は、楽な姿勢で瞑想を深く行うことを勧めていると思われます」
医学的なこともさることながら、私は、この著者の最後の言葉に道元の優しさをみた気がした。
いわれてみれば、何も座ることが目的ではないのである。祈ることや、瞑想に集中するために座るのである。
そのようなときに苦痛を伴う姿勢をしていては、集中も何もあったものじゃない。(並の人間であれば)
思い起こせば、この道元の発言は、本書の著者の発言にも似ている。
著者も一番最初に《お茶が大好きだが足を壊した患者さん》に、《正座をしなくても、お茶は楽しめますよ》と、言葉をかけているのだ。
内容は異なるし、その患者さんがどう受け取るかによっても違ってくるが、著者の言葉の思いやりというニュアンスとしては、上記の道元ととても似ているところがあると思う。
なんだか、文字を通して人の優しさが伝わってきたひと時であった。
そんな道元の曹洞宗についてもう1つ。
著者は、興味深い理由に椅子が関係しているという。
「古代に1回目の椅子の導入期があり、鎌倉時代には2回目の椅子の導入期がありました。鎌倉時代においてその役を担ったのは、曹洞宗や臨済宗といった禅宗でした禅宗を当時の中国である宋から導入する際、椅子も同時に入ってきたのです。――それらの肖像画を見ると、彼らは沓(くつ)を脱ぎ、椅子の上で足を組み合わせて座っている、つまり趺坐しているようです。曹洞宗における椅子は、腰をかけるものではなく、椅子の上に上がって趺坐するもののようです」
さて、今度は、著者は身近にあるものの座り方に正座を見たようだ。
それは、雛人形。
「内裏雛(だいりびな)といわれる男女一対の雛人形も、座り方を考える際、重要な資料になります。内裏雛のモデルは天皇と皇后という説が有力です――仮に内裏雛のモデルを天皇および皇后であると仮定すると、男雛は天皇、女雛は皇后になります」
確かに、そう仮定した上で考えてみると、実際の人物を真似ている人形であるから、よりその時代の座り方が反映されているのではないかと期待できる。
と、ここで、雛人形の座り方を見る前に、著者が男雛と女雛の並べ方を解説してくれている。
「現在では、向かって左側に男雛を置く家庭が多いようです。しかし、かつては現在とは反対に、男雛を向かって右側、女雛を向かって左側に置くことが多かったのです。――それは古来、日本では《左》のほうが上位だったことから分かります。――しかし、明治時代になって、それまでの伝統に変化が見られます。背景にあるのは《西洋化》です。ヨーロッパの国々では、国王などは右側=向かって左側に立ちます。脱亜入欧をめざす時の政府は、天皇や皇族の伝統も西洋式に変えようと試みます。その結果、古来の伝統を変え、天皇は右側=向かって左側、皇后は左側=向かって右側に立ったり座ったりすることになったのです。最初に右側に立ったのは大正天皇といわれ、その後に続く昭和天皇も今上天皇も、右側に位置しています」
当時の日本では西欧化の大きな流れがあり、その変化は、内裏雛にまで影響したのだという。
「男雛は左側=向かって右側、女雛は右側=向かって左側でしたが、明治以降、徐々に男雛は右側=向かって左側に、女雛は左側=向かって右側になっていったのです。ただし京都などでは、今も古来の男雛=左、女雛=右の伝統が続いているといいます」
なんだか、左右左右と目まぐるしい表現であるが、とにもかくにもそうなのだそうだ。
座る場所1つで位がまったく異なり、左右を入れ替えただけでそれまでの習慣が根こそぎ変わるとは、人の立ち位置とはなんと難しいものか……――。
さぁ、いよいよ著者は、その内裏雛の座り方に注目する。
果たして、アグラなのだろうか……?はたまた、正座なのだろうか……?
まずは、男雛だ。
「現在は、どちらもあるようです」
なんだかハッキリしなくて残念だが、現在の雛人形の種類は色々あるのでまぁまぁ納得できる。
「あるいは、楽座といわれる両足の裏をピタリと合わせる座り方も多く見られます。さらには衣服に隠れて《よくわからない》座り方をしている男雛もあります。また、脚を簡略化して、作っていない人形もあります」
なんということか。これでは、本当によくわからない。
脚を簡略化というのも面白い響きである。

  |
| (簡略化とは、このようなことだろうか。『雛人形と雛祭り』より) |
次に、女雛を見る。
「正座の女雛も見られますが、《よくわからない》女雛も少なくありません。なぜかというと、衣服に隠れて、どのような座り方をしているか外からは見えないからです。この傾向は男雛よりもあります」
残念だが、やはり、脚の形はハッキリとは分からないようだ。
見ればすぐに分かると思っていたが、言われてみれば、脚を出した雛人形などお目にかかったことがない。
だが、ポイと投げるにはまだ早い。
著者は、さらに雛人形の時代を細かく読み解いている。
時代ごとに順を追って見てみることにする。
「《寛永雛》は、その名のとおり、寛永時代に作られた雛人形です。寛永雛の写真を見ると、男雛は楽座のような格好をしています。対する女雛の座る姿勢はやはり見えない。しかし、中には綿が入っているようで、袴が膨らんでいます。このことから想像するに、アグラないしは楽座をしていても不思議ではありません」
「次に登場する主な雛人形は《享保雛》です。――男雛はアグラをかいているものが多く、女雛の脚はやはり見えないものが多い。とはいえ、女雛の袴はゆったりしていて膨らんでいるから、アグラや楽座の姿勢を念頭に置いて作っているのではないかと推察することができます。しかし、正座をしているのではないかと思われる享保雛の女雛も、わずかではありますが、確認することができます」
「享保雛に続いて登場する代表的な雛人形は《次郎左右衛門雛》です。《次郎左右衛門》は人の名で、京都の人形師・菱屋(雛屋)次郎左右衛門のことです。1761年ごろ(宝暦年間)――幾つかを見ると、男雛はアグラをかいています。右足が上になっているものも、左足が上になっているものもあります。女雛はというと、やはり衣装に隠れて、よくわかりません。しかし、袴が膨らんでいることから考えると、アグラや楽座をすることも可能だと思います。しかし、なかには正座をしているように見える女雛もあります」
「女雛の座り方に変化が見られるのは、《有職雛(ゆうそくびな)》からです。時期としては次郎左右衛門と雛と同じころに作られた雛人形です。公卿の装束を有職故実に基づいて、雛人形に仕上げてあります。――男雛を見ると、やはりアグラをかいているのが散見されます。しかし女雛は、これまでの次郎左右衛門雛までとは違って、脚の部分(左右)が狭いことに気がつきます。どう見てもアグラをかいていない、否、正座をしていると思える女雛もあります。なかには、男雛も正座ではないかと思われるものもあります。――つまり、宝暦年間あたりは、正座がされるようになってきた1つのターニングポイントになるかもしれません」
「有職雛に続く《古今雛》にも、明らかに正座をしていると思われる女雛を確認することができます。古今雛は主に明和年間(1764〜71)に作られています」
ここまでで、沢山の名前の雛人形が登場したが、あまり聞いたことのない名前ばかりであった。
こんなにも種類があるとは、知らなんだ。
そして、正座のらしき形を見て取れるようになってきたのは、実に説明の後半からであった。
著者も、明治〜平成と時代が下がるにつれて、正座をしている雛人形が増えてきます、と述べている。
古い時代から現代になるにつれて、どんどん正座が見られるようになってくるというのは、実生活での正座の移り変わりと照らし合わせても、理にかなっている変化だと思えるのだった。
著者は、雛人形の次に、福助人形を見る。
童顔、福耳、ちょんまげで「おこしやす」とばかりに少しかがみ、前面に微笑みかけている人形である。なんだか、同じ人形でもまったくの別ものである。
 |
| (福助人形『福助さん』表紙絵より) |
著者いわく、福助人形は裃(かみしも)をつけて座布団に座っていて、決まって正座をしているという。
雛人形で明確な事実が分からず、口惜しい気持であったが、言われてみれば正座をしている人形がここにあるではないか。
そして、著者は、この福助人形がいつから作られるようになったのかを知るには、福助とは誰なのかを考えることがポイントだと述べている。
著者は、具体的に誰だとは定まっていないと述べ、けれど最も有名な話があると、『福助さん』(荒俣宏編著、筑摩書房)から引用して考察の種にしている。
それは、次の文章だった。
「この大文字屋は頭が大きく、背が低かったが、店の宣伝につとめたのでたいそう繁昌した。そして貧民へのほどこしも忘れなかったので、人々がこの店主にあやかるようにと人形を作って毎日祈ったところから、今の福助人形が生まれたという」
著者は、
「荒俣氏は同書で、裃を着る習慣、座布団を敷いて正座する習俗、そして扇子を使用していることから、福助は江戸中期、それも後半に近いあたりに登場したと推測しています――福助伝説は、ほかにもたくさんあるようですが、興味深いのは、決まって正座をしている福助は、江戸中期以降に初めて登場したと思われる点です」
なるほど……たかが人形されど人形である。人の造る色々なものには、時代が投影されるのだな……と思った。
私もこの大文字屋の説には、本当にこれが福助の元祖かもしれないな……と、感じた。
つまり、江戸中期頃には福助のような格好をして商売をしていた人が、たくさんいたのか……。なんだか、とても和みそうな光景である。
さて、和むといえば、著者はくつろぎの空間(?)居酒屋での座り方についても述べている。居酒屋は、江戸時代中期ごろから存在しているようだ。
と、その前に、著者は江戸時代の居酒屋の在り様についてこう記している。
「時代劇などの影響か、その様子については多くの人が誤解しているようです。お燗をした酒を入れる容器は徳利ではなく、チロリという酒器を使っていました。これは、急須を縦長にしたような形をしていて、銅や真鍮(しんちゅう)で作られていました。燗徳利を普通に使うようになったのは、幕末期の嘉永期あたりからといいます」
確かに、江戸時代の酒器といえば徳利が浮かんでしまう。
某盗人が出てくる江戸を舞台とした人気アニメでも、確か徳利が出てきた記憶がある。
さて、では、その居酒屋やそば・うどん屋、料理屋では、どのような座り方をしていたのだろうか。
「歴史的資料を見ると、江戸時代の庶民的な酒場では、やや広めの縁台に座って、その縁台に酒とちょっとしたつまみを置いて飲み食いしていたことがわかります。――大きめの縁台に草履を脱いであがり、アグラをかいて飲み食いしている姿もしばしば見られます。正座をして一献傾けている絵もありますが、ごく少数です。少なくとも、庶民が外でちょっと引っかけるときに、正座をしていたとは思えません」
著者は、この理由に、徒歩をあげている。現代人とは違って、徒歩で移動してまわる江戸時代の人々の足の疲労はかなりのものだろうという推測である。
確かにすべてが徒歩なのに、それでいて座るときまで正座となると、足の疲労はとんでもないものになるだろう。なるほど、納得できる考えである。
更にそれにプラスして考えてみる。
その頃の庶民は裸足に草履であることから、その足は土やほこりに汚れていただろう。
そのため、縁台に座っていたのではないだろうか。
たまに時代劇のはたご(旅館)でも、下女が水の入った桶を持ってきて、客の足を洗ってあげてから座敷に通す場面も見られる。
 |
| (『大錦東海道五十三次 保永堂版』広重 (御油)より) |
宿に泊まることを「ワラジを脱ぐ」と言うことからも、この理由をプラスしても良いだろう。
「囲炉裏もくつろぎのスペースでした。――囲炉裏は暖をとるだけでなく、炊飯をはじめあらゆる煮炊きを行う場でもあります。――男性も女性もアグラをかいたり、立て膝をついたり、横座りや割座をしたりしていました」
思えば、囲炉裏の周りを正座で囲むなんていうことは、あまり想像できない気がする。囲炉裏の周りといえば、やっぱりアグラだろう。板間ということも関係してくるが、火を前にした穏やかな空間の前では、姿勢は正座ではないような……そんなイメージがある。
とまぁ、著者は囲炉裏について、炊飯や煮炊きを行う場でもあった=さしずめダイニングキッチンやリビング、作業場と記しているのだが、そうなると、必然的に作業は低めの位置で行われることになってくる。
著者いわく、その昔、料理は座ってするものだった。
「かつて日本では、まな板や流しはしゃがんで使うものでした。明治時代の東京でも、まだしゃがんで使う流しが一般的でした」
著者は、このことを立証するべく、鎌倉〜江戸時代までのいくつかの古い絵の例をあげている。
それらの絵に共通してみられるのは、どれも10cmほどの4本の足のついたまな板を使って調理をしているということだった。そこには、アグラもしくは立て膝の人間が描かれており、正座で調理をする光景は見られなかったという。
 |
| (『大錦東海道五十三次 保永堂版』広重(水口)より) |
 |
| (左下に調理をしている人がいる。 上図拡大画像) |
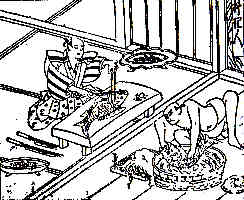 |
| (他にこのような調理風景もある。『人倫訓蒙図彙』【料理(れうり)】より) |
ただ、その調理の場所によっては例外があったようだ。
「江戸時代には、大勢のまかないがいる場合など、立って使う形式の台所もないわけではなかったようです」
その後、明治以降も、個人の家では低位置での作業が続いたようだ。
明治時代には洋風の文化も入ってきていることから、裕福な家庭では七輪の上にフライパンを載せて調理をしている絵もあるそうだ。
「この料理をするときの姿勢が変わったのは、大正時代です。料理も正座をして行うようになります」
それでも正座なのか……と思ったが、家の造り自体が変わらなければ、それは当たり前のことだと納得できる。
考えてみれば、すり鉢や大根おろしなどに使う道具などは、床で使う方が効率がいい気がするのである。実際、私の実家ではカーペットの上にアグラをかき、脚の間にすり鉢を挟んで安定させ、ゴマなどをすっていた記憶がある。
そのような昔からある道具は、現在もあまり形を変えずに存在しているのだな……と、しみじみと思った。
さぁ、話は調理から打って変わって、土下座である。
いったい、正座にどのような関係があるのだろうか。
著者は、こう記している。
「歴史上の土下座をする場面といわれて多くの人が思い起こすのは、大名行列を前に庶民が正座をしてひれ伏している場面でしょうか。―― 一説によると、庶民に土下座を要求できるのは、将軍や徳川御三家に限られていたといいます」
なんと、私にとってはいきなりの新事実である。
私のイメージでは、どこぞの誰かが「大名が来られるぞー!」などと叫び散らし、ふいに知らされた民衆は焦りながら道に土下座の列を作る。そして、大名を目前にして顔を上げようものなら「切り捨て御免!」などと、問答無用で罰せられるような、そんな恐ろしい印象ができあがっていた。
……ところがどっこい、真相はまったくの思い違いだったようだ。
著者は、それについてこう記している。
「『江戸名所図会』に描かれている東海道の大名行列では、旅人たちはよけて見送るか、一緒に歩くかで、土下座している人は見当たりません。――また、行列前には田楽や甘酒、寿司などの食べ物屋が店を出したり、大名行列見物のガイドブックに相当する本も売られたりしているなど、大名行列を取り巻く状況は意外にのどかな雰囲気もあったようです」
事実は小説より奇なり……とは、よくいったものだ。
となると、私が今までTVで観てきた時代物は、一種のエンターテイメントと考えた方がいいのだろうか、否、そうなのであろう。ガイドブックまで出ているとは、恐れ入った。
さて、話を土下座に戻そう。
著者は、正座との関係についてこう記している。
「土下座と正座とは、形がとても似ています。そのためか、正座は罰の一面も併せ持っていたのです」
これは、よく聞く話である。
悪いことをして反省する側としては理にかなった姿勢であると思うが、これを変化させて痛い罰にするといのは、正座の効能(?)・精神性を説く者にとっては、どうにも残念な気持ちになってしまうのだった。
「江戸時代の裁判は、奉行所内の白洲(しらす)で行われました」
 |
| (白洲の写真 岐阜県高山市高山陣屋より) |
白洲とは、この白い砂利のことをいう。
容疑者は、この砂利の上で正座をさせられたのだそうだ。……これだけで心が折れそうだ。
また、『徳川幕府縣治要略』という絵には、裁く側の武士の中にも正座をしている姿があるように見えるそうだ。
「罪人に対する刑罰にも、正座は使われました。『刑罰大秘録』の中には、三角に削った材木を並べ、その上に罪人を正座させ、さらに石の板を膝の上に置き重ねるという拷問の様子も描かれています。これでは、仮に罪を犯していなくても、苦痛に耐えかねて、すぐに《白状》してしまいそうです。また、たとえ膝の上に石の板を置かずに、ただ正座させるだけでも、長時間に及べば、それだけでも十分に拷問になったのでしょう」
なんて痛い話であることか。
TVや新聞、人の話などでも、正座を使った刑罰の話をよく目・耳にしてきた。
でも、これは何か正座とは違う気がするのだ。知れば知るほど、そして、「正座のツライ思い出」として人の記憶に残るたび、ずっとそう思っていた。
だから断言したい。
刑罰に使われる正座という姿勢……これは、断じて正座ではない。
じゃあ、これはなんなのさと疑問が生じる。
これは……《正座とは似て非なる姿勢》である。
土下座と正座での頭の下げ方が似ているように、この刑罰の正座も形は似ているが、中身はまったくの別物なのである。
もっと細かくいえば、同じ日本語の読みでも、漢字で表すとまったく違う意味になるように、同じ姿勢でも中身のまったく違うこの姿勢は、私はに正座とは思えないのである。
これは、ただの苦痛を与える行為である。方法はなんでもいいのだ。
そして、より苦痛を与えたい彼らが思いついたのが、きっと、中でも“シビれという痛みの生じやすい正座を使って更に負荷をかけた姿勢”だったのだろう。これは私の推測であるが、そう思えてならないのである。
思うに、《叱るときに正座をさせる》という意味には、そのような下卑たものではなく、もっと良質な精神性が入っている。
例えるなら、正座をすることによって集中力が増すことから、自問自答を行い反省をさせる・促す……などである。
その過程で起こるシビれと戦わせて、我慢強くさせるということもあるかもしれないが。(無論、身体に悪影響が出ない適度な時間内である)
しかし、土下座と一色多にされては、正座も災難であるなぁ……仮にも、歴史上高貴な身分だけに許された姿勢であり、文化教養でもあったのだから……切にそう思う。
さてさて、土下座から離れ、今度は、正座を表す方言に注目したい。
著者いわく、アグラを示す方言はわずかだが、正座を表す方言にいたっては、ざっと100を超えるそうだ。
「全国的に見ると、同じ正座という姿勢をまったく相互に関連のない別の言葉で表現していて、各地域、文化圏にまたがる方言として残っています。いずれも、かしこまる姿勢を表現していますから、丁寧語の《お》がつくことが多いのが特徴の1つです。幼児語の《ちゃんこ》から始まり、《ひざ》《かしこまる》《ねまる》《きんきん》《つくばう》などの体の部位、姿勢に関連した表現や、姉、母、食事に関する表現、その派生語が多いようです」
なるほど、なるほど……。
著者が「正座の表現」をまとめてくれているので、見てみた。
北海道から始まっており、「おっちゃんこ」と、いきなりなじみのない表現である。
青森県にいたっては、「ひざをおる」である。
これは、ニュアンス的に分かりやすい表現だと思う。
だが、これはどうだろうか。
「ねまる(山形県・宮城県・新潟県)」
むしろ、寝相の名称だと言われた方が、「あぁ、あの丸まって寝るかっこうね」などと納得できる気がする……。
更に、これはどうだろう。
「おかっこまり(神奈川県)」
自分の住んでいる地域の方言なのに、まったく聞いたことがない言葉である。
いったい、どの世代までが使っていたのだろうか。
ちなみに、お隣東京は少し変わってきて、「おかっこま」となっている。
場所がずれるにつれ、少しずつ表現も変わってくるのが分かる。
「おかあさんずわり(愛知県・岐阜県)」という言葉も、なるほどと思える方言である。
多少気になるのが、京都になると「おかあさん座り」と漢字になることだ。ここにどんな思いが入っているのか、私には想像もつかない……。
そして、九州に進むにつれ、「ごちそうさんに座る(奈良県)」「いいおひざ(広島県)」「とんち(山口県)」「えーちゃんこ(島根県)」「おぎょうぎにすわる(愛媛県)」「おかじん(福岡県)」「きんきんじょう(鹿児島県)」と、変化していく。
北海道から比べると、鹿児島にたどり着くころには随分と変わったものだ。まったくの別表現であるにも関わらず、なんとなく正座を匂わせる言葉であるからすごいと思う。
しかし……これらの言葉、どうやって使っていたのだろうか。やはり、日常だろうか。そうとしか考えられないのだが、今となっては謎めいて思えて仕方ない。
親は、親戚を前にして、子供(仮に太郎と名付ける)に対し、
「太郎、ちゃんとごちそうさんに座りなさい」
などと言ったのだろうか。
親戚は親戚で、
「あら太郎ちゃん、いいおひざしてエライわねぇ」
もしくは、
「本当、太郎君もしっかりとんちできるようになったんだな」
とか声をかけていたのだろうか。
普通の会話ならまだいいが、正座ができていないと叱るときにはどんなことになるのだろう。
「こら、太郎!お客様の前では、きんきんじょうになさいといつも言っているでしょう!」
こうなるのだろうか。
他にも色々と気になる方言はあるが、まぁ、方言だからいいのだ。
隣の藩の言葉が異国語に聞こえたというその時代では、これが普通だったのだ。
まぁ、標準語と方言を混ぜて喋ることも滅多にないと思うから、上記のような楽しい会話はそうそう耳にできないだろうが。
……と、納得しつつも、まだ使っている地方があるのなら、ぜひ一度このような会話を聞いてみたくてしかたがない私がいる。
ちなみに沖縄は「ひざまんちゅー」と、とても沖縄らしい分かりやすい表現であった。
なぜか、少しホッとした。
そんな大量の正座という言葉の表現方法があるからこそ、
「明治になって、共通語として新しく《正座》という言葉を作る必要性があったともいえます」
と、著者はしめくくっている。
本当、そうである。その必要が大有りである。
明治維新になって、庶民が正座をするようになったときに、各々が好きな言葉で1つのことを表現したら、混乱を生むことは必至である。
そして同時に、標準語というものが作られたのも、この時期だったのであった。
※【標準語】明治23年(1890)に岡倉由三郎が『標準語』という用語を初めて使った。(デジタル大辞泉より)
さて、ここまでの話を正座を通してみて、少しでも常識・非常識の意識が変わっただろうか。
ちなみに私はというと、常識・非常識の境界線は少しあいまいなものになってきている。
だが、現在は本当に情報過多の時代である。
むしろ、常識・非常識もあいまいに、その2つの間で思考しながら揺れ動いているくらいがちょうどいいのではないかと思うのだ。
こればっかりは、白でも黒でもない、考え中の灰色という位置にいた方が、周りが広く見渡せるような気がする……と思う、今日この頃であった。
次回は、「正座の解剖」とともに、正座をみていきたい。