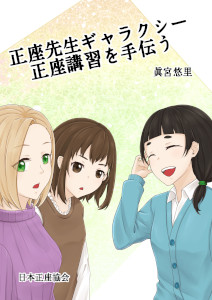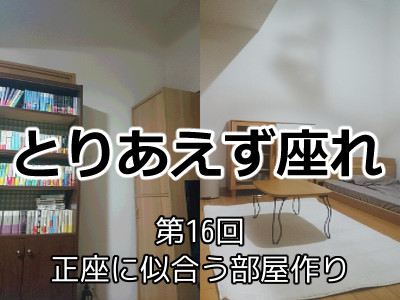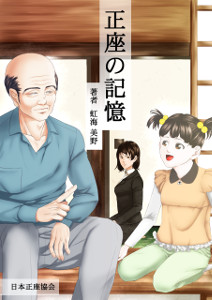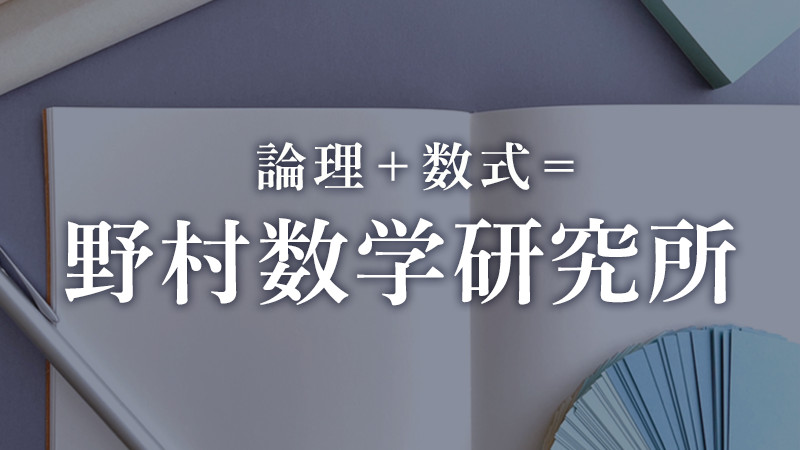[355]お江戸正座25
タイトル:お江戸正座25
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:25
掲載日:2025/05/09
著者:虹海 美野
あらすじ:
文太は茶葉を扱う諏訪理田屋の旦那である。
息子の文吉は十一、娘のおひなは八つになった。
夏に末の弟の文左衛門のところで子を授かった。
見舞いの品を妻と子二人が届けに行ったところ、なかなか戻って来なかった。
文吉が文左衛門が戯作者であると知り、文左衛門の本などを読むのに熱中していたという。文吉が将来店を継ぐことを思うと文太はやや心配になる。
文太は文左衛門を訪ね、そこで文左衛門は正座をして文太と向き合い……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
文太は、茶葉を扱う店、諏訪理田屋の旦那である。
七人兄弟の長男で、次男の暖簾分けまでを父が面倒見て隠居生活に入り、三男から末の七男までは、一応は文太が見守るというか、面倒をみるというかたちで、それぞれに身を固め、店を持ったり、婿養子に入ったりし、毎日の生活に勤しんでいる。
末の弟の文左衛門は、店と同じ名の諏訪理田という戯作者で、大層できたご新造さんと一緒になった。ご新造さんはお武家様でのご奉公を終えた後、数多あったであろう、恐らく左団扇の暮らしが約束された縁談を望まず、周囲にほとんど家もない場所にある建付けのわるい小さな家に一人住んで、家事もままならぬ文左衛門と一緒になった。そうして、住まいはさすがに変えたが、その家でご新造さんは行儀見習いのお教室を開き、家のことも取り仕切り、弟を支えてくれている。戯作者という仕事がどういったものか、文太にはいまいちわからぬが、ご新造さんと一緒になり、早数年ほどが経ったか……。もう、文左衛門の稼ぎでやっていけると聞いているが、ご新造さんはお教室を続けている。
そうして、少し前に、文左衛門とご新造さんが子を授かった。
普段から文左衛門が大層世話になっているご新造さんである。
文左衛門のこと、何から何までご新造さんにしてもらって、すっかり甘えて暮らしているのだろうから、そんな文左衛門と二人暮らしから、子との三人暮らしになり、ご新造さんはさぞかし大変であろうと、文太は思った。そう思ったのは、文太だけではなく、兄弟皆同じだったようだし、ご新造さんの身内だけでなく、昔からの友人であるとか、門下生だった人だとか、誰かしらが、飯や身の回りの世話をしに、入れ替わり、立ち替わり訪れて、ご新造さんは養生に徹し、今ではすっかり回復したと聞く。
ただ、まあ、気丈なご新造さんのこと、やはり無理をするのではなかろうか……。
そう思うと、文太はたまに身体によい茶を子にお遣いで持って行かせたりした。
文太の子は上の息子が十一、下の娘が八つになったところだ。
文太の家は七人男の兄弟だったから、娘が生まれた時は嬉しいのと戸惑いとで、なんとも言えぬ落ち着かぬ思いであった。言うまでもなく、長男の誕生も嬉しかった。文太は自分が長男で、その下に弟が六人いて、あれこれと面倒を見る立場で、なんだか損な役回りだと思うことが多々あった。親や親類縁者に言わせれば、初めての子とあって、誕生した時には盛大に祝ったというが、当の本人にはその記憶がない。だから、長男の文吉が生まれた時には、とにかくこの子が将来、自分は長男で損な役回りであった、とか、もし、この先子を授かっても、その面倒を見たことばかり思い出す大人にならぬよう気を付けることを肝に銘じた。
そうしてその二年後に生まれたおひなは、こんなことを言っては笑われるだろうが、とてもとても文太の娘とは思えぬほどにかわいらしい。旦那さんによく似てますなあ、と言われるのは、食べ物の好みだとか、ふと考えごとをしている時の姿勢なんかであるが、それもなんともこそばゆく、文太はつい、いやあ、そうか? などと返しながら、大層だらしのない笑顔になる。とにかくおひなはかわいらしく、何を着せてもよく似合う。つい、呉服屋を呼んだ時には、予定よりも、多くの反物をおひなに買ってしまう。呉服屋が来る前は、きちんと考えはあるが、おひなを立たせ、そこに呉服屋の持ってきた反物を合わせてみると、どれもこれも大層映えた。まるで、おひなのために織ってもらったかのようである。さすがに見兼ねた妻が、「あなた」と小声で諫め、「ああ、今回だけだ。この機会を逃すと、この着物をおひなが着られないからな」と、次回からは気を付けようと思いつつ、つい財布のひもが緩むような日々である。
もうとっくに反物が決まった文吉が柱に寄りかかり、ふう、とため息をつくのが聞こえる。
こうしてみると、文吉は、文太が思ったのとは違う、子どもの頃のあれこれを抱いていそうではある。
呉服屋は如才なく、文吉とおひなを平等に褒め、いかに今回文太と妻の選んだ反物が質の良いもので、文吉とおひなに似合うかを説き、お商売を進めていく。
背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、足の親指同士が離れぬようにし、「旦那さまとお内儀さまは、いかがいたしましょう」と、続けるのであった。
2
さて、文吉もそろそろ手習いを終え、その後お商売について学ぶ年が近づいてきた。手習いでの算盤はそこそこにできるようであるし、帳面のつけかたなんかも追い追い、お商売の手伝いをしながら覚えさせてゆけばよい。
だがまあ、先は長くなるだろう。
今のうちに、剣術や柔術を学んではどうか、と文太は思った。
茶葉を扱う店の主になるのであれば、茶や香を先に学ばせるべきと考え、折を見ては、そうした学びの場へも連れだした。なかなかに筋がよく、もともとの所作にも、子どもながら落ち着きと品が見受けられる。
普段から、正座をはじめとする所作には気を付けるようにはしつけてきた。
背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、着物を尻の下に敷き、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃え、足の親指同士が離れぬように。
そういうことが、自然とできる子であった。
ほかにも、子に茶や香の嗜みを学ばせたいという家はあり、その様子を見ることもあったが、子によっては、やはり向き不向きというものがあるようであった。
その点、文吉は申し分ない。
茶葉を扱う家の子としての素質十分である。
だが、それだけの視野というのも心もとない。
身体を今からうんと動かし、武道を通しての礼節も身につけてほしいものである。そもそも、子どもとは、本来そういう稽古の方を好むものではないだろうか。
文太にとって、文吉を柔術とか、剣術の師の元へ入門させてやりたい、というのは、将来のお商売云々というより、文吉を慮ってのことであった。
……だが、それを文吉に話したところ、全く心動かぬ様子である。
もともと大人しい子ではあったが、こういう時、「はい、ずっと習いたいと思っていました。ありがとうございます」のような返答を文太は予想、否、期待していた。
しかし、文吉は「はあ」とか、「はい」とか相槌は打つものの、どうにも乗り気ではないようである。しかも、「それは、どうしても通わなければ駄目なの」と、訊く始末である。
「そうではないが……」と文太は言葉を濁し、ほら、手習いで一緒の誰それや、この近所の誰それも通っているだろう。ああいうふうに、道着を着て稽古をつけてもらって、身体を動かして、強くなりたいとは思わぬか、否、誰かに対して強くなれと言うんじゃあない、自分自身が強くなるというか、うん、と文太が続けても、文吉の心は動かぬ様子であった。まあ、本人がこのようにやりたいと思っていないのであれば、入門させても、その先で迷惑になるだろうし、本人にとってもよろしくはないだろう。通ってみて、楽しさを知る、というのも往々にしてあるものだが、どうにもその気配を文吉からは感じ取れなかった。
3
そんな折、そろそろ秋の単衣を用意しようという時に、せっかくだから、文左衛門夫婦に着物を贈るのはどうか、と妻が言い出した。知る限りでは、子の身の回りのものは、あちこちから様子を見て重ならぬように贈られているが、夫婦の着物はさすがになかろうと言うのだった。子が生まれたのに、夫婦の着物を? と文太は首を傾げたが、恐らく今、文左衛門の妻、おようは自分のことは二の次、三の次であろうと言う。財布の事情ではなしに、そういう時期が暫く続くでしょう、と。私もお義母さんに昔、呉服屋さんを呼んで、着物を作っていただきました。今はなかなか気が回らないだろうけれど、そういう時だからこそ、用意しておくのもよいものですよ、と言ってくださいました、と続ける。息子ばかりの母は、それなりに息子の妻となる人、つまり義理の娘を思っているのだろう。そういうことに気づかぬ文太のことも見越して、手配をしてくれていたのだと思う。思い起こしてみれば、ほかの弟たちに対しても何かの折にこうしたものを贈っては、と妻はいつも助言してくれていた。なんとも頭が下がる。
そんなわけで、妻は呉服屋と相談し、文左衛門とその妻おようの反物を選び、秋から着る単衣を仕上げた。
それにお菜を詰めた重箱を携え、文左衛門宅を訪れた。
その時、家にいた文吉とおひなが、一緒に行きたいと言い出した。
玄関先までのいつものお遣いと違って、着物をお渡しするのは少し時間がかかるのよ、まだ赤さんが小さいから、騒いだりしてご迷惑をかけてしまってはいけないわ、と妻は言ったが、大人しくしています、赤さんを見せていただきたいです、と言う。まあ、もともと大人しい二人である。もし、ご迷惑をかけるようなことがあったら、その場ですぐに帰りますからね、と妻に念押しされ、二人はわかりました、と素直に頷く。
文太はお商売もあるし、あの末の弟とはあまり話をしない。
だから、三人で行ってもらうことにした。
くれぐれもよろしく伝えてくれ、とは言ったが、若干口先だけ、という自覚があった。正直に言えば、実の弟である文左衛門よりも、常に文左衛門を支えてくれている、妻のおようさんへよろしく伝えてほしい、といったところだ。
そうして送り出した妻と子二人であるが、一刻(二時間ほど)もあれば、帰って来るだろうと思ったが、なかなか戻って来ぬ。
一体どうしたのか。
もうじき夕餉の時間ではないか。
ちょっとそこまで、と見に行くつもりが、結局文左衛門の家まで着いてしまった。
かくして、妻と子二人はまだ、文左衛門の家に居た。
文左衛門は当初、戯作者の師の元でお世話になっていたのだが、その後独立し、その家を訪ねてみれば、周囲に家もまばらな場所に、隙間風の入る小さな住まいで、窯にはいつ炊いたかわからぬ米がこびりつき、畳は埃や、こぼした飯の固くなったものなんかが点在しており、膝をついて座るのにも、少々難儀する始末であった。なんでも、本人に言わせれば、人に気遣いなく暮らしたい、ということだったが、兄としては、どうしたものか、と思ったものであった。そこへお武家様でのご奉公を終えたおようさんが現れ、大きくはないが小ざっぱりとした家を見つけ、行儀見習いのお教室を開き、三度のきちんとした飯に、清潔な住まいに着物、仕事相手に会う際の支度に至るまでを世話してくれた。
その住まいは常に手入れされており、子が生まれた今も、それは保たれている。夕暮れの家の引き戸の前に立つと、「ありがとうございました」という、溌剌とした文吉の声がした。
目の前に、笑顔の文吉が現れた。文吉は驚きと戸惑いの表情になった。
そうして、その後ろには弟の文左衛門が立っている。
相変わらず、着物をだらしなく着崩しているが、手には本があり、表情は明るく柔らかだ。
その後ろにおひなの手を引いた妻と、子を抱くおようさんがいた。
おようさんは、文太の胸中察したようで、「遅くまでお引止めしてしまい、すみません」と詫びた。
そうして、「この度は、大層な贈り物をいただきました。ありがたく、受け取らせていただきます」と続ける。
「いやいや、うちのが思いついたことですし、この通り、弟の何から何までを世話していただいている身としましては、何かさせていただきませんと、逆に落ち着かぬのです」
慌てて文太はそう返し、「遅くまで妻と子がお邪魔したようで、ご迷惑をおかけしました」と詫びた。
「お父ちゃん、文左衛門さんは、諏訪理田先生だったんだね。うちの店と同じ名前だっていうのは前から思っていたんだけど。今日、諏訪理田先生の本を読ませてもらっていたんだ。貸してくださると言ってくれたんだけど、その場でどんどん読みたくなって、ずっと諏訪理田先生のお部屋で本を読んでいたの」
大人同士のやり取りを見ていたであろう文吉が、とうとう我慢できず、といった様子で、文太の前で飛び跳ねて伝える。
「文左衛門の?」
文吉の『諏訪理田先生』という呼び方が、やや面白くなく、わざと文左衛門と、弟の名で訊き返した。
文太の引っかかりにまるで頓着せず、「うん」と文吉が頷く。
「それで、おひなは、赤さんが寝ている時に、少しおよう先生に行儀見習いを見ていただいていたの」
「お父ちゃん、座礼を今日は教えていただいたの」と、おひなも文太の前に来る。
「それは、それは……」
戸惑う文太の前で、妻は困ったような、嬉しいような顔で微笑んだ。
4
そのうちに、文吉は手習いの午前と午後の間の時間、なんと弁当を持って、文左衛門の家に通うようになってしまった。
弁当は、手習いから一度家に帰って来て食べる手間を省くために、手習いで食べられるよう持たせたものである。
それを持ってわざわざ手習いを出て、少々遠い文左衛門の家に行き、弁当をかきこんで、文左衛門の部屋で本を読んだり、時には戯作の書き方なんかを聞いているようだというのだ。しかも、最初のうちは玄関から訪ねていたが、おようさんのお教室の時間であることもあって、今では庭の方に周って、直接文左衛門を訪ねているという。
子どもが何かに熱中するというのは、文太も知ってはいる。弟たちの中にも、舌が鋭かったり、算術や記憶力に優れ、その片鱗を幼い頃より覗かせていた者がいたのを覚えている。長男としては、ああ、何か言っているな、とか、大人しく遊んでいる分にはこっちに面倒がかからなくて楽だ、というくらいに捉えていたが、ある種の集中力、執着というのは、結構大人になってからの生活にも影響する。弟たちの場合は、婿入り先のお商売で活かせたからよかった。……だが、末の弟、文左衛門はお商売のことを家で学んでいる間も、それが身に入らぬ様子で、とうとう戯作者の元に弟子入りし、本人も戯作者になった。先にも述べたように、文左衛門は本人が満足であっても、とても周囲から見てひとり立ちしてやっていけている、と思えるような生活をしていなかった。とにかく、本のこと、戯作のことばかりで、ほかはおろそかになっている様子であった。
それが、まさか、うちのかわいい文吉に引き継がれているのか?
いやいや、冗談じゃあない。
自分の弟のことを悪く言いたくはないが、おようさんと一緒になるまで、文太、否、大抵の人から見て自堕落的な生活を送る文左衛門のように、大事な文吉がなっては困る。
文太は、文吉に跡取りとして、特別な何かを望んではおらぬ。
文太の兄弟が暖簾分けをし、諏訪理田屋は大きくなったといえば、まあ、大きくなった。婿養子に入った弟たちもそこでお商売に励み、互いに支え合っているようなところもある。だが、それは偶然といえば偶然だし、七人の息子が茶屋で育てば、自ずと道が決まってくるともいえる。
兎に角、文太は、文吉に店を大きくしてほしいだとかいう望みを持ってはおらぬが、店を継いでほしいとは思っているわけである。
そうして手習いを終える日が近づき、そろそろ店のことも、と思っていた矢先に、まさかの文左衛門の元へ通うという動向。
どうしたものか、と文太は溜息をつく。
5
ある時、文吉が文太に話があると切り出した。
朝餉の慌ただしい席で言うのだから、後で時間を取ってくれ、ということだろう。まだ、幼い文吉がそんなことを言うとは。
少し驚きながらも「わかった」とだけ返した。
そうして、夕刻、文太は文吉に来るようにと言い、奥の間へ呼んだ。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合おうように揃え、足の親指同士が離れぬように正座する。
少しして、「失礼します」と障子の前で文吉が声をかける。
「入りなさい」と文太は答えた。
立ったまま、がらりと障子を開け、「お父ちゃん」と言うと思ったら、ずいぶんと改まっているではないか。
文吉はきちんとした所作で障子を開け、会釈してから敷居を踏むことなく座敷に上がり、障子を閉めると、文太の向かいに正座した。
ずいぶん大人びた動作だと文太は思った。
所作については学んだ文太でも、最近ではそこまできっちりと気を付けているかと言われれば、そうでもなかった。
「たまに、およう先生のお稽古がまだ終わっていない時に、そのお稽古の様子を見ることがあって、覚えました」と文吉は、文太の考えを読んだ様子で説明する。
「そうか」とだけ、文太は答えた。
「それで、話とはなんだ」と文太は訊ねた。
「はい。これからお商売のことを学びますが、稽古として、諏訪理田先生のもとへ通うことをお許しください」
……おようの礼儀作法の教室なら、即座によい、と言った。
だが、なぜ、よりにもよって、戯作者の元へ通うのか……。
お商売に向かなかった昔の弟の姿が、まざまざと甦り、それに文吉が重なる。
「……通わなくてはならないのか? 本を借りたり、買って、家で空いた時間に読むのではだめなのか」
真向から否定する気はないが、こんな言い方になった。
なぜ駄目なのか、とは訊かぬが、「通いたいです」と文吉は答えた。
つまり、それが全てであった。
文太がどう言おうと、文吉の意志は決まっている。
お商売はどうするんだ、と出かかるが、文吉はお商売のことも学ぶと先に言い、また、稽古として文左衛門の元に通いたいと言う。
文太は溜息をついた。
「まずは、手習いを終えて、お商売の学び方を見てから判断しよう」と、文太は答えた。
「はい」と文吉は答えた。
6
もう、夏も終わりである。
そろそろ風鈴を外そうか、と廊下に座り、軒を眺めていた。
ふいに、ふわり、と背後から優し気な感触が覆った。
振り返ると、「よかった。やはり似合いますね」と妻が先日買った反物で仕立てた単衣を文太に合わせ、微笑んでいる。
「もう、できたのか」
「はい」と頷く。
「お前は器用だな」
「ええ、お裁縫のお稽古は結構得意でした」
「そうか」と、文太は頷く。
「文吉のことですか」と妻が切り出し、隣に正座する。
廊下の板の上であるが、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬように。
いつもきちんとしている妻である。
「ああ、何かやりたいのは結構だが、うちでお商売に向かぬ弟の様子を見ていただけあって、どうにもこうにも……」
「心配ですか」と、妻が訊く。
「ああ」と文太は短く答えた。
「文左衛門さんは、立派な戯作者の先生におなりですよ。それに、これまでそれほど書物に興味を示さなかった文吉、ひとりの子にここまで学びたいと思わせる力をお持ちです。弟君である文左衛門さんをお認めになっては?」
この妻は、いい家の娘で、まあ、文太とて、世間でいえば、そこそこに大きなお店の旦那であるが、なんというか、こう、考えが柔軟である。
「だが、文吉はうちの息子だ。いずれはここの旦那になる」
「ええ、まあ、私どもはそのつもりでいましたけれど、どうでしょうかね」
「どう、と言うと?」
文太が妻の方を見ると、掛けられていた着物がずれる。
それを妻は隣から受け止め、手元に引き寄せ、きれいに畳む。
「文吉がどうしても、ということであれば、それはそれでよいのではないですか。おひなに婿を取ってもよいでしょうし、もし、おひながそれをよしとしなければ、ここのお店を暖簾分けした文二郎さんのお子さんの誰かが希望すれば、お譲りしてもいいじゃあありませんか」
おい、と妻を嗜めようと顔を上げると、妻は畳んだ着物を膝に載せ、穏やかに文太を見ている。
「それくらい、方法はいくらでもある、ということを私は申したのです。まだ、文吉もおひなも幼いですから。好きにして、だけど、お商売のことも学ばせて、ゆっくりと見守ったらいいじゃあありませんか。今からあれこれ急かしたところで、十ちょっとの子が急に二十五になるわけではなし。だったら、本人の話をうんと聞いて、一緒に考えていった方がよいのではありませんか」
まあ、そうかも知れぬ。
少し、気負い過ぎた。
そうして、ふと、文太は妻を見て、それから足元を見る。
生まれ育ったこの家は、広く、大きく、自分たち兄弟七人が喧嘩をしたり、走り回ったりした場所だ。奉公人も多くここにやって来て、誰かと一緒になったり、自分の店を持ったりして出ては、新たな人間がやって来る。
この家で、しっかりと妻と子を守り、奉公人の生活を支え、店を守ることが文太にとっての、人を慈しむ思いの意思表示であったのだ。
文太の思いを見抜いているかのように、「大丈夫ですよ」と、妻が言った。
「いろいろと気を揉んでいるでしょうけれど、これも親の務めかも知れません。それに、このお店は大丈夫です。こんなにしっかりした主がいるのですから」
「そうか」と文太は頷いた。
なんとも言えぬ安堵感が広がる。
文吉の話から何か変化があったわけではないが、何もかもがうまくいくような気がするから、この妻は不思議である。
そうしてみると、自分もまた、おようさんに支えられていると思われる文左衛門と、そう変わらぬのかも知れぬ。
否、それはない。
さすがに、それは違うであろう。
7
あまり気は進まなかったが、文太は文左衛門を訪ねた。
昼餉を終えた頃で、日当たりのよい家の引き戸の前で猫が昼寝をしている。
猫を起こすのも忍びなく、どうしたものかと思っていると、「お義兄さん?」と小さく声をかけられた。
子を背負い、家の周囲を掃き清めていたおようが立っていた。
文太は会釈すると、「こちらからどうぞ」と、小さな声で庭の方へ案内された。
障子を開け放った文左衛門の部屋の前を通り、勝手口から中へ入る。
おようは手にしていた箒を勝手口の外に立てかけ、手を洗う。
「こんなところからですみません」とおようが詫びる。
「いえ、猫が気持ちよさそうに寝ていて、声をかけて起こすのも憚れましたから」
おようは「文左衛門さんは、昨日版元の方が書き上げた戯作を取りにいらして、今日はゆっくり休んで、先ほど文吉さんとお話をしながら昼餉を摂って、文吉さんを送りがてら散歩をして、戻ってくるはずです」と説明する。
要するに今日は文吉が来るまで眠っており、昼餉を食って、散歩をし、これから戻って来る、ということである。
お商売をしている文太からすれば、なんともまあ、うらやましいというか、だらしのない生活に感じられた。
おようさんは週に何度かお教室を開き、子を育て、家のこともせっせとやっているというのに、とため息が出る。
「今、お茶を淹れますから、少々お待ちくださいね」
「いや、結構ですよ。急に来たのはこっちなんですから」
「お湯は、もう文左衛門さんが戻る頃だろうと、先ほど沸かしておきました。手間ということもございません」
おようは穏やかに笑い、僅かに湯気の出ている茶瓶を見遣る。
文太は「それではいただきます」と頭を下げる。
「お義姉さんが持って来てくださった、お店の茶葉を使わせていただきますね」
茶葉を扱う店だけあって、人を訪ねる時、殊に文左衛門の元へは大抵茶葉を持って行く習慣がある。
「ああ、そのうちにまた持って来ます」と文太は答える。
いえ、そんな、と言いかけるおように、「本当に、文左衛門が、弟がご迷惑をかけてばかりで……」と、文太は常日頃思っている心の内を発するように言った。
「迷惑だなんて」と、おようは茶を淹れながら朗らかに笑う。
「文左衛門さんは大層頑張っておいでですよ。けれど、お仕事のことで苛立つことがございません。いつだって、私の作るものを喜んで食べ、気持ちよさそうに眠って……。そんな文左衛門さんにいつでも私は力をもらっているのですよ」
なんと、特殊なお方だ……。
おようの背でにこにこと機嫌のいい子を見て、文太は、この子がおようさんに似るように、と余計なお世話ながら祈った。
「そんなふうに言ってくださると、私もまだ救われます。……全く、あれは誰に似たのか……」
そう言うと、おようは「文左衛門さんのお部屋にお運びしましょうか」と、茶の載った盆を持ち、文左衛門の仕事をしている部屋へ向かう。
ああ、すみません、と文太は先に通してもらい、文左衛門の部屋に入った。
机の上や、その周辺は散らかっていたが、部屋は風が入り、畳は清められ、日当たりがよい。
つい、ここでごろり、と昼寝をしたくなる。
だが、背筋を伸ばし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬようにし、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃える。
文太の前に茶を置き、「それに、やはりご兄弟です」とおようが微笑む。
大層驚いた。
驚き過ぎて、何も言えなかった。
もう少し驚いていなければ、冗談じゃあない、と怒っていたかも知れぬ。
驚き過ぎて、よかった……。
「猫の昼寝すら、妨げないよう慮る方は、そうそういませんよ」
あ、と文太は思う。
「当初は私、猫が来ようが、昼寝をしようが、こちらの都合しか考えておりませんでした。でも、文左衛門さんが、人差し指を立てて、猫を見遣ったことがあって、そこで私の考えも変わったと申しますか、何やら柔らかくなりました。お義兄さんも、先ほど同じように、猫を起こさぬように気遣っておられるのを見て、『ああ、矢張りご兄弟』だと思った次第です」
文太は「はあ」とか、「まあ」とか、曖昧に答える。
おように指摘されるまで、全く気付かぬことであった。
「それに、家族を大層大事にするのも同じです。お義兄さんが、お商売がお忙しくても、文吉さんのことで今日うちにいらしたように、文左衛門さんは、よくこの子を見てくださいます」
文太は、子が小さいうちは妻に任せきりであったが、おようがそう言ってくれるので、そこは黙っていた。おまけに、文太が今日文左衛門を訪ねたおおよその理由もおようはわかっているようで、その如才なさに、すぐに反応できなかったのも正直なところであった。
「おや、兄さん、どうしたんだい?」
のんびりとした声が庭からした。
文左衛門が、菓子と花を手に立っている。
「あなた、お義兄さんがお待ちですよ」
「珍しい。まさか、兄さんが来るとは思いもしなかったから、手習いの戻りに遠回りをして、菓子を買って、花まで摘んできてしまったよ」
朗らかに笑う文左衛門に、「今、お茶を淹れますね」とおようが言う。
文左衛門は、花と菓子を「土産」と渡す。
「まあ、どちらに咲いていたのですか? 飾りましょう」とおようは白い花を受け取り、「こちらのお菓子、今、召し上がりますか」と、用意している。
一応、「お構いなく」と声をかけたが、夫婦のやり取りであることは文太にもわかった。
8
二人を気遣い、おようは文左衛門の部屋の襖を閉めた。
文左衛門は文太の前で、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬようにし、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃えている。
ずいぶんと行儀よくしているものだと思っていると、「これが元で、師の家を出ましたから」と文左衛門が言う。
「どういうことだ?」
さっぱりわからず、文太が眉間に皺を寄せると、「師の家で夕餉の時間に足をしびれさせ、師の娘さん、今は義理の姉さんにぶつかり、大事な茶碗を割ったのが原因です」と、小さく説明する。
確かに文左衛門の師のお嬢さんと弟が一緒にはなったが、師の家でそのようなことがあったとは……。ほかの弟たちは知っているのかもわからぬが、文太は細かな事情までは知らなかったから、驚くばかりであった。大人しい弟が、まさかそのような失態の上で師の家を出たとは……。……大切な茶碗というのは、どういういったものなのか。知る由もないが、文左衛門を猫かわいがりの父がもし、そのことを知ったなら、泣いて悲しむのではなかろうか。周囲に人のおらぬ家を借りたのも、そうしたことからきていたのか……。もう、何年も前の話であるのに、文太は急に文左衛門が気の毒に思えた。
「お前も、苦労したのだな」
「いえ、おかげで、おようと一緒になれました」
明るい返事に、僅かの間でも同情したことを後悔する。
「それで、兄さん、今日はどうして?」
そうだ、その話だった。
文太はできれば文吉に、文左衛門の元へ通うのをやめさせようと思い、ここへ来た。今日、明日というのではなく、それとなく、理由をつけて断るよう頼もうと思っていた。
だが……。
居心地のよい庭に面したこの部屋に、文吉が来たがるのがわかる。
猫の昼寝さえも見守り、気遣うこの家は、居心地がよいのだろう。
文太の家とて、悪くはなかろうが、文吉にとって、この家と、この弟はこれまでになく、心引きつけるのであろう。
じきに、文吉は手習いを終える。
そうしたら、弁当を持ってここへは通えぬ。
お商売のことを学び始めても、どうしてもという意志があるのならば、通うであろうし、だんだんと興味が薄れるかもわからない。文太としては、その後者を期待していたはずだが、ここへ来て、なぜか、文太をできる限り文左衛門の元へ通わせてやりたい、という思いが湧いて来た。
「文左衛門、教えてほしいのだが」
「なんだい?」
「戯作者というのは、正体を隠して、たまに本を出すということもできるものなのか? こう、ほかの仕事をしながら……」
文左衛門は首を傾げ、「ああ」と頷く。
「版元が出してくれるというんなら、大丈夫なんじゃないでしょうかね」
「……そうか」
文太はおようが淹れてくれた茶を飲んだ。
苦味と甘味が絶妙で、香りもよい。
いずれ、この茶葉を文吉が売る日が来るのだろうか。
「文吉が、こっちに頻繁に来て、迷惑をかけているな」
文左衛門は茶を飲み、饅頭を食べながら、「ああ、文ちゃんね」と、何やら文吉の名を短くした呼び方をし、ゆっくりと饅頭を咀嚼し、時間をかけて茶を飲んだ。
文太には、妙に長い時間に感じられた。
「迷惑だと思ったことはない。来たければ来ればいいし、来たくなくなれば、それでいい」
なんとも、文左衛門らしい返事であった。
どこかに入門しようという時、もしこんな言い方をする師であれば、考え直すかも知れぬ。きっと一人前にしてみせます、くらいの心意気がほしいところである。
……だが、文太は妙に腑に落ちる思いであった。
こういう肩の力の抜けた人間というのは、存外悪くないのかも知れぬ。
特にあれやこれやと学ぶことの多い年ごろの文吉にとっては、何か特別な匂いを感じ取ったのかも知れぬ。
文太は息をつく。
そうして、文左衛門に座礼した。
「そうしてくれると助かる。……文吉が世話になる。よろしく頼んだ」
「うん」と、文左衛門は返事をした。
まるで、饅頭を食うか、と訊かれた時のような返事である。
そうして、顔を上げた文太に「兄さんも、饅頭食うか?」と言った。
どうにも頼りないと思っていた末の弟は、実は結構たくましい。ずいぶんと気づくのが遅れたが、まあ、遅れたら遅れたで、これから知っていけばよい話である。
たまに、文左衛門のところへ通う様子を文吉に聞いてみるのもよかろう。
先ほど玄関で昼寝をしていた猫が庭にやって来ると、文左衛門は「およう、朝餉で残しておいた俺の焼き魚はどこへ置いてある?」と、襖の向こうに声をかける。
おようは勝手口の方にいたようで、「なんです?」と訊き返した後、「ここの窯の隣に置いてありますよ。朝、きれいにほぐして、骨を丁寧に取り除いて、置いておいたじゃあありませんか」と答える。
「そうだった」と文左衛門は立ち上がると、猫に「ちょっと待っておいで」と声をかけ、文太の前を素通りし、猫の飯を取りに行ったのだった。

![[400]お江戸正座38](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)