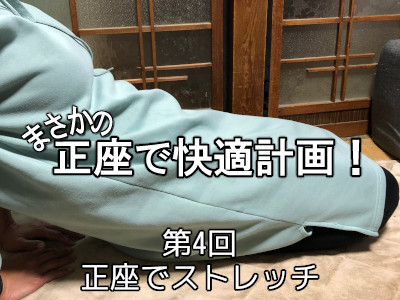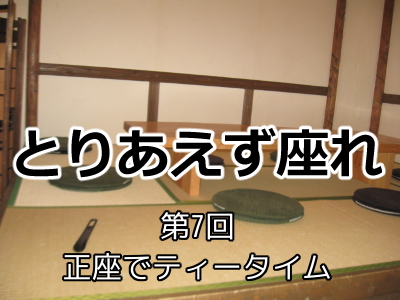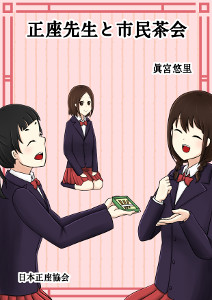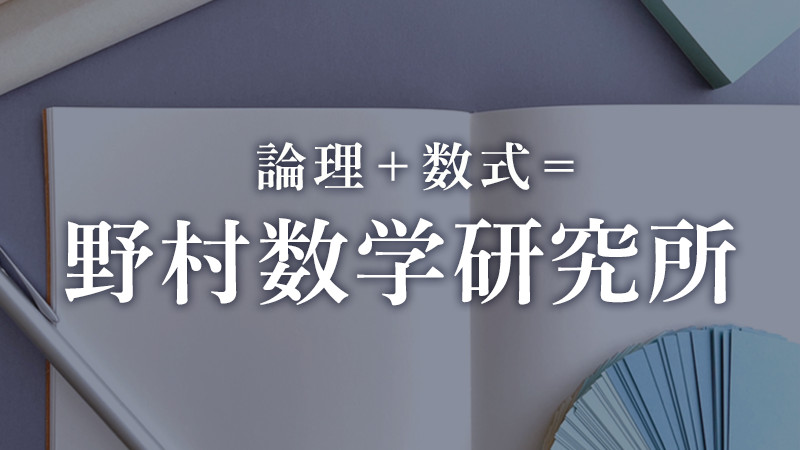[363]お江戸正座28
タイトル:お江戸正座28
掲載日:2025/06/22
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:28
著者:虹海 美野
あらすじ:
おえんは干物屋の三姉妹の次女である。今は材木問屋の手代の吉次と一緒になり、長屋暮らしだ。
長屋暮らしはうまくっているが、家族は水面下のおえんの努力に気づいていないようだ。
そんな折、妹のおすえがなんと干物問屋の若旦那に見初められ、祝言を挙げた。なぜうちの妹が、とおえんは驚く。
一方、実家ではお母ちゃんが足を痛め、姉は子を授かって食が細り、家のことが回らぬ状態に。
おえんは暫く長屋を離れ、実家に戻るが……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
おえんは、干物屋の次女であった。
今は材木問屋の手代の妻である。
おえんの実家は姉が夫とともに干物屋を継いだ。自分の家のことを言うのもどうかと思うが、決して大きくはない店に、よく婿入りしてくれた人がいたものだ。おえんは姉が結婚して間もなく、材木問屋の手代、吉次と一緒になり、実家を出て、吉次の住む長屋に引っ越した。だが、末の妹のおすえは実家におり、姉の夫は姉、それにおえんたちのお父ちゃん、お母ちゃん、それに妹のおすえと暮らしているわけである。それも、人当たりよく、そうかといって、変に気を遣う人でもなくて、小さな店に狭い家でも、実にうまくやってくれていて、おえんは妹ながらに感謝している。
ちなみに、おえんのえん、は、艶、などという洒落た字ではない。生まれた時から、大層機嫌よく、自由に見えたという。それでお父ちゃんは、この子は自由に遠くへ行くだろう、というところから、おえんにしたと聞く。
まあ、その名前からきているかはわからぬが、おえんは物心ついたときから、実家を出ることを考えていた。
実家でのお商売というは、自分たちのかじ取りで行うところは、奮起したり、やり方を変えたりと、やり甲斐もあるだろうが、おえんのうちはそういう気概なく、いくつかの問屋からそこそこによい品を買い付けて、それを売る、ということに徹していて、まあ、近所の人たちから信用があり、お客に困ることもないが、行列ができるような店になることもまずないといったところであった。そうして、自宅でお商売をするということは、誰かが店番をするわけだし、店をきれいにするわけだし、その間にも洗濯物は出るし、めしの支度も誰かがしなければならぬ。それが、おえんには少し合わぬ気がした。これでは今日は羽根を伸ばそう、という日がないではないか。自宅でお商売をしていない人が羽根を伸ばしているとは言わぬが、おえんとしては、どこかに雇われている方がいいように思えたのだった。
そうした時、たまたま店に来た手習いで一緒だった友達と思い出話に花が咲き、久しぶりにうちへ来たらと誘ってもらって行った長屋の一室に、後の夫になる材木問屋の手代、吉次が住んでいた。
長屋では、お菜のおすそ分けは日常茶飯事だし、友達のところへおえんが遊びに行けば、近所の人が饅頭なんかを差し入れてくれる。そうして、独り者だった吉次の元へ友達とともに、お菜だの、菓子だのを持っていくうちに、自然と距離が縮まった。
おえんは、店のお仕着せの羽織を着た吉次が大層りりしく見えた。
狭い長屋住まいながら、自分で暮らしを立てている様も、大人に見えた。
もう、その頃には長屋中の人が、おえんが吉次を想っていることを知っていたから、気を利かせて、今日は煮物を作ったから、帰るついでに吉次のところへ持って行っておくれ、とか、そんなふうに、おえんが吉次を訪ねやすいようにしてくれた。
そうして、ある日、おえんは託された小鉢を横に置き、部屋に上がり込むと、背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、着物を尻の下に敷き、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、親指同士が離れぬように正座し、「私をここへ置いてください」と言った。
「ここで、否、私でいいんですかい?」と言う吉次に、「ここが、吉次さんがいいのです」と答えた。
「では、仲良くやりましょう」と吉次が言うと、わっと、引き戸が開き、長屋の住人がなだれ込んできたのだった。
まあ、そんなふうにして、おえんの縁談は、思いのほか、あっさりとまとまったわけである。
ただ、仲の良かった友達と、このままここで一緒に暮らせる、ついでに頼れる、と思っていた目論見は外れた。
友達は友達で、しっかり想い人との距離を縮め、ちょうどおえんと入れ違いのかたちで、よそに嫁いでしまったのだった。友達のお父ちゃん、お母ちゃんも、友達が嫁いだのを見届けると、兄弟のいる郷に帰り、そこで農作業をしながら暮らすと言って、長屋を出た。
まあ、そのくらいのことは仕方ない。
頑張ろう、とおえんは心の内で奮起した。
長屋のおかみさんたちの輪に溶け込むには、生活を共にするのが早い。
だから、周囲のおかみさんが米を研ぎに井戸に集まってくる頃に、おえんも笑顔で「おはようございます」と言い、米を研ぎ、朝餉が済めば吉次を送り出し、その後はまた井戸端で皿を洗い、今度は洗濯をする。その最中に、おかみさんたちの話に加わる。最初のうちは、以前この長屋に住んでいて、引っ越していった人の話なんかがちょくちょく出て、よくわからぬことがあったが、笑顔でそれをやり過ごし、次第に昨日、今日とおえんの知ることが話題にのぼるようになってきたのだった。
実家暮らししか知らぬおえんを心配し、お母ちゃんや姉、妹のおすえなんかが時折、店の干物なんかを差し入れに、様子を見に来た。だが、周囲と談笑しいているおえんを見て、心底ほっとした様子で、「楽しそうでよかった」、「また来るね」と言う。そうして、おえんはいい人と一緒になって、暮らしにも恵まれて、本当にありがたい、とお母ちゃんが言う。
もう、長屋は話し声なんか筒抜けだから、ここはおえんはうん、うん、と言っておく。本当は、いやいや、私が努力して溶け込んでいるんだよ。何にもしないで、こんな知らない人ばかりの、全て筒抜けのとこでやっていけるわけないでしょう、と思うが、それは言えぬ。
2
長屋暮らしに完全に慣れたわけでもないが、兎にも角にも吉次が毎日帰って来て、一緒に暮らしていけるのは夢のようであった。
これ以上の幸せはない、と思った。
ところが、である。
なんと、妹のおすえが、干物問屋の若旦那と一緒になることが決まったというのだ。
干物問屋は、実家が品を卸してもらっているので、当然おえんも知っている。かなり大きな屋敷で、若旦那のことは知らぬが大旦那もお内儀さんも人柄がよい。使用人もいる家で、どう考えても玉の輿、左団扇の生活ではないか。
一体全体どうしてそういうことになったのか……。
大体、家同士だって釣り合っていないではないか。
小さな干物屋の末娘。
自分の妹ながらというか、自分の妹だからというか、兎に角言ってしまえば、愛想もないし、特別にかわいいわけでもない。家の仕事が丁寧というわけでもないし、洗濯だって、米の炊き方だって、適当である。お裁縫だって、縫い目が揃っていない。お父ちゃん、お母ちゃん、挙句の果てはお客に至るまで、全く気を遣わぬ。つまらぬことはつまらぬと、相手に合わせることをしない。
そんな妹、おすえがどうして、干物問屋のご新造さん(奥さん)におさまったのか……。
いずれ、この長屋でも、おすえの嫁ぎ先の話題が出るだろう。
何せ、おえん、なんて遠いって意味で名づけられたのに、歩いてすぐの長屋に嫁いだのだから。
おすえが干物問屋に嫁ぐ、というのは、この前姉がちょこっとうちに寄った時、隣の壁を気にしながらそっと伝え聞いただけである。
詳細を聞くには、実家に行くのが手っ取り早い。
今日は井戸端での洗濯もそこそこに、実家へ向かった。
途中、ふと迷ったが、饅頭を買った。
おすえは昔から饅頭が好きだった。
姉と一緒につい、おすえのちょっとした失敗を大げさに笑い、おすえが悔しいやら悲しいやらで泣きそうになると、饅頭の出番だった。
もう少ししたら干物問屋のご新造さんなんだから、私が気を遣って饅頭を買って行くこともない、と皮肉りながらも、結局は饅頭を買った。
そうして実家に行ってみると、この日は姉夫婦におすえが出かけていた。珍しいこともあるものだと思っていると、ご近所のご隠居さんだとか、はす向かいの陶器店の夫婦なんかで連れ立って潮干狩りに出かけたという。表向きは行楽だが、実のところははす向かいの陶器店夫婦の歓迎会だとお母ちゃんが言う。確かはす向かいに新しい店が入ったのは、三月以上前のことである。ずいぶんと時間が経っているが、「そうなんだ」と言っておいた。おすえのことを聞くのなら、本人や、話に割りこむ姉がいない方が都合がいい。
お母ちゃんは、「おえんが来たから、ちょっと店番を代わって」とお父ちゃんに声をかけ、すぐ隣の座敷におえんを「こっち、こっち」と促す。
住んでいた頃は、狭い店に家だと思っていたが、こうして帰って来てみると、あんまり日に当てていなくて冷たく、薄い座布団も色のくすんだ襖も何やら心を穏やかにしてくれる。
そういえば、吉次と一緒になることをお父ちゃん、お母ちゃんに伝えたのもこの部屋であった。吉次と並び、座布団を外し、背筋を伸ばし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃え、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬようにし、正座した。
寂しくなるなあ、と漏らしたお父ちゃんに、嫁ぐのは、すぐそこですよ、とお母ちゃんが笑って言おうとし、涙声になったのが、つい昨日のことのようだ。
お母ちゃんは「ありがとうね」とおえんが持って来た饅頭と茶を出す。
茶に何気なく口をつけたら、驚くほどに美味しい。
「美味しいでしょう」とお母ちゃんが、おえんの反応を見越して言う。
「どうしたの、このお茶」
「はす向かいの陶器店、諏訪理田屋さん、本店が茶葉のお店で、引っ越しのあいさつの時にいただいたんだよ。それがあまりにも美味しくてね、うち、あんまりそういう贅沢はしないんだけど、お茶は美味しいものにしようかって、いうことになってさ。まあ、もらったものと同等のは高くて手が出ないけどね、安いものでも、あそこのお茶は美味しいんだよ」
「へえ」とおえんは頷く。
家を出てから、確実に時は経つ。
「それで、何がどうして、うちの不愛想なおすえが、あの干物問屋のご新造さんになるのよ?」
「ああ、そうなのよ」とお母ちゃんが膝を詰め、にじり寄る。
「なんでもね、あの干物問屋の若旦那は、『嘘をつかぬ人でないと一緒にならない』と前から言い張っていたらしくてね」
「そんな人、いくらでもいるでしょう」
鼻白んで、おえんが返す。
「それがあの若旦那に言わせると、おすえだけが、本当に信頼できる娘だって、ことらしいんだよ」
「はあ? なあに、その若旦那、よっぽど女の人で何かあったかした人なの?」
「そういう話はうちは聞いていないけどねえ。見合いは結構したって話だよ」
「見合いってことは、いい家のお嬢さんに会ったって、ことでしょう? 何が不満だったのよ。それとも、向こうに断られ続けたとか?」
「知らないよ。私はあちらさんの干物問屋のご夫婦でも若旦那でもないんだからさあ」
「そんなことわかってるってば。何それ、結局、わからないことばっかりじゃない」
おえんは呆れたが、それでもひとつわかったのは、どうやら干物問屋の若旦那が妹のおすえを気に入って、この縁談がまとまったらしいということだった。
3
世の中には不思議なこともあるもんですねえ、姉の私だって信じられませんもん、なんて言いながら、おえんはどこか誇らしげな気持ちであった。
洗濯に集まったおかみさんたちが、「へえ」とか頷いていたが、「そりゃ、おえんさんの妹さんの気立てのよさだろう?」、「おえんさんの妹さんも大したもんだけど、その相手の若旦那も大したお人だよ。そういうところを見てくれる男がもっと増えればいいけどねえ」、なんていうふうに干物問屋の若旦那とおすえのことを言ってくれた。噂話好きな人たちだから、気を抜いてはいけぬと思っていたおえんだが、存外、こういうところは気持ちがさっぱりしていて、警戒している自分が妙に疑い深く感じられた。
4
お母ちゃんの前では、おすえのことをけなしたおえんであったが、やはり自身の妹。その妹がよい人に見初められ、よい縁に恵まれたことは嬉しかった。
おすえの祝言も済み、やれやれ、と思った頃、お母ちゃんが足を怪我したと、お父ちゃんがやって来た。
医者の見立てでは、骨は大丈夫だが、暫くは足を動かさぬ方がよろしいということと、年のこともあり、疲れも溜まっているようだから、これを機に養生するようにとのお達しが出たと言う。
「だったら、暫くは姉ちゃんに家のことをやってもらって、買い付けはお義兄さんに、店番はお父ちゃんでまわすしかないね、たまに私も様子を見に行くから」とおえんが言うと、お父ちゃんが、「なんで今日、姉ちゃんでなく、お父ちゃんが来たと思う」と訊く。
「なんでよ」とそのまま訊き返すと、お父ちゃんはふう、とため息をついた。
実はお姉ちゃんが子を授かって、ここ何日か食が細り、寝付いているのだと言う。
「ええ」と、おえんはつい、大声を上げた。
つい最近、末の妹が嫁いだと思ったら、今度は姉が子を授かった。
目出度いこと続きだ。
お母ちゃんが足を怪我したのも、ここが踏ん張りどころ、と妙に力んでいたのが裏目に出たのかも知れぬ。
妹のおすえが嫁ぐ前であれば、いやいやながらであろうが、家のことくらいはやってくれていたはずである。
だが、そうはいかぬ。
ふう、とおえんは溜息をついた。
「わかった。暫くそっちに行けるか、今日吉次さんが帰ったら訊いておくから」と返事をした。
お父ちゃんは「済まないな」と何度も言いながら帰って行った。
多分、ここからの帰りに、今日は煮物かなんかを見繕って帰るのだろう。
米は炊けるのだろうか。
お父ちゃんの見繕ったお菜を、寝込んでいる姉は食べられるのだろうか。
さまざまな不安がおえんの中を駆け巡った。
5
吉次が帰って来ると、おえんはめしをつぎながら、実家のことを話した。
椀を手にした吉次は顔を上げ、「それはいけない。うちで飯の用意をしている場合じゃあない。今日は遅いから、明日にでも行って、お義母さん、お義姉さんの具合がよくなるまで、実家を手伝っておいで」と言う。そうして、「俺は仕事があって昼間はいけないが、時々様子を見に行くから」とまで言ってくれた。
つくづくよい人である。
おえんは背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃え、足の親指同士が離れぬようにして正座し、「ありがとうございます」と言った。
「おえんは、どこかのお嬢さんのような佇いだなあ」と、吉次は言った。
「何言ってるんですか。あの小さな干物屋の次女ですよ」とおえんが返す。
「おえんのお父ちゃんもお母ちゃんも、本当にいい人で立派だ。おえんはもちろんだが、お義姉さんも、おすえちゃんも、きちんとした娘さんに育てて。お商売だって夫婦二人で力を合わせて。娘三人を育てて、店を続けるっていうのは、なかなか大変なことだ」
持ち上げている様子はなかった。
吉次は材木問屋の手代で、店での振る舞いや、それこそ処世術というものは身につけている。
だが、基本的にどれが本当の吉次なのか、と思うようなところがなかった。
だから、今言ったことも、本当に思ってのことなのだろう。
「そんなこと、考えたこともありませんよ」とおえんは返す。
「まあ、生まれた家がそうなら、そういうものだと思うものだな」と吉次はおえんの頭を撫でた。
6
長屋のおかみさんたちに朝、事情を話し、おえんは暫くの間使う着替えなんかを携え、実家に帰った。
店番は父がしていた。
「おお、悪いなあ」と、父が立ち上がって、おえんを迎えてくれた。
「ううん。吉次さんが、お母ちゃん、お姉ちゃんの具合がよくなるまで、こっちにいていいって」
「そうか。吉次さんにも悪いことしたなあ」
「朝ごはんはどうしたの?」
そう訊ねると、昨日の夜はお父ちゃんの見繕ったお菜をお父ちゃん、お母ちゃん、お義兄さんで食べたと言う。姉は食欲がなく、さゆしか飲めなかったらしい。
そうして、朝はさすがに飯を作ろうということになり、お義兄さんが米を炊き、お父ちゃんが振り売りから魚を買ったのだが、米はあまりに水気が多く、火を強くして炊き直したら、底が焦げたというし、魚も三分の一ほどが炭になったと言う。
おえんは溜息をつき、「わかった。炊事と洗濯は私がやっておくから、お義兄さんとお父ちゃんはお店の方をお願いね」と言い、持って来たたすきを掛け、土間に入った。
そうしてまず、皿や箸を洗い、今日の昼と夜の分の飯を炊く。
それから、お母ちゃんの寝ているところへ行って、様子を見た。
暫く会わないうちに、やつれたように見えた。
着替えが大変だからか、寝間着のままで、髪も乱れている。
「大丈夫?」と訊くと、「悪いねえ」と心細げな返事だ。
おえんは桶に湯を張り、手拭を入れたものと、お母ちゃんの新しい寝間着を持って、お母ちゃんの元へ戻り、上体を起こして身体を拭き、肩を貸して、寝間着を着替えさせた。そうしてついでに厠へも連れて行き、これでひと段落である。
次に姉だ。
肌がくすんで髪の細った姉が、「おえんちゃん」といじらしい声で呼んだ。
こちらでもおえんは、姉を起こして身体を拭いて寝間着を着替えさせ、何か食べたいものはあるかと尋ねた。
姉は腹は減っているが、何が食べたいかさっぱりわからぬと言う。
じゃあ、これから買い物に行って、見繕って来るから、その中から食べられるものを食べてね、とおえんは言い、買い物の前に、溜まった洗濯物を洗って干し、ふう、と息をついて買い物に出かけた。
いつも吉次と二人だから、炊く米の量も少ないし、洗濯もそれほど時間はかからない。これまで、実家ではどうしていたか。店番やら、掃除やら、何かしらはしていたはずであるが、大概のことはお母ちゃんと姉が手分けしてやっていた気がする。店番や買い物は、おえんとおすえが、お母ちゃんに言われてやっていたくらいだ。
買い物は、ちょうどうちの前を通りかかった振り売りから豆腐を買い、それを土間に置き、近所で野菜を見繕った。水菓子(果物)屋の前を通りかかり、ふと、姉の顔が浮かんだ。水菓子なら食べられるかも知れぬ、と思ったが、財布事情もあり、また買って来たところで姉が食べられるかどうかもわからぬので、そのまま帰り、昼餉の用意に取り掛かった。
お父ちゃん、お母ちゃん、それにお義兄さんに、おえんは大層感謝された。これまで、家でお母ちゃんや姉が当たり前にやってくれていたことである。それが、近所の長屋に嫁いでちょっと戻ってきたら、こんなにも喜ばれる。なんだかそれが、おえんにとっては、お母ちゃんや姉に申し訳ないと思えた。
姉は豆腐と粥を少し食べて、また眠った。
おえんちゃん、ありがとう、ありがとう、とやつれた顔で言うのを見ると、やはり水菓子を買ってやればよかった、という思いが過った。
夜には吉次がお母ちゃんと姉の見舞いにと、饅頭を買って顔を出してくれた。
お母ちゃんと姉は、吉次に礼と詫びを繰り返した。
来客によって、適度な緊張があったのがよかったのか、お母ちゃんと姉の顔色が少しよくなった。食の細った姉が、驚いたことに饅頭を食べた。
この日は、お母ちゃんと姉は床でそれぞれに夕餉を、お父ちゃんとお義兄さんと吉次、おえんが一緒に膳を前にした。
土間のすぐ横の板の間がおえんの実家の食事場所である。
狭い場所であるから、皆、膳の前に正座する。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬように。
幼い頃から、これはお母ちゃんによく言われた。
吉次がおえんの居住まいを褒めたのは、今思えば、そこから来ているのかも知れぬ。
普段、長屋で仕事の疲れから、適当に座って膳を前にする吉次も、お父ちゃんたちの前とあって、正座している。
初めは続かなかった会話も、徐々に広がってゆく。
お商売の話から始まって、天気のこと、共通の知人、そうしてお母ちゃんの足のことと、姉の体調、おえんとの長屋での生活……。
ちょっとした緊急の出来事であったが、こうして義兄や吉次と膳を前にするのは、案外悪くなかった。
何かの祝いの席でなしに、普段の膳というのが、いいのかも知れぬ。
食事の後は、おえんは明日の朝ご飯にとおにぎりを包んで吉次に渡し、戸口まで見送った。
「また、何日かしたら様子を見に来るから」
「うん、ごはんは大丈夫?」
「ああ、もともと一人だったし、こっちは心配いらない」
これから、暗い部屋に一人で帰る吉次におえんは少し心が痛んだが、吉次は「まあ、無理はするなよ」とおえんを慮ってくれた。
7
おえんは、膳を片づけ、土間の横の皆で食事をした狭い板の間に布団を敷いた。今、部屋の奥の間をお父ちゃん、お母ちゃん、そうして二階を姉夫婦が使っている。
階段を挟んで向こう側がお父ちゃん、お母ちゃんの使う奥の間で、こっちの板の間とは、狭い家ながら適度な距離があった。
姉が結婚した後、おえんとおすえは二階から移動し、ここに布団を敷いて寝ていた。
布団に入った後も、何かしら話し、笑ってから眠りに就いた。
今、階段や奥の間を見つめ、一人布団に入ったおえんは、こんなにもうちは広かったのか、と思った。
8
おえんが来て、安静にできたのがよかったのか、お母ちゃんの足の具合はだいぶ良くなった。痛みはまだあるし、歩くのも肩を貸さなくてはならぬが、ずっと横になっているほどでもなくなった。
姉も、粥を少しづつ食べられるようになり、調子が戻ってきたようだ。
そうして、夜は、お母ちゃんは起き上がるのに床が硬い方がいいからと、姉は夜でも水を飲みたくなったりするのに、隣に寝ている義兄を起こしたくないと言って、おえんが寝ている土間のすぐ横で寝ることになった。
お母ちゃんはだんだん動けるようにはなってきたものの、姉は一日寝ているのだから、二階の方がいいのではないか、と思ったが、暑くなるこの季節、土間の横の方が涼しいと言う。
そんなわけで、狭い場所に敷き布団を少しづつ重ねるようにして、母と娘は三人川の字になって眠った。時折、姉の背をさすったり、お母ちゃんが厠へ行くのに肩を貸したりはしたが、二人と並んで眠るのは、えもいわれぬ安心でおえんの心を満たしてくれた。
姉はお婿さんをもらって店を継ぎ、妹は大店の若旦那と一緒になり、なんだかおえんだけが放っておかれたような思いがあったが、こうして母と姉と眠っていると、そんなことはなかったのだ、とわかる。
長屋にあいさつに来て、干物を皆に配ったお父ちゃん、お母ちゃんは、長屋でおえんがうまくやっていけるように思ってくれていただろうし、姉とて、妹のおえんを心配して様子を見に来てくれていた。
おえんが姉の背をさすり、湯呑に水を入れて持って行き、お母ちゃんの着替えを手伝い、起き上がる時に肩を貸すと、「ありがとう」と言う。そのたびに、おえんは心の中で、「私こそ、ありがとう」と繰り返した。
翌日、吉次が新鮮な葉物野菜を籠に入れて持って来てくれた。
材木問屋のお内儀さんが、昔子を授かった時に、葉物野菜をやたらと食べたと聞いたので、菜っ葉なんかを見繕って来ました、と言う。
早速それをお味噌汁やおひたしにして膳に出すと、姉の箸は大層進んだ。
姉が布団を敷いているから、食事をする板の間は狭いが、それでも家族が一緒で、食が細りがちな姉がおいしそうに食事する姿は、嬉しく、皆を安心させた。
泊まって行ってくださいな、というお母ちゃんの誘いを吉次は丁寧に辞して、長屋に戻った。まあ、泊まるとすれば、義兄かお父ちゃんと一緒に布団を並べて寝ることになるから、長屋の使い慣れた自分の布団で一人寝るようが気楽であろう。
吉次と離れて生活するのを寂しく感じる一方で、思いがけぬ実家への帰省は、これまで長屋でおかみさんたちの輪に入り、どこか気を張っていたおえんをほっとさせていた。
9
実家に戻って七日ほど経った日の夕刻であった。
「ごめんください」と店先で声がした。
そろそろ夕餉の支度を、と思っていた頃であった。
「はあい」と、土間から店の方へたすきを外しながら出て行くと、そこには妹のおすえと、仕立てのよい着物を着た若い男の人が立っていた。
「おすえちゃん……」
「おえん姉ちゃん」
おえんを呼ぶ妹の声は、干物問屋のご新造さんになった今も、どこか幼く、変わっていない。そうして、着物は木綿でもよいものを着るようになっていたが、無駄にかわいらしい感じがないのも、また然り。
そこでおすえの夫、つまり義弟が丁寧に名乗った。
家族をこちらに呼ぼうとし、否、それどころじゃないから、そもそもこういうことになったのだ、と我に返る。
「どうぞ、お入りになってください」とおえんは二人を招き入れた。
「お母ちゃんとお姉ちゃんはどう?」とおすえが訊く。
「お母ちゃんはだいぶ良くなったよ。お姉ちゃんも、お粥や葉物のお菜は食べやすいみたいで、だいぶ調子がいいの。人にもよるらしいけど、子を授かって食が細るのは一時期の場合も結構あるらしいから、そのうちにまた食欲も戻るといいと思ってるの。だからって、無理はさせられないけど」
「うん、おえん姉ちゃんに全部任せてごめんね」
おすえがしおらしいことを言う。
まあ、愛想のない子だけど、思いやりがない子ではない。
「うちは大丈夫よ」とおえんは答えた。
お母ちゃんと姉と一緒に眠れる思いがけない機会が嬉しい、というのは、大層身なりの立派な義弟の手前、黙っていた。
そこで義弟が「ここまででいい。ありがとう」と言うのが聞こえた。
気づかなかったが、義弟の後ろに控えていた手代だかが、大きな荷を抱えている。
「一緒にうちで少し休んで行ってくださいな」と、おえんは義弟の後ろにいた男の人を引き留めた。
「いえ、私は……」
「うちの人も商家で手代をしております」
だからどうした、というわけでもないが、おえんがそう言うと、何やら、義弟とその男の人ははっとした顔をし、義弟が「お心遣い、感謝します。では、お言葉に甘えなさい」と後ろの男の人に言った。
おえんは「お父ちゃん、お義兄さん、おすえちゃんたちが来てくれたよ」と声をかけた。
この来客の知らせで、お母ちゃんと姉は寝間着や髪をちょこっと直すだろうし、お父ちゃんとお義兄さんは、何か大きな見舞いをいただいたことを察して出て来てくれるだろう。
10
義弟がおすえとともに持って来てくれたのは、すいかをはじめとした水菓子であった。
「まあ、こんなに」とお母ちゃんも姉も驚いている。
おえんがお茶の用意をしながら、奥の間を勧めようとすると、義弟が「いえ、こちらで結構です」と言う。床についている姉とお母ちゃんを見舞いに来たのだから、ということらしい。
お義兄さんが、奥の間から座布団を持って来る。
「すみません」と義弟が丁寧に頭を下げる。
着物は木綿だが、薄い夏物の羽織は絹であった。
板の間に埃が浮いていないが、おえんはひやり、とする。多分、この場にいる義弟を除いた全ての人が、同じ心持であっただろう。
「大切に、この子に食べさせます」と、姉を見遣りながら言うお父ちゃんに、義弟は、「やはり、おすえさんは、家族のことをよくわかっているんだなあ」と軽やかに言った。
そうして、「みなさんで、召し上がってください。また、持ってきます」と続けた。
「とんでもございません」と家族皆が目を見開き、首を横に振った。
昔から、身の丈に合う暮らしをして、努力はすれど、金銭的な背伸びはしない家であった。買ってくれるからと言って、はい、ではよろしくとはいかぬ。
義弟は、「私は、本当によいところの娘さんと一緒になれて、果報者です」と言った。
「今、なんと?」と、お父ちゃんが訊く。
小さな店に、見ての通りの家で、義弟の家の広間一室で、実家の店も住まいを含めて軽く収まるだろうことは、おえんにもわかる。
義弟は穏やかに笑った。
「おえんさんがうちに来て、欲しいものはないか、と訊いても、足りないものはございません、と言うきりだし、だったら、着物や簪を、と言っても、それも今あるもので足りると、とにかく、欲がない。それが、一緒になって初めて、欲しいものがある、と言う。子を授かって食の細ったお姉ちゃんに水菓子を買ってもよいか、と。……黙って買えばいいものを、本当に律義な人で、うちの母はそれを聞いて、なんといじらしく、律義な娘(こ)なんでしょうと涙ぐみまして。もう、毎日水菓子屋に届けるように頼んで来い、と申しますが、おすえは、そんなこと、とてもとても、とまた遠慮しまして。ならば、持って行けるだけ、持って行こうということになりました」
「おすえを、そんなふうに思ってくださって、ありがとうございます。そちらのお母さんにも、よく思っていただいて」とお父ちゃん、お母ちゃんが頭を下げる。
「何もお構いはできませんが、今度いらした時は、何も持たずにいらしてください」
そこで義弟も頭を下げる。
気づけば、足を怪我したお母ちゃん以外、皆が、背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝で指先同士が向き合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座している。
「どうぞ」と、おえんが茶をそっとお出しした。
よい茶葉があってよかった、とおえんは思ったのだった。
11
なんで、妹のおすえが問屋の若旦那と一緒になって、と思ったものの、実際に夫婦になった妹たちを見ると、それまでの思いはすっと消えた。
よい人だ、と思った。
水菓子を買ってくれたことももちろんありがたいが、うちや、妹をこんなふうに思ってくださるお人はそうそういまい。
たまたま、そのお人の家が裕福であったというだけのような気もしてきた。
それから三日ほど過ぎ、お母ちゃんはゆっくりではあるが歩けるようになった。姉も吉次の差し入れてくれた葉物野菜や義弟からの水菓子で、ずいぶんと顔色がよくなり、食欲が戻るにつれて、調子もよくなり、床上げできるまでになった。これで全快というわけではないだろうし、また食も細るかも知れぬが、まずは一安心である。
もう、明日には吉次のいる家へ戻ろう、という日の昼餉、お父ちゃんがお義兄さんと店番を代わって来た折、「本当にすまなかったな。助かったよ。ありがとう」と言った。
「そんなことないよ。私も久しぶりに帰れて嬉しかった」とおえんは言った。
「お母ちゃんもお姉ちゃんもおすえも、おえんのところへ行って帰って来ると、『おえんは本当に周囲とうまくやれて、大したもんだ』と言っていたよ。お姉ちゃんやお母ちゃんは、もう自分が結婚した身だからね、『まわりとうまくやっていけるように、よく頑張ってる。また何か持って行こう』って言ってたよ」
おえんは、そこで顔を上げた。
お母ちゃんも姉も、一度たりともそんなことは言わなかった。
そんなふうに思っていたのか……。
「まあ、それまで全く別の場所にいた人間が溶け込むのは、なかなか難しいもんだ。それをうまくやっていくのも、大事な力だ」
「うん」とおえんは頷いた。
「それに」と、お父ちゃんは言葉を切った。
「お姉ちゃんも、おえんも、おすえも、本当にいい人に巡り会えた。こんなにありがたいことはないよ」
吉次の顔が浮かぶ。
「うん、そうだね」とおえんは頷く。
そうして、「だけど、それはお父ちゃん、お母ちゃんが、ちゃんと育ててくれたからだよ」と付け加えた。
お父ちゃんは暫し黙り、「おえんも大きくなったな」とくぐもった声で小さく言うと、「ごちそうさん」と膳を下げ、水を張った桶に入れて、店の方に戻ったのだった。
12
動けるようになったお母ちゃんが腕を振るい、さまざまなお菜を詰めてくれた。
おえんはそれを持って、久しぶりに吉次と暮らす長屋に戻った。
夕餉の支度をしていて、引き戸を開けていたおかみさんたちに、「ただいま戻りました」とあいさつする。
すると、「みんな、おえんちゃんが戻ったよ」と、声をかける。
そうして前掛けで手を拭きながら出て来たおかみさんたちは、「大変だったね。お母ちゃんとお姉ちゃんの具合はもういいのかい?」と訊く。
「おかげさまで」とおえんが頷くと、「ああ、本当によかったよう」と、おかみさんたちが口々に言う。
そうして、「吉次さんや、うちの人たちに休みを聞いてね、みんなで潮干狩りに行こうと思っているんだけど、どうだい?」と訊く。
ずっと実家で家事をやっていたおえんは、「はあ」と言いながら、あいまいに頷いた。
「よかった。じゃあ、お弁当を手分けして作って、行こうよ」
潮干狩りの季節はとうに始まっている。
……もしかして、おえんが戻って来るのを待っていてくれたのか。
わいわいと楽しそうに話すおかみさんたちを、おえんは見ていた。
13
「ああ、みんな、おえんの家のことはもちろん心配していたし、大変だねえとは話していたけどね、潮干狩りはみんなで行こうって、言っててさ。だけど、いつ戻れるかわからないし、今回はうち抜きで行ってくれていいと言ったんだが、おえんちゃんが来られないなら、来年にするよって、おかみさんたちが言ってね」
お菜に箸を伸ばしながら、吉次が言った。
「そう……」
お礼を言わなければ。
そう思いながら、お礼を言うのが、建前やうまくやっていくための方法ではなく、心からのものだとおえんは気づいた。
久しぶりに帰った実家は、炊事、洗濯にお母ちゃんと姉の世話で忙しかったが、ほっと落ち着いた。
だが、今のおえんの家はここだ。
吉次との生活があり、それを見守り、この先支え合っていく人たちが、ここにはいる。

![[360]お江戸正座27](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)