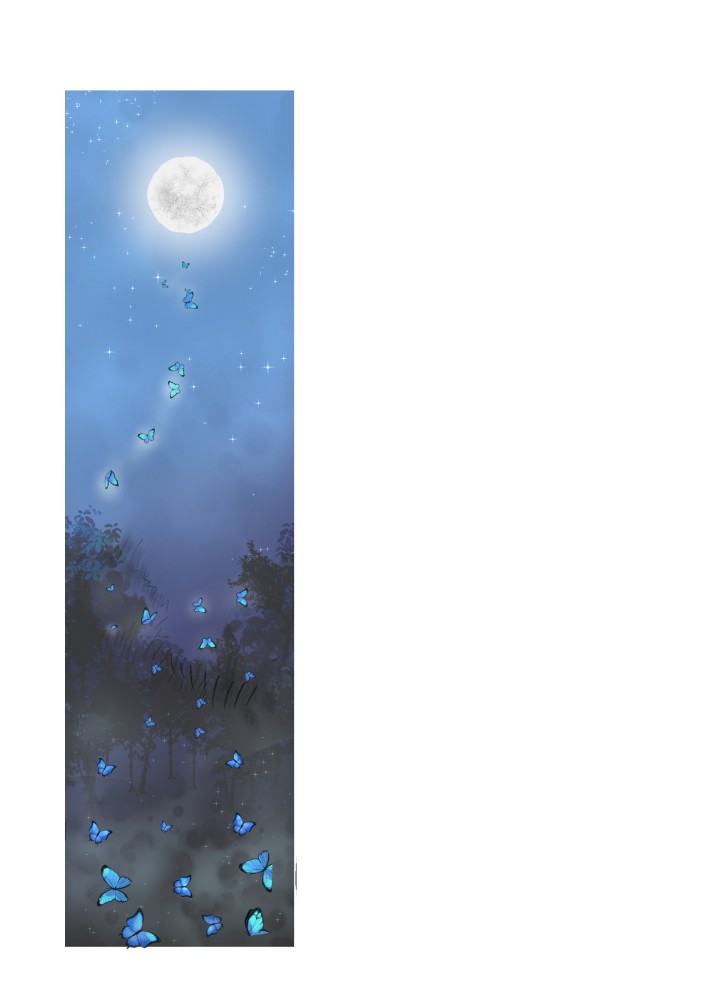[245]正座で月光茶しませんか?
 タイトル:正座で月光茶しませんか?
タイトル:正座で月光茶しませんか?
掲載日:2023/01/28
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
沙渚は、春から高校生になる男気のある少女。華奢で可愛い花織を守る役目になっていた。ある日、花織は小学生の頃から月が怖い、と打ち明ける。
入学予定の高校の行事で、早春登山が行われる。同じ中学からのケンカ友達、姿月リンシも同行する。山頂を目指す一行は、突然悪天候に見舞われ、沙渚、花織、リンシの三人は山小屋へ逃げこむ。吹雪に閉じこめられた中で、だしぬけにリンシは正座をしよう! と言い出す。

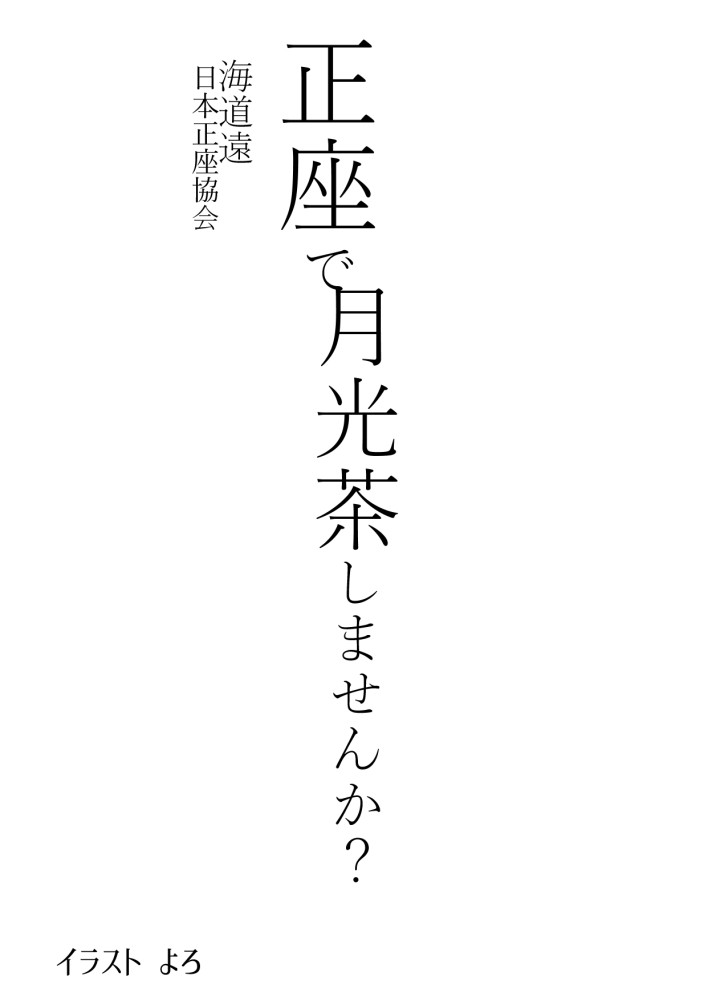
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 越冬する蝶
「入学式の前に、登山のイベントがあるの?」
台所にいた母親が振り向いた。
「そうなのよ。今日送られてきたメールで初めて知ったわ」
春から高校生になる沙渚(さなぎ)は、新入生の行事で入学前の三月に、早春登山に行くことになった。
「ええ? やっと入試が終わって、春休みが終わるまでお弁当は要らないと思ってたのに」
母親は渋い顔をしてから、お弁当の献立を考え始めたようだ。
小・中学時代からの親友の花織(かおり)も同じ高校に進学したから、登山も一緒に行く。
花織は、華奢で名前の通り華のある美少女だ。茶色っぽい巻き毛で、透きとおるような白い肌に朱いおちょぼ口。黒目がちな瞳で、後、二、三年もすると誰もが振り向く美女になるだろう。
沙渚は華奢な花織の守り役の立場で、彼女をからかう男の子がいれば、盾になる。
「さなぎだから、そのうちクワガタムシに変身するかもよ」
などと冗談を言っている。
早春登山が迫ってきたある日、花織とショッピングに出かけた帰りが遅くなって、すっかり暗くなってしまった。空には白い半月が輝いている。
「沙渚……。あのう、変に思ってはイヤよ」
花織が口ごもりながら切り出した。
「小学生の時から、私、月が怖いの」
「え?」
「なんだか見つめられてるみたい……」
月から隠れるように沙渚の後ろに身を寄せる。
「あんなにきれいな白いお月様なのに、なんだか蛾の模様のように感じる時もあるし、青い鱗粉(りんぷん)を感じる時もあるの……」
「何を言うのかと思ったら。花織ってば怖がりさんなんだから。お月様も花織の可愛さに見惚れてるのよ」
沙渚は花織の頭をポンポンして力づけた。
早春登山の一行は、いくつかのグループに分けられた。
五人でひとつのグループだ。その中に、同じ中学から進学した姿月(しづき)リンシという男子が混じっていた。
中学の時に転入してきたリンシは、黒髪で真面目そうな外見のわりに成績はあまりよくないし反抗的だ。仲間の中ではリーダー格で鼻っ柱が強く、教師と意見が合わない時には徹底抗戦するヤツだ。
沙渚とも相性が悪く、日頃からケンカばかりしている。仲に入って止めるのが花織の役目だ。
登山する山は標高一五〇〇メートル。
初心者向きの山だ。初めて履く登山靴、大きいリュックを背負ってして黙々と昇っていく。
「各自、疲れる前に休むんだぞ!」
引率(いんそつ)の教師の声が飛ぶ。
広葉樹の林に覆われているが、まだ新緑の芽はかたい。大きな沢に出ると、深い緑色の水が勢いよく流れている。
「はい、ここで休憩します!」
引率の教師が声をかけた。生徒たちは、やれやれと荷物を置き、谷川に殺到する。
「ああ、マイナスイオンだ!」
男子たちは、顔をじゃぶじゃぶ洗ったり、女子は水をかけあったりしている。
「花織、大丈夫? けっこう汗かいたわね」
「ええ、大丈夫よ、ありがとう」
花織は白い頬を紅潮させ、タオルで汗をぬぐっていた。
「あっちの静かな流れを見てこよう」
ふたりは、皆から離れて沢の支流へ行ってみた。
「広葉樹がたくさん繁ってるわね」
「あ、あれ見て、花織!」
沙渚が一本の枝を指さした。葉の裏に一匹の青い蝶がひっそりと身を潜めている。
「こんな浅い春に、もう蝶が?」
「越冬した蝶じゃないかな」
「蝶って冬を越すの?」
花織が目をくりくりさせた。
「種類によってはそうらしいよ」
「逞しいのね。青色が鮮やかね」
翅(はね)をびったり合わせた姿は、まるで人間が合掌している手のひらのようだ。
そろそろ出立しようとする頃、空模様が怪しくなってきた。
「どうして? 今日は晴天のはずだったのに~~」
「山の天気は変わりやすいのよ」
生徒が騒いでいるうちに、早くも顔面に雨粒が当たり始めた。
引率の教師たちも慌てて指示を出した。
「かなり強い低気圧が次々にやってきます。登頂はあきらめて降ります! 皆さん、レインコートを着なさい」
残念がるどよめきが起こる。
「せっかく母さんがお弁当作ってくれたのに」
「俺なんか自分で作ったんだぞ」
生徒たちを黙らせるように、雷鳴が響いた。
「きゃ~~~!」
生徒も教師も転がるように走り下りた。
激しい雨と稲光に視界をさえぎられ、なんということか、沙渚と花織、そしてリンシは一行からはぐれてしまった。
第 二 章 山小屋
雨の中で、リンシが山の地図をバサバサ広げた。
「この辺に山小屋があるはずだ」
雨の幕の向こうに山小屋を見つけ、どうにか走りこんだ。
山仕事用の物置小屋らしく、扉は施錠されていない。が、雨は雪混じりとなり、地面や茂みがみるみるうちに白くなっていく。
小屋の中に鉄製のストーブがあり、薪木まで積んであった。リンシがリュックからマッチを出して、ストーブに火を点けた。
「良かった、火がついた!」
オレンジの炎が三人の顔を温かく染めた。
夜を通して、春の嵐の咆哮(ほうこう)が荒れ狂う。ケータイの電波がつながらない。
「どうしよう、このままお天気が良くならなかったら……。お母さんもお父さんも心配しているわ、きっと」
花織がベソをかきながら洩らす。
「大丈夫よ。きっとお天気は良くなって山を下りられるわ」
励ましたものの、沙渚自身も不安だった。
突然、リンシが立ち上がった。
「正座の稽古をする!」
「何なの、いきなり」
「正座は精神統一のために適した座り方だ。こういう時こそ、ネガティブな思考が捨てられる。絶対、無事に帰れると信じるために、正座の所作を教えてやる!」
「教えてやるとは何よ、偉そうに!」
沙渚を、花織が後ろから抱きかかえて引き止めた。
「やってみましょ、沙渚」
「よし、やるぞ」
リンシが声をかけた。
「背すじを真っ直ぐにして立つ。大きく胸を張って。床に膝をつく。そして、スカートをはいている時はお尻の下に敷き、かかとの上に静かに座る。両手は静かに膝の上に置く。――どうだ? できたか?」
「うん。順番にやっていたら、できた」
「おし、沙渚も花織もそれでいい」
(いつのまに呼び捨てにされる間柄になったのよ?)
沙渚は少しイラッとした。
「もし眠気に襲われても、背すじを伸ばして『大丈夫、帰れます』と声に出して言うこと。良い方向へ思考を向けること。ストーブの番を三人交代でやるからな」
(何よ、生意気ね。……でも、間違いない指示だってことは認めるわ)
第 三 章 満月の蝶
静かだ。
沙渚はストーブ番をしているうちに、風雨が止んでいることに気づいて、そっと扉を開けて様子をうかがった。
煌々(こうこう)と白い満月が、澄んだ空気の中で輝いていた。辺り一面は銀世界だ。
泣きたいくらい静かだ。
月を見上げていると、小さなものがひらひらと舞い降りてきて、沙渚の唇にとまった。
「これは、蝶々?」
青い蝶だ。口の中に仄かな甘さが広がる。
いつのまにか山小屋の中へ戻っていて――。
触れているのは、蝶ではなく唇に変わっていることに気づいた。
(口移しに、甘く熱いものを流しこんでくるのは……?)
飲みこむと、熱いものが身体の中心に下っていくのが分かる。疲れと不安が溶けていくようだ。
そっと瞳を開けてみる。
白い顔が間近にあった。漆黒地に青色と金糸の刺繍糸の丈の長い着物を着た青年が、沙渚の顔を両手で包んで、口移しに甘いものを流しこんでくる。
(だ、誰っ? こんな山小屋に着物姿?)
顔を背けて唇を離した。
「飲みなさい。寒さに負けてはならぬ」
切れ長の漆黒の瞳が言った。
再び口に甘いものが送りこまれる。まるで体内で作り出されているような濃密さだ。以前から知っているような懐かしい味がする。
(夢……。夢なんだわ、これは……)
耳の奥に吹雪の叫びが戻ってきた。気がつくと、現実に誰かが口移しに何かを飲ませている?
(だ、誰なのっ?)
じたばたした。
(リ、リンシ……?)
リンシは離れて、沙渚の顔を覗きこんだ。
「眠ってしまいそうだったから蜜を飲ませた。眠気が飛んだか?」
(やっぱり、リンシ!)
惑乱と怒りと恥ずかしさが一気に押し寄せてきた。
「何するのよ!」
リンシの胸板を思いきり押した。彼はビクとも動かず、
「ストーブの側に寄れ。しっかり目を開けて」
いつものお調子者の彼ではない。冷静そのものだ。
「花織にも飲ませる」
小屋の隅っこに、花織もぐったりしている。
リンシは彼女の身体を手早く起こして背中をさすりながら、手に持った水筒から口に含み、アゴを持ち上げて口移しに蜜を与え始めた。
沙渚の顔が、かあっと熱くなった。
(な、なに? 私もこんな風に口移しされたの?)
(まるで、まるで……キスそのものじゃないよっ……。ファーストキスもまだなのにっ)
花織も蜜とやらの効き目か、意識を取り戻した。
「その蜜って蜂蜜なの?」
沙渚は勇気を出して尋ねた。
「蝶が花の蜜を集めたものだ。月光蜜(げっこうみつ)っていう。ふたりとも、もう眠るんじゃないぞ。蜜はもう無くなったから」
リンシはさっさと自分ひとりで正座をした。
「リンシこそ眠っちゃだめよ」
「だから正座してるんだよ。お前たちも正座しろ」
沙渚と花織は、顔を見合わせてから気まずく視線を背けた。
(もしかして、花織もファーストキスだったのかな?)
夜が明けて吹雪がおさまり、ケータイの電波も通じるようになった。救助隊がやってきて、三人は無事に山を下りることができた。
満月から舞い降りてきた青い蝶。蜜を与えてくれた夢の中の青年のことが、リンシの面影と重なって現実にあったかどうか分からないままだ。
第 四 章 正座体験カフェ
五月に入った頃、沙渚の自宅の近くに「正座体験できるカフェ」が開店することになった。
「正座体験って何かな?」
「正座なら、習わなくてもできるけど」
「なんだかリンシくんの正座のお稽古を思い出すわね」
花織とふたりで行ってみる。
トレーナーにジーンズスタイルの沙渚と、森ガールファッションの花織とが連れ立って歩くと、まるでカップルだ。
住宅街の奥に、緑の三角屋根の小人の家みたいなカフェがあった。
ステンドグラスの玄関ドアや窓がメルヘンの世界だ。
ドアベルを鳴らして店内へ入ると、カウンターの奥から白髪で蝶ネクタイを着けたダンディなマスターが、にっこり笑って迎えた。
「いらっしゃいませ」
店には数人の客の姿があった。
窓側の席に座った沙渚と花織がメニューの画面を睨んでいると、
「よう! 花の蜜ジュースが最高だぜ」
水を運んできたギャルソンヌ姿の男の子は、リンシではないか。
「リンシ! このカフェでバイトしてるの?」
「違うよ、ここが俺んち。祖父ちゃんがマスター」
カウンターの内側から、マスターが会釈した。
沙渚と花織は、リンシに勧められるままに花の蜜ジュースをオーダーした。
運ばれてきた蜜ジュースとやらは、ストレートなグラスに蝶の模様が入っている。黄金色でさっぱりとした甘さが美味しい。
ふたりとも登山の時に、リンシに唇を奪われた記憶がよみがえる。
花織が真っ赤になっている。沙渚はわざと大声を張り上げ、
「ま、減るもんじゃなし、気前よくくれてやったことにするか」
「沙渚ったら。命の恩人なのよ」
「命の恩人かつ、無礼者よね」
「沙渚ったら……」
「カフェの売り文句、『正座体験』って、リンシが山小屋で稽古させたものと同じだったんだ」
椅子とテーブルフロアの隣には、和室があり、マスターはそちらへも出入りして、お客に蜜入り日本茶でもてなして、正座のお稽古を指導している。山小屋でリンシが指導した通りの正座の所作だ。
「そういえば、リンシはしっかりした正座をしていたわ。お祖父ちゃんのお稽古を受けていたのね」
「正座体験してみる?」
花織が言った。
「もちろん、やってやろうじゃないの」
和室に移動し、他のお客と一緒に、マスターから正座の所作の説明を受けながら、正座してみる。
「皆さん、お上手にできました。そこのおふたりのお嬢さん方も」
マスターの目が細められる。抹茶に仄かに甘い蜜を入れたメニューをご馳走してくれた。
「『月光茶』と言います」
甘すぎず、身体の芯に溶けていくようなまろやかさが見事に日本茶と融合している。
「な、美味いだろ、うちの蜜入りメニュー!」
リンシが自慢げに言いに来た。
彼のことはさておき、沙渚と花織は、すっかり、お祖父ちゃんマスターと月光茶と正座ファンになった。
第 五 章 蝶の導き
花織の所属する銀河鑑賞クラブが、天文台のある山頂に泊まりこみで天体観測することになった。
「七夕に備えて、予行練習の意味もあるそうよ」
花織は銀河を天体望遠鏡で見られるとあって、はずんだ声で沙渚に報告した。
「いいなあ。気をつけてね!」
当日、沙渚は笑顔で送り出したが、クラブの参加者が天文台に到着してから、あいにく悪天候となった。
情報を聞いた沙渚は、ため息をついた。
(早春登山の時といい、お天気に恵まれないなあ)
季節外れの寒波が襲来したのだ。
「寝袋は持ってきているけど、すごく寒いわ」
花織からメールしてきた。
「花織、しっかりして。そうだ。皆と一緒に正座して精神統一したらどうかな?」
「そうね。リンシくんの言ってたように、背すじを正座してネガティブなことは考えない! よね」
「その意気よ、花織!」
励ましたものの、心配になって高校の銀河鑑賞クラブの部室に駆けつけた。残ったクラブ員が詰めていて、気象情報に気をはりつめている。
沙渚に、リンシから一通のメールが届いた。
『お祖父ちゃんと一緒に、花織を迎えに行ってくる』
(花織を迎えに? 天文台に向かったってこと?)
よけい落ち着かなくなった。
(そうだ! こういう時こそ正座だ! 正座体験のカフェに行って、マスターの和室で花織たちが帰れるように祈りながら、正座して待とう!)
お店は臨時休業になっていた。
裏側に回ってみると、お座敷のガラス戸のカギは開いている。沙渚はそっと上がった。
正座して、呼吸を調えて(ととのえて)祈る。
(花織……。無事に帰るのよ)
床の間に飾られたヤマツツジを見つめながら懸命に祈った。
淡いピンクのヤマツツジに青い蝶が一匹、どこからか飛んできて止まり、蜜を吸っている。
近づくと、蝶はひらひらと飛びあがり、床の間の明かりとりの障子の辺りで見えなくなった。
障子の隙間から覗いてみると、向こう側は新緑に満ちた深い森ではないか。
(お庭じゃないよね?)
いつしか緑あふれる世界に踏みこんでいた。見覚えのある景色だ。早春登山の時、越冬している青い蝶を見つけたところだ。
渓流の両側は、ヤマツツジが咲き乱れている。
(そんなバカな。私は正座カフェのお座敷にいたはず――)
不意に青い蝶の一匹が唇にとまった。早春登山の山小屋でのことが思い出された。
口移しで蜜を与えた長ったらしい着物の青年の姿がよみがえる――、リンシのことも。
(リンシ! 必ず花織たちを救け(たすけ)て帰ってくるのよ)
青い蝶は飛び立ち、いざなうようにヤマツツジの群生に沿って翔んでいく。
(待って――)
後を追いかけていくと、突然、視界が開けた。
第 六 章 緋毛氈(ひもうせん)の上で
陽光が燦燦(さんさん)と降る中、色とりどりの花が咲き、青い蝶が無数に飛んでいる。蝶の楽園とはこの光景だ。
(ここは――)
花々の中に緋色の毛氈が敷かれて正座している人影がある。
漆黒の打ち掛けの青年ではないか。風炉(ふうろ)(釜)まである。
「どうぞ」
手を鋭く伸ばして、膝の前に置いた椀を示す。
「月光茶です。どうぞ」
「山小屋の夢で見た、あの――」
緋毛氈を前に、棒立ちになった。
「こちらへ。月光茶を飲むと、温まって心が落ち着きます」
青年の漆黒の瞳の中に青い蝶が見える。
沙渚は言われるままに緋毛氈の上に上がり、正座して茶碗を持ち上げた。
コクのある甘味が身体の隅々に行き渡る。マスターが淹れる月光茶と同じ味だ。ほっとしてお茶碗を毛氈の上に戻した。
「ご馳走様でした。――あのう、こんなところでお茶してる場合じゃないんですけど」
「焦っても仕方ない。あなたのお友達は、リンシがきっと連れ帰りますよ」
「リンシを知っているのですか!」
青年は茶碗をひざ元に引き寄せた。
「彼の行動も、爺やの行動も分かります」
「爺やって?」
「ここで蝶の群れでも眺めていらっしゃい。お友達が山から下りられたら教えてあげますから」
青年は鷹揚な笑みを浮かべた。
(リンシとは大違いだわ。アイツは逆立ちしたって、こんなお上品な笑い方などできないわ)
(でも、面差しがなんとなく?)
陽ざしの中で蝶の群れを眺めているうちに眠くなってきた。
第 七 章 吹雪の中を
顔面に吹きつけてくる雪つぶてを受けて、少年と老人が山の天体観測所目指して登っていた。ひどい寒波襲来だ。
「飛ばされませんように! お気をつけて」
先を行く老人が振り向いて叫ぶ。
「分かってるって!」
「そうですか? さっき数秒ほど、どこかへ意識が飛んでいたでしょう。にやけてましたよ」
「うるさいぞ、爺や! ゴーグルと毛糸の下の顔が見えるのか」
「はい、見えますとも。この爺やには」
ふたりは岩陰で休憩した。
「この強風は普通ではないな」
保温の筒に入っている花の蜜ジュースを飲んでから、リンシがもらした。老人も真剣に答える。
「凍蛾(とうが)将軍がもたらした寒波に違いありません。噂は本当だったのですな。将軍が花織さんを見初めたという」
「花織のことを沙渚が心配している。どうあっても無事に連れて帰らなければ」
「行きましょう、鱗翅(りんし)の君!」
老人が力強く言い、防寒重装備のふたりは、花の蜜を積みこんだリュックを背負って再び歩き始めた。
雪の彼方に天文台の影が見えてきた。
「リンシくん! マスター!」
天文台に到着すると、花織が一番に迎えた。
「よく迎えに来てくださったわ。さあ、皆のいる部屋で暖房に当たってください」
リンシとマスターは、リュックを下ろすのももどかしく、花の蜜ジュースが入ったタンクを取り出した。
ひとつ五〇リットルもあるだろうか。
銀河鑑賞クラブ員たちが驚いている。
「よく、こんな重いものを背負って持ってきてくれました」
さっそく、ふたりはタンクから花の蜜ジュースを次々とコップにそそぎ、配り始めている。
「後続の方々が、食料も運んできますからね」
花織もクラブ員も花の蜜ジュースを飲み、生き返ったようだ。
「冷たいのに熱く感じるよ。胃の底に落ちる感じがビタミンをもらったみたいだ」
「え? このジュース、姿月リンシくんのお祖父ちゃんが作ってるの?」
「今度、そのカフェへ行くよ!」
後続の一団が食料を運んできた。銀河鑑賞クラブ員たちは、命をつないだ。
第 八 章 大きな翅(はね)
瞼(まぶた)にそっと触れたのは翅か、触角か?
いや、ヤマツツジの葉陰でまどろんでいた沙渚を、現実に戻したのは、青年の接吻だった。
「先ほど吹雪がおさまり、天文台に閉じこめられていたご友人たちが帰途につきました。花の蜜茶を皆さんが喜んで召し上がり、元気を出しました」
漆黒の打ち掛けの青年は覆いかぶさって告げた。
「どうしてそんなことが分かるの?」
「山に行って見てきたからです」
「……?」
「信じさせてあげよう」
青年の漆黒の打ち掛けが広げられ、高々と立ち上がった。
鮮やかな青と金糸の刺繍が、沙渚の視界いっぱいに広がる。周りが優雅な曲線のカタチ――。まさしく蝶の翅ではないか。
「この翅でひと飛びしてきたのです」
「……! あ、あなたは誰――?」
「そんなことより」
青年は翅をたたむと、青い蝶に取り巻かれた。
「沙渚、私のことをどう思ってる?」
「どうって言われても――、正体不明の……」
沙渚が上半身を起こした時、驚いた青い蝶たちは一斉に飛び立った。現れたのは小憎らしいアイツ――!
「リ、リンシ?」
白いシャツ姿の姿月リンシだ!
「じゃあ、山小屋でもさっきも花の蜜を口移ししたのも―――」
リンシの面(おもて)に緊張が走った。
「しばらく、ここで待っていてくれ。いいな、まだカフェの座敷に戻っちゃダメだぞ」
「なぜ?」
「なぜでもだ。約束だぞ」
言うが早いか、リンシは身を翻して渓流沿いの道を駈けていく。
沙渚は呆然と見送った。
「正座体験カフェ」の扉を開けて、マスターが登山装備のまま、戻ってきたところだった。
座敷から、リンシが飛び出してきた。
「おお、若様、今、戻りましたぞ。花織さんからも自宅に帰りましたと連絡をいただきました。」
「ああ、爺や。ご苦労だった」
リンシは声を潜めた。
「凍蛾将軍が、この地に降り立った気配がする」
「なんですと」
「どこに降り立ったか探ってくるから、座敷の奥から沙渚が出て行こうとしても、絶対にここから出さないように」
「沙渚さまが?」
「座敷の向こうの世界で待つよう言いつけたんだが、お転婆なアイツのことだ。飛び出して来かねない」
「わ、わかりました」
マスターも気を引き締めた。
第 九 章 凍蛾将軍
案の定、五分も経たないうちに、座敷から沙渚が飛び出してきた。
「マスター! 今、リンシくんが来たでしょう。どこへ行ったの?」
「沙渚さん、落ち着いて。お座敷で月光茶を飲みながら正座しましょう」
急いでカウンターの内側で月光茶を作り、座敷へ運んだ。
しぶしぶ座敷へ戻った沙渚だが、リンシを捜しに行きたくてうずうずしている。
「正座の所作のおさらいをいたしましょう。最初にどうするんでした?」
「背すじを伸ばして立つ……」
沙渚は順番通り、所作をしていった。
「そうです。よくできました。さ、月光茶を召し上がれ」
渋い焼き物の茶碗に入った月光茶をひと口飲むと、少し落ち着いた。マスターがにっこり笑って対面に正座した。
「すべてお話しましょう」
「……」
「リンシさまは孫ではなく、私の仕える鱗翅の君と申されます」
「鱗翅の君?」
「普段は月に住む蝶です。月からこちらを眺めていて、鱗翅の君はある女性に気持ちを奪われました」
「えっ」
「はっきり申しましょう。鱗翅の君は花織さんに一目惚れして、ずっと月から眺めておられました。だが数年前に、ある事情でこちらへやってくると、あなたの方に惹かれてしまったのです」
「な、なんですって?」
空になったお茶碗がひっくり返った。
「リンシは、花織から私に心変わりしたってこと?」
「そうです。花織さんは華やかな方ですから遠くから見て心を惹かれたのでしょう。でも、こちらへ来てみたら、沙渚さんに惹かれたようですよ」
「ケンカばかりしてるのに? 花織の方がめっちゃ可愛いのに?」
「実際に接してみて、あなたの優しさに気がつかれたのでしょう。今回も皆さんの無事を祈られていたでしょう?」
「リンシが、私を……。で、彼はどこへ行ったの?」
マスターの表情が引き締まった。
「花織さんを狙っている野蛮な月の者がいましてな、凍蛾将軍と申します」
「花織を狙っている?」
「はい。凍蛾から花織さんを守るために、私たちは月からこちらへやってきたのです――ところが」
「番狂わせが起こったのね」
(喜んでいいのか、嘆けばいいのか?)
「花織さんを守らなければなりません。鱗翅の君は、凍蛾将軍を捕縛して月へ連れ帰るつもりです」
「あの~~、普通の人間じゃないみたいだから、どうやって捕まえるのか想像つかないんですけど……」
「沙渚さんは心配なさらずとも、静かに待っていて下さればいいのです。凍蛾将軍など鱗翅の君にとっては、どうという存在ではありません」
マスターが一笑に伏そうとした時、いきなりカフェの厚いステンドグラスの扉が砕け散った。
「きゃあっ」
マスターが沙渚をかばって覆いかぶさった。ステンドグラスの破片を踏みしめて、赤黒い鎧を身に着けた大柄な男が入ってきた。
右手に剣を持ち、左の脇には人間を抱えている。
「小賢しい鱗翅のやつ! こんなところにアジトを持っていたとは」
赤黒い皮の面貌(めんぼう)から覗く瞳が黄色く光る。
「鱗翅の爺やだな」
マスターは沙渚を座敷の奥へ押しやった。
「凍蛾将軍、これはまたいきなりのお越しで」
烈風が店内に入ってきた。
「さっき、鱗翅の若造が我の女を横取りしようとしたが、逃したから、こっちからアジトへ退治しに来た。鱗翅が逃げ帰っているであろう。出せ!」
「まだお戻りではありませぬ」
沙渚は目を疑った。小脇に抱えられているのは、花織ではないか。
「きゃあっ、花織! 花織! しっかりして!」
ぐったりとして気を失っている。
「あんた、将軍だかなんだか知らないけど、花織に何したのよっ!」
マスターの前に出て、思いきり怒鳴った。
「なんだ、ねんねのみそっかす! 花織は我のものだ。鱗翅を片付け次第、月に連れて行く」
「何ですって! 花の女子高生に向かって、ねんねのみそっかすですって! 無礼なオジサンねっ」
脳天が噴火しそうになって、立てかけてあった傘を握った。
「沙渚! 落ち着け、手を出すな」
凍蛾の背後から走りこんできたリンシが叫んだ。凍蛾がゆっくり振り向き、薄笑いを浮かべる。
「戻ったな、鱗翅。すぐに片づけてくれるわ」
幅の広い剣がリンシ目がけて薙ぎ(なぎ)はらわれる。
マスターが凍蛾に向かって壺の中身をぶちまけようとしたが、手を止めた。
凍蛾の脇腹から花織を奪い返そうとして、沙渚が力のかぎり彼女を引っぱっていたのだ。
リンシが叫ぶ。
「沙渚、そこをどけ!」
「だって花織が!」
第 十 章 蜜の流れ
花織の意識が戻った。
「ここはどこ?」
チャンスを逃さず、マスターが壺を逆さにした。壺からドクドクと溢れる黄金の蜜は、床一面に――。凍蛾将軍の足元にも広がり巨体は足を滑らせてひっくり返った。
「花織、今のうちにこっちへ!」
沙渚は花織を将軍の腕から引っこ抜いて、匍匐前進(ほふくぜんしん)してカウンターの内側に逃げこんだ。
将軍はベタベタの蜜に足を取られて起き上がれない。
壺からはどんどん蜜があふれ出て止まらず、フロアにかさ高くなり――、沙渚と花織は手をつないだまま、座敷の向こうの世界へ流されて行く――。
「沙、沙渚~~!」
「花織、手を離さないで」
「手が、手が蜜でベタベタ……だめ、溺れそう」
凍蛾将軍も抵抗したが、自分の翅が蜜にまみれて開かない。
「おのれ、鱗翅め!」
窓からは、青い蝶の大群が飛び出してきて将軍の身体じゅうに貼り付いた。
「凍蛾、花織さんのことは諦めな」
リンシがあかんべえをしたが、ふたりの姿が見えないことに気づいた。
「沙渚と花織さんは?」
「蜜の流れに巻きこまれてしまわれました!」
マスターが青ざめて叫んだ。
「あの、ドジ娘たち!」
リンシが後を追った。
第 十一 章 花織の好み
沙渚と花織は、そろって男物のパジャマ姿で、カフェの奥の座敷に、クラゲのように力が抜けて座りこんでいた。髪はしずくを垂らしたままで、おしゃべりする元気も無い。
マスターがやってきた。
「申し訳ないですな~。鱗翅さまのパジャマしかなくて」
「いえ、とんでもありません。シャワーまで貸していただいて」
ふたりそろって正座に座りなおして頭を下げた。
「いやいや、壺から大量の蜜を流してしまった私の落ち度です」
マスターは神妙に謝った。
「そうだよ、爺や。いくらなんでも大量に流しすぎだ。溺れなかったのが幸いだ」
「申し訳ございません……」
花織が女神の微笑で言う。
「マスターはリンシくんと一緒に天文台まで蜜と食料を届けて下さったではありませんか。今回も、私を将軍から救おうとしてなさったこと。頭を上げてください」
沙渚が、
「ところで、あの将軍は?」
リンシがヘアドライヤーを持ってきて、
「お仕置きとして、蜜浸しのフロアの掃除を言いつけてやった。大きなモップを持ったまま、何十回も滑って尻もちついてる」
「まあ。反省してるのでしょ? 可哀想な気が……」
「いやいや、かなりの罪だ。早春登山を吹雪にして銀河鑑賞クラブの山を寒波で襲った。そして、帰宅したばかりの花織さんをさらった!」
「けしからんことですな。すべて花織さんを我がものにするための計画だったとは。横暴な片思いだ」
マスターの表情は硬い。
「俺が月から来ていて良かったな」
リンシは鼻高々だ。
(私に心変わりしていながら、山小屋で両方にキスしたくせに……)
沙渚のつぶやきが、リンシの耳に入った。
「人聞きが悪いなあ。あれは人命救助だって」
「そうかしら。しめた! と思ったでしょう。口移し魔!」
「口移し魔?」
「座敷の向こうの緋毛氈の上でも、うたた寝している時にキスしたでしょう! もはや色情なんとかよ」
「色情なんとか!」
容赦なくコキ下ろされて、リシンはしゅんとなった。
花織が気の毒そうに、
「沙渚、マスターのお話によると、リンシくんは、あなたにメロメロだそうじゃないの」
リンシの肩がピクついた。
「私のことを月から見ていてくれたけど、沙渚に心変わりしたって」
花織はリンシに向かい、
「気にしないでね。私、どっちかというとあなたみたいな線の細い人より――」
カウンターの向こうのフロアに目をやった。凍蛾将軍が、冷や汗かきながら正座の稽古を繰り返している。
「ああいうどっしり型がタイプなの」
リンシは、マスターに肩をすくめてみせた。
「はあ? こっちがふられちまったよ」
第 十二 章 命の恩人
「うおおおおお!」
雄叫びがカフェ全体に響き渡った。
蜜びたしの床の上で鎧をつけたまま、大男がきっちり正座をして両のこぶしを天井に突き上げている。
「できた! ピカピカに掃除した床の上で正座ができたぞ~~!」
沙渚と花織、リンシとマスターは、座敷から飛び出してきた。
「おお、凍蛾将軍、いつの間にか、掃除が終わった後、正座の稽古までしていたんだな。やればできるじゃん」
次の夜、沙渚は再びカフェに駆けつけた。リンシから、月に帰ると連絡があったからだ。
黄金色の満月が昇っている。眩しいくらいの月光だ。
裏庭には、白いシャツ姿のリンシがたくさんの青い蝶に取り巻かれて立っていた。漆黒の打ち掛けの鱗翅の君の面影が重なる。
言葉遣いが違い過ぎて、同じ人物とは思えないが。
「帰るって本当?」
「凍蛾将軍を連れて帰って、月命宮で裁きを受けてもらわなきゃいけないから」
「そう……」
急に心に冷たい風が吹き抜けた。
「そんな顔するな。すぐ帰ってくる」
「本当?」
「お前、俺のことがウザいんだろう? いなくなってセイセイするんじゃないのか。ケンカ友達がいないと寂しいのか?」
リンシのシャツの肘先を、沙渚はつまみ、背伸びして彼のカタチのいい唇にちょこんとキスした。
「早く帰ってきて毛氈の上で正座して、月光茶しましょうね」
リンシは目をパチパチした。
「リンシ、山小屋で命を救けてくれてありがとう。……やっと言えた」
「よせやい」
将軍の身柄を預かって、月夜の丘の上でマスターが待っていた。
翔び立とうとするリシンの背に、逞しい漆黒の巨大な翅が広がり、沙渚の白い頬に青と金色が映った。