[291]咲かずの藤よ、咲け
 タイトル:咲かずの藤よ、咲け
タイトル:咲かずの藤よ、咲け
掲載日:2024/05/30
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
巫女を務める女子高生、茄子美(なすみ)の家は藤の花が有名な神社だ。大昔からある藤の木が、ここ数十年はなぜか花が咲かないので、宮司である父親も悩んでいた。
高校の同級生で同じく巫女をしている紫子(ゆかりこ)の母の羅伊羅(らいら)は、若い頃、神社で巫女の最高位を務めたことがあり、茄子美は尊敬している。
ある夜、花のない藤棚に行ってみると、烏帽子に宮司のような装束を着けた青年に出会った。
藤の精だと直感した茄子美は……。

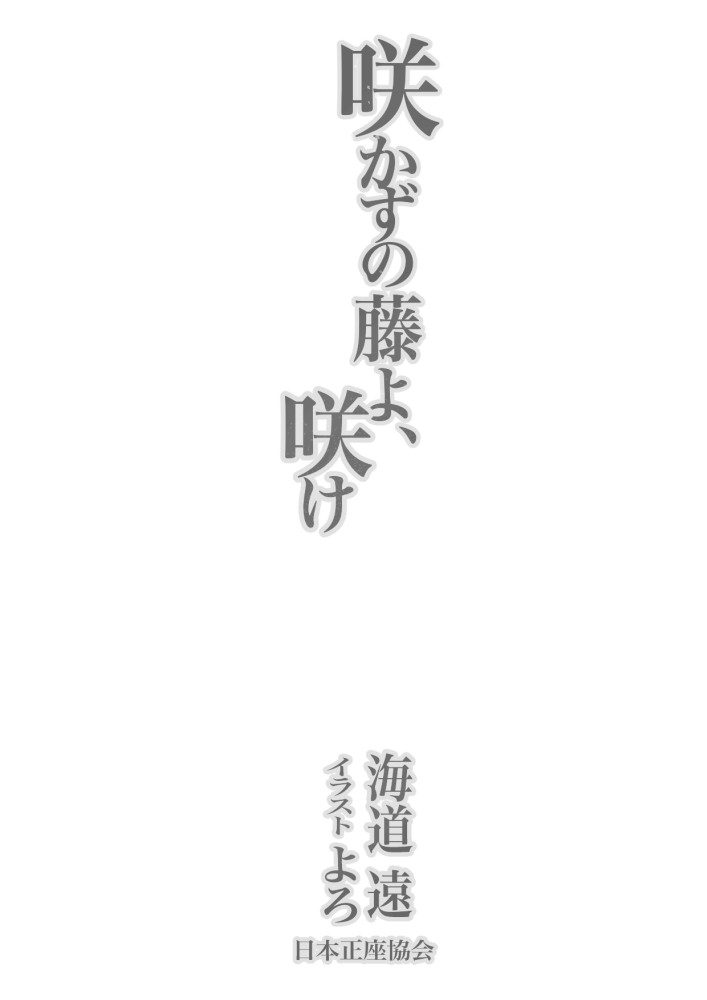
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 なすび
「で、何だったの? 宮司さまの改まっての相談って」
校門を出て、帰宅する学生の人通りが少なくなってから、まつ毛の長い黒目がちな瞳をくるめかせて、紫子(ゆかりこ)は尋ねてきた。お餅のように色が白い。いや、けがれない純白の藤の白さだ。
(ゆかりこは、お母さん譲りのきめ細かい肌の持ち主だからな)
見惚れてから、茄子美(なすみ)は表情を引きしめた。
「例のご神体の藤のことよ……」
言いかけた時、男子がふたり、
「や~~い、なすび!」
「色黒のなすびや~~い!」
からかいながら、ふたりを追い越していく。
「こらあっ! なすびじゃないってば! 茄子美だってば! なすみ!」
茄子美は叫び返した。
男子ふたりは、青いネクタイを風になびかせ、けたたましく笑いながら走っていく。
「まったく高一にもなって、小学生の頃から全然変わらないんだから!」
むくれる茄子美を、ゆかりこは微笑みで包んだ。
「父さんが『茄子』なんて字を使うから、からかわれるんだわ」
「茄子の青紫色はきれいだものね」
「神社の藤に因んでつけたつもりなんだって。父さん、センスないのよ。ゆかりこの紫の字の方がぴったり紫を連想するわ」
「この名前は、以前、私たちみたいに巫女をしていた、お母さんが名づけてくれたの」
「うん。さすが巫女の最上位の一臈(いちろう)を務められた羅伊羅(らいら)さんだけあるわね」
茄子美は、ゆかりこの母、羅伊羅を尊敬して憧れている。才女でありながら物腰やわらかく、いざという時は逞しい。それに、ゆかりこの姉だと言ってもおかしくないくらいに若々しい。
第二章 咲かない藤
茄子美の父親が宮司を務める大藤神社には、何百年も咲かないと言われている藤の古木がある。昔は初夏になると豊かな花房をつけていた写真が残っているのだが、ここ30年ほどは何故、咲かなくなったのかは謎のままだ。
「いい加減に、藤の花を咲かせないとなあ……。茄子美、何か良い方法を思いつかないか?」
ある夜、晩ご飯の後、茄子美は父親と縁側から境内の藤棚を眺めながら、大きなため息をついた。棚には葉が繁っているだけだ。
「藤の花が咲かないこと、お祖父ちゃんも、ひいお祖父ちゃんも、悩んできたんでしょう? 頭が痛いわね」
「今まで代々の宮司があらゆる肥料をやり、植物博士にも診ていただき、手を尽くしてきたが、一向に咲かん」
父親も肩を落としたままだ。
「せめて原因が判ればね。あの藤と話ができれば分かるかもしれないのに」
「花が咲かないのでは、お祭りも途絶えたままだ。地元の氏子さんたち以外にも、観光の参拝客の方々にもお祭りに来ていただきたいいのだが……」
「お祭り? まだ見たことがないわ」
「お前の生まれる少し前までは、藤の花が無くても無理して行事をしていたのだが――。藤棚の下で紫色の毛氈を敷き、子どもはきちんと正座して甘酒をいただくのだ」
「正座して?」
「そうとも! 亡くなった母さんは、正座の正式な所作を知っていたからな。子どもたちに教えていたんだ」
「お母さんもきっと、藤の花が咲くよう祈っているわね」
「茄子美も正座の所作をマスターしなくてはな。お祭りでなくとも、藤棚の下で瞑想や書道の稽古など、やるとなれば計画はたくさんあるのだが、肝心の藤の花が咲かなければ盛り上がらない……」
茄子美はその夜、なかなか寝つけずにパジャマにカーディガンをひっかけ、縁側を下りて境内へ出て藤棚へ行ってみた。
本来なら藤が満開の季節なのに、花はまったく咲かない。月が異様なほど明るい満月だ。一番太い幹が巻きついている棚の柱にもたれて、青白く輝く月を見上げていた。
「藤はたくさんのお水を欲しがるとか。お水も肥料もたっぷりあげるわ。だから、花を咲かせてよ」
第三章 藤の精
「水も肥しも当たり前のこと」
ふと、凜(りん)とした男性の声が聞こえ、青白っぽいひらひらしたものが、茄子美の頬に落ちてきた。
(もしかして、藤の花びら?)
上背のある人影が立っている。
「――あなたは?」
烏帽子(えぼし)というのか、縦長の被りものをした青年が背をかがめて藤棚の中へ入ってきた。幅の広い藤色の着物の裾を引きずっている。父親の宮司が神事の時に着る直衣(のうし)そのものだ。
「もしや、藤の精? ――そうね、藤の精ね!」
茄子美の背中がゾワゾワした。
青年のまつ毛は濃く、鼻梁(びりょう)に品がある。心なしか、やや微笑んだ。
「……どうかな?」
忍びやかな風のような低い声が答えた。
瞳の色が濃い紫になったり薄い紫に見えたりする。甘い匂いは肩にかかる長い黒髪から漂うのか――。
「余の名は紫夢(むむ)。紫の夢と書いて『むむ』と申す。人は【貴公紫さま】と呼ぶ」
「紫夢……。きこうしさま?」
茄子美の緊張は、ガラガラと崩れ落ちた。
(なんて、なんてナルシストな藤の精なの?)
「よいか、【貴公紫】の【し】は、【紫】の余韻を心に響かせて呼ぶのだぞ」
紫の藤の房を描いた扇を口元に当てる様子は、気取りきったナルシストこの上ない。それでいて「俺さま」口調で威張っている。
(なんてずうずうしい! この藤の精の気まぐれのせいで藤の花が咲かないんじゃ?)
茄子美は眉間をしかめた。
「そなた、水や肥しと申していたな。もうひとつ大切な、枝の剪定(せんてい)作業を忘れてはならぬ」
「そんな基本的なこと、父さんはちゃんとやっているわ」
「父さんとは、父上のことか」
「そうよ。私は宮司の娘で、この神社の巫女をやっている大藤茄子美。なすびの茄子と書くけど、なすびじゃなくて【なすみ】ですからね」
「【なすび】……【茄子】の文字だな。これは、いとをかし(めちゃんこ面白い)。笑わずにおれようか」
扇を口元にあてて、藤の精は声を抑えながら涙を流して笑っている。
「……むむむ」
茄子美は近年になく、イラッどころか、ムッカ~~ッと沸き上がってくる熱い怒りを感じた。
第四章 花を咲かせて
朝になって目を覚ますと、茄子美はいつの間にか、自分の部屋の布団に戻っていた。窓の外の藤棚は変わりない。
(昨夜の生意気なナルシスト男は……? 本当に藤の精だとしたら話ができるんだから、花を咲かせるよう説得するチャンスだわ!)
学校へ行っても授業中は、上の空で考え続けた。
ゆかりこが、茄子美の様子が変なことに気づいて、休憩時間に席にやってきた。
「どうしたの? 朝からぼやっとして」
「ううん、なんでもないわ」
ゆかりこに、藤の精と会ったなんて言っても信じてくれないだろう。今のところは言わないことにした。
どう言えば、あの紫夢(むむ)とかいうナルシストは、お願いを聞いて藤の花を咲かせてくれるだろう)
午後からの授業やHRも上の空で考えていた。
(そうだ! 超ナルシストなんだから)
その夜、藤棚の下で待っていると、十六夜(いざよい)の月の夜にも【貴公紫さま】とやらは現れた。
「やっぱり出たわね」
「……幽霊のように申すな。十六夜の月を愛でるついでに、そちがをかしなことを申すのではないかと思い、参ったまでのこと」
「お願いがあるのよ、貴公紫さん」
「何かな」
「藤に花が咲かなくて困っているのよ。花を咲かせてよ。咲かせたら人気者になれるわよ」
「花咲じじいのように申すな。余はまだ若い」
「え? 見た目には若いけど、花咲爺さんより、ず~~~~っとトシがいってるわよね?」
【貴公紫】は、小さく咳ばらいをした。
「そんなことはどうでもよい。それに、人気ならあり余っておる」
「このまま、葉っぱしかなくて、柳みたいに長い藤に負けて悔しくないの? ちょっとこれを見て!」
茄子美はスウェットの上着の中に持っていたタブレットを取り出した。そして、日本全国の有名な景勝地の藤の写真を網羅(もうら)した画面を映した。
第五章 切ってしまおう
「ほほう、これは……不思議な鏡よのう」
「ま、魔法の鏡みたいなもんよ。スイッチひとつで有名な藤の場所が見えるのよ。関東、関西、それぞれ十カ所ずつ選んでみたの。薄紫、青みの強い紫、純白、ピンク。ぶどうの房に似たカタチのや、人間の身長ほど長いもの、藤って色んな種類があるのね」
「お? さっき藤の後ろの方に見えたのは」
「ああ、黄色い花房ね。これは藤によく似ているけど、別の種類で、キングサリという名前の花よ」
茄子美も改めて、隅っこに写っているキングサリという目にしみるようなレモン色の花房を見つめた。
「藤にそっくりだわ。まだ見たことないけど」
「どの藤も素晴らしいが、この神社のかつての藤には及ばぬな」
【貴公紫】は、頭をそびやかした。
茄子美は次に、画面に各地の見物客の数の棒グラフを映し出した。各、景勝地には競って沢山の見物客が訪れている。
「どう? ここの神社の藤が負けていないなら、こんな人出、あっという間に上回れるでしょう?」
「無論だ」
「ほら、見て。みんな、こぞって藤の花を見上げているわ。この神社では、紫の毛氈(もうせん)を敷いて正座して鑑賞会を開くから、みんな【貴公紫】さんの美しさにうっとりするわよ」
茄子美は懸命に藤の精の自尊心をくすぐった。
「夜にもライトアップしたり、ランタナを用意すると暗闇の中に神秘的な魅力があふれるでしょうね」
「灯りの力なぞ借りずとも、余は神秘的すぎる美貌だ」
(うう……)
茄子美は歯ぎしりした。
(ああ言えばこう言う。どこまで憎らしいのかしら!)
ちょっと攻める角度を変えてみる。
いきなり藤の精の袖をめくり上げ、腕をつかんだ。
「思った通り、肌はスベスベ。それでいて藤の幹のように逞しい」
「気安く触れるでない!」
【貴公紫】さまは、藤の描かれた扇で、茄子美の手をペシッとはじくと、素早く袖を整えた。茄子美の手の甲には扇の痕(あと)が赤く残った。
(痛っ……)
堪忍袋の緒が切れた。
「咲かぬなら、切ってしまおう、ぐうたら藤!」
背後に隠し持っていたご神刀を取り出して、鞘(さや)から抜く。刀に月の光が反射した。
「な、何をする、なすびおなご!」
「なすびおなごですって~~~? かんっぜん、アタマ来た! どうしても花を咲かせないなら、幹を切ってしまうわよ!」
第六章 羅伊羅さん
また、逃げられた……。
闇が薄くなり、十六夜の月が山の向こうに沈む頃、【貴公紫】の気配は消えてしまった。
ご神刀の束(つか)を握りしめて悔しさに震えていると、
「茄子美~~!」
バイクのエンジン音が聞こえてきて、母親の羅伊羅と共に鳥居の脇に大型バイクから降りて、ゆかりこが駆けてくるではないか。
「茄子美ちゃん、大丈夫?」
ゆかりこの母親の方が、いつもの落ち着きはどこへやら、ヘルメットを脱いだ髪の毛を乱している。もっと驚いたのは深いパープルのライダースーツを着ているではないか。
「どうしたの、ゆかりこ、フジコさん……、いや、羅伊羅さん」
「お母さんが、ご託宣(たくせん=神様のお告げ)の夢を見たのよ! 茄子美、不思議なものに会ったんじゃない?」
「さすが、元、巫女の最上位の一臈(いちろう)だった羅伊羅さんね。不思議すぎるのに会いましたよ!」
「やっぱり。それは、どんな?」
羅伊羅が娘の前に出て、茄子美の鼻先に迫った。
「藤の精です。藤棚に花を咲かせない、頑固でナルシストで生意気なヤツです!」
今回も逃げられた悔しさに、茄子美は地団太踏んだ。
「それは、直衣を着た青年のカタチをしていた?」
羅伊羅も息がはずんでいる。
「そうです。羅伊羅さん、よくご存知で」
「ああ……。やっぱり紫夢(むむ)ちゃんだわ……!」
羅伊羅は地面にひざまずいて、両手を組み合わせた。
「茄子美ちゃん、その藤の精は悪くないわ。彼は操られているのよ。炎蛾(えんが)という蛾の魔物に。だから、花を咲かせたくても咲かせられないの」
「茄子美まで蛾の魔物に襲われないで良かった!」
ゆかりこは、茄子美の肩を抱きしめた。
第七章 炎蛾
三人は宮司宅に移動して、とりあえず休憩した。早朝だが、宮司も起きてきた。
「どうした、茄子美。ヤケに早いなあ。おや、――ら、羅伊羅さん?」
羅伊羅が身体の線がモロに分かるパープルのライダースーツを着ているので、宮司はドギマギしている。
羅伊羅は話しはじめた。
「私は前世でしばらくの間、藤の精の幼子(おさなご)、紫夢という男の子の世話をしていました」
「あ、『むむ』って【貴公紫】の本当の名前だわ」
茄子美が口走った。ゆかりこは少し戸惑って、
「お母さん、私は初めて聞く話だわ」
「あまり広める話ではありませんからね。人々は前世のことなんて信じてくれないだろうし……」
「羅伊羅さん、炎蛾という魔物はいったい……」
宮司が神妙な顔で尋ね、娘たちは答えを待った。
「炎蛾は――、スズメバチのように好戦的で、策謀をめぐらせて必ず敵を屈服させる残虐非道な蛾です。おそらく彼女は、昔にこの神社の藤の木に卵を産みつけにやってきて、私がむむちゃんを可愛がっていることに嫉妬したのでしょう。蛾は卵を産みつけたまま飛び去らねばならず、天塩をかけて育てることができませんから」
現世では藤の木がご神体、羅伊羅が最高位の巫女である。
「それで、炎蛾が藤の木に花を咲かせなくしたのね」
茄子美は納得した。プライドの高い【貴公紫】が、巫女の世話になっていたなんて言うわけがない。
「炎蛾を退治しなければ、藤の花は咲かないわ」
いつになく厳しい表情で、羅伊羅は言う。
「でも容易いことではないわ。炎蛾の手強さ(てごわさ)は仙界でも響きわたっているくらいですもの」
第八章 正座して謝る約束
茄子美はタブレットを出して、先ほどの景勝地の藤を見ていた。
「あ、茄子美ちゃん、さっきのところ、もう一度見せてくれる?」
藤の片隅に、目に鮮やかなレモン色のキングサリが写っている。
「キングサリは藤にそっくりな形状をしているけど、まったく別の種類で独特の甘い香りを放ち、種子は毒を含んでいるのよ。炎蛾はこのキングサリの毒を利用したと思われるわ」
「まあ!」
「きっと甘い毒の香りを嗅がせて、むむちゃんを思い通りに操っているのだわ」
「あの~~、羅伊羅さん」
茄子美が教室の片隅でそっと挙手するみたいに、弱々しい声を出した。
「改めて確かめたいのですけど、むむちゃんって藤の精で、ご神体のことですよね? 藤棚の一番太い樹の」
「そうですよ」
「わあ~~! どうしよう!」
茄子美は急にソファに立てかけてあった長い剣を両手で握りしめて、ジタバタした。
「お前、それは……」
「父さん、ごめんなさい! 花を咲かせてもらいたい一心で本殿の奥からお借りしたの」
宮司が顔色を真っ白にした。
「それは、ご神刀。まさか、藤のご神体さまに突きつけたりしていないだろうな」
「……だって……、そうでもしないと言うこと聞かない頑固者なんだもん……」
「お前は、なんと罰あたりなことを……」
宮司さまは卒倒寸前である。
羅伊羅が落ち着いた表情で床に正座し、
「宮司さま。大丈夫です。むむちゃんは罰など下したりなさいませんよ」
「本当? 羅伊羅さん」
「私が指導する美しい正座をして謝れば、許してくださる優しい男の子です」
(あいつに正座して頭を下げるのか……)
茄子美の心にもやもやしたものが残る。
「それより、茄子美ちゃん、さっきのキングサリのことだけど、こちらも『目には目を、歯には歯を!』あれを使って、炎蛾を捕えるしかないわ」
「え、炎蛾を捕える? ものすごく恐ろしい蛾のおばさんなんでしょう?」
炎色の中に赤黒い眼玉のついたマントを着た、ぶよぶよの貫禄ある蛾の姿、毛がいっぱい生えた腕や羽ペンみたいな触角が思い浮かんで、茄子美はゾッとした。
第九章 キングサリ
神社の裏山は崖になっており、藤が思ったより広く根を蔓延らせて(はびこらせて)いた。崖の中腹にキングサリが生えている、と宮司は言う。
かなり気温が上がった初夏、辺りに繁る雑草が、人間が苦しくなるほどの勢いで生気を吐いている。
茄子美とゆかりこ、母の羅伊羅は、しっかり登山装備をして崖っぷちを慎重に一歩ずつ一歩ずつ、登っていた。
視線を上げると、こんもり繁った藤の向こう側に、レモン色のキングサリの花房が見える。
「あったわ、キングサリ!」
茄子美が叫んだ。
「ずいぶん高い場所ね」
「こうなったら、崖を登って手を伸ばすしかないわ」
「待って」
羅伊羅が止めた。
「出っぱった岩にロープを巻きつけて落とすから、登るのはそれからにして」
言うが早いか羅伊羅は岩へ登り、ロープを巻きつけた。
「茄子美ちゃん、いい? ロープを渡すわよ」
「はい!」
茄子美はロープを受け取り、胴体に巻きつけると崖に登り始めた。
「わぁ~~~、キングサリのすごい香り! シュンシュンして酔いそう」
「あなたが酔っちゃダメよ。ちゃんとキングサリの蔓(つる)を切り取って、持って帰らなきゃ」
「分かってるわ、ゆかりこ。……色んな木や草がこんがらがって、キングサリの蔓もダンゴになってるのよ」
茄子美は腰に着けていたカマを取り出し、まといつく草や蔓を切り取って、キングサリの蔓だけを引っぱる。
「そうそう、その調子よ。繁みからズルズル出てきたわ」
「どのくらい刈り取ればいいかな?」
キングサリのレモン色の花房も一緒に引っぱり出されて、美しい。
羅伊羅が岩から降りてきて、茄子美の作業を見上げた。
「そのくらいで十分じゃない?」
両手にひと抱えもキングサリの蔓の束を抱えた茄子美を見て、ゆかりこがうなずき、キングサリは無事に収穫できた。
茄子美たちは、三日がかりでキングサリの蔓を使い、炎蛾を捕獲するための強力な網を編み上げた。
第十章 炎蛾の捕獲
いよいよ炎蛾を捕える。
羅伊羅の調べで、炎蛾は産卵期を迎え、幼虫は藤の花の蜜をエサにすることが判っている。三人は神社の藤棚の下で待ち伏せすることにした。
「蛾がやってくる宵までには、まだ陽が高いわね。この間に正座のお稽古をしましょう」
羅伊羅が言い出した。茄子美が【貴公紫】に謝るための正座の稽古だ。
「ところで、茄子美はどうして藤棚の下で出会った【貴公紫】が、藤の精だと判ったの?」
「見ればピンとくる格好をしていたのよ」
「ふうん……」
「疑ってるの? ゆかりこ」
「ううん、早く言ってくれれば、協力したのになって思って」
「やっぱ、疑ってるじゃないの」
「違うってば。正座のお稽古、私もつき合うわよ」
ゆかりこもレジャーシートを敷いた上に乗った。羅伊羅が立ち上がった。
「まず、背すじを伸ばして真っ直ぐ立って。それから膝をシートの上について。できましたか?」
「はい」
「かかとの上に静かに座って。スカートはお尻の下に敷いて」
今日は、スカート姿はゆかりこだけだ。
「はい、ふたりともよくでき……」
羅伊羅が言いかけた時――、
ドッサ―――!
大きな物体が、茄子美とゆかりこの上から落ちてきた。
「きゃあ~~!」
「な、何、これは! デカい!」
ふんわりしているが、チクチクする。
「重い! 苦しい!」
「毛が生えてるわ。チンパンジーでもどこかから脱走したの?」
「違うわ、蛾だわ。炎蛾?」
羅伊羅が近寄って確かめに来た。
「炎蛾だわ。人間ほどの大きさ。いえ、もっと」
赤黒い衣を着た女が、全身にキングサリの蔓と花をまとわりつかせて、茄子美の身体の上に乗ってジタバタしている。
「う……、お、重い……」
うめいている間に女の身体はみるみるしぼんで、キングサリの網の下で小さなカタマリになってしまった。
「しぼんでしまったわ」
茄子美は網から這い出てカタマリを見守った。強い風が吹き、カタマリは黒い塵となって吹き飛ばされていく。
「触らないで!」
甲高い声に驚いて振り向くと、桃色の漢風の衣を着た若い娘が立っていた。髪にはピンクの藤のかんざしを飾って垂らせ、愛らしく結い上げている。
娘は突き刺さるような視線で茄子美たちを睨んだ。
「藤の花が咲かないのは、炎蛾のせいじゃありません。彼女は木に卵を産みつけただけ。卵や幼虫は藤には無害です。幼虫は藤の花の蜜が無ければ生きられないのに、咲かせなくするわけがないでしょう」
第十一章 桃笛
茄子美が問い返す。
「あなたは一体、誰?」
「わらわは桃笛(ももふえ)」
「炎蛾の仲間なの? それとも藤の仲間?」
「さあ、何者かしらね?」
桃笛と名乗った少女は薄ら笑いを浮かべるばかりだ。
「先日【貴公紫】と名乗る気取った藤の精に会ったけれど、どうして藤が咲かないのか何も言わないの」
茄子美が首をかしげる。
「それは藤の精ではなくて、紫の蛾の化身よ」
「【貴公紫】が藤の精じゃないですって?」
「そうよ。アイツは濃い紫の蛾の化身。アイツが藤の色素を吸い取って、藤の花を咲かせなくしたのよ」
「……!」
茄子美は驚いて、言葉に詰まりそうになりながら、
「位の高い巫女を務めていた羅伊羅さんが見た夢から、炎蛾が【貴公紫】から花を咲かせる力を失くしたと判ったのよ」
「ふふふふ……。愚かなこと」
桃笛も負けてはいない。
「本物の藤の精はわらわ、桃笛よ。貪欲な【貴公紫】に色素を吸われて、長い間、花を咲かせることができないの。彼の目を逃れるために、仕方なく桃色の藤を咲かせるにとどまっているのよ。ほら、生気がなくなりそうで衣がぼろぼろ……」
「え? じゃあ……」
(あんチクショウ、やっぱゲス?)
桃笛の言い分に、茄子美は翻弄された。
(羅伊羅の夢か、この娘の言うことか、どちらを信じればいいのだろう?)
「茄子美、今こそ正座して落ち着くのよ」
ゆかりこの声に、我に返った。
心静かに正座してみる。静かに鼓動を調え(ととのえ)、祈りながら正座して、藤棚の下を吹き抜ける風の音を聞き、瞳を閉じた。
やがて――、
桃笛の身体から炎蛾と同じ色の炎が燃え上がるのが見えてきた。
中心に黒い空間がぽっかり空いて、桃笛の心の闇の黒い炎が燃えている。
(そうよ! 【貴公紫】は、ああ見えて誠実なヤツよね。なんと言っても、羅伊羅さんが、しばらく育てたんだから)
(こんな少女に惑わされちゃいけない。神社の藤棚を乗っ取ろうとしている野望の炎が見えたわ)
正座の背中をぐっと伸ばして、力強く瞳を開けた。
(桃笛とやら、私は【貴公紫】を信じるわ)
(ううっ)
愛らしい色白の顔が苦し気に歪み、桃色の花のかんざしが地面に落ちた。
「おのれ、我ら炎蛾一族に盾つきおって」
老婆のしゃがれた声が出た。桃笛は弱々しく飛びあがり、翅(はね)を広げて彷徨っていく。
(桃笛こそ、上空から落ちてきてしぼんだ瞬間に、魂を入れ替えて、被害者を装っていた炎蛾の正体だったのだわ)
茄子美とゆかりこは、身を寄せ合った。
護身のために――大量に採ってきたキングサリは、羅伊羅が押し花にして保存した。
第十二章 奇跡の藤
夏を越えて、その秋、驚くべきことに、神社の藤棚に花房ができてツボミがつきはじめた。
(蛾の力が弱まったんだろうか)
茄子美はもちろん、宮司もゆかりこたち巫女も、氏子さんたちも大喜びだ。藤祭りの準備を始める。その情報はネットでいち早く広まり、「秋に咲く藤」を見物するために大勢の見物客や参拝客がやってくるだろう。
しかし、【貴公紫】の姿を見たものはまだいない。
いよいよ祭りの当日、茄子美は、かねてより宮司が企画していた藤棚の下での催しをした。紫の毛氈を敷いて、スケッチ会、お茶会、甘酒会、そして、もちろん正座の会。
それと、羅伊羅の提案で、キングサリの花の押し花のお守りを参拝客に授与することにした。
「キングサリの毒は種子を豆と間違えて食べないかぎり、大丈夫。炎蛾を捕えるのに、ひと役かってくれたから、きっと守ってくれるでしょう」
宮司も茄子美も大賛成して、巫女さんたち総出でお守りを作った。
境内では駄菓子屋さんや金魚すくい、当てものも用意して、大盛況だ。
茄子美が当てもの係のチビッコの対応に追われていると、ゆかりこがクイクイとエプロンの端っこを引っぱった。
「なぁに?」
「あれ? さっき、桃笛にそっくりな女の子を見たと思ったんだけど」
「桃笛ですって?」
正体が蛾だった強気な女の子の記憶がよみがえった。
かたわらで、タコせんを食べていた小学生の男の子が、
「中国のコスプレみたいなカップルが、金魚すくいしてたよ」
「カップル? 男の人はどんな?」
「前に藤棚の上で、よくお昼寝してた細長い帽子の人だよ」
「細長い帽子の人……」
「茄子美ねえちゃんとも、前に夕暮れに話していたじゃないか。俺、ワンコの散歩の時に見かけたぜ」
「え?」
戸惑っていると、
「これ、見て」
ゆかりこが、金魚すくいの金魚の器(うつわ)を持って見せた。紫とピンクの鱗粉がべったりついているではないか。
「これは……」
「見覚えあるわ。桃笛の衣の色だわ。同じところに紫の鱗粉が」
「紫の鱗粉――、まさか、まさか……」
唇が冷えてこわばった。
「よお」
突然、背後から声をかけられて振り向くと、半年ぶりに見る――、
「【貴公紫】……!」
間違いない。
瞬間、茄子美の耳から、お祭りの雑踏は消えた。
「藤の花が咲いて良かったな。【きこうし】の【し】が【紫】っぽく聞こえないけど」
「そうだ、謝らなければ!」
茄子美は、境内の砂利の上に急いで正座して、丁寧に頭を下げた。
「あの時は、ご神刀を振りかざしたりしてすみませんでしたッ」
「いいってこった。今年は特別に気に入った女が見つかったから、いい卵が残せられそうだ」
「卵……?」
お祭り客にまぎれて行こうとする【貴公紫】を追いかけてきたピンクのひらひらの衣の少女が振り向いた。
(だから言ったでしょう、【貴公紫】は、紫の蛾の化身だって)
鋭い瞳が言っている。
(じゃあ、今まで藤の花を咲かせていたのは……。羅伊羅さんが面倒みていた子じゃないの?)
茄子美の疑問を見透かしたように、桃笛がドヤ顔を向けた。
「蛾の幼虫は面倒みてくれる者を利用して育つのよ。たかがひとりの巫女の前世の記憶に、ちょいと手を加えるくらいは赤子の手をつねるようなものよ」
「【貴公紫】の紫夢が、羅伊羅さんの前世の記憶に細工したっていうの? 桃笛――炎蛾、あんたの命令ね!」
ふたりは連れ立って行こうとする。
「あっ、【貴公紫】! 待って!」
彼が振り向いた。
「よぉく、よ~~く考えて行動を決めてね、悪い存在に騙されないようにね。ナルシストでお人好しなんだから。紫夢ちゃん……」
「むむちゃん……?」
「はい、これ。あなたが藤の精でも炎蛾の仲間でもどっちでもいいわ。悪い存在に騙されないよう、キングサリの押し花のお守りよ。いつも肌身離さず持っているのよ!」
キングサリのお守りを、【貴公紫】の懐深く押しこんで、茄子美はきびすを返した。
【貴公紫】は、しばらく雑踏の中に立ち尽くした。
――その後、紫の蛾も炎蛾のウワサも聞くことはなく、藤の花は毎年あふれんばかりに咲き誇り、人々の眼と心を楽しませた。




![[5]とりあえず座れ 1](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)



