[104]かぐや姫、わらしべ大奥で正座の稽古
 タイトル:かぐや姫、わらしべ大奥で正座の稽古
タイトル:かぐや姫、わらしべ大奥で正座の稽古
分類:電子書籍
発売日:2020/11/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:44
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
月迷宮のかぐや姫は、年老いたおばあさんになっていた。ぼろぼろの月命宮で、侍女も番兵もすべてお年寄りだ。
ある日、侍女のきさらぎが、青い星の天子様がかぐや姫を所望だと知り、なんとかかぐや姫を若返らせらないといけないと焦る。そんな時、青い星のある村で流れてきた桃を食べて若返った夫婦のことを聞きつけて、月に呼び寄せる。夫婦と小さな男の子がやってくる。
男の子の名前は桃太郎。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/2496649

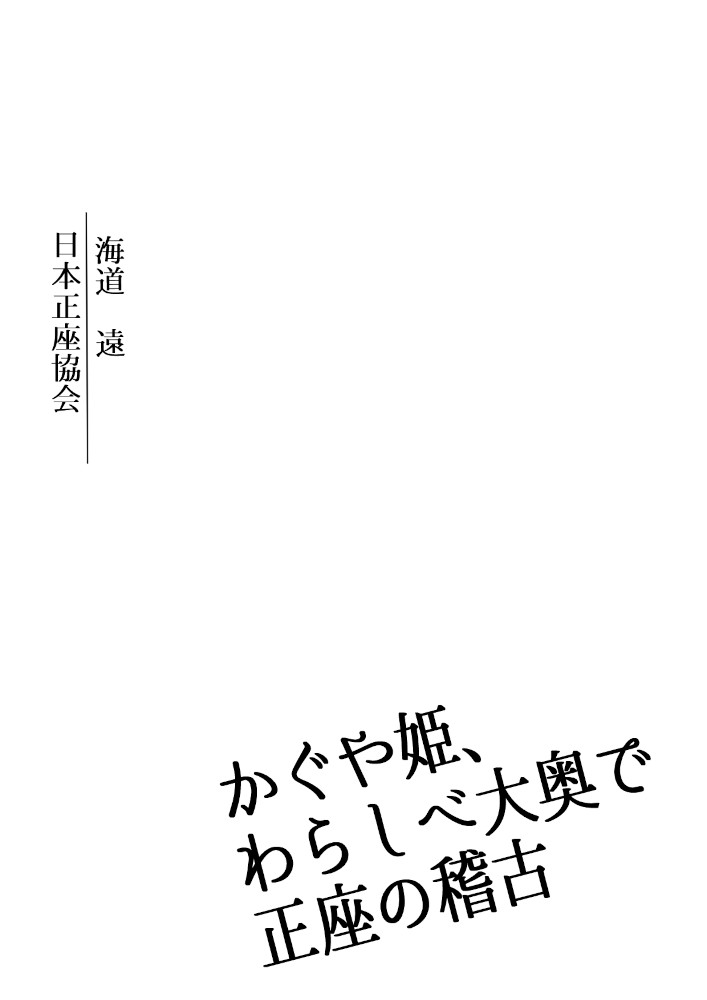
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 若返るという噂
空にぽっかりと浮かぶ月に、月命宮という宮殿があった。
宮殿のぬしは、かぐや姫という。
長い長い年月のうちに月の力は弱ってしまい、姫は五千歳くらい、すっかりしわしわのお婆さんになっていた。
かしずく侍女たちも全部、お婆さんになってしまい、憲兵たちも入歯をふがふがさせたお爺ちゃんだ。腰をかがめて槍を持っている。いや、槍を支えにやっと立っている。
かぐや姫に貢ぐ殿たちもいなくなったので、朱色と金色でピカピカだった月命宮も、禿げたり瓦が落ちたりして、塀はところどころ崩れ、ぼろぼろになってしまった。
かぐや姫がそのように輝きを失くしたので、青い星から眺めている人々からは、新月しか見えない日が続いていた。
そこへ、青い星の大和国の天子様がかぐや姫の、ず――――っと昔の美貌の噂を聞きつけ、ご所望だということが分かった。
侍女頭のきさらぎは、このままではいかん、と一計を案じた。
ある日、かぐや姫の奥宮に上がると、
「姫様、これぞ千載一遇の大チャンスですよ。どうにかして青い星まで行き、大和の天子様のハートを射止めたら、月命宮も姫も若返りますぞ」
「しかし、どうやって天子様のハートを射止めるのじゃ。わらわはこの通り、ふがふが」
きさらぎはにやりと笑った。
「わたくしが、噂集めの侍女から耳よりな情報を得ました。青い星のある村で、川から流れてきた桃を拾い上げた老夫婦に、桃から玉のようなおのこが生まれたそうでございます!」
「桃から? それはめでたいことじゃのう」
かぐや姫は脇息にもたれて、のんびりつぶやくだけである。
「姫さま、他人事ではございませぬ。桃から生まれたというのは、真っ赤なウソだそうで、実は、老夫婦は流れてきた桃を食べたそうなのでございます。すると二人は若がえり、見事に玉のようなおのこが生まれたそうでございます」
「ええ?」
「つまり、その桃を食すれば、姫さまも若返ることができるでしょう」
「そんなこと、うまくいくじゃろうかのう」
「万事、このきさらぎにお任せ下さいませ」
老婆になっても豊満なきさらぎは、太い胸をどん、と叩いた。
「ただいま、密かにその老いていた夫婦を月命宮に連行いたしておるところでございます」
「まあ、手の早いことじゃのう、きさらぎ。……ごほごほ」
かぐや姫は、色あせた扇を口元にあてて咳にむせた。
驚いた。自分も若返ることができると聞いては高鳴る胸を抑えることが出来なかった。
第 二 章 若返った夫婦
例の夫婦が、ぼろぼろになった輿で赤ん坊と共になんとか月に渡ってきて、連れられてきた。
二人は目隠しをされていたが、それを解かれるとぼろぼろの月命宮にあふれている老人たちに驚いた。千人もの老女がカビくさい打掛を着てひしめいている。
かぐや姫が一段高くなっている玉座から小川の流れのような銀髪を垂らしたまま声をかけた。
「わらわは月命宮のかぐやじゃ。そなたたちか。桃を食べ、若返ったというのは」
「そ、そうでございますが、あなた様がかぐや姫? 不老不死ではなかったので?」
夫婦も驚いた。かぐや姫というと、不老不死の月の女王と聞いていたからだ。
「そうなのじゃが、今はこの通り、月の力が弱ってしまい……。ごほごほ。……そこで、そなたたちが食した桃を分けていただきたいと思うてのう」
すると、夫の方が、
「あの桃はたった一個でしたので、食べてしまいましたが、種だけ残しておいたものを植え、苗木が育ちましたので、わらしべ長者様に献上し、桃太郎の金糸銀糸を織り込んだ立派なな戦装束と取り換えてもらいました」
「なんですと」
かぐや姫より、きさらぎが先に叫んだ。
「わらしべ長者とな? それはまずい! その苗、どこへ持っていかれ、何と取り換えられるか分かりませんぞ。あの者は取替えクセがついているからの!」
青い星へやらせていた爺やが答える。
「その桃の苗、わらしべ大奥の奥女中たちに与えられたよしにございます。奥女中たちは毎日、桃を土下座して伏し拝んで食し、美貌を保っているそうにございます」
「わらしべ長者の大奥とな? あのわらしべを持っていた若者、そんなところを持つまでになっていたか」
「桃をひとつ、将軍様に献上して、大奥を丸ごと手に入れたということでございます」
爺やの言葉に、いっそうきさらぎは驚き、
「あの男、そこまで強欲になっていたとは! しかし、それじゃ! その桃を手に入れるのじゃ」
きさらぎの意欲をそそるように、爺やは、
「大奥の守りは厳重の上の厳重。ちょっとやそっとでは入れませぬ。大奥に女中志願した方が容易いのではないかと思われます」
「女中志願じゃと?」
かぐや姫の垂れたまぶたが、やや開かれた。
「姫様、おいたわしや、屈辱ではございましょうが、それしか手はございません」
月命宮の女官が集められ、かぐや姫をなんとか若返らせようと飾り立てたが、飾れば飾るほど老いが目だってしまって滑稽に見える。
「だめじゃな。おしろいを塗るとシワがよけい目立つし、紅はボロボロになって、唇にのらん」
かぐや姫ときさらぎが大きくため息をついた時だった。
桃太郎が、母親の膝からよちよち歩きで降りた。そして叫んだ。
「ぶちでのこじゅちじゃ」
「ぶ、ぶちでのこじゅ? ? ?」
きさらぎが口真似したが、何のことか分からない。
「違う、ぶちでのこじゅちじゃと申しておりゅに。ぶちでのこじゅちを、おにいたんたちにぶんぶんしゅりゅと、坊が大きくなりゅ!」
皆は呆気にとられた。この幼き子はいったい何を言っているのだろうか?
「桃太郎どのの母どの。今、桃太郎どのは何と申されたのじゃ?」
きさらぎが尋ねた。黒髪を後ろで束ねた若い母親は、首をひねり、
「おそらく……ですが、『うちでのこづち……打出の小槌……一寸法師を大きくした打出の小槌をぶんぶんすれば、自分が大きくなる』と申したのではないかと」
きさらぎが、続ける。
「一寸法師? おお! 山から川を下って都に出てきた小指くらいの大きさの武士のことじゃの。大納言の姫君を鬼から守ったという。で、打出のなんとかで桃太郎殿が大きゅうなれば、どうなると?」
「かぐやお婆ちゃんは、坊に恋ちて若返りゅのじゃ」
そこで桃太郎は、母親にずるずるしていたアオバナをチン、してもらった。
「かぐや姫さまが、成長した桃太郎どのに恋して若返るですと!」
きさらぎは飛び上がって喜び、手下共は再び青い星へ急いだ。
第 三 章 打出の小槌の効力
今度はずいぶん時間がかかったが、かぐや姫に仕える女官たちは、一寸法師の仕える権納言様のお屋敷から「打出の小槌」を借りてくることができた。
月命宮の皆と、桃太郎の両親はしげしげと金ピカの小槌に見惚れてから、
「ほほう、これがそうか。そら、これを姫さまに向かって振るのじゃ」
きさらぎが叫んだ時、桃太郎が母親の膝から無理やり降りた。
「違~~う! 坊にぶんぶんすりゅの!」
しかし、遅かった。
老いた上に打出の小槌を振られたかぐや姫は、さらに年老いてやせ細り、玉座にしっかり座ることもできなくなってしまった。
「姫さま、大丈夫ですか」
「気をしっかりお持ちになって」
侍女たちは真っ青だ。
なんとか気を取り直し、桃太郎に向かって小槌を振ると、よちよち歩きだった桃太郎は、みるみる間に背が伸び肩幅も逞しくなり、神々しいほどの青年に成長した。
「おお、この立派な殿方は!」
年老いて弱りきっていたかぐや姫のほっぺが真っ赤になったかと思うと、銀髪だった髪は黒々としたしっとりした艶やかな髪に、頬はつるつる紅く、瞳は星のように輝き美しい姫君に若返った。
きさらぎが姫の膝に泣きついた。
「姫さま~~。おお、間違いなくかぐや姫さまじゃ」
「きさらぎ、そなたも若返っておる」
「あら、これは?」
鏡や泉に自分の姿を映した侍女たちは、全員若返っていた。月命宮も命を吹き返し、金ピカになっている。床が鏡のように光り輝き、庭には緑があふれ牡丹の花も咲き、小鳥が群れている。
「打出の小槌で成長なさった桃太郎様に恋してしまったのは、わらわたちだけではなさそうじゃのう。花も小鳥も皆、恋してしもうたようじゃ」
かぐや姫が鈴のような声で笑い、皆でひやかしあった。
桃太郎も、にっこり笑い、
「それがしがお役に立てればそれで良かった」
きさらぎが胸を撫で下ろし、
「ではもう、わらしべ長者殿の大奥へ行かなくてもようなりましたな」
「待ちや」
かぐや姫が鋭く止めた。
「わらしべ様の大奥では、桃の木を伏し拝んでいるそうではないか。桃太郎様のご両親を若返らせて、わらわたちに打出の小槌の効力で若返らせてくれた元になる桃の木様を大切にする心と礼儀を忘れてはなりませぬ。皆で礼儀の修行に行こうではありませぬか」
「姫様、女中奉公など、本気でございますか?」
きさらぎが仰天した。
「女中奉公ではありませぬ。桃に心から感謝するため、土下座、いや正座を習いにまいりましょう」
「正座……」
「大和民族だけの、後の世の座り方じゃ。恭しく崇めるものに対しての座り方と聞く」
「まさしく、桃太郎様の桃のことでございますな」
かぐや姫はゆったりと微笑み、
「うむ。じゃから、わらわたちはわらしべ様のところで修行させていただくことにしよう」
そういうわけで、かぐや姫の一行は再び青い星へ下り、家来衆と共にわらしべ大奥へと出かけた。
第 四 章 わらしべ長者
「青い星の春は、昔のように花が咲き乱れ、青い空に小鳥がさえずり、かつての月の国のようですねえ」
かぐや姫一行は、わらしべ長者の大きな屋敷に行き着き、お目通り願う。
わらしべ長者は、最初に道で転んでわらしべを拾った時から数十年経ち、恰幅のよいおじさんになっていた。
「こりゃまた、なんと見目好いおなごたちばかりじゃのう。うちの大奥にも佳きおなごがそろっておるが、月の美女とはくらべものにならぬのう」
月からの美女集団にたまげた。
「うちが取り換えた桃に、そんな力があるとはのう。ありがたや、ありがたや。これも、一本のわらしべの効力に勝るとも劣らぬ神通力じゃ」
ここで、わらしべ長者のいきさつを書いておこう。
貧しい男がいた。ある日、お堂で寝ていると夢に観音様が現れ、このお堂から出て初めて手に触れたものを、絶対手放すでないというお告げがあった。
お堂から出て初めて手に触れたのは、転んでつかんでしまったわらしべ。仕方なくそれを持って歩いていると、虻が周りを飛んでうっとおしいので、その虻をわらしべにくくりつけて歩き出す。すると、幼児をおんぶして歩いている女の人がいて、幼児はわらしべの虻を欲しがって泣き叫ぶので、
「観音様のお告げで手放してはいかんということじゃったからなあ」と悩んでいたが、女人が、
「では、このミカンと取り換えて下さい」
というので、取り換えることになった。しばらく行くと、お年寄り連れの男が声をかけてきた。
「どこかでこの年寄りに水を飲ませてやりたいのですが、どこにもありません。そのミカンと、この反物を取り換えては下さらんか」
わらしべの若者は喜んで豪華な反物とミカンを取り換えた。またしばらく行くと、馬が弱って立ち往生している武士と出会った。
「この馬とその反物を取り換えていただけませんか」
困っていた武士が言い出し、わらしべは、馬を休ませ水を与えて元気にした。
馬に乗って道を進んでいくと、大きな屋敷に行き当たった。ちょうど旅に出かけようとしていた屋敷の主人は、わらしべの若者に屋敷の留守を頼み、代わりに馬を借りたいと申し出る。主人は三年以内に自分が帰ってこなかったら屋敷を譲ると言う。若者は承諾し、主人は馬に乗って旅に出発した。
しかし三年待っても五年待っても主人が旅から帰ってくることは無かった。こうしてわらしべの若者は屋敷の主人となり、裕福な暮らしを手に入れることができた。
そして今、将軍様の大奥と屋敷を取り換えることに成功したのだった。
第 五 章 ガマ公家
長者は、桃太郎の両親が取引して戦装束と取り換えた桃のために、立派な社や鳥居を建立した。大奥の者だけでなく、付近に住む者も参拝に来るようになった。若返るだけでなく病の者も、たちどころに健康になるのだ。
彼らは地面の上に筵を敷き、背筋をまっすぐして、着物の裾はちゃんと膝の内側に挟んでかかとに座り、両手は膝の上に静かに置く。そして丁寧に頭を下げるお礼の仕方をしていた。かぐや姫たちもそれに倣って正座して頭を下げ、合掌した。不思議なことに参拝の人々が増えれば増えるほど月の月命宮でも生命力あふれ美しさを取り戻したと、月から便りが届く。
「姫さま、これはなんとしても、桃の木を月命宮に持って帰らなければ。桃の木さえあれば、月命宮は二度とあのようなみじめなことになりますまい」
きさらぎが瞳を輝かせてかぐや姫に言い、自分で頷いた。
社の奥に置かれた桃を拝みに来た者の中に派手な装束のガマガエルのような体形の公家がいた。
趣味のよくない色合わせのお直衣を着て、顔もガマそっくりだ。
共の小者をひとり連れており、イライラした口調で命令していた。
「早く探さぬか! この屋敷のどこかにかぐや姫がおわされるはずじゃ!」
きさらぎがその老人に気づいた。
「姫さま、ちょっとこちらへ」
「どうしたの? きさらぎ」
「遠い遠い昔、まだ姫様が竹取のご両親様とお暮しであられる時に、たくさんの求婚者が現れましたでしょう。あの時、一番、気味悪かったガマそっくりな公家が来ているのですよ」
「ええ? 好色ガマ公家が? 苦手だわ。公家だというのにいつも垢のたまった着物を着て、お歯黒もはげかけているのに無頓着で。毎日しつこくおしかけてきたわ。お断りしているのに、一日に何度も」
かぐや姫の顔が泣きそうに崩れた。
「桃の噂とかぐや姫の噂を聞いてやってきたにちがいありませんわ。警護の者を増やしていただくよう、わらしべさまにお願いしましょう」
きさらぎがわらしべの住む棟へ行きかけた時、転がるように公家が走ってきて、行く手を阻んだ。
「きゃっ、好色ガマ公家!」
「これはこれは、かぐや姫さま、お久しゅうおじゃりまするなあ。相変わらず美しゅうて。へっへっへ」
きさらぎが間に入った。
「お公家さま。ここは社の中です。姫さまのおじゃまをすることはなりませぬぞ」
「ちゃんと、桃の社にお参りおじゃるゆえ、ほれ」
好色ガマ公家は、参道を歩いていって、本殿の前でどっかとあぐらをかき、ガマガエルのように地面に両手をつき、
「かぐや姫さまにお会わせ下さってありがとうおじゃりまする~~~」
虫唾がはしる(ぞっとする)座り方とお辞儀だ。
かぐや姫は歯を食いしばって公家の姿に耐えていたが、ついに叫んだ。
「好色ガマ公家さん、こっちへいらっしゃい!」
かぐや姫は、公家の襟首を持って社の裏へ引きずっていった。
きさらぎと、公家の小者が追いかけた。姫のどこにこんな力があったのだろう。
「姫さま、いったい、何をなさいます?」
「この方の座り方があんまりひどいから、正座を教えてさしあげるのよ」
どこにこんな馬鹿力があったのか、かぐや姫は怪力を発揮して公家を社の裏側に放り投げた。
「姫さま、な、なんでおじゃりまするか」
「あんたねえ、あんな座り方で『桃さま』にお祈りするなんて、無礼千万なのよ! わらわが美しい正座を教えてあげるから、よおく覚えなさいっ!」
「正座……?」
「そうよっ。まず、まっすぐ立ちなさい!」
「はいっ!」
「そう、そして背すじをしゃんと伸ばして!」
「はい、はいっ!」
好色ガマ公家は恐れおののきながら、言われる通りにした。
「それからかかとの上に座るのよ。袴はきちんと膝の内側に入れること」
「はいいいっ!」
「両手は膝の上に!」
「はいっ!」
「違う! そんなべったりした座り方では『桃さま』に失礼だわ! もう一度最初から!」
「はいいいいい!」
かぐや姫のスパルタ稽古を、きさらぎと小者は呆然と見ていた。
ようやくかぐや姫から「まあまあよし」の返事をもらった時には、真夜中になっていて、好色ガマ公家はばったりと地面に倒れてしまった。
「姫さま、やりすぎでは?」
「このくらいしないと、懲りないのよ。ちょっとそこの小者! ご主人さまを引きずって帰りなさい!」
小者はあたふたと大きな公家の身体を持ち上げようとしたが、自分が下敷きになってしまった。
第 六 章 悩みの打ち明けっこ
月命宮の女官たちは、朝夕、『桃さま』をきちんと正座して合掌し、お祈りを捧げた。
毎日、きさらぎの指導で、正座してお辞儀するのが上達していった。座り方はもちろん、合掌する時の指の合わせ方、心からのお礼と感謝が感じられるようになった。
そして、その中にいつしか、わらしべ長者も混じるようになった。
これには女官たちも驚かずにおれなかった。
わらしべ長者が、ある日、かぐや姫を呼んだ。
屋敷の奥にかぐや姫がうかがうと、長者はうかない顔をしている。
「どうかなさいましたか?」
かぐや姫が声をかけると、長者は深いため息をつき、
「わしは……、こんな豪勢な暮らしができる人間ではないのじゃ。どこで生まれたとも知れない貧しい、親も分からぬ人間じゃ。なのに、こんな屋敷に住み、使用人を余るほど持ち、明日の飯にも困ることがない。こんな生活をさせてもらって天罰が下らないだろうかと思うてのう」
「天罰だなんて。元々は観音様のお告げで始まったことなのでございましょう」
「しかしなあ、どうも居心地が悪いのじゃ。わしも汗水垂らして働かないと、使用人に申し訳なくてのう」
「お人が好いのは、お若い頃と変わっておられないのですね。そういうお人だからこそ、観音様はお告げを下さったのだと思いますよ」
「じゃろうか……」
長者の顔は曇るばかりである。
「長者どの、では、今度はわらわの悩みも聞いていただけますか」
「んん? 姫のように美しくて永遠の命をお持ちの方に、悩みがありますのか?」
「それはございます」
姫はやや苦笑して言う。
「ほら、わらわは竹から生まれて大切に老いた両親に育ててもらっておきながら、勝手に月に帰ってしまいましたでしょう」
「それは、姫様は月の世界の方じゃから仕方のないことだったのでは」
「でも、どうしても老いた両親に、心からお礼を申したかったのです。月命宮からの兵どもが、否応なく迎えの車に乗せてしまいましたので、お礼などする間もなく……。でも、本当はいつまでもあの両親の側で暮らしていたかった」
「そうでしたか」
「まあ、仕方のないことと言えば、長者どのも観音様のお教えに従ったのですから仕方ないでしょう。なんだかわらわたちの悩みは似ていますね、長者どの。過ぎたことはどうにもならないのですもの」
ふたりは暮れてきた夜風に吹かれながら虚ろに庭のススキに目をやった。
第 七 章 きさらぎのアイデア
廊下の端から、きさらぎが顔を出して跪いた。
「姫さま、長者さま。大変、はしたなくも今のお話、聞いてしまいまして」
「まあ、きさらぎ」
「侍女どの」
ふたりとも、きさらぎに驚いた。
「今のお立場のおふたり様には、お役目がございますね」
「役目とな」
「はい。長者さまには、大奥含むお屋敷を守っていくお役目が。かぐや姫さまには、月命宮を二度と荒廃させてはならぬというお役目が」
ふたりとも頷いた。
「それさえちゃんとされれば、おふたり様は、人生をやり直すことが出来るではありませぬか」
「やり直す?」
「ほら、打出の小槌で」
きさらぎが余裕で微笑んだ。
「あの打出の小槌で?」
「そうです。わたくし、打出の小槌を権大納言様の元からお借りする時に、効力をいろいろお聞きしました。打出の小槌は普通に振ると、人を成長させますが」
「確かに、桃太郎どのは貴公子におなりになった」
「逆の方向に振ると、人を若返らせる効力があるのです」
「まあ」
「それは」
さらに、きさらぎは続けた。
「ですから、かぐや姫さまは、かつて竹林で翁に発見された時の赤子に。長者どのはお好きな若者時代に戻れるのでございますよ」
「おお!」
第 八 章 旅立ち
「では、さっそくこの屋敷を治める者を捜そう! わしには子がおらぬでな」
「その前に」
きさらぎの眼が鋭く光った。
「桃の苗をわたくしどもにもお分けいただけないでしょうか」
「容易いことじゃ。喜んでお分けしましょうぞ」
「ありがとうございます、長者どの」
かぐや姫が、正座に座りなおして頭を下げた。射干玉の黒髪が打掛にはらりとかかる様の美しきこと、例えようがない。
「ありがとうございます。このきさらぎからも心よりお礼申し上げます」
「よいよい」
長者は、はっと我に返り、
「して、その打出の小槌とやらは」
きさらぎが、女官のひとりを呼んだ。すると、平安朝の一台の車が乗りつけられ、童と夫婦が降りてきた。童は降りてきたというより、飛び出してきたという感じだが。
「かぐじゃ姫しゃま~~~~っ!」
「そ、そなたは、打出の小槌を振る前の桃太郎どの!」
「うん。坊、もう少し母上のお膝に座っていたくて小っちゃくなったの」
「打出の小槌を逆さに振って?」
「うん!」
かぐや姫は可笑しいやら、呆れるやら。
というわけで、桃の木の苗は月命宮に分けられることになり、月が二度と生気の無くなる心配がなくなった。
かぐや姫は打出の小槌の力で、竹林で発見される時まで若返ることになった。長者どのの屋敷で正座の修行をしたので、たとえ赤子であろうと、竹の中でばっちり美しい正座ができる。ちょうどよい太さの竹筒の中で産着の着物を膝にはさんで座ることができるということも試してみた。
月命宮の者たち、女官や家来が月へ帰る日がやってきた。
「では、きさらぎ。すべて頼んだぞ。月命宮が二度とあのように荒廃せぬように」
「はい。お任せ下さいませ」
きさらぎの懐には、桃の苗がしっかり抱かれている。
「かぐや姫さまも竹取のご両親さまと永く永くお暮しすることができますな。天子様のお召しも、好色ガマ公家さまの求婚もお断りになって」
「まあ」
ふたりは笑いあった。
身軽になって旅に出ることにしたわらしべ長者は、遠くなる屋敷を見ながら、草鞋の紐を結び直すのだった。草鞋から藁が一本出ていたので、引き抜いた。
虻が顔の周りを飛んでいる。左手で捕まえて、わらしべに結び付けようとしたが、放してやった。
「自由でいるがよい。自由が一番じゃ」








