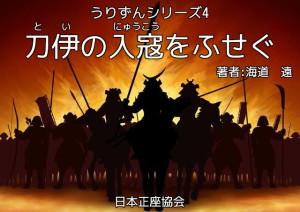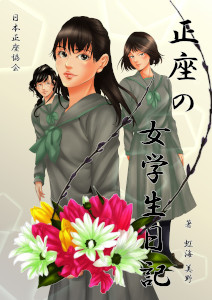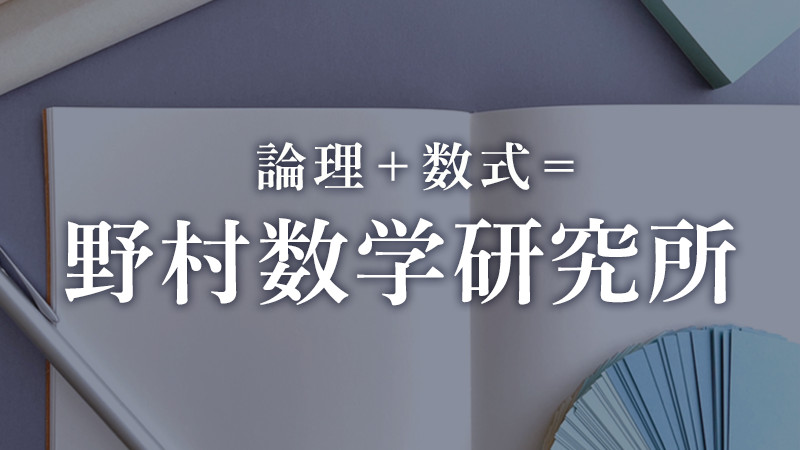[347]お江戸正座23
タイトル:お江戸正座23
掲載日:2025/04/07
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:23
著者:虹海 美野
あらすじ:
おきぬは札差の奉公先から、お内儀さま、ご新造さんのお世話で一膳めし屋を営む佐久造の元へ嫁いだ。
互いに想い合って一緒になれたが、佐久造が本当におきぬと一緒になりたいと思っていたかどうかもわからない。
そんな折、郷の両親が江戸へ来ると言う。佐久造との住まいに両親を泊めたいおきぬだが、佐久造に迷惑をかけるのでは、と言い出せない。
正座をし、向かい合って朝餉を摂る時、佐久造がどうした、とおきぬに尋ねるが……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
おきぬが佐久造と一緒になり、季節は秋に変わった。
おきぬは郷から江戸の札差の家に奉公し、そこでご新造さん付きになり、そうしてそこのお内儀さまとご新造さんにお世話していただき、心密かに思っていた板前の佐久造と一緒になった。
佐久造はもともとご新造さんのご実家の大きな料亭の板前であった。
おきぬが佐久造と初めて顔を合わせたのも、そもそもご新造さんが料亭から札差に嫁いで来た折だ。祝い膳を任された佐久造に何か手伝うことはないかとおきぬが声をかけ、佐久造はそこで、まだ奉公して間もないおきぬに頭を下げ、ご新造さんのことをよろしくと頼んだ。
あの時、強面(こわもて)で、言葉なんかも荒いと思われた佐久造の本当の一面を見た気がした。初対面だったけれど、その人の心の奥を知った気がして、それが特別なことだと思えたのは、後にも先にも佐久造ただひとりであった。
だから、お内儀さまとご新造さんとが、おきぬの嫁ぎ先を考えていると言った時、おきぬは佐久造がよいと答えた。ご新造さんはその答えが余程意外だったようで、何度もおきぬに確認した。初めに佐久造の名を告げた時には、本当に勇気が必要で、消え入るかのような声でその名を発したが、ご新造さんが店に出入りしている手代だの誰だのと、佐久造と似た名をいつくも挙げるものだから、はっきりとその名を伝え、なんだかそのご新造さんとのやり取りで、ああ、本当に私は佐久造さんがいいんだ、と確信したのも事実であった。
佐久造の方はどうかわからぬが、ご新造さんから佐久造がおきぬと一緒になりたい旨を聞き、腰が抜けるほどに驚いた。まあ、自分から佐久造がよいと言っておいてなんだが、なにせ、言葉を交わしたのは、あのご新造さんの祝言の日だけで、その後はご新造さんとご実家へ行った際に、たまに顔を合わせるかどうか、それだけであった。江戸の町娘のように、一緒に出かけることも、互いの意志を確認し合うこともなかったのだから。そうして、嬉しく、安堵した。ああ、望むべきところへ行ける、と思った。
お内儀さまの話では、おきぬを商家のご新造さんにと考えてくださっていたらしいが、おきぬには、そうした望みはなかった。だが、そうしていろいろと考えてくださったことは、ありがたい話である。手習いを終えたばかりの幼いおきぬを、お内儀さまはずいぶんと気遣ってくださった。初めてお内儀さまと顔を合わせたのは、奉公を始める日の朝餉の席であった。奉公人が朝餉を摂る板の間に下りて来て、膝を揃え、おきぬをかわいいと言ってくださったお内儀さまに、おきぬは居住まいを正した。背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は閉めるか軽く開く程度、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬように正座した。そうしてご挨拶をした日からの歳月はあっと言う間であった。
ご新造さんは子を三人授かり、そのかわいらしい子たちの成長にも立ち会えた。背に負った子の温かい重さ、そうしておきぬの両の手をつかむ小さく、湿った手の感触。なんてかわいらしいのでしょう、とおきぬは幾度口にしたかわからぬ。おきぬにも小さなきょうだいはいたので、子の相手は多少慣れてはいたが、それでも幼い子の言葉やしぐさはかわいらしく、新鮮に感じるものである。
若旦那さまとご新造さんの子は皆、やはり賢いのか、手習いに行く前より、絵や文字に興味を示した。僭越ながら、おきぬも手習いには通っていたので、ちょっとした文字の練習なんかは、ご新造さんが忙しい時にお手伝いした。
背筋を伸ばして、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は閉めるか軽く開く程度、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬように正座をするとよいですよと教えれば、その通りに座る子たちであった。
まあ、元気がよくて、うっかり障子を破いたり、置物を壊したり、ということもあったが、ああ、やらかした、といった様子がまたかわいらしい。けがをしていなかったかを確認し、その後おきぬは自分がついていたのにと旦那さまや若旦那さまに詫びたが、一度として叱られたことはなかった。家のものを壊して、その責任を押し付けられる、と考えるところを、まず子のことを気にかける、その優しさで子と一緒にいてくれる、そうして、子にけががないよう、いつも見てくれて感謝している、と。これも、本当にありがたい対応であった。本来なら、障子や置物を破損したなら、何をやってるんだいと怒鳴られるだろうし、置物に於いては、あんたがどれだけ働いたって、買えるもんじゃないんだ、と言われるところだろう。もちろん、詫びる時、そうした言葉や叱責は覚悟していた。ひたすらに、すみません、と謝るほかあるまい、と思ったものだ。
だが、そうした叱責を受けることなく、佐久造との縁談が決まった折には、その支度をお内儀さま、ご新造さんがしてくださった。
おきぬは旦那さまの部屋で、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬようにし、脇は閉めるか軽く開く程度、手を太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃えて正座し、謝辞を伝えた。
寂しくなるなあ、と旦那さまが呟いた。
頭を下げ、畳の目を見つめていたが、その視界が涙でぼやける。
江戸へ来て、白いごはんを食べ、自分用の布団に着物が与えられ、ご新造さん付きになって、初めて見るきれいな菓子や豪華な膳をいただいた。郷の両親やきょうだいに話したいことがどんどんと増えていった。同じものを食べさせてやりたいと思っていると、それを察してくださっていたのか、ご新造さんが藪入りの時に、菓子を持たせてくださった。
ご新造さんが子を授かり、臥せっている時も、おきぬ、おきぬと頼りにしてくださった。そうして、生まれた子もまた、おきぬの名を呼び、走り寄る。それはなんと幸福な時であったろうか。
今でも夢に見る。
ふと目を覚ませば、そこにある天井は札差の屋敷の高いものではなく、小さな貸店舗二階の奥の一室であった。
板前の妻になり、おきぬは目が覚めると前掛けをし、袖をたすき掛けにする。
佐久造はおきぬと一緒になる際、三度の飯も、店で出す膳も自分がやる、と言った。
朝、夫との飯を炊かぬという考えがなかったおきぬは大層驚いたが、佐久造は譲らぬ。だから、朝の水汲み、洗濯、店の掃除、皿洗いに帳面をつける仕事をすることにした。
こんなに楽をしていいのだろうか……。
店に来る客は、「こんなにきれいな子が来てくれて、佐久造は果報者だ」とか、「本当にくるくるとよく働く嫁だ」と言うが、実のところは、それほど何かをしているわけではない。「いえ、私は本当に」と言えば、「こんなに控えめなよい人と佐久造は一緒になれて……」と客は返す。佐久造は、そういう話が出ても、黙々と板場で働いている。そんなことはない、飯は全部俺が作っている、店で出すものも俺が用意してるんだ、と言ってくれた方が気楽なのだが、佐久造は決してそれを言わないのだ。
佐久造は、おきぬと添いたいと言ってくれたらしいが、それは本当だったのだろうか……。
もっといい人がいたのではあるまいか……。
さまざまなことを考えるが、もう、一緒になってしまった。
そうして、おきぬは佐久造と一緒にいたい。
だから、そのことについては、訊けぬままである。
2
郷から便りが来たのは、昨日のことである。
店が賑わっており、お客のお勘定をし、見送ったところで自分宛の文を受け取った。
取りあえず懐に文を仕舞い、すぐに店の仕事に戻る。
店では客が、秋のお菜に舌つづみを打っている。
札差の家でも、初物に敏感な江戸っ子気質で、新しいものが膳に並んだものだが、板前の佐久造は、働き盛りの江戸っ子を相手に飯を出すから、とにかく毎日のお菜の材料選びにも余念がない。その賄いを食べさせてもらっているので、今どういうものが旬であるか、おきぬも随分詳しくなった。
お客がそろそろ栗の入った佐久造の茶飯が食える頃だと言っているのをおきぬは聞いた。
常連さんなのは知っていたが、佐久造が暖簾分けをしてもらってすぐの頃から通い続けているのが覗えた。
そんな折の便りであった。
おきぬの下にいるきょうだいたちも大きくなったので、おきぬのお父ちゃん、お母ちゃん二人でおきぬの元へ会い来るついでに、江戸見物をしていくとい言う。
嬉しさとともに、どうしよう、という思いが過った。
ここは佐久造の店と家である。
郷はそう遠くないが、会いに来てくれるお父ちゃん、お母ちゃんをここに泊めたい。
ささやかではあるが、親孝行をしたい。
だが、そうすると、佐久造に負担がかかる。
布団を借りるのだってただではない。
佐久造の実家は江戸にあって、半刻(一時間ほど)も歩けば行き来できる場所にある。
何度か顔を見せてくれたし、こちらから行ったこともあるが、互いにそれほど長居はしていない。
それなのに、おきぬの親が宿泊というのはよいものなのか……。
早く佐久造に相談しなければ、と思うが、どうしたものかと答えが出ぬ。
そのまま一晩が経ってしまった。
いつも通りやっているつもりだったが、水を汲み、外の掃除をしている間に佐久造が起きて来たことにも気付かなった。
いつの間にか佐久造は飯を炊き、味噌汁を作り、秋刀魚を焼いていた。
「飯にする」と短く佐久造に呼ばれ、「はい。ここをきれいにしたら参ります」とおきぬは店の前を掃き清めながら返事をした。
「いいから、早くしろ。後で俺がやる」と、また佐久造が言う。
ああ、怒らせてしまったか……。
布団も佐久造を起こさぬようにと、佐久造が起きた後に畳んでいたが、それもうっかり忘れていたから、恐らく佐久造におきぬの布団も畳ませてしまったに違いない……。
「はい」と再び返事をし、店に入り、手を洗い、前掛けで拭きながら、座敷で二人、膳を前にする。
一膳めし屋は、床几に小上がりが多いが、佐久造は全ての客が畳の座敷で膳を前にできるようにしている。
短い時間でも、履き物を脱ぎ、畳でくつろぎながら食べるのがよかろうと考えている、と、一緒になってすぐ、佐久造がおきぬに説明した。
その時、そうですねえ、とおきぬは皿を拭きながら頷き、それが済むと座敷を清めた。
お前に手間を取らせるつもりはなかったが、と佐久造は言葉を濁した。
おきぬは、いいえ、清めるにも畳に上がります。これも心地よいものです、と答えた。
郷の家は広かったが、そもそも畳がない。
布団もきょうだいと一緒に使った。
江戸へご奉公に上がった時も、奉公人は板の間で食事をした。
それらに不満があるわけはないが、やはり、畳があるというのは、おきぬにとって特別であった。
当然、多くの客が入るので畳は擦れていくが、佐久造は座敷の畳を古いままにせず、折を見て替えていると言っていた。畳は店の勘定に関係ないと割り切ることもできるだろうが、そういうことに佐久造は気を配る性質である。
佐久造が待つ座敷で、その向かいにおきぬが座る。
二人して向かい合うのは、三度の食事の時だ。
佐久造は背が高く、細身であるが大柄な方で、ここへ来る客のように足を投げ出して食べるのかと思ったが、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は閉めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬように正座し、箸遣いも大層きれいであった。
一緒になってすぐの頃、つい、見惚れると、佐久造は決まり悪そうに、「昔、暖簾分け前に俺の所作を改めた方がよかろうということになって、行儀見習いに短い間だが、通った」と目を合わさずに言った。
「行儀見習い、ですか……」
江戸の裕福な家の娘が通う場所だと思っていたおきぬがそう訊くと、「ああ、若い娘と一緒に稽古は嫌だと思ったところ、常連の質屋の大旦那が間に入って、昼時に弁当を届ける名目で通うようにしてくれた」と言う。
「まあ」
なんとまあ、融通の利く粋なお人がいたものだ、とおきぬは思った。
「お前、諏訪理田という戯作者を知っているか?」
急に戯作者の話になり、内心首を傾げつつ、「はい、おつたさまの持っておられる本をお借りした時に、その戯作者の作がありました」と答えた。
「そうか。俺が通った行儀見習いの師匠の亭主がその諏訪理田っていうので、料亭で仕事をしていると、有名な戯作者の先生っていうのは、ずいぶんとこじゃれた装いなんだが、その諏訪理田ってえ戯作者は、着物をゆるゆると着て、猫にやる煮干しなんかに気を取られている呑気な男だった。その分女房のお師匠さんがしっかりしてるんで、それでちょうどいいのかも知れねえと思った」
江戸という町は、やはり、ちょっと行儀見習いに通うにしても、そのような文化人と縁があるものなのか。
ただ、まあ、おきぬとしては、そのお師匠さんと戯作者の仲よりも、佐久造の様子を知りたい。
「あの、その行儀見習いは、いかがでしたか?」
ちょっと身を乗り出して訊くと、佐久造はやや目を泳がせ、「まあ、てえしたことはなかったよ」と言い、「さ、食って、俺は仕事だ」と茶碗を手に取った。
そうして白湯を飲むと、「お前は好きにしてな。朝の水汲みに掃除までして疲れたろう」と言い、「ごちそうさん」と手を合わせて板場へ入って行ったのだ。
佐久造を想って、一緒になったものの、話したのも一度きりでの結婚だったから、何を話したものか、おきぬはずいぶんと困った。
それは、今も似たようなものなのだ。
佐久造も同じだったろうし、もともと話し上手というわけではなさそうだった。
札差にご奉公していた頃、いろいろな商人がやって来たが、皆話し上手で、こちらが何か言わなくとも、大層滑らかに話題を繰り出した。だが、佐久造には、今日の天気に始まり、町で話題になっていることなんかを話す習慣はないようだった。だから、話すことというのが、あまり多くはなくて、佐久造は店のこととか、少し自分のことなんかをおきぬに話してくれるのだった。
この日の朝餉の時も、それほど話しはしなかった。
ただ、朝おきぬが下足箱の横の棚に生けた花がきれいだ、とだけ言った。
そこからいつもだったらおきぬが、どこでその花を摘んできたとか、札差のお内儀さまが大層花を活けるのがうまかった、といった話しを少しするのだけれど、昨日から郷からの文の返事ことを考えていて、「ええ」と答えるに留まった。
「どうした」と、佐久造が訊いた。
「え」とおきぬは顔を上げた。
佐久造は淡々と自分のことを話し、おきぬもその話関連のことを挙げて、会話をしていた。
だが、このように佐久造がおきぬに尋ねるのは、おきぬが覚えている限り初めてである。
どうした、と訊かれたのはおきぬの方だが、どうしたのかしら、とおきぬは考えながら、佐久造とともに食事を終え、膳を前に手を合わせた。
3
佐久造は、江戸っ子の好物の深川めしをはじめとした炊き込みのごはんをよく作る。出汁が活きており、あっさりとしているが、味と風味がよいと大層評判である。佐久造はそろそろ栗を仕入れたいと言っている。
以前この近くで仕事をしていた大工たちが、少し離れた場所での仕事を開始しても、佐久造の店に来ている、とお勘定の時に聞いた。
「ありがとうございます。これからもよろしくお願いします」と、おきぬは頭を下げる。
「とんでもねえ。礼を言うのはこっちだ。ここの飯を昼、夜と食うようになってから、なんだかわからねえが、身体の調子がいいんだ。腹持ちもいいし、かといってもたれることもねえ。これまでみてえに昼飯の後に甘いものをつまみたいと思わなくなった。店の中もきれいで、飯の間に寝てるわけじゃねえけど、しっかり休めるんだ。しかも財布にも優しいときた。おまけにお前さんみたいな丁寧なおかみさんまで居るとなれば、もう他に行く理由がねえよ」
からりとした笑顔で大工の客は言い、「また来るよ」と店を出る。
このように言ってくれる客は結構いる。
そうして、その客は次に来る時、新たな仲間を誘う。
そうしてその仲間がまた仲間を誘う。
だから、店はどんどん繁盛し、佐久造は忙しい。
佐久造は、元は大きな料亭の板前をしていたから、注文がたくさん入っても、それで慌てることもないし、極端に客を待たせもしない。実に手際がよい。そうして、たくさんの注文があっても、飯や汁物が冷めていたり、盛り付けが雑になったりということもない。客が入り始めから、混雑時まで同じ状態の膳が出る。
おきぬにできるのは、その佐久造のひたむきな仕事の邪魔をせぬよう、膳を運ぶことである。
佐久造の仕事の邪魔にならぬよう……、今切に思うのはこのひとつだ。
お父ちゃん、お母ちゃんに今回会うのは諦めよう。
後で、文を出そう……。
昼の客のほとんどが引けた頃、「ごめんください」と引き戸から涼やかな声がした。
男のお客が多い中、珍しい女性の声であった。
おきぬは膳を下げ、すぐに「いらっしゃい」とそちらへ向かった。
「まだやってますか」
「はい、もちろん」とおきぬは返事をした。
秋の装いの茶の細い縞の単衣に、下駄と髪に挿した櫛は茶に近い赤色で、下駄を預かり、その顔を見れば、たいそう美しい人であった。
人の妻であろうことはわかったが、つい、佐久造のいい人では、と心配になる。
だが、「ほら、あなた、こっちですよ。猫? わかりますけど、食事に来たのだから、今は辛抱なさって。ほら、早く」と後方で手招きしている。
「ああ、すまん」
女性のお客はこれ以上ないほど顔をほころばせ、慈悲深い笑顔を見せた。
そうして、後からやって来たのは、目が覚めるかのような二枚目、……というわけではなかった。
店で見慣れたがっしりとした職人とは異なり、ほっそりとした男の人だった。
髪をきちんと当たって髷を結い、着物も茶に黒の縞の入った装いで、こげ茶の帯と下駄の鼻緒は色を合わせている様子である。
そちらにも下駄をお預かりする旨を伝えると、「ああ、これは、よろしくお願いします」と妙に丁寧である。若干不思議な気もするが、不快さは一切ない。
夫と思われるこの男性は、店内に入ると、「おお、ここは風通しよく、大層心地よいですね」と目を細める。
妻と思われる女性に促され、座敷の奥の方に座る。
所作の美しい人は、奉公していた札差のご新造さん、お内儀さまと、見ていたが、この女性の所作はそれにも増して、きっちりとしているが柔らかさと余裕があり、優美であった。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は閉めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬようにし、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃えて正座する。
「これは、師匠」と板場から顔を覗かせた佐久造が言う。
「お元気そうで何よりです。うちの人が、以前いただいた佐久造さんのお弁当の味が忘れられず、今日は町の散策も兼ねてここまで歩いて来ました」
「遠いところ、ありがとうございます」と佐久造が言う。
「佐久造さん、こちらがおきぬさん?」
師匠と呼ばれた女性が首を傾げる。
「ああ、ごあいさつもせず、すみません。きぬです」
お客と佐久造のやり取りを見ていたおきぬは、はっとし、名を告げる。
「おきぬ、こちら以前世話になったお師匠と、そのご亭主で戯作者の諏訪理田先生だ」
ああ、行儀作法を習ったと佐久造が言っていたお師匠……、とおきぬは思い出し、以前おつたに読ませてもらった戯作を書いた諏訪理田先生が目の前にいる人物なのだ、と理解した。
佐久造のお師匠は、「そう。おつたさんから伝え聞いてはいたけれど……。お会いできて嬉しいわ」と微笑む。
おきぬはその場に背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬようにし、脇は閉めるか軽く開く程度で、手を付き、「きぬと申します」と改めてあいさつした。
「ああ、ご丁寧に。こちらこそ」と、佐久造のお師匠も手を付いてあいさつする。
佐久造はさっと暖簾を店の中に入れ、「どうぞ、ゆっくりしてらしてください」と声をかける。
「お気遣いを」と、諏訪理田先生が礼を伝える。
皆が頼む飯に汁物、お菜が一品の膳を二人は頼んだ。
おきぬは板場で膳を受け取り、順にお出しする。
「ああ、おいしそうだ」と諏訪理田先生が子どものように声を上げる。
二人が食事をしている間、おきぬは裏戸から出て、井戸の横で皿を洗った。
きっと、三人で話したいこともあるだろう。
洗った皿を重ね、それを拭こうと店の中に戻ると、「おい」と佐久造が呼ぶ。
「はい」とおきぬは顔を上げた。
「二人が、少し話したいと……」
「あ、はい」と、おきぬは皿を置き、手を前掛けで拭き、袖をまとめていた襷を外す。
気を利かせたつもりだったが、佐久造が世話になったお師匠が夫を伴って来てくれたのなら、妻として、隣に控えるべきだったか……。
おきぬは佐久造の隣で正座する。
座る前には裾にも気を付ける。
背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は閉めるか軽く開く程度、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬようにし、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃える。
「お仕事中にすみません」と佐久造のお師匠が詫びる。
「とんでもございません。せっかく来ていただいたのに、考えが及びませんで……」
そんなふうに話していると、佐久造が「茶を淹れて来る」と立ち上がる。
「私が」とおきぬが腰を上げかけると、「お前はそこにいろ」と言い、全て空になった皿の膳を手早く片付ける。
「相変わらずだけれど、ずいぶん表情が柔らかくなって。おきぬさんと一緒になって、よほど幸せなのでしょうね」
佐久造のお師匠が目を細める。
「え」と、おきぬは間の抜けた顔で佐久造のお師匠を凝視した。
「近い人ほど気づかぬものですよ」と諏訪理田先生が言った。
「いえね、私もこの人と一緒になれたのは、私が弟子入りしていた師匠のお嬢さんのおかげだったのです。師匠のお宅でお世話になっていた時には、正直馬が合わぬと言いますか、まあ、とにかく、深い話をするような仲ではなかったのですが、その師匠のお嬢さんが妻と仲が良く、私が師匠宅を出た後に、気を利かせてくださったのです。ああ、それは私を思ってのことではなく、妻を慮ってのことですがね」
諏訪理田先生が懐かしそうに語る。
「あなた、そんな昔のことを……」と、佐久造のお師匠が遮る。
「はは、すみません」と諏訪理田先生は素直に詫びる。黙ってろ、などとは、決して言わぬお人柄なのだろう。
このお二人、大層仲が良い。
そうして、息が合っている。
うまくいっている、というのは、こういうことか。
お内儀さまも、ご新造さんも、旦那さまとの仲がよい。
だが、二人で暮らす夫婦というのがどういうものか、おきぬにはいまいちわからぬ。
この佐久造のお師匠と諏訪理田先生は、それぞれに仕事があるようで、そうしてみると、また、佐久造とおきぬとは違う。
佐久造の営む店と住まいに、おきぬがやって来たのだ。
「秋の花を活けたのですか。風流ですね。これから、紅葉も見ごろですし、ススキも趣がある」
諏訪理田先生が飾ってある花瓶の花を見て穏やかに言った。
「あ、はい」とおきぬは我に返る。
「江戸は春もいいですけど、秋もいいものですね。夏は暑さがこたえることもありますけど」
佐久造のお師匠が諏訪理田先生の話を継ぐ。
「はい。こちらに出て来て、お花見や紅葉狩りなどにも連れて行っていただきました」
おきぬが佐久造のお師匠の話に応じる。
「ああ、そういえば、おきぬさんのお郷はここから遠いのですか? ご両親が江戸見物にいらっしゃるのなら、今頃からがちょうどいい時期ですね」
なんのことはない、話の流れであった。
だが、おきぬの心は、ぴん、と張り詰めた。
「え」と、おきぬは目を見張る。
つい、黙ってしまった。
「ああ、なんだか立ち入った話をしてしまって。申し訳なかったわ」
佐久造のお師匠が慌てている。
おきぬは慌てて首を横に振る。
「そんなこと、全くございません……」
……どうしようか。
いっそのこと、ここで相談してしまおうか。
実はお父ちゃんとお母ちゃんが江戸へ出て来ると文が来た。自分としてはもてなしたいが、忙しい佐久造の邪魔をしてはいけぬから、ほかで宿を取って、今回は江戸の見物だけして帰ってもらおうかと思っている、と。
「あの……」
おきぬが言いかけた時、佐久造が茶を淹れて戻って来た。
そうして、各々の前に茶を置いた。
「その話なんですけどね」と、佐久造が言う。
「前から気になってまして、こういう場合、俺が文を出すのがいいのか、やっぱりこいつに書かせるのがいいのか、どうなんでしょう」
……え?
今、なんと?
気づけば、おきぬは涙を落としていた。
「おい、どうした? 腹が減ったか? 茶が熱かったか? おきぬ、どうした?」
佐久造が、佐久造のお師匠と諏訪理田先生の前であるにも関わらず、大きな両の手でおきぬの顔を包み、慌てた様子で見ている。
おきぬは、首を横に振った。
なんだ、この人は、自分のことをこんなにも見てくれているではないか……。
「お父ちゃんとお母ちゃんに来てもらっても、よろしいのですか? お店が忙しいのに、良いのですか?」
「……お前、俺はそんなちいせえ器じゃねえって。信じてくんな」
「……はい。そうします」とおきぬは頷いた。
「あらまあ、行儀見習いの初日は正座の稽古だけで大変だったのに、おきぬさんのことは本当に慎重で……」
佐久造のお師匠の声と、「こら、そんなことを言ったら、二人の邪魔になるではないか。それに佐久造さんは確かに行儀見習いの初日に『しゃらくせい!』と投げ出しそうになったが、料理に関しても確かなお人だ」と言う諏訪理田先生の声が聞こえたが、申し訳ないながら、応じる余裕がなかった。
4
それから半月後、おきぬのお父ちゃんとお母ちゃんがやって来た。
途中、宿を取るほどの距離ではないが、二人は穫れたての栗や野菜を籠に背負ってやって来た。
佐久造は二人のために、様々なお菜を用意してもてなしてくれた。
そうして、夜は親子水入らずで話せるよう、二階にお父ちゃん、お母ちゃん、おきぬで、佐久造は下で寝ると申し出てくれたのだった。
話すことは本当にたくさんあった。
お父ちゃん、お母ちゃんは、できれば奉公先の旦那さまたちにもごあいさつしたいけれど、さすがにそれは無理だねえ、と言った。
おきぬが江戸でよい人に恵まれたことを、感謝していた。
「お父ちゃん、お母ちゃんが本当に旦那さまたちに感謝しているのは、郷に帰った後に毎回伝えていたし、ここへ嫁ぐ時にも伝えたから、もう十分だよ。安心して」とおきぬが言うと、二人は「そうか」と頷いた。
そうして、やはり長旅で疲れたのか、すぐに寝入った。
翌日、店の準備をするよりずっと前に、下からよい匂いがした。
ほくほくとした、甘味を含んだ温かな匂いだ。
降りて行くと、佐久造が「まだ寝ていていい。今日は江戸見物へ行くのに、あちこち歩くだろう」と言う。佐久造は、お父ちゃん、お母ちゃんが来ている間、店のことを一切しなくていいと言ってくれた。それは困る、とおきぬは言ったが、佐久造はもともと俺一人でできていたことだから、困ることはない。……まあ、いてくれた方が助かるし、楽しいが、と付け加えたのだった。
そうして、「もうじき炊けるから、これを、ちょっと手間をかけるが、出かけついでに、おつたお嬢さんの嫁ぎ先の店へ持って行ってくれるか? 昨日もらった栗を使わせてもらった。栗ご飯だ」と手を動かしながら言った。
両親の気持ちを慮って、ただ会いに行くのでは気が引けるだろうから、土産の栗で炊いた飯を土産にと顔を出せるようにしてくれた。
なんと、自分はいい人に出会え、一緒になれたのだろう。
それでも、この人のよさを自分はまだまだわかってはいなかった。
黙って佐久造を見つめていると、「もう少ししたら、朝餉ができるから、お父さん、お母さんを起こしてくんね。持って来てくださった栗を使った炊き立ての栗ごはんで飯にしよう」と言う。
「はい」とおきぬは頷いた。
佐久造のお師匠と諏訪理田先生の言っていた、行儀見習いの話が本当はずっと気になっていたが、また今度訊いてみることにしようと思った。

![[275]お江戸正座2](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)