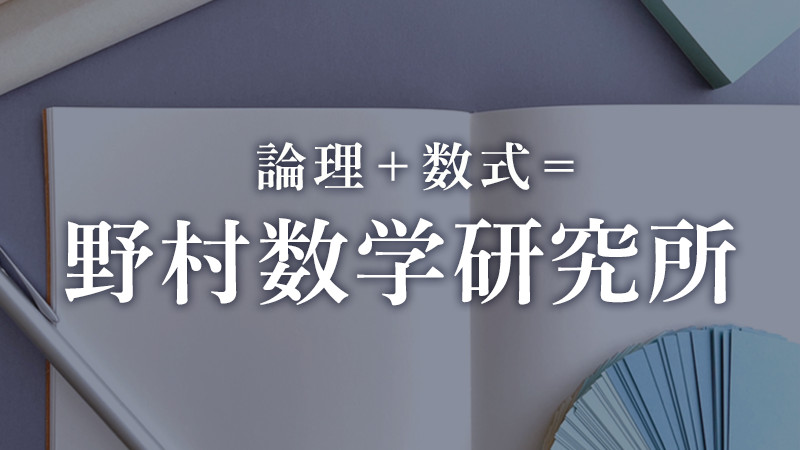[374]お江戸正座31
タイトル:お江戸正座31
掲載日:2025/08/18
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:31
著者:虹海 美野
あらすじ:
平太は大工である。
ここ半年ほど仕事帰りに味噌屋に寄っては買い物をし、長屋のおかみさんたちに差し入れている。
そのお返しにと、おかみさんたちが味噌汁を作り平太に差し入れてくれているおかげで、平太は身体の調子もよく、味噌にも詳しくなった。
平太の目当ては実は味噌屋のおせいであったが、おせいは全く平太の思いに気づかない。
ある日、平太はおせいを曲芸を見に誘うが、そこにはおせいの両親もついて来ることになり……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
朝、平太の家の戸を、大概どこかのおかみさんが軽く叩く。
そうして、にぎりめしと味噌汁を上がり框に置いてくれる。
これは、ここ半年ほどの間にこの長屋でのお約束のようになった習慣である。おかみさんたちが、同じ長屋住まいの独り身の男みんなにこんなふうに世話を焼いているわけではないし、かといって、平太を特別扱い、ましてや、気がある、ということでもない。
平太が頻繁に味噌を買い、それをこの長屋のおかみさんたちに、「よかったら、使ってください」と持って行くから、朝味噌汁を作るついでに椀一杯分を平太のところへ持って来てくれ、ついでにとにぎりめしも付けてくれる、といった具合なのである。
平太はお礼を言い、引き戸を閉めると、一人住まいの部屋に正座する。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬようにし、脇は締めるか軽く開く程度である。
そうして、手を合わせ、差し入れの朝餉をありがたくいただく。
実のところ、手を合わせるのは、めしを作ってくれたおかみさんにではない。この味噌を売ってくれた娘に、である。
平太は江戸の大工である。親方の元に弟子入りして早十年経つ。
最近、親方の娘と兄弟子が結婚した。
そうした影響からか、独り者ばかりの弟子たちも、意中の娘がいれば積極的に動くようになった。
兄弟子の敬蔵(けいぞう)は、少し前にずっと気にかけていた酒屋の娘、おりきに恋文を思い切って渡したらしい。あの敬蔵兄が、恋文だって? と、ほかの弟子と影で腹を抱えて笑ったが、なんとその後、お付き合いをしてもよいという返事をもらったというから驚きだ。
そのおりきの友達である、味噌屋の娘、おせいを平太はかなり前から思っている。だが、全くおせいは気づかない。もともと店番もあまりしない娘のようで、味噌屋に行っても会えるのは、三度に一度あればよい方である。おせいは感じのよい娘だが、なんというか、客を覚えるとか、そういうことをする気が全くないようで、「どうもありがとうございます」とは言ってくれるが、毎度、とか、今日はどれにしますか、とは言ってくれたことがない。
だいたい、独り身の平太が頻繁に味噌を買いに来ることに、何やら感じ取ってくれてもよさそうだが、全くそれに気づく気配もない。
勇気を出して、じきに川開きですね、などと、遠回しに誘ってみても、「ああ、もうそういう時期ですか」と、二度、三度頷き、「ありがとうございます」と言って終わりであった。
なんと鈍い娘か……。
だが、最近、以前よりおせいが店番をする日が増えた。
そうすると、どうにか話したく、平太は店に入る。
そうして味噌を買う。
それを長屋のおかみさんのいる家に、三日前はこの家だったから、今日はこの家に、というふうに配っている。
高い味噌は買えぬが、そもそもどの味噌がどういった味噌汁に合うとか、甘さの強めのものとか、辛めのものとか、そういうことが平太にはわからなかった。だから、最初は店で一番大きい器の、ほかの人も買っているものを選んだ。次に、その隣のを選び、また、その隣のも選んでみた。それをそのまま、長屋のおかみさんに渡した。おかみさんたちは、私はこの前もらったのが口に合うよ、とか、この前もらったのは、普段買わないのだけど、案外おいしかったよ、とか、もらっといて言うのもなんだけど、前回もらった味噌の方が私は好きだね、とか、いろいろのことを言う。
大概、どの味噌を使った味噌汁も平太は飲んでいるから、ああ、あの家はこの味噌が好きなんだ、とか、これはこれで旨いと思うが、とか、そんなことを一応は考えて暮らしていた。
味噌ばかり買って帰るから、当然、飲み屋に立ち寄る時間も金も減る。
長屋では、おかみさんが味噌のお礼にと、何かを差し入れてくれることが増えた。そのおかげか、平太はこれまで以上に体調がよくなり、大工の仕事にも身が入った。まあ、当然といえば、当然であるが、平太にとっては、味噌屋の娘、おせいは、正に開運の神様のような存在になりつつあった。
2
敬蔵が、ちょいといい話がある、と言い、平太を誘った。
何やら浮かれた様子で、明らかに平太のための話というよりは、自身が何かを話したくて仕方がないというのが、透けて見えて、平太は面倒に思った。
自分がちょーっとうまくいってるからって、それを自慢したくて仕方がないのだ、敬蔵兄は……。弟分だからって、仕事以外ののろけまで聞くほど、こっちはお人好しじゃない、と思う。
だが、やはり仕事場の兄貴分。
思っていることをそのまま言えない。
否、言ってもいいが、話に付き合うより面倒なことになる。
渋々、「じゃあ、仕事帰りにでも」と言ったが、この日、思いのほか仕事が忙しく、しかも夕方から大雨が降り出した。
ずぶ濡れで家に帰った頃に雨は止んだ。
身体を拭き、着物を軽く漱いで、取りあえず物干しに干しておいた。そうして、部屋で一息ついた頃に、いつものように戸が叩かれる。今日はどこのおかみさんか、と思って、相手を確認しないで「はい」と土間に片足だけついて戸を開けると、長屋のおかみさんと、敬蔵が立っていた。
「よう」と、酒を手にした敬蔵を上げないわけにはいかぬ。
おかみさんは気を利かせて、二人分の味噌汁を平太の椀と茶碗とによそい、帰って行った。ついでに、そこのおかみさんの旦那が、「よう、お客さんだって?」と、酒の肴にと、めざしを差し入れてくれた。
雨で冷えた身体には、平太にとっては、酒よりも味噌汁の方がありがたい。
敬蔵も、湯気の立つ味噌汁を前に空腹を覚えたのか、先に味噌汁をいただくことにした。
平太はいつものように背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、足の親指同士が離れぬようにし、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃えて正座する。
そうして、味噌汁を前に手を合わせる。
「おいおい、お前、大工をやめて、どこかの寺で修行でも始める気か?」と、敬蔵が訊く。
「そんなんじゃあありませんけどね。ありがたくいただくものですから」
そう言うと、敬蔵も一応正座し、手を合わせた。
「ああ、旨いな」
味噌汁をすすり、敬蔵が言う。
「そりゃあそうでしょう。売っている人が別格ですからね」
平太が頷くと、「お前、これをこさえて持って来てくれるおかみさんたちへの感謝は微塵のみの字もないんだな」と敬蔵が呆れて言う。
「まあ、一応、味噌はこっちで買ってるんだし、持ちつ持たれつってやつで」
「お前、それもいいけど、ずっとこうして長屋の味噌の買い物番でいるつもりかい?」
椀(否、椀の方を敬蔵に譲ったので茶碗)を空けた平太はつと、顔を上げた。
「どうやら、向こうはちいとも、お前さんのことを気にかけてないらしいじゃないか」
平太はぐっと黙る。
「少し、くらいは、わかってくれてるんじゃあ、ない、ですかね……」
尻すぼみになりながら、平太は言った。
「いいや」と敬蔵はきっぱりと首を横に振る。
「なんでも、おりきちゃんに聞いたところによると、おせいちゃんにいい人も思う人もいないと、本人がはっきりと答えたそうだ」
そんな!
……まあ、薄々は気づいてはいた。
だが、こんなにもきっぱりと言われると、さすがにがっくりくる。
そうして、自分が意中のおりきちゃんとうまくいっていることを、話の中に織り交ぜる敬蔵に腹が立つ。
兄貴分でなければ、ああ、わかった、もう出て行け、と追い出したいくらいだ。
なんとか、黙っている平太を前に、敬蔵は「聞いていたか?」と言う。
「ええ、まあ」と、平太は答えた。
「ちゃんと聞けって」
「聞いてますって。こんな狭い部屋なんだから」
「だから、おせいちゃんは、今誰もいい人がいない。いいか? つまりは、今、お前さんにとって、逃したらいけない機会なんだ。わかるか?」
敬蔵が力を入れて、平太を見る。
「ああ、ええ、まあ。だけど、そう言ったって、何か話しかけても、暖簾に腕押しの状態で、全く手ごたえがありゃしません」
「平太、お前は真面目でいいやつだ。それをいちいち誇張しないのも、お前のいいところだ。あれこれ言わず、黙っていい仕事をする。だがな、それを全く知らぬ娘さんにわかってもらおうというのは、怠惰というものだ。店に通っているのは、確かにお前さんの努力だ。だけど、お前さんの努力が必ずしも、おせいちゃんに届く保証はない。否、届いていない。そこはわかるか?」
「まあ」と、平太は小さく頷いた。
「そこでだ」と、敬蔵が身を乗り出す。
「最近、見世物小屋でちょいと手の込んだ曲芸が話題だろう?」
「そうなんですかい」
「そうなんだって! 二度、三度通う輩もいるってんだから、それなりだろう。それに、おせいちゃんを誘ってはどうかい?」
「えええ? 私はただの客ですよ。それが、そんな、いきなり……」
しどろもどろになる平太に、「お前さん、強引に誘えと言っているんじゃない。一応は顔見知りでもある。行くかどうか、訊いてみるだけ、訊いてみりゃあいいじゃあねえか」と敬蔵は言う。
そうして、「ちゃんとこっちでも手は打つよ。俺とおりきちゃんでその曲芸を先に見に行って、おりきちゃんに、いかにその曲芸が楽しかったかとおせいちゃんに話してもらうんだ。あれだけ仲のいい友達が面白いと言ったそばから、それを見に行きましょう、と声がかかれば、どうだ? 行ってもいいと思うんじゃねえか」と続けた。
確かに、敬蔵の言う通りである。
ただ平太が味噌を買いに行って、短い会話をしても、おせいは全くその意図に気づかぬ。
だが、そんなふうにちょっと興味引かれるものに誘われれば、少しは考えるかも知れぬ。
3
かくして、平太にとっての勝負の日が来た。
「はい、いらっしゃい」と店番のおせいが立ち上がる。
この日は昼の休憩時に店を訪れた。
あら、いつもと違う時間なのね、などと言ってくれれば、こちらも話を持っていきやすいが、この半年、味噌を買いに通っても、長い話をしないおせいである。厳しいところだ。
だが、幸い、店にはほかに誰もおらぬ。
今を逃してはならぬ。
「あの、いつもこちらの味噌を買って、おかげで、ずいぶんと身体の調子もよくなりました。いや、元からいいんですが」
ああ、何を言っているんだ、と平太は思いながら、大きく息を吸った。
両の手を握り、目も固く閉じ、一気に伝える。
「それで、お礼と言ってはなんですが、今、大層面白い曲芸が見られるそうなんで、ご一緒にいかがですか。もちろん、費用はこちらで持ちますんで」
言った!
頑張った。
さあ、どうだ。
「本当に? ちょうどよかった。お友達がとても面白かったから、行ってみた方がいいって教えてくれたんで、近々行こうと思ってたんです」
明るい返事に平太は、ぱっと目を見開く。
おせいのかわいらしい笑顔。
ああ、おせいと逢引できる日が来るとは……。
敬蔵兄、ありがとうよ!
「お父ちゃん、お母ちゃん、せっかくだから、ご厚意に甘えさせてもらおうよ」
え?
お父ちゃん?
お母ちゃん?
我に返れば、さっきはいなかったおせいの両親が居る。
そうだ。
だから今日は昼餉の時間を狙ってきたのだ。
おせいは大概、両親とは別に昼餉を摂り、店番を交代する。
それが……。
ああ、平太が一世一代の逢引のお誘いをしている間に、おせいの両親は昼餉を終え、戻って来たらしい。
あの、目を閉じて精一杯の勇気を出している、正にあの時に。
もっとゆっくり食べていればいいものを……。
「よろしいんですかい?」
「費用はこちらで持ちますよ。いつも来てくださるお客さんにそんなこと……」
味噌屋の夫婦二人、すっかり乗り気である。
そうして、そのついでといった感じでおせいが居る。
費用なんかいいから、本当は二人で行きたいところだ。
おせいにして、この親あり。
どうにも、ずれているというか、気遣いしてくれても、それがこちらの望むところと大きく異なる。
「あ、否、費用は大してかかりやせん。私は独り身で、大工をしております。平太と言います。皆さんが曲芸を見られるくらいの小銭は持ち合わせています。いつも、こちらではよい味噌を買わせてもらっていますから、ご恩返しがしたく……」
大工をしていることと、名を伝えた。
ここまではよい。
後半はなんとも苦しい口実になったが、言ってしまったものは仕方ない。
怪しまれる。
断られる……。
だが、「それじゃあ、ご一緒させていただきましょう」と、おせいの父が言った。
「いいんですかい?」
「ええ、今、誘ってくださったのは、平太さんでしょう?」
「はい、はい、そうです」
そんなふうに、うまくいったのか、失敗だったのかはわからぬが、とにかく平太はおせいと曲芸を見に行けることになった。
一緒に出かけられることになったのは、おせいの父のおかげであるが、「おせい、せっかくだから、二人で行っておいで」とは言ってくれぬところは、ややがっかりした。
4
曲芸の小屋は、噂が噂を呼び、大盛況だと敬蔵に聞いていたから、早めに向かうことにした。
味噌屋の店番はおせいの兄がしてくれていると言う。
本当なら、おせいと二人、川開きの始まった、賑やかな江戸を歩きたかった。周囲の若い夫婦のように、あれこれを見て、話したかった。時々、何を話していいかわからなくなり、困ったらどうしよう、と平太はおせいを誘う前には悩んだが、今思えば、そんなことで悩んでもみたかった。
途中で、簪や櫛でも見繕って、おせいに贈りたかった。
『まあ、きれい。嬉しい。ありがとう、平太さん』、なんて、おせいに言われてみたかった。
『つけてみなよ』、なんて、平太がちょっと冷静な口調で言って、おせいがそれをつけて、『どう?』、なんて訊いて、『似合ってるじゃあねえか』、なんて、ちょっと照れて言う。それで、おせいもちょっと照れる。
嗚呼、もう、こういうのを想像し、長屋で一人布団の中で足をばたつかせて興奮していた。
そうして、曲芸を見に行く見世物小屋の方は混んでいるから、『俺につかまっときな』、なんて言って、裾をちょっとおせいがつまんだりして、人が増々ふえてきたら、おせいの手を取って、おせいを振り返る……。
嗚呼、こういうのも想像した。
だが、実際には、「お父ちゃん、ほら、はぐれないようにしてよ、行くよ」と、常におせいは父親がついて来ているかを心配し、おせいの父は「おい、お前、よそ見ばっかすんな」とおせいの母を心配している。
平太は現実に返る。
さっきから、おせいの父も母も、あちこちの店で売っている小物なんかを見ては立ち止まり、花売りの前で立ち止まり、飴屋の前で立ち止まり、玩具を売る者の前で立ち止まり、そのたびに夫婦のどちらかが、「ほら、行くよ」と袖を引く。
平太は、それほど町を出歩かないが、それでも大工の仕事で町のあちこちに行くし、半年前までは兄弟子たちと帰りに居酒屋に寄ることも多かったから、人出の多い界隈は見慣れている。そこでまさか、こんなにも頻繁に立ち止まるとは思わなかった。
だが、考えてみれば、夫婦で味噌屋を営む生活をしていれば、そうそう、人の出の多いところまで遊びに出る暇はないだろう。所帯を持つまでは、平太がおせいとの逢引を勝手に思い描いたように、この夫婦も連れ立って、こうした界隈を歩いていたのかも知れぬ。
正直、おせいと二人で出かけたかったし、あちこちの店につられて足を止めるこの夫婦は面倒に感じないでもなかったが、次第に、平太は何やらせつない気分になっていった。
今日、おせいとともに出かけると言ったおせいの両親は、やはり娘が心配だったのだろう。周囲の娘が結婚する年にはなっていても、おせいを平太に任せて出すのが心もとなかったのかも知れぬ。不思議と、平太はそれに腹が立たない。寧ろ、いい両親だ、と思った。
そうして、ああ、いつか、いつか、こんな夫婦におせいとなりたい、と思ったのだった。
ひと際人の多い場所に曲芸の小屋はある。
はぐれないようにと、平太はおせいの両親とおせいを注意深く見ながら、前に進んだ。
そうして、「こっちです」と、おせいたちをようやく小屋まで連れて来た。
ここまでで、一仕事である。
小屋に入ると、どんどんと奥へと座ってゆく。
平太は端に座り、「真ん中になるべく近い方が見やすいでしょう」と、おせいに勧めた。
おせいは「せっかくだから、お父ちゃん、お母ちゃんがそっちの方に座りなよ」と言い、平太の隣に座った。
おせいの父はまだ隣に誰が来るかわからないからと、おせいの隣におせいの母を座らせ、その横に座る。
おせいの一家は、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬようにし、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃えている。
暗い小屋の中で、平太もいつものように正座し、曲芸が始まるのを待ったのだった。
5
「さあさ、遠慮なさらずに、上がってくださいな」
そんなふうに、おせいの両親は曲芸を見た後、家での夕餉に平太を呼んでくれた。
事前に夕餉は用意していたようで、膳にはごはんに香のもの、煮物、野菜のたくさん入った味噌汁が並んでいた。
まさか、これまでただ店に通って味噌を買うだけだった自分が、この家の家族とともに夕餉を摂るとは、考えもしなかった。
ここでも、平太は正座した。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬようにし、脇は締めるか軽く開く程度にする。
夕餉の席では、曲芸がいかによかったかを、おせいの家族は話しており、おせいの兄にも勧めている。そうして、あの場面もよかった、ねえ、平太さん、と時折平太に語りかける。
確かに曲芸は、大層よかった。
演出の音曲も風情があり、曲芸は物語風に進む。
大きな拍手と歓声に包まれる小屋の中で、おせいも目を輝かせ、しきりに手を叩いていた。その横顔を見られ、平太は心から嬉しかった。
お暇する前、「楽しんでもらえてよかったです」と、平太はおせいに伝えた。
おせいはちょっと目を見開いて、平太を見上げていた。
おせいの父は「大したもてなしもできませんが、またよければ夕餉に寄ってください」と言ってくれたのだった。
6
敬蔵は、平太の報告を聞き、腹を抱えて笑った。
今日は味噌を買いに行くと、夕餉の催促をしているようなので、そのまま帰る平太を敬蔵が飲み屋に誘った。
「なんだ、じゃあ、お前、家族ご一行の案内役みたいじゃないか」
「まあ、そんなもんですよ」
酒を飲みながら、平太は不貞腐れて答えた。
「そういじけんなって、お父ちゃん、お母ちゃんが先に平太を気に入ったなら、しめたものじゃないか。結婚は本人の意志より断然親の判断なんだから」
「……それは、そうかも知れませんけど」
敬蔵は溜息をつき、「もし、どうしてもって時には、おりきちゃんに頼むか?」と、言った。
昔、大工の見習いになりたての頃、もう、明日は行きたくない、と思った夕刻に、「俺から親方にうまく言っておこうか」と言ってくれた時の声と同じだった。あの時、その逃げ道を敢えて作ってくれた敬蔵によって、平太は「すみません。明日もよろしくお願いします」と敬蔵に頭を下げた。
今も同じである。
「ありがとうございます。……もう少し、頑張ってみます」
「そうだな。平太が初めて思った人だからな」
目を上げると、敬蔵は優しく笑っていた。
この人には敵わないなあ、と思う。
そうして、この人と一緒になるであろうおりきさんは、さぞかし幸せであろうとも思った。
7
雨の日の夕刻だった。
ここのところ、味噌の差し入れをしていないから、おかみさんたちからの飯の差し入れも飛び飛びになっていた。
腹が減り、仕方なく、傘を差して煮物かなんかを買いに出かける。
今日は仕事が雨で休みだから、一日家でごろごろして過ごしていた。
米は昨日炊いた残りを朝、茶漬けにして食べたが、何やら味気なかった。
煮売り屋を目指して歩いていると、「平太さんではありませんか」と声をかけられた。
振り返れば、おせいの父であった。
「ああ、こんばんは」
「これから夕餉ですか?」
「ええ」と平太が答えると、「だったら、うちへ来ませんか。ちょうど今、知り合いから干物をたくさんもらった帰りでね」と言う。
「いえ、そんなご迷惑は」と平太が慌てる。
「迷惑なら、誘いませんよ」とおせいの父は笑った。
「ついでに言うなら、来てほしくないなら、誘いません」
「ありがとうございます」
平太が行きやすいよう、言ってくれる心遣いに、頭が下がる。
「おせいも同じでしょう」
ふいにそう言ったおせいの父の顔を、平太は傘を持ち上げ、覗きこんだ。
「このところ、夕餉までの時間の店番を自分からやると言ってくれているのは、まあ、私らに早く休めるようにという親孝行もあるでしょうが、それだけじゃあないでしょう」
おせいの父が何を言わんとしているかを察し、平太はいやいや、そんなことがあるか、と思う。
それが顔に出たのであろう。
おせいの父は「まあ、濡れますから、行きましょう」と、平太を促しながら、話を続ける。
「あの子は、昔からなんというか、物事を重く考えない、気楽な性質でして。そういうところが、親からするとほっとするというか、ああ、この子はこの子なりにうまくやっていけて、それなりに楽しめていると思ってきました」
「ええ」と平太は頷いた。
おせいに引かれたのも、そもそもは、あの朗らかさだった。
適当な感じはあるが、店が多少混んで忙しくとも落ち着いていて、それでいて、どこか気楽そうで、かわいらしい。
「ただまあ、少し以前に気づいたのですが、幼馴染の娘さんとばかり遊んでいたせいか、全く色恋とか、そういうことに疎くて。いやいや、幼馴染の娘さんたちは、それぞれにいい人を見つけましたから、うちのおせいがただ疎い、ということでしょうな。私が知る限りでも、幾人かは、おせいと話したくて店に顔を出していたようなのですが、全くあの子はそれに気づかない。大抵はひと月、二月で来なくなる」
おせいを目当てに来る客がいた、というところで、平太の心が何やら疼く。
つい、俯いた平太に「平太さん」と、おせいの父が語りかける。
「あ、はい」
おせいの父を見遣ると、おせいの父は穏やかな目で平太を見ていた。
「あなたが初めてなんですよ。おせいが店番をして待つのも、半年以上店に来てくれるのも」
何か言わなければ、そう思うが、言葉が出ない。
「ここのところ、夕餉用に飯を多く炊いて、味噌汁も多く作るものだから、最近は朝の味噌汁も野菜の甘いものが一人、二人分残ってね。それを椀に移して、家族のうちの誰かがそれを飲んで、二杯目に朝作った味噌汁を飲むといった具合でね。いつ、平太さんが来るか、来るか、とうちのが作っては、次の日に回すのが日課になってしまった。平太さんが、毎日うちで夕餉を摂ってくれれば、一番いいのですがね」
こんなにも、温かい歓迎の言葉がほかにあるだろうか。
雨のせいでなく、視界が滲む。
「ああ、こんなことを言って平太さんを困らせてはいけませんね」とおせいの父は言う。
「……私は、なんとお礼を言えば……」
「お礼はうちが言う方ですよ」と、おせいの父は言う。
「さあ、雨で身体が冷えますから、一緒に帰りましょう。温かい飯ができている頃ですから。この干物も焼いてもらいましょう」
「はい」と平太は頷いた。
隣に座るおせいと、甘めの野菜の味噌汁を、思い出していた。

![[310]お江戸正座12](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)