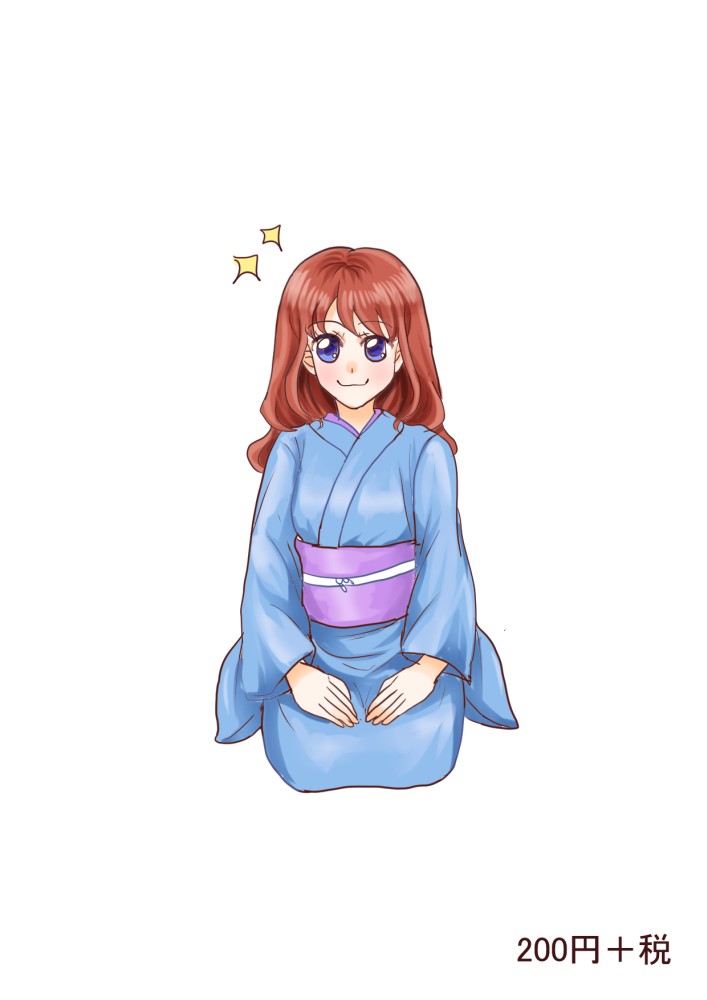[48]青い眼のタンチョウヅル、正座する
 タイトル:青い眼のタンチョウヅル、正座する
タイトル:青い眼のタンチョウヅル、正座する
分類:電子書籍
発売日:2019/03/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:40
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:keiko.
内容
加奈は大学生。教会の信者で、笹小原流の作法教室にも通っている。そして、教室の跡取り、楡彦に片思いしている。
英国人のシスター・スージーは、日本に行方不明の姉を捜しにやってきて加奈の片思いの楡彦に一目惚れ。だが彼は英国留学中、スージーの姉ロザリーと恋人同士だった。そろって失恋した加奈とスージーだったが、楡彦とロザリーにはある事情があった。さて、正座を通して知り合った「若者たちの運命」は……。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1251294

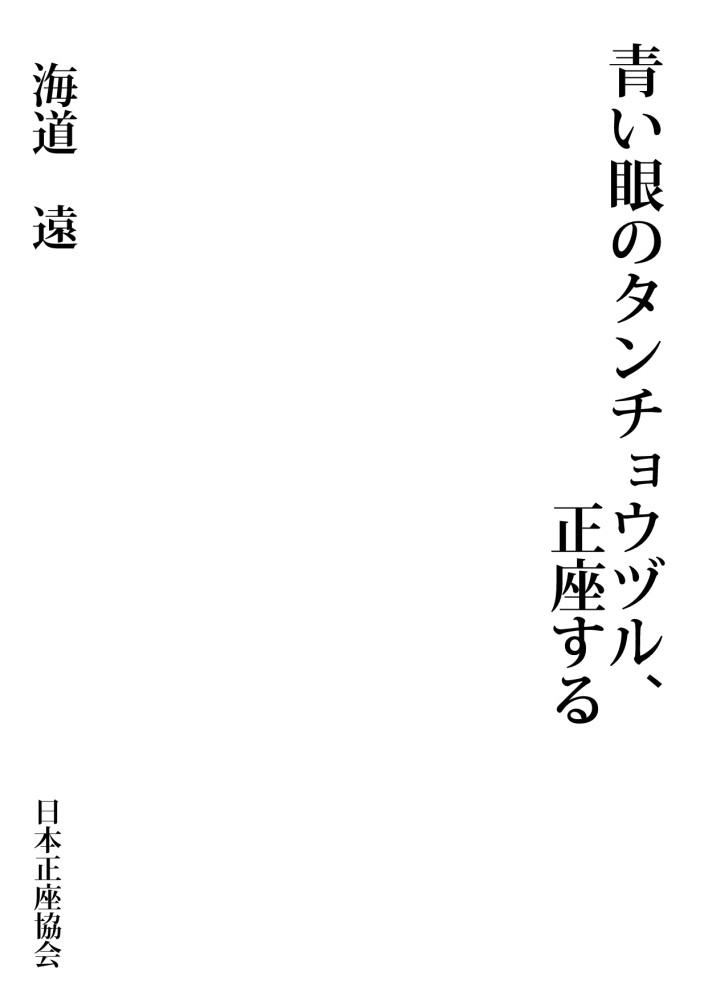
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
教会の空気は礼拝堂も廊下もひんやりとしている。
日曜礼拝が終わり、信者さんたちが、がやがやとしながら帰ろうとしている中、加奈は呼び止められた。この春から、イギリスから研修に来ているというシスターだ。
大学二年の自分とそう変わらない年齢だと思うが、西洋人なので、とても大人っぽい。シスター姿のグレーのドレスも長身で、碧い瞳が美しい。
「加奈さん、でしたわね」
日本語も達者だ。
「はい、そうですが? シスター・スージー」
「あなた、笹小原流のお作法教室に通っているのですって?」
「はい……」
「その、お作法教室、紹介していただけないかしら? ほら、私、日本に来て間もないし、教会にいると普通の日本のお家にいるより畳にも慣れないし、礼儀作法もわからなくて」
「いいですよ。今日もこれから、お作法教室に行くところです」
「まあ、ちょうどよかったわ。ご一緒してよろしいかしら?」
少女のように無邪気な顔でにっこり笑うと、
「ちょっと待っていただけますか」
と言い、教会の奥へ消えた。
秋の深い青空を見上げてから、教会の中庭の池へポチャンと石を投げたりして待っていると、
「お待たせしたかしら」
「シスター・スージー?」
加奈がびっくりマナコになるほど、シスター・スージーは変身! して教会を出てきた。
グレーの重苦しいシスター姿と頭巾姿はどこへやら、肩へ落ちかかる渦巻く金髪、瞳と同じブルーの膝までのワンピース。
女の加奈が見ても、見とれてしまう美しさ、鮮やかさだ。
「どうしたの?」
「だって、シスター・スージー、とっても眩しい。きれいです。女優さんみたい!」
「ありがとう。でも、私の姉の方がもっときれいよ。私はほら、ソバカスが」
「お姉さま?」
そうそう、このシスター・スージーには、行方不明のお姉さんがいるとかいう噂だ。
「姉の方が親日家で学生時代、日本に留学していたほどよ」
ふたりは教会の門を抜けて歩き始めた。
「実はね……」
スージーが急に耳元へ口を寄せてきた。
「加奈さん、あなたの通っているお作法教室に、息子さんがいらっしゃるでしょう」
「え、ええ、若様の楡彦さんですね」
「そう、若様。その楡彦様とお母さまも、教会の神父様のお知り合いなのよ。先日、初めてお見かけして、その……あの……分かるでしょう、加奈さん」
スージーの顔が真っ赤だ。
「ひと目見て、私ったら恋してしまったようなの」
「えええっっ」
立ち止まった加奈から頓狂な声が出た。
何を隠そう、その笹小原流の若様こそ、加奈の片思いの相手なのだ。数年になるだろうか、高校生の頃から、お作法教室に行きだして出入りしているうちに若様を見かけて胸がときめき始めたのは。
それは無理もない。楡彦若様の凛々しさといったら、茶道の袱紗にも嫉妬してしまいそうなくらいだ。
「ああ、袱紗になって握られた~~い!」
なんて、黄色い声でも飛びそうな。男らしい輪郭の顔、肩幅の逞しさ、優しい眼元と声。作法を女の子たちに教える時の紳士ぶりは、西洋人にも勝るとも劣らない。
加奈の複雑な思いも知らず、シスター・スージーは続けた。
「神秘的な真っ黒の瞳、西洋人なみの体格。あの逞しさで、作法教室の若様だなんて」
(お姉さんが行方不明だってのに、のんきな人ねえ、いいのかしら。まあ、仕方ないけど。若様のエビ茶色の袴をお付けになった時の美しい姿と言ったら)
思わず、加奈もボウっとなるところだった。
「ところで、シスター、お姉さまの行方をお探しだとかお聞きしましたが?」
「え、ええ、なんの連絡もなく大学の寮からいなくなってしまって。また大好きな日本へ来ているのかしら? と思い、つい捜しにきてしまったの」
やはり、あの噂は本当だった。シスター・スージーは複雑な表情を浮かべた。
2
ふたりはお作法教室の開かれている大邸宅に辿りついた。
大きな石の門構え、小山に松やつつじが植えられ、屋敷の奥から鹿威しの「コ―――ン!」という音が突き抜けて聞こえる。
「笹小原流」という看板が太く濃い炭で書かれている。
加奈は通い慣れた邸宅の玄関を勝手に上がり、奥への廊下を、シスターを連れて進んでいった。
奥座敷に年配の婦人方に囲まれて、いっそう貫禄のある宗家夫人が床の間を背に座っている。青朽葉色の着物、艶やかな黒髪を結い上げ、宗家亡き後、女性ながら笹小原流を守ってきた人だ。
加奈は廊下に静かに座り、頭を下げた。
「いらっしゃい、加奈さん。おや、その方は?」
宗家夫人が、加奈の背後にいるシスターに気づいていう。
「教会にお仕えのシスターでいらっしゃいますが、こちらでお作法をお習いしたいとのことで、お連れしました」
「ああ、教会でお見かけしたことがございますわ」
「スージーと申します。どうぞ、宜しくお願い申し上げます」
「スージーさん。日本語がお上手ね。こちらこそ宜しくお願いしますよ」
宗家夫人は、笑顔をくゆらせて答えた。
「まあま。お点前でも、一服」
夫人が勧めて、お茶がたてられた。
スージーは慣れない所作で、どうにかお薄をいただいた。
「苦い? ほほほ」
「でも、もみじの形のお生菓子、美味しかったでしょ、シスター。もうひとついただく?」
「まあ、加奈さんたら」
和やかな雰囲気が奥座敷に満ちた。
「それにしてもスージーさん、正座と日本の所作がとてもおきれいね。どこかでお習いになったの?」
「いいえ、姉がとても日本が好きで留学しておりました。その姉から教わっただけです」
「お姉さまが? ここの流派の所作にしか思えないわ。お名前はなんておっしゃるの?」
「ロザリー・ハミルトンと申します」
とたんに、廊下で驚いたように咳が聞こえた。
「ゴホン、ゴホン」
「あら、楡彦? そこにいたの。どうしたの?」
「いえ、何も」
お茶碗を置いたスージーが立ち上がった。
「楡彦さん!」
「スージー、どうして、ここに」
「姉が日本に来てやしないかと、捜しにきたんです。貴方も姉も急にうちに来なくなって、どうしたのかと」
楡彦と呼ばれた若者は縁側から慌てて立ち去ろうとする。
加奈は呆気にとられていた。
「若様とシスター・スージーは知り合いだったの? じゃあ、私がわざわざお教室を紹介することもなかったんじゃないの」
(もともと、好きになったのは、私が先ですからね)
と、スージーを睨んでみる。若様とスージーが自分の知らないことを話すのは面白くない。ところが、である!
「お母さん、この際、僕から真剣にお話があります」
縁側に正座した楡彦は、改まった態度で頭を下げたのである。
3
鹿威しが若緑の庭を突き抜け、「コ―――ン!」と鳴った。
宗家の庭から涼しい風が吹き抜けているのに、楡彦の額には、脂汗がにじんでいる。
「実は、交際している女性がいるのです」
「なんですって?」
寝耳に水の宗家夫人は、思わず持とうとしていたお茶碗を落としかけた。
夫人の周りに取り巻いていた女性たちは、そそくさと席を立ち、去っていった。
「お母さん、驚かれるのも無理はない。僕は昨年の留学中、英国の女性と交際していました。この、スージーのお姉さんと」
「なんですって!」
今度は宗家夫人と加奈が同時に叫んだ。
「結婚を前提にです」
「なんですって!」
次は、夫人と加奈とスージーが三人、同時に叫んだ。
当然、楡彦がいう結婚相手というのは、ロザリーのことである。
びっくりしながら、加奈とスージーは互いの顔を見て、火花を散らした。
(楡彦さんは、私が何年も前から想ってきた人よ。あなたにも、あなたのお姉さんにも渡さないわ)
(いくら姉の交際相手といっても、私は諦めないわ。姉さんにもあなたにも負けない)
しばらくにらみ合いは続いた。
「楡彦」
宗家夫人は座りなおして言った。
「あなたの婚約者候補は私が決めます。いえ、もう決まっているのです」
「母さん」
「ここにいらっしゃる、林加奈さん。お家柄も確かで、お母さまとも長いお付き合いです。こんなにあなたにお似合いのお嬢さんは他にはいないわ。それを、西洋の方とだなんて」
「加奈ちゃん? 加奈ちゃんは妹みたいな存在だ。婚約者だなんて」
「お黙りなさい! こうなったら、加奈さんのお宅に早急にうかがって、ご両親様に正式にお話します」
「母さん、そりゃ、加奈ちゃんのお作法は素晴らしい出来だよ。でも、結婚相手とは……」
弱腰の息子は無視され、宗家夫人は奥に入ってしまった。
翌日、宗家夫人は、さっそく加奈の家に婚約の申し込みにやってきた。
4
加奈の両親は突然のことに、右往左往している。
なんとかお座敷に通し、お茶だけ運んできた母親は、
「どうしよう、加奈。お作法宗家とご縁談だなんて。私、何も聞いてないわよ」
「言おうたって、私だってどうすればいいかわかんないわよ。だいたい、若様の楡彦さんは、ロザリーさんと結婚したいと言ってる。私が無理やり婚約するわけにはいかないわ」
「――でも、あの奥様の剣幕といったら」
ついに、加奈の父親も仕方なく、座敷の床の間の前に座った。
宗家夫人は優雅ともいえる所作で父親の前で美しい地味な紅藤色の色無地の膝を降り、その場に座った。
「お嬢様と息子は数年前から親しい仲です。それに、加奈さんなら宗家の嫁にふさわしい所作をマスターしていらっしゃいます。どうぞ、息子の嫁にお願いできませんでしょうか」
「うちのはねっかえりを、そんな」
額の汗を拭きふき、父親は答えている。
加奈は、というと、夢みたいな話を虚しく聞いている。
(これが本当に、若様のご希望ならどんなに嬉しいかしら)
しかし、これは母親の一方的な縁談なのである。楡彦がうん、というわけない。
そこへ、大股の響きの足音が玄関から聞こえてきた。楡彦が普段のセーター姿で現れた。
「いきなり、すみません。母が勝手なことを」
「楡彦さん!」
「母さん、こんなに突然、言い出したら、ご両親も加奈ちゃんもご迷惑だろう」
母親の腕をつかんでいこうとする。
「楡彦さん、話の途中でしょうが!」
抗う母親を、楡彦は力強く引っぱって、構わず加奈の家を後にする。戸惑いながら、加奈はふたりの後をついていった。
楡彦と母親が帰宅すると、今度は、教会の神父様とシスター・スージーが待ち受けていた。
5
「神父様! これはまた急なお越しですわね」
今度は宗家夫人がびっくりする方だ。
テカテカのポマードを塗りつけた黒髪の神父はグレーのシスター頭巾を被った、シスター・スージーを従え、奥座敷へ上がった。
「宗家の奥様、この子、スージーがシスターでいるのは期間限定なので、是非とも嫁に考えてやってくださいませんか。この子がさめざめと私に言うには、お宅の若様にベタぼれでございます」
胸元のロザリオを揺らして、神父様は懸命に頭を下げたが、
「美しい正座が、西洋の方にできましたら考えないでもありませんけどね」
と、宗家夫人は嫌味がましく言って首を縦に振ろうとしない。
スージーが神父様の背後で立ち上がった。
「こうなったら、加奈さんと勝負するわ!」
宗家夫人も神父様も、ギョッとした。加奈もである。
「シスター・スージー、まだ、日本に来て間もないじゃないか」
「大丈夫ですわ、神父様。姉の教えを母国で受けていましたから。私にも、お師匠先生の納得されるお作法ができましたら、楡彦さんのお嫁さん候補に入れて下さるでしょうか」
というわけで、スージーと加奈は一週間後、宗家夫人とその取り巻きの婦人方の前で『お作法勝負』をすることになったのだった。
6
ふたりとも、着物の着付けから猛特訓して、勝負に臨むつもりである。
ある日、楡彦若様から、宗家の茶室で話したいと連絡が来る。
「何のお話かしら、改まって」
当日、茶室の前で、鉢合わせた加奈とスージーはどぎまぎしながら、同じ思いだった。
やがて、若様のお手で風炉で湯が沸かされ、お茶が点てられた。
そろそろ今年最後の風炉である。壁には萩の花や菊の花。秋のまっ盛りだ。
ふたりがお茶を飲み終えると、若様は静かに話し始めた。
「ロザリーとは、大学で知り合ったが、僕が日本を好き嫌いは関係ない。国境など関係ないんだ。しかし、大学の日本文化サークルで初めて見たロザリーの正座姿の美しさで一目ぼれしてしまった。ふたりとも、無理やり勝負したところで僕のロザリーへの思いはちっとも変わらない。ひどい言い方だが諦めてくれないだろうか」
加奈もスージーも、お寺の鐘が耳の真横で鳴ったような気がした。念を押してふられたのだ。
若様が去っても、ふたりはいつまでも茶室に呆然としていた。
「あそこまで愛された姉さんは幸せだわ」
「ロザリーさんの正座って、そんなに美しいのね……」
ひとり言のようにつぶやきあってるうちに、ふたりは自然と正座していた。いつもはあんなに苦痛な正座なのに、ちっとも痛くない。足より心の方が痛い。ふたりはいつの間にか、どちらからともなく、肩にもたれかかっていた。
7
そんなある日、スージーと加奈が連れ立って教会へ赴くと、聖堂へ入っていくスーツ姿の若様の姿が 庭木の陰からちらりと見えた。
庭のマリア像の陰から見守っていると、若様は神父様と一緒に懺悔室へ入っていくではないか。
加奈が、
「ないしょだけど、懺悔室の声が漏れて聞こえる場所、知ってるわよ」
「加奈さんったら、そんなことしていいの? 人の懺悔を聞くだなんて」
「―――じゃ、このまま帰る?」
「いいえ」
教会の鐘の設置してある塔の真下が、懺悔室になる。懺悔室の声は、塔の空洞を伝い、鐘の側まで行けば聞こえるというのである。
加奈が物置からハシゴを取り出してきて、棕櫚の木の根元から鐘の塔にハシゴを立てかけた。
「誰もいない? 日曜礼拝の信者さんたち、皆、帰られた?」
加奈とスージーは辺りを見回してから、おっかなびっくりハシゴを昇っててみた。上まで上がると足がすくむ。我慢して、耳をそばだてた。
楡彦の声が下から反響して聞こえてくる。
「日本を愛していたロザリーは、イギリスの大学のサークルでも日本の作法教室に通っていて、美しい所作のできる女性でした。特に、正座が。まるでタンチョウヅルのようでした」
「うむうむ」
神父様が頷く気配がする。
「なのに、僕という人間は」
若様の声に涙が混じる。
「僕がドライブへ誘ったばかりに、ロザリーは足を折るケガをしてしまい、正座ができなくなってしまった―――」
加奈とスージーはハシゴを踏み外しそうになった。
「知らなかった!」
「姉さんが急にいなくなってしまったのは、事故のせいね」
「若様がこんなに苦しんでいたなんて!」
8
転げ落ちるようにハシゴを降り、つい踏み外してしまった。ふたりは棕櫚の根元に尻餅をついた。
「いたたた……」
そこへ、ブラウンの髪の美しい女性が歩み寄ったので、ふたりはよけい驚いた。
「スージー、何してるの?」
「姉さん!」
ロザリーは茶色い花柄のワンピース姿で、松葉づえをついてふたりの顔を覗き込んだ。
9
「ロザリー姉さん、どうしてここに?」
「だって、あなたのことが心配だから、マミーが様子を見てくるようにって」
「何してたの? 彼女は?」
「教会のお友達、加奈よ」
青い視線を向けられて、加奈は穴があったら入りたくなった。まるでヨーロッパの中世の名画から抜け出てきたような陶磁器の肌、つやつやとしたブラウンの髪、サファイヤの瞳。この人がタンチョウヅルのように正座したら、かなうわけない。
10
「確かに事故から目が覚めた時は絶望的って言われたけどね」
ロザリーは教会のゴブラン織りのソファの客間で紅茶をすすりながら、クスリと笑った。
「ニレヒコは、私の意識が戻る前に、ショックで帰っちゃったらしいわ」
「どうして、すぐに知らせてくれなかったんだ、ロザリー!」
楡彦若様は、なにもかもに驚いて、肩で息をしていた。
「だって、治るかどうかは、まだ五分五分だったんですもの。日本で手術を受けるまでは」
「日本で手術したのか、ロザリー」
「そうよ、名医がいらっしゃると聞いて。でも、あなたにそれを言ったら、付き添いするとか、責任とって別れるとか、騒ぎだすと思って何も連絡しなかったの」
「おお!」
楡彦は、涙をいっぱい貯めて
「そうとも、僕に君を幸せにできる資格なんかない。別れようと思ってた」
「若様らしいですね。誠実なお人柄だから、ご自分のことが許せないのでしょう。懺悔されるほどですものね」
「加奈ちゃん、どうしてそのことを?」
「あわわ」
「なんですって、懺悔? そこまで思い詰めてたなんて……」
ロザリーは楡彦の手をぎゅっと握った。
11
加奈とスージーがお作法の勝負を披露する日がやってきた。笹小原流の上層部のご婦人方、十数人が居並ぶ中である。
お座敷の奥に、紋付き羽織袴姿の楡彦若様、そして宗家夫人。
やがて、秋の日差しを受けた真っ白な障子が静かに開けられ、真っ白な足袋の加奈がコスモス柄の薄紅色の着物で入室し、お辞儀をした。そして、すらりと立ち、若様と宗家夫人の前に正座し、重々しくお辞儀をする。
続いて、萌黄色の着物で金髪を結い上げたスージーも障子を開けて入るや、続いて美しい正座をして頭を下げた。
「これは……おふたりともきれいな所作ですわ」
宗家夫人が言い、上層部の婦人方も頷いた。
「これでは、勝負がつきませんわね」
「少し」
楡彦若様が口を開いた。
「お待ちください。もうひとり、見ていただきたい人物がおります」
障子が開けられたとたん、青空の一部が射しこんできたようだ。
鮮やかな露草色の着物を寸分なく着こなした西洋女性が、入室してきたのである。まっすぐに若様の前に正座すると、白い指をそろえてお辞儀をし、宗家夫人の前でもそうした。
「これは……まるで 鶴が羽をたたんだような」
夫人の唇からため息が洩れた。
「初めまして。ロザリー・ハミルトンと申します。楡彦さんには、英国の大学でずいぶんお世話になりました」
「あなたがロザリーさん?」
宗家夫人は目を丸くするばかりだ」
「そうだよ、母さん。彼女が親日家のロザリーだ。そして、加奈ちゃんとスージーに、お作法の仕上げ稽古をしたのも彼女なんだよ」
ロザリーはにっこりして、もう一度頭を下げた。
「お師匠様、すべて私がお話します」
加奈が突然、宗家夫人の前ににじりよった。
「若様は英国で事故を起こされ、ロザリーさんは脚を大けがされたのです。そして日本で手術を受け、こうして素晴らしい正座ができるようになられました」
「私たちに、お作法、特に美しい正座を教えて下さったのは、ロザリーさんです」
「まあああ」
宗家夫人はじめ、上層部のご婦人方も、最初は驚き、感嘆のため息を洩らした。楡彦若様も誇らしげな顔だ。
「ロザリーさんこそ、若様のお嫁さんに。私たちからもお願いします。ね、スージーさん」
「加奈さん、でも、お宅までお嫁入りのお願いにうかがったのに……」
「お師匠先生、若様とロザリーさんの瞳をご覧になってあげて下さい。こんなに国境を越えて信じあってらっしゃる恋人たちがおられるでしょうか。完全に、子どもっぽかった加奈が甘い考えでした。とても宗家の奥様にはなれません」
「私も同じ思いです、お師匠先生」
スージーも眼元の熱い涙をぬぐいながら、言った。
「ありがとう、スージー、加奈ちゃん」
楡彦がロザリーに歩みよりながらお礼を言った。
「きっと、美しい正座を習ってるうちに、私たちのわがままも溶けてしまったんですわ」
加奈はスージーと顔を見合わせ、爽やかな笑みを浮かべた。