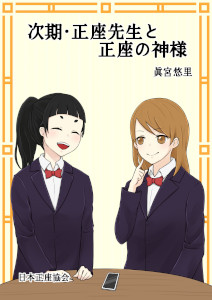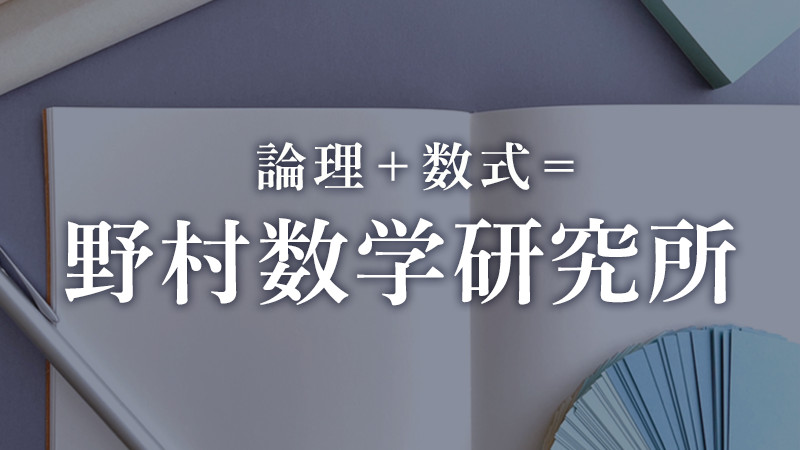[381]お江戸正座33
タイトル:お江戸正座33
掲載日:2025/09/30
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:33
著者:虹海 美野
あらすじ:
由吾郎は材木問屋の跡取り息子である。手習いを終え、お商売を学び始めたある日、姉おいさの夫である義兄がやって来た。
一人息子の竹吉がおいさにべったりで、来年からの手習いが心配なため、二日、三日預かってほしいと言う。
由吾郎の父は、竹吉の面倒は由吾郎が見るようにと言う。
何にでも秀でていると散々聞かされてきたおいさの息子、竹吉は、全く由吾郎に懐かず何も食べない。
挙句に母、おいさの名が出ると突然大号泣し……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
由吾郎(ゆうごろう)は、材木問屋の跡取り息子である。
数年前に姉のおいさは料亭に嫁いで、そこのご新造さんになった。姉が嫁いだのは、由吾郎が手習いに通い始めた頃である。
それから数年が経ち、由吾郎も手習いを終え、今は帳簿のつけかたを学び、お父ちゃんや番頭についてお商売のいろはを習い始めた。
商売仲間との寄合や、それに準じる茶や香の席にも由吾郎は出席するようになった。その前に、由吾郎は父の言いつけで、お作法の教室にも通った。
ほかの娘さんたちと一緒の稽古であったが、由吾郎はそうした場にすんなりと馴染んだ。娘さんたちも、由吾郎とは自然に打ち解けた。由吾郎は姉と二人姉弟だが、年が十一も離れていて、由吾郎が手がかかる年には姉のおいさはもうお稽古三昧で、あまり家にいる時間もなかったから、大人は皆、由吾郎に付きっ切りでよかったのだ。
だからか、由吾郎はおっとりした性格で、さまざまなことをとても丁寧にこなした。子どもたちが入り乱れる手習いでは、取り立てて褒められることもなかったし、先生の興味を引く子どもでもなかった。けれど、由吾郎は家でさんざん大人たちに構われているから、先生がほかの子どもの面倒で忙しく、由吾郎に手が回らなくとも、それを不満に思わなかったし、利発な子を尊敬すれど、同じようになりたいとか、抜かしたいとはゆめゆめ思わなかった。
お作法のお教室は、競い合うということもなくて、先生の言うことを聞いて、所作について学ぶから、由吾郎の気質に合った。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬようにし、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃える。
戸の開け閉めや、お茶の頂き方なんかを学ぶ。
お作法の教室に来る娘さんは、着物や小物も洒落ていて上質である。由吾郎も息子ではあるが、好みの柄の着物を仕立ててもらい、小物も定期的に店に来る商人からおすすめのものや、京のものなんかを見せてもらい、欲しいものを吟味する。
だから、自然と娘さんの簪や帯を褒めたり、それはどこそこの誰それの作品でしょう、などと言っては、娘さんたちをそれとなく喜ばせ、娘さんたちも、由吾郎さんはよくわかっているのね、と由吾郎と打ち解けた。
帰りには、一緒に茶屋に寄ることもあるくらいで、由吾郎はそうした日々に満足している。
茶や香の席、最近では歌詠みの席でも頭角を現し、大層雅(みやび)な跡継ぎですね、などと言われる。
だが、時折、由吾郎が出かけていると思って、番頭や女中なんかが話しているのが聞こえることがあるのだ。
由吾郎さまは、おっとりしたお人柄で……、と話しながら、しかしなあ、姉のおいささまが跡継ぎであった方が頼りにはなったなあ、という話である。
おいささまの頭の良さはこの辺りの子の中でも飛びぬけていた。
あれだけの稽古三昧で、あそこまでしっかりとこなされる人も珍しい。
しかも、お体も並外れて丈夫で。
全く疲れるということがなかった。
見た目はお内儀さまに似て美しいのに、どこにあれだけの体力があるのかと不思議なほどで……。
兎に角、姉、おいさの出来の良さについて、皆が口にする。
姉が褒められるのは、由吾郎とて嬉しい。
だが、どうにも比べられている。
もっと如実に述べれば、自身の劣っている部分を指摘されている、と感じる。
そんなことを言ったって、お商売について学んで、身体を動かして、会合なんかにも顔を出せば、帰って夕餉を取らずに眠ってしまうのも仕方あるまい、と由吾郎は思う。それほど珍しいことでもない、とも思う。
しかし、膳を下げる女中はそうした時、笑い話で、おいささまは、よく召し上がりましたねえ。そうそう、お小さい時から、大人と同じ量を召し上がって、しかも、お稽古の合間に茶屋にも寄って。食べないと力が出ない、なんておっしゃって、その時は、いくらなんでもと思ったけど、一概にそうも言えませんよね。実際、あれだけお稽古事で褒められて、書にも精通して、お稽古事の復習もしっかりされていたんですから……。
そうした笑い話が、いかに、姉のおいさがこの家で大きな存在であったかを物語っている。
そうして、由吾郎はこのままこの家を継ぐが、そんなふうに思い出話として、話されることはないだろう、と思う。
広い座敷で一人、布団に入った由吾郎は、障子を通して届く月の光に目を遣りながら、なんとなく、寂しく思うのであった。
2
そんな由吾郎が寂しく思う暇もなくなるだろう出来事が起こった。
姉の嫁ぎ先の旦那、つまり義兄が突然、家にやって来た。大きな重箱には、義兄が腕によりをかけた料理が詰められているはずである。
突然の訪問を詫びる義兄に、父は「いやいや、こちらから最近出向いておりませんで、来ていただき、助かります」と笑顔で迎えた。
そうして、奥の座敷に義兄を通した。
さすが料亭の板長であり、主人である義兄の所作は美しい。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座している。
せっかくだからと父に言われ、由吾郎は茶を点てた。
「これはこれは……」と義兄は低頭し、お出しした小さな菓子を懐紙で受けて口に入れ、茶をいただく。その流れが何とも優雅である。
「それでは」と、由吾郎は座礼し、部屋を辞した。
その後、父と義兄とで交わされたのは、簡単に言うと、義兄と姉、おいさの長男、竹吉を二、三日こちらで預かってほしい、という話し合いであった。
竹吉は、来年から手習いに通う年である。
気の早いおいさは、自宅でも竹吉に茶のいろはなんぞを教えているという。竹吉もそれを嫌がらず、真面目に取り組んでいるそうだ。
だが、義兄が気にかかるのは、竹吉がおいさから決して離れぬことだと言う。家のことは奉公人に任せられるし、それで不都合もなかったが、さすがに手習いに通う時になってもおいさと離れない、と言い出しては困る。少しの間、おいさと竹吉を離した方がよいのではないか、と義兄は思ったそうだ。おいさにもそう伝えると、おいさはあっさりと、それもそうですねと頷き、けれどいきなり誰も知らぬところへ預けるのは竹吉の負担にもなりましょうし、そうした預け先もございません。すぐ近くのうちの実家などどうでしょう、と提案したと言う。
それで、今日、義兄がそのお願いに来た、ということだそうだ。
竹吉はこちらにとっても孫であるから、もちろん、父は一つ返事で了承した。そうして、そちらのご両親は了承したのですか、と尋ねた。相談すればもちろん、了承いたしましょう。ただ、今両親はここ数年恒例になった湯地場への小旅行に出ておりますので、伝えてはおりません。ひと月もせずに戻って参りますが、こちらでは、竹吉がおいさを恋しがったりしなければ、明日から二、三日預かっていただきたい、ということである。
義兄は手をついて頭を下げ、帰って行った。
「それでお父ちゃん、竹吉を預かるって了承して、大丈夫なのかい」と由吾郎が訊ねると、「そりゃあ、大丈夫に決まっている」と言う。
「だけど、料亭で大事にされている上に、おいさ姉ちゃんにべったりな竹吉の面倒は誰が見るんだい。お商売の片手間というわけにはいかないよ」
そんなことか、というふうに父は由吾郎を見る。
「そんなの、お前さんの役目に決まってんだろう」
「えええ?」
由吾郎は仰天した。
正直、どこか他人ごとで聞いていた話だ。
そのお鉢が回って来るとは……。
しかも、子どもの面倒である。
竹吉は由吾郎の甥っ子ということになるが、ごくたまにおいさが連れて来るのを見るくらいで、世話をしたことはない。厠に連れて行ったことすらない。
その面倒を見るとは……。
書からの帰り道、重いため息をつくと、「由吾郎」と声をかけられた。
手習いで一緒であった立太郎である。
立太郎は船問屋の息子である。まあ、由吾郎もそこそこに大きな店の跡取りであるが、立太郎の家はそれこそ大きなお店で、立太郎はそこの跡取りである。茶や書の教室で一緒になることがあるが、立太郎は剣術の道場にも入門しており、正に文武両道、しかも大きな店の跡取りとあって、同年代の女子(おなご)の憧れであり、また多くの子息にとって頼りになる存在である。
いつものように颯爽とした立太郎を前に、由吾郎は、ため息をつく。
「一体どうした。せっかくの晴天にしけた顔でさ」
「私は曇りや雨の日が好きだよ。青い空を拝めないのは残念だけどね、外を歩いても眩しくなくて、家にいる時に雨音を聞いていると、とても心が安らぐんだ」
人気者の立太郎は、そんな由吾郎の独り言のような話にも真摯に向き合う。
「雅な考えだ。由吾郎の元で働く者は、幸せだろうな」と言う。
「私はそんな器じゃあないよ。いっそのこと、姉ちゃんが婿を取って、継いでくれればよかったとすら思うよ。いっつも、そんなことを心の奥で思っているんだけどね、実は明日から二、三日、その姉ちゃんの息子をうちで預かって、私が面倒みることになったんだよ。……はあ、あの何にでも秀でた姉ちゃんの子の面倒を私が見るって、どういう寸法なんだか……」
足元を見て歩く由吾郎に、「その子は幾つだ?」と立太郎が訊く。
「ええと、来年あたり手習いに行くって聞いているよ」
「そうか。じゃあ、もういろいろとわかる年だな。よし、私も助けに行こう」
何かと忙しい立太郎にそんな時間があるんだろうか……。
そう思ったが、こちらの一方的な泣き言に付き合ってくれた立太郎にそれを訊くのはさすがに野暮が過ぎるというもの。
「恩に着るよ」と言い、別れた。
3
翌日の午後、竹吉は、義兄に連れられてやって来た。
おいさと一緒だと、おいさが帰る時に一緒に行くと泣くだろうと、家でおいさがしっかりと言い含めて送り出したそうだ。
顔立ちやほっそりした体つきは、おいさ、そして由吾郎に似ているといえば、似ている。
だが、今にも泣き出しそうな不安な表情は、気の優しい義兄譲りか。
竹吉は、奥の間で義兄と父が話している間、一言も話さない。
話しかけられても、頷くか、首を横に振るかで、俯いている。そうして、義兄の着物の袖をずっと握っている。
義兄は「私はそろそろ……。竹吉、こちらの皆さんの言うことをよく聞いて、いい子にしているんだよ」とやや後ろ髪引かれる様子で、袖を掴む竹吉の手をそっと離し、帰って行った。
竹吉は黙ったまま、義兄が帰って行った店のたたきの方をじっと見ている。
父が、顎で由吾郎に『なんとかしろ』と促す。
なんとかしろったって、本人がそうしていたいんだから、いいじゃないか、好きにさせておきなよ、と由吾郎は思う。
だが、再度父に促され、仕方なく、竹吉に近づく。
由吾郎は、「竹吉、おいで。私が昔使っていたものだけど、玩具があるから、見てごらん」と、竹吉に声をかけた。
竹吉は全く嬉しくなさそうな、仕方なくといった様子で由吾郎の後に続き、座敷に戻る。
そこで由吾郎が、「ほおら、これで遊んだことはある?」とか、「これはこうするんだよ」とか、玩具を並べて、年甲斐もなく、子ども用の玩具で遊んで見せる。
だが、全く竹吉は反応しない。
困り果てた由吾郎は、「そうだ、おやつがあるんだ。待っていてね」と、今度は菓子器にたくさん入った饅頭を取りに行く。
姉のおいさが大好きだと言っていた店の饅頭だ。
これなら喜ぶだろう、そう思って足早に竹吉の待つ座敷に戻った。
……これは。
竹吉は、由吾郎がいない間に座敷の奥に移動し、膝を抱えて座っている。
仮にも母の生家である。
もうちょっとくつろいでもよさそうなもんではないか。
しかも、玩具はさっき由吾郎が遊んで見せたままの状態で転がっている。
由吾郎は「ほら、お饅頭だよ」と、菓子器の蓋を開けて見せた。
だが、矢張り竹吉は黙ったままだ。
ちょっとだけ顔を動かして、菓子器の中の饅頭は確認したようだった。
そこへ、「ごめんください」と聞き慣れた声がした。
立太郎である。
天の助けとばかりに、由吾郎は「はい」と座敷から返事をし、店の入り口まで走って行った。
まさか、本当に来てくれるとは。
玩具のちゃんばらを携えて来てくれた立太郎が、とてつもなく凛々しく見えた。
「早速来てみたが、どうだ。仲良くやれているか?」
そうさわやかに訊ねる立太郎に、由吾郎は首を横に振る。
「私もね、乗り気ではないにしろ、もう少しどうにかなると思ってたんだよ。でも、どうにもこうにもねえ。本当にどうしたもんか……」
情けない顔で正直に答える由吾郎に、立太郎は笑った。
「まあ、お父ちゃん、お母ちゃんとずっと一緒の子どもが急に一人離れるのは、一大事だろうよ。全くけろりとしている子どももいるようだけれど、その子、その子で違うからなあ」
「それもそうだね。兎に角、来てくれて恩に着るよ」
「何言ってるんだ」と立太郎は笑う。
そうして、座敷の奥にいる竹吉に「おう。私は由吾郎の友達だ。一緒に遊ぶか」と、実に模範的な子への接し方をした。
うんともすんとも言わない竹吉が、やや警戒気味に立太郎を見る。
立太郎は、竹吉をひょい、と抱え、中庭に連れて行く。由吾郎は素早く竹吉の下駄を出してやる。
立太郎は、「ちゃんばらで遊んだことはあるか?」と、ひとつを竹吉に渡した。
立太郎は、もう一本のちゃんばらを、剣術の素振りの要領で振って見せ、「こうやって踏み出すんだ」と教える。
「やってみるか?」
竹吉が頷いた。
さっきから、玩具だの、菓子だので様子を見ていた由吾郎とは雲泥の差である。何とも情けない思いがする。
すると、「ほら」と、立太郎はちゃんばらを由吾郎に渡す。
「ええ、私かい?」
「そりゃあ、急に来た私より、由吾郎の方がやりやすいだろう」
「そんな、私だって、ついさっきだよ……」
そんなふうに言ったが、竹吉は思いのほか、やる気のようである。
ここで断っては、立太郎の厚意を無にすることになる。
「いいよ。遠慮はいらない。かかっておいで」
由吾郎はそう言って、ちゃんばらを大きくかざした。
「胴!」
思いのほかの素早さと力強さで、いきなり脇腹に攻撃を受けた。
しかも、胴って、ことは、剣術を真似ている様子だ。
大人しいと油断していたが、おいさ姉ちゃんの子である。
弱いわけがない……。
「あいたッ」
「おお、竹吉、やるじゃないか。道場に通うか?」と、立太郎は竹吉を褒め、竹吉もまんざらではない顔をしている。
その後も散々竹吉にちゃんばらで負かされ、由吾郎はへとへとになった。
立太郎は「じゃあ、またな」と、竹吉に視線を合わせ、頭を撫でて帰って行った。
竹吉はまだちゃんばらをやりたそうで、由吾郎は、もう番頭でも手代でもいいから、代わってもらおうと思った時、夕餉の準備ができたと声がかかった。
ああ、よかった、と由吾郎は安堵した。
夕餉の席では、竹吉の前にも大人と同じ量の膳が用意されていた。
「足りなかったら、言いなさいね」と、父も母も目尻を下げ、竹吉に言う。
竹吉は背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、肘を垂直におろすようにし、手は太ももの付け根と膝の間に指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座している。
そうして、皆が箸を取っても、竹吉だけはそのままである。
「竹吉、食べていいのよ」と母が言う。
「そうだ。竹吉のお母ちゃんは、それはそれはたくさん食べたからな」
「そうそう。お稽古の間にお団子やお饅頭をたくさん食べて、帰ってからもしっかり夕餉をいただいて」
父と母が竹吉の心を和まそうとしていたのは由吾郎でもわかる。
だが、これまで黙っていた竹吉が瞬きし、僅かに俯いた、と思った途端、うわあああああん、と家じゅうが震えるような声で泣き出した。
そのあまりの声の張りに、由吾郎は驚く。
腹の底から、という言葉を聞くが、正にこういうことを言うのだろう。
「どうしたんだい」
「どこか痛いのか?」
父も母も大慌てである。
「医者を呼ぼうか」
「まず水を飲ませましょう」
そんな二人を前に、由吾郎は竹吉の背をさすり、ちょっと泣き止んだ頃合いを見計らって、膳のさゆを飲ませた。
竹吉はそれでもおいおいと泣いていたが、そのうちに眠ってしまった。
その一連の流れを見ていた両親や女中が、竹吉は由吾郎と一緒がよかろうと勝手なことを言い出し、由吾郎の部屋に竹吉の使う布団を延べた。
竹吉を運んで布団に寝かせた後、親子三人でのいつもの夕餉に戻った。
「お父ちゃん、お母ちゃん、気持ちはわかるけど、竹吉は竹吉なんだからさあ。竹吉の話をしてやらないといけなかったんじゃないか」
「……それもそうだねえ」と、母がしんみりして言う。
「いや、おいさの子だからついな……」と、父も言う。
「おいさ姉ちゃんが今でも自慢でかわいいのはわかるけどさ、その話ばかりされる身にもなってよ」
つい、自身の心の内が出た。
父と母は顔を見合わせる。
「……そんなつもりはなかったんだけどねえ。おいさの前では、由吾郎の話をよくしているんだよ。なあ」
「ええ、そうですよ。『あの子は大人しくしているけれど、しっかりとしている』とか、『お商売のことも根気よく学んでいる』とか、『真面目な上に茶や歌詠み、お香の才もあるんだよ』とかね」
……私はそんなこと、面と向かって言われたことはないけどね。
そう思ったが、取ってつけたような言い方ではなかった。
案外とそういうものなのか……。
否、わからぬ。
「おいささまが恋しいのでしょう。それを我慢なさっていたところ、ふいにおいささまの話が出て、気が緩んだのではありませんか」
そう言ったのは、竹吉の膳を下げに来た女中であった。
三人は顔を見合わせる。
「それはそうだ……」
頷き合った後に、由吾郎は「その膳、一応、ふきんをかけて、私の部屋に運んでもらえるかい? あの様子じゃあ、夜に目が覚めても、誰かに『おなかが空いた』と言えないだろうからね」と声をかけたのだった。
4
翌朝、目が覚めると、ささささっと足音がした。
隣でばさり、と布団を被る音もする。
由吾郎は竹吉に気づかぬ振りをして起き、部屋を見る。
置いてもらった昨夜の膳は全て平らげてあり、ついでに菓子器の中の饅頭もなくなっていた。
狸寝入りをしている竹吉に騙された振りで、由吾郎は部屋を出る。
そうして、この分だと朝餉は入らないだろう、と由吾郎は思った。
……だが、澄ました顔をして出て来た竹造は、朝餉の席に着いた。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、肘は垂直になるようにおろし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指同士が向かい合うようにし、足の親指同士が離れぬように正座している。
そうして手を合わせ、「いただきます」と言った。
この家に来て、「胴!」と、由吾郎の脇腹を攻撃して以来、竹吉が口にした言葉であった。
ええ、さっきあれだけ食べたばかりなのに?
由吾郎の心配もなんのその、竹吉は朝餉をきれいに平らげた。
その様子を見て、父も母もほっとしたようである。
「竹吉、よかったら、遊びに行かないかい? 今日はこの近くで縁日があるんだよ」と、父が言い、母も「玩具やお菓子を買いましょう」と続ける。
竹吉は「はい、ありがとうございます」と答えた。
ああ、これでどうにかなりそうだ、と由吾郎は茶碗を手に思っていた。
「由吾郎、いつまで食べているんだ。お前も早く支度しなさい。竹吉と四人で出かけるよ」
「ええ、お父ちゃん、私も行くのかい?」
「当たり前だろう。竹吉が走り出したりしたら、私らでは追いつかないからね。それに竹吉はお前さんに懐いているんだから」
否、懐いてはいないよ……。
そう思ったが、口にはしなかった。
支度して、出かけよう、という時、「ごめんください」と声がした。
立太郎である。
「今日は昼から忙しいから、朝様子を見に来たんだ。竹吉は元気か?」と訊く。
そこへ、竹吉が走って来て、立太郎の袖を握った。
こういうのを懐くと言うんじゃないか、と由吾郎は思う。
そこへ、「あらあら、立太郎さん、昨日は竹吉を遊んでくださって、ありがとうございました。玩具まで買ってくださって」と、母が出て来て礼を言う。
「立太郎さん、よかったら、一緒に縁日に行かないかい? まあ、私らで出かけるから、そんなに足は伸ばせないが」
そう言う父に立太郎は「ありがとうございます。ぜひ」と、さわやかに応じる。
「いいよ。縁日の誘いなんて、ほかからいくらでも来ているだろう? 昼からも忙しいってのに、何が悲しくて、こんな年寄り夫婦に子どもと出かけるんだよ……」
そこで「由吾郎!」と父に一喝される。
「全く、つい最近まで、『お父ちゃん』、『お母ちゃん』てかわいい息子だったのに、こんな憎まれ口を叩くようになって……」
わざとらしくため息をつく母に、「かわいい息子って、由吾郎叔父さんのこと?」と竹吉が訊く。
こいつ!
私の名前も、叔父だってこともわかってたんじゃないか。
わかっていて、だんまりを続けていたってのかい?
子どもってのは、わかんないね……。
自身もまだ手習いを終えたばかりである由吾郎はなんとなく、腹立たしい気分になる。
「あははは、竹吉はよくわかっているなあ。聡い子だ」と、お父ちゃんが、竹吉が話したことを喜んで、竹吉の頭を撫でる。
「おじいちゃんとおばあちゃんは、年より夫婦なの?」
父の竹吉を撫でる手が止まる。
由吾郎は腹を抱えて笑った。
「竹吉はよくわかっているなあ」
「立太郎さん、遠慮しないで、好きなものを買いましょうね。憎まれ口を叩く息子には、自分で払わせましょう」と母が言い、歩き出した。
5
縁日の人込みの中で、普段から身体を鍛えている立太郎は軽々と竹吉を肩車してくれた。そのおかげで、道でやっている曲芸なんかも竹吉はよく見えて、大層喜んだ。
そうして、やはり親の財布だと、あれこれと食べ物やちょっとしたものなんかも、すぐに買える。
玩具やら菓子やらを買い、上機嫌の竹吉を連れて縁日を巡り、立太郎と別れて、店に戻る。
すると、店の入り口の前でほっかむりをした女がうろついている。
「お父ちゃん、あれはなんですかね?」
「さあて、なんだろう……」
目をすぼめる二人の横で、「あれ、おいさ姉ちゃんじゃないか」と由吾郎が気づく。
「ええ?」
「おいさ?」
それを合図のようにほっかむりの女が顔を上げる。
そうして、大きく目を見開く。
「竹吉!」
人目もはばからず、おいさはそう叫ぶと、大粒の涙をこぼし、ものすごい速さで竹吉に走り寄った。
……まるで、無理矢理引き離された子を見つけたおっかさんじゃあないか。
そっちが頼むから、面倒見たってえのに。
きょとん、とする竹吉をおいさは抱き締め、おおい、おおい、と泣いていた。
いやはや、何にでも秀でていると思っていた姉の最大の弱点は竹吉だったのか……。
離れて堪えられなくなったのは、おいさの方だったらしい。
「人騒がせな親子だよ……」
由吾郎は小さく呟いた。
6
「私はやっぱり帰るよ……」
ふかふかの座布団から、立太郎は腰を浮かす。
これで何度目か。
「ここまで来て、そんなことを言わないでよ。だいたい、立太郎が帰ったら、私一人になるじゃあないか」と、由吾郎が止める。
「だって、こんな豪勢な料亭、十二、三の私らだけで来ていいところじゃあないよ」
「向こうがお礼がしたいって、呼んでくれたんだ。ここで帰ると、別の何かを用意させなきゃあいけないじゃないか。それに立太郎は、こういうところは慣れているんだろう?」
「慣れるって、たまにお父ちゃんたちと来るくらいだよ。それに、由吾郎にとってはお姉さんの嫁ぎ先だけど、私はそうじゃないんだからさあ」
「兎に角、座って」と、由吾郎が立太郎を押しとどめる。
ここは、おいさの嫁ぎ先の料亭である。
先日竹吉の面倒を見てもらったから、義兄がぜひにと、立太郎と由吾郎を店に呼んでくれたのだ。
しかも十畳ほどの完全個室の部屋に、由吾郎と立太郎の二人きりである。
豪勢な襖絵が、そわそわと二人を落ち着かなくさせている。
「失礼します」と言うお運びの声がし、「ほら」と、二人は正座をし直す。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬようにする。
さすがに酒は出ぬが、豪勢な膳に二人は目を見張る。
そうして、お運びと入れ代わりに、義兄が顔を出す。
「先日はありがとうございました。ささやかですか、お礼ですので、遠慮せず召し上がってください」
「とんでもありません」と、立太郎が恐縮する。
「ほら、竹吉、お礼を言いなさい」
義兄に促され、「失礼します」と、大層礼儀正しい声がする。
部屋の入り口で竹吉が座礼し、中へ入る。
そうして、「この度は、大変お世話になりました」と大人びた口調で礼を述べる。
「竹吉、そんなにかしこまらなくても」と、由吾郎は慌て、「そうだよ。竹吉、また今度遊ぼうな」と立太郎が声をかける。
そこで、「うん」と竹吉は頷いた。
「本当に竹吉は立太郎が好きだからなあ。助かったよ」と、由吾郎が笑う。
「本当にありがとうございました」と義兄が再び礼を言い、「どうぞ、ゆっくりしてらしてください。竹吉、行くよ」と、竹吉を促す。
すると、竹吉はつつつ、と走り、由吾郎の膝に乗った。
小さいながらに重みのある感触に、由吾郎は少し驚く。
そうして、ぱっと立ち上がると、そのまま部屋を出て行った。
「これ、竹吉」と、義兄も部屋を出る。
「すっかり懐かれたな」と立太郎が言い、箸を取る。
「え?」と、言う由吾郎に、「気づいてないだけで、由吾郎は老若男女問わず、好かれるんだ。お商売をする上でこの上ない素質だ」と、立太郎は答えたのだった。

![[301]お江戸正座10](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)