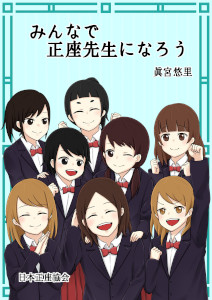[257]合歓の木の根元で正座
 タイトル:合歓の木の根元で正座
タイトル:合歓の木の根元で正座
掲載日:2023/06/03
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
七葉(ななは)と樹馬(いつま)は、物心つかないうちから避暑地の別荘の周りの森で仲良く遊ぶようになり、樹馬がネムノキの樹の下で「正座のお稽古」を七葉に教える。
ある夏、樹馬の姉の千夏が来るが、あまりしゃべらず神秘的。
何年かして、ふたりもじゃれあう年齢ではなくなった。
都会に戻った七葉に、樹馬の家から彼がバイクの事故で亡くなったという知らせが来る。


本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序章
初夏の陽の光は容赦ない。
ぎらぎらとして、盛夏も暑さ厳しいことを予感させる。
帽子のツバに手をやって太陽を見上げるが、ジリジリと灼熱に溶けそうだ。
彼方に見えるのは蜃気楼のように揺らぐ街。
合歓(ねむ)の大木の根元にだけ、ひんやりとした窪みに木陰がうずくまっている。
合歓の枝には、薄紅色の糸状の花が蝶のように群れ遊び……。
第 一 章 避暑地の遊び相手
七葉(ななは)の家族は夏になると、避暑地の別荘で夏を過ごすのが毎年の決まりになっていた。
物心がつかないうちから、両親と木立の深い避暑地の別荘に滞在するのだった。別荘は周りに他の建物も少なく、静寂そのものだ。
一キロほど離れた場所に、一軒だけ別荘がある。石造りでかなり古さを感じる。
七葉は、その別荘に滞在する親子と顔見知りになり、同い年の樹馬(いつま)という少年と遊ぶようになった。
ふたりになると退屈だった森は、がぜん彩りを増し、涼しい木陰や小さなせせらぎに膝まで入って、サワガニと戯れたりした。
やがてセミが鳴きはじめると、樹馬は虫取り網を持って木々をめぐり始めた。
七葉はセミが怖くて見守るだけになってしまうので、セミ採りが好きではなかった。しかし、樹馬が捕獲したセミを必ず放してやるのを見て、
(優しい子なんだな~~)
と思うことがよくあった。
学校の男の子たちみたいに粗野ではないし、おままごとにも付き合ってくれるし、七葉は樹馬が好きになっていく。
かなり高い大きな樹が、ふたりの遊び場の中にあった。なんていう種類の樹なのか分からなかったが、樹馬が植物図鑑を持ってきた。
「これだよ!」
樹馬が図鑑の一ページを指さした。
細かい葉のついた中に、淡い紅色で糸状の花がたくさん咲いている。
「ネムノキの花っていうみたいだよ。夕方になったら葉っぱが閉じるって」
「そういえば、おうちに帰る頃、葉が閉じるわね。香りも書いてある通り甘い匂いだし」
ネムノキ(合歓の木)は、大きな木陰を作ってくれて緑一色の世界の中で、かっこうのままごとの場所だった。
大木から森へは同じような巨木が連なっていて、昼もなお薄暗い。
爽やかな風が吹き抜け、走り回った後もほっと息をつける。
いつものように休憩していると、樹馬は「正座」という座り方を教えてくれた。
「ほらね、こうして真っ直ぐに立つだろ。それから、草の上に膝をついて、あ、七葉ちゃんはスカートの裾をお尻に敷いた方がいいよ。そして、かかとの上に座るんだ。そうすると、きれいに座れるだろ?」
「知ってるわ、この座り方。畳のお部屋ではそうしてお座りするもの。親戚のおうちに行った時も、こうやってお座りするわ」
「へえ、七葉ちゃん、お行儀いいんだね」
「お母さんの前でだけネ」
七葉はペロッと舌を出してみた。樹馬は応えてにっこり笑う。
ネムノキの前の草地に正座する七葉は、ご機嫌だった。
幼いふたりはそんな夏を毎年過ごしていたが、ある夏、高校生くらいの少女が樹馬と共に現れた。
第 二 章 千夏
七葉はいつもの木の下の闇で待っていたが、思いがけない少女の出現にびっくりした。
長い髪を上半分だけまとめて水色の小花柄のワンピースを着ている。
「お姉ちゃんなんだ。千夏っていうの」
「お姉ちゃん? 樹馬くん、一人っ子だと思ってた」
「あんまり、こっちには来なかったからね」
七葉は本当に驚いた。
「お姉さんは千夏さんておっしゃるのね。わたし、七葉です」
七葉が恥ずかしそうに挨拶しても、千夏は言葉少なに返しておいて、木陰に正座して早々と持ってきた本を広げて読み始めた。
(なんだか神秘的なお姉さんだな~~)
長い髪といい、笑顔を見せないところといい、樹馬と仲がいいのかどうかも分からない。
しかし、三人で正座のお稽古をする時には、千夏は瞳を輝かせて、まったく違う人間のようにいきいきとしてふたりに教えた。
千夏自身の座り方の所作もきびきびとしていた。七葉が少しでも所作を間違えると、ピシリと教える。
ある日、いつも愛読書を小脇に抱えている千夏が持っていなかった。
「樹馬、いいわね?」
それだけ言うと、先に立って木陰の濃い山道を谷へ降りていく。
(どこへ行くのだろう?)
七葉はふたりに気づかれないよう、離れてついていった。
やがて谷川の奥に、注連縄(しめなわ)のかけられた洞穴へたどり着いた。
アゴに白いひげを生やした老人が待っていた。藍色の作務衣のようなものを着ている。素早く木の幹に隠れた七葉には気づかない様子だ。
(誰―――?)
白いアゴひげの老人は千夏と樹馬を連れて、足元の湿っぽい洞穴の奥へ消えていった。後を追う勇気まで出なかった。洞穴からは、木の下闇よりもっと冷たい風が吹いてきた。
翌日には、千夏と樹馬は何ごともなかったように、いつもの木の下闇で座っていた。
(あのお爺さんは誰?)
尋ねる勇気は出なかった。
そんな夏が何年続いただろう。
やがて七葉と樹馬も、子供の頃のようにじゃれあって過ごすことはなくなり、なんとなくよそよそしい空気まで漂っていた。
七葉も高校生の夏を迎えた。
樹馬と千夏で正座のお稽古をしていた木の下へ行こうとすると、幹に背中をもたせかけたふたりの人影が見えた。
ひとりは樹馬だ。久しぶりだったが、子供の頃の面影が濃く残っている。つぶらな瞳や濃いまつ毛、鼻筋が樹馬だ。もうひとりは見たことのない女の子だ。
―――樹馬の長いまつ毛や鼻すじは、少女の頬に寄せられている?
胸に焼きごてが押しつけられたような衝撃。胸が苦しい。
―――樹馬がキスしている? 知らない娘と!
七葉は慌てて、昔、洞穴の老人を見た時のように幹の裏側に隠れた。
第 三 章 突然の哀しみ
逃げるようにしてその場を離れた七葉は、別荘に帰るなり部屋にこもった。ベッドにうつ伏せになったが、さっき見た光景がまざまざとよみがえる。
身をひるがえして走り出す時、樹馬がちらりとこちらを見たような気がする。
樹馬が、オフホワイトのポロシャツにハイソックスを履いていた可愛かったあの子が、知らない娘と!
枕を頭の上から被せても残像は去らない。鼓動は高まるばかりだ。
(どうしちゃったのかしら、わたし……。心がちぎれてしまいそう)
強風にあおられたカーテンがバサバサと乱れた。
別荘から都会の自宅に帰った。
新学期が始まったというのに、七葉は勉強にも身が入らないありさまだった。
学校から帰宅すると母親が真っ青な顔で迎えた。
「七葉。気を確かに持って聞くのよ」
「ど、どうしたの、お母さん」
嫌な予感がした。
「樹馬くんがね。毎年、夏に別荘に行く度にあなたが小さい頃から遊んでいた樹馬くん……。夕方、バイクに乗っていて事故を起こして――」
「……」
「避暑地でバイクに乗っていて……、亡くなったというの」
「や、やめて、お母さん、信じたくない!」
耳をふさいでしゃがみこんだ。
七葉はどうやって彼の家へ向かったのか記憶が飛んでいる。多分、父親の運転する車で自宅でのお通夜にうかがったんだと思われる。
なぜか遺影を前にすると頭がクリアになって、子供の頃、樹馬が教えてくれた正座の所作を間違えずにして、大きくなった征服姿の遺影に向かって手を合わせた。
(そうだ、千夏さん……)
千夏のことを思い出した。涙にくれながら弔問客の応対をするご両親の姿はあったが、斎場のどこにも千夏の姿は見当たらなかった。
樹馬の母親が、そっと七葉を二階に呼び出した。
「七葉ちゃん。小さい頃からあの子と遊んでやってくれてありがとうございます」
面影のよく似た樹馬の母親は、七葉の手を両手で包み、伏し拝むようにした。
第 四 章 再会
次の夏がやってきても、七葉は避暑地に出かけるのさえ辛くなり、何年か足が遠のいていたが、母親が慰めた。
「七葉にとって辛いのは分かるけど、大切な思い出の場所でもあるでしょう? 樹馬くんもあなたに元気を出してほしいと思っているわよ、きっと」
ようやく七葉は、別荘へ行く気になった。
別荘は少々痛んでいた。樹馬の一家が住んでいた別荘は、空き家になって荒れていた。
テラスは枯葉の吹き溜まりになってしまっていた。ここでもよくおままごとをしたというのに。
陽ざしが強い。昔、子供三人で正座のお稽古やおままごとをした合歓の木の根元へ行ってみる。ちょうど開花の時期で、水鳥が羽根を広げたような薄紅色の花を咲かせていた。
下草が緑色にびっしりと生えて美しい。樹馬はよく、ここで正座を教えてくれたり大の字に寝転んだりしたものだ。
大人の女性が忽然(こつぜん)と森の中に立っていた。千夏だ。
長い丈の優雅なワンピースを着てストレートの腰まである髪の毛を垂らした姿は、すっかり大人だ。
「七葉さん、しばらくだったわね。きれいになって。今、大学生?」
「はい。ご無沙汰してました。千夏さん」
「こちらへおいでなさい」
千夏は若い緑の地面に誘った。
「木陰で気持ちいいわよ。ここに、昔のようにお座りになってみて」
「正座ですか?」
「ええ。所作の順序、覚えておられるかしら」
「はい」
七葉は、樹馬に教えてもらった順序で正座した。
言われた通りにした時、陽が蔭(かげ)って、森はもっと暗くなり、いつの間にか傍らに若い男性が立っていた。
「……い、樹馬くん?」
あまりに驚いたので息をするのも忘れたほどだ。間違いない。子どもの頃の面影そのままに、すっかり青年になった樹馬だ。オフホワイトのサマーセーターを着ている。
樹馬が側に正座した。昔の所作だ。
「驚かせてごめん。僕は生きているんだ。ほら、まぼろしでもなんでもない。生きてるだろう?」
樹馬の大きな手が七葉の白い手を包んだ。
温かい手だ。樹馬の顔にも葉の影が映り明るい緑色に見えるが、手は温かく本物だ。優しいまなざしも本物だ。
「生きてる――、生きてる! 本物の樹馬くんだわ!」
両手を樹馬の首に回して抱きしめた。七葉の両目から吹き出るように涙がこぼれた。
「どうして――、どうして――、本当に?」
「本当だよ。もうどこにも行かない。七葉の側にいる」
額と額をくっつけ、唇を重ねた。
(樹馬くんの香りだ――)
夢見心地で気を失いそうになった。
第 五 章 明かされた秘密
三人はようやく落ち着いて木漏れ日の中に座った。
「悪かった。驚かせたね」
樹馬が微笑みかけ、七葉もようやくすすり上げていた涙を止めた。
千夏も穏やかに見守っている。
「心配かけて悪かった。すべて話すよ」
樹馬が話すには、十八歳になったら亡くなることに見せかけて、正座を存続する一族の長になることが決まっていた。幼い頃から正座の奥義を洞穴の奥の長老に習いに行っていた。そのための避暑でもあったというのだ。
「でも、決められた人生がイヤで、バイク仲間と遊んだりしたんだよ。反抗期ってやつ」
「あ、あの時の知らない女の子とも?」
思わず、目撃したキスの相手のことを聞いてしまった。
「バイク仲間の子だよ。つい、イライラしてしまって」
樹馬は頭を掻いた。見られたことを承知している風だ。
「樹馬くんのご両親も、正座の一族のことを?」
「知ってるよ。そのことを踏まえて養子として育てられたんだ。実の親は山の洞穴の向こうに住んでいるらしいが、会ったことがないんだ」
「まあ……」
「七葉ちゃん、私はね」
長い髪を肩から背中へ投げて、千夏が話しかけた。
「正座を存続する一族の者なの。樹馬が外の世界で無事に育てられるかどうか、見届ける役目についていたの」
「それで、お姉さんだということにして……」
「ええ。その通り」
「正座を存続させる一族って何なんですか」
不思議そうに眼を丸くする七葉に、千夏は軽く笑い、
「怪しい団体じゃないわよ。そうねえ、言ってみれば平家の落ち武者が築いたみたいな村だって例えればいいかしら。山深く、洞穴の向こうに正座を厳しく守り通してる人たちが昔から住んでいるのよ」
「七葉」
樹馬があらたまった表情で話しかける。
「僕からお願いだ。もうしばらく時間をくれないか。一緒に過ごすには、やらなければならないことがあるんだ」
「さっき、これからはずっと一緒だって言ったじゃないの」
唇を尖らせた。
「申し訳ない。一族内部で反乱が起きているんだ。反乱の輩(やから)の正座の規則はいかがわしい。男は大金を、女は大金と髪を差し出さなければならない。この反乱分子を抑えるために、僕は一族のところへ戻る決心をしたんだ。七葉、君と出会ったから」
「わたしと出会ったから?」
「うん。七葉の正座からは清らかさを感じるからね。そういう正座を伝承していかなくちゃならないと思ったんだ」
「子どもの頃から樹馬くんから正座を教えてもらったからよ。ネムノキの木の下闇で。緑の風が吹き抜ける木陰で。私の一番大切な思い出だわ」
「そう。僕にも大切な思い出だ。クローバーの上で、正座のお稽古したり寝ころんだりしたよな」
「そうね」
「だから、その思い出を守るために、反乱分子を鎮めなければならないんだ。その間だけ待っていてほしい」
樹馬の魂にウソはないことを、七葉はよく知っている。
「分かったわ」
「会いたくなったら、あの、木の下闇で待っていてくれれば戻ってくるから」
「約束よ」
七葉は、樹馬の腕を握りしめた。
第 六 章 捕われの身
樹馬に会いたくなった七葉は、ある昼下がり、彼にメールを送り、木の下闇で待っていた。そうすれば木立の奥から樹馬が来るはずだった。
今日はなかなか現れない。
いきなり、ザザザッと草を踏み分ける乱暴な足音がした。
「あ、あなたたちはっ?」
得体の知れない男たちが数人現れて、乱暴に押さえこまれて目隠しされ、口に布を咬ませられた。――気が遠くなった。
後ろ手で縛られた縄をゆるめられ、意識が戻った時に、やっと判った。荒々しい正座をする反乱分子に捕えられてしまったのだ。
目隠しとさるぐつわを外された場所は、古ぼけて散らかった小屋の中だった。スーツを着た数人の無表情の男が取り囲んでいる。
「お前を、我ら新しい勢力の頭にする。否でも務めてもらう。樹馬に対抗できるのはお前の正座しかない」
つり上がった眼の男が言う。
「どうしてわたしが、そんな務めを」
「お前の正座には人を惹きつける力が見えるからだ。人々を魅了しなければ、我らは勢力を増すことができない」
「樹馬くんの言っていた荒々しい人たちね! いったい何を企んでいるの?」
「……」
「伝統ある正座の流派を乱して、どうしようっていうの?」
「正座……。はん、正座なんぞ我らには勢力を持つ手段にすぎない。どうでもいいことだ」
「何ですって、そんな身勝手なことに正座を使うなんて。樹馬くんが継承してきた、大切な正座を利用するなんて、ひどい人たち!」
「お前は言われた通りに、合歓の木の根元で大衆に正座をしてみせればいいのだ。花が満開になった時に」
「合歓の木の根元で?」
七葉の頭の奥に淡い紅色の花――夕方になれば閉じる細かい葉の様子がよみがえった。樹馬との大切な思い出の場所である。
「いやよ。誰があなたたちの言うとおりなんかするものですか」
七葉は顔を背けた。
「なかなかはねっ返りのお嬢さんだ」
目のつり上がった男が苦笑した。
「今の正座の流派と樹馬がどうなってもいいのか?」
「……」
「どうなってもいいのかと、きいてるんだよ」
七葉の唇が噛みしめられた。
「……言うことをきかなければどうなるって言うのよ」
「こんな持って回したやり方はしないで、力にものを言わせて古臭い流派をつぶすまでだ」
男が吐き出すように言い捨てた。
「なんてことを……。そんなことをすれば、あなたたちの評判が地に落ちるだけよ。いったい目的は何なの」
「決まってるじゃないか。集めた人間たちから金を巻き上げるんだよ」
「――なんてことを! 礼儀正しい正座をそんなことに利用するなんて!」
「お金持ちのお嬢ちゃんに何がわかる? あんただって、別荘を持ってるような生活に慣れきってしまってるんだ。いざ、金がなくなったらどうするつもりかな?」
「見くびらないで。私だって生きていけるわ」
「親にぬくぬくと育てられたお嬢ちゃんが世間にひとり放り出されて生きていけるわけないんだよ。だから、俺たちの言うことを聞きな」
男はナイフを出して、七葉の目の前にひらつかせてみせた。
「命令に従わないと、樹馬の命の保証はしない」
残忍な眼の光が冷たく光った。
合歓の木の根元に、谷から樹馬は急いで走ってきた。
しかし、七葉の姿はどこにもない。草地が多数の靴で踏みにじられ、乱れた跡がある。木の根元にスマホが落ちていた。
「七葉のだ!」
樹馬の顔色が変わった。
第 七 章 正座で平静を
「七葉が奴らにさらわれた!」
洞穴を抜けた世界の座敷に戻るなり樹馬が報告したので、老人と千夏は驚いて側によってきた。
「何ですって、証拠は?」
「もう、やつらからメールが届いている」
樹馬が手を開いて見せたスマホから、
『娘は預かっている』と受信がある。
「見張りをつけておくべきだった! 両親の元だし、避暑地の警察にも別荘の警備を頼んでおいたしと……油断していた僕がバカだった」
樹馬は呻いて柱にこぶしを打ちつけた。
千夏が彼の肩にポンと手を置いた。
「こんなこともあろうかと、私が見はっていたわ」
「えっ?」
「樹馬は、どうも考えの甘いところがあるから。あんたの大切な娘が避暑地に来ていると分かったら、あいつらは狙うに決まってるじゃないの」
千夏は頭をそびやかした。
「千夏!」
「大丈夫よ。あいつらには七葉さんが必要なんだから乱暴なまねはしないわ。彼女だって案外しっかりしているわよ。だから、スマホを落としたのは偶然だったけど、そのままにしておいたの。あっちと連絡が取れるでしょう」
「千夏、それにしても危ない賭けだ。七葉は女の子なんだぞ。もしものことがあったら……」
「落ち着きなさい、樹馬」
「千夏の言うとおり、落ち着くのが一番だ」
それまで黙っていた長老が口を開いた。
「お前は日頃から何のために正座をしている?」
「!」
長老の言葉に、樹馬はハッとした。すぐに床の間の前に移動すると、しっかりした所作で正座して目をつむった。
「それでこそ、正当な作法を継承してきた新しい師だぞ、樹馬」
樹馬はしばらく正座していた。轟いていた鼓動がだんだん静かに整ってくる。
最初は男たちに囲まれて恐怖に歪んでいる七葉の顔ばかりが思い浮かんだが、その想像を頭を振りはらって正座に集中した。
ネムノキの花が満開になった場所で、花柄のワンピースを広げて正座している七葉の姿が浮かんでくるようになった。
(助けてやるからな。七葉)
千夏がやってきて隣に正座した。
「やつら、告知したわよ。〇月〇日、十六時、町の丘にある合歓の木の古木の前に集まるように、市民に呼びかけたわ」
「なにっ、ついに!」
千夏からスマホを奪い取るようにして見てみると、町の中央にあるシンボルの合歓の木の写真が写っていた。
第 八 章 七葉、洗脳される
市民に発信された言葉は、
『心豊かになる正座をお教えします。町のシンボル、丘の上の合歓の木のところで、皆さん、正座して集い(つどい)ませんか』
樹馬、千夏、長老は、じっとパソコンの画面を見つめた。
「運営資金の寄付と称して、入門者から金を巻き上げるつもりじゃ。こんな平和そうなうたい文句では、市民はうっかり入門してしまうぞ」
長老がうなる。千夏も真剣な顔でうなずく。
「七葉さんが利用されると思うわ。団体には、象徴的な存在が必要ですもの」
「七葉が利用されるだって? 千夏」
「あんなに若くてきれいなんだもの。シンボルに使わない手はないわ」
「しかし……」
「もう少し正座してじっとしてらっしゃい、樹馬。当日まで一週間あるわ」
「一週間もこんな気持ちでいろって言うのか? 無理だよ!」
千夏の手から、ポンと手のひらにスマホが渡された。
「七葉さんとテレビ電話できるわよ」
「ええっ?」
スマホのあちら側に七葉が写っている。
「七葉! 大丈夫か、どこもケガはないか?」
夢中で叫んだ。
スマホ画面の向こうの少女は、長い髪を優雅に結い上げられ、化粧されていた。化粧した七葉を見るのは初めてだ。大人びて美しいが、いつもの伸び伸びとした愛らしさがない。
「樹馬くん」
七葉は取り乱しもせず、樹馬に話しかけた。
「わたし、正座の新しい流派に賛同してしまったの。話を聞いているうちに、もっともだと思うようになったの」
「え?」
「今の日本は、心の痛むことばかり毎日起こっているわ。それはすべて、人間のストレスから来ている。いらいらする人たちばかりが問題を起こしているでしょう? そして自我欲にばかり憑りつかれて」
「……」
「新しい正座の流派は、少々厳しいところもあるかもしれないけど、力強い正座をしてストレスに打ち勝つように指導しているのよ。今までの生ぬるい古い教えではダメ」
「七葉!」
「だから、今度の丘の上の集会にも、シンボルとして参加して協力するつもりよ」
七葉は立ち上がって袖をひらつかせた姿を見せた。奇妙な着物姿だ。古代の民族衣装のような打掛を着ている。樹馬は愕然とした。
「そんな恰好をさせられて……。君は洗脳されてるんだ!」
「洗脳じゃないわ。樹馬くん、あなたも考えを改めるためにぜひ、来てね。待ってるわよ」
「七葉!」
画面は真っ黒になった。
樹馬も、千夏も長老もしばらく黙った。
第 九 章 ふたりの合歓の木
七葉の行方が知れないまま、その日が来てしまった。
丘の合歓の木の根元で正座の新しい一派が、人々に呼びかけて集会を行う日だ。
呼びかけは反響があったようで、当日、かなりの人が丘に集まった。
千夏も市民にまぎれて丘を目指した。
(樹馬も来ているはずだけど、朝から姿が見えないし、どうしたのか)
丘の上には、樹齢を重ねた合歓の大きな木が植わっており、市民の誇りにもなっていた。ちょうど花の時期で、淡い紅色の花がたくさん咲いている。優しい繊細な花で日没になると葉は閉じられる。
呼びかけに百人以上の市民が集まっただろうか。皆、正座見物に来たくらいの気持ちなのだろうか。
黒塗りの車がやってきて、作務衣を来た男たちが数人、降り立ち緋色の毛氈(もうせん)を広げた。
男がひとり、マイクを握って合歓の木の前に立った。
「皆さん、本日はお忙しい中、我が合歓の木正座の集会にお集りいただきまして、ありがとうございます。代表代理の者です」
人々は物珍しそうに聞いていた。
「皆さま、江戸時代の初めから本格的に始まったと言われる正座という座り方ですが、改まった席でお決まりのようにしておられることでしょう」
男はマイクを握りなおし、
「正座にも所作があり、正式な座り方があることはご存じでしょうか。日本の作法の中に組み込まれています。今日は皆さまの前で正式な所作をお見せいたします」
男は部下に合図を送り、手下が車の後部座席から手をとってひとりの女性を助け下ろした。それは、民族衣装のような見慣れない純白の打掛を着て、髪の毛も優雅に結い上げた七葉だ。
「七葉さん!」
千夏は思わず小さく叫んだ。隣に立っていた長老が、
「あれが、樹馬の幼なじみの娘なのか?」
「ええ、そうです。すっかり新しい輩になってしまってますね」
「この状況をどう思っているのじゃろう。本当に洗脳されてしまったのかのう」
七葉が皆の前に立つと、民衆に大きなどよめきが起こった。なんとも清らかな美しさにため息が出たのだ。
「今から、この娘が正座をします」
男がマイクで言い、七葉が一歩前へ出て、立ったまま深々とお辞儀をした。
背筋をまっすぐにし、緋色の毛氈の上に膝をつき、着物をお尻の下に敷いてかかとの上に座った。
まるで純白の孔雀(くじゃく)が、正座したように美しい。
民衆からもっと大きいため息が湧きおこった。
「なんと優雅なんでしょう」
「おしとやかな……」
「これこそ、日本人らしい正座の所作ですわね」
民衆の反応が良いことを見てとった男は、
「いかがです! 皆さまもこのように美しい正座の所作を身につけられませんか? 正座は日本人の誇りです。本格的な所作を身に着ければ誇りになります」
七葉が正座したまま顔を上げた。
陽が傾きかけ、金色のかんざしに反射した。淡い紅の花々が艶やかに咲く前でいっそう美しい。
「あんなにきれいな所作ができるなら習いたいわ」
ひとりの女性がもらし、人々も口々に、
「私も習いたいわ」
「僕も、武道やってるから先生に褒められそうだ」
マイクを握った男は、にやりとした。
「合歓の木正座教室参加ご希望の方は、本日ただいまより受付開始します。本日中なら入会金免除させていただきます!」
人々はまたざわめいた。
「今日じゅうなら入会金免除ですってよ!」
「まあ、我が家は来月に娘のお結納なのよ。美しい所作ができて損はないわね!」
入会希望の申し込みが、用意されたテーブルで始まった。
一部始終を見ていた千夏が、やれやれという風に肩をすくめた。
「あ~~あ、皆さん、申し込んでしまうと容易に脱会できないことが分からないんだわ」
「脱会するには法外な代金を取られるんだったな」
「そうなんですよ、長老。入会している間は、とんでもない額の寄付金を強要されるそうです。正座を習うのに大金なぞ必要ありませんわ。普通のお作法教室のお月謝の相場でいいのです。それなのに」
「樹馬はどこへ行ったかな」
「さあ」
マイクを持った男が、また話し出す。
「さあ、今から合歓の木代表の七葉さまが、丘の合歓の木の精霊に誓いを立てるために黒髪を奉納いたします」
千夏と長老は、ぎょっとして七葉に目を戻した。
七葉は正座したまま、作務衣の男に結った髪を解かれた。つやつやした黒髪が背中に広がった。
「七葉さん、女にとって大切な髪を怪しい集団にささげていいの?」
千夏が思わず口走った時、車からもうひとりの作務衣の男が飛び出してきて、正に黒髪に当てられようとしている剃刀(かみそり)の手を蹴り上げた。剃刀は夕空を高く舞っていった。
「七葉!」
振り向いた七葉は、剃刀を蹴った男――樹馬を振り向き、すがりついた。
「樹馬くん!」
「七葉、間に合って良かった!」
七葉は純白の打掛を脱ぎ捨て、樹馬と手を取りあって丘を駆け下っていく。
「女を逃すな! アジトを知られている!」
男が叫んだが、手下の男たちの前に、逞しい男たちが立ちはだかってふたりを逃した。
「樹馬、七葉さん、こっちよ!」
千夏が丘の下に用意しておいた車にふたりを乗せて発進した。丘の上の合歓の木が後ろに遠くなり、夕焼けに包まれていく。
「入会した人たちはどうなるの?」
七葉が少し震えながら洩らした。
「どうせ最初から正座を金もうけの手段にしようとしていた輩だ。ちゃんとした所作が身についていない。やつらの計画は大失敗だ。もう、二度と人々も集まったりしないだろう」
「そう、そうね」
ふたりと千夏は、避暑地の近くまで来て車を降りた。辺りはすっかり夕闇に包まれ、町に明かりが灯り(ともり)始めている。
「七葉、無事で良かった」
樹馬は力いっぱい抱きしめた。
「怖かったけど、頑張ったわ」
「あなたたちったら、知らない間に脱出の手筈を打合せしたのね」
千夏がいたずらっぽく睨んだ。
「七葉を敵の中に置いたまま、指をくわえて見ているわけがないだろ、千夏」
「わたしがあの輩から、そっと端末を奪ったんですよ」
七葉が打ち明けた。
ふたりは幼い頃の合歓の木の根元まで歩いて来て、草地に正座して合歓の木に頭を下げた。それから顔を見合わせて微笑んだ。