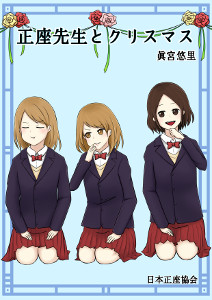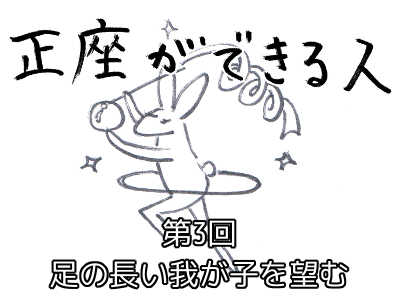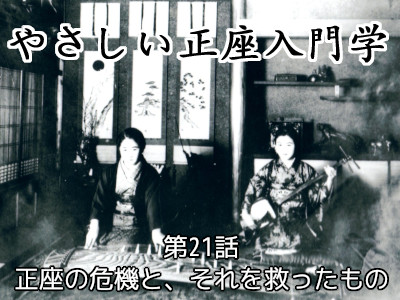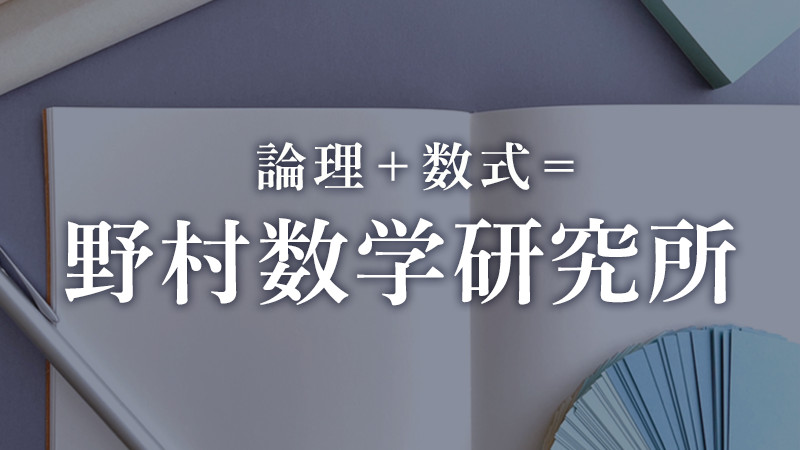[378]お江戸正座32
タイトル:お江戸正座32
掲載日:2023/09/14
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:32
著者:虹海 美野
あらすじ:
材木問屋の娘、おいさは生まれた時から食欲旺盛だ。お琴やお茶、書と習い事三昧の日々を過ごし、どれも師から褒められる出来である。
そこで力を出すからと、おいさは三度の飯以外にもあちこちの店で腹ごしらえをする。
ある時、遠方で見つけた飯屋においさがどうしても入ると言う。
職人ばかりが客の店を前に、お付のおきのはおいさを止めるが、おいさは店に入る。この店の味が気に入ったおいさに、店の板前はある料亭を紹介し……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
おいさは材木問屋の娘である。
おいさが最初の子で、弟が生まれたのは、おいさが十一の時だった。
おいさのお母ちゃんは大層な器量よしで、お父ちゃんがお母ちゃんがほかの人と一緒になる前に、と急いで祝言を挙げたと聞いたことがある。
だから、おいさはお父ちゃんが若い時の子であった。
家業の材木問屋も順調で、おいさはずいぶんと可愛がられ、まだまだ若い祖父母にも大事にされて育った。
身内は当初気づかなかったが、おいさは非常によく食べる子であった。
ああ、この子はよく食べて、そのおかげか風邪一つ引かない。いい子だ、と周囲の大人はそれを喜び、これを食べてごらん、あれも美味しいよ、今度はそれをあげてみようと、いろいろな滋養のあるもの、美味しいもの、高価なものを幼い頃からおいさに食べさせた。
そうして、おいさはそれを実においしそうに、残さずに食べた。
何せ大きな店で大人ばかりに囲まれた家の一人娘だったので、周囲の幼い子がどれほど食べるか身内はよくわかっておらぬ。とにかく、元気によく食べることを喜んだ。
おいさは、食べた分だけどんどん大きくなる、ということはなかった。
背丈も体重も、おおよそ、平均的であった。
だから、長いこと、身内はおいさがよく食べることを喜びはすれど、ほかの子に比べ、とんでもなく食べる子だと気づかなかった。
久方ぶりに雇った丁稚の男の子が、おいさより四つも年上なのに、食べる量はおいさよりもはるかに少ない。「遠慮しないで食べなさい、子どもはたくさん食べて大きくなるもんだ」と、おいさの祖父も父も言った。「ありがとうございやす。奉公先でもっと食っていいなんて言ってもらえて、涙がでるほどありがたいです。だけど、これ以上は腹がいっぱいで。明日、またどうか食わせてください。精いっぱい働きます」と、丁稚は涙ぐんで感謝するばかりである。
ここでふと、おいさの祖父と父は顔を見合わせた。
雇った丁稚が食の細い子なのか……。
通いで来ている女中に訊いてみるが、首を傾げ、「うちの長屋にも子どもは何人かいますけど、ここの丁稚に出しているのより食べる量は少ないですよ。それでみんな、元気に走り回っております」と言う。
「そういえば、あんただって子どもの頃、そこまでは食べなかった」と、おいさの祖母が思い出しておいさの父に言う。
誰に似たのか、と家族は顔を見合わせた。
おいさのお母ちゃんも、その家族も少食だと言う。
そうして、おいさが十一の時に弟が生まれたわけだが、この弟も少食であった。生まれたばかりの時から食が細いので、産婆さんにも医者にも診せたが、「一体何が心配なんですか」と首を傾げられるばかりであった。
おいさの弟も、丁稚も少食ではなかった。
おいさが大食いだった、と気づくまで、ずいぶんと長い年月を要した。
その頃にはおいさは、手習いを終え、毎日習い事三昧の日々を送っていた。
裕福な家の子だから、歌も踊りもお琴もお三味線も書もお花もお裁縫も習った。かなり忙しい日々だが、おいさはどれも真面目に取り組み、また筋もよく、どの師にも大層褒められた。
おいさは所作の教室にも通っていたので、しごく、行儀もよかった。
習い事の前後には、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座し、「本日もよろしくお願いします」、「ありがとうございました」と手をついて座礼する。
よくできたお嬢さんで、と言われるのは、もうあいさつと同じくらい自然に向けられる言葉であった。
だが、お付のおきのは、尋常でないおいさの食欲にいつもはらはらしていた。
習い事が済むと、おいさは必ずどこかで腹ごしらえをする。
先ほど昼餉を召し上がったのに、と思うが、おいさに言わせると、お稽古に集中すると、その分腹が減る、と言う。
そんなことを言ったら、一日中くるくると働く奉公人たちは、一体どれだけの飯を食うことになるのか……。だが、大切なお嬢様。おきのは、いつも黙っておいさに従う。
茶店に寄るくらいなら(それでも団子五本に饅頭三つは食べる)、まだ微笑ましいお嬢様の日常である。
だが、おいさは最近、師の元恩師のお琴のお披露目会に呼ばれ、駕籠を呼び、少し遠方まで出かけた。そうして、その帰りに飯屋に入ると言い出した。店の様子をおきのが見に行くと、きれいな畳の座敷の店ではあるが、中を占めるのは、大工だとかの身体の大きな職人風情ばかりである。とてもとても、お嬢様をあそこに連れてはいけません、私が叱られます、とおきのはおいさをどうにか説得しようとする。おなかが空いたのでしたら、駕籠に乗って家に帰って、何か作ってもらいましょう、と。
だが、おいさは駕籠に乗るだけの力がもう残っていない、今、ここでどうしても食べたい、あの店の出汁の匂いは、確かだ、と言い張る。
もう、ここまで言い出したら聞かないのは、おきのの経験から明白である。
諦めて、飯屋の暖簾をくぐった。
案の定、店に入ると、振り袖姿のどこぞの姫様のようなおいさに、客は僅かの間、箸を止めた。入り口からすぐ見える板場には、いかつい感じの料理人が一人いるきりだ。これはさすがに……、と思うが、おいさは構わずに座敷に上がる。
そこへ、「いらっしゃいませ」と鈴のような声がした。
小柄な可愛らしい娘が速足で出迎えてくれた。
おきのは、内心ほっと息をつく。
この娘がいてくれるだけで、どれほど心強いことか。
おきのの胸中を知らず、おいさは座敷に座り、今日の膳を頼んでいる。
「お連れ様はいかがしますか」と訊かれ、おいさが「遠慮せずいただきましょう」と言うが、おきのは「お付ですから、結構です」と小さくなって言う。
考えていれば、注文もしない者が店に上がり込んでは迷惑であろう。
私は、外でお待ちします、と言おうと思ったが、娘は二人分の茶を出してくれた。そうして、すぐにおいさの膳を持って来る。
ごはんに汁物、お菜の膳である。
よくある飯屋のものだとおきのは思ったが、おいさは、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬように正座し、手を合わせ、「いただきます」と言うと、椀を手に、きれいに汁物をいただいた。その所作たるや、やはりお嬢さんである。
おきのも背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬように正座し、茶をいただいた。
正直、期待していなかったが、苦味と甘さが絶妙の、大層おいしい茶である。
目の前のおいさは、幸せそうに箸を動かす。
「ねえちゃん、いい食いっぷりだな」と、皿を空にした隣の職人風情が声をかける。
おきのは、おいさに何かあっては、と身構えたが、おいさは「はい。大層おいしく、箸が進みます」と答え、同時に空の茶碗を置いた。
「ここの飯はうまいので有名でな、飯が出てくると、みんな、無駄口叩くのが惜しいほど、必死になるから、店は自然と静かなんだ」
「わかります」と、おいさは物おじせずに、従来の友人を前にするように答える。
「ただの世間知らずの嬢ちゃんが入って来たと思ったら、大したもんだな。職人に合わせた飯をこれだけ早くきれいに平らげるんだから」
「食べてこそ、力が出ます。できれば毎日ここへ通いたい。お弁当を届けてもらうのは無理かしら。ああ、おきの、駕籠を使っていいから、毎日ここまでお弁当を取りに行ってくれないかしら」
「大層気に入ってくださったようで、ありがとうございます」と、板場にいた板前がやって来た。
そうして、膳を下げながら、「立ち入ったことをお聞きしますが、お住まいはどのあたりで?」と訊く。
住まいのおおよその場所と材木問屋の娘だと伝えると、そこなら、少し歩きますが、橋の先に料亭がございます、と板前が言う。
板前が言うように、おいさの家からは少し歩くので、おいさの家族も恐らく、料亭に行くにしろ、もう少し近場で済ませているはずである。
板前は、そこで修業し、こちらで店を出した、と言った。
自分は安い値で、気安く入れる飯屋にしたが、技術と舌の感覚は、しっかりとあの料亭の大旦那に仕込まれた。
だから、わざわざ駕籠でここまで来るのなら、料亭で昼餉を摂るのとかわらないのではないか。夜は酒の席も多いが、昼間はお嬢さんでも入りやすいでしょう、と言う。
確かに駕籠を頼む時間や費用を考えれば、高級な料亭であっても昼餉なら、負担にはなるまい。否、おいさはもともと、あちこちでよく食べるから、今さら費用がどうとの言うのもおかしな話である。
兎に角、よいことを教えてもらい、おきのはほっとした。
そうして、恐らくは、黙っていれば、金に糸目をつけず、毎日弁当を買いに来ると言う客を前にしても、親切な提案をしてくれるこの板前の気風のよさに、頭が下がった。
2
善は急げ、とおいさは、翌日、書とお茶の稽古が済むと、早速教えてもらった料亭を目指した。本来なら、おいさのお稽古が済めば家に戻り、ここでおきのも昼餉の時間で、まあ、僅かだが休めるはずである。だが、元気なおいさは颯爽と歩き、橋を渡る。
その先に、大層立派な料亭が見えた。
大きな入り口に、人の姿はなかった。
もしかすると、もう昼の商いは終わったのかも知れぬ。
板場からは、出汁のよい香りとともに、「やはりこれでいこう」、「うん、兄ちゃん、それがいい」という会話が漏れ聞こえる。
新しいお品書きの相談であろうか。
「うん、これでいこう」
「兄ちゃん、それがいい、うん」
同じ会話が繰り返される。
「あの、ごめんください」と、おいさが、その出汁の匂いに釣られ、板場に声をかけてしまった。
「ああ、おいさ様」と、おきのがおいさを止めようとしたが一足遅く、おいさは板場に足は踏み入れてはおらぬが、顔は突っ込んでいる。
兄弟と思われる板場の二人は、びくり、と驚いた様子でこちらを凝視している。
おきのは、「申し訳ございません」とまず詫び、昨日飯屋に行ったことと、そこの板前にこの料亭を教えてもらったことを説明した。
「そうでしたか」と、人の好さそうな兄弟は納得し、「せっかく来ていただいたのに申し訳ありません。昼餉の時間が終わってしまいまして、夜までお待ちください」と、丁寧に詫びる。
本来なら、時間外に勝手に板場を覗いたこちらが詫びる場面である。
だが、おいさは全く意に介さず、「あの、先ほどから何の相談をされているのですか」と尋ねる。
普段は教養あるお嬢さんであるが、如何せん、食のことになると、熱心が過ぎるのだ。
「お菜の味付けをですね。今、相談しておりまして」
ご丁寧に兄弟が説明する。
「あの、そのお鍋の中は、全て出汁なのですか?」
板場を覗きこんだままのおいさが訊ねる。
「ええ、そうです。うちでは何か新しいものを作る時、一通りの材料、組み合わせを試し、そこから相談して、何がよいか決めております。初めは、今よりずっと時間がかかりましたが、だいぶこうしたことも板についてきまして」
「へえ」と、おいさが目を輝かせる。
「それ、私も味見しては駄目ですか?」
「え」と、兄弟は顔を見合わせた。
「いやいや、お客様に、仕上がっていないお菜をお出しするわけにはいきません」
「私、まだお金を払っていませんし、客間にも通してもらっておりませんから、お客ではありません」
こういう屁理屈を言う知恵がおいさにはあるのだ。
かわいい、かわいいとおいさを見守るおいさの両親と祖父母だが、最近は、そうしたおいさの言動を心配するようになってきた。
おいさは材木問屋の娘だから、持参金はたくさん用意できるし、いい縁談にも恵まれるだろう。だが、このおいさ、少々出来が良すぎる、と奉公人ながらおきのは思う。
書の腕もなかなかであるし、お花も、踊りも、お琴もお三味線も、お茶も、どれも上手にこなす。恐らく、もともと頭がよく、要領もよいからであろう。だが、どこかに嫁ぐとすると、多分、お相手は番頭のいる、大きなお店になる。そうすると、妻が帳簿を預かってやりくりしたり、店に出る必要もない。穏やかに微笑んで、旦那様を慕うような娘を、相手方が望むことが多い。そんなことは、一奉公人のおきのでもわかる。
ここで、この人の好い兄弟を怒らせると、せっかく教えてもらった近場のおいさの腹ごしらえ場所に通えなくなるではないか……。
はあ、と内心おきのは溜息をつく。
だが、顔を見合わせた兄弟は、「もし、よろしかったら、どうぞ」と、きれいに器に盛ったお菜を二種類出した。
「こちらに決めましたが、最終的にこちらも捨てがたい思いもありまして」と説明し、「あちらにどうぞ」と、板場のすぐ隣にある座敷に案内してくれた。
さすが、大きな料亭は襖絵も華やか、大きな器に活けられた花も品があり、座布団はふかふかである。
物おじせずに、おいさは座布団に正座する。
部屋の外で控えようとしたおきのも、兄弟は部屋へ促し、膳を用意してくれた。
恐縮しながら、おきのは、膳の前に正座する。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬようにする。今日は、おいさのお茶の稽古に師の先生に当る方も同席される日だったから、おきのもよそ行きの着物に足袋を履いて出かけた。そういう日で本当によかった、とほっとする。
おいさは「いただきます」と箸を取り、野菜を煮込んだお菜をいただく。
「こちらは、鰹の風味を活かして、醤油も利かせたお菜ですね。こちらは、昆布出汁で、みりんで甘みを出したお菜ですね」
「ええ、ええ」と、兄弟が頷く。
「おきの、どう思う?」
おいさが話している間に、両方の皿に箸をつけたおきのは、はっと顔を上げる。
おきのに料理の詳しいことはわからぬ。
今はおいさのお付だし、奉公を始めたばかりの頃は、お家の味というものがあり、おきのは水を汲んだり、火を起こしたりするのが仕事で、女中頭が料理をし、その味をお内儀様が確認するのが常だった。
「……どちらも、とても美味しいです」
おきのは小さく言った。
「私もそう思います」
え、とおきのは、おいさを見る。
味にうるさいおいさが、おきのと同意見とは……。
否、おいしいのは確かだが、もっと、細かいことを言うのだとばかり思っていた。
「これ、どちらかをお客様に選んでもらってはどうかしら? どちらかだけでは勿体ないわ。本当はどちらもお出しするのがいいと思うけど、ほかにもお菜が出るのでしょうし。だったら、選んでいただいたらいいと思うの」
「おきの」と、おいさが、書きつけ用の筆を促す。
「はい」と、すぐにおきのは懐から筆記具を出す。
おいさには、何かを書き付けておく習慣があり、その筆記具を懐に用意しておくのは、おきのの役目であった。
おいさは茶の席で使用する懐紙を出し、そこにお品書きの要領でお菜の品名を書き、下に先ほどの味付けの簡素な説明と、それぞれに鰹と昆布の絵を付け加えた。
「上質な紙を使えば、お店の品は落ちないと存じますが」と、おいさは言う。
介入し過ぎではないか、とおきのははらはらする。
あの家の娘は、高級料亭のお品書きにまで口出しした、などと、どこぞから話が広まれば、付いていたおきのの責任にもなる。
だが、この兄弟、実におっとりしている。
「ははあ、それはいい案ですね」と頷いている。
根っからのいいところの子というのは、人からの意見をこうも素直に受け入れるものなのか。それとも、もともとの気質なのか。どちらにしろ、品のある兄弟である。面(おもて)もきれいだし、毎日よい食材を使い、それを料理し、自らも食べる人というのは、身体に無駄がなくすっきりとしていて、均整がとれている。
「あの、この案をいただいても、よろしいでしょうか」と丁寧に兄弟は訊ねる。
「もちろんです」と、おいさは頷く。
おいさも、お内儀様の美しさを引き継ぎ、またお稽古三昧の成果で品もあるので、初対面であれば、非の打ちどころのないお嬢さんに見えるだろう。
3
おいさが、この大きな料亭のご新造さんになったのは、それから暫くしてからのことである。
おきのは、おいさのお付になってから、生涯をおいさと共にするものだと思っていたが、おいさの嫁ぎ先では、ご新造さんのお付の習慣がないことと、おいさ自身が、この旦那様とならおきのがいてくれなくても大丈夫だと言ったことで、材木問屋の一女中に戻ることになった。おきのにとっては、突然の、拍子抜けするような展開であった。
おいさは初めて料亭を訪れて以来、稽古の合間にこの料亭に通い、そのたびに、様々な膳をいただいた。そうしてそこで、兄弟がお品書きの絵が、どうにもうまくいかず、以前案をいただいて、鰹や昆布の絵を描いてはみたが、昆布はぼろきれのよいにしか見えぬし、鰹はそもそも魚としてすら認識してもらえぬと嘆く。
それでおいさが行くたびに、得意の書も活かしてお品書きを書くようになった。
兄弟はそれのお礼にと、いろいろなお菜をおいさに出した。
おいさはもちろん、お代は払うが、兄弟は、あれも、これも、とおいさがよく食べるのを知ると、旬の食材を使ったものや、手に入りにくい食材を使ったお菜を惜しげもなく出してくれる。
どうして、こんなによくしてくださるのですか、と訊くと、私たち兄弟は、どうにも新しいお菜を出すのに、自信が持つまで時間がかかります。ですが、おいささんが食べてくださるのを見ていると、ああ、大丈夫だ、と思えるのです。なんだか、安心して、力が湧くのです、と兄弟の、とりわけ兄が力を込めて言う。目には涙さえ浮かんでいた。
おいさは首を傾げ、変わったお人と、言っていたが、その後、文のやり取りや、毎日のおいさの腹ごしらえに通ううちに、それぞれ特別に思うようになったようだった。
料亭の長男は、両親とともに、おいさの家を訪れた。
この日は家じゅうを磨き、随分と忙しかった。
おきのは早朝から掃除に加わり、その後おいさの支度を手伝った。
料亭の長男と両親がやって来て、それぞれに正座して、向き合った。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬように、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃える。
おきのは、茶を出す役割を仰せつかった。
緊張している様子だが、優しそうなご両親であった。
なんでも、兄弟の下にいるお嬢さんは札差の長男の元へ嫁いだのだとか。
どうか、おいさ様をよろしくお願いします、という思いを込めて、おきのは座礼して、その場を離れた。
4
おいさの食欲は、嫁ぎ先では、寧ろ褒められているとおきのは聞いた。
お品書きも買って出て、大層達筆な字で仕上げているそうだ。
おいさの両親は、本当によいご縁があって、と事あるごとに口にする。
そうして、おいさがいた時より、遥かに少なくなった米やお菜の材料の減りを、寂しく思っているのがわかる。
おいさのお付は、空腹を訴えることが多く、おきのははらはらすることもあったが、今となっては、おいさのおかげで、この江戸でずいぶんといろいろな店に入り、そうしておいさのご相伴に預かった。
恐らく、もう十分すぎるほど、江戸の店には行っただろうし、団子や饅頭もいただいた。だから、今はもう、それらを食べたいとも強くは思わぬ。
ただ、おいさが嫁ぎ、ふと寂しそうにする旦那様一家を見ていると、おいさは、同じ江戸に暮らしてはいるけれど、暫く会っていない家族が恋しくなった。今度の休みには、饅頭を土産に買って帰ろうか。そのうちに、足を伸ばして、あの飯屋に連れて行こうか。あそこなら、おいさの財布でも、家族を喜ばせられるだろう。
そんなことを思うと、幸せな思いがこみ上げる。
ああ、きっとおいさ様の旦那様になられたあの方は、おいさ様が喜ぶようにと、日々板場に立っているのかも知れない。そうして、おいさ様は、それを知ってか知らずか、嬉しそうに、お菜をいただくのだろう。
ずっと近くにいながら、お嬢様であり、遠い存在であったおいさが、嫁いだ後になり、おきのはふと、おいさを身近に感じるのであった。

![[347]お江戸正座23](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)