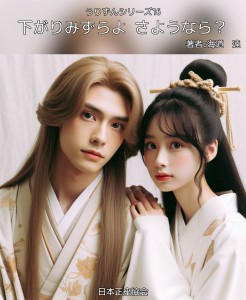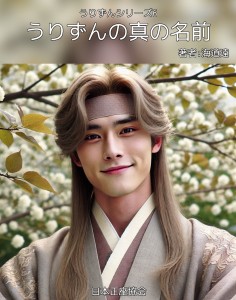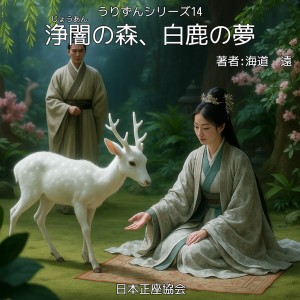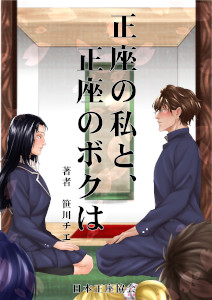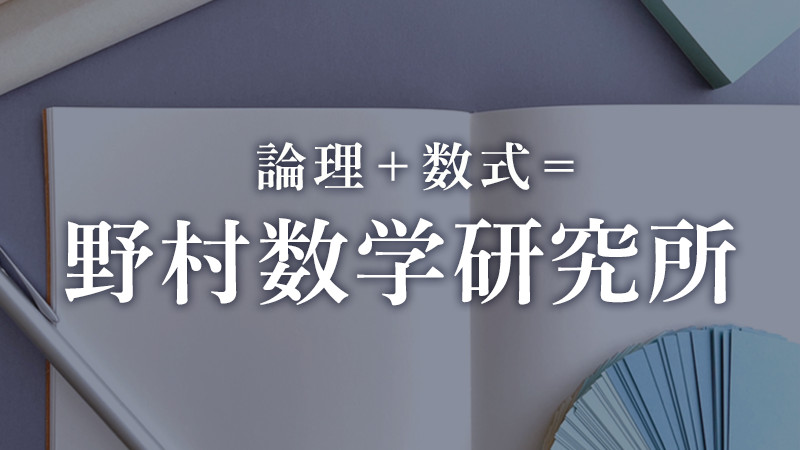[326]うりずん、正座して視座(しざ)を知る
 タイトル:うりずん、正座して視座(しざ)を知る
タイトル:うりずん、正座して視座(しざ)を知る
掲載日:2024/12/16
シリーズ名:うりずんシリーズ
シリーズ番号:2
著者:海道 遠
あらすじ:
春の長雨が長引いて、湖国の衆宝観音さまは疲れていた。お詣り客も蒸し暑さから弱っていた。馬宝刀(まほと)少年の元に、山寺の流転(るてん=正座修行中)から手紙が来た。うりずんという青年が子どもたちに正座や、読み書きや「うりずん拳法」を教えているという。
うりずんは、以前、湖国の寺に滞在したことがあった。

本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序章
うりずんとは、沖縄(琉球)の2〜4月の気候をいう。やっと冬から抜け出て、適度に晴れと雨があり、一番過ごしやすい気候。このお話では、その時節の神、精霊である。普段は沖縄に住んでいる。
視座とは、物事を認識する時の立場をいう。
第一章 うりずんの噂
湖国のある寺の庭に、はんなりと、たおやかな片膝座りでじっと座り続けている衆宝観音さま。
伏し目がちな瞳は、宝―――つまり、人々が汗水垂らして貯めた財や得を積む心を見守っているという。
信仰する人々は多く、お姿に合掌する人々は引きも切らない。見守られているからこそ、平和な日々を送れていると湖国の民は信じているのだ。
その年、春の長雨がいつもの年に増して長引いて、湿気の多い日々が続いた。
そのせいか、衆宝観音さまは疲れていた。
じっと片膝立てで座っているだけなのだが、立て膝をするのは左の膝と決まっている。もう一方の右脚は岩の上に寝かせたままだ。
1日中、動けずに人目にさらされるのも辛いものだ。
お詣り客もまた、蒸し暑さから不快そうに顔の汗を拭っていた。
ある日、観音さまは弟子の馬宝刀(まほと)少年に愚痴をこぼした。
「都の観光から流れてくるお客さまの数の多いこと……たまには温泉にでも行きたいわ〜〜」
「脚でもお揉みしましょうか?」
元は羅刹(らせつ)だった弟子の馬宝刀少年だが、今は改心して観音さまに忠実に仕えている。真面目にお寺で雑用しながら、独学でいろいろ勉強している。
「ありがとう。馬宝刀くん。じゃあ少しお願いしようかしら」
馬宝刀が手を貸し、台座を降りて寺の奥へ移動して、衆宝観音さまは横になった。
馬宝刀は観音さまの背中を揉みはじめる。
「ああ、気持ちいいわ。馬宝刀くん、マッサージが上手ね」
「来る日も来る日もたくさんの観光客相手じゃ、疲れますよね。特に観音さまはお美しいから、写真に納めようという方々がたくさんで」
「お詣りしてくださる方が多いのは、ありがたいのだけれど……」
「そうそう、この前、山寺の流転くんから手紙が来ましたよ」
「あら、あなたと仲がいい流転くんね。山寺の皆さん、お元気かしら?」
「はい。そのようです。山寺の境内に新しい塾を作った青年の教えが好評なんだそうです。勉学や拳法はもちろん、正座をいろんな面から、みんなで考えてみたり……」
「へぇえ。それは、万古老師匠もお気に入りそうな塾じゃないの。あっ、ソコソコ、そのツボが気持ちいいのよ! 馬宝刀くん、マッサージのツボがよく分かってるわね」
「その塾を開いた青年もマッサージが上手だそうですよ。一度、彼の手当を受けられませんか? と手紙にありました」
「まあ、そんなこと言って、馬宝刀くんは本当のところ、百世ちゃんに会いたいのでしょう」
「え……そんな」
馬宝刀は少し赤くなって手を止めた。正座師匠の弟子、百世(ももせ)とはお互いに、ほのかに思いを寄せている。
「その青年の名前は、何ておっしゃっるの?」
「本名は分からないけど、うりずん兄ちゃんってみんなから呼ばれているそうですよ」
「うりずん兄ちゃん……? うりずんですって――?」
ガバっと、衆宝観音さまは起き上がった。途端に「ゴキッ」という音がして立ち上がれなくなった!
「イタタタッ!」
(うりずんって……まさか、あのうりずんでは……)
第二章 湿り魔のじとじと
紺色の胴着が似合っている青年は、今日も山寺の境内で子どもたちを集めて身体の鍛錬をしている。
動作を揃えて拳法らしき型をやっている。
「そこ! もっとワキを締めて腕を繰り出すように!」
「ハイッ!」
「エイヤッ!」
十代前後の子どもたちが、一斉に掛け声を揃えて【うりずん拳法】の動作をしている。
百世が走り込んできた。
「うりずん兄ちゃん、大変なの!」
「どうした? 百世ちゃん」
みんな、拳法の動きを止めて百世に注目した。
「湖国の衆宝観音さまが……ほら、うりずん兄ちゃんも知ってるでしょう」
「あ、ああ」
うりずんの胸が、どっきり高鳴った。
知っているどころではないのだ。お互いに両想いだなんて、百世が知ったら、なんと思うだろう。
「腰を痛められたって、今、馬宝刀から思念が来たのよ! うりずん兄ちゃん、湖国まで診察に行ってあげてくれない? 村から馬を借りてくるから」
「よしっ! 皆、今日の稽古はここまで! 集まって!」
うりずんの呼びかけに、弟子が集まってきてゴザの上に正座をした。
「ありがとうございました!」
少年たちとうりずんは、向かいあって挨拶して解散した。
百世が馬を引いてきた。ふたりは馬の背に乗ると、湖国に急いだ。
寺の門前には人々が群がっている。観光客に混じって地元の村人も押し寄せている。
「衆宝観音さまが腰を痛められただなんて……」
「大変なことだ! おいたわしい……」
百世とうりずんは、馬を下りて寺の奥へ人々をかき分けて急いだ。
寺のご住職の奥様が待っていた。
「万古老師匠の弟子で百世と言います。医者の心得がある者をお連れしました。衆宝観音さまは奥ですか」
「ええ、こちらです、どうぞ!」
ご住職の奥様は待ってましたとばかりに、ふたりを招き入れた。
庭を横に見て、奥の静かな一室に案内する。
廊下に正座して、障子の内側に声をかけた。
「衆宝観音さま。山寺の百世さんがお医者さまをお連れくださいました。お開けしますよ」
障子が開けられた。
観音さまが顔をしかめて褥(しとね)の上に横になっている。馬宝刀が傍らについていた。
障子が開けられ、湿気がいっぺんに吹き飛んだかのような爽やかな風が吹きこんだ。若葉の繁った黄緑色を連想させるような。
衆宝観音さまは胸いっぱいに深呼吸をした。甘酸っぱい香り―――。遠い昔に味わった……。その香りが吹き込んできた―――!
息を吸っている間だけ、腰の痛みが遠のいた。
(なんと―――、懐かしい香り―――。うりずん……あの方の香りだわ―――)
「観音さま。観音さま。山寺から来られたお医者さまですよ。お気をしっかり!」
馬宝刀が助け起こそうとしたが、観音さまは、うめき声をもらして再び横になる。
馬宝刀が素早く席を譲り、うりずんは正座して深々とお辞儀をしてから、観音さまの脈を取った。
一瞬、ふたりは見つめあった。短い時間だったが、こちらまで溶かされそうな熱を帯びていた。
「どう? うりずん兄ちゃん」
百世の問いに、うりずんは表情を変えず、観音さまの腕を布団の中へ戻した。
「この際、しばらく庭に座られるお務めはお下がりになり、お身体を休められた方がよろしいでしょう」
「そんなにお具合が良くないの? 観音さまは今まで、お休みされたことなんかないと思うわよ」
「うむ。今年は特に、湿り魔のじとじとが力を強めているようだから……」
「湿り魔のじとじと?」
「ああ。私の故郷、南の島の湿気を操る妖怪だ。下手するとナメクジを大量に発生させて感染の病を流行らせ、村のひとつやふたつ、全滅させちまう厄介な魔物だ。そいつが勢力を伸ばして倭国の本土のあちこちを蝕んで(むしばんで)いるらしい」
うりずんは、やや暗い面持ちになって言った。
「もし、湿り魔の病のせいだったら、観音さまの足腰の痛みはただの疲れではないかもしれない……」
第三章 早春の風の神
馬宝刀と百世が寺の庭から湖を眺めた。
「今年の春は長雨が続いて、今日のような曇りの日でも暑くて汗びしょびしょだ。畑の作物も雨ばかりで新芽から腐っちまうって、農家の人が言ってた」
「そりゃあ、困るよね。作物に響くのでは……」
「春の長雨が去らないうちに、梅雨入りでもしようもんなら、じとじとしっぱなしだ」
馬宝刀は、田畑も眺めてため息をついた。
「不思議だな。うりずん兄ちゃんて、人の側に寄ると湿り気が去って汗が引っ込む気がする。さっきも観音さまが、うりずん兄ちゃんに会っていきいきしていたようだ」
「さすがに南国の神様だなあ」
「観音さまの腰の痛みも早く治るんじゃないかな?」
「そうなりますように」
ふたりして願った。
寺の山門にふたりの男が走り込んできた。
「ご住職さま〜〜!」
「村に病人が出ましただ〜〜!」
「この蒸し暑さに飲み水が腐っちまったんだ!」
ご住職がすぐさま、玄関に出て詳しい状況を聞き、村へ薬師を手配した。緊迫に満ちたやり取りが、奥に寝ている衆宝観音さまにも聞こえた。
「大変なことになったわ。私もこうしてはいられない。早く村へ行って、村人たちのために水が腐るのを防がなければ!」
上半身を起き上がった観音さまは、顔をしかめた。
「まだ無理なさってはなりません。村へは、私がご住職と行って、様子を見てきますから!」
うりずんが引き留めた。
「あなた……うりずん。南国の雲の峰まで行って、爽涼(そうりょう)の神を呼んできてほしいのだけれど、お願いできる?」
「え?」
「爽涼の神を知っているでしょう? 早春の気候のあなたより強力な夏の爽涼の神なら、この蒸し暑さを一掃してくださるはず」
うりずんはしばらく考え、
「分かりました、衆さん。では、私の言うことを聞いてください」
「……はい」
「私が帰るまで正座していてください。疲れたら横になっても構いませんが、立膝座りや横座りはしないで正座していてください。脚の痛みを早く取るためです」
「分かったわ、うりずん」
衆宝観音は、若々しい首筋をふんわり抱いた。
うりずんは、廊下から馬宝刀と百世を呼び、百世に、
「私は今から南国の雲の峰まで行かなければならない。その間、衆さんを頼む。決して庭の台座に戻られないで、ちゃんと布団の上で正座していてくださるよう見張っていてほしい」
と頼んだ。
「衆さんって?」
「あ、衆宝観音さまのことだよ」
「うりずん兄ちゃん、あなたは一体……?」
「南の国では早春の爽やかな気候を『うりずん』と呼ぶ。私はそれを采配する者なのだ――」
ふたりは飛び上がった。
「それで、あなたの周りには、いつも爽やかな風が吹いているんだね!」
「それより、村で湿り魔が起こす病が発生した。私などより遥かに強力な爽涼の神を呼んでくる! その間、百世は衆さんを頼むぞ」
(『衆さん』だって。うりずん兄ちゃんたら、いつの間に観音さまとそんなに親しく……)
「わ、分かりました……」
百世が生返事をした。
「百世、ボウッとしてないで! 観音さまの部屋へ行くぞ!」
馬宝刀の声に、百世は我に返った。
衆宝観音さまが脚を痛めているのも構わず、病の気配が出た近隣の民は、寺の台座にたくさん押し寄せていた。
「衆宝観音さま!」
「どちらに行かれました? ワシの村では、この長雨のせいで病人が出ましただ!」
「湿気のために、庭や畦道(あぜみち)、家の中までナメクジが大量に発生しちまって、あいつらが腹に持っている寄生虫が病をまき散らしているだ!」
「観音さまは、我らが汗水垂らして作った作物も、我らの身体もお守りくださるはず! どうか、この長雨と蒸し暑さを取り去ってくださいませ!」
「赤ん坊や子ども、老人まで病にかかり苦しんでおります。どうか、どうか、台座の上に姿を現してくださいませ!」
ご住職の奥様が村人たちを説得に当たっている。
「村の衆。ご心配はごもっともですが、どうか落ち着いてくださいませ。観音さまはお腰を痛めて療養中なのです。今しばらく、ご休息の時間を与えて差し上げてください」
「いつまで待てばよろしいので?」
「はっきりとは申し上げられませんが、今、動けば、観音さまのお腰や、おみ足がますます痛まんでしまわれます! 何とぞ、何とぞ、お願いいたします」
「うう~~ん、しかしのう」
「ただいま、うりずん青年が南国へ爽涼の神を迎えに行っています。爽涼の神が村の病魔を退散させてくれるでしょう。それまでの辛抱です」
「爽涼の神ですと―――?」
「初夏の爽やかな風を呼ぶ神様のことだそうですよ」
第四章 雲の峰へ
うりずんは、疾風のような速さで馬宝刀とそれぞれ馬に乗り、倭国の南の端からは舟に乗り、南国目指して爽涼の神が住まう雲の峰まで急いだ。
雲の峰は高地にある更に高い台地で、清々しい風が一年じゅう吹いて黄金の光が満ちている。うりずんとて爽涼の神に会ったことはない。果たして頼みを聞いてくれるかどうか、まったく判らない。
しかし、今はそんなことを心配している場合ではない。湖国の村で病が流行りだしてしまったのだ。
ふたりは山すそに馬を置いて、峻険な山を登っていった。
南国にこんなに高く峻険な山があるとは、意外なことだった。倭国の内にこんな険しい土地があるとは思われなかった。うりずんが生まれ育った南国よりも、高い山々が連なっている。
「馬宝刀、大丈夫か、足元に気をつけよ!」
「はい!」
下界よりもかなり涼しいが、ふたりの額には大粒の汗が光る。空気が薄く胸が苦しい。
ふたりは周りの岩をつかみながら、一歩一歩慎重に登っていった。うりずんは、時たま振り向いて声をかける。
「馬宝刀、爽涼の神が祀られている祠(ほこら)まで、もう少しのはずだ。頑張れ」
「は、はい」
「あの峰の向こうのはずだ」
しばし、山肌に止まり休憩すると、眼下一面に緑の草原が広がり、茶色い馬が点在している。
「人間や神仙の者がいる気配がしないな」
ふたりは再び、山頂を目指して登りはじめた。
――ヒヒ―――ン!
山頂から馬のいななきが聞こえた。
ようやくふたりが頂に登りつくと、一面の霧が辺りに立ち込めていた。
霧の奥に濃い緑にこんもりと囲まれて、朱い祠(ほこら)らしきものがぽつんと見える。
「あそこが爽涼の神の住処(すみか)かな―――。鳥居の奥には祠というより厩(うまや=馬小屋)がぼんやり見えるが」
第五章 爽涼の神
霧の奥から蹄の音が、かっぽかっぽと響いてきた。
雲の隙間から一条の光が地上目がけて降りてきて、だんだん足音の主(ぬし)がはっきり見えはじめた。
なんと伸びやかな美しい栗色の筋肉を持つ脚。つやつやと輝くたてがみといい、しっぽといい深く黒い瞳といい、神々しい姿であろう。馬独特の吐息の匂いを含んだ清々しい風が、うりずんと馬宝刀を取り巻いた。
ふたりは下界での湿気を忘れ、身体の内側に本来の若い力がみなぎってくるのを感じた。
「若造たちよ、何者だ?」
駿馬(しゅんめ)から低く響く、人の言葉で問われた。
なんという威厳を持った馬か―――。身体は栗毛、たてがみは金色である。背後からの一条の光を受けて眩しい。
「あ、あなたが爽涼の神ですか」
「いかにも」
「私はうりずん。春風の精です。後ろの少年は衆宝観音さまの弟子で馬宝刀と申します」
ふたりはその場に恭しく正座して、慎重に頭を下げる。
「我のことを【爽涼】――と、皆が呼んでおる。この地に光と汚れなき風を吹かせるのが、天帝よりの命だ」
うりずんがもう一歩前に出て、頭を垂れた。
「湖国の村人たちが湿り魔の害に遭い、病を多発しております。どうか爽涼さまのお力を借り、湿り魔を追いはらいたいのですが、お力添え願えませんでしょうか」
「どうか、お願いいたします!」
馬宝刀も必死の表情で背後から頭を下げた。
「……」
爽涼の神が押し黙る。
「どうか!」
「うりずん。いかにも南国の春の風よのう……、そして、馬宝刀とやら。お前は以前、残虐な羅刹でありながら、そこから抜け出し、衆宝観音さまの懐で愛情深く世話になったようだな」
瞳の奥まで、爽涼の心の眼に見つめられた。
しばし、山の風の音が響き―――。爽涼は答えた。
「断る」
「えっ!」
うりずんと馬宝刀は思わず眼を見開き、爽涼を見つめ直した。
「な、なぜ――、一刻も早く湿り魔を退治しなければ」
「病人が溢れているのです!」
「断る!」
爽涼はもう一度、ふたりの願いをニベもなくしりぞけた。
第六章 敵のことを知れ
「なぜですか。爽涼さまのお努めは、世の中の湿気を取り除き、光あふれる世界を保つことではないのですか」
うりずんはすがるように問いかけた。
爽涼は「ぶるん!」と鼻息を吐き、
「うりずんと馬宝刀よ。我の力を貸す必要はないと判断したゆえだ。お前たちふたりは、十分に衆宝観音の熱い愛情を受けて成長した。湿り魔から村人を守る力も十分備えているはずだ」
「そ、そんな……」
「己(おのれ)の胸に手をあてて己の実力を知れ。そして、敵のことも知れ。お前たちは湿り魔がどのようなカタチをし、どのような心持ちでいるのか分かっているのか。敵のことを知るのも大切なことだ」
馬宝刀が弱々しい声で、
「そういえば湿り魔のことは村人たちの噂で、でかいヒキガエルの姿をして、ナメクジみたいな角があり、ナメクジを大量発生させて寄生虫の中の病原をまき散らすとか聞いたことがある」
「――想像するだけで胸くそ悪くなるな。――では、お前は湿り魔の姿を見たことはないのだな」
爽涼の神が念を押した。馬宝刀は決まりが悪そうにうなだれた。
「はい……。見たことがありません……」
「では、対話したこともないのだな」
「はい……」
「では、敵を知るために、ふたりして対話してくるがいい。湿り魔にも言い分があるかもしれぬぞ。つまり、いろんな人に会い、視座を広げるのだ。それから、正座をして心を落ち着けて考えるのだ。村人のウワサだけの話を信じるか、村のご住職からの話を信じるか、荘園の役人の情報を信じるか、【視座】を高くすると、どの立場から見るかによって物事の見え方が違ってくる。その中から自分の結論を見い出すのだ」
うりずんと馬宝刀は顔を見合わせた。しばらく見つめあって、うなずいた。
「分かりました、爽涼の神さま。湿り魔と対話してきます!」
第七章 見慣れぬ女
うりずんと馬宝刀は、爽涼の神の協力を得られないまま、湖国に帰ってきた。
村では予想通り病が蔓延(まんえん)して、人々は救護院に運ばれていたが、元気な者も打つ手がなく、指をくわえて見ているしかない状態だった。
うりずんと馬宝刀は寺の衆宝観音を見舞い、爽涼の神の協力を得られなかったことを、土下座して謝る。
観音さまは何も言わず、静かに考えた。
(なるほど――戦う前に己と敵についてよく知り、あらゆる立場の者から物事を視るということね……。爽涼の神さまがおっしゃることは、ごもっともだわ)
寺の救護所へ、旅の女性が、4、5歳くらいの男の子を抱いて走り込んできた。
「どなたか、どなたか、この子を助けてやってください」
ご住職が出てみると、
「マムシに咬まれたのです! 助けてやってください!」
「おお、そりゃ大変じゃ! そこへ寝かせて毒を吸い出してやりなされ」
男の子は真っ赤な顔をして、すでに発熱しているのが分かった。ご住職も傷口から毒を吸ってやったが、
「ううむ、これで熱が下がればよいのじゃが」
寺の山門をうろうろしている、ぼろぼろの色褪せた着物を着た女がいた。
「あ、あの女、さっきから何が用なんだか、山門のところにずっとうろうろしているのよ」
百世が近づいて話しかけた。
「何かご用ですか?」
「あ、あの、これ……」
女は髪の毛をザンバラにして顔がすっきり見えず、気味が悪い。若いのだか年寄りなのだかも判らない。
「これを、さっき、マムシに咬まれたという男の子に……」
手に持っていたビイドロの瓶(びん)に、茶色い液体が入っている。
「マムシやスズメバチに咬まれた時に、よく効きますから――」
「塗り薬なの? 本当に効くの?」
「効きます! 私が長年かけて作った薬です」
うりずんがやってきた。
「そこな女! マムシに咬まれた時の薬とか。何を原料に作ったのだ?」
「月桃草(げっとうそう)とヤマカズラの葉と、ナメクジを大量に三年漬け込んだのです」
「わあっ!」
瓶を持っていた百世が落としそうになって、流転に渡した。
「本当だ……。ナメクジが入ってる……」
流転は泣きそうな声を絞り出して、うりずんに渡した。
もう一度、女を見ると、女はしっかり頷いた。
「ふむ。ナメクジの虫さされの薬は聞いたことがあるな……。百世も流転も、ナメクジだからってそう毛嫌いせずに。――よし、ダメもとで塗ってやろう」
男の子の側へ行き、マムシに咬まれた傷口に塗ってやった。
「わわっ! うりずん兄ちゃん!」
百世と流転は慌てたが、うりずんは手早く塗ってしまった。
「大丈夫かな……」
男の子の額と傷口を濡れた布巾で冷やしてやりながら、待ってみることにした。
第八章 ナメクジ薬の効き目
夕闇になり、寺では流行の病の患者であふれているが、マムシに咬まれた男の子の熱は下がりはじめた。母子はホッとしている。
瓶を持ってきた女は、その様子を見届けてから山道へ去っていこうとする。うりずんが、そっと後をつけた。
山道は葉陰が多く地面が湿っているが、初夏の林を渡ってくる風が気持ちよい。
女は山の奥へ入っていき、今にも崩れそうな草庵(そうあん)の中へ入っていこうとする。
「あ、待て! いや、お待ちあれ!」
うりずんが叫んだ。
女が振り向いた時、眩しいほどの光に包まれた一頭の駿馬が、そこに立っていた。
「爽涼の神さま! やはりそうではないかと思いました。我らを試したのですね。おや?」
うりずんは眼をこすって見直した。かばうように立っていたのは、確かに爽涼の神だが、その背後にみすぼらしい女が隠れていた。
「うりずん、あの薬は信用してよいぞ。マムシに咬まれた傷に効く。そして、湿り魔が流行らせた病にも温めて飲めば効く」
馬の爽涼の神の声は、落ち着いている。
「では、苦しんでいる村人たちも助けられるのですか?」
「ナメクジの寄生虫を食べてしまうと命とりになるが、南国の月桃の葉で漬け込めば、毒虫に咬まれた時の薬になるのだ。のう、湿り魔の女」
「ええっ、そのみすぼらしき女が湿り魔?」
「うむ。この女は長年ナメクジを研究しているのだ。どんなに軽蔑されても【湿り魔じとじと女】と呼ばれても、自分の意志を貫いて湿っぽいところに住み、一年じゅうナメクジの学問をしているのだ。私も力を貸してやっているし、手伝いもしてくれる」
女がざんばらの髪を耳にはさんで、おずおずと答える。
「わたくしは『たゆな』と申します。爽涼の神様のお手伝いをしております」
髪の毛の分け目からちらりと見えた目元は、白い額に、まつ毛が濃く品のある美しさではないか。
(人は見かけによらないなあ~~)
百世と流転は同時に思った。馬宝刀も思ったに違いない。
【たゆな】が、細々とした声で、
「あの薬は、衆宝観音さまのおみ足の痛みにも効くかもしれません。試してみてください」
「馬宝刀。責任は我が取るゆえ、観音さまにも試して差し上げてくれないか」
爽涼の神がいななきながら言った。
「わ、分かりました……」
馬宝刀はびくびくしながら、ナメクジ入りの瓶を受け取った。
第九章 衆宝のおみ足
衆宝観音の足の痛みは、十日ほどすると引きはじめた。
甘い香りを含んだ透明な風が耳元をかすめていく。観音さまは、膝の辺りに薬を塗っている手を感じて、目を覚ました。
慌てて衾(ふとん)をたぐり寄せて足を隠した。
「これは……驚かせてしまい……」
うりずんは、正座していた位置から身体ひとつ分、しりぞいて頭を下げた。
「報告がございます。爽涼の神が思いがけず、湿り魔の女【たゆな】の研究を擁護しておられまして、この薬は、その女が作り出した塗り薬です」
「ふたりきりの時くらい、もっとくだけた物言いでいいのよ、うりずん」
うりずんは、頭をかいて言い直す。
「衆さんの右膝の痛みに効き目があるようなので、手当てしたんだ」
「うりずん……」
観音さまは衾(ふとん)から腕を伸ばした。うりずんの大きい手のひらが受けとめて握り返す。そのまま衆宝は起き上がり、青年の胸に寄りかかった。
「何年ぶりでしょう。帰ってきてくれたのね」
「衆さん……」
「分かっていたわ。山寺で子どもたちに拳法の修行をさせている青年がいると聞いた時から……貴方の早春の風の香りを思い出し……」
観音さまの眼に涙が溢れた。
「帰ってくるとも。約束を交わしたではないか。何度生まれ変わろうとも、衆さんのことだけを考えている」
「うりずん……」
障子の外に、人の気配がした。
「観音さま、お薬の時間でございます」
百世が部屋に入ろうとしたが、真っ赤になって障子を閉めた。
「なんとなく感じていたけど、観音さまとうりずん兄ちゃんが、こんな熱い仲だったなんて!」
ドキドキする胸を押さえた。
やがて、村の流行り病は峠(とうげ)を過ぎ、平和が戻ろうとしていた。
うりずんは衆宝観音の衾をたたみ、改めてキリリと立った。そして膝を着き、衣をお尻の下に敷き、かかとの上に座った。
「衆さん……、よくぞ私を爽涼の神へ使いにやってくれた。礼を言う」
「え?」
「爽涼の神は重大なことを教えてくださった。【戦うなら、己のことも、敵のこともよく知れと】」
「……」
「私は湿り魔を噂だけで知り、姿かたちも確かめずにいた。どうやって流行り病を防げばよいか、まったく知らないまま、爽涼の神の力だけに頼ろうとしていた。だが、爽涼さまは目を覚まさせてくださったのだ。一方的に無知な自分の【視座】にいるだけではどうしようもないと――」
「――」
「もし、爽涼の神さまに会わなければ、【たゆな】のことも知らず、ナメクジの薬を作れることも知らないままだっただろう。――流行り病を防ぐ手立ても分からぬまま、村の方々も救えず、衆さんの足の痛みを治めることもできないままだっただろう」
「――爽涼の神さまに深くお礼を言わなくてはね」
「南国へ帰って、また崖を登り神様の祠へ行ってお礼を申し上げてくる。【視座】を変えることを教えていただき、ありがとうございました、と」
「うりずん、だんだん立派な大人になっていくわね」
「なるさ! 私は衆さんの想い人なんだから」
「違うわ。わたくしが、早春の風の精うりずんの想い人なのよ」
ふたりは手を取り合った。
「あ~あ、聞いてらんないわねぇ。衆宝観音さまがこんなに恋におぼれるタイプだったとは!」
廊下で百世が肩をすくめた。
「【視座を変えてみる】――。大切なことだな」
馬宝刀が繰り返しつぶやいた。
「一発、あたいが万古老師匠に講義してやろうかしら? 何千年も同じ教えを繰り返していても、視座を変えなきゃ進歩はありませんよって! 」
「おい、百世! 冗談だろ? 」
「さあ、どうしようかな? 」
ぴょんぴょん跳ねていく百世の後を、馬宝刀は追いかけた。