[109]まれびとの正座、遥か未来
 タイトル:まれびとの正座、遥か未来
タイトル:まれびとの正座、遥か未来
分類:電子書籍
発売日:2021/01/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:52
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
遥か未来、宇宙訓練学校の卒業生、サマー、スコナ(女生徒)とジャスの三人は卒業試験に異星の探査をするために異星にやってきた。
初めて海を見る三人。
海岸にひとりの女がいた。
三日目に話しかけると言葉が通じた。
彼女の方から「まれびと」と言ったのだ。稀に訪れる人のことを言う。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/2646789

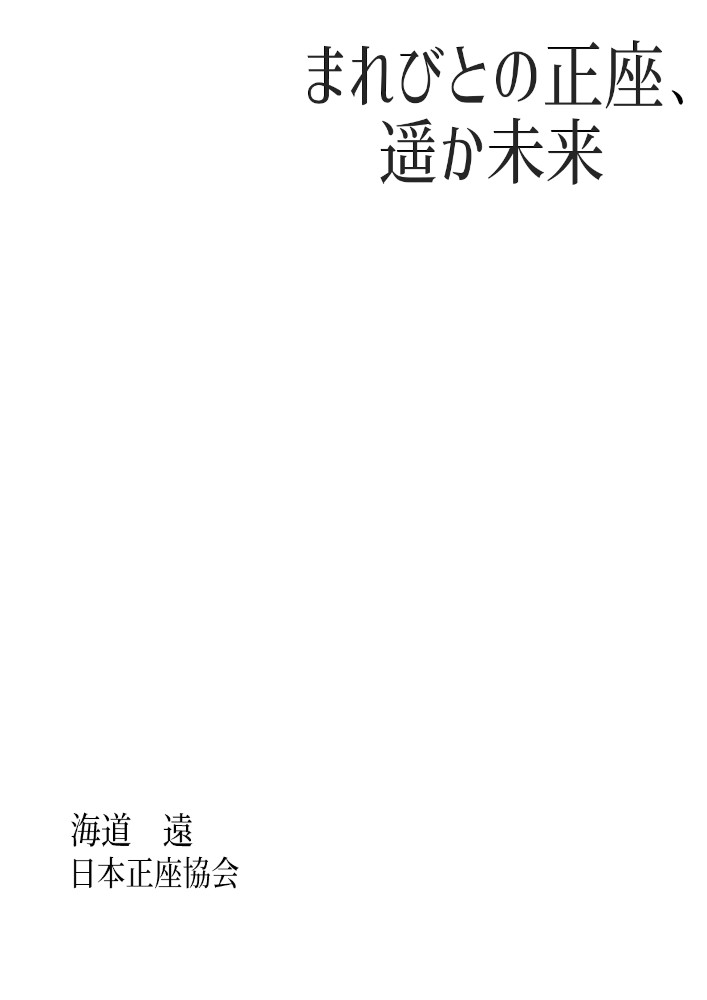
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 ある惑星の女
「後、二タイムズで着陸します」
サマーがマイクに向かい、ステーションに連絡した。
小さな探査機が青い星に着地しようとしている。乗組員は三人のみ。キャプテンを務めるサマーと、成績が首席の女史スコナと、ジャスというおどけた面のある男子学生だ。
キャビンも小型で三人の席が、暗闇に美しく点滅する夥しいメカの黄緑色の光に押しつぶされそうになりながら、やっとこさのスペースだ。
三人は、ある惑星の宇宙航行学校の卒業試験に挑んでいる。
昔から存在は確認されているものの、未知の惑星に着陸するのが、彼らの卒業課題だった。彼らの惑星の宇宙研究センターでも、この惑星の着陸は初めてのことで、キャプテンを務めるサマーは意気込んでいた。
片腕のスコナは優等生で信頼できる。あまり成績のよくないジャスが足を引っ張らないよう祈っている。三人のチームワークが揃わなくては卒業試験にパスできない。
星雲の端っこの端っこに、小さな惑星があった。
その昔は動物も植物もたくさん栄え、大きな海と大きな大陸がいくつもあり、大陸には実に様々な地形があり、山脈、草原、砂漠、森林地帯、氷原などに適応した動植物が発生、進化しては滅び――を繰り返していた。
類人猿も生まれ、人類が誕生し、人類は惑星の自然を変えてしまう科学を生み出し、間違いを犯した。
結果、人類は滅亡に近い打撃を受け、高層ビルが林立した都市はすべてが廃墟と化した。
生き残った人類を捜索する政府ももはや、ひとつも残っていない。
人々はちりぢりになり、生き残った動物を狩猟したり草や木の実を食べるしかなかったが、それは科学の発達した世界を経験した人類にとって、どんなみじめなサバイバルだっただろう。
ここまでは、サマーたちの母星の調査で判明している。
サマーたち三人が着陸した場所は砂漠だった。
一面の砂の世界。温度は摂氏五十度くらいある。草原地帯まで移動する。酸素濃度は故郷の惑星と同じだと判明しているが、一応はヘルメットを装着して下船する。
乾燥した砂原のあちこちに草むらが点在しているだけの静寂な世界だ。
「海岸へ行ってみるか。ここから一キロだ」
スコナは厳しい顔で、
「油断禁物よ。地表はともかく水の中はどうなっているのか遠隔操作でも調査できてないんだから」
彼らは草原地帯を二キロほど歩いて海へやってきた。
「故郷の海の色とはちがうな。エメラルドブルーだ」
久しぶりに波の音が聞きたくて潮風を味わいたくて、三人ともいてもたってもいられなくなり、ヘルメットを脱ぎ捨てた。
「なんて気持ちいいんだ」
「明らかに故郷の星の海とは違うぞ」
「潮の香りも違うわ」
三人は思うぞんぶん潮風を吸い込み、潮騒を聞いた。
「あれは? 人間?」
ジャスが岬の先端に黒く小さな人影のようなものを見つけた。まさか? と思いながら近づいてみる。
そこには、淡い緑色の長い髪をした生命体がいた。サマーやスコナたちと見かけは変わらない。生命体が振り向いてはっきり判った。女性だ。
突き出た崖の先端に膝を折って座っている。
サマーたちの気配に振り向いたのは、藍色の長い衣服を着た腰まである髪、細く長い手足の女性だ。
「これは……稀人……」
女はつぶやいた。
思わずサマーたちが目を見張る。言葉が理解できるのだ。
「い、今、『まれびと』って言ったよな?」
ジャスが言う。
「あ、ああ」
女が立ち上がった。淡い髪が絹のように風に弄ばれる。
「『まれびと』って確か珍客みたいな意味よね」
スコナが眉間にシワを寄せたまま言う。手元には、数千の言語の翻訳機を搭載した端末を持っている。それは用なしだった。
サマーが一歩、歩みより尋ねる。
「あなたはこの惑星の人ですか」
……しばらくしてから、いきなり女は岬の岩を蹴り、海へと飛びこんだ。
第 二 章 星の歴史
次の日にサマーたちが、再び岬の先端に来てみると、また座っている。そして海へ消える。
三日目―――。
どうやら言葉は通じるようなので、サマーがゆっくり近づいてから話しかけた。
「我々はこの星のことを調べに来ただけだ。危害は加えない」
女は振り返ったままだ。
「よかったら、分かるかぎりこの星のことを教えてほしい」
女は三人を代わる代わる見つめてから頷いた。
ぽつりぽつり話し始めた。
「この星は数千年前までとても繁栄していた……」
深い哀しみを湛えた瞳だ。
「しかし、ある日戦争が始まり、都市はことごとく破壊され、生き残った人々は数百人。私はその少数の生き残りの子孫」
女は言葉を切った。
「星が繁栄していた時代を私は知らない。そして……」
「そして?」
「この『正座』という座り方も沈む以前の一族が伝承していた座り方だ。でも、海の中へ生き延びた生き残りも、後、数百年もすると、この座り方ができなくなってしまう」
「できなくなってしまう?」
よく見ると、きちんと膝を折った座り方はサマーも初めて見る。
「その座り方は『正座』というのだな?」
「うむ。ある一族には伝統ある座り方だ」
女は言葉を続ける。
「『正座』は、もし心が荒れた時でも『心の平穏』を取り戻してくれる座り方だ。でも、近い将来できなくなってしまう――」
「どうして?」
サマーが尋ねる。
「私たちの海の中の町にくれば分かります」
「海に没した町?」
三人は顔を見合わせた。
サマーたちは自分たちの探査機に戻った。
しばらく各自のコックピットに座って黙っていた。
「海に没した町だって?」
三人同時に口を開いた。
「あの調査結果は事実だったのか」
「人類滅亡の危機に直面した人間たちが、海に沈んだ町と共に生き延びたということ?」
「まさか。この星の人間たちは水の中で呼吸できなかったはずだ」
スコナもジャスも首を振った。
サマーが、慎重に言う。
「しかし……、宇宙には考えられない生命体が存在する。水の中で呼吸できるように進化したのかもしれない」
三人はもう一度顔を見合わせて押し黙った。
第 三 章 海底の町
探査機は、かなり強固であり多機能を搭載している。真空でも水中でも侵入可能だ。
サマーは言った。
「あの海中へ探査機で潜ろうと思う。ふたりは?」
ジャスは素っ頓狂な声を出した。
「えええっ! 海の中へ? 滅亡したような星の海の中へ行くのか?」
スコナは落ち着いて、
「やはりね。サマーなら行くって言うと思っていたよ」
不敵な笑みを浮かべてウインクした。
「スコナ姐、度胸あるなあ」
「あんただけ残る? ジャス」
「い、いや、ふたりが行くって言うなら行きますよ。ただ、帰還日が迫っている。間に合うのかい? サマー」
「間に合わせるさ、ジャス。ここまで興味をそそられることを目の前にして、行かずにおれるかい」
自信満々でサマーは答えた。
「外洋へ出てしばらく行くと大きなホールがあって海水が流れ込んでいる。そこを降りて行って」
女が言う。
「海にホールが空いてるだって?」
三人は海辺の女に海底へ探査機を案内させていた。
女は海に潜ってしまい、探査機は紺碧の海の上を飛んでいく。ジャスが叫んだ。
「サマー、あれ見ろ! 本当に海にホールが空いてるぞ!」
直径五十メートルもあるだろうか。海面にぽっかりホールが空いていて周囲の海水が恐ろしい勢いで流れ込んでいる。
「何だ、これは。こんな現象、初めて見るぞ……」
三人とも目を見張った。
ホールから離れたところに、ぽっかりと彼女が浮いてきて、
「この真ん中を降りて行って。ちょうど私たちの町の広場に降りられるわ」
その先導を信じてサマーは探査機をホールの中にゆっくり下ろしていった。三六十度、巨大な滝に囲まれた中を、探査機はゆっくり降りていく。
操縦桿を握るサマーの額に大きな脂汗が浮かび、メカを監視するスコナとジャスも真剣な目をして睨みつけながら、流れ込む海水のすごさに驚いている。
かなり下方に大きな円が見えてきた。石でできている。
「あそこへ着地すればいいんだな」
サマーがうめくように言い、微妙な操作で探査機を石の台の上に持っていき、ようやく着地させた。
探査機の巻き上げる風に、周りの水のカーテンが揺れる。
サマーたちは、ほっとして各自のメカの上に突っ伏した。しばらくして顔を上げると、周りには巨大な滝があり轟音と共に大量の海水が落ちていた。
「なんだろう、この海のホールは」
「ここでじっとしていても仕方ない。勇気を出して降りてみよう。ヘルメットをかぶって」
サマーがふたりに促した。
スコナとジャスは言われた通りにヘルメットを被って用意をした。
降りてみると耳が割れそうな水の轟音だ。不思議なことに流れ込んだ海水はどこへ流れているのか、皆目、見当がつかなかった。ただ海面のホールから円柱形に空間が空いているばかりだ。
水のカーテンの中に、立ち泳ぎしながら手招きする、あの女の姿がある。
「この中へいらっしゃい」
「行くか」
サマーはゴクリとつばを飲みこみ、女のいる水中へと進んだ。カーテンを分けて水中へ入る。他のふたりも進んだ。
三人が被るヘルメットは、ある程度の水圧にも耐えられるし、背中には小型の酸素ボンベも背負っていて三十分は、潜水できる。
濃い藍色の世界が広がっていた。
百メートルくらいの深さなので、浅瀬に集う魚たちの姿は見えない。
ぼんやりと巨大な影の四角い石が厚い藻に覆われて並んでいる。どうやら町だったところだ。
高層ビルが海底に沈んでいるのだ。
あの女が三人を案内していく。
(あの女、素潜りだ)
やがて、藻に覆われた建物が小型なものになってきた。
住居だと思われる。
ふと覗く顔がある。サマーたちが進むにつれ、壁の向こうから覗く顔が増えてくる。男あり、女あり、若いのも年とったのも。
その人間たちが泳いで三人の前に出てきた。
「―――」
三人は唖然と見入った。
第 四 章 女の願い
そこで皆が目撃したのは、海中の町に住む半身半魚の生き物の姿だった。中には二本足の人間も確認する。
「私たちはやがて半身半魚に進化するの」
女が言う。
「だから、二本足がなくなると、もう正座ができなくなるの」
(……)
「でも、私は正座という座り方をこのまま絶やしたくない。心の幸せを与えてくれる正座を。この座り方を継承していた一族の生き残りとして。それが私の務めだと思うの。でも私もいつ、魚の下半身になってしまうかもしれない」
「そんなに早く?」
サマーの瞳が驚きに見開かれた。
「進化がそんなに早く進んでしまうのか」
「自分にも分からない。私の母は、眠る前は人間で、翌朝、目を醒ますと下半身が魚になっていた」
「お願いがあるの。聞いてくれる?」
女の勧めで、三人は海岸で正座の練習をする。
「まっすぐ立って。静かに膝を折って、かかとの上に座り、下半身の衣服はお尻の下に敷く。視線はまっすぐ前に。両手は膝の上に静かに置く」
三人は砂浜の上で彼女の手順通り、正座をしてみた。
座ると波の音だけが耳に響いた。心が無になるのが感じられる。
「不思議だわ。本当に正座すると、ちがう星の慣れない海辺にいるというのに、心が鎮まる」
スコナがしみじみ言った。
「ありがとう。どうにかして、この正座を遺したいのだが、この星の人類はすべて魚類になってしまう。せめて異星であっても正座を継承できたらと思っている」
「そうだとも! こんな素晴らしい文化、遺すべきだよね」
普段から落ち着いたサマーが乗り出して言ったので、ジャスもスコナも少々意外な顔をした。
「力になるとも!」
「本当ですか?」
「そのためには……。あなたを私たちの星に運ばなければならない」
サマーの瞳がぎらついた。
スコナは即、反対する。
「今さっき、教えてもらったじゃないの。それを私たちが帰ってから広めるのはダメなの?」
「そんなのダメだよ。この人の正座は、連綿と続いてきた一族の末裔そのものが続けてきた本物の伝統だよ。俺たちにうまく伝えられるはずがない」
サマーは豪語した。
第 五 章 サマーのもくろみ
四人の乗った探査機は地球へ向けて飛び立った。
いつ人魚になってしまうかわからない女のために、カプセル型になった個室にはいってもらうことにした。
個室には楕円形の窓があり、遠くなっていく故郷の星を、女は眺めた。
スコナがやってきた。
「居心地はどう? もし人魚になってしまった時の水も積んであるから心配しないでね。私たちの星で『正座』を教えるために耐えてね」
「ありがとう、スコナ」
人魚は弱弱しく微笑んだ。
三日の航行で、探査機は故郷の星に帰り着いた。
教官が不機嫌な顔で待ち構えていた。
「お前たち、遅刻だ。時間内に戻れなかった者は留年だぞ」
サマーが降りていって、教官にすり寄った。
「僕たちの卒業うんぬんは、後回しです」
言いながら、小さなモニターを持ってきて、探査機内の女を映した。
「な、誰だね、これは。訓練生以外乗せるのは禁止だぞ」
次にモニターに映ったのは、カプセル型の部屋の三分の一が水に浸されていて、女に大きな魚の尾がついている姿だった。
「……」
教官は絶句した。
「教官、お話があります。ちょっと校舎の一室をお借りします」
校舎の一室で先に口を開いたのは教官の方だった。
「探査機に乗っているあの生き物は何だねっ?」
「異星の生命体ですよ。知的生命体を発見したんです」
「……」
もう一度、タブレットの映像を見入り続ける教官に、サマーが語りかけた。
「人魚は学会に高く買い取られるでしょう。きっと見たこともない大金に化けるはずです」
「サマー、き、君はあの人魚を学会に売りつけようというのかねっ?」
「いけませんか? 異星の知的生命体は学会に役立てるべきです。それにそのお手柄で僕の卒業や就職先も安泰になりますよね?」
「君、あんまりいい成績ではなかったが、そこまで考えてるのか」
「教官だって、もっと昇進なさりたいでしょう? 校長とか、いや、学会のトップとか」
「サ、サマー!」
誠実な学生だと思っていたサマーが言い出したことに教官は目を白黒させた。
スコナが女の部屋を訪れた。
「残念ながら人魚になってしまったわね」
「ええ」
「でも、あなたから教えてもらった『正座』はこの星で教室を開き、きっと広めてみせるから安心してね」
「ありがとう、スコナ」
「気分はどう? 温度差は? 水の質も違うけど大丈夫?」
「今のところは大丈夫。食事は海藻さえあればいい」
海藻しか食べられない人種なら仕方ない。
「あなたが陸で暮らせる場所を考えるわね」
「スコナ、本当にありがとう」
「いいのよ。ところであなたの名前は?」
「名前……?」
「あなたは最初に私たちを見て『まれびと』って言ったけど、私たちにとってはあなたがとても神秘的な『まれびと』だわ。『まれびと』って呼ぶわ」
探査機発着基地は海が近いので潮騒が聞こえてきた。
スコナが持ってきた車椅子に座って『まれびと』が探査機を降りた時、
「海が近いのだな。潮の香りが故郷と同じだ。見たいな」
というので、スコナは宙港の端っこへ車いすを押していった。
海の色は、よく晴れた空の下で藍色に輝いている。少々風が強いので白い波頭が見える。
「あ?」
『まれびと』の彼女が、小さな声を発した。
「スコナ、海へ飛びこめるところまで連れていってくれるか? きっと帰ってくるから」
「ええ? 飛びこんでどうするつもり?」
「いいから、お願い!」
スコナが戸惑いながら、崖のスロープでは注意深く車いすを押していった。
『まれびと』が待ちきれない様子で膝かけをとりはらい、海に向かって身体を躍らせた。
白い飛沫が上がった。
「まれびと~~~」
スコナは海面から視線を外せずにいた。
第 六 章 ジャスの活躍
スコナの端末にサマーから電話が来た。
「どこに行ったんだ。あの女を連れて、校舎に帰れ」
「今、海辺よ。彼女が海を見たいっていうから連れてきたら、飛びこんでしまって」
「何い?」
電話の向こうのサマーの声がひきつった。
「今、そっちへいく!」
すぐに走ってきたサマーは、カンカンに怒っていた。
「どうして海辺へ連れて来るんだ! 彼女は大切な大切なサンプルだぞ! 俺たち卒業試験の業績だぞ!」
「サマー、そんな言い方って……」
スコナはサマーの豹変ぶりに驚いた。
しばらく待ったが帰ってこない。
「どうして彼女を自由にしたんだっ」
「サマー、考えてごらんなさいよ。故郷の星から遠い遠い異星へ連れてこられた彼女の心境を。海があったら恋しいと思うのは当たり前じゃないの」
スコナが碧い瞳で睨みつけた。
「そんなこと知ったことか。彼女は大切なサンプルだぞ。今世紀、いや地球史上最大の発見物だぞ」
「発見物……ものなんかじゃないわよ、サマー!」
スコナが本気で怒りだした時、水平線の辺りにひときわ白い波が立った。
眼下の岩場に彼女が海面から顔を出した。
「『まれびと』!」
スコナがひざ掛けを持って駆け下りた。が、次の瞬間には彼女は消えていた。
教官の命令で潜水救助隊まで出動したが、彼女の姿は見つけられなかった。
それから二日経った日のこと、てっきり寮へ帰ったと思っていたジャスからスコナにメールが入った。
『海の女を保護してるぜ』
スコナは目を疑いながら、彼の実家だという家に行ってみると『まれびと』が元気でいた。
「『まれびと!』心配したわよ! 良かった、無事でいてくれて!」
ジャスの家のソファに座っている彼女を思いきり抱き締めた。
「ジャス、お手柄よ。いつも足引っ張るあんたにしちゃよくやったわね」
「よけいなこった」
むくれてから、ジャスが言うには、
「俺、サマーと教官がしゃべってるのを聞いてしまったんだ。彼女を学会に買い取ってもらって、多分、サマーは学会に大手柄で迎えられるんで、卒業試験どころか、いい就職先までゲットしようとしてるんだ!」
「なんですって! あのサマーが!」
スコナの次くらいに優等生で真面目と言われていたのに、なんということだろう。
「そいでさ、あいつらは今、彼女のことを本人がいないんだから証明しようがないだろ。先に『正座教室』開催しますってコマーシャルするんだよ。いや、もうしちまったけど。ネットで」
「えっ?」
スコナが急いで端末を見ると、『世界で初めて。正座教室行います。初心者無料』と、ネットに流れていた。
「ジャス、やるじゃないの」
「へへっ。そうとなったら、スコナもちゃんと正座が説明できるように練習しておいてよね」
「そ、そうね」
人魚の彼女本人が呆然としている間に、スコナとジャスは守備よく会場を借りて「正座教室」を始めた。
第 七 章 世界で初めての正座教室
『正座教室』が始まって一か月。
その国の人々は好奇心から、だんだん生徒が集まりはじめ、スコナとジャスは頑張って教え続けた。
彼女本人の姿は隠し通したままだ。
サマーは何度も電話やメールをよこしたが、スコナとジャスは取り合わなかった。
そのうち、教室のどこかに人魚がいるという噂がたって、生徒はよけい増えた。
スコナが講師となって、奥様方や、女の子たちひとりひとりに丁寧に教えている。
「背すじを真っ直ぐにしてお立ちになって。膝をつき、かかとの上に静かに座って。その際、ドレスの裾はお膝の内側に挟んで下さいね。両手はそのままお膝の上に置いて下さい」
「先生、なんですか、この変わった座り方は。ソファの上ではできませんわね」
「遠い遠い星の、そのまた遠い遠い昔、ある国での座り方だそうです。その国は海の底に沈んでしまったという伝説が残っているのです」
「まあ、宇宙航空訓練学校におられた先生のお話ですから、信じてしまいますわ」
「信じて下さる下さらないはご自由ですけれど」
「信じますわ。ねえ皆様。絨毯の上で正座のお稽古してお茶いたしましょうね」
朗らかなやり取りを隣室で『まれびと』の彼女が聞いている。
(ありがとう、スコナ、ジャス)
それから熱心に端末で、星の海洋の状態を見つめていた。
宇宙航空学校の卒業試験の合格祝いのパーティーが、湾に停泊する大型客船で行われた。
スコナもジャスもおしゃれして出かけた。今頃は船上でゴージャスなひとときを過ごしているだろう。
あの日からサマーは姿を隠したままで、教官は淡々と教壇に立っていた。『まれびと人魚』の彼女は、岬に建つ正座教室でお留守番だ。
岬の正座教室には、大型客船でのパーティーの賑やかな笑い声や音楽がもれ聞こえてくる。しかし、彼女は端末を睨んだままだ。
『まれびと』の彼女がふと端末を置いて、窓にすり寄った。大型客船に向かう小さなクルーザーがあった。
「あれは……」
彼女の顔色が変わった。
そして夜の海の水平線近くに視線を投げて、もう一度真っ青になった。
(誰か!)
叫ぼうと廊下に出たが、正座教室には誰もいない。部屋に戻って慣れない端末から必死でメールを打ったが、うまく打てない。
端末を放り出し、教室を出て海岸へ這いずっていき、丘の上から海へダイブした。
彼女の泳ぎは恐るべき速さだ。イルカのようにクルーザーに追いついた。
「サマー!」
クルーザーの舵を握っていたサマーは、跳びあがるほど驚いた。あれほど捕獲したかった彼女が夜の海から現れるとは!
「サマー、船のみんなに知らせて!」
「お前! ここで会ったが百年め、絶対、逃すか!」
サマーは捕えようととびかかってきたが、彼女は押さえつけられても叫んだ。
「お願い、知らせて! 海に穴が開く!」
「は?」
「見ただろう、私の星で。海に大きな穴が開いていたのを。あの現象がここでも起こる!」
「なに?」
サマーの脳裏に大海にぽっかり空いたホールがよみがえった。
「ホールが空き始める時と同じ海の気配がする。このままではあの船は巻き込まれる。スコナとジャスが!」
「……!」
ようやくサマーにも彼女の真剣さが伝わった。
パーティーの開催されてる船だけではない。湾内に停泊している船、すべてが危うい!
第 八 章 湾に陥没する穴
船のパーティーは、ますます賑やかに盛り上がっている。
「この海にぽっかりホールが空くだって?」
(誰が信じてくれるだろう、そんなバカげたことを!)
サマーは焦った。自分が見てきた事実がまた起ころうとしているのに、誰にどう伝えれば信じてもらえるだろう?
校長や教官たちに言っても信じてもらえまい。
『まれびと人魚』が言った。
「私が皆の前で、この姿を見せる。そうすればきっと信じてくれる。異星人がいるということ。その海の不思議なこと」
健気な瞳だ。本気でよその星の人間たちを救おうとしてくれているのだ。
罪悪感という重いものがサマーにのしかかってきた。クルーザーで客船に向かっていたのは彼女を取り返したかったからだ。
(俺は、なんて心の狭い人間だ……)
「お願い。私をあの船に乗せて!」
『まれびと』の声に我に返った。
「し、しかし、そんなことをしたら、君は好奇の目にさらされてめちゃくちゃにされてしまう」
「そんなことより、湾内の人たちを救うことが大事でしょう」
「君は……」
サマーは客船の脇にクルーザーを近づけ、連絡して乗船させてもらうことにした。
パーティー会場では、キラキラとまばゆいシャンデリアの下、ダンスパーティーがたけなわに行われていた。ワルツが奏でられ、卒業生の女の子たちはここぞというおしゃれに身を包み、男子もタキシードで決めて、相手をリードしている。
校長や教育長たちは奥のテーブルで上機嫌で乾杯している。
ダンスしていた学生たちが、突然「わっ」と恐れる悲鳴をあげた。
会場のメインドアから、ボーイに引き留められながら、ふたりの人物が入って来ようとしていたからだ。
「誰なの、ずぶ濡れじゃないの」
「それに……それに……」
「サマーよね、あれ。横抱きにしているのは……」
「下半身がイルカみたい……」
「まさか、まさか」
仰天の目という目が、サマーの抱いている人魚に集まった。
その人魚が叫ぶ。
「この船の一番偉い人はどこですか?」
会場はざわめいた。
「しゃべったぞ!」
「しゃべれるの? いったい、本物の人魚なの?」
「み、みんな、彼女は卒業試験の宇宙探査機で着陸した星に住む人魚だ。彼女の言うことを聞いてやってくれ」
サマーが叫んだので、よけい驚きは広がった。
スコナとジャスも駆けつけてきた。船長もやってきた。
「皆さん、信じて下さい。この湾の海面にもうすぐホールが開きます! このままでは湾内に停泊している船が全部、海底に落下してしまいます! 一刻も早く船を沖へ避難させて下さい!」
一同、呆然とした。
「本当だ。私の星の海にはホールが突然、海に現れ街を飲みこんでしまった。見たね? サマー」
「あ、ああ。本当です。彼女の言う通り、俺たちはホールの底まで探検してきました。海面に直径五十メートルほどの穴がぽっかり空いてしまうのです。え、『まれびと』。どうしてその時のことを?」
「私は千年前、ホールが空く瞬間を目撃したのだ」
サマーは『まれびと』の身体を落としかけた。
「千年も生きられるはずがっ」
「私が異星人だと知ってるはず。そんなことより、早く船の避難を急いで下さい」
船長補佐の男が慌てて会場を飛び出していった。
パーティー会場にいた全員が、我先にと出ていこうとパニックになった。
「この船にお乗りの皆さん、落ち着いて。すぐに湾内に停泊中の船や海上保安本部に連絡します。落ち着いて速やかに下船の準備をして下さい」
悲鳴のあふれる大騒ぎは、海上保安本部のサイレンと共に、湾全体に広がった。
数時間後―――。
湾の中央にぽつりと空いた穴はみるみる広がり、湾の海べりぎりぎりのところまで水没してしまうのに、そう時間はかからなかった。
避難が早くできたために被害者は出なかった。
海岸の住民も、船の持ち主も呆然と夜明けの湾に陥没した海の穴を見つめていた。
第 九 章 宇宙の神に詫びる正座
「きっと、あの星の海の神が怒ってるんだわ。『まれびと』をこんな遠い星に連れてきてしまって」
スコナがぽつりと言った。
「おそらく―――」
『まれびと』も頷いた。
「海のことは、宇宙じゅうの星が察知するのだ。こうなったら、私が詫びなければおさまるまい」
「『まれびと』まさか、あなた……」
「うむ、スコナ。私が正座して海の神、いや宇宙を統べる神に心から詫びる。心をこめた正座して。それしか神の怒りを鎮める方法がない」
「正座してお詫びするのね」
『「まれびと人魚』は岬の尖端に連れて行ってもらい、地面に降りた。
背すじを正し、かかとに静かに座り、両手は膝の上に。
水平線の彼方が暁色になった。
昇りくる太陽に向かい、『まれびと人魚』は宇宙の神に深々とお詫びのお辞儀をした。
(考え浅く、宇宙の黄金律を乱してしまいお許し下さい。どうか、この星の海を元通りにして下さい)
潮騒が辺りに響く。
ホールはそのままだ。いつまで経ってもそのままだ。『まれびと』も頭を下げたまま、びくともしない。
やがて正午が過ぎ、陽がかたむき、夕暮れが迫る気配が漂い始めた。
潮騒がやや大きく響きはじめ、スコナたちは顔を上げた。
水平線から白い波が迫ってくる。
やがて大きな壁のようになって迫ってきて―――。ホールを覆いつくした。これほどまでの大波のうねりを、海岸から目撃することはなかった。
海岸の皆が呆然とするうち、うねりは鎮まりはじめ――、ホールは静かな海面に戻っていた。
岬の突端で頭を下げ続けていた『まれびと』は、地面に崩れ落ちた。
うっすらと目を開けると星の海だった。
重い頭をゆっくり上げると、見覚えのある狭い部屋の中、楕円形の窓から宇宙空間が見えていた。
「気がついたね、『まれびと』」
スコナの声だ。
「一応、健康状態に異常なしだったけど、気分は大丈夫?」
「え、ええ」
「安心して。あなたの故郷まで帰るところよ。サマーとジャスとで送っていくわ。サマーは心からすまなかったと思ってる」
「ホールは……」
「あなたのおかげで湾は静かに戻ったわ」
「良かった」
「正座は、私たちが広めていくからね」
彼女は嬉し涙を溜めて頷いた。
「……ありがとう。私の星に来てくれた『まれびとたち』」
「あなたもね。最果ての星にいた『まれびと』の人魚姫」
ふたりは微笑み、黒いビロードに散らばった宝石のような宇宙空間を見つめた。
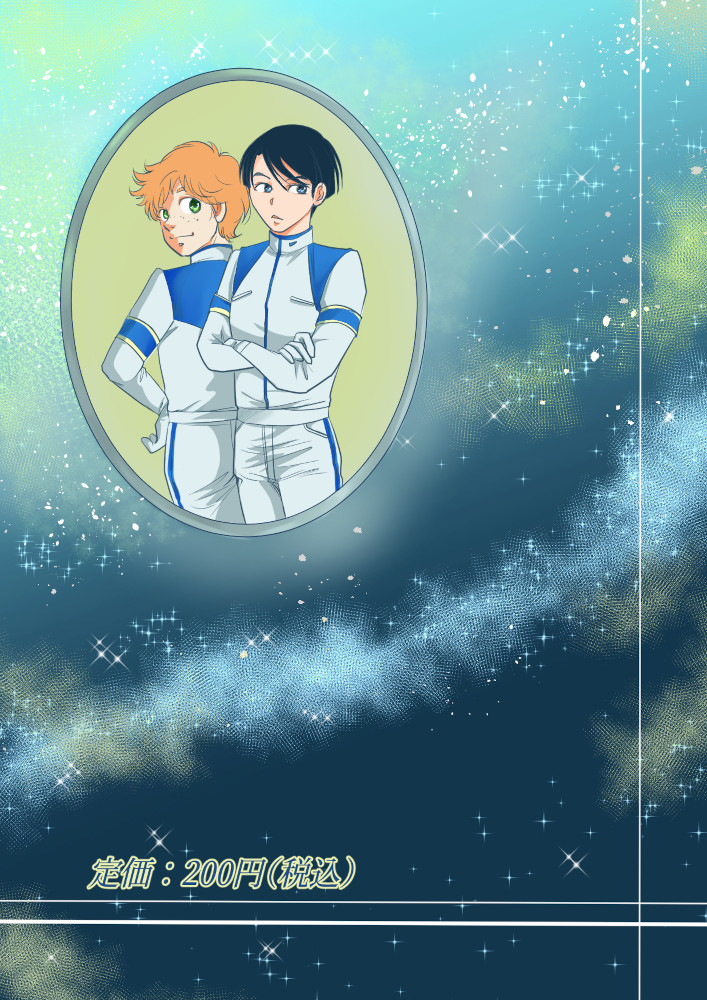

![[3]正座のマンガを描いてみた](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)





