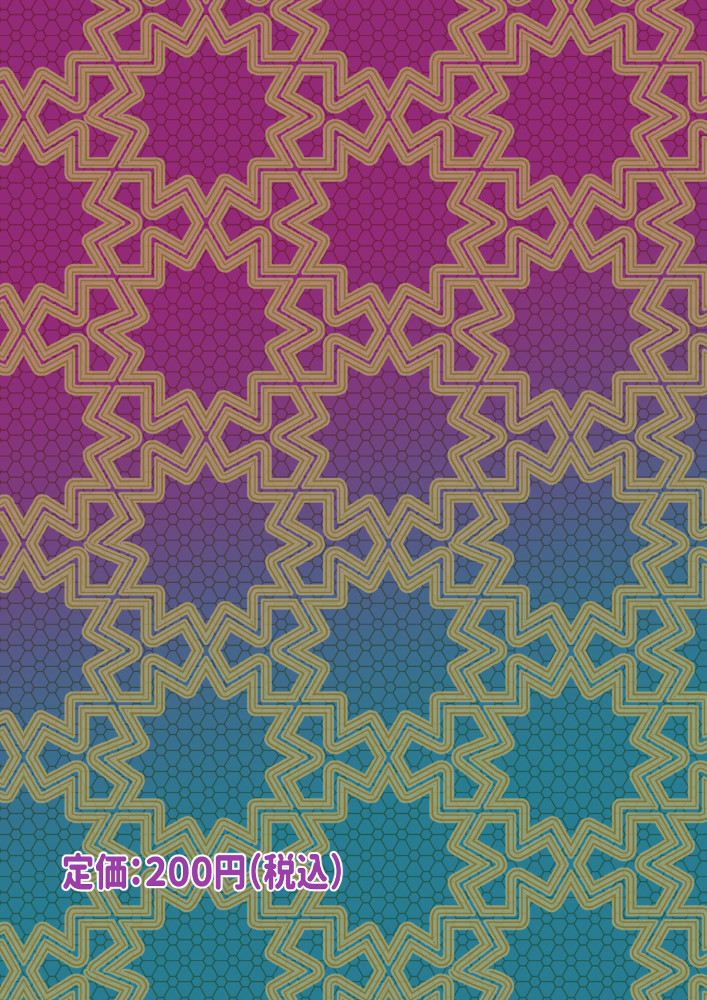[114]正座浴場を作ろう!
 タイトル:正座浴場を作ろう!
タイトル:正座浴場を作ろう!
分類:電子書籍
発売日:2021/03/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:48
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
ミズホは大学を卒業したばかりの海外ボランティア員。
イスラム教のとある国に、庶民の生活調査のためやってきた。
日本ではお行儀を習っており、正しい正座を広めるように
師匠から頼まれていた。
正座は神様へのお祈りの「座礼」と似ていることに気づく。
市場の土産店の青年ダヤンの姉のファーサという絨毯織りの女性と知り合い、仕事柄、肩や腰の痛みに苦しんでいることを知る。さて?
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/2787384

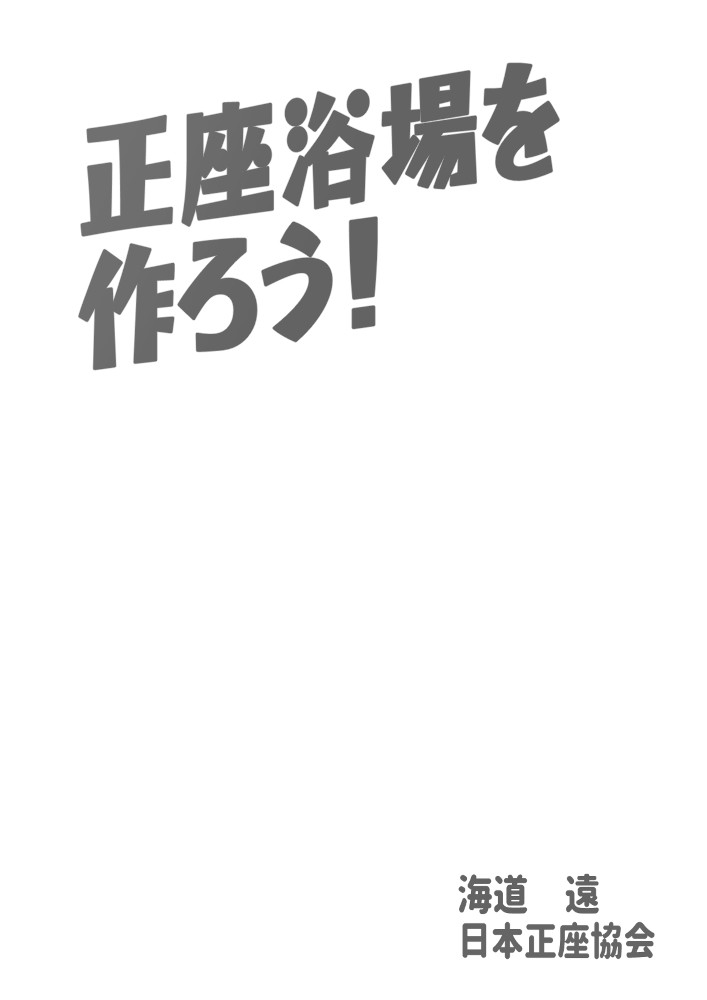
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 イスラム教の都
ミズホは大学を卒業したばかりの海外ボランティア員だ。
たっての希望だった海外ボランティアに参加できて、胸を弾ませていた。
赴任地はイスラム教の国だ。
ボランティアの先輩で野川さんという男性が指導してくれる。
人々は敬虔な信者で一日五回、コーランという経典を読みながら、ひざまずいて額を床につけ、お祈りを捧げる。
女性たちは頭に布をかぶり、肉親の前でしか布を取らない。食する食べ物もタブーがある。この風習に慣れなければならない。
そして、もう一つ、ミズホは日本にいる時にお作法教室に通っており、師匠から是非、派遣された国で「日本の正座教室を現地で開いてほしい」という希望を伝えられていた。
ミズホはイスラム寺院に行って、国民がお祈りする姿を見学し、正座はイスラムの「座礼」と似ていることに気づく。
野川さんが、行動を共にしてくれ、下町のスーク(市場)へ出かけた。
スークはたくさんの人々が集い、果物や装飾品の金のアクセサリーを旅行者に売ろうとしている商売人の声が渦巻いている。
「どうだい、おねえさん。金細工のネックレス。似合うと思いますよ」
金キラした装飾品や置物が天井や壁からいっぱいの店先で、若い男がミズホに声をかけてきた。
「いえ、私は」
「そんなこと言わずにさ」
その時、十歳くらいのピンクのヒジャブ(頭にかぶる布)を被った女の子が血相かえてやってきた。
「ダヤン! お母さんが」
「どうした、ラーナ。またお母さんの具合が良くないのか」
言うなり、青年は店を放っておいて少女の後を走り出した。
ミズホと野川さんも後に続いた。
スークの裏側に広がる住宅街は石造りの迷路になっている。ミズホと野川さんは、少女とダヤンという物売りの青年の後を、必死でついていった。
やっと石造りのひとつの入口にたどり着いた。
ミズホがそっと覗くと、奥に寝台があり、横になっている女性がいるようだ。
「姉さん。どうした。いつもの仕事のやりすぎか?」
ダヤンが尋ねる。
「多分、そうだろう。腕や背中が痛くて、絨毯が織れなくなった」
部屋の隅には織りかけの絨毯がそのままになっている。
「絨毯織りは、疲れる作業だからな。根をつめるなと、あれほど言っておいたのに」
「ダヤン。だって、私は父親のいないこの子、ラーナを育てなくてはならないんだよ」
「だからって無理しちゃだめだろ、姉さん」
ミズホは野川さんに通訳してもらって、女の子に尋ねた。
「お父さんは?」
「あたいが小ちゃい時に、お家を建てる工事の事故で死んじゃったんだって」
「そうだったの……」
(お母さんに元気にお仕事してもらわなければね)
「あなた、ラーナと言ったわね」
ミズホが声をかけた。
「今日、お姉さん、初めてイスラム寺院へ行ってお祈りするの。良かったら一緒に行ってくれない?」
「でも、母さんをひとりで置いておけない」
「じゃあ、俺が一緒に連れていってやろう」
ダヤンが言った。
夕刻、ミズホはラーナからピンクのヒジャブを貸してもらってイスラム寺院へ行った。
入口で、男女は別れる。お祈りする場所が分けられているのだ。
「よう、ダヤン。いつの間に嫁さんをもらったんだ」
ダヤンと同年代の青年たちが、からかって声をかけてきた。
「お前たちなんか、結婚式に呼んでやるもんか。どうだ。きれいな花嫁だろう」
ダヤンも応戦してから、男性の祈る場所へ行った。
青いタイルに囲まれた、万華鏡のように美しい世界だ。
たくさんの人が集まってコーランを広げている。コーランを置く木製の台を利用している人もいる。
信者たちの座り方は正座に似て、床にぺたりと座る。ミズホは端の方にそっと座った。
しばらくざわざわしていたが、導師と呼ばれる老人がやってくると、信者は波をうったように静かになった。
導師がコーランを読み上げ、最後に「神は偉大なり!」と叫び、信者たちもそれに続いた。
ミズホにはわけが分からないが、寺院の雰囲気や信者の座り方に親近感を持ち、荘厳な雰囲気を味わった。
やがて、真っ赤な夕陽に照らされて、信者たちは額を床につけて祈り、立ち上がり、また座って頭を床につける動作を五回繰り返した。
第 二 章 浴場を作る
翌日、ボランティアの事務所で、野川さんが言った。
「正座は浴場の浴槽の中でやると肩コリや腰痛の痛み緩和になるそうだね」
「野川さん。私、日本にいる時に、正座教室に通っていて師匠からも、教わったことがあるんです」
「じゃあ、なお更」
「絨毯織りで働く女性のために、浴場があればいいですのにね」
「この国の浴場は男性用しかないんですよ。近くに歴代の浴場博物館がありますから行ってみますか?」
「ええ、是非」
ふたりは観光客向けの浴場博物館に出かけた。
浴場博物館の中は、まるで王宮だった。
天井から太陽光が差し込み、青や緑の緻密な模様のレンガがまばゆく輝き、とても共同風呂とは思えない。
もっともそれは王族専用のお風呂だ。
庶民用と言っても男性用だけだが、そちらもまずまずの広さで豪華ではあった。プールのような大きな浴槽に何人もの男が身を浸し、垢すり男にマッサージも受ける様子の絵画が展示してある。
「女性は? 女性はマッサージも垢すりもしてもらっちゃダメなの?」
「宗教の戒律上、絵画にして展示ってわけにはいかないでしょうね。もっと小さな浴場か、自宅で水浴びするかだと思いますよ」
野川さんは答えた。
「そりゃ、ひどいじゃないの」
ミズホは口をとんがらかせた。
しばらく事務所で考え込んでいたミズホは、
「正座浴場を作りましょう!」
瞳を輝かせて叫んだ。事務所の皆や野川さんは驚いた。
「浴場は大半が富裕層向けの高額な代金だわ。とても労働者が利用できる金額じゃない。でも、本当に浴場を必要としているのは、ラーナのお母さんのような労働者なのよ」
「それは分かりますが」
「赤字経営の公衆浴場がないか、探そうと思うの。それを借りる形で代わりに経営するの。古くても改修すれば使えるでしょう」
言うが早いか、ミズホはもう外へ飛び出して車を出そうとしている。
野川さんも慌ててついていった。
町の中に古くて修理できないまま放ってある浴場、赤字経営で困っている浴場などが三か所見つかった。
ミズホは早速、持ち主を探して話してみた。
一か所だけ、賃料を払ってくれるなら貸そうという浴場が見つかった。
ミズホは持ち主の男性にお礼を言い、中の様子を見せてもらうことをお願いした。
博物館で見たような豪華な浴場ではないが、まずまずの大きさで、ふたつに別れていて、ひとつに百人は入れそうだ。今は営業時間ではないのでガランとしている。
三、四人の強面の男たちが、たむろしていた。
ミズホたちを見ると、近づいてきた。
「日本人か」
「はい。この浴場をお借りしたいと思っています」
「俺たちはここで雇われている垢すり男だ。俺は、アブザーイという。あんたたちが借りたら、俺たちはクビとかいうんじゃないだろうな」
「そんなことはしません。あなた方にも、ちゃんと賃金をお支払いして、この浴場の利益から借り賃もお支払いするつもりです」
第 三 章 垢すり男に正座の稽古
男たちは眉の濃い浅黒い顔をしていて、ミズホたちを信じていない。ギョロギョロした眼で日本人を珍しそうに見つめる。
「本当です、信じて下さい」
「しかし、女に垢すりするらしいじゃねえか」
「女性には女性の垢すりの方にやってもらいます」
「しかし……、女が他人に垢すりしてもらうなんて神様の教えに逆らいやしないか」
「それは、大丈夫です。私、女性たちに日本の座り方もお教えしようと思うんです」
自分でとっさに出た言葉にミズホ自身、驚いた。
(そうよ! 浴場に集まってくる女性に正座をお稽古してもらい、浴槽に浸ってもらえば疲れは取れる、お稽古もできる。一石二鳥じゃないの!)
なんて良い閃きだろう。
「日本の座り方?」
「ええ、正座と言います。コーランの時の座り方とよく似ているんですよ」
「それが何なんだ」
「お湯の中で正座をしてもらうと、疲れが取れやすいんです。絨毯織りに疲れた女性たちを元気にできるんですよ」
「本当か?」
「じゃ、アブザーイさんもやってみて下さい。男性の絨毯織りの方もおられるし、垢すりだって疲れる作業でしょう?」
「そりゃ、まあな」
「まず、背筋を伸ばして真っ直ぐに立ちます」
アブザーイは大柄なので、見上げて話さなければならない。
「床に膝をついて、静かにかかとの上に座ります。両手は膝の上に置く」
アブザーイは、ぎこちないながら言われたとおりにやってみた。
「はい、それでいいです。これを、浴槽の中でやってみて下さい」
「浴槽の中で?」
「浮力がありますから難しいですよ」
「こんなので疲れが取れるのかねえ」
「この浴場を私どもが引き受けてから是非、やってみて下さい」
アブザーイの連れふたりも、稽古してみた。
そこへ、浴場の持ち主の親方がやってきた。
「日本のお嬢さんの申し出を受けることにした。お前たち、ゴネたりしてはなんねえぞ。赤字経営の浴場を立て直してくださるってんだから。片方のヒビの入った浴槽も直してくださるそうだ。」
アブザーイたちは、様子を変えてミズホに一礼した。
「ヒビの入った浴槽? そんなこと聞いてませんわよ」
第 四 章 浴場修理、完成
そうそううまい話はころがってないものだ。
赤字経営の浴場が見つかったまではいいが、片方の浴槽にヒビが入っているとは、契約した後で聞かされた。
野川さんが事務所で苦笑いした。
「こうなったら、片方の浴場で利益が出て、もう片方のヒビの入った浴槽を修理する代金まで儲けなくちゃなりませんな」
「とんだ詐欺にあったようなものだわ」
「まだいい方ですよ。こちらが何か盗まれたわけではない」
「それはそうですけど」
「どうします? 諦めますか」
「諦めるなんて。ここまで来たからには浴場を営業して、正座教室も開きますわ」
ミズホは憤然と言い放った。
先日、体調の悪かった絨毯織りのファーサという女性の家へ行ってみる。
戸口から覗くと、薄暗い中で壁から絨毯を垂らして、せっせと絨毯を織っているファーサの姿が見えた。
「もう大丈夫なんですか?」
ミズホが尋ねるのを野川さんが通訳してくれた。
「はい、いつものことですから。一日休むと稼ぎが減ります。頑張らないと……」
「でも、身体が一番大切よ。無理しちゃいけないわ」
「ええ」
ファーサは織物の手を休めずに続ける。
「あのね。私、浴場経営をすることになりました。女性にもたっぷりお風呂へ入ってもらってマッサージや垢すりもしてもらおうと思って」
「まあ、浴場なんてぜいたくな」
「大丈夫です。少しの代金ですから。それに、日本の座り方の正座を習っていただくこともできます。その分は無料です」
「正座?」
「はい。腰痛や、身体の痛みが取れる座り方です」
ファーサはクリーム色のヒジャブ越しにチラリとミズホを見て、ため息をついた。まったく信じられていない。
そこへ、背後から若い男の声がした。
「よお」
スークの土産物屋のダヤンだ。
「ダヤン! 来てくれたんだね!」
すぐにラーナがまとわりついた。
「浴場を復活させるそうじゃないか、日本のお嬢さん」
「どうしてあなたがそれを」
「すでに市場の連中には知れ渡ってるぜ。日本の女の子が浴場を始めるって」
「まあ、噂って早いのね」
「本当に浴場の経営なんてするのか? あんた、まだ学生じゃないのか」
「大学を卒業したばかりです。イスラムの国も商売も初めてです。現地調査に来ただけのボランティアです」
「やめとけ、やめとけ、そんなド素人にこの土地の商売ができるわけない」
「そうでしょうか。やってみなければ分かりませんわ」
ミズホとて自信はない。けど、恵まれない母娘と知り合ったせいで、浴場を開業することになってしまった。座礼が正座に似ていることがきっかけだ。
ミズホはこのご縁を、偶然ではないように感じていた。
思いがけず、ボランティアの仲間やダヤンの商売仲間、お得意様の客までが、浴場修理のために募金してくれた。
ミズホは日本から持ってきたお金を全部、投入した。
ようやく、そのお金で浴槽のヒビが修理できた。
「お風呂が使えることになったわよ。ファーサ、ラーナ、入りに来てちょうだい」
ファーサの家に迎えに行くと、彼女は驚いた。
「本当かい? 本当にあんた、浴場を作ってくれたの?」
「はい。ダヤンさんとお友達も資金を出してくれましたのよ」
「お母さん、このお姉ちゃん、やると言ったらやるんだ。すごいよ。垢すりの男だって言いなりだよ」
ラーナが言った。
「ラーナ、言いなりだなんて。よほど怖い女みたいじゃないの」
「その通りだよな。怖いよな。言うこときかないと、アッラーの神様に言いつけられるぞ」
ダヤンがおどけて言った。それからミズホに向き直り、
「ミズホさん。よくやってくれた。俺からも礼を言うぜ」
「そんな。ダヤンさんたちも資金協力して下さったから実現したんですよ」
ミズホは心からありがたいと思い、一日も早く、労働して疲れている女性たちに浴場を使ってもらいたかった。
第 五 章 浴場、開業
いよいよ修理された浴場が開業され、労働階級の男も女も利用するようになる。
ミズホは入口に日本の銭湯の番台のような席を作ってもらった。
時には自分が座り、浴場の様子を見るつもりだ。
ファーサが、絨毯織り仲間の友人と浴場へやってきた。ラーナも一緒だ。
「ミズホ、来たわよ」
「いらっしゃい、ファーサ、ラーナ。ゆっくりしていってね」
女性労働者たちは、労働の後に浴槽でゆっくり温まるだけでなく、垢すりやマッサージまでしてもらえるとあって、喜んでいる。
「皆さん、もしよかったら、日本の正座という座り方を覚えて下さい。無料でお教えします。正座して浴槽の中に座ると、疲れの取れ方が更に増します」
「日本の座り方?」
脱衣場で、ミズホは正座の見本を見せた。
「へえ。これで疲れがもっと取れるの? なんだか信じられない」
「変な座り方だね。浴槽の中じゃ、もっとのびのびしたいよ」
女性たちはあまり乗り気ではない。
一週間経ったが、ミズホに正座の稽古を教わったのは、ファーサとラーナだけだった。
ミズホはがっかりした。
せっかくここまで頑張ったのだから、この国の人にも正座に馴染んでもらいたい。
夜、宿舎に帰ってから、日本の正座の師匠に電話してみた。
華世子先生という四十歳の先生だ。日本には数えきれないくらいの教室を持っている。
「どうしたの、ミズホさん。この前まで自信満々だったじゃないの。正座とそちらのお祈りの座り方が似ているって」
「わたしの考えが甘かったのですわ。座り方が似ている程度で、こちらの方が日本の正座を習ってくださると思っていたのが」
ミズホには珍しく、しゅんとしていた。
「当たり前じゃないの。座り方が少しくらい似ているからって、民族性も宗教もまるきり違うんですから、そう簡単にはいきませんよ」
華世子師匠は、ミズホを少々叱りながら余裕で言った。
「今までとんとん拍子に行き過ぎたんです。あなたは周りの皆さんにもっと感謝しなければいけませんよ。野川さん、ダヤンさん、公衆浴場を貸して下さった親方、垢すりのアブザーイさんたちなど。いい方ばかりじゃありませんか」
「はい……」
「難関はこれからです。浴槽で正座してもらえば、身体の疲れが取れることを皆さんに実感してもらうことです。これしか正座のお稽古を受け入れてもらえる手立てはありません」
「おっしゃる通りです」
ミズホは自分が思いあがっていたことを反省した。
「私、自分で浴槽の正座のお稽古してみます。浮力に勝って正座できたら疲れが取れることを、皆さんに実証してみます」
「ミズホさん、その意気だわ。今度の報告を楽しみにしていますからね」
華世子師匠は、電話を切った。
第 六 章 ミズホ、水着を着て
数日後、女性専用の浴場では、珍しい出来事が起きていた。
日本人女性の経営者が、水着姿で浴槽の横で何かの説明を始めたのだ。浴場にいた女性たちはいっせいに注目した。
ちょうど居合わせたファーサとラーナも驚いて見つめていた。
「皆さん、これから、私の国、日本の正座という座り方をご説明します」
浴槽の側に立ったミズホは、なんと真っ青のビキニ姿だった。
「まず背すじをまっすぐにして立ちます。それから静かにかかとの上に座る。もし衣服をつけているときは、膝の中に裾を折って入れ、かかとの上に座ります」
女たちは遠巻きにして見つめている。
「何だと思ったら、いつものミズホさんの正座とやらの説明か」
「何回も同じことを……」
女性たちのおしゃべりを小耳に挟んだ女性たちがあちらへ行こうとした時、ファーサが立ちはだかった。
「ちょっと待っておくれ。ミズホさんは、私たちのことを親身になって考えてくれてるんだよ。私が体調を崩して寝込んでる時も毎日様子を見にきてくれてラーナを預かってくれて、これからの私たちの力になりたいと浴場まで初めてしまった。今度は私たちがミズホさんの願いを叶えてあげる番だよ」
日頃、もの静かなファーサが必死で訴えたので、女性たちはたじろいだ。オマケに小さなラーナまで母親の前に出てきて言う。
「本当だよ、おばさんたち。お母さんはここのところ調子が悪かったんだけど、ミズホさんの言うことを聞いて浴槽で『せいざ』ってもんをしてみたら、疲れがスッと退いていったんだって。今じゃすっかり元気だよ」
「ラーナ……」
ミズホは胸がいっぱいになり、ラーナの細い肩を抱きしめた。
改めて、ミズホの正座の仕方が説明された。
浴槽に身を入れてから、もう一度正座し、浮き上がらないように頑張った。
どうしても浮き上がってしまうが、頑張って逆らった。
「これを繰り返すと、体幹が鍛えられ正座も上手になり、身体の疲れも取れやすくなります。どうぞやってみてくださいな」
女性たちは浴槽に身を浸し、のろのろと正座を始めた。
「あら、身体が浮き上がっちゃうわ」
「どうしても身体が傾いてしまう」
「やっぱり無理よ、こんなの」
「いったい、これが疲れを取るのとどういう関係があるのよ」
「やっぱり馬鹿馬鹿しいとしか思えないわ」
「やめよ、やめよ。早くマッサージしてもらおう」
女性たちは、次々に浴槽から出始める。
「あ、待ってください。皆さん。もう少しだけ頑張ってみてください」
ミズホは叫んだが、女性たちは次々と浴槽から上がり、マッサージの寝台へ向かう。
脱衣室には、見慣れぬ白く長い衣、白いターバンであごひげの男がやってきていた。
イスラム寺院の導師の使いだと名乗る。
「座礼以外の外国の座り方を指導しているとはどういうことだ」
男は怒っていた。
水着にバスタオルを巻いたミズホが急いで浴場から出てきた。
「浴場経営者のミズホと申します。この度はお騒がせしております。私は決して座礼を否定しているわけではありません。この国の特に絨毯織りの女性たちを健康にしたくて始めたことなのです」
「なんという恰好をしているのだ、女が肌を見せるとは!」
導師の使いの男は頭から湯気を出して怒鳴りつけたので、野川さんが、ミズホを脇へ引っぱっていった。
「待って、野川さん。導師さまに分かっていただかなくては」
隣の脱衣場や浴場にいた男たちも、何ごとかと覗きに来る始末で、騒然となった。
ざわざわした中で、よく通る女の声が突き抜けた。
「皆さま、お静かに願います」
日本の和装をした麗しい女性が、浴場へ入ってきた。
「あっ、華世子先生!」
ミズホが叫んだ。
それは、日本でお作法教室をいくつも開いているミズホの師、華世子師匠だ。
第 七 章 華世子師匠と野川さん
「寺院の導師さまですね。わたくしは日本で正座を教えております、一宮華世子と申します。ミズホの師です。先ほどはミズホが失礼な格好で、御前に出たこと深くお詫び申し上げます」
百合の花のような凜とした姿で華世子師匠は膝をつき、着物の裾を膝の内側に入れ、かかとの上に座った。その様は本当に神々しい。そして恭しく頭を深く下げた。
導師の眼もくぎ付けになった。
「弟子の失態はわたくしの失態です。深く深くお詫び申し上げます。寺院へ参りましてでもお詫びいたします」
「……」
導師は、ゴホンと咳をひとつした。
「誰か通訳せよ」
素早く野川さんが、華世子師匠の言葉を通訳した。
「しかし、弟子のミズホのしたことは、すべて貧しい信者様のことを思ってやったこと。どうかどうか、お許しいただけませんでしょうか。この通りです」
「師匠!」
素早く洋服を着たミズホも、師匠の背後に座り、正座して頭を下げた。
その場の騒ぎが鎮まり、一同はシンとした。
「……分かった。ミズホと申す女が、貧しい者のために浴場を開いたのだな」
導師は華世子の言葉を繰り返した。
「そうでございます。ミズホの申したことは真実でございます。二十年以上にわたり、正座を研究し教えている身です。厳しい労働に疲れた身体は、浴槽で正座をすると癒されます」
野川さんが、眼で合図を送った。
浴場の奥からアブザーイが出てきて、仲間と一緒に導師さまを取り巻いた。みるみるうちに彼を裸にして、頭のターバンまで脱がせて担ぎ上げる。
「これ、何をする、お前たち。導師に向かって!」
導師は半泣きの声で担がれたまま浴場へ運び込まれた。
「導師さま、少々手荒ですが、このまま浴槽の中で俺の教えに従って、日本の『正座』をしていただきます」
「なに~~~? わしを誰だと思っている? こんな手荒なことをしおって!」
「しかし、導師さま。聞くところによると、腰痛がひどくて、コーランが重くて、肩も痛いそうではないですか」
導師の表情がギクリとなった。
「誰がそんなことを?」
「信者のみんな知ってることですよ。では、まっすぐ立って。湯の中でもしっかり。膝をついてかかとの上に座る! そうです。そのままじっとして!」
「貴様、誰に向かって命令している! わしは導師だぞ」
「でも痛いの、治したいでしょ? 後でマッサージもしてさしあげますから」
「むむ」
導師はアブザーイに何度もダメ出しされ、ゆでだこになるほど湯舟の中で正座を頑張った。
寺院に返してもらえないまま、三日間も続いた。
ミズホが、浴場に駆けつけた。
「アブザーイさん。導師さまを開放してください。後で私たち、どんなお咎めを受けるかわかりませんよ」
「導師が腰を痛めてるってのは、本当だ。前からお忍びでこの浴場へ来ていたからな。きっと痛みが治って感謝するはずだ」
「で、でも」
尚も止めようとするミズホの背後から、野川さんが声をかけた。
「ミズホさん。アブザーイさんの言うことは本当ですよ。寺院での導師さまは、腰によく手を当ててらしたし、コーランが重くて肩が下がっていましたから」
「野川さん、そんなことまで調べていたの?」
野川さんは、パチンとウインクした。
「もしかして野川さん、華世子師匠にもお話していたのね?」
「はい、ずっと」
野川さんはメガネの奥の優しい眼でにっこり笑った。
第 八 章 痛みが治る
華世子師匠は、ボランティアの事務所でゆっくり「チャイ」を味わっていた。
「ご馳走様でした。チャイも特別なお味でよろしいこと」
ゆっくり湯のみを置くと、立ち上がっていつもの和装で浴場へ向かった。
浴場では、ようやく正座の稽古から解放された導師がへろへろになって脱衣場で座りこんでいた。
アブザーイとミズホが見守っている。
「導師様。しっかりなすって下さい。三日間通しでお稽古したわけじゃありませんから。今日の夕方から寺院に復帰してもらわなければなりません」
「今日の夕方から復帰ですって?」
「そうです。腰も肩の痛みも、正座とマッサージでいくらか治っているはずです。いかがですか? 立ってみてください」
導師は下着一枚の姿で立ってみた。
「ほ、本当だ。腰も肩も痛くない。こんなに軽く立てるのは久しぶりだ」
導師の表情は晴れ晴れとしていた。
「正座が効いたのか? だとしたらありがたいことだ! おい、垢すり男、正座の稽古をしてくれて礼を言うぞ」
アブザーイが、
「なんのなんの、正座の先生はこのおばさんだぜ。それと勧めてくれたのは、ミズホさんだ」
「正座の先生、ありがとうございました。おかげで長年苦しんできた腰痛と肩の痛みがよくなりました。これからも浴場で正座の稽古をいたします」
痛みが軽くなって心も軽くなったのか、導師様は人が変わったように優しくなった。
「ミズホさんと言ったね。よく労働者のために浴場を開いてくれた。わしからも礼を申し上げる」
ちゃんと教わったとおりに正座して頭を下げた。
ミズホも慌てて正座した。
「女性専用の浴場は、もっと数を増やさなければいけません。導師様のお力でもっと増えていきますように」
「分かりました。さっそく今夜のお祈りの言葉に添えて申します」
「ありがとうございます」
ミズホは心からありがたく思い、頭を下げた。
「アブザーイさんたち、ありがとう」
夕方の寺院には、ファーサとダヤンとラーナも来て、ミズホと一緒に正座教室の成功を祝ってくれた。
「まだまだ続けていかなきゃね」
コーランの見学に来ていた華世子師匠も、寺院の美しさと敬虔な信者たちに感激していた。
「ミズホさん、わたくし、この国が気に入りましたわ。もうしばらく滞在しようと思います」
「先生、日本の正座教室はどうなさるんですか?」
「あなたが代わりにやっておいてちょうだい」
「そ、そんな!」
ふたりは笑いあった。