[54]おすわり保育園
 タイトル:おすわり保育園
タイトル:おすわり保育園
分類:電子書籍
発売日:2019/05/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:44
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:keiko.
内容
おすわり保育園では、前代未聞の膝まくらでお昼寝が実施されていた。新米保育士の夏希が始めたのだが、一年ぶりに保育園の後継者、靖が帰ってきて驚き、大反対。園児の首によくないというのだ。
一度は引き下がった夏希だったが、遠足に行き、思わぬ出来事に遭遇する。
さて、お昼寝に正座の膝まくらを実施している保育園の運命は?
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1339563

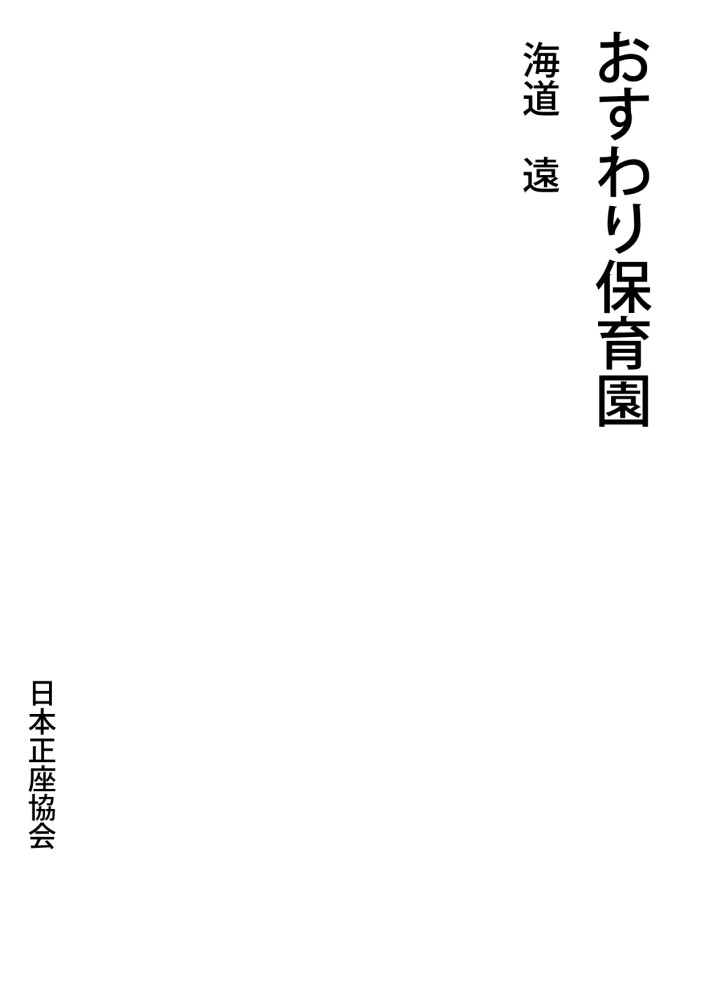
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 一年ぶり
クマとウサギのついた可愛い円柱の門をくぐると、手洗い場の横につながれていた柴犬の「おっちん」が両耳をピンと立てて、わん! と鳴いた。そしてキュウキュウ鳴いて回っている。
「おっちん、元気だったか!」
靖は、ジーンズのまま運動場の地面に膝をつき、おっちんにさんざんお帰りの洗礼を受けて顔じゅう、よだれにまみれてしまった。
「わかった、わかった、おっちん。いい子にしてたんだな。どうだ? 保育園に変わりないか? 母さんは元気か?」
靖が保育園に帰ってきたのは、一年ぶりだった。
自分が跡を継ぐべき保育園のために、大学を卒業してからすぐに他府県の保育園を武者修行に廻ってきたのだった。
「う~~ん、懐かしいなあ、おすわり保育園! 僕もここにいたのが昨日のようだ」
庭に満開だった桜も散り、すっかり葉桜になって、つつじが咲き始めようとしている。出発する時の一年前の風景と同じだ。
靖は慣れた青い屋根の保育園舎に向かって歩いていき、下駄箱の並ぶ玄関を愛し気に眺めて通り過ぎた。カラフルに色紙作品やクレヨンで描かれた園児の絵の飾られた廊下が続き、遠くからオルガンの音色が聞こえている。そして、ひとつの教室をガラッと開けた。
同時に眼を見開く。
「なんだ、この昼寝風景は!」
「どなたでしょうか?」
保育室に座っていたオレンジのバンダナから短い三つ編みを肩まで見せた女性保育士が振り向いた。園児たちは、ただいまお昼寝中だ。
「まあ、靖、お帰りなさい。連絡なしでびっくりしたわ!」
靖の背後から、人差し指で「し~~っ」としながら声をかけたのは、母親で園長の雪代先生だ。
「今はお昼寝の時間だから」
「見りゃわかるよ。だけど、このお昼寝は何なんだ?」
三歳児の園児たち十五人は、そろって女性保育士の膝を枕にして寝ていたのだ。事務員さんや食堂のおばちゃんたちも混じっている。
「母さん、いや、園長。どうしてこんな寝方をさせているんだ? うらやま……いや、ゴホン、先生たちは正座しなくちゃならないし、子どもたちも眠りにくいでしょう」
ひとりの若い保育士が園児の頭をなでながら振り向いた。先ほどのオレンジのバンダナの女性だ。
「それは……あのう」
雪代園長がやってきて、
「夏希先生、私の息子、この保育園の次期園長よ。近辺の保育園めぐりをして研修してきたの。あなたとは初めてね」
そして息子の方を向き、
「靖、こちら三歳児を受け持っていただいてる夏希先生よ。短大を卒業されたばかり」
「ああ、よろしく」
靖は、心ここにあらずの返事をして、
「で、このお昼寝のやり方は?」
「この蓮くんがですね……」
オレンジのバンダナのゆがみをちょっとなおし、夏希が説明を始めた。
「弟さんがふたりいらっしゃるんですが、お母さまの胸を赤ちゃんが。そして背中をもうひとりの弟さんが占領してらっしゃるので、蓮くんの場所は膝だけなんです。家にいる時はいつもお母さまの膝にくっついていないと不安なんだそうで、お昼寝も膝まくらでしか寝られないんだそうです。それで蓮くんにこのスタイルを始めたら、みんなもやってみるって」
「そして、みんな、このポーズが気に入ってしまったってわけか」
靖は肩をすくめて部屋を見回した。園児たちは、安らかな寝顔で満足そうに女性たちの膝の上ですやすや眠っている。中には、膝の上によだれを垂れている子、『まま……』と、寝言をもらしてる子までいる。
「僕は反対だ!」
靖の声が響き渡った。保育士たちは、ギョッとして彼の方を向いた。
「どうしてですか? みんな、こんなに気持ちよさそうに寝ているのに」
真っ先に反論したのは夏希だった。
第二章 反論
「どうしてだって? 君はこの膝まくらお昼寝のどこにメリットがあるというんだ?」
「安眠してることが一番のメリットです」
「デメリットが多すぎる。その一、園児の自立心を妨げる。その二、保育士の負担が大きい。ほら、他の仕事に動けないじゃないか。その三、板張りの正座は足が苦痛だ。その四、保育部署以外の食堂のおばちゃんや事務員さんまでが自分の仕事に支障をきたす。その五、この寝方。首に負担がかかるに違いない。膝に頭を乗せるには、首を曲げて不自然な姿勢をしなければならん」
「お言葉ですけど、靖先生、今の世の中を分かってらっしゃいますか」
夏希は表情をキリッとさせた。
「園児たちは保育園に来ている間、寂しいのです。いくら私たち保育士がお世話しても、本当のお母さまにはかないません。人肌が恋しいのです。ギュっとしてほしいのですが、一対一じゃないのでそれはかないません。なかなかお昼寝してくれない蓮くんが、たまたま膝の上でやっと寝てくれて、皆も真似して離れなくなってしまったのです。お母さまはお仕事しなくちゃいけません。保育園とは、そのためのもの」
「そ、そのくらい分かってるさ、僕だって」
「せめてものスキンシップが、人情と好奇心あふれた人間を育てるんです」
「君に説教されるいわれはない」
頭にきた靖は、むくれて保育室を出て行った。
夏希も頬っぺたを膨らませて、プイと背を向けた。
「ちょっと、靖。あの夏希先生、新任だと思えないくらいよくやってくれてるのよ。園児たちもなついているし、行動力はあるし」
息子の後を追いかけてきた雪代園長が慌てて言った。
「僕は、非合理的な膝まくらのお昼寝には反対です」
靖はスマホを触ると、父母会全員集合のミーティングのお知らせを送信した。
その夜、緊急父母会が 保育園で行われた。
とりあえずは三歳児のクッキー組とキャンディ組だけ。
「……と、いうわけで、膝まくらのお昼寝が始まったのですが、お母さま方はいかが思われますか?」
キャンディ組の担任、夏希も神妙な面持ちで参加していた。膝まくらのお昼寝に変わったことを、保護者に報告していなかったのだ。
「私たち、何も報告を受けておりませんでしたわ」
一番に口を開いたのは、派手な赤いスーツを着た亮くんママである。
「ご報告が遅れまして、その件につきましてはお詫び申し上げます」
園長先生が頭を下げた。
「反対ですわ! こんな甘えん坊な眠り方。いつまでたっても、うちの子が自立しないじゃありませんか」
亮くんママは鼻息荒く興奮している。
「でも、あの、よく眠れると思います」
夏希は立ち上がって言った。
「人肌の温かさを感じて寝るのは、とても良いことだと思います」
「先生方もそれでよろしいのですか? 担任、副担任の先生方では、人数が足りませんし、その場を離れられないでは、お昼寝の時間にはかどっていた他のお仕事ができないのではありませんか?」
「それは、なんとか年長さんの先生や事務員さんにもご協力いただいてやっております」
「そんなの、いつまで保てることでしょうね? それより、子どもたちの首は疲れないのでしょうか? わたくし、そちらの方が心配ですわ」
「そうなんです、亮くんママ。僕の知り合いに整形外科医がいますから、話を聞いてみます」
「大丈夫ですよ、園児たちはちゃんと寝返りをうってますから」
夏希が必死で反論する。
「園児さんたちの身体に関わる大切なことだ。これは引けない」
「そうね。お医者さまのご意見をきけば、安心して膝まくらのお昼寝ができますわね」
園長の雪代先生が夏希をなだめ、少し場は和らいだ。
「先生たちのご負担は申し訳なく思っています。うちの蓮が甘えん坊なもので、変なクセのせいでこんなことになってしまい……」
泣きそうな顔、小さな声でやっと言ったのは、蓮くんのお母さんだ。肝っ玉母さんのタイプでぽっちゃりと身体は大きいのだが、気の弱そうな女性だ。
「蓮くんママ、蓮くんが特別、甘えん坊なんかじゃありませんよ。お子さんはみな、甘えん坊なんです。できるだけたっぷり愛情を注いであげた方がいいに決まってます」
「あなた、ワタクシがうちの子に愛情を注いでいないとでもおっしゃりたいの?」
亮くんママが目じりを釣り上げて言ったので、蓮くんママはよけい小さくなってしまった。夏希は蓮くんママをかばうように反論した。
「そ、そんなことは申しておりません」
「何ですか、あなた、新卒の先生のクセに、保護者に楯突くおつもり?」
夏希と亮くんママがにらみ合って一触即発になったので、靖が仲に入った。
「とりあえず、整形外科医の意見と所見を聞いてから、再度、皆さまにお集まりいただくことにいたしましょう」
解散になったが、蓮くんママは、夏希にいつまでも謝っていた。
「すみません。夏希先生にご迷惑をおかけして。うちの蓮が甘ったれなばかりに」
「謝ったりなさらないでください。膝まくらお昼寝を始めてから、お母さまを恋しがって泣く子がいなくなりましたし、教室でもけんかが減り、落ち着いて遊んでくれるようになったんですよ。それに蓮くんは甘ったれなんかじゃありません。お友達と元気よく遊んでますよ」
「そうなんですか」
「靖先生と亮くんママに、絶対、分かっていただきましょう。自信をお持ちになってね、蓮くんママ」
「ありがとうございます。夏希先生」
蓮くんママは夏希に両手を握られて、やっと微笑んだ。
後日、整形外科の先生が、実際にやってきてお昼寝風景を見た後、ひとりひとりを触診程度に首を診て回ったが、
「三歳児なら、しょっちゅう動きながら寝ますから、大丈夫だと思われますが、何か異常の見られる子がいれば、すぐに医院に連れてきてください」
という頼りなげなものだった。これでは反対意見のママさんたちにしっかり膝まくらお昼寝を勧められない。夏希はがっかりした。
「医者がはっきり大丈夫、と太鼓判を押すまで、膝まくらお昼寝は中止とさせていただきます」
次の保護者会で、靖が言い渡し、亮くんママは勝ち誇ったように頭をそびやかし、夏希と蓮くんママはしょんぼりした。
第三章 遠足で
そんなある日、保育園でバスでの遠足が実施された。
園児だけが参加の遠足だ。やや遠出になるが、ハイキングコースとして知られる山地へ出かけることになった。
可愛いマスコットがカラフルに描かれた車体のバスが出発、見送りのお母さんたちは、笑顔で手を振り見送った。
三歳児にしては、年長さんと一緒のコースを頑張って登って,お弁当を食べ、下りたらしい。
無事に帰りのバスに乗り込んだまではよかったのだが―――。
バスに付き添いで乗っていた、夏希はじめ保育士さんたちのスマホが一斉にけたたましく鳴り響いた。
大きな橋の手前でバスは大きく揺れ、園児たちは悲鳴を上げた。
「地震だ!」
運転手さんが叫び、バスに急ブレーキをかける。
「きゃあっ」
「お母さん、怖いよ、怖いよ」
「わ~~ん、わ~~~ん」
揺れはかなり長かったが、皆で抱き合い、団子になってるうちにおさまった。
「みんな、ケガはない?」
クッキー組の担任、岡谷先生が叫んだ。
幸い、誰もケガはしていない。
夏希と岡谷先生とバスの運転手さんが、ほっと胸を撫でおろしたのも束の間、やがて周りが騒がしくなり自衛隊のヘリが飛んできた。
地元の消防団の法被を着たおじさんが、バスをバンバンと叩き、運転手さんが急いで扉を開ける。
「ここから一キロ先のどんぐり橋が曲がってしまったんだ。通行止めだ」
「ええっ、じゃあ、後戻りですか」
「それもできない。ここの後ろ三キロ地点で土砂崩れがあって、道が塞がれてしまってる」
「ええ?」
夏希と岡谷先生は顔色を変えた。行くもならない、戻るもならない。
知らせが保育園に入り、心配して保育園に駆けつけてきていた、お母さんたちも顔色を失くした。
「橋と山崩れの間で立ち往生ってこと?」
「どうするの、もうすぐ日が暮れるわ。あの子たち、食事はできるの? どこかで眠れるの?」
「個人のケータイがつながらないのよ。山が電波の邪魔になってるんだわ。自衛隊の無線だけが頼りで、子どもたち、ひとりひとりのことは分からない」
ざわざわするばかりだ。テレビもどうなることかと地震現場を映していたが、どんぐり橋と山崩れの間に村はなく、少しの農家があるだけでとても園児たちの歩ける距離ではない。それに余震がいつ来るか分からない。
「どうしよう、うちの子、暗闇がダメなのよ」
「食べ物は補給できるのかしら」
「おしっこ、ちゃんとさせてもらってるかしら」
「きっと泣いてるわ。バスに乗ってる大人は、三人の保育士さんと運転手さんだけよね」
「ああ、あの子にもっと優しくしてやるんだったわ」
「ほんとは、膝まくらが大好きなのよ。忙しいから『ダメ、ダメ』って言ってたけど、もっと膝まくらさせてやるんだった!」
「保育園のお昼寝だって、膝まくらさせてやれば良かった」
「亮くんママが強硬に反対なさらなければ、私は膝まくらのお昼寝は賛成だったのよ」
そんなことを泣きながら言い出す母親もいる。決まりが悪くなった亮くんママは、
「では、あの時、はっきり賛成です、とおっしゃればよかったのよ」
「なんですって、そんなことしたら、ママ友たちは分裂しちゃいます」
「今でも分裂してるじゃないの」
靖が、大きな声で、
「今、そんなことを言ってる場合じゃないです。できるだけ正確な情報を手に入れるよう頑張りましょう」
母親たちは我に返った。
夜が来た。カエルがかまびすしく鳴き始めるはずだが、地震が起こったためか、しんとしている。
どんぐり橋は曲がった後、川に落ちてしまい、山崩れも大型機械が入らないので、地元消防団と自衛隊が徒歩で近づくことしかできない。
夜、遅くなってから、遠くから懐中電灯の光が近づいてきた。
「食料、持ってきたぞ~~」
夏希たちが顔を出すと、消防団員が村人と一緒に炊きだした食料や、コンビニからできる限りの飲料やパンなど、そして毛布などをもってきていた。
夏希は、両手を合わせて拝みたいほど感激した。
「わ~~い、温かいおでんだ!」
「ジュースもある」
早速、毛布でくるまれた園児たちが、食べ物を見て目を輝かせる。
お腹を満たされた園児たちは、ひと息ついた。夏希もほっとした。しかし、余震が頻繁に起こっている。その度に園児たちの悲鳴があがる。
「また、揺れた!」
「怖い、怖いよ、お母さ~~ん」
「ママ~~~~~!」
夏希は一生懸命、園児たちを慰めようとした。
「落ち着いて、大丈夫よ。しばらくの辛抱よ」
「しばらくって?」
夏希が答えに詰まってると、甘えん坊の蓮くんが、
「そんなの、いつまでだかわかんない。泣いたって何にも始まらないぞ。ボクたちは先生の言うことを聞いておとなしくしていようよ」
そんなしっかりしたことを言ったのだった。
それでも、真っ暗のバスの中で眠れる子はなかなかいない。夏希や岡谷先生が順番に膝まくらして寝つかせようとした。
お昼寝の時にやっていたように、手のひらで背中や肩をトントンして。
すると、泣きじゃくっていた子どもが、だんだんコックリし始めた。何が起こったのか、子ども心にも心配しすぎて疲れたのだろう。
そうして、ひとり寝て、ふたり寝て、保育士たちが順番に寝かしつけていくと、全員がバスの座席で眠りに落ちた。
最後のひとりを、そっと膝から下ろすと夏希の脚はガクガクだった。
第四章 おっちんの遠吠え
翌朝、自衛隊と地元消防団の必死の復興作業のおかげで、バスの背後の道路の土砂が取り除かれた。これでバスが後戻りできる。
バスの後続の車も、一台ずつUターンし始めた。バスも狭い道路をなんとかUターンし、大木が道路に押し流された土砂でいっぱいのところを、そうっと通っていく。時速十キロくらいだ。
ガードレールがへし曲がり、少し窓から顔を覗かせると、茶色に濁った谷川が遥か下に見える。
「怖いよ、夏希先生、バス、通れるの?」
ツインテールがほどけてぐしゃぐしゃになった舞花ちゃんが、心配そうにつぶやく。
その時だった。ものすごい地響きが辺りを包んだのは!
「何ごと?」
「きゃ――!」
怖さにくっついてくる園児たちを抱きしめながら、夏希は、身体中をうちつけ、どっちが上か下か判らない真っ暗闇に落ちていった。
「うぉう~~~~、うぉう~~~~~」
保育園の庭で、「おっちん」が、なんともいえない悲しい声で吠え始めた。
あまり長く鳴き続けるので、靖が様子を見に行く。
「どうした、おっちん。落ち着け。何か感じるのか?」
おっちんは耳を寝かせて遠吠えをやめない。空を、園児たちが遠足に向かった方向をむいて一向にやめない。
「どうしたんだよ。いつもおとなしいのに」
その時、雪代園長が庭に走り出てきた。
「靖、靖、大変、来てちょうだい」
「どうした」
保育室に戻ると、母親たちも真っ青だ。
「朝、やっと土砂が取り除かれて、バスが迂回しようとした矢先、余震が起こって土石流がバスを飲み込んだらしいの」
「なんだって!」
靖も顔色を失くした。
自衛隊のヘリからの映像をパソコンで見ることができた。
山から幅一キロくらいにわたって新しい土石流ができていた。所々で埋もれた家屋の屋根や、巻き込まれた車のタイヤなどが見えるばかりだ。
「なんてことだ……」
母親たちも目を見張りながら、身をしぼってその様子を見いるばかりだ。
「どうか、舞花、生きていて」
「蓮、弟たちも待ってるわよ、無事に帰ってくるのよ」
「亮さん、お願い、生きていて」
母親たちは口々に泣きながらうめくばかりだ。
おっちんの遠吠えが、よけい甲高くなってきた。
「よしっ」
靖は、庭へ飛び出し、自分のジープのエンジンをかけた。そして、おっちんのリードを持ち、一緒に乗り込んだ。
「靖、どこへ行くの」
「決まってるじゃないか、あの現場だよ。これ以上、指をくわえてじっと待ってられない」
「でも」
「ほら、おっちんがさっきから子どもたちを心配して行きたがってる」
言うが早いか、靖はおっちんだけを乗せ、ドアを閉めてジープを出発させた。
(ひと山越えれば、現場に着ける。子どもたちを救うのが、保育園をやっている俺の使命だ!)
しかし、現場へ到着するのも困難だった。市街は地震のために倒れた住宅や塀、樹木などで満ちている。ジープが通るのは至難だった。あちこちで住宅が泥に飲まれ、避難する人々の列。
靖がやっと到着したのは、もう陽が山の端に沈んだ頃だった。とっくにジープは投げ出し、おっちんとどろどろになって土砂の中を暗闇にまぎれて歩いている。
持っているのは大きい懐中電灯とスコップだけだ。
その光を見つけた自衛隊員が泥の中を叫びながらやってきた。
「君、ここは危険だ、立ち入り禁止区域だ、すぐに退去しなさい」
「しかし、僕の保育園のバスが、この泥に巻き込まれて」
無理やり退去させられそうになった時、おっちんが、キューン、キューンと鳴きながら泥でできた小山を掘り始めた。
「どうした? おっちん」
靖が懐中電灯をあてると、おっちんがオレンジ色の見覚えのあるバンダナを引っ張り出してきた。
「これは、夏希先生の……」
さらに泥の中からバスに描いてある可愛いマスコットの色が、少しだけ見えた。
「ここだ!」
靖は無我夢中で掘り始め、自衛隊員が大隊に連絡した。
第五章 無事に
奇跡的にバスから園児全員と大人三人が無傷で救出された。ストレッチャーでひとりずつ病院に運ばれたが、全員まったく無傷だった。知らせを聞いた園長と保育園の母親たちは、すぐさま病院に直行した。
子どもたちは母親に会うと泣きもせずケロリとしていた。母親たちは大泣きしながら我が子を抱きしめた。
「よくぞ、無事でいてくれたわ」
「うん。夏希先生がね、バスの背もたれをお母さんのお膝だと思ってしがみつきなさい! って、大声で叫んだんだ」
蓮くんは落ち着いて言い、少し向こうのベッドにいる夏希と顔を見合わせた。
聞いていた母親たちは、夏希と蓮くんを交互に見て呆気にとられた。その表情はみるみるうちに感謝に輝いた。
「夏希先生がお昼寝の姿勢を膝まくらにして下さったおかげで、子どもたちにしがみつく根性とコツができたんだわ」
「そうだわ、まさしくそうよね!」
口々にママたちは夏希にお礼を言った。
「そんな。私はただ無我夢中で子どもたちをどうしたら守れるか、と思っただけです」
「夏希先生。僕からもお礼を言います。そしてお詫びと。膝まくらお昼寝が、命を救うことに役立つことだったのに、僕は反対してしまい……」
「靖先生、今回は誰より、おっちんのお手柄です。もう少し遅れていたら、バスの中の酸素は無くなっていたんですもの」
病院の窓の下で、おっちんは自衛隊員にリードを持たれて見上げている。靖が窓を開け、
「おっち~~~ん。皆、元気だぞ! お前のおかげだぞ!」
「ちょっと、靖先生、そんな大声で呼ばないでくださいな」
顔を真っ赤にして夏希が慌てた。
「どうして?」
靖が少し考えてると、園長先生が、
「名前よ、名前」
「あ、そうか、ごめんごめん、夏希先生。どうしてこんな名前つけたのか、僕、分からないんだよ」
「分からない、じゃないわよ。靖」
園長先生が笑いをかみ殺して言った。
「あなたこそ小さい時、膝まくらばかりしてお昼寝してたから、その思い出に犬におっちんて名前をつけたのよ。お母さんの実家の地方では、おすわりのこと、おっちんていうでしょう。だから保育園も『おすわり保育園』」
「あ、そっか、そっか」
靖は頭をぼりぼり掻いた。偉そうに一人前の顔をしていても、お袋さんには頭が上がらないのだ。
「じゃあ、もともとうちの保育園は『膝まくら』と関係あったのですね」
夏希がクスリと笑いながら言うと、雪代園長先生はにっこり答えた。
「そうなのよ。なんだか不思議なご縁ね。私も靖のお昼寝の時には正座して、ずいぶん痺れてしまったから、痺れない極意も習得ずみよ。ちゃんと保育士さんにも伝授しなくてはね」
「それは、すぐにでも教えてください!」
園長先生と夏希は笑いあった。
こうして笑いあうことができるのも、今度の地震で犠牲者が出なかったこと、家屋の損害も推定よりは大幅に少なかったからだ。
「みんなもケガがなくて本当に良かったわねえ。まずはおうちに帰って、思い切りお母さんのお膝で膝まくらしてもらってね」
「は~~~い!」
それから一週間。
そのあいだ、おっちんのおちゃわんの中には特級お肉のドッグフードが山盛り入れられた。
「靖先生、もうダウンですか。五分も経ってませんよ。正しい膝まくらは、まず、しっかりとした正座からです!」
ストップウォッチを持った夏希が保育園の床の上でへばっている靖先生に向かって怒鳴っている。
「だって、床で痛いんですよ。それに俺、筋肉を曲げているのが辛くて……」
「何を泣きごと、言ってらっしゃるんですか。お昼寝は最低一時間半ですよ」
「そんな……、せめて座布団を敷かせてくださいよ」
「ダメです。座布団など敷いたら、膝の位置が高くなって、本当に園児たちの首に負担がかかってしまいます」
「…トホホ……」
「お母さまから痺れの防止策を教えていただいたでしょ」
「痺れどころじゃないよ、これは! 向こうずねが折れそうに痛い! たまらん、痺れの方がまだマシだ!」
「ダメです、すべては園児のため」
「夏希先生、君、厳しいんだねえ……」
泣きべそをかきながら洩らす靖が窓の外へ目をやると、園児たちに囲まれて、おっちんが美味しそうに特級ドッグフードをもりもり食べていた。








