[17]あなたのお悩み解決します! ~不良と正座とお茶会と~
 タイトル:あなたのお悩み解決します! ~不良と正座とお茶会と~
タイトル:あなたのお悩み解決します! ~不良と正座とお茶会と~
分類:電子書籍
発売日:2017/02/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:64
定価:200円+税
著者:文里 荒城
イラスト:時雨エイプリル
内容
校内で不良と恐れられている斉藤辰也は、茶道部部長の渡里撫子に片思いをしている。
しかし二人に、ほとんど接点はない。
そのため少しでも彼女に近付きたいと、辰也は茶道部主催のお茶会への参加を決める。
だが辰也は正座ができなかった。練習するも上手くいかず、お茶会は日に日に迫ってくる。
焦った辰也は、悩みを解決してくれると校内で噂されている『お悩み相団』へ「正座ができるようになりたい」とメールをするのだが……?
販売サイト
販売は終了しました。

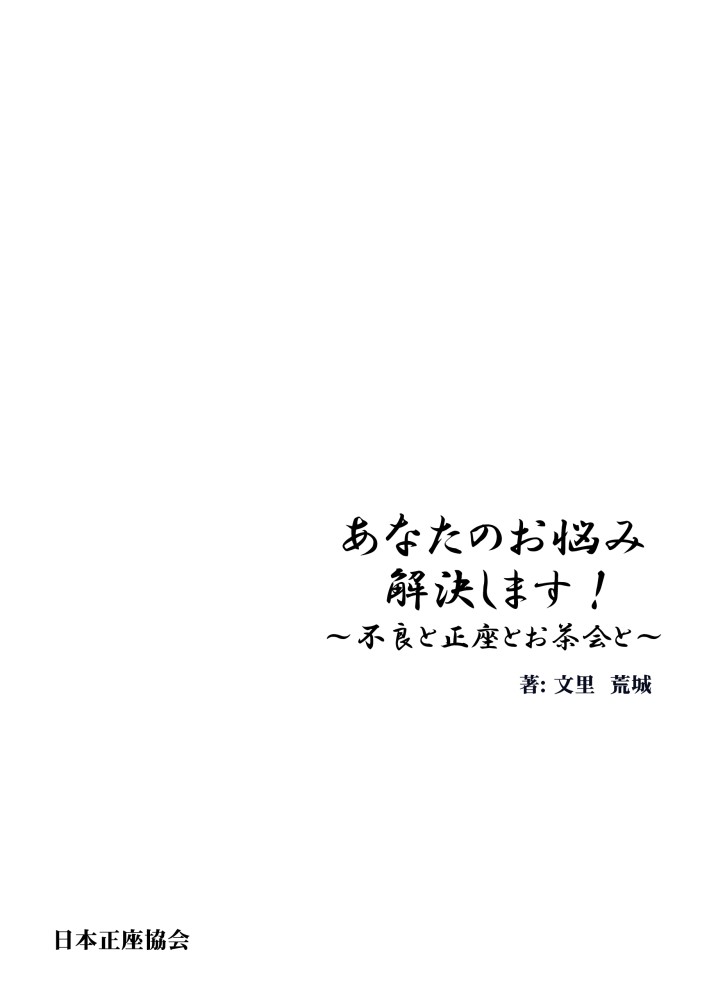
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
夕陽丘高校の北校舎四階。薄暗い廊下の一番奥に、その教室はある。
一歩足を踏み入れれば、正体不明のラップ音が響き渡る。幽霊が出るという噂もある。
そのせいでこの教室は、もう随分と長い間使われていなかった。生徒どころか、教師ですら近付かない。
――だが、その教室に、制服を着た一人の少女の姿があった。
少女は分厚い眼鏡の下の目を細めながら、イスに座って、スマートフォンを操作している。
「『田中君に告白したいです。三年C組、馬場』。えっと、次は……『バスケ部の一年です。先輩からレギュラーの座を奪いたいです。助けてください。一年A組、井上紀彦』。それから……」
唇から紡がれる声は、自信なさげにか細い。
彼女はメールを読み上げる度に、ちらりと視線を上げる。微かに首を動かすその動きにつられて、胸辺りまでの長さがある重い三つ編みが揺れた。
と、同時に、パキ、という音が教室に鳴り響く。断続的に続く音は、しかしどこから発生しているのか、何が原因なのか、分からない。
「ま、待ってください。そんなに急かさないでくださいよぅ……」
教室には、少女一人の姿しかない。それなのに彼女は、誰もいない空間に向かって、そんな情けない声を上げた。
「ちゃ、ちゃんとこうやって読み上げてるし……ユウカさんの言う通りにだってしてるじゃないですか。この間もチラシ作り頑張って……ひゃっ」
パチパチと教室中に音が駆け巡る。偶然なのか、窓から勢いよく風が吹き込み、埃っぽいカーテンを激しく揺らした。カーテンの揺れ動く様は、まるで見えない生き物が暴れているかのようだ。
「うぅ……く、口答えなんてしてません……」
今にも泣きそうに眉尻を下げ、少女は呟く。
「読みます、次のメール読みますからぁ……」
窓の外から聞こえる放課後の喧騒と、教室に響くラップ音。その隙間を縫うようにして、少女は言う。
そして改めてスマートフォンを操作する。メールの受信画面を開き、未読のそれに目を通して、内容を読み上げようとする。
「あれ……この差出人って……」
けれど少女は、メールの内容を読み上げるより先に、きょとんと目を瞬かせた。
2
放課後になり、廊下には、帰宅しようと談笑しながら歩く女子生徒二人の姿があった。
楽しそうに話していた彼女達は、人の気配を感じたのか、ちらりと背後を振り返る。
そしてぎくりと、顔を強張らせた。
それから慌てたように壁際へ寄る。
女子生徒らが寄ってくれたおかげで、廊下には道ができた。
その空間を横切って男子生徒――斉藤辰也は廊下を進む。
通り過ぎた辰也は、歩きながらも背中に視線を感じて、その居心地の悪さに苦渋の表情を作った。
ただでさえ目つきの悪い顔が、それにより、さらにキツいものへ変わる。どれくらいキツいかというと、辰也が歩いてくると気付いた生徒らが、慌てて道を空けるくらいだ。
辰也のコンプレックスは、人相の悪い自分の顔だった。この顔のせいで色々と苦労した。街で因縁をつけられたことは、一度や二度ではない。色素の薄い地毛の茶髪も、辰也の人相と相まって、校内での辰也の立ち位置を、不良に格付けている。
おかげで、まだ入学して三ヶ月ほどだというのに、辰也は見事、生徒らから避けられていた。
そうやって一定の距離を置かれながら廊下を歩いていた辰也は、階段へ差し掛かった。そのまま辰也は早足で、階段を上ろうとする。
「斉藤君」
するとおっとりとした声が、辰也の名前を呼んだ。
その声に辰也は息を呑む。大きく心臓が跳ね上がり、足を止めると勢いよく顔を上げた。
「わ、渡里、先輩……」
見れば、一人の女子生徒が――渡里撫子が、ゆっくりと階段を下りてくるところだった。
「どこか行くの?」
整ったその顔に柔らかな笑みを浮かべ、撫子は辰也の隣で足を止める。小さな顔の横には、可愛らしくまとめられたお団子。
「え? な、なんででッスか?」
「上に行こうとしてたみたいだから」
「あ、いや、べ、別に何もないッスよ。それより先輩は、今から部活ッスか?」
思わず口調が早口になってしまうのは、階段を上ろうとしていた理由を誤魔化すためでもあったが、何より、彼女に話しかけられたことが嬉しかったからだった。心臓がドキドキして、顔が熱くなる。
「うん、そうなの」
そんな辰也に対して撫子は、穏やかな口調で答えた。微笑む姿は、可憐な花を連想させて、それがさらに、辰也の心臓を落ち着かなくさせる。
「が、頑張ってください」
「ありがとう。それじゃあ」
優しい笑顔と共に、撫子は片手を振ると、階段を下りて行く。
「あ、そうだ。斉藤君」
だが不意に、撫子は立ち止まると振り返った。
撫子の背中を見つめていた辰也は、突然振り返った彼女に驚く。
「明日なんだけど……」
撫子は、辰也を見上げて形のいい唇を開く。が、すぐに、どこか困ったように笑った。
「……なんでもない。じゃあね」
そして撫子は、スカートの裾を揺らしながら、階段を下りて、行ってしまった。
辰也はしばらく、その場から動かなかった。
撫子の顔を見ることができた。他愛のない世間話程度であるが話ができた。それだけのことが嬉しかった。
「明日……」
辰也は呟き、持っていた鞄の持ち手を強く握り締める。
それから何かを決意するかのように、勢いよく階段を上り始めた。
3
「あの、今度茶道部の主催するお茶会があるの。よかったら、どうかな?」
数日前、撫子にそう言われながら手書きのチラシを渡されたとき、辰也はあまりにも驚きすぎて、普段は鋭い目を丸くさせることしかできなかった。
「オレ……ッスか?」
「うん。そのお茶会でわたし、部長引退だから。色々な人に声を掛けてて」
思わず聞き返した辰也に、撫子はそう答えた。
それを聞いて、撫子にドキドキしながらも辰也は、何故彼女が自分に声を掛けたのか納得する。
むしろそんな理由がなければ、お茶会という場に、不良と噂されてみんなから避けられている自分を、誘うわけがないのだ。
「もし暇だったら、来てね。それじゃあ」
撫子はそう言って笑うと、小走りで去って行った。
その後ろ姿と、反射的に受け取ったチラシを、辰也は交互に見る。
色取り取りのペンが使われ、可愛らしいイラストの添えられたチラシは、あまりにも自分に不釣り合いだった。
しかもお茶会なんてものに、辰也は興味を持ったことなどない。そんな場に自分が似合うとも到底思えない。
けれど……。
辰也はじっと、チラシを見る。
このお茶会に参加すれば、これを機にもしかしたら、撫子と距離を縮めることができるようになるかもしれない。
せっかく撫子から直接誘われたのだ。誘ってくれたその気持ちを無下にしたくない。その理由が例え、ただの人数合わせだとしても。
そのため辰也は、数日後に開催されるお茶会への参加を決めた。
……の、だが。
ぴりぴりと、まるで電流を流されたかのような足の痺れに、辰也は呻き声を上げながら地面に倒れ込んだ。
「いっ……」
倒れた衝撃で、さらに痺れが強くなる。といっても強くなったのは一瞬なのだが、その一瞬の痺れの強さは、通常の比ではない。
悶絶して動けない辰也の頭上には、綺麗な青空が広がっている。少し目線を上げた向こうに見えるフェンスの下には、部活動に勤しむ生徒達のいるグラウンド。
辰也は、夕陽丘高校の屋上にいた。
撫子にお茶会へ誘われたあの日から、辰也は放課後になると、毎日ここに来ている。
というのも、正座の練習をするためだ。
お茶会では、ずっと正座をしていなくてはいけない。そのため辰也はまず家で、試しに正座をしてみた。しかしこれがなんと、五分ももたなかった。
三分も経てば膝が痛くなり、五分もすれば両足が痺れに襲われる。
それから辰也は、正座の練習をする毎日だった。場所に屋上を選んだのは、単純に人がいないからである。屋上は原則、生徒の立ち入りが禁止なのだ。
家族にも練習姿を見られたくないため、辰也にとって屋上は、練習場所として最適だった。
だがこの数日間、正座の練習をしてみたものの……十分は我慢できるようになったが、それ以上の正座は、未だにできないでいる。
足の痺れが治まってくるのを感じながら、辰也はハアと大きく溜め息を吐いた。
「こんなんで明日行けるわけねぇよ……」
明日が、そのお茶会の日だった。
だが今のままでは、参加しても格好悪い姿を見せるだけだ。
「どうすりゃいいんだよ……」
辰也は項垂れる。屋上に自分以外いないため、どれだけ情けない声を上げても、誰かに聞かれることはない。
――はずだった。
「あの……斉藤辰也、さん?」
「ッ!?」
突如名前を呼ばれて、反射的に辰也は起き上がる。が、足の痺れはまだ完全に治りきってはおらず、起き上がった衝撃により痺れが足先から頭の先までを電流のように流れ、辰也は息を呑んで悶絶した。
「だ、大丈夫ですか?」
そんな辰也の姿に、辰也に声を掛けた誰か――声音からして少女だろう――が、駆け寄って来る。
「だ、大丈夫だ!」
情けない姿を見られた羞恥で顔を赤くしながら、辰也は近付いてくる少女を見た。
ひと昔前の真面目を絵に描いたような、三つ編みの髪型。分厚い眼鏡。気弱そうな顔。
地面に倒れ込んだ辰也は、そんな彼女を見上げる形になっている。スカートの丈が短ければ、咄嗟に目を逸らしてしまうような事態になっていただろうが、彼女のスカートが長いおかげで、そんなことにはならずに済んだ。
「お前、確か同じクラスの……えっと……」
クラスメイトであることは覚えているのだが、喋ったこともないため咄嗟に名前が出てこない。
「叶紬です」
そんな辰也の心情を悟ったのだろう。おどおどと少女、叶紬は言った。
それから紬は、足の痺れで動けない辰也を見て、何やら納得したように頷く。
「やっぱり、あのメールは斉藤さんなんですね」
「メール? 何のことだ?」
「茶道部主催のお茶会までに、正座ができるようになりたい」
紬から紡がれる言葉に、辰也は驚いた。
その文には覚えがある。何故ならそれは、辰也がメールで送った文章、そのままだったからだ。
「なんでお前がそれ……」
事態が掴めずに辰也が尋ねると、怯えたように紬が肩を竦める。驚きのあまり、尋ねる辰也の声は低くなり、彼女を見る目も睨むようなものになっていたらしい。
それでも紬は、視線を彷徨わせつつ、か細い声ながらも、答える。
「あの……お、お悩み相団から派遣されて来ました。あなたのお悩み、解決します」
そう言って紬は、「よろしくお願いします」と辰也に頭を下げた。
4
夕陽丘高校には、ある噂がある。
とあるメールアドレス宛に自分の悩みを送ると、それを解決してくれる『お悩み相団』という存在。
それはただの噂だが、生徒はもちろん、教師の間でも囁かれているほど、有名だった。友人のいない辰也ですら知っているくらいだ。
ちなみに相談ではなく相団なのは、悩みを解決するための団体として、相談の談と団体の団を掛けているかららしい。が、あくまで噂であるし、辰也はそんなことに興味はない。
とにかく。
あまりにも正座ができず、このままではお茶会に参加できないと危機感を覚えた辰也は、藁にも縋る思いで、噂を実践した。お茶会までに正座ができるようになりたい。そうメールをしたのが昨日のこと。
そして今日――お悩み相団から派遣されたと、紬がやって来た。
本当にお悩み相団から派遣されて来たのか、紬に対して疑問は残る。しかし彼女は、お悩み相団しか知らないはずの、辰也が送ったメール内容を知っていた。そのためひとまず辰也は、彼女を信じることにした。
場所を変えようと言った紬と共に、辰也は屋上を出た。そして彼女が、練習場所として辰也を連れて来たのは。
「えっと……ここで練習、しましょう」
「こ、ここって……幽霊教室じゃねぇか!」
教室の扉を開ける紬へ、思わず辰也は叫ぶ。
幽霊教室とは、入るとラップ音が鳴ったり、幽霊が出ると噂されている、誰も近付かない教室だ。辰也も、この教室に来たことはない。
「い、嫌ですか?」
「そりゃ……」
言いかけて、辰也は言葉を飲み込む。
ここで頷けば、まるで幽霊が怖いと、泣き言を言っているかのようで、情けない。
「……お前は怖くねぇのかよ」
「私は、別に。ここだったら絶対誰にも見つからないと思いますし……電気もあるから、暗くなっても大丈夫です」
辰也へ答えた紬は、教室の扉を開けると、先に中へ足を踏み入れてしまう。
先々進んでしまう紬を引き止めることもできず、一瞬迷うような素振りを見せたものの、辰也は自分も、幽霊教室へ入った。
紬がここまで動じないのだ。もしかすると、ラップ音だのという噂は、嘘なのかもしれない。
――だが。
辰也が教室へ入った途端、正体不明の音が教室に響き渡った。
教室へ足を踏み入れた辰也の動きが止まる。
「では、えっと……」
しかし紬はラップ音を怖がる様子もなく、窓際に立つと、辰也へ振り返った。このラップ音は彼女には聞こえていないのか。そう思えてしまうほど、紬は怖がる様子も、冷静さを失う様子もなかった。
「は、始めましょうか」
辰也を怖がっているらしく、おどおどしている、紬。そんな彼女が怖がっていないのだから、この教室は怖い、嫌だ、なんて辰也が言えるはずもなく。
「……あ、ああ」
渋々ながらも辰也は、埃っぽい教室の真ん中で、正座の練習を始めることになったのだった。
「で、では、えっと……。あ、はい。まずは、斉藤さんがどれくらい正座ができるのか、見せてください」
遠慮がちに紬に言われて、辰也は床へ腰を下ろす。鞄を横に置いてスニーカーを脱ぐと、膝を曲げ、折りたたむようにして、足に体重を乗せる。手は適当に、膝の上へ。
特に会話をすることもなく、無言で辰也は、正座を続ける。その間にも、ラップ音は鳴り続いていた。必死に辰也は、その音を意識から追い払う。
……そして、五分が過ぎた頃。
「っ……」
辰也は表情を歪め、眉根を寄せた。
足が重くなり、感覚がなくなる。痺れの前兆だ。
しかしここでやめるわけにはいかない。身動き一つせず辰也は、このまま何事もなく、感覚が元に戻ることを祈る。
だが、辰也の願いも虚しく。
「ぐっ……」
不意に、辰也は頬を引き攣らせた。
痺れとも痛みともつかない感覚が、足の先から太ももにかけてを一気に流れる。
呻き声と共に、辰也は硬直した。ほんのちょっと動くだけで、一気に地獄を見ることになる。
「……十分と、少し。これは……」
そんな辰也を見ながら、紬が何やら視線を彷徨わせる。まるで誰かに教えを乞うように。もちろんこの教室にいるのは辰也と紬だけなので、彼女が教えを乞う相手はいないのだが。
「んだよ、文句あんのか……?」
びりびりとした痺れに悲鳴を上げそうになりながら、辰也は紬を睨んだ。
正座ができるようになりたい、そうお願いしたのは辰也だが――だからといって、こんな姿を見られるのは、恥でしかない。その羞恥を誤魔化そうと、思わず凄んでしまった。
「そ、そそそ、そんなつもりは……!」
対して紬は、ぶんぶん首を左右に動かす。辰也に怯えているのは明白だった。
しばらく耐えると、痺れは治まる。ちらりと辰也が紬を見れば、彼女は遠慮がちに頷いた。もう一回やれ、ということだろう。
それを辰也は、ラップ音を聞きながら、何度も繰り返した。
その間紬は、何かを言いかけたり、「で、でも……」と自問自答のような、よく分からない独り言を言っていた。
その度に、辰也はイライラする。始終鳴り響くラップ音も耳障りだ。
紬は一体、何のために自分をここに連れて来たのか。というより、お悩み相団として、辰也の悩みを解決してくれるのではなかったのか。
紬はただ、離れたところから辰也を見ているだけ。これでは、一人で練習していたのと何も変わらない。むしろ、足が痺れて悶絶する恥ずかしいところを見られていることを考えると、一人での練習の方がマシだった。
チッ、と辰也は舌打ちをする。
きっと自分は、紬に騙されたのだ。腹の内で彼女は、情けない辰也の姿を見て笑っているに違いない。
足の痺れの前兆を感じると同時に、辰也はバン! と床を叩いた。
視界の端で、びくっと大袈裟なほど、紬が体を跳ねさせる。
「さ、斉藤、さん……?」
「やってられっか! こんなこと!」
辰也は少しよろめきながらも立ち上がると、乱暴にスニーカーを履き、鞄を持った。そのまま教室を出て行こうとする。
「何が協力します、だ! お前何もしてねぇじゃねえか! これだったら一人のがマシだ!」
「あ、あの、待……」
「うるせぇ!」
背後で紬が足を踏み出す気配がした。が、辰也が怒鳴ると、それは止まる。
紬は辰也を怖がっている。怒っている辰也を無理に引き止めることなどできないに違いない。
みんなそうなのだ。辰也は何もしていないのに、勝手に怖がる。もしくは睨んでいると勘違いをして怒ってくる。もちろん辰也は、自分の話し方にも問題があることは自覚しているが、それにしても、だ。
だから、撫子だけだった。自分のことを怖がらないでいてくれるのは。真っ直ぐに自分を見てくれるのは。
そんな彼女に誘われたお茶会へ、行かないわけにはいかない。もう正座の練習ができる時間もほとんどないのだ。早く屋上に戻って、一人で……。
「そんで一人で練習して、どうにかなんの?」
「……え?」
教室の扉に手を掛けた辰也は、聞こえてきた声に目を瞬いた。
その声は、紛れもなく紬のもの。けれど、喋り方も、雰囲気も、ついさっきまでの彼女とは違っていた。
扉に手を掛けたまま、辰也はゆっくりと振り返る。
背後に立っている紬は、いつの間にか眼鏡を外して、近くの机の上にそれを置いていた。そのまま彼女は、辰也が見ている前で三つ編みを解く。胸辺りまでの黒髪が、カーテンと共に、窓から流れ込んでくる風に揺れた。
「練習しても正座ができなかったからメールしてきたんだろ? 明日までにできるようになんの?」
「それは……」
堂々とした、強気な表情の紬に圧倒されて、辰也は言葉を失くす。
実際、このまま一人で練習を続けて正座ができるようになるかは、分からない。
「けどお前といてもそれは変わらねぇじゃねえか。つかなんでそんないきなり変わって……?」
「あたしのことはどーでもいい。……ま、あたしからしても、あんたのことはどーでもいいけどさ」
両腕を組んだ紬は、大股で辰也へ歩み寄る。
「あんたがお茶会に参加できなくても。撫子さんと接点の持てる機会を失っても」
「っ!?」
眼前で足を止めた紬に見上げられながら、辰也はぎょっと目を剥いた。
「お、おま……な、なんで、それ……!」
「あんたがメールに書いたんだろ」
紬に言われて、そういえばそうだったかもしれない、と辰也は思い出す。お悩み相団へのメールには、解決したい悩みと理由も細かく書く方がいい、といわれているからだ。
「お、お前、そのこと絶対誰にも言うなよ!?」
顔が赤くなるのを自覚しながら、辰也は紬を睨み、怒鳴る。
対して紬は、にっこりと笑った。
「もちろん」
おどおどと気弱な様子もなく、勝ち気な笑みを刻んだ唇で、彼女は答える。
「でも、そうだな。このまま逃げるんだったら、うっかり口を滑らせることもあるかもな」
辰也は絶句した。その脅しに対して。突然豹変した紬に対して。
「で。出てくの?」
紬からの質問に、辰也は答えられるはずもなかった。
5
結局辰也は、幽霊教室で正座の練習を続けることになった。
教室の真ん中で正座をする辰也の前には、両手を腰に当てた紬が立っている。
「まずあんたは、姿勢がダメだ」
「姿勢?」
「背筋を伸ばせ。で、手は太ももの付け根と膝の間に置く。肘を伸ばして……手は重ねない。八の字だ。膝もくっつけずに、少し開いて」
紬はテキパキと、辰也の体を触って姿勢を変えていく。
「重心は少し前にして、かかとと足の甲に体重を掛け過ぎないように」
紬の指示を意識して、辰也は背筋を伸ばし、体重の掛かる位置を調整する。それだけでなんだか、格好よく正座ができている気がした。
「それが正しい正座。よし、始め」
辰也が頷けば、紬は近くのイスに腰を下ろして、足を組んだ。
「……さっきは悪かったな」
「何がだ?」
無言で正座をしていた辰也は、不意に紬に話しかけられて、聞き返した。
「協力するって言ったのに、確かにちゃんと指示とかできなかったから。人見知りでさ。ごめん」
「いや、別に……」
先ほどはイライラしてしまった辰也だが、時間の経った今では落ち着いている。
「でもあんたのダメなところもちゃんと分かった。例えばその足。あんたずっと同じ足に体重掛けてるだろ」
「え?」
指摘された辰也は、思わず自分の足を見下ろした。そんなつもりはなかったのだが……。
「別にずっと同じ姿勢をする必要はない。むしろ定期的に重心は変えてもいい。あんまりもぞもぞするのは見た目が悪いけど、たまになら大丈夫だから」
「なるほど……」
「同じ足に体重を掛けることで血流が圧迫される。それが痺れの原因だ」
紬に頷き、辰也は意識的に、重心の位置を変える。
「……そういえば、あんたどーして撫子さんのこと好きなの?」
暇だったのだろうか。「今日はいい天気だね」とでもいうような軽い口調で、紬が尋ねてきた。
唐突な質問に、辰也は反射的に吹き出す。
「なっ……」
「あ、言いたくなかったらいーよ。単純な好奇心だから」
紬は笑いながら、顔の横で片手を振った。
そんな彼女を横目で見た辰也は、顔を背ける。辰也が何も言わなければ、教室は沈黙に包まれた。
「……前、あの人が変なやつに絡まれてるとこ、見かけたんだ」
沈黙が居心地悪く、また、暇だったこともあり、辰也はぽつりと口にした。
どうせ紬には、撫子を好きなことはバレている。それに――今の彼女は、辰也を怖がっていない。怖がらず、自分を見てくれている。辰也はそれが嬉しかった。
「それを助けたんだ? 優しーじゃん」
「別にそんなつもりなかったけど。ただああいうの、見ててイライラするだけだ。そんでたまたま、ここで再会して。先輩、オレに話しかけてくれるようになって。それが――嬉しくて」
同じ学校の先輩と後輩だなんて、辰也は知らなかった。偶然の再会を、辰也は初め、なんとも思っていなかった。
けれど撫子が会う度に、自分を怖がらずに話しかけてくれるのが嬉しかった。校内で唯一、彼女だけが自分に優しくしてくれた。そして気付けば、好きになっていた。
「先輩は部長だから、お茶会のチラシを配ってた。オレにチラシを渡したのも、部活だから。でもオレは、誘われて嬉しかった。先輩の最後の茶道部としての姿見てぇし、オレもいいとこ見せてぇ」
一度話し出すと、言葉はするすると出てきた。口調にも熱がこもる。
「そっか」
しかし、優しく目を細め、どこか楽しそうに打たれた紬の相槌を聞いて、辰也は我に返った。
「っ、そ、それより、お前なんか調子乗ってねぇか!? さっきまであんなびくびくおどおどしてたくせによ!」
顔が熱くなるのを感じた辰也は、それを誤魔化すように、紬へ怒鳴る。
すると紬は笑いながら肩を竦め、イスから立ち上がった。
「あたしトイレ行ってくる。あたしが戻るまで正座、頑張れよ」
紬は机上の眼鏡を手に、笑いながら教室を出て行った。
紬が教室を出て行くのを見送り――ふと辰也は、幽霊教室に一人取り残されてしまったことに気付く。
体には思わず緊張が走った。だが。
「……あれ」
そこで初めて辰也は、あんなにうるさかったラップ音が、いつの間にかなくなっていることに気付いたのだった。
6
それから十分後。
「お、お待たせしてすみません……」
遠慮がちに、外から教室の扉が開かれた。
そこから顔を覗かせたのは、眼鏡と三つ編みの少女、紬である。彼女は気弱そうな表情と共に、辰也のいる幽霊教室の中を覗き込んだ。
それを見て、辰也は怒鳴るような声を上げる。
「おい!」
「ひっ」
鬼のような形相の辰也を見て、紬は怯えたように息を呑んだ。悲鳴を上げなかったのは、恐怖のあまり声が出なかったからだろう。
「さ、さっきは偉そうなことばかり言ってごめんなさ……!」
それでも必死に声を絞り出し、紬は勢いよく頭を下げる。
そんな彼女に、辰也は続けて、叫んだ。
「見ろ! オレ、足痺れてない!」
「え? ……あっ!」
嬉々として叫んだ辰也に、紬は一瞬、ぽかんとした。が、すぐに、辰也が未だに正座をしているのを見て、表情を驚きのものに変える。
「す、すごいです、斉藤さん!」
喜ぶ紬に、辰也も笑顔で頷いた。
紬に姿勢やらを正されて、もう二十分は経過していた。それなのに足は痺れていない。
嬉しそうに教室へ入ってくる紬を見て、辰也は床に手をついて立ち上がろうとした。
……が、その瞬間、足を痺れが襲う。
「いっ……!」
中途半端に腰を上げた状態で、辰也は動きを止めた。
「さ、斉藤さん、足の痺れを抑えるには、地面を蹴り上げるといいそうです! その衝撃によって、血流が一気に流れだすとかなんとか……!」
「こ、この状態で蹴り上げるとか、拷問かよ……」
辰也が呟くと同時に、先ほどまで治まっていたラップ音が、再度鳴り出した。それに辰也はぎくりと体を硬直させる。だがその動きが痺れを増長させ、低く呻いた。
「あ、あとは膝裏をマッサージしたり、足の指を手で反らすのも効果があるみたいです! 他には、えっと、正座してる最中に足が痺れてきたら、正座したまま、つま先だけを立てて床につける方法を……その、跪座っていうらしいです! それをしたらいいかと!」
「先に……言ってほしかった……」
焦る紬の説明を聞きながら、辰也は痺れに悶絶する。
けれど、お茶会へ参加する大きな一歩を踏み出したことが、嬉しかった。
7
気付けば外はもう暗く、完全な下校時刻になっていた。
辰也と紬は、並んで校舎を出て、校門へ向かう。
「それでは斉藤さん、明日、頑張ってください」
校門を出たところで足を止め、紬は言った。
「ああ。今日はサンキュー。本当に助かった」
「いえ、私は何もできませんでしたし……」
「正しい正座のやり方とか教えてくれたじゃねぇか」
そう言いながら辰也は、じっと紬を見る。
「あ、あの、何か……?」
辰也の視線に気付き、怯えたような表情で、紬が尋ねた。
もう辰也との会話にも慣れてきたはずなのだが、未だに紬は、おどおどとしている。もしかするとそれは、辰也が怖いからではなく、彼女の性格なのかもしれない。
「いや……お前って、二重人格か何かなわけ? 途中全然違うやつになったみたいだったっつーか」
「そ、それは……」
眼鏡の下の目を、紬は困ったように彷徨わせる。
その様子は、眼鏡を外して髪を下ろしたときの、堂々としたものからはかけ離れていた。
「……ま、いいけど」
自分から訊いたものの、紬にそこまで興味もないため、辰也は肩を竦める。
「じゃ、オレ帰るわ」
辰也はそう言って、紬に背を向けた。足を一歩踏み出す。
「……おい、今日のこと、誰にも言うなよ。メールのことも」
が、一歩踏み出したとことで、足を止めて振り返った。
「も、もちろんです!」
脅すように辰也がギロリと睨めば、紬は何度も、首を縦に振る。
それを確認してから辰也は、軽い足取りで家へ向かって歩き出したのだった。
8
お茶会が行われる茶道部の部室は、南校舎の一階、廊下の一番奥にある。
八畳ほどの広さのそこには、お茶会へ参加する生徒らと、お茶会の準備に追われている着物姿の茶道部員の姿があった。
参加する生徒らは、壁に沿って並べられた座布団の上へ順番に座り、お茶会が始まるまでの時間を、談笑して楽しそうに過ごしている。
――そこへ、靴を脱ぎ、辰也が畳へ足を踏み入れると、一瞬、部室が静寂に包まれた。
だがすぐに静寂は消え、代わりに生徒らや茶道部員達が、声を潜めて話し出す。辰也と目が合わないように、それでいて、辰也のことをちらちらと見ながら。
それに居心地の悪さを感じながらも辰也は、近くの座布団に腰を下ろす。すると隣に座っていた男子生徒が、怯えたように少し辰也と距離を取った。
様々な視線が辰也を貫く。喋る小声が耳に届く。それに気付かないフリをして、辰也は正座をして、お茶会が始まるのを待つ。
「そろそろ時間だけど、どうかな?」
ふと部室の入り口から、声が聞こえた。咄嗟に辰也が振り返れば、そこには、着物を着た撫子の姿。
和風美人という言葉は、彼女のためにあるに違いない。そう思ってしまうほど、撫子の着物姿は、似合っていた。
思わず辰也が見惚れていると、撫子と目が合った。
撫子は辰也を見て、一瞬驚いたような顔をする。
しかしすぐに、どこか嬉しそうに微笑んでくれた。
微笑を浮かべた撫子の姿は眩しくて、それだけで辰也は、ここに来てよかったと思えた。
9
辰也は、お茶を立てる撫子の姿を見つめながら、一晩掛けて調べたお茶会のマナーを必死に思い出して、見よう見まねで他の者に倣う。
紬に言われた通り、正座の際は背筋を正し、重心は前へ。体重も、両足に掛けるのではなく、片足に。その片足が痺れそうになれば、そっともう片方の足へ体重を移動させる。
「っ」
だがその内、それだけでは逃れられない、足の痺れる感覚があった。
そのため辰也は、足の指先を座布団の上に立てる。確か紬はそのやり方を、跪座と呼んでいた。
それを実践すると、次第に足の痺れが治まっていった。
これなら、大丈夫だ。
自分へ言い聞かせながら、辰也は安堵と共に、進むお茶会の流れと、撫子を見つめる。
10
お茶会が終わると、参加していた生徒らは、一斉に足を崩した。中には立ち上がろうとする者もいたが、みんな足の痺れに襲われているらしく、悲鳴を上げたり、悶えたりしている。
そんな中辰也は、ふらついたりすることもなく立ち上がった。
「せん……」
そのまま辰也は、撫子へ声を掛けようとした。
だが撫子はいつの間にか、参加者や、茶道部の子らと、何やら楽しそうに談笑を始めていた。
それを見て、辰也は撫子へ話しかけるのをやめる。
そしてそのまま、部室をあとにした。スニーカーを履いて、廊下へ出る。鞄は教室に置きっ放しなので、それを取りに行ってから帰らなければいけない。
遠くなっていく部室を背後に感じながら、辰也は息を吐く。
それは溜め息ではなく、安心や、感嘆に近かった。
あれだけできなかった正座が、できるようになった。撫子に情けない姿を晒さなくて済んだ。撫子の茶道部としての姿を見られた。
例え撫子と距離を縮めることはできなくても――それだけで充分、このお茶会に参加した意味があった。
「ま、しゃーねぇよ」
元々、住む世界の違う人なのだ。今までの関係でも、辰也は幸せだ。
そう思いながら、廊下を進む。
すると。
「さ、斉藤君!」
背後から撫子の声が聞こえてきて、辰也は大きく目を見開いた。勢いよく体ごと振り返る。
見れば撫子が、着物で歩き辛そうにしながらも懸命に、辰也を追いかけてきていた。その足元はあまりにもぎこちない。それは着物だから、という理由なだけではなさそうだった。
「きゃっ」
「先輩!」
転びかけた撫子へ、咄嗟に辰也は駆け寄る。抱き抱えるようにして、彼女の体を支えた。
「あ、ありがとう」
が、顔を上げた撫子と目が合った途端、辰也の顔は一気に熱くなった。
「す、すんません!」
辰也は、撫子がバランスを取って立ったのを確認すると、急いで彼女から手を離し、一歩距離を取る。
そんな辰也に、撫子は恥ずかしそうに笑った。
「わたしこそごめんなさい。緊張してたからかな。普段は足が痺れることなんてないんだけど……」
どうやら撫子が転びそうになったのは、足が痺れてしまったからだったらしい。
はにかむように笑う撫子も可愛くて、辰也の胸は一層大きな音を立てる。
「斉藤君すごいね。みんな足が痺れて動けなかったのに、涼しい顔で颯爽と出て行っちゃって。みんな言ってたよ。すごいって。お茶飲むときもね、みんな斉藤君のこと見てた」
「そ、そんな……お、お世辞はいいッスよ」
「お世辞じゃないよ。わたしも正座してる斉藤君の姿、綺麗で……すごく、格好いいと思った」
「え……」
ふわり、と撫子の頬が、桃色に染まる。
その姿に、辰也は呼吸を忘れた。褒められたことが嬉しくて。胸がいっぱいになって。
「ご、ごめんね、呼び止めて。それだけ言いたかったの。今日は来てくれて、本当にありがとう。えっと……そ、それじゃあ」
撫子はそう言って、辰也へ背を向ける。
そんな撫子の手首を、咄嗟に辰也は掴んだ。
「あ、あの、先輩」
驚いたように振り返る撫子へ、辰也は緊張しながら、けれど勇気を振り絞って、震える唇を開いた。
「こ、このあと……一緒に帰りませんか」
辰也を見る撫子の目が、丸くなる。
その表情を見て辰也は、撫子に拒否をされる覚悟をする。
「――うん」
だが撫子の答えは、辰也の予想とは違っていて。
笑顔の撫子につられて、辰也も満面の笑みを浮かべた。
11
幽霊教室と呼ばれているそこから、紬は外を眺めていた。
「あの二人、上手くいったみたいだな」
そんな紬へ、声が投げかけられる。
紬が隣を見れば、そこには、長い黒髪の少女が立っていた。夕陽丘高校の制服に身を包み、気の強そうな表情を浮かべた少女は、校門へ並んで歩く二人の背中を見ている。
その背中は、斉藤辰也と、渡里撫子のもの。
「はい、よかったです」
眼鏡の下の目を優しく細めて、紬は頷いた。
呟く紬へ、ふふん、とどこか嬉しそうに、少女が笑う。
「これもあたし達、お悩み相団のおかげだな」
自慢げに笑う少女を横目で見ながら、紬はハアと溜め息を吐いた。
「……ユウカさん」
そして少女――ユウカの名前を呼ぶ。
「今回は上手くいったみたいですけど……お願いですから、勝手に憑依したりしないでください。私肝が冷えました。あの斉藤さん相手に、あんなことするなんて……」
昨日、辰也へ言った様々な言葉を思い出して、紬は身を震わせる。
辰也への偉そうな口調。辰也を脅す言葉。すべて紬の意思で発したものではない。
「別にいーだろ。何もされなかったんだから」
対してユウカは、けらけらと明るく笑う。
そんな彼女に、紬はなんともいえない顔になった。
紬は未だに、信じることができない。
こうやって笑っているユウカの姿が、自分以外に見えないなんて。
このユウカの声が、自分以外にはラップ音に聞こえるなんて。
この教室に住み付いている幽霊こそが、お悩み相団のメンバーだなんて。
「お前の教え方が悪い。あんなのイライラするに決まってる。憑依されたくなかったら、あたしの指導方法を、あんたが直接斉藤に伝えればよかったんだ」
昨日うるさいほど響いていたラップ音の正体は、正座の指導をしようとしていたユウカの声だ。紬の役目は、そんなユウカの言葉を、辰也に伝えることだった。
だが紬は辰也に怯えてしまい、上手くそれを伝えられなかった。
それに痺れを切らしたユウカが、紬に乗り移った。
つまり、昨日辰也へ正座の指導をしたのは、紬の体に乗り移った、ユウカだったのである。
「でも今回は驚きの連続だったよ。まさか、斉藤からもメールが来るなんてな」
そう言ってユウカは、校門を出て小さくなる、辰也と撫子を見つめる。
「『お茶会に斉藤が来るようにしてほしい』って撫子さんからの相談があったあとに、斉藤からの『お茶会に参加したい、正座ができるようになりたい』だからな」
「はい。まさかお茶会のチラシ作りを手伝って、撫子さんが斉藤さんへそれを渡したあとに……あんなことになるなんて、思ってもみませんでした」
「実は撫子さんは斉藤に恋していた。斉藤も撫子さんを好きだった。両思いだったんだな」
「はい。……でもそれなら、私達が協力しなくても、二人はいずれ仲良くなっていたんじゃ……?」
首を傾げる紬に、ユウカはひょいと肩を竦める。
「そうかもな。でも、そうはならなかったかもしれない。少なくとも、今二人が仲良くなれたのは、努力したからだ。撫子さんは、勇気を出して斉藤を誘った。斉藤は、頑張って正座ができるようになった。努力ってのは何かしらの形で報われるもんなんだよ」
納得したような、しないような。曖昧に紬は相槌を打つ。
「……ちなみに、そのためにお茶会のチラシ作りに協力したり、正座について徹夜して調べた私の努力は、どこで報われるんでしょうか……?」
辰也と撫子の悩みは解決され、二人はいい関係になれそうだった。それは嬉しいのだが……では、それに対する、紬への対価は何なのだろう。
するとユウカは、唇の両端を吊り上げた。
「メール、見てみろ。そしたら分かるよ」
「メール……?」
訊き返しながら紬は、ポケットからスマートフォンを取り出し、それを操作する。そして、お悩み相団のメールアカウントを開いた。
「あ……」
そしてそこに届いている二通のメールに、目を丸くする。
届いたメールの一通は、撫子から。もう一通は、辰也からだった。
内容はどちらも、協力した紬に対する、お礼のそれ。
「嬉しいだろ? 対価は何か。強いて言うなら、こういうことだ」
そう言ってユウカは、浮かべる笑みを深くする。
「お悩み相団、悪くないだろ?」
ユウカに、紬は何も答えない。だがその表情は、嬉しそうなそれで。
しかしすぐに紬は、ハッと我に返ったような顔をすると、勢いよく首を左右に振った。
「で、でも私、ユウカさんの跡を継いでお悩み相団のメンバーになるわけじゃないですから! ユウカさんが末代まで呪うって言うから、協力してるだけ……というか、協力させられてるだけですから!」
「はいはい。いい加減諦めて、あたしの跡継いでくれたらいいのに。じゃないとあたしも成仏できないよ」
「し、知りません、そんなの」
ぷい、と紬はそっぽを向く。
そんな紬に、ユウカはクスクスと笑った。
「よし、じゃあ次の相談者のとこに行ってこい。三年の馬場さんのとこだ」
「えっ!? 撫子さんと斉藤さんの悩みを解決したばっかりなのに、もうですか!?」
「悩みはたくさん送られてくるんだ。あたしは霊感のあるあんたに憑依しない限りここを出られないんだから、あんたが行くしかないだろ」
「で、でも……」
「つべこべ言わず、さっさと行く!」
「は、はいぃ……」
ユウカに怒鳴られて、紬は反射的に、急いで教室を出て行った。
――かくして。
お悩み相団の悩み解決は、続いてく。








