[346]鳳凰の涙でシャンプーしましょ!
 タイトル:鳳凰の涙でシャンプーしましょ!
タイトル:鳳凰の涙でシャンプーしましょ!
掲載日:2025/04/04
著者:海道 遠
イラスト:よろ
あらすじ:
正座修行中の少年(本当は300歳)の流転(るてん)が、洞窟の前の池で釣りの糸を垂らしながら古書を読んでいると、正座師匠、万古老の悲鳴が聞こえてきた。
胸まである白いアゴヒゲが、干からびたムラサキウマゴヤシ(アルファルファ)みたいになっているではないか。
最近の干魃(かんばつ)で水分が不足したからだ。【鳳凰の涙】で、しなやか術を施さないと元に戻りそうにないらしい。

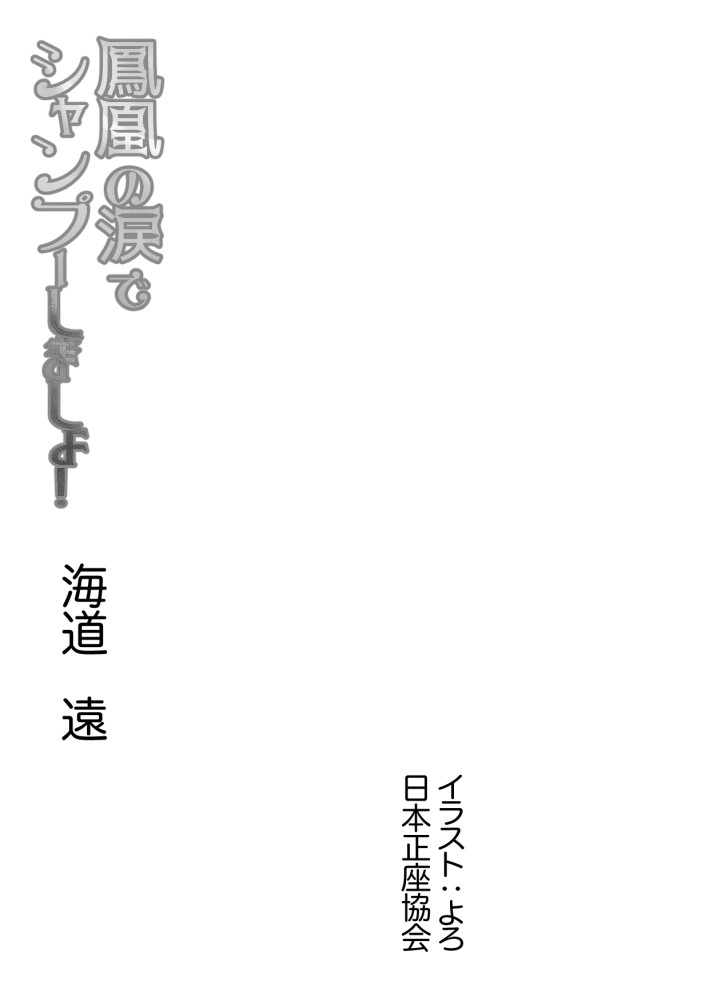
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 ヒゲがガサガサ
正座修行中の少年(本当は300歳)流転(るてん)が、洞窟の前の池で魚を釣りながら古書を読んでいると、池の向かい側から、
「ふぇ〜〜ん、ワシのヒゲが〜〜っっ!」
正座師匠、万古老の悲鳴が聞こえてきた。
「どうしたんですか、お師匠!」
師匠は池の面で顔を映しながら、あたふたしていた。胸まである白いアゴヒゲが、ガサガサになってしまっている!
「その、干からびたムラサキウマゴヤシ(アルファルファ)みたいなおヒゲは!」
「流転〜〜っ、どうしよう、若い時はお前みたいな藍色のツヤツヤで、女の子にひっぱりまくられてたモテヒゲが〜〜!」
どうやら、最近の干魃(かんばつ)で水分が不足してキューティクルがめちゃくちゃになってしまったようだ。
昨日まで絹糸のような光沢を放っていたのに、
「池の水もだいぶん減っちまったもんな……」
流転は情けなく池に目をやった。魚が水不足でうまく泳げない様子だ。
「どうしたのお? あれっ、お師匠、そのヒゲは!」
流転の弟子仲間の女の子、百世(ももせ)も泣き声を聞いて早起きしてきた。
「お師匠、ヒゲはどうしたらなおるのか、分かりますか?」
流転が尋ねてみると、
「こりゃあ、鳳凰の涙でしなやか術(とりーとめんと)をほどこさないと元に戻らないらしいと思うぞ。前の旱魃になった時もそうじゃったから」
【鳳凰の涙?】
「お師匠は艶やかな白髪のアゴヒゲでなくちゃ、正座を教える力が出ないと言ってる。こうなったら、鳳凰を捜しにいくしかないな」
流転は百世にやれやれ、と肩をよせてみせた。
ふたりは万古老のために一大決心して、鳳凰を探しに行く旅に出る。スポーツマンシップならぬ「弟子ップ」だ!
まず、天気のことに詳しそうな女の風神、雷神のふたりに鳳凰の居場所を尋ねに行くが、
「しばらく雨が降る予定はないね。あたいたちもヒマで困ってるのさ」
という返事だった。
次は丘の上の巨大樹に尋ねに行くが、葉のざわめきで答えた。
「残念ながら、私の樹に鳳凰が来たことはないな。役に立ってやれずにすまないな、少年たちよ」
「少年たちじゃないのよ。あたいはれっきとした女子よ、巨木のおじさん!」
「そ、それは失礼しましたな、お嬢さん……」
湖畔の寺に座する、たおやかな衆宝観音にも尋ねにいったが、
「鳳凰さんの行動? 神獣さんだよね。わらわは仏界のことしかわからないから……、残念だけど羅刹の救い方しか、どうも詳しくなくて」
「そうなのか……」
流転が百世の後を追って去りかけた時、周宝観音が、
「あ、ちょっと待って」
お堂の奥から古びたヒョウタンを出してきた。
「これは確か、お寺にいらした高僧の言い伝えだけど、鳳凰が飲むとかいう醴泉(れいせん)が入っているらしい」
耳の横でヒョウタンを揺らしてみた。チャパチャパという音がする。ヒョウタンに巻き付けてある巾着袋には、何かの実が入っている。
「これを持ってお行きなさい。鳳凰が飲んでくれるかもしれないから。それと、巾着袋の中身は貴重な竹の実です。ヒョウタンに付けてあるのは、おそらく鳳凰さんが食べるからでしょう」
「ありがとうございます。周宝観音さま!」
流転はその場で丁寧に座礼をし、観音は目を細めて見送った。
「鳳凰の生態を知らなくちゃね!」
ひとり言をもらしながら、百世の後を追った。
ふたりが村はずれを当てもなく歩いていると、どこからともなく、見知らぬ女が現れた。赤い民族衣装に手首や足首にじゃらじゃらした飾りを着け、巻き髪を触っている。
気さくに話しかけてきた。
「あんたたち、髪の毛がしなやかになる方法を捜してるの?」
「あんた、誰だい? 俺たちのあとをつけてきたのかい?」
流転が尋ねた。
「あたいの赤絹のような髪も最近バシバシでさぁ。鳳凰に協力してもらわねばと思っていたところなのさ」
「じゃ、おねえさんは鳳凰の居どころを知ってるの?」
「鳳凰は梧桐(あおぎり)に住み、竹の実を食べ、醴泉という甘い水しか飲まないよ。しかし――、今は干魃で醴泉は枯れ、竹の実も後100年は生らないだろうね」
「100年も待つの?」
「それだけじゃない。鳳凰が満足する正座をして頭を下げなければ涙は出ないよ。何せ、彼らのプライドは蓬莱山(ほうらいさん)より高いらしいから」
「えええ~~!」
百世と流転は、のけぞってから情けない顔になった。
「もし、鳳凰の涙をゲットしても、万古老のアゴヒゲの手入れはあたいがやるんだからねっ」
おねえさんはダメ押しした。
「おねえさん、あんたはいったい?」
「あたいは赫女(かくじょ)。絵師だよ。かつては万古老の妹弟子だったのさ。それとヒゲのシャンプー係」
「万古師匠の妹弟子だってえ?」
ふたりは飛び上がった。
「妹弟子がいたなんて初めて聞いたぞ」
「あたいの万古老のアゴヒゲの手入れ役は、天帝様がお決めになったから譲らないわよ。昔はよく青い髪も洗ってしなやか施しの術をしてあげたもんさ。彼は絵のモデルだったからね」
赫女という女は、ちょっと得意げに言った。
「絵のモデルだって~~?」
「まあ、藍万古の姿の時だったら、絵のモデルも務まるんじゃない?」
百世が言い、流転は「なるほど」と思った。
「髪が藍色の青年の姿なら、絵のモデルもできるだろう。しかし、洗髪係は天帝様が決めたのか……」
百世と流転はしょんぼりした。
「じゃあ、あたいたちではダメなのかな」
「う〜ん、とにかく、ダメ元で鳳凰さんを探してみよう」
「ねえ、流転。さっきの赫女さんていう女の人……」
「ん?」
「万古師匠の妹弟子にしては、なんだか昏い(くらい)瞳をしていなかった?」
「そうかな? 師匠の妹弟子だったっていうんだから、取りこし苦労だよ、きっと」
梧桐がどこに生えているか検索するために、流転が懐から四角い「ナビ」を取り出してスイッチを入れた。
「そんな便利なのがあるんだったら、鳳凰を探すために早く出してよ!」
「これは梧桐の生えている場所しか分からないんだよ」
「くそ〜!」
「百世、言葉遣いがお下品ですよ!」
流転に叱られて、百世はむくれた。
第二章 鳳凰、おいで!
「検索した場所で付近の村人に聞いて回って、鳳凰の目撃情報を集め、どの梧桐に鳳凰の巣があるか突き止めよう!」
流転は、やる気いっぱいの顔で百世に告げた。
「流転、珍しくポジティブじゃない。でも、梧桐がこの草原に何本生えてると思ってるのよ?」
「鳳凰だって干魃できっと喉が渇いているよ。彼らが飲む醴泉っていう水を持って行って枝の上で待つんだよ!」
「醴泉を手に入れたの?」
「うん! 衆宝観音さまが、気を利かせて素早く持たせてくださったんだよ!」
流転は、ふところから醴泉入りのヒョウタンを出して見せた。
「平和な世にしか存在しない水らしいのに、よく手に入ったねえ」
得意そうに、
「それと、鳳凰の食べ物の『竹の実』もね!」
ピーナッツくらいの大きさの黄色い果実を、数個、懐から出して見せた。
「ええっ? 100年に一度しか生らない『竹の実』を?」
「鳳凰の食べ物ってどんな味がするんだろう?」
百世が素早く奪ってかじりついた。
「百世、やめとけ! 俺たちが食べてもきっと不味いぞ」
「ブホッ、本当だ! 歯も立ちゃしない。硬くて渋いだけだ。さては流転、お前も味見したな〜〜」
梧桐の生えている森にたどり着いたが、思ったより樹は少ない。ひび割れた大地に数えるほどの樹しかなく、待っても待っても鳳凰がやってくる気配はない。
毎日、ジリジリとした太陽が照りつける。
「鳳凰よ〜〜! おいでおいで〜〜! ここに甘い水がたっぷりあるぞ」
「竹の実もあるぞ〜〜!」
しかし、空にはカラスとスズメが飛んでいるだけだ。
「鳳凰ちゃ〜ん、ここにおいで〜〜! ちょっぴり涙を分けてほしいんだけどな〜〜」
渇いて割れた大地にふたりの声だけが虚しく響いていくだけだ。
「里の村人達に聞いて、かなり絞り込んだんだがな〜~」
いきなり真上から、きれいな女の声が降ってきた。
「百世! 流転!」
ふたりが見上げると、孔雀のピーちゃんに乗った孔雀明王、まゆらちゃんが空中で静止している。正座仲間でもあるまゆらちゃんは、明王さまの中でひとりだけ温和なお顔をして、腕が四本あり、それぞれ蓮の花や仏具や極楽に生る果実を持っている。
流転たちの正座師匠でもあり、とても親しい。
「あんたたち、こんな寂れた山で何をやってるの?」
「まゆらちゃん! 万古老師匠のヒゲがバサバサになっちまって、鳳凰の涙でしなやか術を施さないと治らないらしいから、鳳凰を待ってるんだよ」
ピーちゃんが低空飛行し、まゆらちゃんが地上に飛び降りた。
「万古老ったら、またヒゲのお手入れサボったのね! 何十年かに1回はそうなるんだから」
ふたりはうなずいた。
「これだけ雨が降らなきゃ仕方ないけどね。でも、あんたたち、鳳凰の悲しみの涙でしなやか施し術したって治らないよ!」
「えっ、そうなの?」
百世と流転は顔を見合わせてから、まゆらちゃんとピーちゃんに視線を戻した。
「あんたたち、鳳凰を悲しい目にあわせたいわけじゃないでしょう」
「そりゃそうだよ! 知らなかったんだよ!」
「ふふふ」
まゆらちゃんが含み笑いをした。
「涙って、2種類あること忘れてやしない?」
「2種類――? あっ、悲しい時の涙と嬉し涙か――!」
流転がピンときた。
こんな時、いつもなら騒ぐはずの孔雀のピーちゃんは、
「なんだよ! 鳳凰、鳳凰って! 俺さまこそ鳳凰のモデルになった原型なんだぜ! 孔雀はキジ科なんだから!」
と、得意そうに胸を張ってまつ毛をバサバサしている。
「ええっ、そうだったの?」
まゆらちゃんが驚く始末だ。
「じゃ、鳳凰さまの涙と同じ涙が流せるの?」
「そ……それは無理だけどよ」
ピーちゃんは、足の爪でクチバシの横をポリポリ掻いた。
「応龍(おうりゅう)っていう龍から進化したヤツが、雨を降らせたり、蓄えたりできる」
「まあ、ピーちゃん、そんなことを知ってるの?」
「アタボウよ! 鳳凰の先輩なんだからな!」
流転と百世も身を乗り出した。
「じゃあ、応龍さまに会いに行って、雨を降らせていただこうよ! 澧泉が作れるだろう?」
「そりゃそうしたいけど……今、応龍はいないんだ……」
情けなさそうに、ピーちゃんの頭の上のかんむり毛がしおれた。
「いない? どういうわけだ?」
「龍から成長した段階のものだって言ったろ。それが、今、いないらしいんだ。龍から進化してもらわないといけない」
第三章 醴泉=甘酒
「応龍になっていない龍だって?」
百世と流転が顔を見合わせた時、
「応龍なら心あたりがある!」
また、頭上から声がして、かたわらの巨木から降りてきたのは、唐のお菓子作りの師匠、リ・チャンシーではないか。
「リ・チャンシー先生!」
百世も流転も大喜びで迎えた。
「どうしてここへ?」
「旱魃続きで、どうしておられるかなあと思って洞窟へ行ったら、万古老師匠がヒゲをチリヂリにして泣いていたので、事情を聞いたのだ。世界一美しい馬アハルテケみたいなピカピカだったヒゲがとんでもないことになっていたな。お気の毒に……」
「そうなんですよ、困って、鳳凰の涙をゲットするために旅に出たんです」
「そっか! 君たちが青桐の生えてる林にいるんじゃないかなと思って、待っていたのさ。ドンピシャだったな!」
リ・チャンシー先生は、アハルテケに負けない白い歯で爽やかに言った。
「そうです。お師匠のヒゲがあんなになってしまったから、雨を降らせられる応龍を探しているのですが」
流転が説明したが、リ・チャンシー先生は、
「それよりまず、この干魃をどうにかするのが先ではないかな? 日照りの女神にお願いして手加減してもらい、それから雨師(うし)――つまり、応龍と話し合って雨を降らせてもらえば――」
「あれれれ、一周回って応龍の話に帰ってきたよ。じゃあ、応龍のことを雨師って呼ぶのか?」
「そうだよ、流転。問題は日照りの女神と雨師が平和的に話し合ってくれるかどうかなんだ。犬猿の仲だからな」
リ・チャンシーは腕組みした。
「あちゃ〜〜! さもありなん……」
百世と流転は同時に叫んだ。
「赤い応龍って【鳥の王】って言われて、一番強いんでしょ。 どんなカタチしてるの?」
百世が聞いた。
「応龍は龍の身体に鷹のような羽根を持っている。その羽根でバサバサ羽ばたくと、不思議と空に雨雲が湧き出てくるんだ。そして……激しい長い雨が降る。大地は潤うどころか、川は氾濫し、田畑は水びたし、家や橋は流れてしまう」
「それは、手加減してもらわなきゃ困るね。日照りの神は話の分かるヤツかい?」
「日照りの神には会ったことがないから、わからないや」
リ・チャンシーは申し訳なさそうに頭を掻いた。
「ちょっと、ちょっと……」
腕組みして考えこんでいた、まゆらちゃんが「待った」をかけた。
「【鳥の王】だって? そんなに強大な力を持っているなら!
応龍って鳳凰のことじゃないの?」
「あっ!」
「ああ〜〜〜!」
一同は叫んだ。
「そうだよ、多分! いや、99パーセント当たってる!」
「俺たち、とんだ方向違いの考えしてたけど、その通り、きっと応龍=鳳凰なんだよ!」
※諸説あります。
「じゃあ、とりあえずは鳳凰が飲む澧泉は作れるね! 俺、一度、どんなのか、飲んでみたかったんだ!」
ピーちゃんが嬉しそうに言った。
「そうとなったら、醴泉を作ろう!」
リ・チャンシーが、
「醴泉ていうのは甘酒のことだよ」
「リ・チャンシーさん、作れる?」
「ああ、お手のものさ。しかし原料の米が必要だぞ。どこもかしこも田んぼが干上がっていて、昨年の米を残している者に分けてもらわなきゃならん」
「それに、酒はじっくり醸造しなきゃならんから、作るのに一年はかかるぞ」
「そうか……」
百世と流転はがっくりした。
「ほんの少しでいいんだけどなあ。甘酒作るのは、元のものがあれば、霊力ですぐに何倍にもできるから」
リ・チャンシーが何気なく言った言葉に、流転はハッとした。すぐに衆宝観音からもらった甘酒のヒョウタンをふところから出し、見せてみた。
「これで足りる?」
「おお、なんだ、持っていたのか! これだけあれば、100樽分くらいの甘酒は作れるぞ!」
「やった~~~!」
流転たちはバンザイした。
第四章 日照り神
何日間か、リ・チャンシーは流転や百世と共に、近隣の村の衆にもお願いに回って人手を集め、甘酒作りに没頭した。
流転の持っていたヒョウタン入りの甘酒が、リ・チャンシーの手によって何倍もの量の甘酒に出来上がった。村から樽をたくさん借りて100個の樽に醴泉を詰めた。
ヒョウタンの栓を抜いて、匂いをばらまきながら「醴泉ありますよ~~」と、呼びかけていると赤い鳳凰に巡り逢えた。
「鳳凰さん、飲み水の醴泉をお持ちしました」
流転と百世が荷車に積んで運んできた、樽を開けて献上しようとすると……、
「醴泉だ!」
「私が飲むのよ!」
「いえ、私が先よ!」
白、黄色、紫色の四羽の鳳凰たちが上空に現れるや、赤の鳳凰も混じり合ってクチバシで突きあい、羽根を無茶苦茶に絡み合わせてケンカをはじめる。
一羽の鳳凰が鋭い爪で樽を蹴ってしまい、樽が岩にぶつかり、タガが外れて壊れてしまった。
が、バラバラになったのは樽の木材だけで、中に入っているはずの醴泉はまったく散らばらない。次々に転がった樽も、すべて空っぽだ。
「あれ?」
「醴泉が入ってないわ!」
樽が100個分の醴泉(甘酒)は、皆、空っぽだ。あまりの暑さに作り上がったとたんに干上がってしまったのだ。
「う、うそだろ〜〜?」
壊れた100個分の樽の残骸の中で取り残された流転たちは、醴泉を失ったショックと、熱線のように強力な熱さに呆然とする。
「ホホホ……」
更に熱風が吹いてきて、岩山のてっぺんから声がした。
「わらわの真の姿は、日照り神の魃(ばつ)。これくらいの水分は直ぐに干上がらせてしまうよ!」
真っ赤な髪をなびかせた女が、瞳の中に邪悪な炎を燃えさせて立っている。熱くてとても近づけない。
「赫女とかいう女だ!」
流転と百世は、地面に手をついた。
「だめだ、こんなに日照り神の力が強かったら、いくら作っても醴泉は干上がってしまう……」
そこへ万古老が、震える足で転びそうになりながら、杖を突きながら岩だらけの山道を登ってきた。
「ワシのヒゲのために……苦労をかけるな、百世と流転……。しかし、もうよい」
百世と流転とまゆらちゃんが駆け寄る。
「もうよいって? 師匠……」
「ワシのヒゲより人びとの水と食料の方が大事じゃ。ワシからあらゆる雨と水の神にお願いしてみる」
「そ、そんなお力があるんですか?」
「無理なさるとヒゲだけじゃなく、お身体に障ります」
「これは常々、正座という礼儀を教えているワシの義務でもあるのじゃ。人間、ちゃんと基本の生活ができてこその礼儀、正座じゃ。飢えたり喉が渇いていたり、生業(なりわい)が立ち行かなくなったりしては、礼儀や正座が二の次になっても仕方あるまい」
万古老の瞳の中に誠実な執念が燃えている。流転たちは、圧倒された。
「万古!」
孔雀明王のまゆらちゃんが呼びかけた。
「雨の神にお願いする前に、干魃の神を弱らせる方法があるわ! 太古の昔、干魃の神(太陽の子どもたち)に矢を射た者がいるそうよ!」
「そ、そんなことをして大丈夫なのかね?」
「私が知っているのは、跋という女の悪鬼よ! 彼女は異常な熱で人を殺めてしまおうとしているわ!」
「まゆらちゃん、もしかして、その女は真っ赤な髪をしているんじゃない?」
流転が聞いた。
「そうよ!」
「じゃ、アイツだ! 万古老のしゃんぷう係だとか言ってた……、あの岩山に立っている赤い髪の女だよ!」
「な、なんですってえ?」
まゆらちゃんの緑色の髪飾りが立ち上がった。
「あれはワシの妹弟子なのだが、お転婆でな」
「あの娘が? だからと言って熱の放ちすぎは許されないわよ!」
「確かにそうだが、弓矢で射るのだけは許してやってくれんかの? ワシがなんとかするゆえ」
万古老はすがりつくような眼で懇願した。
第五章 万古老の訴え
翌朝、万古老は蓬莱山のある方角に向かって、慎重に正座した。藍万古の姿になり藍色の長い髪とアゴヒゲ姿になって、身なりも整えて風伯(風の神)に、呼びかけた。
『風伯どの! 風の神よ! どうかお願いです。干魃が去って豪雨が襲ってきたら、雨の神を吹き飛ばしてください!』
丁寧な座礼を繰り返した。
やがて、空に大きなみどり色のお腹を出っ張らせた風伯が現れた。女の風神と同じく大きな布を膨らませて持っている。
「正座師匠の万古か。おや、若い姿になって、相当、本気の願いじゃな。分かった分かった。このところの旱魃は長いなあ~~と、我も思うていたところじゃ。日照りが続いても雨が降り続いても、人間は困る。頭の痛いことじゃのう」
「誠に……」
「よし、豪雨が来たら、ワシの力で雨雲を吹き飛ばしてやろう」
風伯から承諾をもらえた。
藍万古は岩山の頂(いただき)から、叫ぶ。
『この世のあらゆる神よ、今こそ考えてほしい。誰のおかげで自らが存在しているかを――』
『特に雨を統べる神々に申し上げる! 龍神どの、雨神どの、鳳凰どの、麒麟どの、すべての雨水に関係する神よ、自らが存在しているのは誰のおかげと思われる?』
応龍らしい翼を持った龍が雲間から下りてきた。
「それは、天帝さまが我を生み出してくださったからだ」
藍万古がそれに応じ、
『確かにそれに間違いない。しかし、そなたも雨神どのも存在させてくださっているのは、何の力もない人間のおかげですぞ!』
「ちっぽけで無力な人間の?」
応龍が意外そうに言った。
『応龍どの。人間はちっぽけで無力じゃが、彼らなりに短い命を積み重ねて頭をひねり、独特の文化をあちこちで多く育て、自分たち以外の創造物を創り出した』
『けっこうな知力や長い歴史を経て知恵というものを持っておる。現に、我々――神仙の者や、雨神どの、龍神どの、鳳凰どの、麒麟どの、その他もろもろの神を創り、存在させてくれているのは、よ~~く考えると、人間に外なりませぬ』
【天帝さままでもが、人間の創造物であると申すのか?】
赤い鳳凰が恐る恐る尋ねた。
『まさしく! 人間こそ万物の創造主である!』
(そ……そこまで言っちゃう?)
流転がツバをごくんと飲みこんだ。
後は皆、言葉なく立ち尽くし、ようやくハっと、その場に正座した。百世もまゆらちゃんも所作正しく正座する。
背すじを――身体の芯を真っ直ぐにし、その場に膝を着き、衣をお尻の下に敷き、かかとの上に座る。
『創り出し、存在させてくれている人間どもの生活を苦しめるようなことは、我らの立場からすると言語道断ではありませぬかな?』
「ふむふむ、確かに……」
赤い鳳凰が他の鳳凰たちとダンゴのようにこんぐらがったまんま、うなずいた。
『日照り神の魃が熱を発しすぎた時には、雨水の神々よ、人間どもの地を雨で潤わせてやろうではありませぬか。さもないと、人間は飢えて死に絶えてしまいますぞ。気高き我々が恩を仇(あだ)で返すようなことをして良いものでありましょうか!』
藍万古は『気高き我々が』という言葉を大声で叫び、神々の自尊心をくすぐった。
応龍も、こんぐらがってケンカしている鳳凰たちも、青い髪をなびかせて説得する藍万古の言葉に聞き入った。
第六章 よみがえる緑
流転と百世、そしてリ・チャンシーは、拍手をはじめた。
「万古師匠、ご立派!」
「カッコいいです! さすがは長年の正座師匠!」
万古師匠は、戦の神、真武大帝(しんぶたいてい)へ、リ・チャンシーに使いに立ってもらい、「弓矢をもらい受けたい」と、懇願した。
弓矢は紫の龍神によって届けられた。
いよいよ、弓をつがえ、妹弟子の魃に巨大な矢を向ける。
「兄弟子さま! 私を射抜くおつもりで巨大な矢を?」
「魃! お前の魂は暑すぎる夏によって邪悪な色に染まってしまったと見た。今すぐ熱を冷まさなければこの矢を放つ!」
赫女は目を見開いて震えはじめた。日照り神の魃になってしまったことを悔いた。
「ば……万古兄さま! 兄弟子さま、どうかお許しください! 赫女が思い上がっておりました! 天帝さまのご任命とはいえ、正座師匠の座に就くことを先越され……妬んでいたところを、この夏の暑さに乗じてよけい熱くしてしまったのです」
赫女――日照り神の魃は恐れおののき、ひび割れた地面に正座し、ひれ伏した。膝や手のひらが真っ赤になっていく。
「お前の過ちを正すため、矢で射抜くのは私の役目だ」
ひび割れた大地に、赫女の涙が落ちた。
「申し訳……ございません……」
「今後はよく考えて行動せよ。ワシの妹弟子である立場も考えよ」
藍万古はようやく眉間の皺をゆるめ、弓矢を下ろした。
たちまち雨雲の群れが走るように寄ってきて、雨が降りはじめる。焼けついていた平原はたちまち水を吸い、やがて――、草や木の芽があふれて美しい緑が広がる。
熱が冷めてくると魃の髪も薄紅色に変わり、冷静な絵師の娘、赫女の姿に戻った。火傷した両の手のひらを見つめ、
「そうだ。私はこのような緑したたる風景を描いてみたかったのだ……どうして忘れていたのだろう」
赫女はつぶやいた。どうやら熱を持ちすぎたことを深く反省したようだ。
鳳凰たちは美しい樹木に感動して涙を流し、流転と百世はすかさず、ヘチマ(瓜の実を乾かしたもの)で吸い取り、オケに絞った。
「鳳凰の涙が手に入った!」
流転と百世は嬉し涙を流し、それを見た鳳凰はもらい泣きの涙を流す。なかなか涙が止まらず、かなりな量になった。
「鳳凰の涙がいっぱい溜まったぞ」
百世が感心して、
「涙の種類って、わりとたくさんあるんだなあ。鳳凰さんたちが、からまって苦しそうだから、ご自分たちの涙で洗ってさしあげよう」
今度こそ樽に溜めた鳳凰の涙を、思いきりバシャッとかけた。
びしょびしょになった鳳凰たちは、それぞれ20本ほどある長い尾の羽根を、するりとほぐしてようやく一羽ずつに離れ、自由になって空に浮かんだ。
絵師の赫女に戻った魃は、大きなえぷろんを着けて、身構えた。
「万古兄さん、じゃあ、私がお詫びに鳳凰さんの涙で髪もヒゲも洗って、しなやか術を施してさしあげるわ!」
「いや、それはボクらが!」
流転と百世が乗り出す。
「いえ、藍万古のシャンプー係はわらわよ!」
まゆらちゃんが黙っているはずはなく、三つ巴の戦いが始まろうとした。
「まあまあ、待て。みんなで分業にすればよいではないか。とりあえず、大地に雨が降って良かったことだ」
リ・チャンシー先生が皆を落ち着かせて、胸を撫で下ろした。
万古師匠の洞窟の前で、たらいを前に受けて赫女が固定し、流転と百世が少しずつジョウロで鳳凰の涙をかけながら、青いアゴヒゲをもみ洗いする。
「だめだめ、赫女さん、ちゃんと正座して、たらいを持って」
「そういう、あなたたちも正座してジョウロを使うのよ。そうっとよ!」
藍万古のガサガサになった青いアゴヒゲも、髪も、みるみるしなやかになっていく。
背後では孔雀の団扇を持って、元カレの濡れたアゴヒゲを乾かそうと、まゆらちゃんが待ち受けている。
「これで、万古師匠のムラサキウマゴヤシみたいなアゴヒゲは、元のしなやかさを取り戻すだろう」
ほっとしながら、リ・チャンシーはアゴに手を当てて眺めていた。
(これからは心して、無力な人間を大切にしなければなあ……)
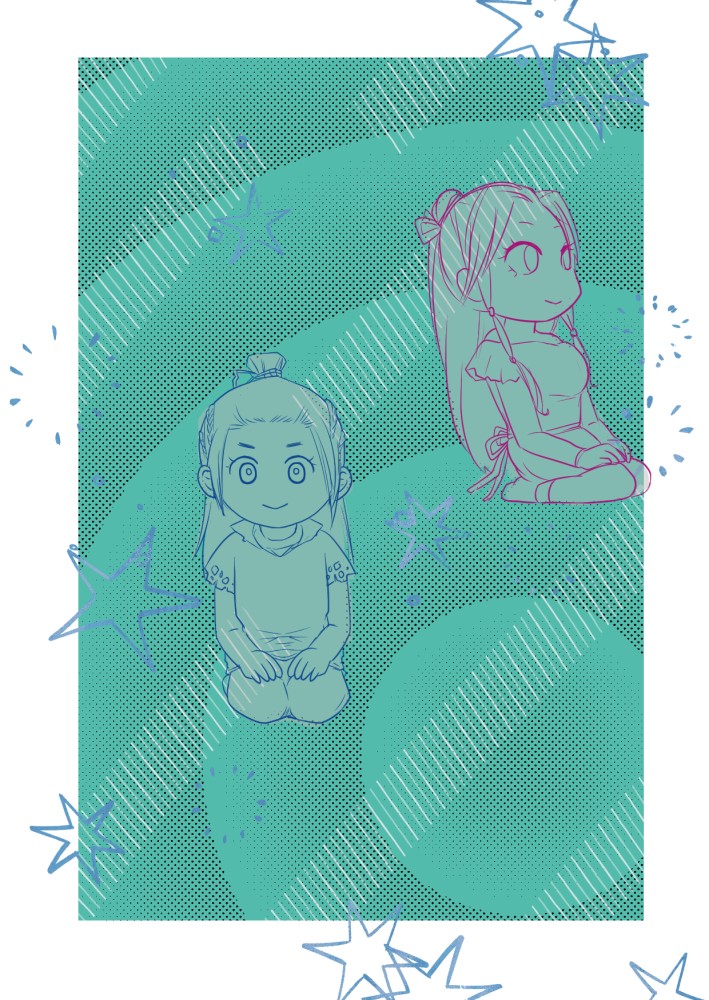

![[208]正座フェロモン・夢好(ムスク)](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)





