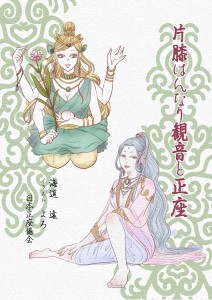[102]オレンジの面影の中で正座
 タイトル:オレンジの面影の中で正座
タイトル:オレンジの面影の中で正座
分類:電子書籍
発売日:2020/10/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:48
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
京都でひとり暮らしの事務員、透子(とおこ)は冬の帰宅途中、洋館の庭にキャンパスとイーゼルが倒れたままになっているのに気づき、訪問する。
出てきたのは美しい正座で迎えた紬を来た老婦人。手をついて丁寧なお辞儀で迎える。
暖炉の部屋に通され、好きなロッキングチェアを触っているうちに身体が温まってうたた寝してしまう。
さて?
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/2420251

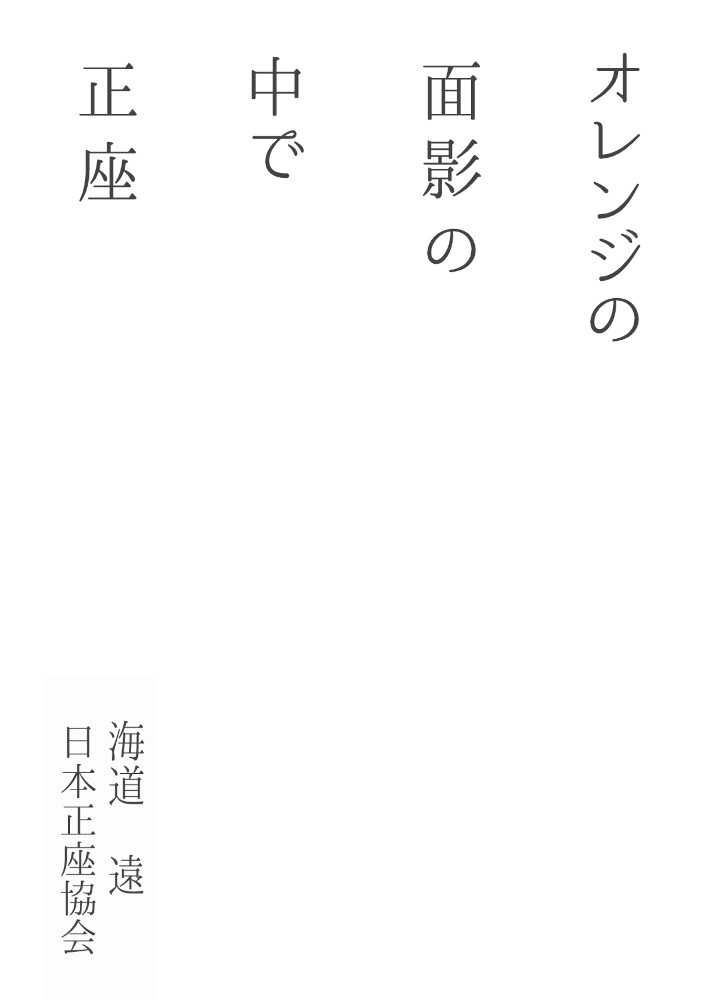
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 目覚めるとオレンジ
大きな暖炉の炎が揺れる布のようにゆらゆらしていた。炎のオレンジ以外は茶色で、ぼんやりしている。
(オレンジの沼みたい……)
透子は眠くて眠くて仕方なかった。
この感覚は、遠い昔、喉が腫れて痛い時に、
「今日と明日は寝ていなさいよ」
体温計を確かめてから、喉元まで布団をかぶせ、とんとんとする母親の手の感触に安心して、眠っていたい感覚に似ていた。
額のタオルを絞りなおすために立っていった母親の面影を思い出させた。そして、もうひとつの面影。
(あの声は……)
『透子ちゃん、久しぶり……』
(あの声は、確か……)
オレンジの暖炉の炎の中で、同じ色のセーターを着た、あの人の声では……。
毛布が肩からずり落ちて、ふと目を開けた。自分が絨毯の上に座り、ロッキングチェアにもたれかかっていることに気づく。
なんということか、初めて訪問した家でうたた寝していたのだ。
「どうしよう、見ず知らずのお宅で、私ったら」
暖炉に負けず自分の頬が、かあっと熱くなった。
いくら風邪気味で疲れていたとはいえ、厚かましい女だと思われたことだろう。毛布を握りしめながら床から動けずにいた。
暖炉の巻木がパチパチと爆ぜる。
かなり大きな洋間で、ロッキングチェアには暖かそうな赤いタータンチェックのショールが掛けてあり、編みかけの編み物や編み棒もある。壁紙もベージュの趣味の高い花柄だ。それらがオレンジ色に染まり、まるで絵本の世界だ。
レース越しの窓の外はもう真っ暗である。
(もうすぐ冬至だもんなあ)
しまったという風に透子は、おでこを叩いた。
天気予報で最強寒波とか言っていた。
勤めからの帰り道、速足で急いでいたら、路地の中の洋館の塀から鮮やかな朱い実がたわわに成っているのが見えた。庭の中ほどには山茶花の木も何本かあり、暮れには可愛らしい赤い花をたくさん咲かせていたのを見かけた。
あまりの寒さに厚手のショールを巻いていても、しゅくっと首をすくめて襟を立ててしまう。
これから帰っても、冷たく暗い部屋が待っているのかと思うと、暗い気持ちになっていた。
ふと、その洋館の鉄の柵の向こうの石畳に、イーゼルと八号くらいの大きさのキャンパスが倒れているのが見えた。強風で倒れたのだろう。このままでは、雪も降りそうな気配だし、早く片づけなければ痛んでしまうのに、誰も出てこない。
鉄の門を押してみると、開いた。
透子は知らず知らずその数メートル先にある飴色の窓の明かりに引き寄せられ、石畳を踏んで、キャンパスとイーゼルを拾いあげた。
玄関へ着くと、重厚な木製の扉に馬の蹄のかたちのドアノッカーがついていて、コンコンと鳴らしてみた。
「ごめんください」
反応はない。
北風が強くなってきた。
「あのう、ごめんください」
透子はもう一度、声を大きくして呼んでみた。
やはり答えはない―――。と思ったところへ、扉の斜め上のしゃれた感じの玄関灯りが点った。
「どなた」
返事が聞こえた。
「あのう、お庭にキャンバスが」
しばらく間があり、応えがあった。
「どうぞ?」
透子がそっとドアを開けると数メートル先の上り口に、老婦人が目を見はるほど良い姿勢で正座して、待ち受けていた。趣味のよい紬を着ている。
膝から滑らすように両手を下ろし、前についた。
「いらっしゃいませ」
あまりの丁寧な応対と美しい正座に、イーゼルとキャンパスを持ったまま透子はしばし、立ちすくんでしまった。
第 二 章 ロッキングチェア
「キャンパスが庭に落ちていましたよ」と、言いたかっただけのお宅の洋間にあがることになってしまったのだった。
「暖炉の前のロッキングチェアで温まっていきなはれ」の、ひと言で。
ロッキングチェアは、年季が入ったものだとすぐわかった。焦げ茶色の木目が光っており、何年も可愛がって使われたのが感じられる。
きっと、この屋敷の何代か前の住人が愛着深く座っていたに違いない。うっとりと見つめている間に睡魔に襲われた。
扉のノブがガチャっと鳴った。
鈍い色の金属のドアノブに、透子は瞳を吸い寄せられた。
(どんな顔をすればいい?)
「よう眠れましたか」
老婦人が鈍いドアノブの向こうから姿を現した。玄関で丁寧に正座で迎えてくれた方だ。
老婦人とは言っても、髪は真っ黒で薫るような優しい微笑みを浮かべている。鼻筋が通って上品な顔立ちだ。
「は、はい、そのう、毛布、ありがとうございました」
透子は慌てて、毛布をたたんで立ち上がった。
「あ、そのままで」
老婦人は、暖炉の前まで木製の重そうなお盆を運んできて、暖炉の前に置いた。彼女の頬もオレンジに染まり、額の皺が浮き彫りになる。
「どうぞ」
大きなマグカップになみなみと注がれたミルクティーがふたつ。
「よろしおしたらお飲みやす」
(近頃、聞かない懐かしい言葉だ。お祖母ちゃんがこんな京ことばだっけ)
「いただきます……」
マグカップをゆっくり持ち上げ、ひと口飲む。まるで、子供の頃、母親が温めてくれたミルクの味そのままだ。
老婦人に伝えると、眉が下がってよけい優しい顔になった。
「すみません。通りがかっただけですのに眠ってしまい、お茶までご馳走になってしまいまして」
「よろしおすえ。ひとり暮らしやさかい、誰にも遠慮はいりまへん。ロッキングチェアいかがどした?」
「つやがとても素敵です。持つのが夢なんですけど、私の住まいには似合わへんので、なかなか持てません」
「よろしおしたら、いつでも座りに来ておくれやす」
「いえ。私、そろそろ失礼します」
「まだよろしいやおへんか。暗うなりましたけど、宵のうちどすえ」
それでも、これ以上はあまりにも失礼と思い、急いでコート掛けにあったコートを羽織り、逃げるように玄関を出た。
静かだと思ったら風が少しおさまって、小雪が舞っていた。
第 三 章 セーター
永観堂の紅葉が、透子は大好きだ。あの人と出逢った場所だ。青もみじの頃だった。
「交際してくれないか」と言われたのが炎のような燃えるオレンジの頃。紅葉の頃盛りだった。紅葉の名所はあまたある京都だが、永観堂が一番、好きな理由はやはりそれゆえだ。
アパートに帰り、冷え切った部屋に灯りを点けると、ひとりなのがしみじみ感じられた。
思いがけず、帰宅途中に暖炉のある豪華なお宅におじゃましてしまったせいだ。なんの警戒もなしに老婦人は透子に、
「よろしかったら温まっていきまへんか。今日は冷えこみますさかい」
と、声をかけてもらったのだった。
遠慮がちにおじゃましてみると、大きな洋間に暖炉があり、部屋全体がオレンジ色のホオズキのようで、憧れのロッキングチェアまであった。
「どうぞ、おかけになってくださいな。ソファなり揺り椅子なり、暖炉の側なりお好きな場所に」
婦人は屈託なく言うので、初めて会った気がしなかった。
少女の頃から憧れていたいたロッキングチェアに夢中になってしまい、撫でまわして木の感触を味わってるうちに床に座りこみ、もたれて寝てしまったらしい。座った時には正座のはずだったのだが、眠ってる間に横座りになっていた。
(あんなに理想どおりのロッキングチェアをお持ちの方に出会ったのは偶然やろか)
そんなことを思いながらアパートのストーブが温まるのを待った。
あの婦人もひとり暮らしだと言っていた。
透子自身も今、ひとり暮らしだ。洋服たんすをそっと開け、二段めに入っていたオレンジとブラウンの大幅なよこしまのデザインのセーターをそっと抱きしめた。
三年前まで、これを着てくれる人がいた。今はひとりだ。頬に押し当てていると、まだあの人の匂いがする。……と思った。
このセーターを着て永観堂の境内を歩く姿が、ありありと甦った。
「悪いけど、僕には派手かな。オレンジなんて着たことがない」
ラッピングを解くなり、申し訳なさそうに彼は言った。
「着てみたらええやないの。挑戦したら、おしゃれの幅が広がるさかい」
「いや、やはり悪いけど、この色を着る勇気が」
「ほら、今、紅葉の真っ盛りでしょう。これを着て、寺社仏閣めぐりしましょうよ。どっちが鮮やかかな」
「勝手に話を進めるなってば。観光客のたくさんいるところへ、これを着て?」
彼はさんざん抵抗したが、ついに根負けした。
次のデートで待ち合わせた時に、透子がおそろいのオレンジのセーターを着てきたのを見て、やれやれという風な顔をした。
第 四 章 再び、梅もどきの庭へ
(あの老婦人にお礼をしなくては)
透子は思った。
(もう一度訪ねて、菓子折りでもお持ちしようか、返って失礼になってしまうかな)
いろいろ考えて、聞いておいた番号に電話してみた。
受話器が上がる音がした
「あのう、柿の葉寿司はお好きですか?」
「はい。好きどすえ」
老婦人の声は明るかった。
「お越し下さいますの? そしたら、お吸い物でもお作りしてお待ちしてますわ」
「あ、いえ。今日はお玄関で失礼します」
透子は慌てた。それでは、もう一度お礼に来なくてはならなくなる。
「そんなことおっしゃらんと、ご用事があらへんのやったら、ご一緒に夕飯をいただきましょう」
老婦人に押された感じで、結局、夕飯の約束をした。
内心嬉しい。ひとりでの夕飯は、もう心が根を上げている。
梅もどきの塀が見えてくると胸が高鳴った。馬の蹄のドアノッカーを鳴らすと、にこにこ笑った老婦人が出てきた。
「ようお越しやす」
扉の内側に入ると、玄関ポーチのチューリップ型の灯りの飴色の暖かいこと。
そこで、気づいた。前回は気づかなかったのだが、玄関の壁に、女性を描いた大きな肖像画が飾ってあった。
紅葉が真っ盛りの背景、少し斜めを向いた女性の油彩画である。クリーム色のセーターを着てブラウンとオレンジ基調の花柄のフレアスカートをはいて、お寺のような大きな畳敷きの部屋に美しい姿勢で正座している。
「晩秋らしい絵ですね。正座が引き締まっていますわ」
「これどすか? お気に入りどすか」
「はい」
「この前の風邪ひきはいかがどすか」
「ありがとうございます。もうすっかり良くなりました。あの日、暖炉で温まらせてもろたおかげ様です」
にっこり返した。
座敷へ通されると台所からいい匂いが漂ってきた。
あさりのすまし汁だ。老婦人が盆に塗りの黒光りした椀で運んできた時、分かった。
透子はお椀を開けてから、寿司の包みを開けて皿に並べながら、
「あさりのおすまし。私の大好物です」
お世辞ではなく、本当にそうだった。
「そう、良かった。柿の葉寿司も私の大好物どすえ。おおきに」
「鯖寿司とどちらにしようと思ったんですが」
「どちらも好きどす」
「まあ」
「さあ、いただきましょう」
ふたりとも正座して合掌し、お箸に手をつけた。
小さなアパートには、小さなダイニングテーブルが置いてあるだけの殺風景さだ。正座して向かい合って食事をいただく美味しさ、楽しさを忘れていたが倫江の正座は目をひいてしまう清々しさではないか。
柿の葉寿司は、奈良と和歌山が有名だが、関西では好まれて食べられる。鯖、鮭などが具の押し寿司で、柿の葉で包まれている。
「美味しおすなあ」
優しい眼元が笑った。透子は再び伺って良かったと思った。
「奥さん、本当にありがとうございます」
「奥さんやなんて、倫江さんて呼んでおくれやす」
薫るような笑顔でそう言われた。
「そしたら、そう呼ばせてもらいます。私は透子と申します」
第 五 章 倫江の過去
食事の途中で倫江が佃煮を出して来て、さらに食事は進んだ。何気ない世間話をしながら楽しい時間は過ぎた。
「また、長居してしまいました」
透子が食器を片付けようとするのを、
「そんなん、放っておいてくださいな」
「でも、そんなわけには」
「お客さんにそんなことしてもらえへん。ほんまにそのまんまにしておいて」
仕方なく透子は引き下がった。
倫江がさっさと食器を下げ、しばらくするとコーヒーのソーサーをふたつ運んできた。渋い抹茶色のソーサーだ。
「コーヒー、お好きどすか」
「あ、はい」
「洋間にいきしましょう」
先日と同じオレンジ色の暖炉が燃えていた。前は気づかなかったが、暖炉の脇に薪木がたくさん摘まれている。
(女には巻き割りは無理だろうし、誰か雇っているのだろう)
ふたりでソファに座り、食後のコーヒーをいただいた。
「静かですねえ。お家が道から奥まっているから物音ひとつしないですね」
「静かなのはいいんですけど淋しおすえ」
しかし、倫江は、少しも淋しそうに見えない。
「私の京ことば、ちょっと、おかしおすやろ」
いきなり言い出した。
「いいえ。私は京都の地元育ちですけど、おかしいと思いませんよ」
「そうどすか。ほんなら好かった」
倫江はひとつ息をついてから、
「私ねえ、京都市内に出てきたのは八歳の時で。それまでは両親と北の丹後半島の育ちでね、父が事業に失敗して、こちらに出てきたんどす」
透子は頷いた。
「そやから、日本海側の言葉がしみついていて、時々、京ことばに混じっているかもしれへんの」
「大丈夫です。まるきり京ことばですよ。丹後半島は子供の頃、毎夏、泳ぎに行ったんで土地勘があります」
「そうどしたか」
コーヒーの渦巻の湯気が、倫江の頬をなぶっていく。
「私はずっと市内です。上京区です。今はここから歩いて五分ほどのアパートにひとり暮らしです」
「お勤めは?」
「事務職です。小さな会社の」
倫江が何度も頷いた。
「ご両親はご心配でしょうね。お嬢さんのおひとり暮らし」
「そうでもないみたいですよ。実家を離れた時は、母親がお惣菜作って週に何回も来たり電話してきたりしましたけど、だんだん減って」
「そんなことはありまへん。親というものは」
ふと、透子は倫江に身内のことを訊きたい衝動にかられたが、何故か憚られた。
「柿の葉寿司もよろしいけど、私、こう見えてファーストフードも大好きなんどすえ」
「まあ、想像がつきませんでした」
「若い方とおしゃべりするのも大好き。週に何回かは、お稽古事に通ってますのえ。アロマや万華鏡教室。年齢がまちまちの方が来はります」
「そうなんですか。ご趣味が多いんですね」
「趣味まで行きまへんの。ずっとお稽古のままでしょう」
苦笑する倫江が、本当に人柄が良さそうなのが伝わった。
第 六 章 割れた湯呑み
仕事について十年。ひとり暮らし始めて七年。
毎日、同じことを淡々とこなす。
大学を出て何になりたいとか特別な夢はなかったので、不満はない。会社の人間関係も、まあまあうまくいっている。
ただ―――。
あの人がいなくなった痛手は大きい。三年経っても引きずっている。熱烈な恋愛でもなく、ただ、会社仲間と出かけた永観堂で知り合い、半年後に交際を申し込まれておつきあいしていただけだ。結婚を意識したこともなかった。冬には狭い部屋で寄り添っていると心地好かったのは確かだが。
しかし、いなくなってみると、存在の大きさを知らされた。
アパートには彼の生活用品がかなり残されていた。
職場の誰にも最初から今まで、彼のことは話していない。それが、最近、囁かれているような気がするのだ。三年も経った今になって。
「透子さんの彼氏さんて、三年前に事故で亡くならはったんやて」
「今も忘れられんで給湯室で泣いてはるねんて」
誰からともなく、そんな噂が透子の耳に届いていた。
後輩の女子が、そんなことを噂しているらしい。
(何故、今になって)
気の毒がられて哀れみをかけられてるようで、あまりいい気はしない。
職場に特に頼れる先輩もいない。苦痛になってきた。よけい、彼のことが忘れられなくなるではないか。
ある日、職場での噂を思い出していて、何気なしに彼の湯飲みを食器棚から取り出して眺めていて、手を滑らせた。湯飲みは床に落ちて砕け散った。
瞬間―――周りの世界がバラバラになったように感じて、全身から力が抜けた。胸がどきどきした。亮太の死を知った瞬間の恐怖がよみがえった。
透子はようやく跪いて散らばった破片を拾おうとしたが、手を止めた。彼の湯呑みが割れてしまった。もう二度と元に戻らない。彼の笑顔は現実には見られないのだ。
涙が溢れてきていた。
気がついた時には、倫江の邸宅に飛びこんでいた。
「ど、どうしはりましたのえ」
廊下の奥から、倫江が小走りに駆けてきた。
「倫江さん、私―――」
それ以上は胸がいっぱいになって何も言えなくなった。涙が後から後からあふれて、倫江の白い割烹着を濡らした。
倫江から貸してもらったハンカチが、ぐっしょり濡れてしまった。
しばらくすると、やっと昂りがおさまってきた。
「すっきりしましたか?」
洋間の床に座りこんでいたふたりは、透子がひとしきり泣くまで正座してじっとしていた。
「は、はい、すみませんでした。ご迷惑をおかけして」
「迷惑やなんて。そんなこと思てしまへん。透子さんのご事情はよう分かりましたえ」
透子は、彼――亮太という恋人がいたこと。彼が三年前に亡くなったこと、今頃になって勤め先で、そのことが知れ渡って不快に思っていること。すべてを倫江に打ち明けたのだった。
倫江なら、聞いてくれる人だと思った。聞いてくれるだけで気がすんだのだ。
「大丈夫?」
「はい。聞いて下さってありがとうございました。勤め先のことも何日かしたら自然と消えるでしょう。本当に私ったらいい歳をして何を泣いているのだか」
「もしや、亮太さんが亡くならはった時に、あまりなショックで泣けへんかったのと違いますか?」
倫江の言葉に、透子は下を向いたまま頷いた。痒いところに手が届くような倫江の言葉だ。
「透子さん、いつも私の正座を褒めておくれやさかい、正座をお教えしまひょ。もっとすっきりしますえ」
「正座を?」
「お座敷へおいでやす」
倫江は座敷に招き入れ、
「背すじをまっすぐにして畳に膝をつきます。そしてかかとの上に座って。スカートの裾は膝の内側にはさんでね。両手は力を抜いて膝の上に置きます」
透子は言われるとおりにした。いつも気にかけずに正座していたが、姿勢など意識してみると気分が引き締まった。さっき泣いていたことが遠くへ行った気がする。
思えば、肖像画の女性も清々しく背すじを正して、かかとの上に座りスカートの裾も礼儀正しく膝の内側に挟み、両手は静かに膝の上に置き、正座をしていた。少しはそれに近づけたのかもしれない。
「お上手どすえ」
倫江が褒めてくれ、気分はすっかりおさまった。
ふと窓の外に植木を隔ててアトリエのような建物があることに気付いた。
「そういえば、キャンパスとイーゼル……」
最初に伺うきっかけになったのは、キャンパスとイーゼルが庭に倒れていたからだ。
(倫江さんは油絵でも描かれるのやろか)
透子の心に小さな疑問が湧いたのだった。
第 七 章 誕生日
やがて春が来た。
倫江の暖炉もしばらくお休みすることになった。
四月に入り、桜もほころんだ頃、久しぶりに透子は倫江のお宅に顔を出した。
冬に泣いてしまったこともお詫びしたかったのが、そのままになっていたからだ。
門戸を開くと、真冬とはまったく違う世界が広がっていた。
梅もどきの赤い実は緑の葉に変わっていたが、足元には雛菊とピンクのオキザリスと芝桜の花が咲き乱れ、薔薇の大きな木が何本もあり、柔らかい黄色に、花びらのふちだけはオレンジという明るい色の大輪がたくさん咲いていた。
倫江が丹精込めて世話しているのだろう。見事な庭だ。
透子は、前に目にしたアトリエを見た。高い植木の向こうに、やはり立派な建物がある。レースのカーテンの内側には、絵画がたくさん並んでいる。
ドアノッカーを鳴らすと、
「はぁい」
元気よく倫江の声が聞こえてきた。
「しばらくでした、倫江さん。お元気でした?」
「透子さんもお元気そうやね。さ、さ、あがってあがって」
靴を脱ぐ前に、玄関の大きな壺に庭に咲いていた薔薇がてんこ盛りに活けてあるのに気づいた。
「この薔薇、見事ですね」
「一本目の木はかなり年数が経ってますのやけど、どんどん増えてしもてねえ。主人と所帯を持った時に買った、この家の庭に昔から咲いてましたのや」
庭の薔薇を眺めながら、お座敷で先日のお稽古通りの正座をして待つ。
倫江の正座は見事だ。背筋がしゃんとしていて年齢を感じさせない。もっとお稽古して彼女に近い正座が出来ればいいなあ、と思いながら、透子は先日のお稽古通り何回も正座を繰り返した。
廊下に足音がして、と思ったとたん、透子の目の前に黄色くてオレンジの花束が溢れた。あの薔薇だ。リボンがついている。
「お誕生日、おめでとう」
透子は面食らった。
「どうして私の誕生日を? 言うてへんはずやのに」
「さあ、なんでやろね」
倫江は惚けるように笑って、花束を持たせた。
「ありがとうございます……」
薔薇に顔をうずめて、心からお礼を言った。この色合いの薔薇が、透子は一番好きなのだった。
花屋さんの前をふたりで歩いている時に、亡くなった亮太にも言ったことがあったが、亮太はまったく無関心に「ふうん」と答えただけだった。
そして、サプライズはまだ続いた。倫江が大きなクリームケーキを持って現れたのだ。
「これでお祝いしましょう」
「倫江さん、これ、もしかして手作りですか?」
彼女は、大きく頷いて胸を張ってみせた。こういう時に堂々としているのが、倫江らしい。
「まあ、喜んでいただきますわ」
倫江は、鼻歌を歌いながら蝋燭を立てて、縁側のカーテンを閉めた。部屋が真っ暗になり、蝋燭にマッチで火を点けていった。
そして、歌った。
「ハッピーバースデー、透子さ~~ん、ハッピーバースデー、ディア透子さ~~ん~~~、はい、透子さん、ふうってして!」
急き立てられて、ふうう、とした。
蝋燭の火は見事に一度に消えて、倫江が満面の笑みで拍手した。
「ありがとうございます……」
深々と頭を下げた。こんなことは何年ぶりだろう。高校時代に女友達がやってくれた時以来だろうか。
「娘がおりまへんさかいね、私、こういうこと一回やってみたかったんですよ。そやからご遠慮なくね」
お言葉に甘えることにした。
ケーキをいただきながら、久しぶりの春の歓談は、なんと楽しかったことか。しかし、どうして倫江は、誕生日を知っていたんだろう?
「あのう」
ケーキを食べ終えてから、透子はバッグからチケットを二枚取り出した。
「今度、もしよろしかったら、ご一緒していただけませんか?」
それは、ヨーロッパ中世の美術展のチケットだった。
「お好きかな、と思って」
「いや、まあ、これ、行きたかったんやわ。おおきに。一緒に行きましょう」
「喜んでもらえて、嬉しいです」
透子もほっとして微笑んだ。
座敷続きに広い仏間があり、そこにもどっしりとした木目の座卓が置いてあるが、透子はふと背中に視線を感じた。
振り返ったが、誰もいない。
ただ、煙草の匂いが残っている。ついさっきまで、そこで誰かが煙草を吸っていたような。人の気配さえ残っている。
首をかしげながら、なんとなくやり過ごした。
第 八 章 肖像画
「透子さん、今日は見てもらいたいものがあるの」
倫江が立ち上がって、廊下を歩き始める。庭に突き出た部屋への廊下を歩いていく。透子も急いでスリッパを履いて後に続く。
行った先は、ウッド造りのアトリエだった。壁は木製だが、床は畳敷きになっていて和風になっている。たくさんのキャンパスや絵の具、描きかけの絵が置いてある。静物画も、風景画も、人物画も。
透子はアトリエの真ん中に正座して絵画を見回した。
一番、大きなキャンパスの絵は、透子の好きな永観堂の紅葉の絵だ。
「永観堂……」
「そうよ、想い出あるでしょう」
倫江の言葉に驚いて彼女を見ると、
「この絵をご覧なさい」
畳の上に正座してちゃんと額装してある大きな絵を見た。髪の長い女性が、お寺の畳敷きらしき部屋で紅葉をバックにまっすぐ正座している。
「これは、玄関にあった肖像画」
「そう。この肖像画の女性はあなたですよ、透子さん」
「えっ」
驚いて見直した。そういえば、顔の感じが自分に似ている。髪の、ひたいの生え際や視線の向け方など。
「どういうことですか? この絵は倫江さんがお描きになったの?」
「いえ、まさか。私に絵心はないわ」
「じゃあ」
「この絵は、亡くなった主人が描いたの」
「えっ」
いきなりの話の内容が理解できない。
「ごめんなさいね。わけがわからへんねえ、主人は画家でしたの。このアトリエで絵を描いていました。亡くなったのは七年前。じゃあ、昔に描いたはずなのに、何故、あなたを描けたのか不思議やね。私も不思議に思うわ。そやけど主人がそう言うから確か」
透子は正座したまま微動だにできなかった。
倫江の言葉の意味がよくわからない。
「主人は、亡くなってから行った世界で、ひとりの青年から写真を渡されたっていうの。その写真に写っている女性の肖像画を頼まれたって」
「……」
「その写真がこれよ」
倫江が紬の襟元から出してきた写真を見て、透子は眼を釘付けにされた。
いつぞやふたりで永観堂を訪れた時、溢れる赤や黄色の紅葉をバックに亮太が写したものだ。
亮太は携帯電話の時代に生きながら、フイルム写真も好きだった。
「私、私だわ。確かに。髪が今より長いから気づかなかったけど、私だわ」
震えてきた。
「倫江さんのご主人が、亮太さんから私の肖像画を頼まれた―――?」
「信じられへんのも無理あらへんね。私ね、夢の中で主人によく会いますのんえ。主人も夢の中でこの家に自由に帰ってきていて、肖像画を描いたんどす」
倫江は、写真を透子に渡した。
「頼んだ青年が、特別大切な人で特別の場所だから、ぜひお願いしますって念入りにお願いしたそうよ」
「特別、大切な人で……」
写真が一気に涙でぼやけた。
「亮太さん、倫江さんのご主人と天国で逢ったんですね。それで、倫江さんは、私の好きなものや誕生日をご存知だったんですね」
「お誕生日に、何ひとつプレゼントしたことがなかったから、肖像画をプレゼントしようと思ったそうよ」
「まあ」
冬の日、暖炉の前で眠ってしまった時、亮太の夢を見たのはそういう意味があったのか。
「主人たら頑固な人でね。その絵だけは、暖炉の部屋のロッキングチェアの上に立てかけて描くと言ってきかなかったの。その間、私はロッキングチェアに座れず、床で正座したまま見守ってましたのえ」
「いや~~、それは悪いことをしました。でも、倫江さんの正座は美しくて周りの人もシャキッとさせますから、ご主人様もそれを見て、肖像画の中の私を描いてくれはったんと違いますか」
「そうかもしれへんねえ、透子さん」
アトリエの大きな窓が春の風で両開きになった。吹きこんできた風には、黄色くて縁がオレンジの薔薇の香りが溢れている。
正座の膝の上に自分の写真を置いたまま、透子はいつまでも背筋を伸ばして座っていた。
(ありがとう。亮太さん。透子のことを見守っていてくれて)
オレンジの縞のセーターを着た亮太の姿が何度も瞼の裏に去来した。