[37]正座の幸福
 タイトル:正座の幸福
タイトル:正座の幸福
発売日:2018/8/01
シリーズ名:須和理田家シリーズ
シリーズ番号:4
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:44
定価:200円+税
著者:虹海 美野
イラスト:時雨エイプリル
内容
高校生の須和理田サクラはダンス部に所属し、華やかな友達三人と過ごしている。
しかし、須和理田家は母の意向で居間が和室、正座などの行儀についてのしつけを重視する家庭だった。
友達の家庭と比較し、地味な家族をサクラは不満に思うも、心の底では母のことを尊敬している。
ある日学校の執行部が募集をかけ、サクラは新たな出会いを求めて友達と応募する。
選考の場の雰囲気に呑まれ、自己アピールに失敗するサクラだったが……。
販売サイト
販売は終了しました。

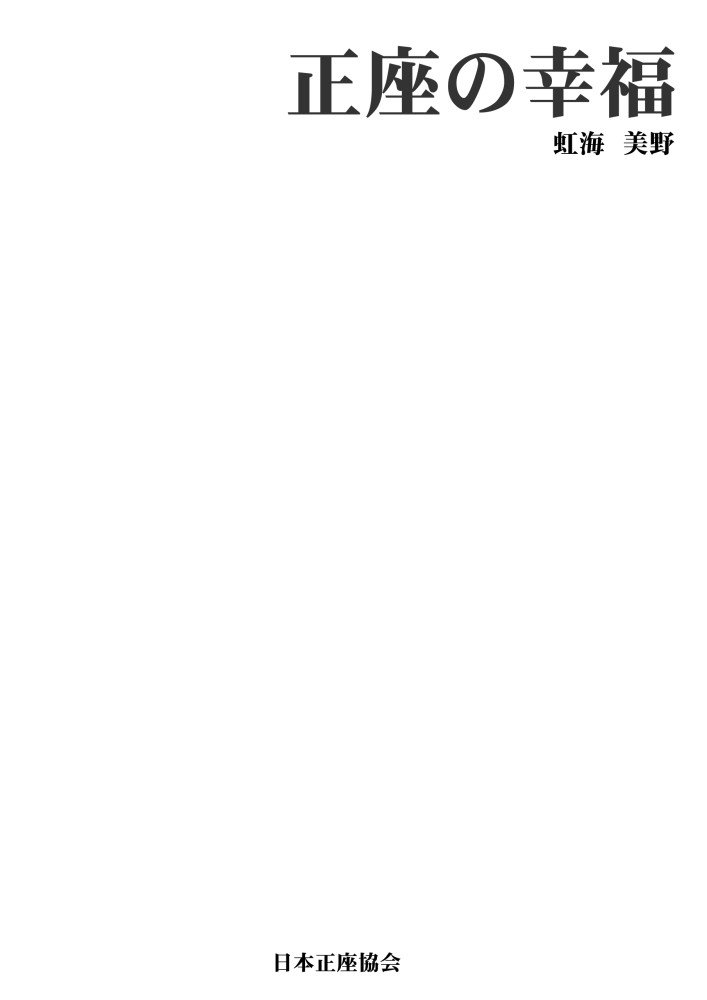
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
須和理田サクラは高校生である。家族構成は父、母、兄にサクラの四人。父と母は高校の同級生で二十代半ばに結婚し、翌年の春に兄、緑が生まれ、その翌年の初夏にサクラが生まれた。現在サクラが暮している最寄駅からひとつ下り方面にある駅で下車し、バスで十五分ほどのところに、父の実家、母の実家がそれぞれある。父は大学卒業時より勤めている会社に徒歩で通勤し、母は市内に二店舗ある地元民に愛される和菓子屋さんのひとつでパートをしている。この和菓子屋さんで母は高校の終わりごろより大学在学中にバイトをしていた。大学卒業後に就職し、結婚を経て、兄、緑を妊娠後に退職。サクラが小学校中学年になるまで育児に専念していたが、その間、母の母、つまり緑とサクラの祖母がこの和菓子屋でパートを開始し、現在は祖母と母がほかの主婦パートさん数人とともに勤めを続けている。和菓子屋で母がバイトをするに至った経緯は、母が高校時代に茶道部でお茶菓子を定期的に買いに行き、お店の人と懇意になり、大学の推薦入試の合格が出た秋の終わりに、ちょうどお店でバイトを探しているという話を聞いてから、というものだったらしい。
兄はサクラより一学年上で同じ高校に通っている。趣味は囲碁と園芸という、退職後のおじさんのようだが、本人は全く気にした様子もなく、囲碁クラブと園芸部を兼部し、充実した高校生活を送っているようだ。最近は学校内の活動だけでは物足りないらしく、広い庭のある父方の祖父母宅へ通い、曽祖父が遺した囲碁の本を読んだり、家庭菜園を行ったりしている。どう見てもリア充から程遠い生活だが、驚いたことに学校内でもちょっと目を見張るようなきれいな同学年の女子と兄は付き合っていた。兄は先にも述べたように文化部に所属しているが、足だけは速く、体育祭ではクラスの選抜リレーに出てはそこそこの活躍を見せている。妹のサクラから見て、一般的に女子が兄の特徴を挙げるとすればそれくらいだ。あまり納得はできていないが、あのきれいな先輩は足の速い男子が好きという趣向なのだとサクラは考えている。兄の性格、一般女子からの関心の低さを考えても、兄から果敢にアピールするというのは無理そうだ。
ここまでが、だいたいのサクラの家族説明だが、サクラは何となく、この家族に馴染んでいないというか、不満があった。父、母、兄は何の疑問も持たず、淡々と今の家族での生活を送っている。
口数の少ない父に、学生の頃よりバイトは和菓子屋、高校生の頃の部活は茶道部、現在のパートも和菓子屋という母に、囲碁クラブと園芸部に所属する同じ高校の兄は、サクラにとってあまりにも地味というか、物足りなく感じるのだった。
2
サクラは子どもの頃から、学校での劇や音楽会での役やポジションにこだわるところがあり、仲良くなる子も同じような感じだった。
サクラは中学から、学校内では花形とされるダンス部に入っている。高校でもそうだ。正直なところ、新入生歓迎会の時に生徒席から送られる拍手喝さいに憧れての入部だった。体の柔軟性やリズム感といった適正は二の次で、とにかくダンス部に入ろうと決めていた。学校内で女子に存在感を示すと感じるのはバスケ部、女子に支持される女の子が多くいるのがバレー部、特定の仲間がたくさんいるのが吹奏楽部というサクラの中での位置付けがあったが、バスケは地域でバスケをしてきた運動神経がよく、少し勝気な子が大部分を占めていたし、バレー部は練習時間が長いことで有名で、吹奏楽部は少なからず楽譜が読めなければならない。一方サクラの通う中学のダンス部は、子どもの頃よりダンスを習っている子はそのままダンスレッスンに通い、学校のダンス部には入らないことが多い。そのため大半の子が事実上初心者であり、且つ外見に自信のある子ばかりのダンス部をサクラは選んだのだった。
現在、サクラの周囲は同じ部活の子や、他の部活でも比較的活発で派手な容姿の子が多い。校則に触れない程度で化粧をし、髪を整え、制服の襟もとを開けたり、スカート丈を調整する。仲良くなってサクラがよく目にするのは、友達と「ママ」とのツーショット写メだった。とても親子とは思えない、友達のような「ママ」ばかりだ。サクラは母とそんなツーショットを撮ることはなかったので、そういう時には、友達の「ママ」を褒める側に徹した。褒められた友達はまんざらでもなく、「ママ」が昔芸能事務所からスカウトされたことがあるとか、雑誌に載ったことがあるとかいう話を披露した。しかし、高校からバスで真っ直ぐに自宅に帰り、大学に入ってからは地元の和菓子屋でバイトをしていたサクラの母に、そんな華やかな自慢話があるわけもなかった。
五月下旬、ダンス部の練習を一階トレーニングルームでしていた時、この日行われた保護者会に出席した親が、会の終了後何人かずつで話しながら教室から出て来た。先輩の合図で一度動きを止め、「こんにちは」と皆で挨拶する。遠慮がちに会釈する保護者はサクラの友達三人の「ママ」と、サクラの母だった。三人の友達の「ママ」はセレブ主婦御用達の雑誌の表紙や、美魔女、と呼ばれる年齢を感じさせない女性の代表のようなファッションだった。一方のサクラの母は薄い水色のタイトスカートに白いブラウスだった。三人の友達の「ママ」をサクラは「モデルさんみたい、とても高校生の子がいるように見えないね」と褒めた。友達三人はサクラの母を「サクラと似ている」と言うに留めた。友達三人は満足した様子で、何事もない顔をしていたが、サクラにはこの一件が引っ掛かった。
帰宅後、サクラの母は「お友達のお母さん、本当にきれいね」とひとしきり感心していて、それが余計にサクラを苛立たせた。
娘の欲目を差し引いても、容姿ではサクラの母は、友達三人の「ママ」に引けをとらなかった。むしろ、サクラの母は年齢による体型の崩れも見られず、肌も髪も艶がある。薄化粧に留めている分、バランスやつくりの整い具合の良さもわかる。
ただ、自分を美人です、とプロデュースする気がまるでない人だ。
母にとっての基準は自分であり、周囲ではなかった。それは子どもの頃からわかってはいたが、世の中に優劣、勝ち負けというのは存在する。母のようにしていては、サクラは敗北感を味わわなくていい場面においても、勝手に相手に勝者を意識させてしまう。
そこまで考えて、サクラが思い至るのは、母のしつけだった。
~に負けないように、ということはテストでも運動会でも言われたことはなかったが、箸の使い方、姿勢や正座についてはことのほかうるさくしつけられた。小学校、中学校、高校ともに移動教室や修学旅行は座敷での食事だった。この時「須和理田は行儀がいい」と、あちこちから褒められた。昔家族で旅館に泊まった時に、朝食を部屋食ではなく和室の食堂でいただくことになった際にも、須和理田家は全員姿勢がよく、きちんと正座してきれいに食事をしていた記憶がある。あの時サクラは子ども心に、なんで他の家の人はきちんと座って食事ができないんだろうと不思議に思ったものだった。
正座をする時は両膝をつけるか、にぎりこぶしひとつ分程度の開き具合にすること、足の親指同士が離れないようにすること、背筋をまっすぐに伸ばすこと、スカートは広げずにお尻の下に敷いて座ること、ということをかなり小さい時に母から言われた。
もともと父も母も姿勢がよく、いつもきちんと正座をしていたので、特に違和感もなく、兄も幼い頃から自然に正座をしていた。
ただ、うちはお行儀についてはそういうしつけをするけれど、よその家の子には、その家の方針があるからあなたが無理強いしたりはしないようにね、と母はつけ加えたのだった。
勝気なサクラは、時折注意したり、何か言いたくなることがあったが、女の子同士の付き合いで、アドバイスであっても注意であっても、相手から求められない限りはしない方が穏便にやっていけることは、正座に限ったことでないと承知していたので、いつも黙っていた。
3
「サクラちゃんて、お嬢様育ち?」
ふいに話しかけられ、サクラははっとした。
今日は先週の夏祭りでのダンス発表の仲間内の打ち上げで、カラオケに行った後ファミレスで食事をしていた。部活の子の友達つながりで、他校の男子が五人参加している。その中の一人がサクラに話しかけていた。
「全然そんなことないけど」とサクラは答えた。
和風好きの母は自宅の居間も和室にしているが、もともと贅をつくした日本家屋、というわけでもなく、洋間でも和室でも対応可能という一室を和室にしたため、和の風格が漂う、というよりは、昭和の香りがするといった方がしっくりくる。食事も野菜が中心で、味付けは天然だしが基本で薄めである。『お嬢様育ち』という言葉から連想されるゴージャスな暮らしぶりとは程遠い。
「姿勢がよくて、こんなに箸遣いがきれいな人、見たことなかった。なんかすれた感じもないから」と男の子は続ける。
すれた感じもない、というのは、自宅での野菜が多い食事で肌や髪、爪が健康的だからだろうとサクラは思う。これみよがしなメイクをしていなくて、髪色を変えていなければ、そんなふうに見えるものだ。
「そんなことないって」
そう言ったのは、サクラではなく、友達だった。
勝気な性格はお互いさまなので、こういう友達の妨害はそれほど意外ではなかった。
「普通にこの子、購買のパンとか買うよ」
もう一人の友達も続ける。
「あ、サクラはいつもお弁当だっけ? 野菜が多いおかずと、日本茶」
『そんなことないって』と言った友達が、微妙な訂正を加える。
「日本茶? 渋いね」
日本茶で男の子が少し笑うと、一気にその流れを作るように、サクラの兄の部活動のことや、サクラの母が和菓子屋でパートをしていることにまで話が及んだ。
友達三人はサクラが男の子に褒められた話題から遠ざかることに集中して、サクラの笑いネタになりそうな情報をしゃべり続けた。そして、その話題で、男の子が笑ってくれれば一石二鳥、という空気だった。
こういうことはサクラの仲間たちでは珍しくなくて、入学後に一緒にお弁当を食べるようになった頃から、『毒舌だけど面白い』性格だとお互いに言い合っていて、仲間内でのちょっとしたことにツッコミを入れては笑ったりして、更に仲良くなってきた。サクラだって、友達の小テストで苦し紛れの変な回答を見つけた時には他の子に言って、皆で笑ったこともある。
帰ってからそのことを母に話した時、母は「自分で考えた面白い話ならいいけど、人の失敗を自分の笑いとして人に提供するのはルール違反だと思う」と真面目に言った。せっかくの面白い話が台無しというか、そんな返答なら教えなければよかったとサクラは機嫌を損ねて部屋に入ったが、翌日になっても母の言葉はサクラの心から消えず、友達に昨日笑ったことを謝った。友達はサクラを見て、少しの間を作った後に「もういいよ」と言ったけれど、きっとごく小さなものであっても、サクラの言葉は友達を傷つけていたのだと自覚した。些細なことだったけれど、それはサクラが高校で新たな友達との関係を築く上でとても重要なことになった。
自分自身で気をつけ始めたことだからこそ、無自覚にサクラの家族を話題にして男の子の気を引こうとする友達の行為が、サクラを傷つけた。
『うるさいなあ、人のこと言える? そっちだって』と、言ってしまえば、それで話題は変えられるし、やり返したことでスッキリもすると思う。けれど、勝気であるサクラは、全く勝ち負けにこだわらない、あの母の教えを覆せない。言った当人である母は、サクラとのそんなやり取りも忘れてしまっているかも知れないが、サクラの中では、この先もこうした状態になるたびに、悔しさに堪えてその場をやり過ごすことになり、周囲はサクラが我慢するに至る母の言葉を知ることなく、面白おかしいで済ませてしまうのだろう。サクラも自分の母があの母でなければ、恐らくそんなことは考えなかったと思う。母の幼い頃からの思い出の話は、もし母が同級生だったら友達にすらなっていなかったと確信するほどのサクラの心にも響くものがあり、サクラは母という人をとても素直に受け止められる。
母が子どもの頃憧れた家の庭には桜の花が咲いていて、そこで会った女の子とおじいさんが忘れられなかったこと、高校生になって気になる男の子とその後付き合いはじめ、その男の子の家が子どもの頃に憧れていた家だと知ったこと。子どもの頃に会ったのは、その男の子のおじいさんと妹だと知った時の、湧き上がるような温かな気持ち。その男の子の家に結婚の挨拶に行った時に丁寧に迎えてもらったことや、子どもがおなかにいた時に体によいおかずを考えて作ってもらってうれしかったこと……。
母の住まい、家族への食事には、小さな記憶を大切にし、温めてきた思いが込められている。
小さな母の中にある物語は、母という人を通し、一つの道となり、今のサクラの家族の支柱となっている。
……そんなことは、わかっている。
わかっているから、もどかしい。
友達の自慢話に頷くだけの自分が。
そして、本当は臆病な自分が。
大切な家族のことを友達との話題の中に簡単に出すことを、サクラは無意識のうちに躊躇っていた。
勝ち負けが好きな子と友達になりたかったのは、確かにサクラ自身だ。自分にも、そういうところはある。けれど、その話題に家族を持ち出し、勝ち負けの判断基準にされることが恐かった。そういう目安を持たない家族が、サクラから語られることにより、友達から無遠慮に価値基準を決められることが嫌だった。
どこかで家族が友達の家族より下に見られると考えている自分が、本当はとてもとても嫌だった。
「……野菜は、身体にいいんだよ。お茶を持ってきているのは、温かいものを飲めるメリットもあるし、落ち着くからだよ」
サクラが笑ってそう言うと、「そうだよね」とか、そんな曖昧な同意の言葉が重なり、話題はほかに移っていった。
4
翌日の学校では、皆なんでもなかったように、いつも通りに仲良くしていて、サクラの家族の話題が出たことも忘れられているようだった。
体育の水泳では朝からタイムを計った。水泳部の子はもちろん、バレーやバスケ、ハンドボール、陸上など基本的に毎日運動している子はタイムもいい。サクラの友達は水泳部の子と一緒のスタートでタイムを計った。一緒に泳いだ子との順位で成績がつくわけではないが、負けず嫌いの友達は真剣な面持ちでゴーグルをつけ、合図とともにプールに飛び込んだ。激しく上がるバタ足の飛沫に、友達の必死さが伝わる。「頑張れ」と、プールサイドにいる他の友達と声援を送る。
ダンス部の子は、普段鍛えていることに加え、もともとのプロポーションのよさもあり、やはりプールサイドでも目立つ。そして自分に自信があって、負けたくない気持ちを前面に出す。
やっぱりこの仲間がいい、とサクラは思う。
昨日の小さなわだかまりで、今の友達を失いたくはなかった。
この日は一時間目の水泳の後に英語のテスト、歴史のテスト、授業中に必ず当たる数学と気が抜けず、午後のホームルームではサクラはうたた寝していた。後ろの席から椅子の脚を軽く蹴られ、振り返ると友達が黒板を差している。
生徒会からの執行部募集というものだった。
活動内容は文化祭や学校説明会、及び入試説明会や入学説明会、入学式といった来校者が大勢訪れる日に、学校前や校内の通路で挨拶をしたり、案内をするらしい。主宰は生徒会となっているが、事実上職員では補いきれない来校者への対応への応援要請といったところだ。生徒会、部活の三年生が一学期の始めより夏休みまででほぼ活動を終えて受験に専念する時期に入り、二年生の引き継ぎとともに、学校生活に慣れた一年生を含め、新たな執行部員を今から募集するという説明が加えられる。
確かにサクラが中学生の時に文化祭や学校説明会に来た時、とても感じのよい在校生があちこちに立ち、挨拶して迎えてくれたし、行きたい教室を聞いた時にも親切に応じてくれた。
「一緒にやらない?」と友達が言う。
「面倒じゃない?」
「でも、学校活動に積極的に参加したってことで内申にもプラスされると思うし、ああいう執行部はかっこいい先輩が多いよ」
確かに、とサクラは思った。
ダンス部への入部に後悔はないが、周囲の運動部の友達は部活内での男の先輩との交流がいかに楽しいかをよく話していて、女子だけのダンス部であるサクラたちには、そういった男の先輩と一緒に活動する中で距離を縮めるというのが以前から羨ましかった。それに確かに執行部などで活動する男の先輩は人望が厚く、性格ももちろんよく、どういうわけか外見もよかった。成績がいいのは言うまでもないらしい。接点がなければ遠くから見ているだけだが、一緒に活動するとなればチャンスもあるかもしれない。
「これ、希望すれば誰でもなれるの?」
誰かが学級委員に質問した。
「一応、ここには『当校の模範となる行いのできる生徒』が条件になっています」と学級委員は手元の紙を見て言った。
「はい、やります」
友達が手を挙げ、サクラも一緒に手を挙げ、少し離れた席にいる仲間二人もサクラ達に目配せして手を挙げた。
5
後日、執行部活動説明、選考の日程が教室の後ろに貼り出された。
「え、これ、希望者が全員なれるんじゃないの?」
サクラは友達と紙を見ながら、気楽に立候補したことを後悔し始めていた。
学校説明会などで挨拶に立つ在校生に、スカート丈が短かったり、ワイシャツの第一ボタンを外していたり、髪を少し茶色にしている人はいなかった。皆、きちんとしていた。それは、こういった「選考」がなされていたからだったのだろう。
当日少し早めに着いた集合場所の視聴覚ルームは、絨毯が敷かれ、パイプ椅子は片付けられていた。
広い視聴覚室の隅にあるホワイトボードには、『自己紹介』、『立候補した動機』、『執行部でやりたいこと』と書いてある。
あれを言うらしい。
どうする、と友達同士で小声で言い合った。
まだ『やめます』、と言ってもいいのだろうか。
けれどそこへ同学年の男子とはちょっと違う大人な感じで素敵な男の先輩が入って来て、「こんにちは」と微笑みかけられ、サクラたちは小さな声で「こんにちは」と返し、その場に留まった。その後生徒会や執行部ほか、希望者が視聴覚室に集まった。
希望者は二年生も含めて全部で五十人くらいいて、先輩達は希望者が多いことを喜んでいるようだった。執行部は生徒会と基本的に活動し、人数が足りなくなると、生徒会役員の友達や各部の部長なども補助要員として駆り出されることがあるらしかった。
活動内容などをよく通る声ではきはきと説明していった生徒会の先輩は、そこでだいたい円になって座るように指示し、皆の顔が見える状態で、ホワイトボードに書かれた自己紹介などを順番にしていくように言った。室内に僅かな緊張が走り、生徒会の先輩は、じゃあ僕からやってみます、と言って、淀みなく自己紹介や動機、やりたいことを話していった。緊張をほぐすための気遣いだったが、あまりにきちんとした生徒会の先輩の後に、同じようにしなくては、というような別の緊張感が漂う。
サクラたちが話したことのない、顔だけは知っている同学年の真面目そうな女の子も輪の中に数人いて、その子たちは休み時間や水泳の時間とは違った、堂々とした自信のある態度で選考に臨んでいる。今の友達と一緒にいることにどこか優越感を抱いていたサクラは、この場で自分の視野の狭さを感じた。いつもクラスの中心的なポジションにいるサクラや友達は、教室とは違った雰囲気の中で、明らかに委縮している。それでも持ち前の活発さで友達はなんとか自己紹介などをうまくまとめた。しかし、勝気ではあっても雰囲気に呑まれたサクラはそうはいかなかった。自己紹介でまずクラスを言い間違えて「失礼しました」と訂正し、その後の項目も全て最小限の特徴のないものに留め、「頑張ります」とどうにか締めくくった。正座をした両膝に手を添え、言い終わると、申し訳なさから一礼した。
やっぱり来るんじゃなかった、とサクラは後悔した。
合格者は明日担任より報告とのことで、そのまま解散になった。
6
この日は部活が休みだったので、友達はプリクラを撮りに行こうと言った。いつもなら一緒に行くサクラだが、とても行く気分ではないので、帰ることにした。
家族が地味で友達に自慢できないとか、友達はうちの家族のことをわかっていないくせにばかにするとか、色々思ったものの、自分自身はどうなのだということをサクラは延々と考え続けていた。考えても落ち込むばかりだったサクラだが、スマホに友達とのラインが入って、液晶画面を操作する。
これから友達の家に行くから、よかったら一緒に行こうということが書いてあった。
返事をする前に、友達三人が駅へ向かう道からまわって、サクラの歩いていた前方から走って来た。
「どうしたの?」
「なんか、元気ないからそのままほっとくの心配だねって」
「……ごめん、ありがとう」
サクラは小さく言った。
友達はサクラの両側に立ち、肩を抱いたり、頭を撫でたりしながら、コンビニでおやつを買って行こうとはしゃいだ。
「サクラは飲み物何がいい?」と訊かれ「緑茶って言ったら、笑うでしょ」とサクラが俯いて言うと友達は笑った後で、「この前はごめんね」と言った。
「いいよ、別に」
まだ俯いたままだったが、サクラは心が少しだけ軽くなっていくのを感じた。『何のこと?』と言われたら、きっとこのまま帰りたくなっていたと思う。
友達の家へ行くと、玄関に踵の細いハイヒールが一足あり、居間のソファにはブランドのバッグが投げ出されていた。システムキッチンから出てきた友達の「ママ」は、今年流行のサクラたちの年代の子が着るようなファッションで、明るくサクラたちを迎えてくれた。
「お邪魔します」と挨拶し、ぞろぞろと友達の部屋へ行く。
やっぱりおしゃれで、うちとは違う、とサクラは思う。
ごく普通にしている他の友達は、きっと自分の家も同じような感じなのだろう。
「散らかってて、ごめん」と言われて通された友達の部屋は、白いロココ調のデザインで統一された部屋だった。学生の部屋の定番だとサクラが思っていた小学校入学時に買ってもらった学習机や、百科事典が並んだ古い本棚も友達の部屋にはなかった。
部屋を友達と一緒に見ていると、中学か高校で模様替えしたと思われる部屋の中で、同化していないものがあった。ベッドの枕の隣にある巨大なぬいぐるみは、あちこちがほころびている。
何となく、三人の視線がそこへ集中し、この家の友達もそれに気付いた。
大丈夫かな、とサクラは咄嗟に心配になった。きっとあのぬいぐるみは友達にとっての支えみたいな存在だ。
「あ、この子、おじいちゃんとおばあちゃんが昔買ってくれて、今も一緒なんだ。今日、天気よかったから、ママが布団と一緒に干してくれたんだと思う」
そう説明した友達の声は明るかったけれど、どこか不安そうだった。支えを揶揄されて、どこまで攻防線を張れるか、きっと友達の心は揺れている。
「あの」と小さくサクラが声を出しかけると、「いいね、そういう大切なものって」と、隣にいた友達がスクールバッグを置きながら言った。この前、サクラのお弁当や日本茶のことを男の子たちに話して笑いを取った子だった。その意外さに驚きながらもサクラもすぐに「わかる」と頷き、「いいお母さんだね」と続けた。どこか気後れしてしまう華やかな友達の「ママ」の、友達に対する素朴で優しい一面を知った気がした。
もう一人の友達も表情を切り変え、「うん、かわいい」と頷いていた。
どこかほっとした、温かな空気が四月から『友達』として行動を開始した四人を包んでいた。
まだ、高校生だし、時々うっかりしたことを言うけど、いいことも言える。自分の友達はいい子だって、本当にそう思えるとサクラは思った。
友達の家では卒業アルバムを見せてもらったり、居間に移動してアイドルのコンサートのDVDを見た。
帰りにサクラはごく自然に「今度、よかったらうちにも来て」と言っていた。
7
翌日の放課後、サクラは教室で担任の先生に呼び止められた。
「執行部に決まったから、生徒会室に行くように」
サクラは何のことだかすぐに理解できなかった。
一緒にいた友達もさすがにやや困惑した表情で「え」と声を出した。
担任の先生は他の生徒に部活のことを聞かれ、そのまま立ち去り、サクラたちだけがその場に残った。
「駄目だった人が呼ばれるっていうのと言い間違えたのかな」とサクラは言った。
友達が「とにかく生徒会室に行ってきたら? 私たち先に部活行ってるから」と言い、もう一人の友達が「先輩には言っておくから」とつけ加えた。
「ありがとう」とお礼を言って、サクラは一般の教室が並ぶ長い廊下を急ぎ、渡り廊下より先にある生徒会室に向かった。
『生徒会室』と大きなゴシック体で書かれた紙が貼られたドアの前は通り過ぎたことはあったが、中に入るのは初めてだった。
ドアをノックすると、すぐに扉が開いた。
中には生徒会長の先輩がいた。
「こんにちは。須和理田さん」
名前で呼ばれ、生徒会長の先輩があの場にいた人の名前を記憶していたことにサクラは驚く。
「これから執行部の活動について説明する予定なんだけど、まだ皆来ていなくて……」
「あの、先生に執行部に決まったって言われたんですけど、私、多分、違います」
「……違うって?」
そう聞きながら、生徒会長の先輩はドアを開け放ってサクラに中に入るよう促し、サクラは生徒会室に入った。
「私、この前うまく自己紹介もできませんでした。多分、隣の人か、誰かと、間違っているんだと、思います」
「え」と生徒会長の先輩は、机に置いてある紙を手に取り、「須和理田さんですよね」と再度確認した。
「はい」
「採用になっています」
「基準って、どうなってるんですか」
生徒会長の先輩は落ち着いた様子で、かなり混乱しているサクラを見た。
「前にも説明しましたが、これからこの学校のことを知りたいと思っている人をきちんと迎えられる人に執行部に入ってもらっています。多分、須和理田さんは、自己紹介が短かったことを言っていると思いますが、先生や僕らの基準はそことは少し違います。須和理田さんは、正直自己紹介が始まる前から執行部に来てもらいたいと思っていました。これは先生が言ったことだし、僕らも同じでした」
「はあ……」
「取りあえず座ってください、という指示で、初めからずっと姿勢よく、きちんと正座をしていたのは、須和理田さんだけでした。決して正座をしている人に重点的に執行部をやってもらいたいというわけではないですが、学校見学に来る人って、須和理田さんも覚えがあるかもしれないですけど、在校生に質問したりする前に、まず遠くから在校生を見ますよね。その時、きちんと姿勢よく立っていることってとても大事なんです。少なくとも、この学校の先生や僕らはそう思っています。だから姿勢とか、所作とか、あと、言葉遣い。須和理田さん、間違えた時にすぐに『失礼しました』って、言ったの覚えていますか? あのガチガチに緊張している場面で、無意識にそう言えるのも、やはり大事なんですよ。須和理田さんにはこれから、もう少しリラックスして堂々と話せるようにしてもらいたいっていうのはありますけど、他の新しい執行部の人や僕らは、須和理田さんの姿勢とか、所作とか、そういうところを学べたらいいと思っています。これで、納得してもらえましたか?」
「はい」とサクラは大きく頷いた。
きちんと正座をする習慣は、須和理田家のしつけの賜物だった。
そして、丁寧な言葉遣いもまた、笑いを優先する前に一呼吸置いて話の内容を考えるような、ノリよりも周囲を慮る須和理田家の習慣だった。
「これから、よろしくお願いします」とサクラが言うと、生徒会長の先輩は「こちらこそ」と笑った。
ちょうどそこへ他の生徒会役員や、執行部に決まった生徒が入って来た。
部活の友達には、生徒会長の先輩からの説明をごく簡潔に、「正座していたことと、『失礼しました』って言ったことだったみたい」と話した。友達はそれで納得したようで、特に仲間内でサクラだけが執行部に入れたことにわだかまりは残さなかった。
この日、家に帰るとサクラの母は夕飯の支度をしているところだった。「ただいま」と玄関から台所に入って来たサクラに母は顔を上げ、「おかえり」と言うと手元に視線を戻し、根菜類や葉物野菜が何種類か入っている小さめの鍋に、味噌を溶く。
「お母さん、ありがとう」
ふいにそう言ったサクラの言葉の真意をわかっていない様子の母は、手を止め、不思議そうにサクラを見つめた。








