[25]正座のご縁
 タイトル:正座のご縁
タイトル:正座のご縁
発売日:2017/09/01
シリーズ名:須和理田家シリーズ
シリーズ番号:2
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:44
定価:200円+税
著者:虹海 美野
イラスト:時雨エイプリル
内容
平成に年号が変わる少し前、高校二年生の左方リツは彼氏のいない地味な茶道部員だった。
茶道部に入部当時、正座で足がしびれていたリツが茶道部を選んだのは、小学生の頃通りかかった一軒の桜に和室のある日本家屋に憧れてのことだった。
リツはクラスが優勝を目指す体育祭で失点してしまい、クラスメイトの須和理田がその分を取り戻すべくリレーで活躍する。
その後の会話で須和理田は文化祭でリツの茶道部へ行くと約束するが……。
販売サイト
販売は終了しました。

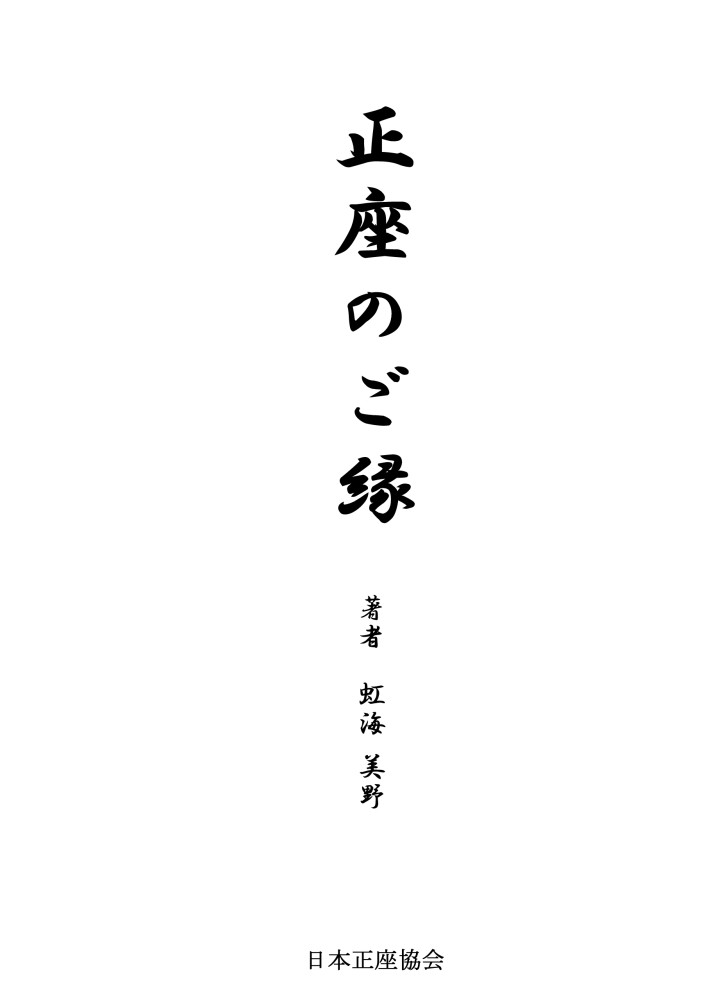
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
これは平成に年号が変わるほんの少し前に高校時代を過ごした左方リツの恋と正座にまつわる物語である。
リツは高校二年生だ。共学に通うものの、未だに彼氏と呼べる存在はなく、それ以前に友達と呼べる男子すら一人も浮かばなかった。当時の都立高校の制服は紺地や茶色、グレーの無地に赤のネクタイなどが主流だった。リツの高校も例外ではなく、グレーのジャケットにスカートという当時からしてみればオーソドックスな制服だった。女子のスカート丈が極端に短くなるのは、まだ少し先で、ソックスは足首からひざ下の白が原則だった。髪は自宅で茶色く染める高校生はまだ少なく、多くが黒髪のロングだった。JKという言葉が存在しない、まだまだ女子大生がもてはやされていた時代だった。そして、恋愛至上主義の時代だった。
義務教育が終了したものの、世間では子どもとみなされていた多くの高校生は、そんな世間一般の目に見えない包囲網を突破するように何かに向けて疾走し、また世間にまだ守られている高校という生活空間の中で、その恩恵を享受すべく、学校生活を満喫し、恋に迷走していた。
若葉が大きく成長し、その色を濃くし始めた五月、リツは一階の校舎一番奥に位置する茶道室でお茶を点てる。昨年は茶道初心者の新入部員で、お茶を点てる人の向かい、三人目の位置である三客の席に正座し、その作法を学んだ。
昨年茶道部に入部したのは、リツを含め五名だった。そのうちの二名は他の部活(主に運動部など活動日が多い部活)を辞め、当時二年生だった現三年の部長と仲が良かったので、その縁で入部した先輩だった。リツの他の一年生部員は花井さんと和菓ちゃんで、二人とも浴衣は自分で着られるし、お花も活けられるという大和撫子な女子だ。お茶についての知識ももちろんあって、花井さんと和菓ちゃんの入部には当時の部長をはじめとする部の先輩も、顧問の先生も目を輝かせた。
一方のリツはといえば、和室での新入部員歓迎会を兼ねたお茶会で、すでに足を一人しびれさせていた。新入部員のためにと先輩方がお小遣いを出し合って、近所の和菓子屋さんで買ってきてくださったお茶菓子のいただき方もさっぱりわからず、そもそもその前に正座の限界が来て、うまく立ち上がれなかった。「どうして茶道部に入ったの?」と、おっとりしたお嬢さん風情の和菓ちゃんは、足のしびれに全神経を集中させて戦慄しているリツにさらっと笑顔で尋ねた。きっと、その場にいた女子全員が抱いた疑問だった。
「お茶を、学びたかったんです」とだけ、リツは答えた。
他に、どう説明していいのかわからなかった。
リツは、すっかり慣れた正座でお茶を点てながら、もうずいぶん昔のことを思い出す。
まだ小学三年生の頃、リツはスイミングスクールで知り合った隣街に住んでいる子と仲良くなった。その子と遊ぶ約束をし、リツの住む新興住宅地の広がる地域から、初めて隣町へと入った。隣町はリツの暮らす新興住宅地よりも駅から離れ、大通りまで出ないとスーパーもコンビニもない地域だったので、この地域の住人に用がなければ来る用事もなかった。友達に貸すと約束した漫画とお菓子を黒のナップザックに入れ、友達に教えられた通り住宅街を進む。大きな松や立派な門構えの家ばかりが並び、とても静謐な雰囲気が漂っているのが、子ども心にも感じられた。
静かな春の午後のことで、昨夜の雨で湿ったあちこちの庭土の匂いが立ちのぼり、アスファルトの幅の狭い道には柔らかな花の香りが満ちている。心地よさに上を向き、足取り軽く歩を進めたリツの視界に、はらはらと白い花弁が舞った。三月のクラス替えの前のお別れ会の紙吹雪、一月の空から降ってきた初雪を思い出した。アニメでもCGでもない。映画で見る、行ったことのない国の映像でもなかった。今、リツの踏みしめているこの日本という国の、徒歩で来られる隣町の春の午後は、確かにリツの心を留めた。手の平を広げ、桜の舞いおりてくるのをリツは待つ。
「お花、少し分けましょうか」
静かで、柔らかい声がした。
花弁の舞う桜の木のある家の駐車場から、おじいさんがこちらを見て、穏やかに笑っている。駐車場に車はなく、そこに自転車が置かれ、おじいさんは外したタイヤのチューブを水を張ったバケツに入れている手を止めている。自転車の修理をしながら、自宅の前で立ち止まっているリツを見ていたらしい。
「いえ、そんな、見るだけで十分です」
リツが慌てて断ると「そうですか」と、おじいさんはそれに応じた。
立ち去ろうとしたリツは、「これ」と高くリツより更に幼い声に呼び止められた。小さい女の子が、そっと小さな枝についた桜を差し出した。
花は精巧でいながら、確かな命の力があった。受け取った手の中に小さな完成された世界があった。
目の前の女の子は、それを知っている気がした。
知っているから、リツに教えてくれている気がした。
「スグル」
家の中から呼び声がすると、女の子は自転車を修理しているおじいさんの脇を通り抜け、庭へと入って行った。
通り沿いに広い庭がある家で、庭に面した和室には縁側がついていた。縁側には座布団が並べて干してある。縁側の前の物干し台横には砂場があり、プラスチックのシャベルやバケツ、水鉄砲が転がっている。
女の子は縁側の前で靴を脱ぐと、開け放たれている座敷へと入って行き、その姿は見えなくなった。
「ありがとう」という遅すぎるリツのお礼は、おじいさんが引き受けてくれる気がした。
女の子が入って行った床の間のある広い畳の部屋には、濃い影がたちこめている。
この時リツは漠然と、靴の中で熱くなっていた、ソックスを履いた足で、あの畳を踏みしめることを想像した。
瀟洒なダイニングセットのある洋室が素敵だという既存の憧れが、この時かき消えた。
家というのは、人々が暮す中で確かに息づいていくのだと知った。
あの和室に溶け込めるような所作には、何が必要だろう……。
あの時の思いが、高校入学後の部活紹介の際、茶道部を見て甦った。
月に一度は茶道の先生がやって来て、指導してくださる。
和服を普段着として着こなす五十代くらいの女性だ。
お茶の先生というと、ピリピリした人を想像し、一年生の五月にはずいぶん緊張したが、もともとこの高校の卒業生だったという先生はとても温和で、茶道初心者で正座もいまいち慣れていないリツにも優しかった。
スカートは広げて正座せずに、お尻から膝の裏側まで敷くようにして正座する方がよいことや、足の甲やかかとに体重をあまりかけない方が足がしびれないことを、にこやかに教えてくれた。当時はスカートが皆長かったので、正座をする時に膝を完全につける必要がなかったのはよかったとリツは後々思うことになる。
今年はお花を習っていた一年生と、その友達二人が入部してくれた。この一年生三人は漫画研究部との兼部らしいが、漫画研究部は放課後のおしゃべりも兼ねてほぼ毎日集まっているそうなので、文化祭の前の配布用部誌制作時期以外は問題なく来られるということらしかった。とりあえず、茶道部の存続危機にならずよかったとリツは思っている。茶道部の活動中に、何かの漫画ネタで異様に盛り上がって悶絶していることがあるけれど、まあいいことにする。
2
五月に入り、高校ではすぐに体育祭が行われる。
普段日に当たる機会のないリツが夏のプールの授業の前に日焼けする唯一の機会だ。それは、別にいい。リツが日焼け止めを塗れば済むささやかな事柄だ。それよりも気がかりなのが、二年のクラスで一緒になった仲間は、三年の卒業まで一緒だということだ。三年の四月にまたクラス替えで新しい顔ぶれの一年が始まるのであれば、多少気まずくなってもあと何ヶ月かで別のクラスになる、という気楽さはある。が、卒業までの二年間というとそれなりに居心地のよいポジションを確保するために、多少はクラス貢献も必要になる。そして、二年生最初のこの行事で一位をとることに、毎年二年生は全力を傾ける。男子の棒倒しはすさまじく、女子の棒引きもかなりの必死さだ。騎馬戦もある。「左方さん、しっかり!」の声というか、怒声に必死に「はい」と言いながら、走る、引っ張る、攻める。それがリツの昨年の体育祭で、今年はそれに更に殺気がこもることは必至。かなり気が重かった。
周囲ではクラスから選ばれた応援団が朝と放課後、練習や衣装作りに大忙しの様子だったり、体育祭実行委員の呼び出しが昼休みにもあったりして、その忙しさとともに新たな出会い満載でリア充組も続々と誕生している。
正座をしても全く足がしびれることのなくなったリツは、今日も一年腐女子三人組が新たなネタで悶絶しているのを横目にお茶を点てる。今日は三年生が塾に行く前に少し顔を出してくれた。茶道部は遅くまでかかることがないので、他の部活が活動している時間には下校する。体育祭を前に応援団が振りで使用する流行曲があちこちから聞こえ、体育祭実行委員会の詰めかけている生徒会室隣の教室からは賑やかな声が漏れている。その中をリツは和菓ちゃん、花井さんと歩く。体育祭を前に盛り上がる放課後の気配に気後れしていて、それをお互い口に出さないように、無理矢理話題を探す。こんな時、「正座で足がまだしびれてる」と言って、ふらふら歩いていた一年生の頃が懐かしくなる。足のしびれで頭がいっぱいで、学校内の盛り上がりまで気が回らなかった。「大丈夫?」と笑っていた和菓ちゃんも、花井さんも同じだったかもしれない。
体育祭予行で、クラス全員リレーのアンカーを走る男子が足の親指を負傷した。大きな怪我でなかったのが幸いだが、リレーは参加不可となった。リツたちのクラスに限らず、体育祭前の練習で負傷者が出るのは珍しくないものの、高得点となる全員リレーのアンカー欠場決定は大きかった。ざわついた教室で、誰かが「須和理田は?」と言った。
後ろの席で机に突っ伏して寝ていた男子にクラス中が注目し、誰かが「楽也、起きろ」と声をかける。
前の席の男子が須和理田楽也というやたらと名字の長い男子を教科書の角でチョップし、直後に須和理田は前の席の男子の両頬をジャンケンブルドックの時の要領で掴んだ。
「リレー、二回走って」と周囲に言われると、須和理田は「わかった」とだけ言い、前の男子の頬から手を離し、再び突っ伏した。
これが、リツが須和理田楽也というクラスの男子を個人的に覚えた最初だった。
リツが須和理田と話をしたのは、その週の金曜日、体育祭の前日だった。
体育祭前日で部活が休みになることを忘れていたリツは、持って来た自分の茶碗を抱えて帰るところだった。この茶碗は茶道部に入部して一ヶ月後に自分のために陶器市で選んで買ったものだ。先輩たちの茶碗を見せてもらい、どんなものがよいか色々考えていたが、陶器市で見つけた青に桜が描かれた抹茶茶碗を見つけて、即決した。これしかないと思った。陶器市で買ったものなので、もう同じ茶碗は買えないと思う。
そんな大切なものを持っていても足元に気をつけないリツである。
誰かの落としたプリントで滑り、思い切りこけた。
机と机の間の狭い通路で両手が前に上がったうつ伏せ状態で顔を上げると、片手で茶碗の入った箱を誰かが持っていてくれた。
須和理田だった。
「左方さん、大丈夫?」
「はい、大丈夫です」
伸びたままリツは返事をし、立ち上がった。
箱に入っていて、布で包んである茶碗は大きな弁当箱に見えないでもなかった。
「あ、それ、弁当じゃなくて、茶碗が入ってるの。割れなくて、本当に助かりました。ありがとう」
いまいちわかっていなさそうな須和理田を見て「茶道部」とリツが短く説明した。
「和菓子食べる部活?」
多分、他に思いつかなかったのだろう。
「うん、まあ、そう。和菓子、好き?」
「うん、好き」
なんだろう。この給食のメニューが好き的な素朴で無邪気な言い方と、リア充な二人のような返答は。
カオスが、リツの頭を駆け抜け、すぐに霧散した。
反射神経のいい須和理田のおかげでリツの茶碗は無事だった。
とにかく、それを今は喜ぼうと思った。
3
体育祭の朝は小雨が降ったが、天気予報では次第に雨雲は遠ざかる、と言っていたことから、体育祭は決行された。
半袖の体操着の上にジャージを羽織り、クラスカラーの鉢巻きをして、椅子を校庭へと運ぶ。
予行でのリツのクラス順位は二位だった。
団体競技の大縄跳びと女子の棒引きが一位だったことで、他の競技の結果を含めても上位につけていた。
女子の棒引きは女子全員参加で、リツは憂鬱だったが、適材適所を心得ているリーダーの女子が、運動部の精鋭メンバーを走らせて棒を奪い、途中まで運んできたところからは足は遅いものの律儀な文化部メンバーが陣地へ運ぶ作戦を立て、それが功を奏した結果となった。
予行の時の要領を心得ていたリツだったが、残念ながら作戦は二度通じなかった。足の遅いリツが棒を引き受けたところを、狙って来た集団で引っ張り返された。必死に棒にしがみつき、ずるずると引きずられたものの、その抵抗空しく棒は相手の陣地へと運ばれて行った。他の文化部女子も同じ状態で、精鋭メンバーが戻って棒を奪い返したものの、やや遅かった。結果、棒引きは一本差で負けてしまった。
リツは不甲斐なさに顔を上げられなかった。
リーダーの女子は大所帯のバレーボール部の次期部長だけあり、人格もリツより数段上で、「ごめん、私の作戦ミスだったね」とリツに声をかけ、膝を擦りむいたリツを救護室まで連れて行ってくれた。優しく接してくれているが、正面を向いたその横顔からは悔しさが感じ取れ、小さな溜息も漏れたのをリツは見ていた。謝る言葉を繰り返せば、余計に相手の負担になると感じ、黙っているしかなかった。
もし私があそこでもっと速く走れていたら、もっと頑張れていたら。
消毒後にガーゼを貼った膝を見つめ、リツは晴れの日の雪のように心が消えていく気がした。
お茶を点てられても、正座で足がしびれなくなっても、こういう時に役に立たなかったら、意味がない……。
私、どんな時代に生まれたら、褒められる存在になっていたんだろう……。
好きでもない歴史を遡り、遡って、戦国を除外し、江戸、平安へと遡り、そこで自身の身分が姫や貴族でないことを察し、あの頃の女性ってどうやって生計を立ててたんだろう。私にできる仕事ってある? と、逃避の果てにまた落ち込んだ時だった。
「足、大丈夫?」
最初、自分にかけられた声だとリツは気付かなかった。
平安の女性の生活力について考え込んだまま顔を上げ、そこで須和理田がリツを気遣っていることに気付いた。
「あ、う、うん。すみません、本当に」
「すみませんって、何が?」
「さっき、一本差で負けたから」
「あれは仕方ないよ。男子の棒倒しはもともと全然勝ててなかったし」
須和理田なりに気を遣って、予選から惨敗だった男子の棒倒しを出したらしかった。確かにクラスの男子には闘争心がなく、リツたちのクラスの男子が守る棒は開始直後には相手によって引き倒されていた。茶道部のリツですら、あれはちょっと、と思ったが、大きな失点の原因が自分にある以上、「本当だよね」とは絶対に言えない。
会話が続かずに困っていると、「でも」と須和理田が言った。
「リレーは、速いから、勝てる」
須和理田は応援合戦の始まったグラウンドを見た。
リア充組にとっての最大の見せ場も、地味なリツやホームルーム中に教室の後ろの席で寝ている須和理田には、正直無関心な種目だった。
須和理田の視線は応援団の趣向を凝らしたダンスではなく、リレーで走るコースに向けられていることにリツは気付いた。
「真面目に走って、勝つから。左方さん、怪我したけど、全員リレーは走れる?」
「うん、あ、でももともと遅いのに、更に遅くなったら……。だけど、走る。リレーだけは絶対頑張って走る」
「俺もできるだけ速く走るよ」
須和理田は、そこまで言うとリツの隣を離れた。
ぼんやりとそんな須和理田の背の高い後ろ姿を見ていると「先輩、今の彼氏さんですか」と、部活の後輩三人組が走り寄って来た。
「いえ、今のは向こうが私に施してくれた慈善事業です」とリツは答えた。
須和理田は、言葉通り「真面目に」走った。二番走者で一気に半周分の差をつけ、一位を守った。そのおかげで五番走者のリツにバトンが渡った時も独走体勢で、リツがかなり遅かったものの、何とか順位を守り通せた。しかし、その後二番手のクラスのバトンが陸上部の男子に渡って同着、次の走者で順位が入れ替わった。
嗚呼、とリツはまた俯く。
正直、リツ個人は体育祭での順位に興味はなかった。なんとか推薦がもらえるくらいの成績を維持して無難に学校生活を過ごし、三年生の秋に希望大学への進路が決定している、というのが目標である。
けれど、今回の体育祭に賭けているクラスメイトを自分のせいで落胆させたくなかった。責任逃れ、という負のベクトル感情とは少し違っていて、特別な間柄でなくても同じ教室で過ごす人の喜ぶ顔が見たい、という気持ちがリツなりにあった。それは本当にリツにとっての優先順位では下位に属する願いだった。けれど、どうにかならないか、と走り終わった今になってリツは切実に思った。リア充経験ゼロのリツには、こういう時大声でクラスメイトを応援するという選択肢がなかった。ただ、黙って行方を見守るのみである。
逆転したクラスは、そのまま一位独走状態に持ち込んだ。リツのクラスはバトン渡しに手間取り、三位に転落した。
二位に浮上した隣のクラスからは大きな声援が発せられる。
六番手、七番手のクラスでも巻き返しが起こり、走り終わった応援団はコーナーの中から大きな旗を振り、声の限りに自分のクラスを応援する。
前の走者が走り出すと、アンカーのたすきをつけた須和理田は、軽く飛び跳ね、空を仰いで深呼吸してから、他のアンカーの生徒とともにコースに立った。
助走を開始した須和理田はバトンパスのラインギリギリまで走り、バトンを受け取ると、一気に加速した。
速かった。
リツに言えるのはそれだけだった。
いつの間にかリツは立ち上がり、叫んでいた。
周囲の声にかき消されて、何を叫んだか、リツは自分でもわかっていなかった。
須和理田は半周で一人を抜き、ゴール直前で最後の一人を抜き、一位でゴールした。
大歓声が起こった。
すごい、すごい、すごい……。
全然期待していなかった高校生活で、こんなに嬉しかったことはなかった。
皆に囲まれた須和理田は、クラスの男子に胴上げされている。
まだ選抜リレーが残っているのに、優勝したくらいの喜び方だった。
さっきリツを救護室まで連れて行ってくれた女子も胴上げのすぐ傍で喜んでいる。
よかった、本当によかった……。
胴上げに力尽きた男子たちから転げ出された須和理田は、「左方さん、勝てた」とリツの方に来た。
湿った泥がついたシャツの背や髪を振って、汚れを落としている。
「すごいね、こんなにすごい体育祭、私は初めてだった。特技があるって、走るのが速いって、いいね。私は全然何もなくて、でも、それでも楽しいと思った」
「左方さんも、茶道部で頑張ってるんでしょ」
……覚えていたか。
「うん、文化祭で一般の人を呼んでお茶会するくらいしか発表ないけど」
「すごいね。俺、文化祭は劇の裏方しかやったことない」
「もしよかったら来てください。お茶菓子でます」
しまった、と思った。去年あちこちで先輩に言われてやった呼び込みをそのまま言ってしまった。
「俺が行っていいなら」
社交辞令という言葉を須和理田は知っていたらしい。
毎年来てくれるのは、茶道部だった卒業生や国語の先生、部員の友達と相場は決まっている。来るわけがない。わかっていたけれど、それで、よかった。
4
クラス全員リレーで逆転優勝した後、全力疾走した須和理田のやる気と体力が一気にダウンしたこともあり、選抜リレーは六位に終わり、二年始めの行事での優勝は逃すことになった。
そのまま中間テスト、期末テストが押し寄せ、夏休みに入った。
文化祭の準備で七月下旬と八月上旬、下旬に学校へ行く日があり、部活の大会も合宿もないリツは律儀に参加していたが、須和理田と会うことはなかった。もともとクラスの男子は三分の一くらいしか来ないのが暗黙の了解となっていて、須和理田はクラスの三分の二の男子に属していたようだった。
須和理田が来ないと落胆していたことをリツは自覚していた。
会ったら、何か話せそうな気がした。
気だけはしていた。
新学期に入り、昇降口で須和理田と顔を会わせたものの、お互いに何も言わずにタイミングをずらして教室へ向かった時、リツは脳内で「現実」という巨大な文字にノックアウトされている自分を描いた。ドラマで見ている「おはよう」と言う主人公の女の子の上目遣いと、ちょっと恥ずかしそうに視線を逸らしながら「おう」と応じる男の子の図は所詮、ハッピーエンドがお約束されている展開のごく一部だ。
物理の授業でリツが答えられず困っている時も須和理田は寝ていたし、文化祭の準備で大きな荷物を運んでいても、他の男子と喋っている。
取るに足らないささやかなピンチに、水面下で想い合っている男子が助けてくれるというのが、お約束ではないのか……。
いや、想い合っているわけじゃないか。
かーっ、これだから男子に縁のない女(自分だよ)は困るよ。
私は分相応に大人しく生きていければ、それでいいんだ。
自分自身をリツが説得している間にも、物理の授業は進み、気付くとまたわからない公式が増えていた。
リツのクラスの出し物に決まった迷路は、教室の机を大かた外に出し、段ボールの壁を作ったものだったが、意外にも盛況だった。受付の係の当番のほかはやることもなく、朝のホームルーム後、文化祭が始まってから、リツは須和理田を見ていなかった。
受付の担当時間が終了し、リツは茶道室に行った。
茶道部のお茶会は一日二回、午前と午後に行われる。三年生は五月の体育祭前にほぼ部活を引退するリツの高校の茶道部では、文化祭にお茶を点てるのは二年生と決まっていた。リツと花井さん、和菓ちゃんの三人はアミダでお茶を点てる順番を決め、初日の午前を花井さん、午後をリツ、二日目の午前を和菓ちゃん、午後を花井さんとなった。
午前中は卒業生や、花井さんの両親が来てくれた。午後は後輩の中学時代の友達が来てくれるはずだ。まあ、せいぜい三人か、四人。
リツは茶道室でお湯の準備をする。花井さんと和菓ちゃんもクラスの当番を終えて来てくれた。
お花は午前から飾ってあり、座布団を整え、一応多めに用意しておいたお茶菓子の数を確認する。
時間になったので、「どうぞ」と引き戸を開けた。
来てくれた後輩の友達に会釈し、後輩の一人のお母さんだという女性に挨拶する。友達や後輩の家族に会うと、いつも最初に「似ている」と思う。今回もやはりそう思っていたリツは、そこで沈黙した。須和理田が立っていた。学校で迷子になった? というボケにもならないボケが浮かんだままで、後輩が「どうぞ、どうぞ」と須和理田を促す。後輩の友達?? いや、違うでしょう。
体育祭でした約束を、リツは忘れていなかった。
心の底から「あれ、どうしたの?」と言いたかったけれど、約束を忘れていないから、本当は来てくれることを期待していた。期待して、来てくれない時の悲しさを覚悟できず、期待しないようにして、それでも、期待していた。
そして、須和理田は来てくれた。
「先輩、泣いてます?」
後輩に聞かれ、「花粉症」と嘘をついた。
お客様が揃い、リツはお茶を点てる。
その間にお菓子が勧められる。
須和理田は女の子二人と後輩のお母さんとの間に座り、居心地が悪そうだった。お菓子の取り方も、緊張した面持ちで、前の二人に倣っている。
ああ、どうして私は須和理田をこんなところへ呼んでしまったんだろう。
お茶を差し出しながら、リツは猛烈に後悔していた。
部員を含め、女子は皆、須和理田の一挙一動を微動だにせずに見守っている。
須和理田が周囲に倣ってお茶をいただいたところで、周囲の女子は大きく安堵していた。
お茶会が終了し、立ち上がる際に後輩の友達が足をしびれさせ、お互いに支え合った。
直後にリツは須和理田が足のしびれで転倒することを想定し、「須和理田くん、ゆっくりでいいから」と言いかけた。だが、須和理田の姿勢は真っ直ぐに保たれ、膝は少し開いた状態で揃っていた。そうだ、ここへ来て座ってから、須和理田は緊張していたものの、ずっとこのきれいな姿勢で正座をしていた。
須和理田は少しもよろけることなく立ち上がり、リツに「じゃあ」と小さく言って茶道室を出た。
5
一日目の文化祭が終了した後、リツは校門を出るところで須和理田に追いついた。
「あの、今日はありがとう」
一気に後ろから声をかけたリツに、須和理田は「ああ」と小さく頷き、「お茶とお菓子、ごちそうさまでした」と言った。
「いえ」と言った後、何を言うべきかリツは考えあぐね、「正座、ずいぶん上手なんだね」と言ってみた。
須和理田はまた「ああ」と頷いてから、「うち、ソファセットがなくて、和室だけだから」と答えた。
「あ、そうなんだ」
「今どき、珍しいよね」と言う須和理田に「ううん、すごくいいと思う」とリツは力を込めた。
「私が茶道部入ったの、小学生の時に、和室のあるすごく素敵な家を見たからだったくらいだから」
「ああ、そうなんだ」
「知ってるかな。ここから大通りをバスで行ったところに、公民館と塾とコンビニが建ってる交差点があって、そこ入ってすぐの住宅街がうちなんだけど、その更に奥に入っていった結構古い家が並んでいるところ」
「ふうん、うちそっちだけど、どの家だろう」
そんなことを話しながら一緒にバスに乗り、同じ交差点のところで降りて暫く一緒に歩いたのが、リツにとって初めての男子との下校になった。
リツが子どもの時に憧れた桜の咲く日本家屋が須和理田の自宅であることは、それから十年近くが経ち、順調に交際した須和理田に連れられ、リツが須和理田家を訪れた時に判明することとなる。








