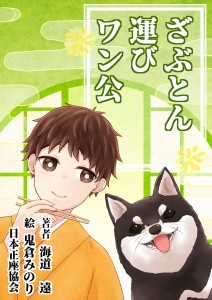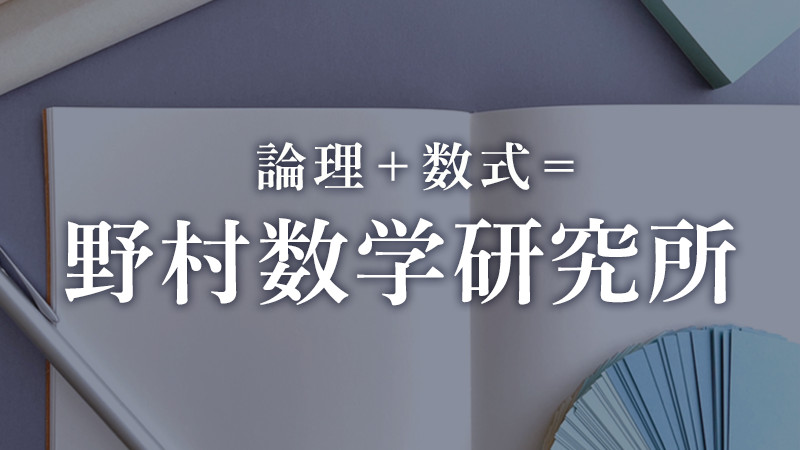[385]お江戸正座34
タイトル:お江戸正座34
掲載日:2025/10/21
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:34
著者:虹海 美野
あらすじ:
竹吉は料亭の息子で温室育ち。
お母ちゃんが大好きな九つになる一人息子である。
そんな竹吉の目下の悩みは、お母ちゃんといつも一緒にいることを手習いの子どもにからかわれること。
じっと堪えていた竹吉だが、今年から従妹のおていが同じ手習いに通うという。
そうして、お母ちゃんはもう竹吉の手習いの送り迎えには来てくれぬ。
おていを守る立場になった竹吉だが、おていと二人でいるところを竹吉をからかう子どもらに囲まれ……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
竹吉は料亭の息子である。板場はお父ちゃんと叔父ちゃんとが仕切っているが、人を多く雇っていて、客間はどれも広く、襖は豪華絢爛で、ふかふかの座布団を用意している。大きなお店(たな)の旦那衆の会合や、大旦那の食事で利用され、仕出し弁当の注文も常に入る。
つまりは、竹吉は坊っちゃん育ちである。
だが、ただ遊びほうけているのではなく、手習いと併行し、店のことも学んでいた。算盤や書だけではない。最初に学んだのは、下足番と掃除であった。これが竹吉の生まれた店の教えで、いくら大きな店の息子でも、学ぶのは奉公人と同じ手順でというものであった。仕事を教えてくれる年上の丁稚を~さん、と呼び、指示に従い、次第に覚えていく。もちろん、丁稚や手代は遠慮があるだろう。いずれはこの店を取り仕切る跡取り息子だ。怒鳴りつけたり、延々説教することはない。だが竹吉はそんな店の人間の足元を見る子どもではなかった。幼い頃に丁稚が叱られているのを見たことがあるし、場合によっては手代が番頭から注意を受けるのも知っている。それが必要なことでお店が廻っているのもわかる。そうすると、言われる前に気を付ける、進んで動くことが身に着く。
店で幼い頃より働けば、お客とは自然と顔見知りになる。
この地域の札差の旦那衆や、大店の若旦那なんかは、顔馴染である。
中でも常連の大旦那は、竹吉の祖父の代からのお客である。竹吉の祖父にとっては、大事なお客であり、また時にはお商売やそのほかの相談相手でもあるという。昔は夜にお酒も嗜まれたらしいが、今は昼間に飯を軽めにした膳を頼む。昼間に来るから、竹吉と顔を合わせることも多い。竹吉は祖父も好きだが、この大旦那が好きである。あれこれ子どもの立ち位置で話しかけない。子どもによっては、苦手に思うかも知れぬが、竹吉には、それがよかった。
ほかの客や近所の人からは、あの家は、お商売について子を甘やかさず、きちんと仕込んでいる。それを受け入れる竹吉も従順で聡い子だと、もっぱらの噂である。
お客の前では、商いを学ぶ、幼いながらに感心な子だと言われる竹吉だが、竹吉の内面はもちろんそれだけではない。
竹吉は大のお母ちゃん子である。
竹吉、竹吉、と家族みんなが竹吉をかわいがってくれるが、その中でもお母ちゃんは別格である。
竹吉は時が許す限り、お母ちゃんの膝の上にいるし、お母ちゃんが何かしている時はその隣にいつもいる。ちょっとお母ちゃんが腰を浮かせば、「どこに行くの」と、ついて行く。もう大きくなったが、昼間の厠もできる限りお母ちゃんに付き添ってもらいたい。寝る時ももちろん、お母ちゃんと一緒である。
だから、竹吉はお母ちゃんと離れている時は、心の奥でじっと我慢をしている。お母ちゃんと離れると、身をひそめるように大人しい。
まだ手習いに行く以前のある日、竹吉のお母ちゃんが茶を点てると言うので、竹吉もそれに同席した。いつも着ているのとは違う着物で足袋を履き、懐紙も用意した。
そうして、背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座する。
そこへ通りかかった大旦那。
お母ちゃんは丁寧にあいさつし、「よろしかったらいかがですか」と尋ねた。
「よろしいのですか?」
「ええ、ぜひ」
松吉は自身の席を譲るのと、大旦那の膳は茶の席の後でと板場に伝えるために黙って立ち上がった。
この時、大旦那は「ずいぶんと聡い子で」と目を細めた。
そうして後日、「竹吉に」と言って、大層美しい茶菓子の詰め合わせを持って来てくださったのだった。
褒めてくれたことや、菓子をくれたことで大旦那のことを好きになったのではない。ただ、子どもに対して、茶のことがわかるのか? と軽視する見方や態度のない人であることが、竹吉を無意識に安心させた。
それをお母ちゃんに言うと、「本当に心の大きい人というのは、ほかの人にやたらと威張ったりしないものです」と教えてくれた。この人がお母ちゃんでよかった、とほかのお母ちゃんがどんな感じかはよくわかっていないが、そう思った。
ただ、この時言ったお母ちゃんの言葉は、しっかりと竹吉の心に届いた。
だったら自分は、心の大きい人になりたい。
威張ったりするのはよくない、と。
この悟り自体は悪くはなかった。
だが、まだ竹吉は幼かった。
そうして、周囲は良識のある大人ばかりであった。
理不尽がない世界で竹吉はお母ちゃんの後を始終追って、安心して暮らしていた。
これが過保護だとか、温室育ちだとか考えなかった。
一応手習いに行く前に、どういう強硬手段かわからぬが、お母ちゃんの実家に預けられた。ほんの二、三日であるが、幼い竹吉にはあまりにひどい仕打ちに思われた。お母ちゃんの実家の祖父母もお母ちゃんの弟も大層優しかったし、お母ちゃんの弟の友達の立太郎さんまで面倒を見てくれて、ずいぶんと気遣ってもらったが、竹吉本人はそれどころではなかった。まあ、結局竹吉以上に辛かったのは実はお母ちゃんの方で、お母ちゃんが耐え切れずに竹吉を迎えに来たのだから、もうどうしようもない。
兎に角、そんなふうに育った竹吉である。
予想通り、手習いではほかの子にからかわれた。
お前、いつも外を歩く時にはお母ちゃんと一緒だな、と揶揄される。(家でも常に一緒であるが)
ほかにも、お付が送り迎えをする家の子もからかわれたが、竹吉の場合はお付が送り迎えをしてもいい家の子でありながら、いつもお母ちゃんと一緒である、ということがからかいの焦点だった。
お茶もお花も書も秀でており、凜と美しい竹吉のお母ちゃんは、材木問屋の娘であった頃から、周囲に一目も二目も置かれる存在であったと聞く。今も衰えのないお母ちゃんは、やはり美しく、目立つ。そのお母ちゃんが「竹吉、竹吉」と、猫かわいがりし、手習いで朝送り届ける時には名残惜しそうな顔をしているし、手習いが終わる頃にはいつも待っていて、竹吉が出て来ると両手を広げて迎える。最初の一年目はまだそれでもよかったが、二年目、三年目となると、竹吉より小さな子でも家が近ければ一人で来る子もいて、あのお兄ちゃんはいつまでお母ちゃんと一緒にいるのだろう、と思われているようであった。
ある日、運悪く、竹吉をからかう子どもら数人に出くわした。
手習いの行き来は先述の通り、お母ちゃんが一緒だから、彼らは表立って竹吉をはやし立てない。だが、竹吉が店で下足番をしており、お客さんを店先まで見送って戻る折に、その子どもらに遭遇した。
今日はお母ちゃんは一緒じゃないのか、とか、いつもお母ちゃんと一緒の竹吉、とからかわれた。
言い返そうとも思ったが、本当のことだから、それは違う、とも言えない。
俯いて堪えた。
そのうちに彼らは飽きたのか、去って行った。
一人取り残された竹吉がふと顔を上げると、駕籠を下りた大旦那がいた。
大旦那はいつもの様子で、「今日もお店の仕事かい?」と言い、竹吉が頷くと、「今日のおすすめは何か教えてくれるか」と続けた。
……見ていたのではないか。
そう思ったが、大旦那が言わぬ以上、竹吉もそのことは口にしない。
竹吉は店へ案内し、大旦那がいつも使う部屋へお通しした。
大旦那は高齢であるが、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座する。
箸遣いも食べ方もきれいである。
帰りに大旦那の下駄をお出しし、手を貸し、駕籠に乗るのを見届けた。
そうして夜、布団に入ってから、大旦那はなぜ、助けてはくれなかったのだろう、と思った。大旦那はここいらでは、顔の知れた重鎮である。一声、注意してくれれば、竹吉へのからかいは止んだであろう。
なんとなく、竹吉の中に不信感が芽生えた。
2
「え、おていちゃんは女の子だけの手習いに行くんじゃなかったの?」
夕餉の時に、竹吉はそう訊き返した。
おていは、この家の離れに住む、叔父ちゃんの娘で六つになる竹吉のいとこである。
おていもこの料亭の娘でお嬢さんで、てっきり女の子だけの手習いに行くものだと竹吉は思っていた。
おていも竹吉同様に一人っ子で、やや人見知りの性格である。
だが、根は大層強い気質で、自分の考えを曲げない。
これが、ちょっと面倒くさい。
どちらのお父ちゃんも昼餉、夕餉は板場で忙しい。お母ちゃんたちも、忙しい時間にはお店の方に出る。
そういう時、おていの面倒を見るのは、竹吉の役目であった。
おていがまだ幼い頃は、それでもお店の人がおていを見ていてくれたのだが、一年くらい前から、だんだんと竹吉が任されるようになった。
昼間は庭でおていのままごとに付き合い、夕餉の後は絵草紙を読んだりする。
おていは竹吉を『竹吉兄ちゃん』と呼び、大層懐いたが、その分遠慮がない。ほかの大人の前だともじもじとしているのに、竹吉には、あれはやだ、これがいい、やっぱりそれにする、おなかが空いた、違うことをしたい、と好き放題である。竹吉は「はいはい」と返事をし、「うん、うん」と辛抱強く話を聞いた。
面倒には感じるが、おていは竹吉にとって妹同然であった。
そのおていが、『竹吉兄ちゃんと同じ手習いに通いたい』と言い出した。
おていの父である叔父ちゃんは「よろしくな」と、すっかり竹吉を頼りにしている。
構わないが、面倒なことにならなければいい、と竹吉は思った。
3
おていが手習いに通う初日は、ほかにも初めて手習いに来る子どもが何人もいた。親が文机を持ち、一緒に手習いに行く。竹吉はおてい一家とお母ちゃんと手習いに行った。以前竹吉をはやし立てた子どもたちは、黙って竹吉たちご一行を抜かして行った。
手習いに着くと、おていは事前に叔父ちゃん叔母ちゃんに言われた通り、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座し、「よろしくお願いします」と先生にあいさつした。
「こちらこそ」と先生は大らかな笑顔で迎える。
「竹吉も、こうやってしっかりあいさつしてくれたなあ」と竹吉にも笑顔を向けた。
そういえばそうだった。
お母ちゃんに礼節について説かれていた竹吉は、初日におていのようにあいさつした。それを褒められた折、竹吉をはやし立てた子らが、つまらなさそうに竹吉を見ていて、少し嫌な予感がしたのを思い出す。
手習いが終わると、おていのお母ちゃんと竹吉のお母ちゃんが待っていた。
「今日はみんなでお祝いよ」と、お父ちゃんたちが祝い膳を用意してくれたことを話す。
わあい、と喜ぶおてい。
「竹吉、お母ちゃんが送り迎えするのは、今日を最後にするわ。明日からは、おていちゃんをしっかり守って一緒に行くのよ」とお母ちゃんが言う。
ふと、寂しい思いがしたが、「うん」と返事した。
おていは、子どもだけで出歩けるとあって、大はしゃぎである。
「おなかが空いたら、竹吉兄ちゃんに言えばいい? どこかで何か買ってもいい?」と、ぴょんぴょんはねながら訊く。
「そうねえ、暫くはおうちに帰って来なさい。慣れたら、考えましょうね」と叔母ちゃんは嬉しそうだ。
帰って来ると、祝い膳が用意され、エビや卵焼きといった、おていの好きなご馳走も膳に並んでいた。
隠居生活を満喫している祖父母におてい一家、竹吉一家の八人でそれぞれの膳を前にする。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座する。
「おてい、これからはしっかりと勉強を頑張るんだよ。何か困ったことがあったら、竹吉お兄ちゃんにお言いなさい」と、祖父が改まって言う。
「はい、頑張ります」と、おていは行儀よく答えた。
4
こうして、竹吉はおていを連れて手習いに行くようになった。
家の前では、竹吉のお母ちゃんとおていのお母ちゃんが並んで手を振っている。
竹吉がつい最近までお母ちゃんと手習いに行っていたのに対し、おていは初めから竹吉と二人で行くが、大層張り切った様子で手を振って手習いに向かった。
おていの足で手習いまで行くからと、少し早く家を出たので、この日の朝は、竹吉をはやし立てる子らには会わずに済んだ。
竹吉は内心、ほっとしていた。
一方のおていは歌ったり、店の前を掃き清めている人にあいさつしたり、道端の花を見たり、竹吉の気も知らずに楽しそうだ。自分もこれくらい楽観的にやっていければなあ、と竹吉は思う。
それでも、竹吉の手をしっかり握るおていの手は小さいし、桃色の着物と簪もかわいらしい。
こうして、無事手習いに到着し、この日からこのおていとの手習いの行き来が竹吉の日常になった。
手習いでは、おていは今日は何を習ったとか、何を勉強したかとか、叔父ちゃん叔母ちゃんに報告するようで、毎日が楽しいらしい。
毎日、手習いの前まで送ってくれるお母ちゃんと離れる時に不安で泣きたくなった自身とは大違いである。
竹吉は、自身とは違うおていを、どこか誇らしげに感じていた。
そうして、自身のたくましさや無邪気さに気づかぬおていに頼りにされていることも嬉しかった。ずっと、おていにとって、頼りになる存在でありたいと思った。
だが、ある日、とうとう手習いの帰りに竹吉をはやし立てる子どもらに遭遇した。
彼らはおていの手前もお構いなしに、これまでのように竹吉をからかった。
「お母ちゃんと離れられない竹吉が我慢してらあ」、「お母ちゃんはもう来ないのか」、と口々に言う。
おていは「なあに、うるさい! 邪魔だよ、どいて」と、物怖じせずに言ったが、まだまだ小さい。
「うるさいのもどくのもお前だよ」と言われれば、うっと涙ぐむ。
おていの涙に、竹吉の心も委縮し、泣きたくなった。
だが、ここで、竹吉はおていの手を強く握った。
「お前らは、自分のお母ちゃんが嫌いなのか! どうなんだよ。お母ちゃんが好きでお前らに迷惑かけたか!」
子どもらが顔を見合わせる。
初めて言い返した竹吉に戸惑っている。
「なんだよ」と、にじり寄る子どもらに、竹吉はおていの前に立ちはだかった。
「おていに近づくな!」
じっと、竹吉が子どもらを見据えた。
「ほら、もうどちらも、もういいんじゃないか」
穏やかな声だった。
駕籠から降りた大旦那が立っている。
竹吉とおていを囲む子どもらに、「言いたいことを伝えるのは悪いことじゃあない。だけど、そろそろもう、言い方を考えなさいな。それくらいはわかる年でしょう」と、諭す。
子どもらは下を向いている。
「竹吉も強くなったなあ。ちゃんと自分で言えるじゃあないか。もう、大丈夫だ」
大旦那は大らかに笑う。
そうして最後に子どもらを見渡し、「無理に仲良くせんでも、うまくやってはいけるでしょう。この爺が見ておるからな。知っているだろうが、爺が直接見てなくても、爺には店の人も、付き合いの長い人もたくさんいるんだ。言っていることは、わかるな?」と言うと、駕籠に戻って行った。
5
今日は、お茶の稽古でおていが茶を点てた。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬようにする。
あの手習いの帰りの一件を、おていも竹吉も誰にも言わなかった。
大旦那もあれから何度も店に来て、竹吉と話すが、そのことに触れぬし、竹吉の家族にも話していないようだった。
相変わらず、竹吉はおていとともに手習いに通っている。
6
今日は、お作法のお教室におていが通うのに、竹吉も久しぶりに稽古してもらうことにした。
普段から一通りのお作法は心得ているが、やはり先生を前に習うと気が引き締まる。料亭の家の子として、学ぶべきことはこれからまだあるだろう。
そうして、お稽古を終え、竹吉はおていを連れて歩いていた。
そこへ、あの竹吉たちをはやし立てた子どもたちが通りかかった。
竹吉は警戒し、向こうも黙ってこちらを見ていた。
おていが「どこ行くの?」と訊く。
僅かの間があった。
だが、無邪気に訊ねるおていに向こうもわだかまりが解けたのか、「……これから、うちの隣で生まれた猫を見せてもらいに行くんだ」と一人が答えた。
「猫?」とおていが目を輝かせる。
後ろで竹吉は黙っていた。
「……一緒に来る?」と別の子が訊いた。
「いいの?」
おていが大きな目で、相手を見上げる。
「構わないけど……」
「やったあ! 竹吉兄ちゃん、行こう」と、おていが飛び跳ねて言う。
今日はお稽古の終わる時間が早いから、帰りに菓子を買ってゆっくり帰って来ていい、と言われていた。それが、猫を見に行くのになるだけである。
「……うん」と竹吉は頷いた。
「こっち」と、子どもらが歩き出し、竹吉はおていと手をつないでそれに続く。
「うちと方向、同じだ」と竹吉が言った。
「そうだよ。知らなかったのか?」
「うん」
お母ちゃんといつも一緒だから、というのは、お互いに言わなかった。
こうして、この日を境に、竹吉はおていとともに、この子らと連れ立って、手習いに行くようになった。
賑やかな様子で手習いに行く竹吉たちを、大旦那は時折見かけるのであった。

![[381]お江戸正座33](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)