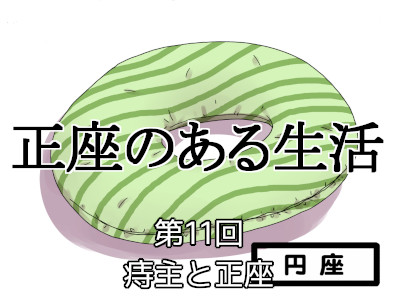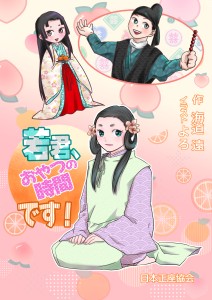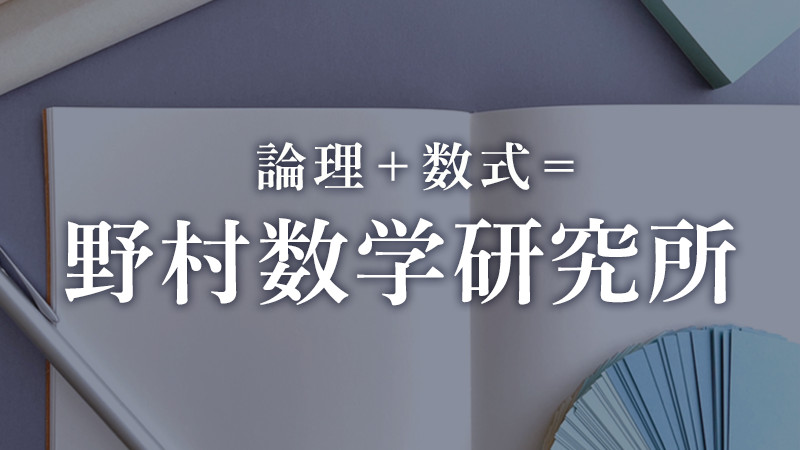[389]お江戸正座35
タイトル:お江戸正座35
掲載日:2025/11/19
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:35
著者:虹海 美野
あらすじ:
お麻は小さな料理屋の娘である。
店は年の離れた兄が継ぐので、いずれはほかの飯屋で働こうと考えていた。
ある日、店で暇を出されたお麻は遠出し、偶然剣術道場で後ろ姿だけを見たお人に心引かれる。
だが、帰ってみると、お麻の縁談話を伝えられる。お相手は高級料亭の跡取り息子の竹吉さんというらしいが、お麻は気が進まない。
竹吉に会ったお麻は、お麻の想い人と一戦交えることを提案し、竹吉はそれを承諾し、道場へ通うが……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
「わざわざ済みません」と、竹吉は店の勝手口の方で、詰めてもらった弁当を女将さんから受け取った。
「いえいえ、こちらのこそ、遠いところお越しいただいて」
「大した距離ではありませんから」
「こちらからお届けするところを……」
「とんでもございません。お忙しいところを申し訳ありません」
「お嬢様、いえ、ご新造さんは息災ですか?」と女将さんに訊かれ、「はい。相変わらずで、どうしても、どうしてもこちらの膳がいただきたいと申すもので、けれど、店をそうそうに離れるわけにもゆきませんし」と竹吉は苦笑する。
「こちらも、随分と不義理をしておりまして。こんなふうに来ていただけると、嬉しゅうございます。くれぐれもご新造さん、ご主人によろしくお伝えください」
「ありがとうございます」
「駕籠をお呼びしましょうか」
「いえ、それには及びません」
「寒いですから、どうかお気をつけて」
こんなやり取りの後、竹吉は裏手から表の通りに出た。
そこへ店の入り口から、「お客さん」とたすき掛けに前掛けをした娘が飛び出して来た。前をゆっくりと歩く職人に「忘れ物です」と、分厚い首巻を渡す。
「おお、こりゃあ、うっかりしていた」
「お渡しできてよかった。今日は寒いですから」
「ああ、ありがとうな」と、悠々と歩くお客に、娘は頭を下げた。
雪が今にも降ってきそうな冷え込みの厳しい日であった。
素足に下駄をひっかけ、たすき掛けをした娘はさぞかし寒いだろうが、しっかりと客を見送っている。
松吉はふと、自身の首巻を娘のその薄い背にかけてやりたいと思った。
だが、娘は白い息を吐き、空を見て伸びをすると、店に入った。店に入る折、顔が見えるかと期待したが、冷たい風に煽られた暖簾で、その面(おもて)は隠れた。
それが松吉には、やや心残りであった。
お麻(あさ)は、料理屋の娘である。店は、一回り以上離れた兄、久太が継いでいる。店はさほど広くないが、座敷にはきれいな畳を入れ、出す膳は、食材は安く仕入れられるがよいものを厳選し、丁寧に出汁を取り、手間を惜しまぬお菜を、客を待たせることなく、手際よくお出しする。
場所と店の構え、値段から、客のほとんどが職人である。
近所で仕事をしている大工が仲間とともにやって来て、仕事場がほかに移っても、わざわざ店まで昼餉、それが無理な距離であれば夕餉に新たな仲間を連れてやって来る。
今日の昼餉にも、「またこの近くで仕事があるんだ」と、大工がやって来た。年はお麻より五つから八つくらい上だろうか。何か月か前に親方と一緒にやって来て、そこの仕事が終わるまで通ってくれた。そうして今度は、「仕事場を親方に任されているんだ」と、得意気に弟分を連れてやって来た。
「おめでとうございます」と大工の出世を喜ぶ。周囲の常連さんや、初めてやって来たお客も、共に、「そいつぁめでてえ。頑張り時だな」などと、鼓舞する。そういう店が、お麻は好きである。
こんな感じで、大柄で強面のお客が多いが、それでもお父ちゃんが店を出して以来、店でのもめごとはないと言う。
それに一役買っているのかどうかわからぬが、お麻の店では、お客も店も忙しくとも、膳をお出しした後、正座し、「どうぞ」と座礼する決まりがあった。背筋を伸ばし、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように。
忙しくとも、飯の時間は必要で、そこへ来た人へ礼を尽くす、というお父ちゃんの考えらしかった。
大声で仲間と話す職人も、丁寧に「どうぞ」と膳を前に座礼を受ける時には、どこか改まった顔する。だが、それをしゃらくせいだとか言って、無下にするお客はこれまでいない。
まあ、それは板場を仕切り、店を切り盛りするお父ちゃんが、それこそ強面な板前だからかも知れない。
お麻のお父ちゃんは、ここから少し離れたところにある高級料亭の板前をした後に、そこの主人のご厚意で、自分の店を持った。その高級料亭はもともと、小さな料理屋で、その頃、お父ちゃんはまだ幼い子どもであったが、毎日店の主人の料理の仕方を見に行き、そのうちに下足番をするようになり、やがて板前になった。そのお父ちゃんの成長とともに、店はどんどん大きくなり、今は押しも押されぬ高級料亭になったのだそうだ。
この店を出させてもらう際、ご主人が密かに心配したのが、お父ちゃんの荒々しい所作であった。料理は確かだが、一人で店を切り盛りすると、膳を運ぶのもお勘定を伝えるのも、自分でやるようになる。それをうまくやれるだろうか……、と心配し、お作法の教室に一時通わせたと聞く。そのおかげで、お父ちゃんは丁寧な所作と、多少の気の長さを習得できた。
お麻のお母ちゃんは、もともとは札差で住み込みの女中をしており、そこでご新造さん付きになり、頃合いを見計らって、お内儀さんとご新造さんとで、お母ちゃんの嫁ぎ先をどうするかと話を進めた際に、お母ちゃんは、お父ちゃんの元がいいと言ったのだそうだ。お母ちゃんもご新造さん付きでご奉公していたから、丁寧な所作が身についており、また、細かなことにも気を配れる。
そんな家で、お麻は育った。
だから、結構幼い頃より、所作についてはお教室にこそ通ってはおらぬが、おおよそのことは心得ていた。
店を手伝うようになり、膳を出す際にも、言われた通り、背筋を伸ばし、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物は尻の下に敷き、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座する。
先にも述べたように、店の中でもめごとが起こったことがないが、まあ、起こらぬように努めるのも、店で働く中では大事なことである。江戸っ子気質で気の短いお客も多いし、気の荒い人も多い。そういう中で、お麻は手際よく、そうしてたくましく、お商売を学んできた。
店は兄が継ぐし、追い追い、誰かと一緒になるだろうから、そうしたら、どこかに働きに出てもよいと考えている。
これだけ忙しい店で、身体の大きな職人のお客ばかりを前にそそこそ互いに楽しくやれているのだから、大概の料理屋で働ける自信がある。それがお麻の誇りでもあった。
そうして今日、たまには遊びに行っていい、と言われ、遠くまで足を伸ばした帰り、道を一本入った通りで道場を見かけた。そこで、大層凛々しいお人をお麻は見つけた。
後ろ姿しか見えなかったが、身体はほっそりとした方なのに、動きが俊敏で、竹刀のぶつかる音が小気味よく響いた。
あんなお方と一緒になれたら……、とお麻はふと、夢見心地になったのだった。
2
そんなお麻の夢を木端微塵にする出来事が起こった。
そもそも、お麻に急に遊びに行っていい、と両親が言ったのも、今となってはおかしな話である。
ただ嬉しく、素直にでかけ、そこで素敵な人を見かけて帰って来たお麻に、お父ちゃん、お母ちゃんが、寝起きに使う二階の座敷に来るようにと言う。
土産に買った饅頭もそこそこに、お麻は二階に行った。
いつもきびきびと働くお父ちゃんとお母ちゃんだが、今はとても静粛(せいしゅく)な佇まいである。
背筋を伸ばし、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物は尻の下に敷き、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座している。
お麻もその向かいに正座した。
「実はね、今日、お客様がいらしたの」と、お母ちゃんが切り出す。
「うん」とお麻が頷く。
「お父ちゃんが昔板前をやっていた高級料亭の話は知っているね?」
これまた、うん、と頷く。
ちょうど今日、遠出したのがそっちの方だったから、あいさつのひとつでもした方がよかったのか……。
いやいや、いきなり着古した着物の小娘が「ごめんください」と行ける場でもない。
「そこの料亭がどうかしたの?」
ここでお父ちゃんとお母ちゃんは顔を見合わせる。
「そこの料亭の兄弟は、お父ちゃんを兄のように慕ってくれた人たちだ」
「……うん」
お父ちゃんが話し出し、お麻は頷く。
「お父ちゃんがこのお店を始めた後、立派な板前になって、それぞれに所帯も持った」
「うん」
「それでな、そこの長男の息子もそろそろ所帯を持ってもいいのではないか、と」
「……うん」
妙な沈黙が流れた。
「なんでその話を私にするの?」
「あちらさんからな、息子の嫁に、お麻をどうか、という話があってな……」
お麻は思わず、立ち上がった。
「だって、高級料亭の跡取り息子でしょ? いくらでもお相手はいるでしょう?」
「いや、まあ、そう、なんだが……」
お父ちゃんが狼狽えている。
こんなことは初めてだ。
いつも言葉少なに、けれど仕事に手抜かりなく、お客が皆満足して、また通う料理をするお父ちゃんは、迷いのない人に思えた。
それが一体どうしたのか。
「ねえ、それって、お父ちゃんにとって恩義のあるお店からの話だから、断れなかったってこと?」
「お麻!」と、お母ちゃんが嗜める。
「だって……」
「とにかく、落ち着きなさい」とお父ちゃんが言う。
「はい」とお麻は再び正座する。
「これだけははっきり伝えておく。あちら様になんの目論見もないし、うちでも恩義があるからとか、そういうことはない」
「じゃあ何?」
疑いの目でお麻は、前に座る両親を見た。
兄とだいぶ年が離れている娘だから、きびきびとして、それなりに厳しい二人も、何かにつけてお麻には甘かった。だから、お麻は兄の久太よりも、両親に言いたいことを伝える。今回の話も、もし久太であったなら、「わかりました」と、多くを口にせずに了承したのだと思う。
お父ちゃんは暫し言うべきことを頭の中で巡らした様子で瞬きし、話し出した。
「お相手は竹吉さんといって、とても優しく、高級料亭の跡取りだからと威張ったところもないし、頼りにもなる人だ。竹吉さんのご両親のことも当然よく知っている。こんなに安心してお麻を託せるところはないと、お父ちゃんは思う」
……お父ちゃん。
普段口数が少ないけれど、そんなふうにお麻のことを案じてくれていたとは……。
だが、お麻にも言い分はある。
「気持ちは嬉しいけど、私、そんなにやわじゃありません。うちを出て、どこかの料理屋に勤めることだって考えています。ちょっとやそっとのことで、私はくじけませんから」
「お麻、あなたが思っているよりも、世知辛いこともあるのよ」
全く、この子は、と言いたげな顔でお母ちゃんが続ける。
「もちろん、いい人もたくさんいる。お店に来てくださる人もそうだし、お父ちゃん、お母ちゃんがこれまで働いてきた先でも、本当にどうお礼を言っていいかわからないくらい、いい方ばかりだった」
「それは、お母ちゃんがいい人だからでしょう?」
お麻はお母ちゃんをじっと見る。
お父ちゃんはこの近くの生まれだけれど、お母ちゃんは違った。それほど江戸から遠くはないが、農家の生まれで、手習いを終えた後に札差の家に住み込みの女中で仕えた。一人で使えるお布団があって、白いごはんが嬉しかったとお母ちゃんが言っていたことがある。今のお麻より五つも下の当時のお母ちゃんは、そんなふうに嬉しいことを今も覚えていて話すが、仕事は楽ではなかったと思う。そう考えると、お母ちゃん、そしてお父ちゃんなりのお麻への親心も全くわからないではない。
まず食べるのに困らぬ高級料亭に向こうから来てほしいと言ってくれているし、嫁ぎ先はお父ちゃんにとって恩があり、また親同士互いをよく知る人ばかりである。おまけに、少々遠いが歩いて行ける場所である。
それは、わかる。
ありがたい。
だが、大事なことをひとつ、忘れていないか。
……お相手である。
先のお父ちゃんの話では、その竹吉さんとやらはお仕事もきちんとでき、性格も優しい方だと言う。
まあ、親からすれば、もう言うことはないのだろう。
だが、そういうものだろうか。
それこそ、大きな商家の婚姻となれば、本人がどうこう言う前に話が決まっているのがほとんどだ。
だが、お麻は、評判の料理屋の娘ではあっても、あくまでも小さな店の娘である。
現にお父ちゃんとお母ちゃんだって、事前に互いの意志を確かめ合ってから一緒になったではないか。
おまけに、どこの誰ともわからぬが、お麻は今日、ちょっと素敵だと思うお方を見かけたばかりだ。
お麻の結婚の話のために、お麻に暇を出したというのに、なんとも間の悪い結果になった。
3
縁側に面した裏庭でぼんやりしていると、「ほら」と、菜っ葉を混ぜ込んだおにぎりが差し出された。
見ると、兄の久太である。
夕餉をいらぬと言ったのを気遣って、久太が用意してくれたのだろう。ありがたく、それをお麻は受け取る。
家では茶漬けをかきこむ日も多いけど、万が一にも、その高級料亭のご新造さんになったら、こんな生活とも無縁なのだろうか。
「……会うだけ会ってみたらいいじゃないか」
何とも、気楽そうに言う。
自分のことではないからだ。
「断われないでしょう。お父ちゃん、お母ちゃんはいい人だって言うばっかりだけど、どう考えてもうちの方が立場が弱いよ」
久太は溜息をつく。
「お父ちゃんも、お母ちゃんも、根性のある人だ。お母ちゃんは人当たりがいいし、誰にでも優しいけど、大事な娘を相手側に言われるがままに縁談に駆り出しはしない。それはお前もわかっているだろう」
……確かにそうだ。
うちのお父ちゃん、お母ちゃんなら、どんなに大きなお店(たな)からの話であっても、不承知なところへ娘をやらないだろう。
「だけどさあ、お父ちゃん、お母ちゃんから見ていい人が、私にとっていい人かはわからないでしょう」
久太はううん、と唸った後、「まあ、大概の人がいい人だと言うなら、お前の方から断れないのがわかれば、うまく取り計らって、自分の方が気に染まなかったとかなんとか、言ってくれるもんだ。そのくらいは期待してもいいと思う」と言う。
そうして、「それにしてもさ、厳しいところで働くことは厭わないのに、左団扇の高級料亭のご新造さんになるのを嫌がるのも珍しい話だよ」と続け、「だから、そこじゃなくて、お相手のことを、」と言うお麻を置いて戻って行ったのだった。
4
「これは……」
お麻は竜宮城のような立派な店構えの高級料亭の前で立ち尽くした。
前々から、こっちの方の橋の先にお父ちゃんがお世話になった料亭があるとは聞いていた。だが、実際に来てみると、その店の大きさに圧倒される。
とても正面から入る勇気がない。
どこでもやっていける、と自負していたが、いやはや、自負している傍から無理だと思う店を前にしてしまった。
いやいや、待て、落ち着け。
違う。
もともと気の荒いお客が来るお店でも大丈夫だと自負していたのだから、このお店を将来働く店に入れなくともよいし、無理だと思うこともないのだ。
そうだ、しゃんとしろ!
そんなふうに自身を鼓舞していると、「おや、飯屋のお麻ちゃんじゃないか」と声をかけられた。
「ええ、お客さん、なんで?」
つい最近も仕事場が近いからと、弟分を連れて来た大工のお客が立っている。
仕事道具を肩に担いでいるので、ここで飯を、というのではないらしい。
「俺は、ここの竹吉に用があるんだ。昔からの友達だ」
「えええ? そうなんですか?」
「ああ、昔のよしみで、俺が大工になってからは、ちょっとした修理なんかを頼まれるようになってね」
このとんでもなく立派な料亭の跡取り息子と、この大工のお客が昔からの友達というのが、いまいち結びつかぬが、この店の跡取りで竹吉というのが、お麻が見合いをする相手であるのは確かだし、この大工のお客が言う竹吉も同じ人だろう。
「実は、私もちょっと竹吉さんに用がありまして」
大工のお客は不思議そうな顔をしたが、それ以上は訊かず、「じゃあ、一緒に行こう。今は昼餉の時間が終わって、こっちの方にいるだろう」と、慣れた様子で正面の入り口ではなく、塀の勝手口から入って行く。
それにお麻も続いた。
「おおい、竹吉」
そう呼びながら、庭の飛び石を進み、離れの方へ向かう。
まあ、裕福な家というのはこんなにも家や庭に手をかけられるものなのか、とお麻は感心するばかりだ。
「おお」と、呑気な声がする。
ほっそりとした、優しい面(おもて)の、上品なお人である。
離れの縁側に座り、猫を膝に乗せて撫でている。
「こいつは元気か?」
「ああ、魚の身をほぐして、湯がいたものをいつも食べているよ」
「さすが高級料亭の猫は毛艶が違うなあ」と大工のお客が笑う。
そうして、縁側の竹吉の隣に座る。
昔から仲がいいというのが覗える。
「子どもの頃、うちの近所で生まれた子猫を竹吉が大層可愛がってね。その子猫が大きくなって生んだ子猫を、竹吉が一匹引き取ったんだ。料理屋で猫は無理だろうと俺は言ったんだけど、竹吉の従妹の住むこの離れに置いてもらって、ここで猫の世話をして、板場に戻る時は身体を拭いて着替えるという約束で、こうして猫を飼っているんだ」
大工のお客が説明してくれる。
「へえ、そうなんですか」
猫を飼いたければ、親の言いなりになるばっかりじゃあないんだね、とお麻は内心思う。
相談するだけの意志はあるらしい。
「ところで、直してほしい引き戸っていうのは、どこだい?」と、大工のお客が訊く。
「ああ、こっち……」と竹吉が言いかけ、お麻を見る。
「こちらのお連れさんは?」
「ああ、お麻ちゃんだ。よく行く料理屋の娘さんだ。しっかり者で、話も聞き上手だし、機転も利く」
……そんなに褒めてくれるとは。
「それこそ、竹吉のところに来てくれれば、言うことないんじゃないか?」
喜んだのも束の間、とんでもないことを言う。
店のお客でなければ、足を踏んでいるところだった。
竹吉が黙り込んだところを見ると、見合いの話がいっているのだろう。
何かを感じ取ったらしい大工のお客は、「じゃあ、俺は戸を直すとするか」と、先ほど竹吉が言った方へと向かった。
竹吉が付き添わなくていいのは、大方使用人が居るからであろう。
二人と一匹になると、竹吉は「こちらから出向くところを失礼いたしました。竹吉です」と頭を下げた。
「麻と申します」と、お麻も頭を下げる。
「突然お訪ねしまして、申し訳ありません」
「いえ」と、竹吉は首を横に振る。
猫が膝にいるので立てないのであろう。
竹吉は五つから八つくらい年上であろうが、髪も肌もきれいである。もし女の人であったら、さぞかし美しいのではないか。
そう思うと、お麻は自身が大層がさつで場違いに感じられた。
そもそも、こんな大きなお店の跡取りで、しかもきれいな若旦那……。
こっちが断るというのも、おかしな話だ。
「あの、お尋ねしたいことがあって参りました」
「なんでございましょう」と、竹吉は丁寧に返す。
『なんだい』くらいで返してくれれば、こっちもやりやすいものを……。
お麻は爪先に力を入れる。
「あの、竹吉さんはよろしいのですか? ご両親が縁談を決めて、それでよろしいのでしょうか」
竹吉は少し首を傾け、お麻を見る。
猫が竹吉の膝からひらり、と降り、お麻の足元にまとわりついた。
柔らかく、温かい。
心がふっと柔くなる。
「両親が『この人』というのなら、確かだろうと思いました」
竹吉がゆっくりと立ち上がる。
思ったよりも背が高かった。
お麻は竹吉を見上げる。
ここで、『はい、そうですか』と、引き下がるわけにはいかぬ。
「ご両親を信じられるのは、素晴らしいです。ですが、私はご両親が言うのなら、と相手を決める方の元へは行けません」
竹吉が瞬きする。
「竹吉さんが、『この人』と思うところから、始めていただきたいです」
「おっしゃる通りですね」と、竹吉は素直に頷く。
どうにもつかみどころのないお人だ、と思う。
ここで『生意気だ』とか腹を立ててくれれば、こっちもやりやすい。
「それで、実際にいらしてくださったんですね。ありがとうございます」
「ああ、はい」と、お麻は曖昧に頷く。
否、違う。
いいお人だと思う。
物腰が柔らかく、品があって、もし一緒になったら、穏やかな生活が送れるだろう……。
ああ、違う、違う。
お麻は混乱する。
そうして、どれだけ動転していたのか……。
「私、想う人がおります。この先の剣術道場に通われている方です。そのお方と一戦交えてくださる気はございますか?」
そう訊ねると、「ああ、あそこの道場ですか」と、のんびりと頷く。
「わかりました。いつ、行けばよろしいでしょうか」
……しまった。
ハッタリで言ったものの、あの素敵だと思ったお方がどなたかわからぬ。
「ええと」としどろもどろになり、以前お見かけしたおおよその時刻だけを伝えるに留めた。
それでも、「その時間なら、少々なら出られますから、明日から参りましょう」と言う。
「……では、突然失礼しました」と、そそくさとその場を去ったのだった。
5
翌日から、竹吉は本当に道場に来た。
端の方に背筋を伸ばし、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、袴は尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬように正座する。
お麻は道場から少し離れたところで、あの想い人を待ったが、何日経っても現れなかった。
それでも、竹吉は文句も言わず、道場に来ていた。
ある日、店に昼餉の終わりしな、あの大工のお客が来た。
そうしてお勘定を済ませ、外へ出る際、「お麻ちゃん、ちょっといいかい?」と声をかけた。
暖簾を仕舞うのを口実に、大工のお客と外へ出た。
「お麻ちゃん、この前、少し竹吉と話すのが聞こえたんだ。そこは勘弁してくれ。それを踏まえて、話したい。竹吉は知っての通りの金持ちの一人息子で、お商売は厳しく仕込まれていたが、とにかく箱入り息子というか、お母ちゃんにべったりな子で、俺は手習いの頃、友達と一緒にそれをからかった。その時、竹吉は『お母ちゃんが好きで悪いのか』、『お母ちゃんが好きじゃないのか』と真っすぐに俺たちに訊いたんだよ。まだ、覚えている。ちょろいやつだと思ったけど、芯はしっかりしているんだ。親の言いなりとは違う。本人なりの信条がある。そこだけは、わかってやってくれないか」
お麻は俯く。
「なんだか、行きがかり上、私の方で竹吉さんでは不満のような感じになってしまいましたが、実際、竹吉さんが私では不満なんじゃないんでしょうか……。私で竹吉さんに釣り合うとは到底思えません」
「そんなことか」と、大工のお客は笑う。
「竹吉は釣り合うとか、そういう基準で一緒にいる人間を選ばない。竹吉のお父ちゃん、お母ちゃんもそうだ。どっちも裕福な家で育っているが、あまりそういうことに重きを置かない人たちでさ。まあ、それでお商売をしっかりやれているんだから、本当に見習いたいもんだよ。お麻ちゃんとのことは知らないが、それでも竹吉は両親に聞いた話で、お麻ちゃんと一緒になろうと、完全に決めるところまでゆかなくとも、前向きに考えようと思ったんじゃないか」
……それならいいのだが。
「知っての通り、竹吉はいい加減なやつじゃあない。仕事もそうだし、周囲の人も大切にする。この前の猫の様子でもそれはわかったんじゃないか」
確かにそうだ。
子どもの頃からの友達がそう言うのだ。
飼っていた猫も大切にされていたし、あの人懐こさからも、周囲の人が皆優しいのがわかる。
「ありがとうございます」と、お麻は俯いて頭を下げた。
「竹吉との縁談がどうなるのかわからないが、俺はお麻ちゃんを応援する」
そう言って、大工の客は颯爽と仕事場へ向かって行ったのだった。
そうして、お麻の中で、実はもう、竹吉のほかに一緒になる人は考えられない、という思いがあることに、気づいた。
6
「竹吉さん、ごめんなさい。今日まででいいです。十分です」
お麻は、道場の入り口で竹吉に頭を下げて、詫びた。
「私は構いませんよ。お麻さんとの約束を果たせるまで、通います」
「いえ、もう、いいです。いつまで待っても、私がお見掛けした方は現れませんし」
「おお、今日も来たか」
お麻が顔を上げると、この道場の師匠がやって来た。
竹吉とお麻は頭を下げる。
「話は聞きました。それで私の方でもお麻さんがこの道場の前を通った日以降、稽古に来た門下生を一通り確認しましたが、竹吉がここに来た数日の間、全ての門下生が一度は顔を出しているのですよ」
そんな!
それでは、お麻が見たのはどなたなのか?
「お麻さん、物は試しで、ちょっと見ていていただけますかな」
師匠はそう言うと、竹吉を促す。
そうして、道場に入り、座礼し、互いに竹刀を持った。
小気味よい竹刀の音が響く。
「あ」と、お麻は目を見開いた。
やがて、竹刀の音が止んだ。
そうして、竹吉と師匠が戻って来る。
「私の勘は当たりましたかな」
お麻は顔を上げる勇気がなく、消え入るような声で「はい」とだけ言った。
何がなんだかわからぬ竹吉に、師匠は「おめでとう」と言い、道場へ戻った。
7
お麻は、どちらにしても、竹吉がよかった。
初めて会った日から、お麻の無茶な提案も受け入れた。
声を荒げたこともなければ、苛立った様子を見せたこともなかった。
穏やかで優しい、そうして、しなやかで、大層心の強い人であった。
そうして、初めて道場で偶然見かけた素敵なお人もまた、竹吉であったのである。
なんともまあ、間が抜けているというか、何重にもおめでたいというか……。
道場からの帰り、お麻は「竹吉さんがよい方だというのは、十分承知しておりますが、なぜ、こんなことにまで付き合ってくださったのですか」と訊いた。
竹吉は「私も同じことがあった身ですので、できる限りの協力は惜しまないつもりでした」と答えた。
え、とお麻は黙る。
そうして、竹吉を見上げる。
「竹吉さんは、どのようなことがあったのでございますか」
竹吉は穏やかに笑う。
「冬の寒さの厳しい頃、後ろ姿だけですが、とても可憐で、そうして立派に商いをしている娘さんをお見かけしました。お麻さん同様、後ろ姿しか見られなかったのですがね……」
……てっきり、竹吉の方では、誰かを想うことなく、ただ縁談の持ち上がったお麻とそのまま一緒になる心づもりなのだと思っていた。
まさか、想い人がいたとは……。
「あの、そのお方はどうされるおつもりですか」
なんとなく、心のおさまりの悪さを感じつつ、お麻は訊く。
「私も、お麻さんと同じです」
「ですから、そのお方は……」
竹吉がお麻を見て、小さく頷く。
「私、でございますか?」
「はい」と、竹吉は頷く。
「ずいぶん前に、お店の方に母に頼まれて、お弁当を取りに参りました。お商売の忙しい時間でしたから、裏口で受け取って帰ったのですが、その時、店の外までお客の忘れ物を持って追いかけ、そのお客が立ち去った後も寒い中、しっかりと頭を下げた娘さんがいたのです。ああ、こういう人がいい、と思いました。ですが、正面からは見られませんで、先日友達とうちへいらした時、すぐには、あの時の娘さん、つまりお麻さんであるとわからなかったのです」
なんだか、身体中の力が抜けた。
お麻は「そうでしたか」と、大きく息をついた。
「あの、よろしければ、少し早いですが、うちで昼餉を召し上がって行きませんか」と、松吉が言った。
8
なんだか、あまりにいろいろのことが一度にわかって、どこかで休みたいという思うで、つい竹吉の厚意に甘えてしまったが、考えてみれば、松吉の店はあの竜宮城のような大きな店である。
そこへ娘一人でとは、さすがに行きにくい。
そう言って辞退しようとしたが、「大丈夫ですよ。ちょっと昼餉を、というお客さんも多いですから」と松吉は言う。
そのちょっと、という感覚が、もうお麻の周囲とは違うのだが、松吉はわかっているのか、いないのか……。
言われるままに通された個室は、これまた豪勢であった。
お麻の店ならお客がいっぱいになる広さの座敷に、たった一人である。
掛け軸に活け花、豪奢な襖絵。
鴨井も何やら手が込んで洒落ている。
そうして、座布団は、新しい布団のようにふかふかである。
どうにも落ち着かぬが、お麻は背筋を伸ばし、肘は垂直になるようにおろし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、着物は尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬように正座した。
間もなく、松吉自らが膳を運んで来てくれた。
美しい器に盛られたお菜は、旬の食材と高価な食材が織り交ぜられていた。
「どうぞ」と、向かいの畳に竹吉が正座する。
「いただきます」と、お麻は手を合わせた。
汁物をいただき、そのまろやかさと香りの高さ、そうして、大層舌に馴染んだ味に目を上げる。
「お父ちゃんと叔父ちゃんもずいぶんと紆余曲折を経て、毎回出汁から考えますが、その基本は、お麻さんのお父さんからの教えです」
「はい」と、お麻は頷いた。
食材や器は違っても、根本的なところが同じであることがわかる。
「うちのお父ちゃんは、こちらの先代に学ばせていただいたのですね」
「そう聞いております」
穏やかで、幸せに満ちた時間であった。
この時が、この人と、この場でずっと続く、そう思ったのがお麻だけでないことは、もうお麻にもわかっていた。

![[378]お江戸正座32](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)