[39]正座の貴公子
 タイトル:正座の貴公子
タイトル:正座の貴公子
発売日:2018/10/01
シリーズ名:須和理田家シリーズ
シリーズ番号:5
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:48
定価:200円+税
著者:虹海 美野
イラスト:時雨エイプリル
内容
高校に入学したカヤは、友達の付き合いで見学に行った囲碁クラブで座布団を貸してくれ、畳にきれいに正座する男子、緑と出会う。
貴公子のように品のある緑が気になるカヤは、球技大会で対戦相手の上級生に緑が足をかけられたところを見て、皆の前でそれを口にする。
一方で囲碁と園芸が好きな緑との距離を縮められず、なりゆきで見学へ行った囲碁クラブで失言してしまう。
落ち込むカヤだったが、緑はカヤに何か伝えたいらしく……。
販売サイト
販売は終了しました。

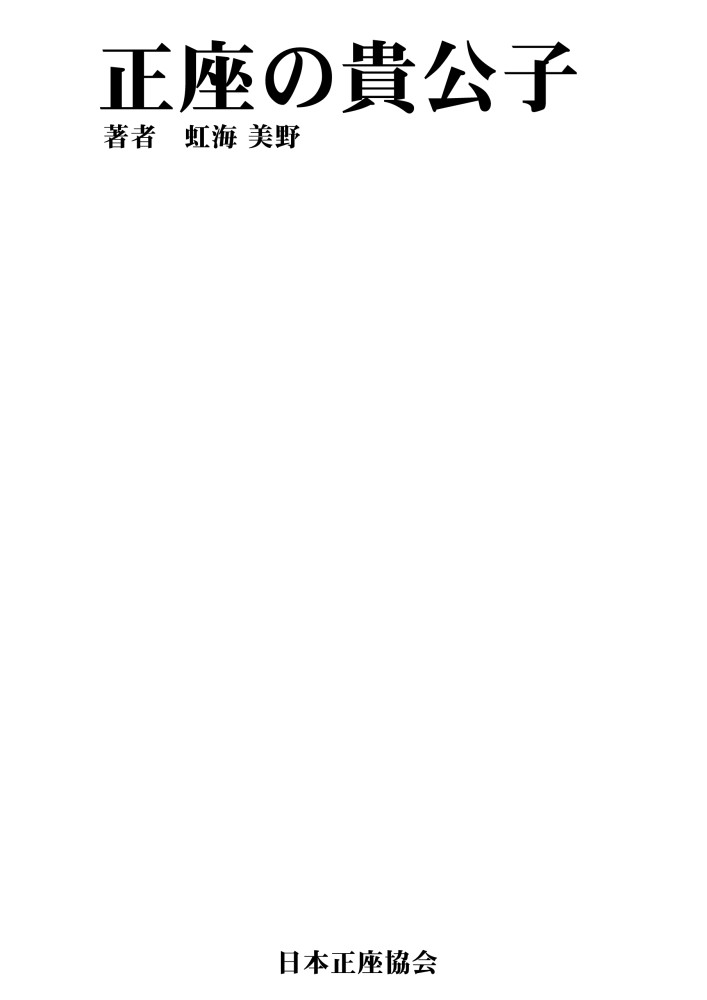
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
これは、四年後のオリンピックが東京に決まった頃の、おおまかに『ごくごく最近』とみなされる現代の女子高生、紀羅美カヤの正座と恋にまつわる物語である。
紀羅美カヤは四月に高校に入学した。どの高校でも行われる新入生歓迎会で部活の発表が行われ、朝や昼休みは新たな部員獲得競争、放課後は仮入部で校内は賑わっている。
カヤの元へは上級生がマネージャーのスカウトに頻繁に訪れていた。サッカー部、ラグビー部、野球部、男子バスケ部、男子バレー部……。周囲のまだ打ち解けていない女子の羨望の視線を感じつつ、それらの勧誘をカヤは全て丁重にお断りしている。
カヤと中学から仲のいい多田師浩介は、カヤと一緒にいる時に「じゃあ、部員で入りませんか」とついでのようにスカウトされ続け、そのたびに先輩に失礼がないよう気をつけた様子でやはりお断りをしていた。
浩介は生徒会に入る気でいる。生徒会は部活とのかけ持ちができるが、浩介は生徒会以外にやりたいことはないらしい。
カヤの中学からは、カヤと浩介だけが今年の入学者だったことに加え、同じクラスになったので、なんとなく入学式や新学期の教室で手持無沙汰になると話していた。そのため、少し経ってから、カヤは浩介と付き合っているのかと新しく友達になった女子に訊かれることが多い。カヤは否定し、もちろん浩介も否定している。
浩介の理想とするのは所作や言葉遣いの美しい女子なのだそうだ。浩介の持論によると、良家の子女であれば作法や立ち振る舞いなど幼い頃より家庭や習い事で身に着きやすく、また社交の場でも美しい所作の大人と接する機会が多い。しかし、一般家庭でもそういったしつけをしている家庭はないわけではなく、一般人の場合必ずしも必須とは言い難いそうした所作を身につけている女子こそが素晴らしいということだった。
この学校にそういった女子がいることを浩介は期待していたらしかったが、教室内にそれらしき女子を見つけられなかったと落胆していた。そして仮に見つけられたとしても、相手の女子が浩介を気に入るとも限らないとカヤは指摘し、だいたい浩介やカヤが通う学区内の公立中学から多くの生徒が入学する高校という時点で中学とさして変わらないということに、なぜ浩介は気付かなかったのかと追い打ちをかけた。
カヤは浩介に部活を見学してみようと提案された。教室内で理想女子を見つけられなかった浩介は、一縷の望みを部活にかけたらしい。本当は浩介だけで勝手に行ってもらいたかったが、女子のみの部活もあり、見学しにくいと言うので、浩介に追い打ちをかけてしまった責任も感じ、渋々カヤは同行することにした。女子のみの部活動では、さもカヤが一人で部活見学に行けない恥ずかしがり屋さんで、浩介はそんな中学時代の友達に付き添うといった風を演じる点は納得がいかず、訪れる部活先で「どう?」と親切そうにカヤに訊く演技を浩介がするたびに、カヤは隠れて浩介の足を踏み、浩介は笑顔を張りつけてそれに耐えていた。
2
浩介が見学を希望したのは、いずれも文化部だった。放課後の活気ある声が聞こえてくる校庭や体育館から遠ざかり、しんとした廊下を歩く。茶道部や華道部、料理部、書道部とまわり、浩介の彼女候補となる女子の出現を待ったが、なかなかそういった女子はいないようだった。もともと浩介の見学は部活動への入部を検討するものではなかったので、それほどどの部活にも長居することはなかった。どちらかというと、こういった文化部より、カヤはラクロス部やテニス部、チア部に興味がある。入学してからすぐのマネージャースカウトラッシュで部活からやや遠ざかっていたカヤだったが、やはり放課後の校内を歩くと自然に部活への意識も強くなった。
最後に浩介が訪れたのは囲碁クラブだった。
校舎端にある畳の部屋で活動は行われているとのことで、引き戸をそっと開け、入口に立った。
室内では和気あいあいと活動が進行していると想像していたが、張り詰めた緊張感の中、碁盤を挟み、二人の男子が向き合っていた。室内はカヤが思っていたよりも広く、均等に細長い折りたたみ式のローテーブルが並べられ、そこに碁盤が置かれている。現在は三つの対局が行われていたが、入ってすぐのテーブルで対局中の二人に十人ほどの部員と見学者が見入っている。ホワイトボードには、初心者でもわかるように簡単な囲碁の説明が書かれていて、いくつかのテーブルで初心者のための対局が行われていた様子だが、今皆が見入っている対局が気になり、中断されたようだった。
同じ一年のカラーの上履きを履いている女子が、後からやって来た浩介とカヤに『静かに』という視線を送る。面倒なところに来てしまったとカヤは後悔した。
疲れ気味だったが気を遣い、カヤはそっと戸を閉めた。しかし、とん、と引き戸を閉めた時の音が響き、一瞬張り詰めていた空気が停止した。
手前側に正座していた男子が振り向き、「あ、」と浩介に手を挙げ、浩介も遠慮がちに手を挙げた。どうやら浩介は知り合いがいる部活を最後に覗きに来たらしかった。浩介の知り合いはカヤと目が合うとそのまま数秒カヤを見て何か言いかけた後、小さく会釈し、カヤも一応それに倣っておいた。
先輩方が「どうぞ」と、この緊張感が解けた僅かの間に中へ入るように勧めてくれる。皆狭い出入り口で上履きを脱ぎ、順番に座敷に入る。
思いの他見学者は多く、席を外している対局中の場所から座布団を拝借しても、数が足りなかった。
すると「これ」と浩介に手を挙げた男子が、使っていた座布団を軽くはたいてカヤに差し出した。
「いえ、」と遠慮したけれど、「僕、慣れてるんで」と短く言い、畳に直に正座をすると再び碁盤に集中した。
恐縮しつつも、カヤは浩介の知り合いが貸してくれた座布団に座った。
浩介の知り合いは両膝を揃えて正座し、真っ直ぐに背筋を伸ばし、首をやや傾けて碁盤を見る。
額から鼻筋、顎に至るまで、本当にきれいな横顔だった。長い睫毛が半ば伏せられた瞼から真っ直ぐに伸びて影を作り、時々考え込んで顎や鼻先に触れる指先や爪も清潔感があった。
しっかりとした艶やかな髪や、透き通るような肌、少し華奢で均整の取れた身体。多分整髪料もスキンケア用品も使っていない。素のままの彼の身だしなみが逆に素材の良さを前面に出しているとカヤは思った。
貴公子、という言葉がカヤの中に浮かんだ。
名前を知らない、今、目の前にいる素晴らしく美しい正座をし、凛とした名前を知らないこの人を呼ぶならそれが一番しっくりとくる、と。
カヤはすっかりこの浩介の知り合いに見惚れ、そして座布団の上で斜め座りをしている自分に気付き、急に恥ずかしくなった。男子を前に恥ずかしく感じたのは、人生でこれが初めてのことだったかも知れない。
3
浩介の知り合いは須和理田緑といい、隣町にある中学の出身だった。浩介とは塾が中学三年間一緒だったらしい。カヤの中で、貴公子という言葉は須和理田緑に変換された。
翌日も囲碁クラブの見学に行きたかったが、もう浩介は囲碁クラブに用はないらしく、おまけに囲碁クラブの活動は週に二度だけだった。
須和理田緑との接点が持てずにカヤはそれから一週間を過ごした。
しかし、その翌週には球技大会があった。
カヤは時間を見つけては緑を探した。緑との接点が持てない間、緑に彼女ができてしまったら、と気が気ではなかった。何となく、緑は女子に告白されたらそのまま受け入れそうな感じがした。それは困る。
緑はサッカーに出ていた。球技大会はサッカー、バスケ、バレーボールで校庭、屋外にあるハードコード、体育館でそれぞれに複数の試合が行われる。バスケに出場したカヤは、一回戦の一年生同士で勝ち、二回戦で三年生に当たって負けた。敗者同士の試合はないため、午後は応援するのみの気楽な立場だ。
午前中のうちに緑がサッカーに出ているのを確認しておいたカヤは、最近仲良くなった女子の友達と午後からは男子のサッカーを見学していた。前日までの雨でサッカーを行う校庭は湿っていたが、五月晴れの空が広がり、コートわきの幅の広い階段や芝生からは多くの生徒が声援を送っている。
緑のクラスは一年生対二年生で、審判は二年生が担当していた。
パスを受けた緑が走り出す。
文化部なので運動は苦手なのかとカヤは勝手に思っていたが、緑は無駄のない動きで二年生をかわして行く。その姿にも品があり、さすが貴公子、とカヤは心の中で感嘆した。
そのままゴールに見えたが、正面から来た二年生に足をかけられ緑は転倒した。「あっ」とカヤは声を上げる。試合を見ていた緑のクラスメイトもざわめき、様子を見ている。
審判の男子が笛を吹いてファウルを伝えたが、足をかけた二年生はそれを否定しているのがカヤのいる場所からもわかった。転倒した緑はそんな彼らを見ながら立ち上がった。大きな擦り傷からは血が滲んでいる。
だんだんと足をかけた二年生に審判が押され始めている。もともと審判の指示に従うのがルールなのは誰もが知っているが、守られるかどうかは今の段階では微妙だった。
『あれ、足かけられたよね』と、緑のクラスメイトが小声で言い合っているのが聞こえてくる。
カヤは立ち上がり、「あの、足、かけたの私、見てました」と大声で言った。
緑のクラスメイトが小声で言い合うのを止め、ふいに発言したカヤを見上げた。
隣に座っている友達にも「ね」と同意を求め、友達は明らかに困った顔をしたが、小さく「うん」と頷いた。
再度審判から告げられたファウルを二年生は渋々受け入れたが、「うるせえんだよ」と吐き捨てるようにカヤに向けて言った。
緑のクラスメイトは心配そうにカヤを見ている。
カヤは顔色を変えず、その場に座った。
間もなく試合はフリーキックで再開された。
カヤは子どもの頃から、『正しいと思ったことはきちんと自分で言える人間になりなさい』と言われてきた。ただ言われていた時には、そういうものだと捉えただけだったが、子ども同士の世界での小さな物事のかけ違いが生じるたびに、それは必要なことだと思うようになった。
小学校の低学年の時、通っていた市内のスイミングスクールは、同じ建物内にヨガや体操教室、ダンススクール、英会話などのカルチャースクールが併設され、夕方までの時間帯は子ども向けのカルチャースクールも多く開講し、たくさんの子どもが来ている場所だった。カヤもスイミングの他に、体操を習っており、週に二度通っていた。スイミングのカヤのコースはこの日検定で、その後は自由時間だった。検定の緊張から解放され、皆がロープで仕切られたコース内を自由に泳いでいた。
この時、スイミングスクールに通うカヤと同じくらいの年の水着を着た子どもと、服を着た子どもが走ってプールサイドに入って来た。初めはふざけている様子だったが、服を着ている子の持ち物を水着の子が色々取り出し、そのまま走っている途中で、小さな何かをスタート台の方からプールに落とした。服を着ている子はプールの底を見て泣きそうになり、そこへコーチが駆けつけた。カヤは何となく、その様子をプールから見ていた。スイミングに通っていない子が教室のある時間にここへ入ったことをまずコーチは咎め、その流れで水着の子は服を着た子が勝手に物をプールに落としたと嘘をついた。コーチはしてはいけないことをした時に叱ると恐いと有名で、そう言ってしまった水着の子の気持ちもわからないでもなかったし、そのままにしておいてもよかった気がしたが、カヤはプール内に落ちたものを水中に潜って拾い、二人とコーチの立つスタート台の方まで泳ぎ、まず落ちていた物を服を着た子に手を伸ばして渡した。そして少し迷ってから、『この子がこの子の物を取って、わざとではないけど、プールに落としたのを見ました』と伝えた。その後のことは覚えていない。けれど、言った後にこれでよかったと強く確信した感覚はカヤに残り、それは未だに続けられるようになった。
友達は小さくカヤを肘で突き、「ああいう時には、先輩とか先生とかに言ってもらった方がいいって」と言ったので、カヤは「急に訊いたりしてごめん」と、巻き込んだことを謝った。
「っていうか、あの男子もさ、部外者の女子がわざわざ言わなくても、自分で足かけられたって言えばいいのに」
……そういう考え方もあるのか、とカヤはスニーカーを眺めながら思った。
ただ思ったことを言っただけだったが、もしかすると須和理田緑にも迷惑に思われたかも知れない。
「あ、ねえ、すごい」
急に切り替わった友達の声でカヤは顔を上げる。
緑がさっき足をかけられた先輩を抜き、ノーマークになっていたクラスメイトにパスを出した。パスを受けた緑のクラスメイトはさっきの騒動のこともあったためか、二年生を前に一瞬怯んだが、すぐにシュートを決めた。僅かな沈黙の後にわっと歓声が上がる。
試合終了の笛が吹き、緑のクラスは二年生に勝ち、準決勝に進んだ。
試合を見守っていた緑のクラスメイトは立ち上がり、サッカーコートへと駆けて行った。
グラウンドから去り際、緑と目が合った気がしたが、カヤのところへさっきファウルのことで審判ともめた二年生の男子が来て、視界は遮られた。二年生の男子は「さっきは失礼な言い方をしてすみません」と、小さく頭を下げた。意外なことでカヤは驚きながらも「部外者が口出ししました」と自分の立場を自覚したことは伝えた。二年生はその後、審判をしていた男子にも謝りに行っているようだった。
その様子を見ていたカヤが再び緑を探した時には、緑はクラスメイトに救護室に連れられて行った後だった。
ほとんど話していないのに、好きになることはあるのだろうか、とカヤは授業中考えていた。
須和理田緑、という名前と出身中学についてはそれとなく浩介から聞き出したが、それ以上を聞くのは躊躇われた。
学校内では早くも付き合い出した子が少なからずいて、誰がいい、という話はかなりあちこちで出ている。
その中で、須和理田緑の名前は今のところ一度も出てきてはいなかった。
中学校の時もそうだったが、人気のある男子というのは、明るく社交的で、髪型や制服の着方も本当にさりげなく工夫している。目立つ、わかりやすい、というのがカヤの印象だ。それにプラスし、背が高いとか、イケメンとか、運動部に入っているとかで、人気の順位は左右されていく。そして人気のある男子というのは、やはりそれなりに人間性も好感が持たれることが多く、清潔感があり、おしゃれにも気を配っている。
そういう観点から考えれば、須和理田緑は社交性もなさそうだし、目立つ存在でもないと思う。
けれど、碁盤を挟んだ真剣勝負の中であっても、座布団が足りない時には気遣いを見せた。球技大会で足をかけられた時には何も言わなかったけれど、最終的に試合に勝つゴールのアシストをするかたちで、本人なりに納得しているように見えた。
カヤからするともどかしい性格に感じられる一方、何もかもをハッキリさせずとも本人なりに納得しているらしいマイペースな面は、不思議な心地よさを感じさせた。
4
この週は放課後、女子の友達に誘われ、水泳部、ダンス部、チア部を見学しに行った。
正直、カヤとしては浩介とまわった文化部の見学より、よほど面白く、興味が湧いた。
小学校まで水泳と体操をやっていたというカヤの経験も買われ、裏表のなさそうなさわやかで目のキラキラした素敵な女の先輩に積極的に勧誘され、悪い気はしなかった。
どの部活に入るかを相談して決めることを約束して、自転車通学の友達と別れた。
今日は囲碁クラブがある日だと思い出し、カヤは校舎へ戻り、そっと囲碁クラブを見に行った。
引き戸は開いていて、廊下から室内を覗いたが、緑はいなかった。
部員が気付いて「中へどうぞ」と言う申し出をカヤは慌てて断って、走り出した。
何をやっているんだろう、と自己嫌悪に陥り、昇降口を出ると、中庭の花壇の前にいる緑を見つけた。
緑は花壇の手入れをしていた。緑の横には引き抜かれたと思われる草が小さな山を作っている。
砂を踏んだカヤの足音で振り返ってくれることを期待したが、緑はそういう点では気が利かない。
暫く後ろから様子を見ていたが、元来結論を早急に欲しがる性格のカヤは我慢できず、「掃除?」と声をかけた。
そこでゆっくりと緑は周囲を見回し、カヤを振り返った。
「あの、囲碁の方、いなかったけど」
「囲碁? ああ」
のんびりと考えた様子で緑は一人頷いた。
「園芸の方も入ろうと思って、先週一回だけ活動に参加したら、できる時に花壇の世話をしてくれると助かるって三年の先輩が言ってたんで、今日ちょっと花壇の手入れをしてから囲碁の方に行こうかと思って」
「そう、……なんだ」
囲碁も興味ないが、花も残念ながらカヤは興味がなかった。
それでも緑の背後から花壇を覗くと、きれいに雑草が除かれている。
先日カヤが見惚れた緑の指先は爪の中に土が入り、乾いた土でかさついている。残念に思うはずだったが、カヤはそんな緑を好きだと思った。
「これから、囲碁の方行くけど、一緒に行く?」
思いがけない提案で、「え」と短く声を発したままカヤはその返答に困った。
女子としてはこの後一緒に帰るとか、せめてこの場で話すくらいの提案がほしいところだが、緑はあくまで囲碁の予定を変えるつもりはないらしく、またカヤが緑と話したくとも囲碁に興味がないことまで思い至らないらしい。
緑は「ちょっと待って」と雑草をまとめて校舎の裏側の方へ行き、水を入れたじょうろを手に戻ってくると花に水を遣った。じょうろを戻しに行き、手を洗う。
「じゃあ、行こうか」
「え、あ、う、うん」
行かない、私はここで帰る、と言いだせないまま、カヤは再び囲碁クラブに行くはめになってしまった。
「あの、」と緑が何かを言いかけて一度黙り、それから「水泳、昔、やってた?」と訊いた。
「うん。水泳、やってたの?」
共通の話題ができるかと思い、そう訊き返すと、「ううん、僕は」と緑は曖昧な返事をし、そこで会話は終わってしまった。
せめて緑の趣味だとわかる囲碁や園芸の話をしたいが、全くカヤにはわからない。
結局そのまま沈黙が続き、囲碁クラブの活動場所である和室に到着してしまった。
5
「須和理田です、遅れました」
そう言って緑は慣れた様子で和室へ入って行った。
「先輩が待ってるよ」と、誰かが言い、早速緑との対局が始まるようだった。
「お友達?」
男の先輩が碁盤越しにカヤを見る。
「あ、さっき昇降口で会ったので、一緒に」
ここでカヤはクラスと名前を言うべきだとわかっていたが、入る気のない部でそれも躊躇われ、黙っていた。
「ま、見るだけでもどうぞ」
カヤの意を汲んでか、そこまで考えてはいないのか、人のよさそうな先輩が座布団を出し、カヤに勧めてくれる。
「すみません」とカヤは小さく言い、正座した。
緑は先日のように背筋を伸ばして正座する。肘を垂直におろし、両膝は軽くつけられ、白い靴下を履いている足の親指同士が重ねられている。
それと比較し、とりあえず今日は正座をしたものの、自身は緑のようにはいかないとカヤは思った。それでも、正座をするだけ個人的には一歩前進といったところだろうか。
先輩と緑が囲碁を始めると、部員が周囲でその様子を眺め始める。
「須和理田ってすごい強いけど、どこで囲碁やってた?」と見ている先輩の一人が訊く。まだ会話をする余裕のある緑は、「小学校の頃、囲碁教室があったんです。そこに暫く通ってたんですけど、人気ないからその教室なくなっちゃって」と答えた。
「その後は?」
「テレビで見たり、あと、お父さんの実家に囲碁の本とか、碁盤とかあったんで、それ使ったり。たまにお父さんの実家の傍にある囲碁の会に入れてもらったりしていました」
「お父さんの実家が囲碁をやってたってこと?」
「父の祖父が好きだったと聞いていますけど、父の祖父以外は誰もやらないらしくて、僕が大切にするなら使った方が父の祖父も喜ぶだろうって」
「へえ」
囲碁には興味のないカヤだが、緑の子どもの頃の話には耳を傾けた。
「じゃあ、園芸は?」
「そっちは、うち野菜をやたらと消費する家なんですけど、うちはあんまり庭とかないんで、最初は自宅の小さいプランターを使って、それから父とか母の実家の庭で初心者でも育てられる野菜を作り始めました。まあ、毎日は通えないんで、実質的な面倒は見てもらっているんですけど」
「俺らが言うのもなんだけど、サッカーとか野球とかって須和理田は選択肢になかった? 男子の部活って、大抵そういうのが出るでしょ。最初」
「……僕は自分のミスで迷惑かけたりすること考えると駄目で、あんまり向いてないなって」
「それわかるわ」と、誰かが言い、周囲に笑いが広がった。
カヤはその中で一人笑えず、この前の球技大会の緑の姿を思い出していた。もう少し勝気というか、意志をハッキリ表に出す性格であれば、緑はかなりの運動能力を発揮できるはずだと思った。
「この前の球技大会の時も、走るのも速かったし、運動神経いいと思うから、運動部に入らないの勿体ない気がする」
カヤとしては、嘘偽りない言葉だった。
緑の運動能力に対する自己評価の低さを見過ごせず、いつもの癖で正しいことだと思い、発言していた。
発言した後、カヤに部員の視線が集中していることに気付いた。そして、この言葉により同年代としては落ち着いた大人な性格である面々が多い囲碁クラブであっても、皆少なからず気分を害していることも十分にその視線から伝わってきた。
「別に、運動苦手な人間が囲碁やるわけじゃないし」
そう言ったのは、この前浩介と見学に来た時にもここで見かけた記憶のある一年女子だった。きっと、真剣に囲碁に取り組みたいと思って入部した人だろう。
カヤは「すみません、囲碁のことを否定したかったんじゃなくて、須和理田くんの運動神経がよさそうだったから」と謝った。
「須和理田くんの話をしに来てるのか、囲碁の見学なのか、どっちなんですか」と、別の女子に突っ込まれた。笑いを含んだ口調を心がけたらしいが、誰も笑っていなかった。
カヤはさすがに言葉に詰まった。
ハッキリ物事を口にしない人をカヤはそれぞれの考えと捉えてきたが、言えるのであれば言った方がいいと考えたことは何度もあった。けれど、いつも明確に口にできることばかりではなくて、まして自分では公にしたくないことを人に指摘された時の居心地の悪さがあるということを今、猛烈に感じていた。
「……活動の邪魔をして、すみませんでした」
カヤはそう謝った。
すぐに立ち去ろうとしたが、足が痺れていて、よろめいた。
とっさに腕を支えられ「大丈夫?」と訊かれた。
顔を上げると、緑がカヤの腕を取り、心配そうに見ている。
惨めだった。
人生でこれほど惨めな気分はなかったと思う。
「大丈夫。邪魔してごめん」
カヤは緑から目を逸らし、それだけ言うと、一人部室を出た。
6
一階の廊下でスマホを見ると、友達からチアに入りたいと入っていた。
既読無視状態になってしまうのもまだ付き合いの浅い友達同士では微妙なところで、カヤは明るくチア部に賛同していることと、まだ自分は少し考えることを書いておいた。
トレーニングルームからは、明るい声が聞こえてくる。
昇降口へ向かう途中、通り過ぎながら見遣ると、私服の女の人二人が、チア部の熱烈な歓迎を受けていた。カヤの通う高校は比較的運動部の活動場所が多いが、いつも決まった場所ではなく、いくつかの運動部は何曜日は体育館、トレーニングルーム、渡り廊下手前のスペースというように活動場所は変動している。トレーニングルームは他にもダンス部や、ジャグリング部が使用している場所だ。
今日はチア部の日だったか、と思いながら見ていると、部員四人が横に並んで密着し、少し腰を落とす。内側二人の膝の上に来校者の女の人の一人が乗り、部員とともにきっちりとポーズを決めた。それを他の部員がスマホで撮っている。チアの部員は皆ほっそりとしているけれど、その様子から基礎トレーニングを入念に行い、鍛えていることがうかがえた。多分、来校者の女の人は卒業生なのだろう。もう一人の来校者の女の人とも記念撮影をし終え、部内は更なる盛り上がりを見せていた。
先輩の前を素通りするのも気が引け、会釈して通り過ぎると、「あ、待って」と声をかけられた。
「先輩、この前見学に来てくれた一年生の紀羅美カヤさん。まだ入部は決まってないんですけど」
部員の先輩に手を引かれ、カヤはチア部の集まるトレーニングルームに入った。
「体操の経験者なんで、入ってくれると嬉しいんですけど」と部員の先輩は卒業生にハキハキと伝える。
髪の長い子は後ろの高い位置で結び、本番ではリボンをつけるので、チア部の子は普段から髪を一つに結んでいる子が多い。卒業生もその名残なのか、進学先でもチアを続けているのか、髪は高めの位置で一つに結ばれている。バランスよく筋肉のあるほっそりとした体型に、自然と力の込められたしっかりとした表情を前に、つい先ほどのことで不安定になっているカヤは気後れする。
「あれ、なんか今日元気ないね」
横から部員の先輩がそれに気付く。
「今日はどっか部活見学してきたの?」と、他の部員の先輩が訊く。
「え、チア入ろうよ」という先輩に、「さっき花壇のところで男の子と一緒にいたけど、同じ部に入るとか?」とまた他の先輩が重ねて訊く。
「あ、いえ、囲碁クラブは私、全然やったこともないし、これから先もできそうもないし、無理でした」
カヤは慌てて答える。
「部活は授業と違って、好きなことや得意なことをやる時間だからいいんだよ。カヤちゃんだっけ? が、チアに入っても入らなくても、それも本当に自由だと思う。だけど、別の部活で活動して、その上で仲良くすればいいことだよ。チア部だって、サッカー部とかバスケ部とかの子と付き合っている子、たくさんいたし」
何となく、カヤの事情を察したらしい卒業生は、そう言って笑った。励ましてくれる話の例でも、やっぱり囲碁クラブはないんだな、とカヤは思ったが、さすがにそれは口にしなかった。
「そうか、そうですよね」と小さく言った後、泣きそうになったカヤに卒業生の先輩が「じゃあ、カヤちゃんに特別に」と言って、チアの部員に目配せした。
チアの先輩たちはそれですぐに動き、音楽を流すと、ポンポンを持って、普段学校名の入るところをカヤの名前に置き換え、カヤへのエールを送ってくれた。
下校中の生徒も足を止める中、恥ずかしさもあったが、この温かくて真っ直ぐな部活に入りたいと思った。
拍手し、「ありがとうございます」と言ったカヤに部員の先輩は「新入部員一人確保」と恥ずかしそうに言って、皆を笑わせた。
7
カヤがそれから暫くチア部を見学して校門を出ると、そこに緑が立っていた。
緑はカヤに気付くと、すぐにカヤの方へ来た。
「あの、さっきは、大丈夫?」
「うん、もう平気」
「あの、ずっと、紀羅美さんに言いたいことがあって」
「え」と、カヤは黙りこんだ。
これは、告白だろうか? いや、それはない。
囲碁に興味がないなら来ないでくれとか、そういう話だ、きっと。
カヤは緑が話すのを待った。
「紀羅美さん、昔、駅の傍のスイミングスクール、行ってたよね?」
「は? うん、小学校の時ね」
スイミング? と思いながらカヤは頷く。
「紀羅美さんに、言わないといけないことがあって」
だから何? という言葉をカヤは堪えた。
「昔、囲碁習っていた時にそこで友達に会って、スイミング行ってないのに、友達とプールの方に行って、先生に叱られそうになったことがあった。だけど紀羅美さんのおかげで僕がやってもいないことまで叱られずに済んだことがあった。……小学校の時で覚えてないかもしれないけど。あの時、プールに入った僕の碁石も拾ってくれた。帽子に名前書いてあって、それを覚えていたから、入学式の時に気付いた。四月の囲碁の時にすぐお礼を言いたかったんだけど、どう言っていいかわからなかった。今頃急にそんなこと言われても困るだろうっていうのもわかっていたし、だけど、お世話になったまま本人に何も言わずに居続けるのも違う気がした。その後、サッカーの試合の時もファウルのこと、紀羅美さんが言ってくれた。だからやっぱりお礼も言わないとと思って、囲碁に行くならその時言おうと思ってたんだ」
緑はカヤに割り込ませる隙を与えず一気に喋った。
喋った後のことまで考えていないようで、沈黙が流れた。
「……そうなんだ」
カヤは拍子抜けし、「だったら、別に囲碁の時じゃなくてもよかったのに。お礼なんて、そんな気にしなくてもいいのに」と言った。言ってから、次第に昔の記憶が甦り、小学生の時スイミングスクールで拾ったのが碁石で、コーチに見たことを伝えた時の子が緑だと気付いた。あんなに昔のことを覚えている緑に、カヤはかなり驚く。
「そうなんだけど。浩介と、付き合ってるのに、わざわざ教室まで行ったりすると、迷惑かと思ったから」
「え? 浩介?」
緑は頷いた。
「付き合ってないよ。浩介は正座とか、そういう所作がきれいな女子を探しているんだって。私みたいに正座してもすぐ足が痺れるような女子はさ……」
明るく言ったつもりで、後半はさっきの囲碁クラブのことが思い出され、自然と声のトーンが落ちた。
「僕は!」
ふいに緑が大きな声を出した。
「な、何?」
「僕は、大切なことを言えなくて、いつも後悔している。でも、遅れても、今、紀羅美さんにお礼を言えてよかったと思っている。本当は、紀羅美さんみたいになりたかった。自分のことは嫌いじゃないよ。だけど、小学校の時、困っていた僕のところへすっと泳いできて、ハッキリあの恐そうな先生に意見を言って助けてくれた紀羅美さんは、決してなれないけど、僕のなりたい姿だった」
「ありがとう」とカヤは言うのが精いっぱいだった。
そんなふうに覚えていてくれたんだね、と。
すぐに付き合おうとか、結論を急ぎたい性分のカヤだったが、緑の振り絞った言葉と勇気で、何も言えなくなった。
お互いの違いについて認めたり、近付きたいと思ったりしながら、それぞれの部活の終わる時間に合わせて一緒に帰るようになった二人が正式に付き合うようになるのは、もう少し先のことになる。








