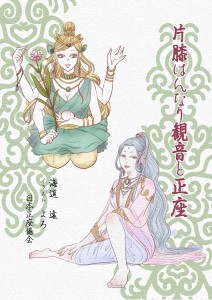[63]正座サーファーと人魚
 タイトル:正座サーファーと人魚
タイトル:正座サーファーと人魚
分類:電子書籍
発売日:2019/08/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:44
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:keiko.
内容
エーゲ海の人魚の娘ルゥルゥは、ある日サーフィンしている青年サーフと出会う。
が、どうも普通の乗り方ではない。ボードの上に座ろうとしているらしい。
青年は華道教室の師匠の母親と対立して、風変りサーフィン大会で「サーフボードの上で美しい正座をしてみせる」と誓ったのだった。
何度練習してもうまくいかず海へ落ちるサーフを、ルゥルゥは懸命に手伝う。
ある日、サーフが岩で足を怪我してしまうが、ルゥルゥや、親友スープに励まされる。
そして大会の日はやってきた。母親たち華道の一行まで応援に来て、大会はどうなることやら。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1484866

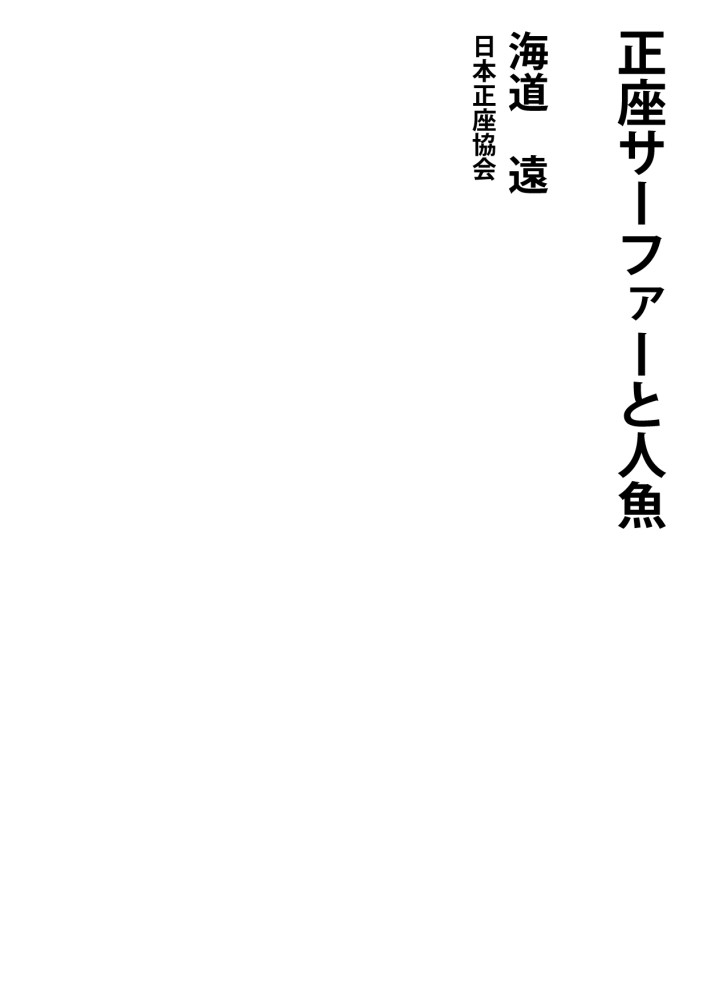
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 エーゲ海にて
どこまでも広がる青い空とエメラルドブルーの海。
ルゥルゥは鼻歌を歌いながら腰まである縮れた金色の髪を整えていた。
岩場にひた寄せる波の音に混じってルゥルゥの黄緑色の尾びれがピタピタと波を打つ。
岩場の後ろには、人間たちのビーチ。
「この頃、泳いだり、変な形のもので遊ぶ人間たちが多くなったわ。アネモーヌ様が愚痴るのも無理ないわね」
ふと気づくと、波間にサーフボードの上で何かしようとしている若者がいる。いったん立ち上がって座ろうとしているようだが、何度もひっくり返っている。
ルウルゥは好奇心を抑えきれず、彼のところへ泳いでいった。
「何をやっているの? 黒髪の人間」
若者は「んん?」てな顔をしたが、しぶしぶ答えた。
「風変りサーフィン大会で優勝してやるんだ。人のやらないことをやってみたいのさ」
(他の、板の上に立って波乗りしてる人はスイスイ楽しんでるのに、変わった人ね)
仲間の人魚たちが海水に長い髪をそれぞれ、海藻みたいにゆらゆらさせてやってきた。
「ルゥルゥってば。人間に捕まえられるわよ」
「アネモーヌ様に叱られるわよ」
とたんに若者がまた落っこちて、波に翻弄されていく。ルゥルゥは急いで後を追った。
砂浜で意識を取り戻した若者は、目の前に金髪の女の子がいるのにびっくりして素早く離れた。そして、下半身の黄緑色の大きな魚の尻尾にも!
「お、お前、もしかして人魚?」
「わかんない。これが私。ルゥルゥっていうの。あなたは?」
「お、俺は、やま……、いや、サーフって呼んでくれ。その尾びれ、水着じゃないよな? イルカみたいに大きいけど」
「水着って何?」
「まあいい」
サーフは、おっかなびっくり近づいてきて砂浜に座った。
「君には分からないだろうけど、聞いてくれ。俺はここから遠い遠い国の人間だ。ジャポンという。あの座り方は『正座』といって、俺の民族だけの座り方だ。だから今度の風変りサーフィン大会で、正座でサーフィンのロングタイムを残したいのさ」
「ジャポン……。渡り鳥から聞いたことがあるような?」
沖では、ルゥルゥの仲間たちが心配そうにふたりを見ている。
「ルゥルゥったら……本当に老女アネモーヌ様に叱られるわよ。どんな目にあっても知らないから」
アネモーヌは巨大イソギンチャクの魔女である。怒らせると恐ろしい。
「つまり、『正座』って座り方は、日本、ジャポンに伝わる世界一の座り方だってことを風変りサーフィン大会で世界に発信したいんだよ!」
「わかったわ!」
ルゥルゥが眼を輝かせた。
「いいわ、手伝ってあげる。あなたが海の底に落ちないように、板を支えて」
「そりゃ助かる。大会は来月なんだ」
ふたりはますます盛り上がった。
第二章 魔女アネモーヌ
それからというもの、サーフの練習にルゥルゥが手を貸すことになった。サーフの相棒、スープというジャポン青年もやってきたが、ルゥルゥは上半身だけしか海上に出ないので人魚と気がつかない。
「どしたんだよ、こんな可愛子ちゃんを、どこで」
「ロマンティックに浜辺で気を失っていたら、マウス・ツー・マウスされたんだよ」
「え! マジかよ」
「ははは」
何回も波を待ってボードの上に正座しようとする。
うまくいかない。落ちる度にルゥルゥが素早く泳いできてサーフを押し上げる。水平線に毎日、真っ赤な夕陽が落ちていくまで、それは続いた。
ルゥルゥが、遂にアネモーヌに呼び出された。
深い深い海底の窪み、岩に何種類もの珊瑚が生えて、魚もあまり近寄らない不気味な海域である。
「この頃、人間の海岸へ行ってるそうじゃな」
長い紫色の触手がうねうねと動き、岩穴の中から金色の眼が光っている。ギリシャ神話のメデューサの蛇の髪のように、髪がイソギンチャクの触手になっているのだ。
しかし、海の一族の長老お婆なのだから、ルゥルゥたちはおとなしくしているしかない。
「あんまり海岸に近づくでないよ。人間に捕らわれるのが関の山さ。あやつらはわしらを目の敵にして喰うか、見世物にするらしいからねえ」
「はい……」
生返事をするが、ルゥルゥはサーフの元へ行くのをやめる気はない。変なかっこうで波に乗ろうとしているジャポン人とかいう人がとっても気にかかるのだった。
第三章 母親への啖呵
サーフがボードの上で正座しよう、なんて思ったのは母親への反発からだった。母親は華道深山流家元、深山園子女史である。
お華に向き合う時は、絶対に背筋をまっすぐ伸ばしてキリリとした、寸分の乱れもない正座を弟子に指導している。
それは、毛筋一本ほども乱れぬ、水鳥が魚を狙う刹那のような完璧な正座の姿である。でなければ、作品の花に歪んだ気持ちが表れてしまう、と教えた。
園子は華道をする時には、一糸乱れぬ『正座』でなければならない、と日本人として誇りに思っていた。
一人息子のサーフも幼い頃から正座で華道を教えられた。
次期家元として、衆目の前で恥ずかしくない華道を教えなければならないので、華を活ける美しい所作を厳しく指導された。
華道のみならず行儀作法や座り方までである。その正座なのである。
まだ若いサーフは、そんな厳しい生活と、好きでもない華道の家元という決まった道のりがイヤになり、友人に誘われて始めたサーフィンにばかり出かけるようになった。
波の激しさ、面白さはサーフの憂さを晴らしてくれた。
気がつくとどっぷりはまりこみ、一年中、海へ通っていた。
「あなた、海でばかり遊んでいるそうじゃないの」
「爽快だよ、お袋」
日焼けした顔で息子は答える。
「何が爽快よ。ロクにお稽古にも出てこないで」
「ひと目を気にして、家ん中で、ちまちま花を触ってるより、ず―――っと気持ちいいぜ」
「なんですって」
母親の眼が吊り上がる。
「そんなにサーフィンがいいんだったら板の上で正座してみなさいよ。出来るものならね」
「え?」
思いがけない母親の言葉だった。
「精神統一できてこその正座でしょう? サーフィンも、精神統一して花を一枝切って宇宙を創るのも同じことでしょう。できるはずです。波の上で正座して滑ってみなさい。そしたら、あなたのサーフィンも少しは見直してあげるわ」
「どうして縛り付けられなきゃならないんだ」
「あなたが海にうつつを抜かしているからよ。もし成功したら、海へ通うのを許してあげましょう」
相変わらず、とげとげしい母親の言葉である。サーフは後に引けなくなった。
「分かったよ! サーフボードの上で正座してやるよ! 正座が世界一の素晴らしい座り方だって、世界中の人に分かってもらうよ! そんでもって、華道もな!」
第四章 サーフ負傷
母親に大きなことを言った手前、絶対にサーフボードの上で正座しながら滑らなくてはいけなくなった。
サーフィン仲間のスープがギリシャに滞在していて、そこへ押しかけたのだった。ギリシャはエーゲ海、イオニア海、地中海に面していることもあり、近年交通網も発達してサーファー人口が急増しているのだった。
宝石のような海で、毎日、毎日、波に乗った。
普通の乗り方なら、そこそこ波をキャッチして滑れるのだが、波を待っていざ、立ち上がりながら正座しようとすると、バランスを崩してしまう。
周りのサーファーたちが面白がって注目しようと、かまわずサーフは粘った。
そんな矢先だった。ひとりの人魚と出会ったのは。
「お袋が人魚を見たら、どんな顔するかな?」
畳の上で花の枝を睨みつけてばかりいる母親がびっくり仰天した顔を想像しようとしたが、どうしてもできない。浮かんでくるのは、真っ赤な怒りの炎をめらめらと背中にしょった母親の恐ろしい姿と形相ばかりだ。
「あのお袋さん、怖いもんな~~。同情するよ」
隣のベッドで手枕して寝ころんでいたスープが苦笑した。
「俺ぁ、家元なんかになるのは真っ平なんだ。女々しく花なんかいじってられるか!」
ある日、致命的な事件が起こった。ボードから落ちて沈んだサーフが岩場で脛を大きく切ってしまったのだ。二十針くらい縫う怪我だ。幸い骨には異常もなかったが、しばらく練習できない。
「うううむ。俺としたことが!」
病院のベッドの上で悔しがるサーフだが、どうしようもない。
「全治十日だから、風変りサーフィン大会までには治るさ」
付き添いのスープが慰めるが、
「サーフボードの上で正座する練習が進まない!」
サーフはベッドに拳を叩きつけた。
病室に、車いすがひとつ滑り込んできた。
「あ、あんたは!」
溺れた人のふりをして、ストレッチャーで運ばれ、病院に潜入して力を振り絞って車いすに這いずり上がり、乗り換えたルゥルゥだった。ひざ掛けで尻尾を隠している。しゅんとしていた。
「私がもう少し早く泳いでいければ、サーフはコーラル・リーフ(珊瑚でできた海底)まで落ちずにすんだのに……」
「いや、ルゥルゥ、君には何の責任もない。ただ……この傷は完治十日だ。大会が迫ってるのに、まいったよ」
風変りサーフィンの大会は二週間後に迫っている。
実は、日本の母、深山園子にも招待状は送ってある。大会で見事に優勝して、『家元、継ぎません宣言』をするつもりなのだ。
目の前で見れば、あの頑固な母親も諦めるだろう。
だが、この怪我、「万事休す!」だ。サーフは頭を抱えた。
サーフの苦しみようを見たルゥルゥは、大きなため息をついた。
(今は何を言っても、サーフの耳には入らないわ)
「車椅子を海岸まで押していってくれる?」
スープにウィンクして頼んだルゥルゥはひざ掛けをめくり、下半身の黄緑色のひれをチラリと見せた。スープは真っ青になって車椅子の手を放し、しばらく冷たい病院の廊下に立ちすくむ。
「どうしたの、海岸まで押していってうれないの?」
「いや、押しますよ。ただ、そんな大きな魚の尻尾、初めて見たんで……」
もごもご言いながら、車椅子の後ろに立った。
第五章 思いがけない助け手
人魚の仲間を集めて、ルゥルゥはわけを話した。
「そういうわけで困っているの……」
「だから、人間なんかに関わると面倒なことになるのよ」
「もう、これ以上はやめておきなさい」
眉をひそめて仲間は口々に言った。
「私はサーフの願いを叶えてあげたいの!」
「ルゥルゥ、どうしてそんなに……」
「私、サーフが好きなの。大好きなの! 真剣な瞳。どうしても自分の思った通りにサーフィンするぞ! サーフボードの上で正座するぞ! って意気込み。純粋な人でなければできないわ」
「ルゥルゥ……」
人魚たちは顔を見合わせた。
「考えがあるの」
ルゥルゥの瞳が異様に光った。
魔女のアネモーヌの住まいの洞窟へ向かった。
「ルゥルゥ、待ちなさい」
仲間の人魚たちが引き留めようとする。
「アネモーヌ様にお願いしてみるわ」
「よしなさいよ。アネモーヌ様にこんなことが知れたら、私たち、みんな処刑されるわよ。ホオジロザメの巣で!」
「でも!」
深い海で数人の人魚たちが揉みあってるところへ、年老いた声が響いた。
「わしでよければ力になろう」
それはタコのオクトパス老人だった。何百歳の大ダコだろうか。吸盤が並んでいる八本足をうごめかせ、頭(というのだろうか)口の上の部分はしわしわで重そうにぶら下がっている。
「おじいさん……」
「その人間を板にくっつけておけばいいのじゃろう?」
「ええ、まあ、そうなんですが」
オクトパス老人は八本の太い足をくねらせながら花火のように、パッと開けてみた。そして平たい岩に巻きつけてみる。なかなかのスピードだ。
「こんなもんでいいかな?」
ルゥルゥは、嬉しそうに海の中でくるくる回転した。金髪も一緒にぐるぐる回った。
「そう、その吸盤さえあれば、サーフは大丈夫よ! よろしくお願いね、オクトパス爺さん!」
人魚の娘たちは、ルゥルゥとタコの老人を心配そうに見守っていた。それは、長老の魔女、アネモーヌにばれやしないかという懸念だった。
第六章 大会始まる
さて、風変りサーフィン大会の日が来た。
天気は快晴、中央アジアから強い北風が吹いて良い波が来ている。サーフィン関係者や見物人で、浜にはいつもより人が多い。
世界各国の肌の色が入り混じる。
その中でひと際目立つ一団がやってきた。
派手なリゾートファッションに身を包んだ、やや年配の婦人たちだ。
「山雄!」
中でも真っ赤とオレンジの混じった南洋柄のドレスを着た婦人がサーフにぶんぶん手を振った。
サーフは気づくなり、ボードを置いて駆け寄った。
「お袋! まさか来てくれるなんて……」
深山園子は照れ臭いながらもウキウキした様子で、三十人ほどもお弟子さんを従えている。
「そんなつもりじゃなかったんだけど、お弟子さんたちに話したら是非、一緒にエーゲ海に行きたいっておっしゃるから」
サーフはため息をついた。
「お前、『山雄』って名前だったのか! どうも何回きいても本名を言わないと思ったら! 深山山雄? 海とは正反対の名前じゃないか」
スープが真っ赤になって笑いを堪えている。
サーフは母親に向かって、
「俺の大会なんかよりエーゲ海に惹かれたんだろ。お願いだから、そのピンクのレイ、外してくれ。ハワイじゃないんだから」
確かにハワイ旅行の象徴のような赤い花の首飾りであるレイは、エーゲ海では目立ちすぎる。しかし、婦人たちにはまったく耳に入らない。母親以外、思い思いにビーチで遊び始めた。
「言っとくが優勝できなくても俺は、家元なんか継がないからな!」
サーフの言葉は邪険だった。
「はいはい、わかりましたよ」
母親は相手にしていない。お弟子さんたちと騒ぎながら、見物席へ行ってしまった。
ひと気のない岩場へ歩いていった。
ルゥルゥが緊張した面持ちで胸まで潮に浸かって待っていた。
「どう? 傷の具合は」
「ああ、大丈夫だ。昨日、抜糸もしたから自由に動ける」
「オクトパス爺さん。あの人がボードの裏側からあなたの膝を抱えてくれるからね」
波間でタコの足が挨拶代わりに、二、三本ぴしゃりと水しぶきをあげた。
(誰かに補助してもらうのは、規定に反するんだが……)
サーフの胸に釈然としないものがある。
(でも、ここまで皆に心配してもらっちゃなあ~~~~。お袋も来てしまったことだし)
「じゃあ、私とお爺さんは、沖で待ってるから頑張ってね!」
ルゥルゥは笑顔で泳いでいった。
第七章 オクトパス爺さんとの挑戦
いい風が吹き始め、いい波が来始めた。
開会宣言がなされ、一風変わったことをするサーファーたちは海へ出て波を待つ。
波が来た。
ボードの上に立つ者、お手玉しながらとか、ヴァイオリンを弾きながらとか、二人組になってボールをパスしながらとか、珍しいことをこなしながら見事に波に乗っていく。声援があがる。白熱してきた。
「俺がただ正座して乗ったとしても、すごく地味じゃないか」
サーフは第一団の選手を見て自信を失いつつあった。
背後から肩を叩かれた。まだピンクのレイを首から下げた母親である。
「自信を持ちなさい! 日本人だけの凜とした正座姿は、誰にも見劣りしないわ。大和魂を見てもらいなさい!」
「お袋……お袋がそんな風に応援してくれるなんて」
まさか、年がら年中、華道の家元を継げとばかり言ってる母親の言葉とも思えない。
「何のために、エーゲ海まで来たと思ってるの、地球を半周して」
「よし、大和魂を見せてやるっ!」
サーフはボードを抱えて波打ち際へ走っていった。
絶好の大波が来た。
それまでボードの上に腹ばいで待っていたサーフは身体を起こし、正座した。怪我した脛に痛みが走るが堪える。
ボードの裏側からオクトパス爺さんが八本足でがっしと膝に巻きついた。
「ありがとよ、爺さん!」
ボードの裏から爺さんが唇を突き出してにやりと笑った。
クレスト(波の頂上)に乗れた。
サーフは両手を水平に広げた。さながらタイタニックだ。海上をどんどん進んでいく。横で大道芸みたいなのをしているサーファーを追い抜かしていく。ルゥルゥは遠くから見守っていた。
「その調子よ、サーフ」
浜では、
「行け、山雄―――!」
大声援を送る母親に、お弟子さんやスープは気おされていた。
その瞬間―――。
サーフの身体はポーンと弾かれたように宙に浮いて、ゆっくり落下して海に落ちた。
それを見るや、ルゥルゥは尾びれに力の限りをこめてサーフを追って海中へ潜った。
海流に漂った、オクトパス爺さんがよれよれになって、
「すまんのう、やはり、わしゃあトシじゃ。これ以上は支えてやれん……」
くにゃくにゃと海底に沈んでいった。
「サーフ、サーフ、しっかりして!」
サーフを抱きとめて海面に上がったルゥルゥは彼の頬をぴしゃぴしゃ叩いた。
「あ、ルゥルゥ、もう少し頑張りたかった……」
「まだ二回戦があるわよ」
そこへ、
「やりなさい、若者!」
深遠な女の声が聞こえてきて、猛スピードでやってきた紫の触手を何本もなびかせた怪物の姿―――。
「アネモーヌ様?」
ルゥルゥは眼を見開いた。
第八章 最後の勝負
「ルゥルゥ、あんたのやってることくらいお見通しだったよ」
「アネモーヌ様……」
耳まで避けた口でアネモーヌは「くっく」と笑った。が、それを目の当たりにしたサーフは血の気がひいた。
「さ、今度はわらわが老オクトパスの代わりに触手の吸盤で若者、そなたの膝を抱え込むゆえ、今一度、挑戦してみやれ」
「アネモーヌ様、ありが……」
ルゥルゥがお礼を言いかけるのを、サーフは遮った。
「どこの海の女王様か知りませんが、申し訳ないけど遠慮させて下さい。さっきオクトパス爺さんの助けを借りてやってみようだなんて思った俺が浅はかでした。今度は自分だけの力で!」
「おお……?」
アネモーヌは勢いに驚いた。
「見直したぞ、若者! 聞けば、遠い遠いジャポンの国の人間だそうじゃな。そのジャポンが世界に誇る『正座』という座り方を、今度こそ披露して見せてくれい」
「サーフ、大丈夫?」
「大丈夫さ、ルゥルゥ。これに優勝したら、俺と結婚してくれるよなっ」
「え……」
真っ赤になったルゥルゥを残して、サーフは波を待つ位置に泳いでいった。
ルゥルゥ、アネモーヌ、スープも母親たちが見守る中、絶好の波が、本当にこの季節一番のような波が来た。
もう一度、ボードの上に正座する。今度は下からの支えは一切ない。立つよりずっと難しいが、サーフは先ほどのように両手を左右に突き出し、やじろべえのようにバランスを取りながら波の頂上に達した。
浜辺の見物客がどよめく。
「あれは、いったいどういうポーズかしら……」
と、首をかしげている。
「皆さん、あれは日本の『正座』という座り方ですよ~~~。凜としてカッコいいでしょう!」
母親の園子が、ここぞとばかりに大声を張り上げるが、見物客に反応が無い。
「おばさん、ボクが英語で叫びましょう」
スープがにっこりして園子に助け舟を出した。
「風変わりサーフィン大会をご見物の皆様! あれなる座り方は、ジャポンの『正座』という座り方です! 凜と背筋が伸びてカッコいいでしょう! ジャポンの武士道にも通じているんですよ! ジャポンのサムライの座り方です!」
見物客たちは、
「サムライ?」
「ジャポン?」
「聞いたことあるわねえ。そういえば、しゃっきりして綺麗なポーズだわ」
ざわめきながら、サーフの行方を見守った。
サーフの乗ったボードは波を軽やかに滑っていき―――、他のサーファーたちをぐんぐん抜いて、滑りきった。そして、波を飛び出して空中を舞った。
群衆が叫び、指さした。
(やりおった……)
沖から見ていたアネモーヌとオクトパス爺さんが思わず抱き合った。
第九章 最後に残った宿題
「風変りサーフィン大会、優勝おめでとう!」
スープが乾杯の音頭を取り、その夜、海岸のホテルで祝賀会が開かれた。
「これで私の誇る華道の正座は、世界に知れ渡ったわね!」
はしゃぎまわってお弟子さんたちとハイタッチしまくっているのは、園子だ。
「お袋、いつの間に『華道の正座』になったんだよ」
「文句言わないの。優勝したおめでたい日に」
(あれほどサーフィンに反対してたのは、どこの誰だよ)
苦笑しながらも、サーフは子どものような母親の笑顔を可愛くさえ思っていた。
紫のとばりが降りた夕暮れ、ルゥルゥはいつもの岩場で尾びれを海面に打ちつけたりして待っていた。
サーフが走ってきた。
「おめでとう、サーフ」
「ありがとう、皆のおかげだよ。ルゥルゥ、君が一番、親身になってくれて」
喜びに震えて見つめあった。
「さっき言ったとおり、俺の嫁さんになってくれ」
「ええ、ええ、サーフ。喜んで!」
ルゥルゥの黄緑に光る尾びれごと抱き上げた。
「俺のお姫様」
「私の変な王子様」
おでこをくっつけてクスリと笑いあった。
それから一か月後。
華道深山流の家元の屋敷である。
スーツを着たサーフとピンクの優雅なドレスを着たルゥルゥが横抱きにされて園子の前にいた。
「俺の選んだ花嫁のルゥルゥだ。俺は深山流の家元はやらん。このルゥルゥが家元を継ぐ。だから、お袋、一から教えてやってくれ。華道とそして正座を」
サーフの手が花嫁のドレスの裾をまくり上げた。そこには黄緑色の魚の尾がついていた。
園子はただ、口をパクパクしていた。
「この通り、ルゥルゥは人魚だ。人魚が正座できるかどうかは、お袋の腕にかかっている! これが成功して世界配信できれば、深山流の名はもっと世界の果てまで轟きわたるぞ、お袋!」
「そ、そんな……」
「おっと、反対しても無駄だぞ! 婚約発表は世界配信したから。風変りサーフィンの優勝者のフィアンセにクレームつけたら、深山流の看板はどうなるかな? それと、世界中から称賛されたボードの上の『正座』の評判も」
「や、や、山雄~~~~~!」
地団太踏む園子だった。
「お母さま、よろしくお願いします」
美しい黄緑色のひれを見せて畳の上に座ろうとしているルゥルゥが挨拶した。