[256]授業参観で正座
 タイトル:授業参観で正座
タイトル:授業参観で正座
掲載日:2023/05/27
著者:海道 遠
イラスト:鬼倉 みのり
内容:
来年、大学を卒業する美紗は、母校の青空小学校で二週間の教育実習を六年生に行うことになった。
教室に向かうと、机を並べて靴のまま歩いているカリンという少女がいる。カリンは芸能界を目指しているのでステージ代わりに机の上を歩いているという。
「やめさせなければ」と思った美紗は、カリンの家を訪ねると、父親は元、俳優で歌手の柚原多聞(ゆずはらたもん)だった。
彼は行儀作法を習っている美紗にカリンの正座の稽古をお願いする。

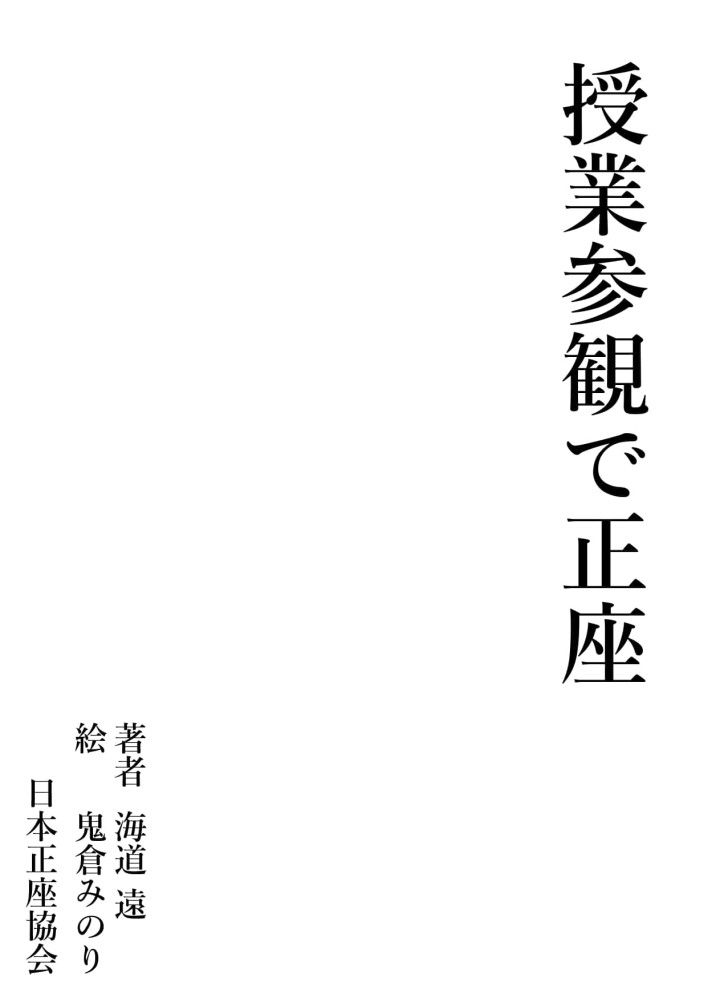
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 教育実習
「何年ぶりだろう?」
校門をくぐると、脇の大きなクスノキが迎えた。
何百歳だろう。小学校に入学する頃と変わっていない気がする。
「もしかして十年ぶり? 小学校を卒業してから、来年、大学卒業予定だから。懐かしい給食の香り! がやがやした子供たちの声と校舎特有の匂い! 匂いは変わってないわ」
美紗は、子供たちの遊ぶ校庭を横切って、校舎に入ると懐かしさがいや増した。
来年、大学を卒業する予定の美紗は、母校の青空小学校で教育実習を行うことになったのだ。
準備は万端整えてきたはずだが、母校の教壇に立つと思うと、昨日から胸のドキドキが止まらない。
職員室に挨拶に行き、若い男性担任に自己紹介した。
「これから二週間、教育実習させていただく、大杉美紗です。宜しくお願いします」
ひょろりとしたメガネの男性教師が答えた。
「六年一組担任の麦野です。よろしく」
温和そうだが、上着もネクタイもよれよれで頼りなさそうだ。
「これから二週間、全教科の授業をしてもらいます。もちろん、僕がつきそいますが。そして、二週間目の午後二時限が参観日になっています。そこで総仕上げということにしたいと思います」
「はい。分かりました」
(最後の日に参観日……。緊張するなあ)
始業ベルが鳴った。
「教室へ行きましょうか。生徒たちに紹介します」
教室へ近づくと、キャアキャアとはしゃぐ声が聞こえてきた。
扉を開けたとたん、ひとりの女の子が並べた机の上を歩いているところが目に飛び込んできた。周りで応援してる女の子たちと、
「先生に言いつけるわよっ」
と、ぶうぶう言ってる女の子たち。その子たちが麦野先生と美紗の入ってくるのを見つけざま、言いつけに来た。
「センセ―――! カリンちゃんたら、また机の上を歩いてるんですよ!」
「これこれ、カリン。机の上から下りなさい」
「だって、これもステージに立つ練習なんですもん」
「もう授業が始まるから、下りなさい」
「ベーだ。パパに言いつけてやるもん!」
カリンと呼ばれたロングヘアの女の子は、麦野にあかんべえをして、やっと床に下りた。
「さあさあ、みんな、席について!」
みんなドタバタして席についた。
麦野先生の連れてきた若い女性に視線が集まる。
「きょういくじっしゅうせいって、あの人のこと?」
「きょういくじっしゅうって何?」
「先生になる前の稽古だって」
「へえ、あの人、先生になるのか」
麦野先生が手を叩いた。
「はい、みんな静かにして! 今日から二週間、授業して下さる教育実習生の大杉美紗先生だ」
美紗が教壇に上がり、震える声で挨拶する。
「大杉美紗です。教師になることを夢見て勉強してきました。みんな宜しくお願いします」
「あんまり美人じゃないわねえ。洋服のセンスも時代遅れだし」
露骨な悪口を言ったのは、さっき、机の上を歩いていたカリンという少女だ。
「柚原(ゆずはら)! 先生に向かってなんて口のきき方だ。謝りなさい」
麦野先生が叱っても、カリンはプイと横を向いたままだ。
(おしゃまさんねえ。クラスにひとりはああいう子、いるのよね)
美紗はため息をついた。
第二章 自己紹介
気をとりなおし、
「はい、では自己紹介してもらいます。先生、皆さんにお会いするの初めてでしょう。何にも知らないからお願いします」
「えええ~~~」
不満のうめき声がする。皆、自己紹介がキライなのだ。
「じゃあ、出席簿順ね。青木りいささん」
三つ編みをした女の子が立ち上がった。
「えっと、青木りいさ。好きな科目は国語。ピアノ習ってます。好きな食べ物はハンバーグとチョコパフェです」
「岩城五郎。好きな教科は、体育。サッカークラブに入ってる。自慢はこの太腿(ふともも)。好きな食べ物は焼肉!」
「植村真可太(まかた)。大将の『まかっち』って呼ばれてる。好きな教科は無い! 好きな食べ物はとにかく肉! あと白いご飯だ」
ふっくらした男の子が胸を張って言った。
「ね~~え、先生は?」
女の子が尋ねた。
「私ですか。好きな食べ物はハンバーグね。趣味は映画鑑賞。大学の他にお作法習ってます」
「お作法ってな~~に?」
「行儀作法のことよ。日本で、どんな時にどんな立ち方、座り方、歩き方をするのか勉強してお稽古するの。特にその中では正座のお稽古が好きです」
美紗はにっこり笑って答えた。
「正座って?」
「ほら、足のしびれるやつよ」
「畳の部屋でご飯食べる時は、正座で食べなさいって言われるわ」
という女の子がいた。
「マジ? 季実ちゃん」
机の上を歩いていたカリンが、いかにも軽蔑の視線で言った。
「正座なんかしたら、足が伸びなくなっちゃうのよ。だから、私、パパから『正座禁止』って言われているの。将来モデルか女優を目指してるんですもの」
「ふうん、もう小六にもなったら、オーディションのひとつやふたつ、合格してるんでしょうね?」
季実も負けじと言い返す。とたんにカリンはふくれた。美紗が口をはさんだ。
「正座したら、足が伸びなくなるなんてことはないわよ。先生は正座のお稽古を初めて十年になるけど、それから股下が十センチ伸びたわよ」
「十年で十センチ? すごい!」
確かに美紗は背が高い上、脚が長い。
「だから、正座のお稽古しても大丈夫よ」
「じゃ、先生、机を並べてステージ作って歩く稽古もしていいわよね? 私、来週オーディションがあるの」
「え、どこからそんな話になったの?」
カリンのペースに乗ってしまったようだ。
「ダメです。机の上を歩くなんて。机に失礼でしょう」
「でも、パパがカリンは絶対に女優にならなきゃダメだって」
「パパ?」
美紗は聞き直した。
「さっきからあなた、パパがパパがって言ってるけど、お父さまが女優になりなさいって言ってるの?」
「そうよ。私のパパはすっごくイケメンで、元、俳優で歌手だったんだもの。だからカリンも女優になりなさいって」
(ステージパパか)
それからやっと自己紹介に戻り、二時間の教育実習は無事に済んだのだった。
第三章 カリンのパパ
カリンは、机を並べて歩くレッスンをやると言ってきかない。
そこで、初日ではあるが美紗は申し出てみた。
「カリンさん。お父さまにお会いしてみたいの。突然だけど今日か明日の夜、おうかがいしてもいいかしら」
「いいわよ。今もいると思うけど」
「そうなの? じゃ、おじゃまさせていただいていいかしら」
美紗は、下校するカリンについていった。
静かな住宅街を歩いていくと、いきなり大声や奇声が聞こえてきた。
「な、何? この声は」
「大丈夫、大丈夫」
カリンはひときわ大きいコンクリートの四角い建物に入っていく。奇声は、その建物の中から聞こえてくる。
「パパ、ただいま! お客さんだよ」
カリンが入っていったのは、どうも住居と思われる建物とは隣接した四角い建物だ。看板に「たもん劇団」と書いてある。
「劇団?」
入口で待っていると、三十代半ばの男性が汗をふきふき出てきた。
端正な顔立ち、身体もがっしりしている。
「お客さんてのは、あんたか?」
「どうも、突然おじゃましまして。私、今日から二週間、カリンさんのクラスで教育実習させていただく大杉美紗と申します」
「先生ですか。宜しくお願いします。何かご用ですか?」
「あのう、カリンさんが、教室の机を並べて歩くと言ってるんですが、お行儀がよいとは言えません。やめてもらうよう言ったのですが、お父さまが勧めていらっしゃるとかで……」
「ああ、そうです。ステージを歩くレッスンにもってこいだと思ったもので」
「いくらなんでも靴を履いたままでは困りますわ」
「でも、常にヒールに慣れておかないとレッスンになりませんので」
しばらくして、着替えたカリンがやってきた。その間に美紗は小さな事務所に通され、父親が紅茶を淹れた。
「学校の教室ではやめていただけませんか」
「ううむ、どうして?」
「どうしてって、机は勉強する神聖なところだからです」
「ステージを歩くのも神聖なレッスンです。それに、カリン本人が机の上を歩きたがるものですから」
父親は娘のわがまま放題にさせているようだ。
「担任の麦野先生はどうおっしゃってるんですか」
「好きにして下さいと」
(麦野先生ったら、ずいぶん気弱なんだから!)
美紗の心の中で怒りの炎が燃え上がってきた。
「麦野先生と相談してまいります」
かなり頭に来ていたが、美紗はそのまま失礼することにした。
第四章 パパの劇団
帰りがけにふと、看板が目に留まった。
「あのう、劇団の看板がありますが、お父さまは劇団を?」
美紗が尋ねた。
「はい、小さな劇団ですが、ここで団員が練習しています」
隣の建物から奇声が聞こえるわけが分かった。
「パパは昔、有名な俳優だったのよ。今はこんな劇団にくすぶってるけど、アカデミー賞候補になったことだってあるんだから」
カリンが得意そうに、父親の腕にぶら下がって言った。
「カリン、黙っていなさい。おしゃべりがすぎるぞ」
「あ、もしかすると、柚原多聞(ゆずはらたもん)さん……ですか?」
「そうです」
それは、美紗も中学生時代からよくテレビドラマや映画でも見ていた俳優の名前だった。
「まあ、柚原多聞さん! よく拝見していましたわ。刑事ものや、恋愛もの、ホームドラマも。いろんな役をされていましたね」
見るからに、素人離れした美丈夫だ。青年の時期を過ぎて、よけい魅力を増したように思える。
「パパは歌も歌っていたのよ」
「そういえば、歌手活動も……。TAMON(タモン)さんというお名前でしたね」
「はい。今は歌手活動は辞め、俳優の後輩の指導に当たっています。カリンは女優になりたいと申しますので、やるとこまでやりなさいと言ってますが」
「そうですか。ところでカリンちゃんのお母さまは?」
「母親も女優でしたが、五年前に病で亡くなりまして。カリンもまだ小さかったものですから、僕が俳優活動を休止して家にいる時間を多くしたのです」
「……そうだったんですか」
勝気そうなカリンだが、クラスの皆の前では弱みを見せないで頑張っているわけが分かったような気がした。机の上を歩くのも精一杯の自己主張かもしれない。
劇団員が稽古している横で、ひとりでバレエのレッスンをしている。
(頑張れ、カリンさん)
美紗は心の中で言って、そっと帰った。
第五章 正座教室へ
それから二日ほど経ったある日、美紗が職員室で帰り支度をしていると、来客があった。
カリンの父親である。ノーネクタイだが、ちゃんと上着を着ている。
「柚原さん、何かご用でしょうか。麦野先生は今、会議中ですが」
「あ、いえ、大杉先生にお話があるのです。突然来てしまってすみません。少しお時間あるでしょうか?」
「はい。大丈夫ですよ。教室へ行きましょうか。もう放課後で空いていますから」
ふたりは教室へ移動した。
柚原は子供用の椅子にキュウクツそうに座った。
「カリンのことですが」
「はい」
「実はあの子はいつも強がっていますが、とても女優になんてなれる子じゃないんです。バレエもだめ、日舞もだめ、うちの劇団に所属していますが、演技もだめ。今度受けるオーディションも絶望的です」
「でも、女優になる気は満々のようですね」
「亡くなった母親と約束しましたから。本当は人様の前で何かやるなんて苦手な子です。器量だってそんなにいいとは思えない」
「柚原さん、それは言い過ぎですわ。カリンちゃんは可愛いですよ」
「ありがとう、先生」
柚原多聞は大きなため息をついた。
「本当にあの子に得意なことがひとつあればいいのです。それを探してやりたいと思っていた矢先に、大杉先生が『正座』を習っておられると知りましたので、カリンにも正座を習わせればいいのではないかと思いまして」
「カリンさんに正座を? それはもう、私の通っている教室は年配の方から子供さんまでおいでなので、大歓迎だと思いますよ」
明るい顔で美紗は答えた。
第六章 失敗
翌日、美紗は正座教室にカリンを連れて行った。
「この子が電話でお話した柚原カリンさんです。師匠、どうぞ宜しくお願いします」
玄関で、カリンは美紗と一緒に師匠に頭を下げた。
師匠は五十年配の和装の似合う美人だ。カリンがきょろきょろして、
「畳がいっぱいの部屋ねえ。椅子はないの?」
「ほほほ」
師匠が笑った。
「正直なお嬢さんねえ。ここは畳ばかりの家よ。もうすぐお弟子さんがたくさん見えて、お作法のお稽古をなさいます。日本のお作法をお習いするところですから、畳ばかりよ」
「なあんだ」
「カリンさん、お師匠さんのお話を聞くにも、ちゃんと正座しなきゃお行儀がよくないわ。私が正座の正式な方法を教えてあげましょう」
「……うん」
「はい、背筋をまっすぐにして立って。そうよ。畳に膝をつけて。スカートをお尻の下に敷いて、かかとの上に座る。そう、それでいいのよ」
美紗が言ったとたんに、カリンは前のめりに転んでしまった。長い丈のスカートを膝で踏んづけてしまったのだ。
カリンの顔が真っ赤になった。
「はい、もう一度やりましょう」
美紗が励ましてもう一度やってみたが、またスカートの裾を踏んでしまい、前にひっくり返った。それに立ち上がる時も裾を踏んづけてしまい、うまくいかない。
「カリンさん、今度からもう少し短いスカートにしましょう」
「だって、今の流行はマキシ丈でしょ。カリン、流行のしか着ないもん。他のは持ってないもん」
ふくれっ面で、カリンは言い訳した。
美紗は正直、身長が高くても小学校六年生の女の子にマキシ丈の洋服が似合うとは思えない。
「じゃあ、カリンさん。うちに絣(かすり)の着物があるから、お貸ししましょう」
師匠が助言した。
「まあ、それはよいことだわ。ありがとうございます。カリンさん、お借りしましょう」
「仕方ないわね」
カリンはふてぶてしく答えて、師匠の後について行った。
第七章 学級会で
師匠の絣の着物を貸してもらって、カリンは正座がスムーズにできるようになった。
「良かったわね。カリンさん。上手に正座ができるようになって」
美紗が褒めると、カリンは紺に赤と黄色の入った絣の着物が気に入ったらしく、
「着物って、小さい時の七五三くらいでしか着たことない。でも、なんだか着心地がいいわ。絣って晴れ着と違ってなんだかいいわ」
照れ臭そうに言った。
「気に入って下さったのなら良かったわ。このまま、お茶の教室にも参加していきなさい。今日はお茶のお作法はいいから」
「はい」
カリンは笑顔で師匠に返事した。
その日から毎日、お作法教室に通うようになり、正座も上手にできるようになった。
「カリンさん。正座の基本は、日舞とバレエにも役立つはずですからね」
師匠が言うと、カリンはすっかり教室を続ける気でいる。
「でも、学校の机の上を土足で歩くのはよした方がいいわね」
「わかりました」
聞き分けよく返事したので、美紗もホッとした。
「クラスの皆も正座をお稽古すればいいのに……」
カリンがそんなことを言いだした。
「だって、まっすぐ座るって、気持ちもしゃんとして気持ちいいんですもの」
「それは、そうしてもらいたいのはヤマヤマですけど」
師匠がクスリと笑う。
第八章 カリンの提案
「そうだ! せめて参観日には、皆、正座して授業を受ければいいのよ。大杉先生の最後の授業になるんだし」
カリンはさっそく学級会の議題に出し、みんなは最初、「えええ~~?」と言っていたが、
カリンが話し出した。
「あのね。カリンのママ、カリンが小学一年生の時に病気で亡くなったの。ママはパパと結婚する前、女優だったの。カリンに立派な女優さんになるのよっていつも言っていたの。劇団翡翠塚(ひすいづか)みたいな」
「劇団翡翠塚? あの有名な?」
「うん。だから、ママとの約束のために頑張ろうとしてたの」
「で?」
「でも、バレエも日舞も全然だめだった。そこへね、教育実習の大杉先生が来られて『正座』を習うことになったの。最初はひっくり返って失敗ばかりしてたんだけど、身体をまっすぐにして、お話を聞いたり読み書きしたりパソコンしたりするとすごく気持ちいいって気がついたの」
「へええ~~」
「ふうん」
幼い頃から家庭で正座教育されている希実は、余裕で聞いている。
カリンの熱意ある説得は、クラスの皆の心を動かした。
「じゃあ、参観日に皆で正座してみるか!」
ガキ大将の「まかっち」まで言い出したので、クラスは全員一致した。
第九章 感激の正座
それから十日あまり、美紗の教育実習期間は飛ぶように過ぎ、いよいよ最終日になった。
給食が終わると、男子が物置からゴザを三十枚くらい運んできて、机を廊下に運び出し、教室の床に敷き詰めた。
そろそろ、保護者が姿を見せ始めた。
廊下に山積みされた机を見て、何ごとかと思ったようだ。
お母さん方がざわざわしている中に、美しいオジサムがやってきた。
「まあ、あの方、どなたですの?」
「ダンディな方ね。どなたのお父様かしら」
「どこかで見たことないですか?」
「そういえば……、俳優の柚原多聞さんに似ていませんか」
「あら、そういえば、そっくりだわ!」
お母さん方のかまびすしいこと。子供のことはそっちのけで、柚原多聞に視線が集まっている。
美紗が様子を見にやってきた。
柚原が、教室に敷かれたゴザを指さして、
「これはいったいどういうことですか?」
「今日の授業参観は、生徒たちが正座で授業を受けることになったんです。姿勢がいいのは気持ちいいって、カリンちゃんが皆を説得したんですよ」
「カリンが? あいつめ、また目立つことを無理して……」
「カリンちゃんは正座教室で上達しましたよ。本当に良いことだと実感して皆を説得したんです」
「そうなんですか? 何をやってもだめなカリンが」
「案外、行儀作法に向いているのかもしれませんよ」
周りのお母さん方は、柚原と美紗の会話を聞いていた。
「今日の授業は正座してやるんですか?」
「はい。皆、寺子屋ごっこなんて呼んでます。すみませんが、お母さま方も、靴だけはお脱ぎになって下さいね」
「ま~~っ! 正座して授業を!」
お母さん一同は驚くやら、呆れるやらしていたが、生徒たちが決めたことなら……と、ひとりずつ靴を脱いでゴザの上に上がった。
いよいよ午後からの授業が始まった。
科目は算数だ。机の代わりに入れた長机で、皆は正座して教科書を広げた。美紗は図形についての授業をした。
生徒たちは皆、姿勢よく前を向いている。
「まあ、うちの子があんなに姿勢がいいの、初めて見ましたわ!」
「しっかり注意を先生の話に集中して」
「なんだか感激しますわね」
お母さん方からそんな声が聞かれた時、全校の参観日風景を巡回しにきた校長と女性教頭がやってきた。
「こ、この教室のゴザはいったい? どういうことかね、教頭」
「何も報告を受けておりませんわ。ゴザを敷いて正座で授業をするなどと」
「楽しそうではないか、しばらく、わしらも正座して授業を聞いて行こう!」
校長の言葉に女性教頭は、呆れながらも付き合った。
突然、校長と教頭がやってきたので美紗は慌てたが、どうにか図形の授業を進めた。
第十章 父兄も正座
ほどなく五時限目の算数は終わった。
生徒たちは、稽古の甲斐あってか平気な顔をしていたが、痺れてしまったのは校長と教頭である。
「いたたたた……」
「立てませんわ、校長!」
「一週間に一度でも正座での授業をするべきだな」
ようやく生徒たちに支えられて立ち上がった校長と教頭は、ふらふらしながら廊下を歩いていった。
「槇原くんのお母さま、いかがでした?」
「正座の授業ですか? とても良かったですわ。子供たちがお行儀よくて」
「ねえ、わたくしたちも正座して参観しませんこと?」
ひとりの母親が言い出した。
「よろしいですわね。授業を受ける者も参観する者も、日本ならではの正座で授業に臨むなんて」
相談がまとまりかけていたが、五時限めからまったく正座していない麦野先生が申し訳なさそうに、
「すみません、担任でありながら正座が出来なくて」
驚く告白をした。
「麦野先生、できないんですか?」
「ええ、僕、この通り細い上にO脚でしょう。安定しないんですよ」
情けなそうに頭をかいた。
「先生、できなければ特訓あるのみです!」
美紗とカリンが両脇からがっしりつかみ、先生を立たせた。
「無理ですよ~~~」
麦野先生は、じたばたした。
第十一章 カラオケ
そこへ、思いがけず女性教頭が戻ってきた。後からやってきた校長が何やら箱型のものを持っている。カラオケだ。
女性教頭がいつになく興奮している。
「お腹に力を入れれば体幹が安定して正座ができるようになりますよ。お腹に力を入れる――腹式呼吸には、歌を歌うのが一番です!」
ひっつめ髪にメガネをかけた教頭は、カラオケが大好きらしく金ピカのマイクを麦野に渡そうとしている。
「歌、何か歌えるでしょ。それと、そこの父兄の方!」
カリンの父親に声をかけた。
「私ですか?」
「そうです。歌手のTAMONさんでしょう。わたくし、ファンでしたの。コンサートへよく行かせていただきましたわ」
教頭の頬は紅潮していた。
「どうぞ、麦野先生に何かの歌の一節でけっこうですから、腹式呼吸から指導してあげてくださいませんか」
「えっ……今ですか」
「最後の六限目は音楽でしょう。ちょうどいいじゃありませんか」
第十二章 「シットダウン・オンディ・アース」
お母さんたちが歓声を上げた。
「きゃあ、TAMONの生歌が学校で聞けるなんて!」
「なんて素敵!」
断り切れなくなった柚原は、頭をかきかき、
「歌わなくなって数年になるんですが、うまく指導できるかな。麦野先生、お願いしますよ」
「な、なんとかやってみます。腹式呼吸ですね」
弱々しい返事をしながらマイクを受け取った。
お母さんたちから、さらに歓声が湧きおこり、手拍子が始まった。
「『シット・ダウン・オン・ディ・アース』よね! TAMONと言えば」
校長が曲を探し出した。
「麦野先生、始まりますよ。下腹に力を入れて」
麦野は一生懸命、画面に歌詞が出るのを見つめた。
「行きますよ、先生! はいっ!」
『♪ 青い惑星のてっぺんで君を見つけた
僕の隣に座るのは君だけ、君だけだ。
青い星のてっぺん。それは愛の花園……
耳元でささやくように歌うと、
周りの眠り花も眼を覚まして歌うよ。
むらさきの光が輝き
触れ合う肩が震える』
柚原のリードで麦野先生は歌った。
「あら、麦野先生、歌がお上手」
美紗もお母さん方も、感心した。夢中で歌っているうちに正座も安定している。
「先生、ちゃんと正座して歌ってらっしゃるわ」
美紗とカリンは顔を合わせた。
お互いにマイクを握っている柚原と麦野先生も顔を見合わせた。
手拍子に夢中になっていたお母さんたちも、皆、ゴザの上に正座した。
「シット・ダウン・オン・ディ・アース、シット・ダウン・オン・ザ・ラブ……ラブ・ユー・オンリーワン、」
柚原と麦野先生はいつしか、肩を組んで歌っていた。
「オンリー・ワン、オンリー・アース、イッツ・マイ・ミューズ……」
美紗も、ふたりと父兄や子供たちにつられて正座したまま歌を口ずさんでいた。
第十三章 正座ができた
歌い終わった時、教室は一体となっていた。
皆からどっと拍手がわき上がった。
「皆さん、ありがとうございます! おかげさまで正座が出来ました!」
びっしょりの汗で濡れたメガネをハンカチで拭きながら、麦野先生は興奮していた。柚原と握手を交わし、それを見た校長と女性教頭も握手を交わした。
六限目の終業ベルが鳴る時、一同は達成感のあまり気が抜けて放心状態だった。
「麦野先生、良かったですねえ」
「ありがとう、美紗先生、柚原さんも」
「こちらこそ、久しぶりに歌えて気持ち良かったですよ、麦野先生!」
「パパ、カッコ良かったよ!」
カリンが鼻高々で、父親にハグした。
「みんな、見たでしょ。こんな素敵なパパを持った私は、机の上を歩いても許されるのよ!」
「カリンさんてば! それはダメですよっ」
美紗が叫んだ。話は堂々巡りしてしまったようだ。
カリンがいきなり美紗をハグした。
「ありがとう、美紗先生、私、女優と歌手と正座のお師匠さんになるわ!」
「欲張りさんねえ」
第十四章 十三詣り(まいり)
美紗の教育実習は無事に終わった。
十日ほどしてから、美紗はカリンに電話した。
「カリンちゃんとお父さまのおかげで、無事に教育実習を終えることができたわ。ありがとう」
「いえ……」
カリンは珍しくはにかんでいた。
「ちょっとお礼をしたいのだけど。カリンちゃんは数えで十二歳でしょう? 私の母は京都の出身だから、神社で十二歳の時に『十三詣り』というのをして知恵を授けてもらったんだけど、カリンちゃんも十三詣りしない? 私が近くの神社に連れて行ってあげるから」
「十三詣り? ふうん、どうしようかな」
「着物で行くなら着付けしてあげるわよ」
パパの多聞は十三詣りと聞いて、記念撮影に早くもワクワクしている様子だ。カリンは行く気になった。
当日、水色に紅白の梅の柄の振袖を美紗に着付けしてもらった。
「今日からは、大人の寸法の着物を着るのよ」
付き添いの美紗は小紋の着物姿、パパは慶事の黒のスーツ姿でカメラを持参している。
鳥居をくぐり、「十三詣り」の旨を巫女さんに伝えると、半紙を差し出して、
「好きな漢字を一文字、書いてください」
と、言われた。
「好きな漢字? う~~ん、悩むなあ」
カリンはさんざん迷ってから、筆で、「座」と書いた。
「あ、ゆがんじゃった! 下手な字ねえ。イヤになるわ」
「まあまあ上手じゃないの。あら、カリンちゃん、『座』と書いたの? 『芸』とか『歌』じゃなくていいの?」
「うん。先生に教えてもらった『正座』、楽しかったもの」
その後、本殿で漢字を書いた半紙と共に、宮司さんがお祓いの祝詞(のりと)を述べてお祓いしてもらった。
カリンは、しおらしく照れた様子で、
「正座の参観日、皆で歌ったこと、小学校最後の学年のいい思い出になったわ」
「私も本物の先生になる前に、あなたたちにお会いできて良かったわ、ありがとう、カリンちゃん。さあ、今度は私が先生の採用試験を頑張る番よ!」
「うん! 頑張ってね、美紗先生。パパと応援してるわ!」
「ありがとう。あなたにも『座』の文字が幸運をもたらしますように」
ふたりはにっこり微笑みあい、多聞パパは、目を細めてその様子を眺めていた。








