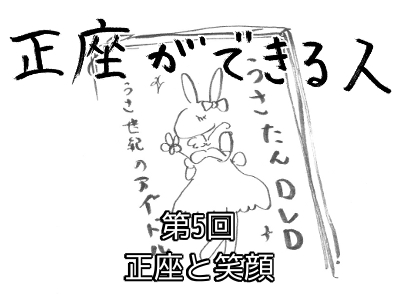[19]ばあちゃんと猫と正座
 タイトル:ばあちゃんと猫と正座
タイトル:ばあちゃんと猫と正座
分類:電子書籍
発売日:2017/04/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:36
定価:200円+税
著者:久木 わこ
イラスト:時雨エイプリル
内容
自宅と会社を往復するだけの毎日を繰り返していた優太。いつものように疲れて帰ってきた夜、とある事をきっかけに亡くなった祖母の事を思い出す。
祖母はいつも正座をしている人だった。優しい祖母が教えてくれた、正座の大切さとはなんだったのか。祖母の教えを思い出すうちに、優太が気づいた事とは果たして……。
販売サイト
販売は終了しました。

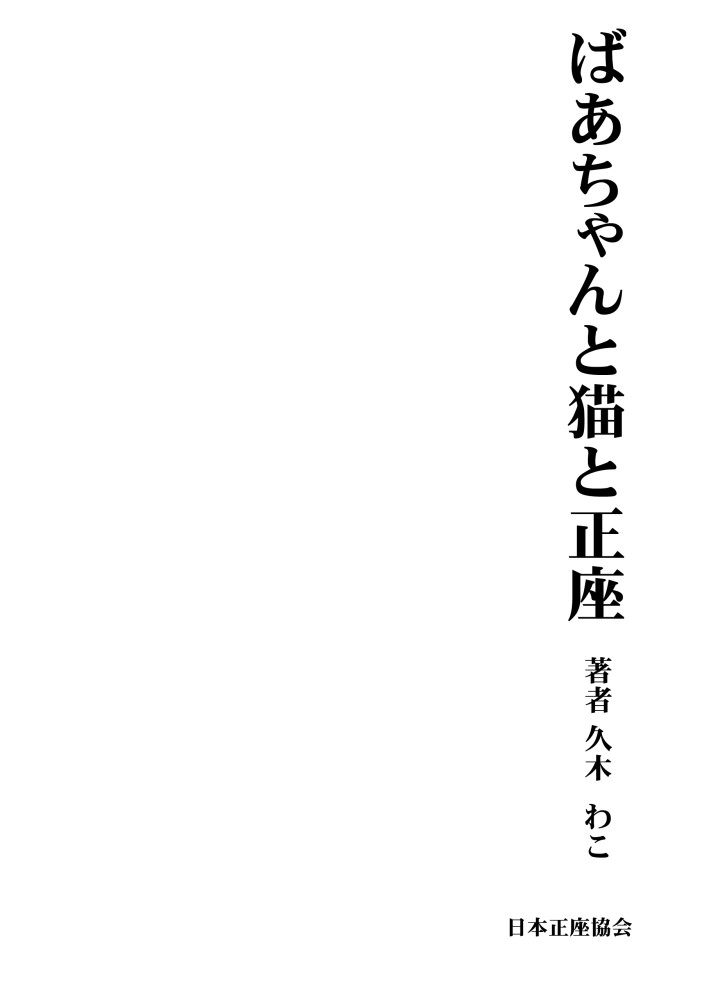
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
乗り込んだ電車は終電のひとつ前だった。金曜日の疎らな車両の中、一駅先へと向かうまでの時間を退屈に過ごした。用もないのにスマホを手に持ったまま、疲れた体はやる気を出さない。座る姿勢はどうにもだらけた。
この車両にいる俺以外の人間は、男と女がそれぞれ一人。男はサラリーマンだろう。ネクタイは緩みかけ、見るからに飲んできた帰りといった風体だ。赤い顔をして、足は前方に広げて投げ出し、だらしなく座席へと凭れかかっている。
足も腕も組んでいる女は、固く閉じた目を開ける気配がない。腰掛けている座席の背凭れに、頭を預けて眠りこけていた。その体は無防備に、やや右側へと傾いている。平和なこの国に住む人間の特権だろうか。隣に置いてあるバッグの口は、盗ってくださいとでも言わんばかりに開け広げてあった。
昨日とも、一昨日とも、目にするものに大した差はない。似たような光景を毎日見ている。もうとっくに飽き飽きしていた。男が二人でも、女が三人でも、カップルが一組だったとしても。深夜前の電車内に緊張感などありはしない。漂うのは寂れた空気。疲れた心地が重くのっしりと覆い被さっている。
結局は俺も一度として姿勢を正すことなく、降りるべき駅には発車からほんの七分で到着した。いつも七分だ。必ず七分で着く。毎日変わる事のない移動時間を、俺はただぼんやりと過ごすだけ。ひっそりとした駅へと降り立ち、ほぼ人のいない改札を抜ける。自宅の方へと向けた足は、どうにもこうにも重かった。
大学を卒業したのが七年前。二十二歳の時だ。その年の四月からは会社勤めが始まり、以来ずっと同じ仕事を続けている。
給料はそこそこ。やり甲斐はまあまあ。労働時間はひたすらに長い。残業代は会社から規定通りに出ている。だからいわゆる、ブラックではない。しかし帰る頃にはくたくただ。仮に早く帰れたからと言って、遊びに繰り出す気力もないが。
駅から自宅のアパートまでは、歩いて大体五分か六分。その途中にはコンビニがある。食料の調達がてら、立ち寄る事も結構多い。
けれど今夜は寄らなかった。今はこれと言って買う物もない。そのまま真っ直ぐ家へと向かい、駐車場を通り過ぎれば玄関はもうすぐ目の前だ。
いつもならば足を止める事はない。ところが今日は、足を止める出来事が起こった。出来事と、そこまで大層に言うほどの事でもないけれど。ただ、猫がいただけだから。どこからともなくひょっこり現れ、俺の目の前を通り過ぎた。
「……」
なんとはなしに、揺れるしっぽを目で追いかける。暗がりを照らすライトの下で、その猫は不意に俺を振り返った。茶トラの猫だ。その辺によくいる猫。じっとこちらを見ているから、俺もその場から動かずに猫を見下ろした。
「……なんだよ」
つい、だった。話しかけていた。俺には猫に話しかける趣味なんてない。だがあまりにも、こっちを見てくるものだから。
それは威嚇か、それとも違うのか。近づけば逃げていくかと思ったが、意外にも猫は逃げなかった。そっと歩み寄り、猫の近くで腰をかがめる。気まぐれに手を伸ばしてみたら、驚くほどあっさりと頭を撫でさせてくれた。
「お前、ノラか……?」
茶トラの猫はとても人懐っこいようだった。ニャアと一声、可愛らしい鳴き声まで聞かせてくれる。いつもならここから真っ直ぐ玄関を目指すはずなのに、俺の足は動こうともしなかった。
その場にしゃがみ込み、猫の頭をやわやわと撫でる。猫はやはり大人しい。
「……まいご?」
猫と目が合ったから問いかけ、問いかけてから自分で自分に顔をしかめた。酔っている訳じゃない。猫と話す癖だってない。けれどここまで来てしまえば、なんだかもうどうでもよくなる。
ゆっくりと、駐車場の端の方へと移動した。俺が歩けばこの猫もついてくる。ついて来そうな予感がしたため移動をしてみたのだが、本当にここまで懐っこい振る舞いをしてくれるとは。
コートが汚れるのも気にならず、駐車場の端の方で縁石に腰を下ろした。鞄もその横に置き、両手で猫を可愛がる。ニャアと再び声を上げた猫。それを見ていてふと、俺の頭の中には古い記憶が流れ込んできた。
子供の頃の事だ。俺は実家にいて、そこにはまだ亡くなる前のばあちゃんもいた。俺が大学に入って一年が経った頃に他界したばあちゃんは、背筋のピンと伸びた、心の優しい人だった。
年相応の雰囲気を纏っていたばあちゃんは、それでも常に元気な様子が窺えた。それはなぜだろうか。おそらくだが、背骨が曲がっていなかったからだろう。ではなぜ老いとともに背骨が曲がる事もなく、常に真っ直ぐと姿勢を正していられたのか。
ばあちゃんはいつも正座をして過ごしていた。それが習慣だった。茶の間のテーブルの前でも、縁側から外を眺めるひと時でも。あとは仏壇の前で、ご先祖様と死んだじいちゃんに手を合わせる時も。
俺にとってばあちゃんは正座の人だった。真っ直ぐと凛々しい、それでいて優しい、正座の似合うお年寄りだ。ばあちゃんの膝の上には必ずと言っていいほど猫が乗っていた。実家では猫を飼っていて、丁度この猫と同じような種類だった。茶トラの懐っこい猫。それがいつも、ばあちゃんの膝の上で安心したように丸まっていた。
2
「ゆうちゃん、こっち来てごらん」
俺に優太という名前を付けてくれたのはばあちゃんだった。名前をくれたばあちゃんは、俺のことを専らゆうちゃんと呼んでいた。
ゆうちゃん、こっち来てごらん。小学生の頃、ばあちゃんはしばしばそう言っては俺を手招きした。正座をしたその膝の上には、大抵いつも猫が乗っている。猫の背を撫でながら、にこにこと優しそうに笑っていた。
「はい。食べなさい」
「うん」
ありがとうと言うと、ばあちゃんは俺の頭を撫でてくれた。そうして手の中に落とされるのは何かしらのお菓子。クッキーだったりチョコレートだったり、饅頭だとか大福だとか。
うちの父親は営業職の会社員で、母親は主婦でもあり看護師でもあった。家族仲は良好だったが、共働きの両親は家を空けている事も多い。だから俺は、必然的にばあちゃん子になった。
ばあちゃんの側に座り、ばあちゃんからもらったお菓子を食べる。それは俺の習慣だった。体育座りでお菓子を食べる俺を、ばあちゃんはにこにこと穏やかに見つめていた。
「ばあちゃん」
「なあに?」
「ばあちゃんはなんでいつも正座なの?」
そんな質問をした時の俺は、あまり正座が得意ではなかった。座っている時には足の甲がゴリゴリと痛くて、足を崩した後にはじわじわと痺れがやって来る。その痺れは痛いながらも普段は味わえない感覚で、子供だからこそ面白いと感じる部分は確かにあった。けれどやはり、苦手だった。どうしてわざわざ辛い座り方をするのか分からなかった俺に、ばあちゃんは穏やかに笑いながら教えてくれた。
「正座はいいんだよ。背筋がまっすぐ伸びるからね」
俺を少し見下ろしながら、ばあちゃんはいくらか顎を上げて背筋が伸びている事を示した。体育座りをしたままばあちゃんの顔を見上げる。その姿にはどこか、威厳のようなものがあったように思う。
「ほら。こうすると胸も張れるでしょう?」
「うーん?」
「やってごらん」
「うん」
ばあちゃんが言う事はだいたい正しくて、ばあちゃんの助言を聞き入れるとほとんどの事は上手くいった。
小学校の国語の授業で、俺は音読をするのがとても苦手だった。それを相談した時に、アドバイスをくれたのはばあちゃんだ。早口にならないよう、焦らずゆっくりと読んでみなさい。そう言って教えられた通りに練習をしていたせいか、俺はクラスで一番の音読が得意な生徒になった。
運動は好きだったけど得意なわけではなかった。かけっこの順位はビリケツから数えた方が早いくらいだった。それをばあちゃんに相談した時は、足元ではなく前を見て走りなさいと教わった。見るのはゴールだけでいい。きちんと姿勢を正して、真っ直ぐ前を見て走りなさいと。言われた通りに実践してもクラスで一番にはなれなかったが、真ん中よりも上くらいには進歩した。俺は走るのが好きになった。
ばあちゃんの言う事は絶対的に正しくて、俺はこの時も素直に正座をしてみようと思えた。そこはばあちゃんの部屋で、床は固い板張りではなく弾力性のある畳だった。しかしそれでもやはり、足の甲はゴリゴリと痛い。もぞもぞと動いて座りやすい体勢を探っている俺を、ばあちゃんは気長にじっくりと待っていた。
「どうだい?」
「うーん……。ちょっと痛い」
「毎日こうしていると慣れるんだよ」
ふふっと笑うばあちゃんはどこか楽しそうだった。俺の背にポンポンと触れ、その動作に促されるようにピシッと背筋を伸ばした。
「ほらゆうちゃん、胸を張ってみなさい。気持ちがいいから」
そうやってばあちゃんは、俺に正座を教えてくれた。
うちの実家は平屋建てで、良く言えば昔ながら、悪く言えば古臭い家だった。さすがに年季が入っているだけあって老朽化も進み、あの古めかしい家にも一昨年にはとうとう全面的なリフォームが入った。
けれど俺が実家暮らしをしていた間は建築当初のままだった。茶の間と床の間が畳を敷き詰めてあるのは言うまでもなく、ばあちゃんの部屋をはじめとして、両親の部屋も俺の部屋もその床は日本人の心たる畳。和か洋かと聞かれれば間違いなく和であり、良く言うモダンな雰囲気とは全くかけ離れた家だった。
しかしだからこそ、正座をするには最適な家でもあったのだ。それはどこか落ち着いた雰囲気を感じ取ることができた。ばあちゃんの側にいる時、正座をして背筋をまっすぐに伸ばしているだけで、物事を穏やかに考える事が出来ていた。
「ばあちゃん」
「はいはい。なんだい?」
「俺ちょっと出かけてくるけど」
「うん。気を付けるんだよ」
高校に入学してからも俺は相変わらずのばあちゃん子だった。しかし小学生の頃のように、常にベッタリしている事はなくなった。変わったのはいつからだったろうか。高校生の時だろうか。中学生の頃だろうか。小学校を卒業するまでは確かに、ばあちゃんの手から毎日おやつをもらっていたのに。
中学校に上がった頃にはすでに、学校の授業が終わってから早々に家へと帰ることは稀になっていた。俺は中学でバスケ部に入部して、特別強い訳ではなかったが友達と過ごす時間は楽しかった。おやつが欲しければ部活帰りに、仲間とコンビニに立ち寄って甘いものを買う。中学生の元気の良さで騒ぎながら道を歩けば、帰宅するのはいつも夕飯ぎりぎりだ。
けれどばあちゃんはいつも、笑顔で俺の帰りを待っていた。疲れただろうと言っては温かい夕食を俺の前に出した。そしてばあちゃんは必ず、俺と一緒に食事をとってくれた。
中学の時には部活が一番楽しかったが、高校に入学してから新たに始めたのはアルバイトだ。家の中にいる時間はさらに短くなった。それでもばあちゃんの顔を見なかった日は一日たりともない。
朝になって俺が目覚める時間には、とっくに起き出していたばあちゃんが朝食の支度をしている。常に正座をしていたばあちゃんは、ご飯のときでももちろん正座だ。背筋を伸ばし、テーブルの前で正座をしているばあちゃんは、物を食べる時の動作がとても綺麗だった。
夜は夜で俺が帰るのを待っていて、笑顔で出迎えてくれた後には温かい夕食を出してくれる。これだけは何があっても変わらなかった。俺はばあちゃんの作ったご飯が好きだった。背筋を正してご飯を食べるばあちゃんを見ていると、それだけで落ち着いた気分になれた。
「優太ってなんかちょっとオジョウヒンだよな」
「はあ?」
「食ってる時の姿勢とかめっちゃいい」
休日に高校のクラスメイトと出かけ、安いレストランで昼飯を食べていた時だった。中学の頃から一緒にいる友人に、そんな事を言われた記憶がある。
姿勢がいいと言われる事は昔から少なくなかった。意識してそうしているつもりはない。ただ周りから見ると俺は姿勢がいいらしい。ばあちゃんにそのことを言ってみれば、きっと正座をしているからだねと。ばあちゃんはあの時、にこにこしながらそう答えた。
ばあちゃんを見て育った俺は、成長する中で正座をする習慣が身についていた。ご飯を食べる時はいつの間にか、ばあちゃんに合わせて正座をしている。お茶の間でテレビを見ていた時にふと、自分が自然と正座をしている事に気づいた時は少し苦笑した。
目の前を飼い猫が通り過ぎれば、正座をして呼んでやるだけでトコトコとこっちに向かってやって来る。俺はそのことを知っていた。そのため猫を抱っこしたいときは、正座をして名前を呼んでやればいい。猫の名前はトラだ。俺は時々正座をしながら、トラの名前を呼んでいた。たとえどんなに些細な事であっても、ばあちゃんの存在は俺にとっての手本だった
俺は正座が似合うばあちゃんの孫だ。両親と過ごすよりも、ばあちゃんと過ごした時間の方が長い。ばあちゃんが教えてくれたことは、俺にとって絶対的なものだった。
ばあちゃんと、ばあちゃんの膝の上で丸まる猫は、日々確実に老いを重ねていった。若い俺にとっての毎日は成長の連続であるが、ばあちゃんと猫にとっては毎日が老いの積み重ねであった。けれど猫は何歳になろうが気ままにのびやかであり、ばあちゃんは何歳になろうとも背筋がぴんと張っていた。食事の時もそれは変わりない。俺はばあちゃんの姿勢を常に目にしていた。自分のお手本であるばあちゃんを、俺はいつも真似ていた。
食事の時の姿勢がいい。これは正座の賜物だ。俺の財産だ。大袈裟なようだけど、全然大袈裟な事などではない。ばあちゃんが教えてくれたことは、俺が守っていくべきものだった。
ばあちゃん子だった俺は少しずつばあちゃんと過ごす時間が減っていったが、頭にあるばあちゃんの表情はいつも笑顔だったし、朝晩に必ず目にする正座姿はいつまでたっても凛々しく美しいままだった。
そんなばあちゃんを残し、俺は実家を出ることにした。進学と同時に家を出て、大学の近くに部屋を借りた。
出発の日、ばあちゃんは玄関で俺を見送った。当時のうちの玄関は正しく古き良き日本の象徴であり、上り框が非常に高い位置にあった。ばあちゃんは客人が来るとまずはそこで正座をして出迎え、近所の牛乳屋の世間話だとか、町内会のお知らせだとか、そういった話を聞くときにも上り框が活用されていた。
親しくも、内と外とで距離を置く。そんな雰囲気がうちの玄関にはあった。だから俺が土間に降り立った時は、ばあちゃんの元から巣立つ時だった。正座をして俺を見送ってくれたばあちゃんの顔は忘れない。外に出ても背筋を正し、胸を張って生きられるように。ばあちゃんは小さかった俺に、丁寧に優しく、根気よく、生きる術を教えてくれた。
そうして大学に入学してから一年後、俺を笑顔で送り出してくれたばあちゃんが死んだ。夏になるにはまだ少し早い頃だった。母さんから知らせを受けて、俺は慌てて実家に戻った。
病気ではない。老衰だ。ここ最近は少し、元気がなかったらしい。それでもいつものように振る舞って、直前まで正座を崩すことはなかったそうだ。床に就いたのは二日前。ばあちゃんはもう、起き上がることをしなかった。
葬儀の最中、俺は正座をして背筋を伸ばしていた。ばあちゃんが教えてくれたことだ。きちんとできるようになったと、胸を張って見せてやらなければならない。だから泣かなかった。前を、見なければならなかった。
葬儀に参列してくれた人は多い。遠くから来てくれた人も、ずっと付き合いのあったご近所さんも、みんなが静かに悲しんでくれた。みんなが俺の代わりに泣いてくれた。泣いてくれたのだ。ばあちゃんはそういう人だった。
俺を送り出してくれたばあちゃんを、今度は俺が見送った。ばあちゃんを見送った次の日、俺はまだ実家にいた。大学もあるから明日には帰らなければならない。正座をして、ばあちゃんの位牌をしばらく眺めていたが、帰る準備をしなくてはと足を立たせた。
子供の頃のように足は痺れなくなった。ばあちゃんの言った通りだった。毎日やっていたから慣れたのだろう。昔は正座をしていた足を崩した直後、ビリビリと襲い掛かってくる痺れに悶えていなければならなかった。うずくまっていれば遊びだと勘違いした飼い猫にじゃれつかれ、あっちに行けと俺は騒いで、それを見ていたばあちゃんは朗らかに笑っていた。
痺れなくなった自分の足を見下ろした時、そんな事を思い出した。しかしそれと同時に別の事にも気が付いた。あの猫がいない。自由で気ままな猫が。ここ最近、猫の姿を見ていない。
「……なあ母さん、トラは?」
「ああ……おばあちゃんの部屋よ。どうしても動こうとしないの」
どこか痛々しい表情をして母さんは言った。それを聞いた俺がばあちゃんの部屋に入ってみると、猫は本当にそこにいた。いつもばあちゃんが座っていた場所で、顔を隠すようにして丸まっている。声をかけても触っても、頑なに動こうとはしない。餌を与えても決して口にはせず、猫はその夜、いつの間にかいなくなっていた。
見つけたのは翌朝だった。場所は裏庭の日陰。ひっそりと、誰にも見つからないように死んでいた。冷たくなった猫を抱き上げた時、気付かないようにしていた事が急に現実となって押し寄せてきた。目の前を滲ませる。涙が勝手に、流れて行った。
ばあちゃんはもういない。あの正座姿はもう見られない。だから猫は、寂しかったのだと思う。こいつはきっとばあちゃんがよかった。正座をしたばあちゃんの、温かい膝の上が良かったんだ。
3
俺がばあちゃんから教わったことはなんだったろうか。俺は今、背筋を伸ばしているだろうか。
暗い駐車場で猫を撫でながら、ばあちゃんと過ごした昔の記憶を一つ一つ辿っていった。正座なんてここしばらくしていない。胡座をかくか、椅子に座っているか、何かに寄り掛かっているか。そのどれであっても姿勢は良くなかっただろう。俺はもうずっと長い間、胸を張って生きていなかった。
「……お前、うちに来るか?」
ばあちゃんの膝の上が好きだった茶トラの飼い猫。あいつにそっくりな茶トラの野良猫に、俺はこっそり問いかけた。
夜の駐車場、それも固いコンクリートの上だ。ここで正座をしてみる勇気はさすがにない。けれど自分の家の中であればできる。もしもこの猫を連れて帰ったら、こいつは俺の膝の上に乗ってくれるだろうか。正座をして前を見たら、今よりも少しくらいは胸を張る事ができるだろうか。
思い出したばあちゃんの顔は相変わらず優しかった。背筋を伸ばしなさい。胸を張りなさい。教えてくれたのは生きるために必要な正座のやり方だ。
自宅前の駐車場で出会った猫は、あのあと近くの動物病院に連れて行った。検診をしてもらうためだ。結果は良好。とても健康だった。ノミの一匹さえもついていない。
迷い猫の届けが出ていないかも、いくつかの機関に問い合わせてみた。あまりにも警戒心がないから、もしかすると飼い主がいるのではないかと思って。けれど該当しそうな情報は出ていない。探している飼い主はいなかった。
俺が住んでいるアパートは、幸いな事にペットの飼育が許可されている。俺は動物の中で猫という伸びやかな存在が一番好きだ。そしてこの猫は、ばあちゃんの膝の上が大好きだったあの猫と良く似ている。だからもう、飼うべきだと思った。
4
「おお、こいつ?」
「うん」
「名前は?」
「トラ」
「わー。ふつう」
「うるさいよ」
とある日曜日。失礼な事を言うのは古い友人である健介だ。普段は地元で生活しているが、近くまで来ていると突然連絡が入ったのがさっきだった。仕事のために出てきたらしい。
久々に会おうかという話になり、猫を飼い始めたことを電話口で言って聞かせた。見てみたいと言ったのは健介。だから駅まで迎えに行って、たったいま自分の家まで戻ってきた。
玄関を開ければトラが必ずお出迎えをしてくれる。知らない人にも警戒心の無いトラは、名前を馬鹿にした失礼な客人にも愛嬌を振りまいていた。
俺が歩けばトラも足元に擦り寄ってくっついてくる。リビングへと入り、背の低いセンターテーブルを目指す。その上には手に持っていたスマホと鍵を置いた。
「適当に座ってて」
「おう」
ついて来ようとするトラを健介の腕の中に預け、俺は一先ずキッチンへ。二人分のコーヒーを用意してリビングに戻れば、健介が胡座をかいた足の上にトラを乗せて遊んでいる。
うちにソファーはない。以前はテーブルの近くに横長のソファーを置いていたが、トラと駐車場で出会ってから早々に処分した。理由はとても単純なものだ。昔の習慣を取り戻すため。テーブルの前に俺が腰を下ろすと、健介は物珍しそうにこっちを見てきた。
「……なんで正座?」
「なんでって?」
「いや……」
正座をしている分、少しだけ健介よりも目線の位置は高くなる。子供の頃、俺はばあちゃんの顔をよく見上げていた。正座をしたばあちゃんは優しくて凛々しかった。
「これだと伸びるだろ。背筋」
「ああ……。そう言えばお前、昔から上品なとこあったよな。食ってるときとかすげえ姿勢よくて」
高校生の時と変わらない健介の物言い。あの頃に俺をオジョウヒンだと称したのは健介だった。思わず笑ってしまえば健介は首を傾げ、それと同時にトラがその腕の中からするりと抜け出した。
やって来るのは俺の元。正座をした膝の上にすっと乗り上げてきた。当然のように堂々とした顔をしているトラを見ると、ばあちゃんの膝がお気に入りだったあの猫のことを思いだす。トラという名前は同じ。あの猫からもらった名前だ。
「これが一番いい」
「んー、正座?」
「うん。トラが気に入ってるんだ」
自分の名前を呼ばれたのが分かったのか、トラはパタリと緩やかにしっぽを揺らした。顎の裏を撫でればゴロゴロと言い出す。ばあちゃんを追いかけていったあの猫も、今頃は優しい膝の上で寛げているだろうか。
「なあ?」
トラに向けて、同意を求めるように聞いてみた。トラは可愛くニャアと鳴き、正座をした膝の上で居心地良さ気に丸まった。