[236]波の音につつまれて座る

タイトル:波の音につつまれて座る
発行日:2022/10/01
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:44
販売価格:200円
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
女子大生の珠希と映美は、梅雨の開けた海に遊びにきていた。珠希が真珠のペンダントを落とし、拾ってくれたのは美大生で父の会社の仕事も手伝う、大浜波遠という耳の不自由な青年だった。
珠希と映美は海岸にある彼のアトリエへおじゃまする。
不思議なことに、波遠は真珠をすべて紅くしか描けないことで悩んでいた。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/4207662

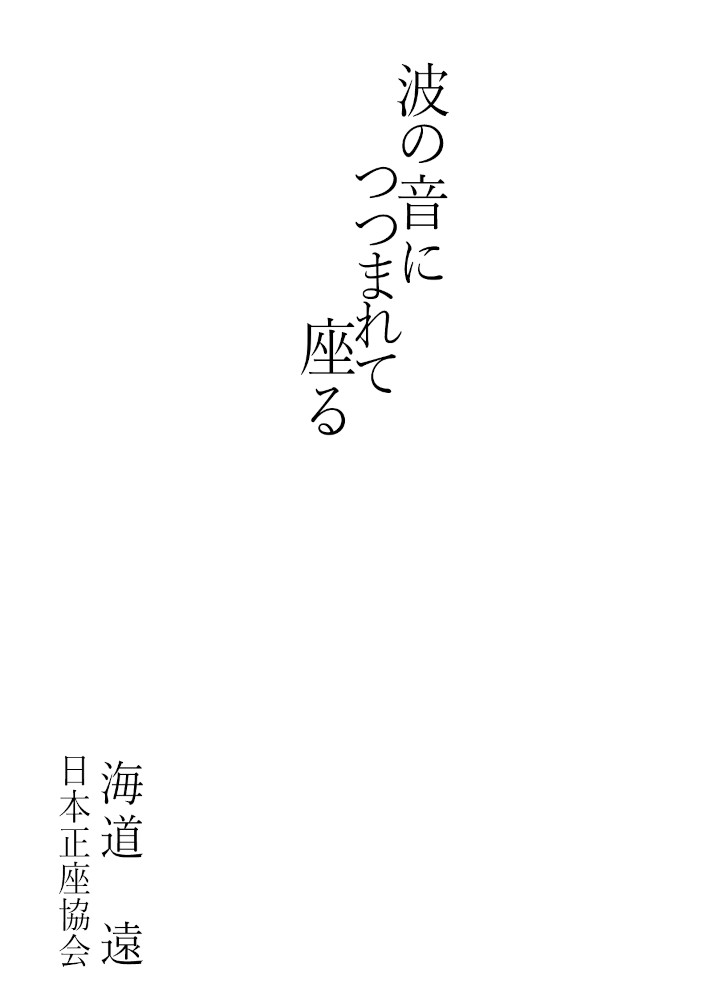
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序 章
波の音と胎内の音は同じだという。
波の子守歌と母親の声が僕の耳に残っている。
不思議なものだ。自然界の音は何も聞こえないというのに。
第 一 章 真珠を赤く描く
梅雨が明けた。
海水浴客でにぎわう浜辺だが、早朝なので人出はまだ少なく爽やかな風が吹いている。
女子大生の珠希は、友人の映美とふたりで波の打ち寄せるみぎわを歩いていた。
流行りの丈の長いくすんだピンクとグリーンのワンピースを着ている。色違いのおそろいだ。珠希はサンダルを脱ごうとした。
「珠希、サンダル脱いだら砂が足にいっぱいついちゃうわよ」
「いいじゃない、ちょっとくらい」
「でも、足を洗い流すところがないわよ~~」
「波で洗ったらいいわ。それとも、映美、泳いじゃう?」
「ええ?」
「実は下に水着着てるのよ」
「私もよ!」
ふたりが急いでワンピースを脱ごうとしていると、珠希が真珠のペンダントを落とした。
後ろを歩いてきた白いシャツの青年が、砂の上に落ちたペンダントを拾う。手のひらの上の真珠を見て顔を強張らせた。
「あ、拾って下さったんですね。ありがとうございます」
ペンダントを落としたことに気づいた珠希が振り向いた。
青年は呆然と海を眺めている。やがて両耳を押さえてうずくまり、手から真珠のペンダントがスルリと落ちた。
「どうしたんですか?」
珠希が何度か声をかけ続けると、青年は顔を上げたが、肩で息をしている。もう一度、海を眺めてから落ち着いたようだ。
「大丈夫ですか」
青年は額の汗を拭いてうなずき、スマホを取り出して打ち始めた。
『僕は耳が聞こえなくてうまく話せませんから、ここに打ちます』
珠希と映美はうなずく。青年は再びペンダントを拾い、
『真珠を握ると、いつもは聞こえない波の音が聞こえるんです』
「波の音が? 私の声は?」
青年は申し訳なさそうに、
『それが……波の音だけしか聞こえないんです』
球希は察してスマホを取り出し、打って画面を見せる。スマホでの筆談というわけだ。
『真珠を握った時だけ聞こえるってどういうわけですか?』
『僕にも分かりません』
青年はようやくペンダントを返し、
『すみませんでした。僕は、美大二年の大浜波遠といいます』
『東珠希です。○大医学部二年生です』
『僕のアトリエがすぐ近くにあるんです。よろしかったら寄っていかれませんか』
『アトリエ?』
『日本画家なんです。駆け出しですが』
珠希と映美は青年のアトリエにおじゃました。
ログハウスのような木造りの広いアトリエには、油絵具の匂いが満ちている。
絵画の中で貴婦人が首につけているネックレスも指輪も、貝殻の中に転がっている真珠も、すべて紅いので珠希と映美は言葉を失った。
『あのう、これは真珠ですか?』
マネキンのモデルは純白のネックレスをしている。
珠希は呆れたように肩をすくめた。
(この美しい真っ白な光沢の真珠を見て、真っ赤な色を塗るなんて、芸術家って分からないわ)
波遠が再び、スマホに打つ。
『不思議に思われるでしょうね。僕は真珠が大好きです。モチーフとしても存在としても愛しています。真珠色にしたいのですが、どうしても勝手に手が動いて紅く描いてしまうのです』
『いったい……』
『亡き母も真珠が好きでした。僕が幼い頃に亡くなったんですが。それに――』
彼は右耳に手を当て、
『真珠を握ると、聞こえないはずの耳に波の音が聞こえるんです。波の音と胎内の音は似ていると言われています。胎内にいる時から母の声は聞こえていました。【美しくお座りなさい】――と』
「まあ、なんて神秘的……」
映美が洩らした。
『母は美しく正座できることを誇りに思っていました。膝に置かれた白い手には、いつも輝くばかりの真珠の指輪が輝いていました。僕が幼い頃から【美しくお座りなさい、そうすればきれいな心になれるから】と繰り返し言って、正座の稽古をさせました』
(まあ……)
珠希たちは顔を見合わせた。
『お母様の思いが強く残ってらっしゃるんですね。でも、どうして紅く塗ってしまわれるのかしら?』
『お母様の肖像画は描かれてないのですか?』
映美が訊いた。
『あります。奥に』
壁には白い布を被せられた大きなキャンバスがある。
『見たいです。見せてください!』
珠希と映美、ふたりそろって声を上げたが、
『またいつかね』
波遠は逃げた。
スマホに着信があった。父の秘書の今井が東京に帰るように呼んだのだ。波遠は表情を引き締めた。
第 二 章 東京の父親
波遠の父親、大浜は珊瑚の取引の会社を経営している。
波遠が東京の本社に帰ると、少し白髪が目立ってきた父親は不機嫌な顔をしていた。波遠が社長室に入るなり苦虫を噛みしめたような顔で迎え、スマホに言葉を送ってきた。
『のんきにアトリエで絵など描いている場合ではないぞ。珊瑚の相場がよくない。損害額を最小限に食い止めろ』
『分かりました』
部屋を出て行こうとすると、もう一度父親から、
『いつになったら美大をやめて仕事に専念するのだ、あんな稚拙な絵が世の中に認められるものか』
以前から美大をやめて会社の仕事をしろ、の一点張りだ。
波遠のこぶしが握りしめられて震える。自分の絵を侮辱されるのは毎度のことだが耐えがたい。
ましてや珊瑚が好きではないのに、その仕事をするのは乗り気ではないが厳格な父親の命令で仕方なくやっている。
その上、好きな真珠は、何故か真珠色に描けないのでますます悩みは重くのしかかってきていた。
夕方近く、仕事が一段落すると、父の秘書の今井が廊下からメールを送ってきた。
『大丈夫ですか、波遠さん。お顔の色が良くありませんね』
『ああ、あまり寝ていないからな。いつもありがとう、今井さん』
『気の置けない私のなじみのレストランを予約しましたから行きませんか』
『ありがとう。喜んで行かせてもらいますよ』
今井は四十歳くらいでとても温和な秘書だ。父親と波遠の橋渡しをしてくれる。歳の離れた兄のような感じだ。
ふたりはこじんまりとしたレストランでゆっくりテーブル席に着いた。
『いかがですか、作品のでき具合は?』
今井は波遠の画家活動まで心配してくれる。
『なかなかうまく描けないな。二足の草鞋を履いていると気が散ってしまって』
ステーキを切り分けながら、苦笑いする。
『でも、波遠さんの作品は注目されているんでしょう』
『真珠を描きたいのに、紅い珊瑚を描いてしまう画家としてね。奇妙に思われてるんだろうな』
『いえいえ、描かれた珊瑚の宝飾品も、右に出る者はないほど素晴らしい出来栄えだと評判だそうですね。私は陰ながら応援していますよ』
『僕の……』
波遠の持つワイングラスがテーブルに置かれた。
『僕の本当に描きたいのは、真珠なんだよ』
テーブルのろうそくに照らされた面差しに苦悩が刻まれている。
数日して、会社の受付から波遠のパソコンにメールが来た。
『東珠希とおっしゃる方が面会においでですが、アポなしだそうです。お断りしましょうか?』
『東珠希……?』
少し考えてから波遠は、返信した。
『お会いします。少々お待ちください、とお伝えください』
エレベーターで一階の受付に降りてきた波遠を見て、ロビーに座っていた珠希が立ち上がった。
「……」
『よくおいでくださいました。どうかしましたか?』
珠希もスマホを取り出し、
『いえ、なんでも。先日お会いした時と違う人みたいだったので。しっかりネクタイを結ばれて……』
『あなたも、髪をまとめておられるので先日とは別人のようだ。外でお茶でも飲みますか』
ふたりは木陰の濃い樹々に囲まれたカフェでひと息ついた。
『お仕事中に、突然すみませんでした』
『いや、僕も、もう一度お会いしたいと思ってたんですよ。アトリエに来て下さってありがとうございました』
スマホを読んだ珠希は、
『もし、よろしかったら連絡先を交換していただけませんか? 打ってから画面をお見せするより楽でしょう』
と返してきた。波遠は微笑んでうなずいた。
『僕もそう思っていたところです。珠希さんから言ってくださって助かりました』
珠希は、アイスティーを飲む波遠をチラチラと眺めていた。
(この人、企業戦士というよりは、やはり芸術家肌だわ。海辺でラフな格好をしていた方が本当の姿なんだわ)
『時間の空いた時に、また僕のアトリエに遊びに来てください』
『あら、何か進展があったんですか?』
『あなたをスケッチしてみたくなりました』
『画学生の常套手段ですね』
『そう思いますか』
『いえ、全然。見るからに【うぶ】ですもの。波遠さんって』
波遠はぎょっとして顔を上げた。
『そういうあなたも、珠希さん。箱入り娘でしょう』
ふたりは笑いあった。
第 三 章 波遠と珠希の悩み
珠希がいきなり波渡の職場に押しかけたのには、わけがあった。両親から縁談を勧められたのだ。しかし、医学部に入学したばかりで、そんなつもりはなかった。
一応、名前だけは聞いた。
珊瑚取引会社社長の息子で、胡渡宗一郎だそうだ。
(「胡渡」って珍しい苗字だわ)
そのくらいの感想しかなかった。突然の縁談に気分が落ち込んだので、何故か波遠に会ってみようと思い立ったのだった。
次の日曜日に、さっそく波遠と海辺で会う約束をした。
浜辺に着くと、磯の岩に座った彼の後ろ姿が見えた。燦燦と降る真夏の陽射しを受けて、水平線をじっと眺めている。
『波遠さん』
メールすると、彼は振り返って寂しげに微笑んだ。
『やあ。波の音を聞いていたんだ』
手のひらには大粒の真珠が握られている。
『立派な花珠(キズがなく美しい真円真珠)真珠ね』
『母の形見なんだ。僕の父はとても厳格な人でね……。母をよく叱っていた。どうして穏やかな母が叱られるのか分からなかった。夢でうなされるほど父の怒鳴り声が恐ろしかった』
『今でもそう?』
『うん……。仕事ができなくて、今度は僕がしょっちゅう叱られている。父の厳しい目には恐れおののく』
珠希は波遠の腕をぎゅっと握った。
「私の両親も厳しいのよ。勝手に決めた相手と結婚させようとしてる」
『え? なんて?』
珠希がメールでなく、ただつぶやいたので、波遠には聞き取れなかった。
『いえ、なんでもないわ。暑いわね。もうお昼に近いわ』
陽が真上に来て焼けつくようだ。ふたりはアトリエへ向かった。
波遠があらかじめエアコンを入れておいたので、生き返ったように涼しさを浴びる。
『見てくれるかい』
奥のキャンバスの布を取り去った。大きな絵だ。何号というのか珠希にはわからないが、大きめのふすまくらいはあるだろう。
そこには和服姿の二十代半ばの女性が正座して、左手の薬指にはめられた指輪を見ている姿が描かれていたが、指輪の石の色だけがまだ塗られていない。
『迷ってるんだ。僕は真珠色に塗りたいんだが、また、ひとりでに紅く描いてしまうかもしれない』
『汗が……。波遠さん、あまり思いつめない方がいいわ』
『指輪の色をどうするかは考えずに、母親の正座姿だけを思い出すと落ち着いて考えられるんだけど……』
『お母様から正座のお作法を習われたんでしょ? なら、私も習いたいわ。教えてくださいますか?』
波遠の瞳が輝いた。
『いいとも。忘れてる所作もあるけど僕でいいのなら』
立ち上がってカーテンの一角を開けた。そこには和室があった。
『まあ、イグサの香りがして素敵な和室ですね!』
『炉も使えるようにすれば茶室に変身しますよ』
珠希は波遠に促され、アトリエのスリッパを脱ぎ、和室に上がった。
『こうして真っ直ぐに立ちます。身体の芯を意識して……』
珠希も傍らに立つ。
『そして、床に膝をつき、スカートはお尻の下に敷き、かかとの上にそっと座る。両手は膝の上に置いて』
『これでいいかしら』
『完璧だよ』
白い歯を見せて波遠はにっこりした。
ふたりはしばらく眼を閉じて瞑想した。彼方から波の音が、珠希の耳に届いた。
『正座したおかげで心が穏やかになれた気がするわ。両親とも冷静に話し合えそう』
目を開けてから波遠が、
『珠希さん、君はどうして医者になろうと思ったの?』
『……中学生の時にね、仲良しだった子が交通事故で亡くなったの。それで、私も命を救う仕事に就きたくて』
『亡くなったご友人が君の道を決めてくれたんだね。人生って不思議なものだね。縁が縁を呼んで……』
『この前、海辺で真珠のペンダントを落としたから、波遠さんと知り合えたんですよね。そして今、ここにいる……』
正座から、自然と波遠の肩にもたれかかった。彼のカタチの良い唇が目の前にあった。珠希は首を伸ばしてそっと唇を重ねた。波遠の手から大粒の真珠が転がった。
窓の外には真っ白な波がしらが見えた。
『真珠に香りがあるとすれば、こんなミントみたいな香りかしら。波遠さんの白いシャツからはそんな香りがするわ』
波遠は窓の外の海に視線を投げた。
(胎内にいた頃の音が聞こえる気がする……)
第 四 章 胡渡宗一郎
今井と数人の部下が待っていた。
『今日は、胡渡氏と十三時から第一会議室で商談の予定です』
『ありがとう。承知しているよ』
胡渡宗一郎は、波遠の父親の会社、大浜産業の大きな取引先の代表取締役である。三十五歳で、彼の父親である社長が今も現役だが、息子の彼が片腕だ。
胡渡り珊瑚という品種がある。
イタリアで生産され、ペルシャを経て運ばれてくる珊瑚のことだ。
日本では、何百年も昔からこのイタリアの珊瑚がペルシャや中国を経由して運ばれてきた。真珠もアラブ海で産出され、同じようなルートで日本に運ばれてきた。似た存在なのだ。
明治時代にこの仕事を始めたとされる宗一郎の祖先にあたる人物が苗字を「胡渡」と決めたらしい。
今井がメールして目配せした。
『宗一郎氏は、父親より貪欲です。わが社を吸収しようという目論見は明白です。気をつけてください』
『気をつけろと言っても、僕なんか彼の前では鷹の前のスズメ同然じゃないか』
あの男と商談があるというだけで、波遠はアトリエに籠もりたくなった。
彼の眼は父親より鋭く、まるで猛禽のようだ。
今にも胡渡宗一郎の策略にはまって、会社を危ない目に合わせてしまいそうだ。もしそうなれば、父親は烈火のごとく怒るだろう。あの遠い日のように。
こめかみがズキズキ痛んだ。
自分という人間は、つくづくビジネスには向いていない。つくづく父親が嫌いだ。あの男、胡渡宗一郎が嫌いだ。つくづく珊瑚が嫌いだ。あの色が嫌いだ。
ビルの窓から見える真夏の空さえうっとうしく思えた。
『しばらくロビーにいる』
『波遠さん! 胡渡さんたちはもうすぐ見えますよ! 波遠さん』
今井のメールを見ようともせず、エレベーターで一階に降りた。
我ながらみっともないとは思ったが、息苦しくて我慢できない。
エレベーターの扉が開いた。
真正面に待っていたのは――珠希だった。
(珠希さん、なぜ?)
「波遠さん――!」
彼女もおろおろして冷静さを失っている。
ガラスを隔てた玄関に車が到着し、胡渡宗一郎が部下と共に降り立った。眼鏡を光らせた面持ちは、相変わらず冷徹で愛想のかけらもない。
波遠の後を追いかけてきた今井が気づいて、玄関へ急いで行った。
(観念するしかないか)
胸のところで両手をもみ絞っている珠希に、波遠は、
『夕方に、また』
とメールした。
今井に出迎えられた胡渡宗一郎が、数人の部下を連れて歩いてきた。
「これは若社長、しばらくでした」
波遠が手を差し伸べて握手を交わしてから、エレベーターに戻ろうとした時、宗一郎が足を止めた。
「珠希さん……。東珠希さんではないですか」
宗一郎が珍しく驚いた様子で立ち止まった。
「胡渡さん! どうしてこちらに?」
「こちらの大浜産業はうちの社がお世話になっていますので。おや? 若社長とお知り合いなんですか?」
「は、はあ」
視線を外して珠希は返事した。
「それは奇遇だなぁ。大浜若社長、この方が、私の婚約者の東珠希さんです。今後とも宜しくお見知りおきください」
わざと自慢するようにロビー中に響くような大声で、宗一郎は満面の笑みで言った。
波遠が耳が不自由ながらも、ある程度、唇の動きが読めることを知っているのだ。
波遠の眼が見開かれた。
(珠希さんが胡渡宗一郎の婚約者――?)
晴天の霹靂とはこのことだ。波遠の大切な母の形見の真珠が砕かれたような気がした。
「胡渡さん、婚約だなんてまだ何も決まっていませんわ!」
「いや、私は決めています。私が決めたことは誰にも止められない。珠希さん、あなたは私の夫人になるのです」
自信満々に言い残して、宗一郎はエレベーターに乗りこんだ。遅れて波遠も乗りこみ、今井が慌てて後に続いた。
第 五 章 母と父の罪
連絡しておいたカフェに、珠希は待っていた。
足早に入ってきた波遠を見るなり立ち上がった。
「波遠さん! 私、あの方と結婚しませんよ! さっきのは胡渡さんが勝手に言ったことです」
途中まで言って、スマホを取り出したが、波遠がその手の上に手を重ねた。
『分かっている。あの男の言うことより君のことを信じるよ』
「波遠さん……」
力の抜けたように腰を下ろした珠希は、微笑んだ。
『それにしても、君の縁談相手があの男だとは、世間は広いようで狭いね』
『知りません。両親が勝手に探してきたんですもの』
『ご両親の眼は確かだよ。あの男は確かに仕事はできるから、君は一生、お金には困らないだろう。ペルシャ産の珊瑚の恩恵で』
『お金儲けのできるだけが、幸せにしてくれる人とは限りません。それに、私は波遠さんのことを――』
少し傾いてきた夏の陽射しが、彼女の頬をよけい輝かせた。
カフェの扉が開いたと思うと、今井が飛びこんできた。
『波遠さん! すぐ社に戻ってください! 会長が倒れられました! 今、救急車を呼んだところです!』
波遠と珠希は、立ち上がってカフェを飛び出した。
病院の雰囲気は、いつ行っても好きになれない。
幼い頃、自分が頭から出血して運び込まれた時の記憶、母親が持病を悪くして見舞いに通った記憶がよみがえる。
今回は父親だ。医者は脳溢血だと言った。
「とにかく安静に。しばらく集中治療室に入ってもらいます」
医者は言った。
ガラス越しにしか、父親と会えない。酸素マスクをあてられて眠っている父親はいつもの威厳ある人とは別人にしか思えない。波遠は廊下の壁にふらふらともたれた。
(今まで会っても、話さないか、言い争いしかしなかった……)
「しっかりして」
珠希が寄り添った。
数日して、意識が戻ったと連絡を受け、今井と病院に駆けつける。医者から少しの時間なら話をしてもよいと言われた。
波遠は恐る恐る、父親のベッドの傍らへ近づいた。たくさんの医療機器が点滅している。
「なみと……」
弱弱しく父親の唇が動いた。波遠は唇の動きを懸命に読もうとした。
「あれには、あちらに行ったら謝らなければいかんな……」
「あれ」とは亡くなった妻のことだ。
「お父さん、気弱なことを」
波遠は、なんとか口を動かして励まそうとする。
「それより、お前にもだ。怒り任せにお前にも当たり散らし、突き飛ばしたはずみに机で頭を打たせてしまい、耳を不自由にしてしまったのはわしだ……」
「……知っていました」
飛び散った血の色が、波遠の脳裏に焼きついてよみがえる。あの色の呪縛から逃れられないので、真珠の色まで紅く塗ってしまうのだ。
「あれは、お前のことを心から愛しておった……。本当に愛した男の子どもだったからな」
「それもうすうす知っていました」
父親の落ちくぼんだ目が少し見開かれた。知っていたのか、と驚いている。
「母も過ちを悔いていたことでしょう。ひと言も言い訳せずにあなたに従っていました。お父さんもさぞ苦しんだことでしょう。すべては過去のことです。僕はあなたを赦します……」
「なみと……」
父親の頬に、一筋の涙がすべり落ちた。
第 六 章 弔いの席を経て
それからしばらくして、父親は息を引き取った。
葬儀は近親者とほんの少しの部下とだけで行われた。近親者は息子の波遠と父親の兄弟たち数人である。
大規模な社葬を執り行うかどうか、社内で会議が行われたが、波遠の知らぬ間に書かれた遺言には「葬儀は密葬で」と記されていた。
あの父と思えない計らいに、波遠は亡くなる際の父親の弱弱しい顔を思い出した。
珠希が「是非に」と、波遠に寄り添った。
住職が読経する間、じっと合掌しながら正座する波遠の姿は美しかった。
親戚の伯父や伯母が焼香の順番を待つ間に、
「波遠くん、喪主として堂々としているわね」
「父親から会社を継ぐことになったんだ。気持ちが張ってるんだろう」
「それにしても、あの正座の姿、母親の姿を思い出すわ。正座姿の美しい人だったもの」
「そういえば」
内緒声でそんな噂をした。
九月の半ばになり、父親の仕事の引継ぎが終わった。四十九日の法要も終わり、ようやく波遠はひと息つけるようになった。
海岸にあるアトリエに行ってみると、人影もまばらになっていた。初秋の海は毎年寂しい。
「波遠さ~~ん!」
視界に紅いものがちらちらするな、と思ったら、ワインカラーのワンピースを着た珠希が海岸を走ってきたところだった。
勢いのまま、波遠の胸に飛びこんだ。
「会いたかった!」
波遠も彼女を力いっぱい抱きしめた。紅いワンピースのせいで、まるで人魚を抱きしめているようだ。
初秋の寂しさがいっぺんに吹き飛んだ。
アトリエで珠希が見守る中、波遠は母親の肖像画に向かった。
『絵を再開するのね』
『うん。上手く描けたら胡渡展に出品するつもりだ』
『胡渡展?』
偶然にも胡渡宗一郎と同じ名前の絵画展だ。やはりイタリア産でペルシャ経由の由来から付けられた名前らしい。
『結果はどうであれ、これが最後の作品にするつもりだ。後は父の遺した仕事一本にしようと思う』
『そう。あなたがそれでいいのなら、私はついていくだけよ。胡渡さんとの縁談は正式にお断りしました』
波渡がスマホを見て振り向いた。
『……わかった』
キャンバスに向かうと、珠希も声をかけられないほど没頭する波渡だ。シャツの胸のポケットには、母の形見の真珠が入っている。
ペインティングナイフや筆がキャンバスの上を何度も舞った。
第 七 章 肖像画の指輪
十月も末になり、木の葉が少しずつ色づき始めた。
大学のキャンパス内を歩いていた珠希は、スマホの着信に気づいて急いでバッグから出した。一緒にいた映美もおしゃべりをやめて待った。
「波遠さんから? なんて?」
「すぐに海辺のアトリエへ来てくれって!」
言うが早いか走り出した。
「あ~~ん、珠希ったら、私とお茶しようって言ってたのに!」
「ごめん! また今度ね!」
「もう、最近、いつもこうなんだからっ」
口では文句を言いながら、映美はやれやれ、と肩をすくめて小さくなっていく珠希の後ろ姿を見送った。
アトリエに着いて、ノックもせずに珠希は飛びこんだ。
「波遠さん!」
もうひとつドアを開けると、波遠はキャンバスを背に奥に立っていた。
「できたのね……」
波遠が一歩ずつ近づいた。
広いふすまくらいの大きなキャンバスに、和装で正座した女性が描かれていた。先月に見た時には指輪の石は、まだ塗られていなかったが、今日は輝く純白の真珠が描かれていた。
「真珠が描けたのね、波遠さん!」
波遠が胸を張って頷いた。
『やっと描けたよ。ありがとう。描いているあいだ中、波の音につつまれていた。君がつつんでくれたおかげで、僕は純粋な胎児に戻れたようだ』
真珠の光沢の気高さに、珠希は魅入った。本物とはまた異なる存在感がある。
指輪をはめて正座している女性の表情も、以前に見た時よりもいきいきとしている。
「す、素晴らしいわ。胸が熱くなるほど感動しているわ、私」
ひざまずいてから自然に正座した。絵画にかしずくように。
波遠も彼女の正面に正座した。そして、胸ポケットから取り出し、珠希の左手の薬指に真珠の指輪をはめた。
「波遠さん……」
「母の形見だけど、受け取ってくれる?」
一生懸命、声に出した。
「はい……。はい……」
珠希の眼から、真珠があとからあとから溢れた。







