[60]海を見つめる正座のモアイ
 タイトル:海を見つめる正座のモアイ
タイトル:海を見つめる正座のモアイ
分類:電子書籍
発売日:2019/07/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:52
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:keiko.
内容
地質学博士、白石美岩子と考古学チームが協力して、イースター島の正座しているモアイ像の調査と考古学的調査が行われることになっていた。
イースター島の海辺に正座し続ける青年の噂が入ってきた。考古学教授、神乃博士の息子、最愛(もあい)だ。さて、美岩子が助手の内賀と共に島に到着してみると、青年は意識ここにあらずという感じだったが、嵐の夜、自分は前世の前世で美岩子の恋人だったと思い出す。
やがて、海底に赤ん坊を抱いたモアイ像が海上に引き上げられることになるが―――。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1436409

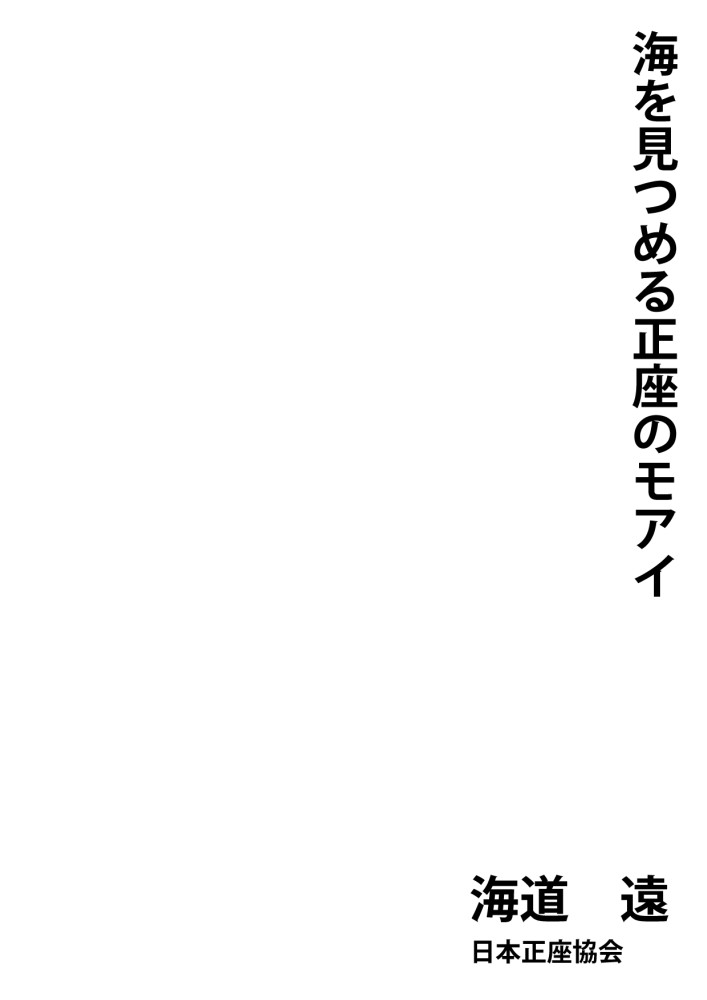
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 海を見つめる男
「神乃最愛? 男なんでしょう? なんていう名前でしょう!」
地質学研究所の窓から水平線を眺めていた美岩子が、キッと後輩の内賀至郎を睨みつけて振り返った。細い銀縁メガネがきらりと光る。
「お父さんが、モアイ像の研究に熱心な考古学者の神乃博士でしょう? 女の子だったら漢字は同じで読み方を『もあ』にするつもりだったらしいです」
内賀も肩をすくめて答えた。
しかし、美岩子のしかめっ面は解けない。内賀はビクビクし始めた。
白石美岩子は、まだ三十歳でありながら、地質学博士なのである。
この夏、父親の白石博士が計画した、イースター島のモアイ像の調査研究に加わることになった才媛だ。
「いくらなんでも、息子に最愛と名付けるなんて変わった人ね」
「あ、でも白石博士だって岩石研究を愛するあまり、お父上が『美岩子』と名付けられ……」
そこまで言って、内賀はアッと口をふさいだ。
美岩子は自分の名前を気に入っていないのだ。顔面が岩のようなイメージを持たれて、今まで親が薦めるお見合いの話や、友人からの紹介が、まとまらなかったという噂だ。
背が高いし肩もいかついている。しかし、しかめ面さえやめれば、たまご型の美人だ。ただ、お堅いから縁が無いのだろう。
いや、そもそも学問に身を捧げているので結婚など考えていないが、名前は、やはり気に入らないと公言している。
美岩子と助手の内賀は他のメンバーより先にイースター島に向かうことになった。
「何か言ったか? 内賀」
イースター島に向かう飛行機の中、隣の席で美岩子は洩らした。
「いえっ何も」
内賀は慌ててぶんぶん頭を横に振る。
美岩子には、ひとつ気になることがあった。
考古学者の青年が何日もイースター島の海岸に座り込んでいるというのだ。それも、正座して。
モアイ像は島に千体近くあるが、正座しているものもある。古い時代のもので、何故、正座しているのかは大きな謎だ。殆どのモアイ像は頭部だけか、胴体は地中に埋もれているか、アフという台座に乗せられているというのに。
それを一日中正座しながら見つめている、変わり者の青年が神乃最愛だということが判り、
「キラキラネームじゃあるまいし」
苦笑している美岩子だった。
(モアイ像のように正座して海を見ている男って?)
彼と協力して正座しているモアイ像の調査をするというのが、計画の骨子だ。
いまひとつ乗り気でない美岩子の横で小心者の内賀は彼女の臨席であることにドギマギを隠せなかった。顔面に吹き出る汗をぬぐってばかり、チラチラと横顔を見ていた。
第二章 イースター島での出逢い
日本からタヒチのファアア空港まで六時間。ファアア空港からイースター島まで六時間。合計十二時間の空の旅である。
タヒチは観光客であふれている。
太陽が降り注ぐリゾート地、どこまでも透き通ったエメラルドブルーの海。
海辺でゆっくりする人々を見て、内賀はよだれを垂らさんばかりだ。
「内賀、私たちは任務でイースター島へ行くんだ。背中を焼きながらいちゃついてるカップルなんぞ、放っておきなさい」
美岩子は愛想のかけらもない言葉を投げた。
イースター島への便が飛ぶまで、美岩子はホテルでパソコンに向かっていた。
ファアア空港からイースター島への便がやっと飛んだ。六時間かかる。イースター島は絶海の孤島なのだ。窓からは紺碧の海が広がっている。白い飛沫をあげてゴジラが泳いでいても不思議ではないような深い深い海だ。
島へ到着すると、村や市場の賑わい(といっても、まばらなものだが)には目もくれず、荷物をしょったまま、神乃最愛が正座しているという海岸へ急いだ。
「荷物くらいホテルに置いてきたっていいでしょう、ハアハア」
内賀が汗をかきかき、美岩子の後を追う。
申し分ない晴天である。青い空と光るグリーングラスと、彼方に見える水平線。グラスには、茶色い馬が草をはんで点在している。
「あ、あれじゃないですか」
内賀が指さす方向を見てみると、海に向かって傾斜面にひとつのモアイ像が立つ。
男はモアイ像の隣に側に座っていた。美岩子が息を弾ませながら到着した。
「……神乃最愛さんですか?」
サファリ服を着て正座していた男が何度か声をかけられると、やっと振り向いた。
三十代半ばだろうか。耳の隠れた髪はボサボサ、ヒゲは伸び放題。洋服はいつ着替えたのか? というズタボロ雑巾みたいになっている。美岩子と内賀は呆然とした。
前髪の隙間から見える青年の眼は虚ろでちゃんと意識があるのかどうかさえ分からない。
「神乃最愛さんですか?」
美岩子が咳をひとつしてから、もう一度尋ねた。
波の音がひと際大きく届き、やがて青年の眼に光がともった。
「ビワビワ!」
突然、叫ぶや青年は立ち上がり、美岩子を両手で抱きしめた。
「な、何を……」
もの凄い力で抱きすくめられ、美岩子は動けない。
「放して下さい! 失礼な人ね!」
ようやく美岩子はこじ開けるようにして、青年の腕から抜け出した。
「ビワビワ……俺だよ。忘れてしまったのか? ずっとここで待ってた……」
「何のことですの? 神乃さん、ふざけてらっしゃるなら許しませんよ」
「ビワビワ……」
もう一度、神乃が抱きしめようとした時、美岩子はやんわりと、しかし強く拒絶した。
「あ……」
神乃はようやく、
「ああ、僕は今、何を……あなた方は?」
「日本から来た白石チームの者です。お分かりになりまして?」
神乃はきょとんとしている。
「どうやら、何もお分かりでないようね。私は白石美岩子と申します。しばらく滞在してモアイ像の研究を共同でさせていただきます」
さっさと握手をすませた。
第三章 ビワビワ
美岩子と内賀にひきずられるように、神乃は白石チームの滞在先ホテルへ移動した。
「とりあえず、シャワーを浴びてさっぱりしてから打合せ致しましょう」
個室に神乃を押し込むと美岩子と内賀もそれぞれの部屋へ収まった。内賀はドアの内側で苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。
夕方、ロビーへ降りてきた神乃はヒゲを剃り、ポロシャツも着替えていたので別人のように身ぎれいになっていた。しかし、目は虚ろなままホテルのラウンジの窓から海へ目を向けて、
「ビワビワ……」
ずっとつぶやいている。
内賀が、そっと言う。
「あの人、大丈夫でしょうか、あんな状態でモアイ像の研究なんてできるんでしょうか?」
「こっちが聞きたいわよ」
美岩子はイライラが止まらない。
「意識がここに無いような人と一体、何ができるの?」
「……とりあえず夕食には、まだ早いわ。しばらくロビーで休憩しましょう。夜には父たちも到着予定よ」
ところが、あれほど晴れていた空に黒い雲が湧き上がってきた。ロビーのシャンデリアに灯りが灯され、彼方の海に三角波が立ちはじめた。
「嵐になりそうね」
風が唸りをあげはじめ、棕櫚の木は頭をもたげ、ホテルは揺れた。客たちが悲鳴をあげた。一回も座っていない神乃が落ち着かなくなった。
「苦しいのか、ビワビワ! ビワビワ、どうした、私にできることは何だ。言っておくれ」
泣き叫ばんばかりにひとり言を繰り返す。
「神乃さん、どうなさったの、落ち着いて」
ホテルは島の内陸部にあるので波が直撃する恐れはないが、次第に大きな雷鳴が轟く。稲光の閃光がロビーの人々の姿を浮き上がらせた。
「ビワビワ、今行く!」
神乃はついにホテルから出て駆け出した。父からキーをひったくるや、美岩子はジープに乗り込んでハンドルを握った。
天地が暗黒に近い中、稲光が一瞬、辺りを真昼にする。
びしょ濡れのまま走り続けて神乃は叫ぶ。
「ビワビワ~~~! 今、行くからな~~~!」
彼の行く先には正座したモアイ像がある。坂を転がり下りようとした背にジープのヘッドライトが当たる。
美岩子がジープを降りた時、目の前は稲妻で真っ白になった。
突然、静寂に包まれた。今までの雷鳴はどこへ―――?
気がつくと美岩子はドロまみれの地面にくずおれるように、正座していた。
「ビワビワ!」
神乃の声に美岩子は我に返った。
「私はいったい……こんなところに座って……」
「ビワビワ、やっと逢えた!」
ガバと抱きしめられた。ラベンダー色の光の中、雷雲が急ぎ足で去ろうとしている。天使のはしごが雲間から何条も降りてきて水平線を照らした。
殆ど顔面が摩耗して表情のわからない正座したモアイ像が、微笑んでいるようだ。
「私……私はビワビワ……」
美岩子の唇がひとりでに動く。
「そうだ。俺だよ、幼なじみのモアイだよ。ビワビワ」
神乃最愛の乱れた前髪から覗く瞳が輝いていて、とても懐かしい光だと美岩子は気づいた。
第四章 思い出の中の少年
青年の瞳を見つめているうちに、美岩子の脳裏に様々な場面が流れた。
幼い頃からいつもモアイ像の側で遊んでいた子。お祭りの時も大人たちに混じって一緒に飛び跳ねた子。大人の手伝いで木の実を採ったり、火を起こしたり、畑で働いている時も手伝ってくれた男の子。
海へ漁にいくその子を『無事に帰りますように』と祈った夜明け……。
いつも心の中でつぶやいた名は……島の石像と同じ、
「モアイ(最愛)だ―――! そして私はビワビワ……」
十歳を越える頃にはビワビワはモアイ少年を熱く見つめるようになっていた。
その頃からモアイ少年は膝を折りたたんで座るモアイ像の側で過ごすことが多くなった。ビワビワも横に座る。
『どうして毎日、ここに来るの?』
『後ろから敵がやってきて波に飲まれていった人を思って座り続ける女性のモアイなんだよ。これは』
『後ろからの敵って、どうしてそんなことが分かるの?』
『この座った像から伝わってくるんだよ。その時の混乱が』
モアイ少年の説明から、戦う人々、逃げ惑う人々、焼き払われる家屋、紅蓮の炎などが目に浮かぶようだ。部族間同士の戦いなのか、西洋からの侵略の手が伸びた時のものか。モアイ少年の前世の記憶から、ふっと美岩子は現実に戻った。
「それで、ここに座ってるモアイ像の恋人は赤ん坊を抱いて海へ飛び込んだのね?」
モアイ少年の姿はかき消え、大人の最愛は頷いた。
「そう。それが前世のお前だ。今は俺の横にいるけどね」
「え?」
「ビワビワ、お前だよ。俺の子を守って敵に追われて海に消えたのは」
「ええっ?」
「お前はこの像の生まれ変わりなんだよ」
最愛は日焼けした胸にビワビワを抱きしめた。ビワビワに最愛の力強い鼓動がどくんどくんと響いた。
「ああ!」
美岩子の脳裏にビワビワだった前世の記憶が怒涛のように甦る。
「さっき、モアイ少年だったあなたが言ったことは」
「俺たちが少年、少女だったもうひとつ前の前世の話だよ」
美岩子の頬がカァッと熱くなった。目の前のむさ苦しかった変人の青年は、昔の、そのまた昔からの恋人だった―――?
「やっと逢えたね、ビワビワ。海を眺めながら待っていたよ」
「神乃……最愛……モアイ……。あなたのこと、神乃さんじゃなく『最愛』って呼んでいい?」
「もちろん、ビワビワ」
最愛は美岩子の肩を抱き寄せ、口づけた。青年の乱れた髪から香ばしい香りがした。雷雲は去り、静かで情熱的な潮騒がつむじのようにふたりを取り巻いた。
第五章 海底のモアイ像の行方
ホテルの白い壁の広い一室。
白石博士は研究チームの全員が席に着くのを待って、マイクを持ち立ち上がった。
「チームの諸君。今回の調査の目的は、海底に沈んでいるモアイ像の実態調査と前後の歴史解明です」
博士は皆の顔を見回し、
「そのために我々、地質学チームと神乃博士の考古学チームが協力して海に眠っているという伝説のモアイ像の捜索を実行したいと思います」
両チームの面々は強く頷いた。総勢十五名だ。
海底にモアイ像が沈んでいることは最愛も美岩子も、勘ではっきり感じているが、チームの前では一切、口を開かず傍観していた。
モアイ像の大体の位置までは、協力して突き止めるが、秘めた事情まで最愛は語るつもりはなかった。
かつて恋人で、赤ん坊まで成したビワビワのモアイ像は、そのまま海で眠らせてやりたい。美岩子も思いを同じくしていた。
中型のクルーザーが海岸に待機し、研究員が乗り込む。
その様子を一望できる草原岩の上に、ひとり睨みつけている男がいた。
内賀至郎だ。
「ああ、くわばら、くわばらとはこのこった」
ツバをペッと地面に吐き、
「あの牝ギツネ、人をさんざんアゴで使いやがって。急に最愛とかいう優男といちゃつき始めて……。俺様の男としての面目は丸つぶれだ」
内賀の卑屈な顔がよけい醜くゆがむ。
「今に見ていろ~~~」
小心者ほど変なプライドは高い。可愛さ余って憎さ百倍というところか。
船上のチームが湧きたった。真下の海底にモアイ像の存在を認めたのだ。
電波で確認すると赤ん坊を抱いて斜めになっているが、足は正座して岩の上に転がっているらしい。
白石博士が大きく頷いた。
「やはり推測通り存在した。これはこのままにしておこう」
誰からともなくデッキに出た研究員たちは海面に向かって黙祷した。
第六章 意外な発言
「待ってください!」
いつの間にか、小さなボートがクルーザーに横づけされて、乗り込んできた内賀がいつにもない大声で言った。
「博士、せっかく発見したのに、このままでは海の中で朽ちてしまうだけですよ」
研究員たちはざわめき、最愛と美岩子も内賀に注目した。
「引き上げろとでもいうのかね、内賀くん」
博士も白い眉を怪訝に寄せた。
「そうです! 貴重な遺産は引き上げて島に展示するんです! 観光客をもっと呼び寄せられますよ!」
「は……?」
「例えば日系人の多いペルーの観光会社に売り込んでツアーを組んでもらうんです。日本特有の正座をしているモアイ像なんて、丘の上の一体と、この海底のモアイ像だけですよ。どんなに希少価値があるか」
「何をするつもりだね、内賀くん」
「もちろん、研究費の寄付集めです! 引き上げた我々が見物料をもらうんです。貴重なモアイ像は有効に使わなければ」
「正気なのか?」
美岩子が叫んだ。
「いつの間に、そんな貪欲になったんだ、内賀くん」
美岩子の言葉など聞こえなかったように、内賀は身を乗り出し、
「そうだ! ペルーから日系人の観光ツアーが来たら、モアイ像を正座で鑑賞会、やりましょう!」
博士が口を挟もうとしたが、彼の弁舌は止まらない。
「博士、モアイ像を愛して長年研究してこられたのでしょう。丘の上のモアイ像と海底のモアイ像が別れ別れで可哀想だと思いませんか? 二体とも正座しているから、きっと同じ時代に同じ種族が作ったんでしょう」
研究員たちは、しばらく黙り込んでいた。
「そうだな……」
最愛が沈黙を破った。
「ふたり、離れ離れじゃ可哀想だな……」
「最愛……」
「内賀くんの言う通り、ペルーの日系の方々も日本人ならではの正座という座り方を見直してくれるだろう」
このイースター島の祖先は台湾付近から太平洋を渡ってきたと言われている。もしかして、日本人に近い血が混じっているかもしれないという説まである。
「正座は日本人の誇りを示す座り方だ。それをペルーの日系人の方々が知ってくれれば……!」
最愛も話しているうちに熱を帯びてきた。
「最愛、本当にそう思っているの」
美岩子は最愛の瞳の輝きに驚いた。先ほどまで前世のモアイ像たちは静かにしておこうと言っていたばかりなのに。
「見物料がほしいわけじゃない。僕も考古学をやってきて僕たちのことは別にしても、正座したモアイ像というものにとても興味がある。正座しているところをたくさんの人に見てもらいたい気持ちはある」
「前世の私たちを見世物にする気なの?」
美岩子は真っ青だ。
第七章 モアイ、海上へ
とんとん拍子に話は決まり、海底のモアイ像は引き上げられることになった。白石博士までも日本人の誇り、「正座」という座り方に心を動かされたからだ。
美岩子は依然として反対だったが、周りの皆が内賀を筆頭に計画を進めはじめ、口を挟む余地がない。
この影響で日本チームの滞在期間は大幅に伸び、まず海底のモアイ像を引き上げるクレーン車が手配され、人手も増やされた。
そして、ついにモアイ像は何百年かぶりに海上へ引き上げられ、太陽の光を浴びた。高さ三メートル。重さ十トン。海中にいる間に藻だらけになっていたが、確かに胸に赤ん坊らしき小さな人型を抱いている。
ひとつのホテルが出資して丘の正座モアイ像と並べて設置することになった。設置場所は、元々、正座モアイ像のあったラクララクの丘に文句なく決定した。
古代からのモアイ像は、モアイ工場からどうやって運ばれたか、さんざん議論されたが、今回はクレーン車の活躍でふたつのモアイ像は、人力で苦労することなく並んで丘に立った。
「これで本当に再会できた実感がするよ、ビワビワ」
ずっと真剣に作業を見守っていた最愛は、満面の笑みを浮かべて美岩子を抱きしめた。
(本当にこれで良かったの?)
美岩子の表情は曇っている。
ジープで待機している内賀の唇が憎々し気な笑みを浮かべた。
内賀は人が変わったように営業マンになっていた。さっそく南米へ飛び、ペルー、コロンビア、チリの旅行社にイースター島ツアーの新しい見ものをアピールして回った。その他の日系人の多い国も候補として挙げ、契約を取り付ける電話を何本もかけたのだった。
「これで、たくさんの人に正座したモアイ像を見てもらえますよ」
イースター島に戻るなり、意気揚々と報告する内賀は、今まで美岩子の背後でビクビクしていた男とは別人のようだ。
「内賀くんにこんな才覚があろうとは思ってもみなかったよ」
白石博士も相好を崩して一同を見回す。
しかし、いくら見物人が増えようと寄付金が集まろうと、手放しで喜べない美岩子だった。
(こんな大騒ぎにしたくない……、せっかく最愛と再会できたのに)
その最愛が乗り気なようなので、自分の気持ちを言えないのである。
一か月後、早くも第一回目のツアーが決まり、正座モアイ鑑賞会が行われることになった。ペルーの数社の観光会社の募集人員は即、埋まっていった。
第八章 モアイ像、倒れる
絶海の孤島の彼方、水平線に静かに真っ赤な夕日が沈んでゆく―――。
美岩子はひとり、オレンジ色に染まりながら二体のモアイ像の周りを歩いた。
二体ともアフと呼ばれる石の台座に乗っている。古くて顔面の保存状態は良くないが、なんとなく二体とも笑みを浮かべているように見えなくもない。
原材料の石が柔らかい性質なのに、よくここまで保たれた、と思わずにいられない。
さて、いよいよペルーからの最初の観光客が空港に到着した。
ホテルに荷物を預けるや、彼らは一斉に二体のモアイ像のところへ向かった。数十人はいるだろうか。
「本当だ、変わったモアイ像だねえ、他のと全然違うよ」
「かなり古い時代のらしい」
「顔も他のみたいに長くないね」
「足を折り曲げて座っているね。昔、日本からペルーへ渡ってきたお祖母ちゃんと同じ座り方だ」
「正座というんだそうですよ」
老若男女、観光客のおしゃべりが彼らを見守る美岩子と最愛にも聞こえてくる。
「なるほどね、南米へ渡った日本人移民たちは、畳のないところでも、しばらくは正座していたようだね」
最愛は遠い眼をして当時の移民たちに思いを馳せているようだった。
「不思議なことよね。千年前後も前に造られた正座モアイ像と百年前に南米に渡った人たちが同じ座り方をしているなんて」
その神秘には、美岩子も感激せずにはいられない。そっと最愛の肩にもたれかかり、モアイ像のシルエットを眺めた。
―――その時だった。
海底から引き上げたモアイ像がぐらりと動き、ゆ~~るりと傾いていったのは。
「キャ――――!」
「わぁぁっ!」
観光客から悲鳴が上がった。
蜘蛛の子を散らすように観光客たちは、巨大なモアイ像の身体から飛び離れた。
モアイ像は斜面に轟音と共に倒れ、真っ二つに割れて転がった。
ひとりの女性が片足を抑えて悲鳴をあげた。すぐさま、観光社のガイドと見張りにたっていた研究チームの何人かが女性に駆け寄る。
美岩子と最愛も俊敏に動いた。
女性は片足を押さえて座り込んでいた。右足と岩が接触したようだ。病院から迎えの車が来た。ホテルからも野次馬が集まってきて、静かで小さな島は大騒ぎになった。
「なんてことだ……。設置には十分、安全を期していたはずなのに」
最愛は呆然と唇をかんだ。
研究チームのホテルの一室である。白石博士の表情も重く沈んでいる。
「ケガ人は三人。三人とも軽傷で、犠牲者が出なかったのは不幸中の幸いだ」
「設置を担当した業者のやり方にも確認を急がせています。博士」
最愛が白石博士に報告した。苦しそうな表情である。
(私の……前世の前世だったビワビワのモアイ像が割れてしまった)
美岩子は、まるで自分の身体の一部を失ったかのような気がした。
(内賀にすべてを任せてしまったのがいけなかったんだ)
「その内賀はどこへ」
「騒ぎに紛れて島を脱出したらしい」
「どこかに隠れているのかもしれない。あんなにお金の亡者になるなんて」
(今まで従順に、黙々と助手を務めていた男だったのに。海底のモアイ像を知ったとたんに大胆な行動をとり始めるようになって)
「金の亡者だけだったんだろうか?」
最愛がぼそりとつぶやいた。
「同じ男だから分かるんだ。彼の、君を見る眼は……熱く滾っていた」
「え……内賀が……?」
美岩子は改めて最愛を見上げた。
第九章 今度こそ
ケガをした観光客三人は少し遅れてペルーへ帰っていった。
しかし、イースター島でのモアイ像の事故はテレビやネットによって世界中に知れ渡ってしまった。海から引き上げられたモアイ像も三つに割れてしまい、研究チームには絶望の色が満ちていた。
「内賀の観光ツアーに賛成はできなかったけど、こうなってみると残念だわ」
浮かない顔の美岩子である。
「君らしくないぞ、ビワビワ」
最愛が白い歯を見せて眩しく笑いかけた。
「正座したモアイ像はもう一体あるじゃないか」
(あっ……、確かに。元から最愛が見つめていた像がある)
「あのモアイ像を南米の人々に見てもらえば、再び自分の祖国を味わってもらえるわね」
最愛は力強く頷いて美岩子の希望に満ちた視線を受け止めた。美岩子も、モアイ像を観光客を通して世界中の人に見てもらう決心がついたのだった。
そしてチームの会議で最愛は提案した。
「観光ツアーは続行しましょう! お金もうけが目当てじゃありません。正座したモアイ像を南米の日系の方々に……いえ、世界中の人たちに見てもらい、日本の正座姿を知ってもらうんですよ。今度こそ、百パーセントの安全対策をして!」
博士や研究員たちは、しばらく最愛を見つめて、しわぶきひとつ立てないでいたが、やがて誰からともなくバラバラと拍手が聞こえ、全員から力強い拍手になっていった。
再度、モアイ像見物のために青空の下、整備工事が始まった。最初の時よりも研究チームの面々も真剣だ。
そんな時、内賀をチリの首都、サンチヤゴから車で一時間の港湾都市バルパライソで見かけたとの噂が入ってきた。
最愛と美岩子は、すぐさまサンチアゴに向かった。
サンチアゴは高層ビルの立ち並ぶ立派な都市だ。その第一港湾都市であるバルパライソもまた、近代的な人口過密な大都市だ。
そこから更に、南へ下った小さな港を割り出した。インターネットのおかげで情報が入る。
寂れた町。灰色の海と空。かなり南だ。
ネットで内賀の人相を拡散してみると、いくつか情報が特定されてきた。町の北の外れで日本人らしき三十歳くらいの男を見かけると。
ふたりはレンタカーを走らせた。
砂漠の中のレンガ造りのまばらな家々が埃っぽく並んでいる。
一軒だけ、酒場がある。カウンター席に真昼間から酔っぱらって、うつぶせになってる内賀がいた。痩せた背中がよけいうなだれて見える。
「ど―――せ、俺あ、何の取柄もないつまんねえ男だよ。ふん。ざまあみろ、お前たちの計画なんかぶっつぶしてやったさ」
「何を言ってるんだ、この外国人」
「悪酔いしてるんだよ、放っておきな」
マスターや他の客も迷惑している様子だ。
そこへ最愛と美岩子は入っていった。
「内賀……内賀至郎くんだろう」
内賀は埃まみれの顔を少し持ち上げた。空っぽのグラスを握りしめ、
「へん、こんなところまで追っかけてきやがったか」
「そりゃ、追いかけてくるよ!」
怒鳴りつけるなり、美岩子がカウンターから引っ剥がすように彼の首ねっこをつかんだ。
「内賀、あんた、なんてことをしてくれたのよ! 見物人にケガを負わせるなんて。苦労して海から引き上げたモアイ像が泣いてるよ。かなりズサンな設置業者だったそうじゃないか」
喰ってかかる美岩子に、内賀は苦笑で応じた。
「珍しがって、すぐにやってくるからさ。俺の思うツボになりやがった」
「なんだって?」
「モアイ像は壊れるわ、ツアーは大失敗、俺の最後の細工が良かったんだな、モアイ像が倒れやすい仕掛けをやっといたのさ」
「内賀っ!」
美岩子はぐでんぐでんになっている男を自分の方に向かせた。
「あんたがこうなるようにしたってこと? ケガ人まで出してしまったんだよ、なんてこと考えるんだよ、内賀。あんたはずっと真面目に助手を務めてくれてたじゃないのっ」
「言うことをきいてたのは……あんたに気に入られたかったからさ」
「な?」
「それを、風呂にも入らずにずっと海を眺めてる変人男にのぼせちまいやがって……」
「内賀……」
襟首をつかんでいた美岩子は手を離した。
床に転がった内賀はわめいた。
「さあ、煮て喰うなり、焼いて喰うなり好きにしてくれ」
ひとしきりわめくと、いびきをかいて眠ってしまった。
それまで黙って見ていた最愛が、歩み寄って内賀の身体をよいしょ、と肩に担ぎあげた。そしてレンタカーの荷台に乗せた。
「最愛! そんな男を連れて帰るの?」
「……落ち着いて、ビワビワ」
穏やかな表情で運転席に座る最愛に「ビワビワ」と呼ばれて、美岩子は引きさがる。
「彼には自分の犯した罪を償ってもらわなければ。知って裁かれなければならない。ケガ人まで出したんだ。僕の―――赤ん坊を抱いたモアイ像まで破壊されたこともある」
最愛の瞳の奥に、自分よりも激しい憤怒の炎が燃えていることを、美岩子は見てとり、助手席に乗り込んだ。
「あのモアイ像は割れてしまったけれど私がいるわ」
「そうだな、ビワビワ」
車はバルパライソの町に向かって発進した。
第十章 母は島の人
三か月後である。
「おお、立派に修復できたのう」
丘を降りながら相好を崩したのは、最愛の父、考古学教授の神乃である。ごま塩のあごひげを生やした紳士は息子を見て駆け寄ったのだ。
「父さん、ありがとう。来てくれて」
「話に聞いて心配していたが」
イースター島の一角には正座したモアイ像を見物する場所が甦っていた。アフ(台)の上に左側には以前からのもの、右側には割れた赤ん坊を抱く、海から引き上げられたモアイ像が置かれ、周囲には地中深く打ち込まれた強固な柵が設置されているので、直に触れることはできないが、地震が起こってもモアイ像の下敷きになることはなさそうだ。
観光客たちは「正座」という座り方を見て、珍しがったり、懐かしがったりしている。
「うむ。順調なようだな」
神乃教授が頷いたところへ、最愛は美岩子を前に押し出した。
「父さん、この人が美岩子博士だ」
「ビワビワさんかね」
美岩子はいつもの男勝りはどこへやら、はにかんで教授と握手した。
「初めまして、教授。教授のことは父からもよく……」
「しっかりした女性だな、最愛。母さんが生きていたら喜んだろうに」
最愛の母親は、実はイースター島の島民だったことを教授は打ち明けたのだった。若い頃から研究に来ていた教授と現地民の娘が結ばれ、生まれたのが息子の最愛だと。
「最愛さんから聞いています」
美岩子はにっこりして答えた。そして話を戻し、
「先日の事後処理は、ケガ人の治療費だけで、訴えられることもなく世界遺産損壊の罪にも問われずにすみました」
「その、事故を計画した青年はどうなったのかね?」
「内賀至郎ですか。彼も心から詫びて、修復作業を手伝ってくれました」
「それでいいのかね、美岩子さん」
「ええ、最愛さんがそれでいいとおっしゃったので」
最愛と美岩子は顔を見合わせた。
そして、手をつないで緑あふれる丘を登り、待たせてあった馬二頭にそれぞれまたがった。
草原を越えて島の反対側の海岸に出る。馬は砂浜の上をサクサクと歩いていく。
水平線がコバルトブルーにくっきり見え、波の音が耳を打つ。背後には、アフに並んだモアイ像たちのシルエットがずらりと並ぶ。
「最愛、あなたのお父様とお母様も、そして、その昔―――。ビワビワと夫もこうして海を眺めたんでしょうね」
「水平線の向こうの向こうに住む民族に思いを馳せたのかもしれないな」
「正座をする民族、私たちの」
ふたりは神秘を感じながら、熱い視線を絡ませた。








