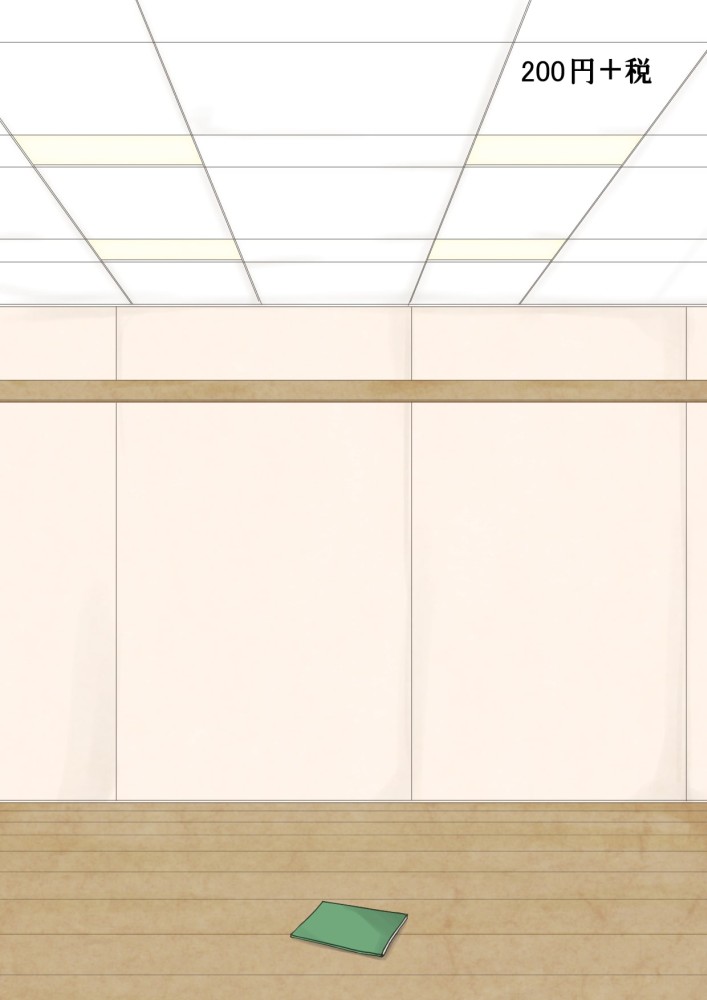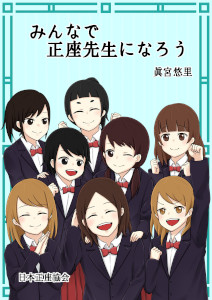[46]背筋正して心見つめて
 タイトル:背筋正して心見つめて
タイトル:背筋正して心見つめて
分類:電子書籍
発売日:2018/03/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:44
定価:200円+税
著者:空色大福
イラスト:鬼倉 みのり
内容
高校の演劇部に所属している藤野亜希子は、ある公演で希望している役から降板させられる危機に直面する。亜希子が近所に住む祖母に相談すると、返ってきたアドバイスは「姿勢を正して座る」ことだった。亜希子は想像していなかった祖母の助言に驚いてしまうが、物は試しと正座を始めてみる。
果たして亜希子は、正座との出会いで何を思いどのように変わっていくのだろうか。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1251277

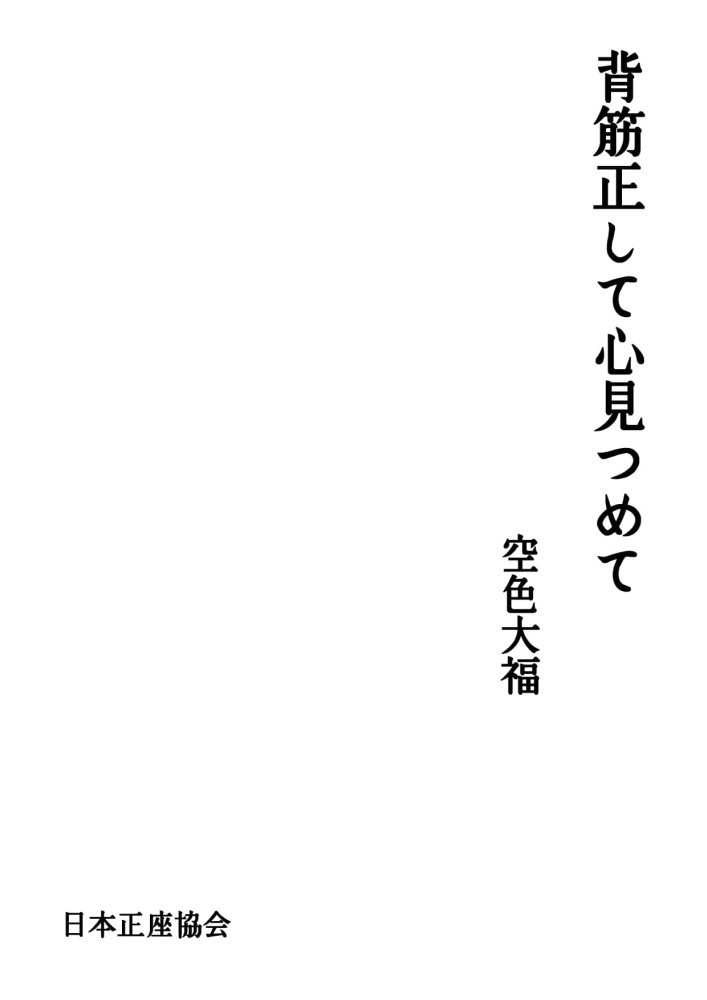
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
私、藤野亜希子は、高校入学時に当時の三年生が主体となった新入生歓迎公演を見て演劇部に入部した。
舞台に立っていた先輩たちは、大げさではなくキラキラと輝いて見えて、自分も人の心を動かせる舞台を作りたいと思った。
それから一年半が経った二年生の秋、先輩たちが最後の文化祭を終えて引退し、私たちが部活の中心となった。
今は冬休みに行う公演のため、稽古をしながら役者やスタッフを決めるための審査をうけている。今回の公演は新入生たちが主役を務めるため、私はサポートとして準主役に立候補した。
演技が悪ければ先輩だろうと容赦なく落とされるため、先生の前で行う稽古は毎回体が震えるほど緊張する。
「……そこまでっ!」
先生の鋭い声と手をたたく音が稽古場に響いた。
演技をしていた生徒たちが、それぞれの役柄から普通の高校生の顔に戻り、舞台に見立てた部屋の一角からピリピリと張りつめた空気がフっと緩んだ。
体の緊張が緩むと、服の下でどっと汗が噴き出してきた。
「それじゃ、個別に講評していくぞー。呼ばれるまでは各自休憩しておけ」
先生の言葉を合図に、生徒たちは部屋のあちこちに散っていった。私も、荷物を置いていた壁際に向かい、タオルと飲み物を取り出す。床に腰を下ろして水分補給をしていると、ジャージ姿の大柄な女子が大股でこちらに向かって歩いてきた。
彼女は霧島朋。二年間同じクラスで、私と同様高校入学と同時に演劇部に入部した、部活仲間であり、一番の友人だ。
彼女は、大道具や照明操作、さらに台本制作など、裏方の作業をすべてこなせる万能選手だ。今日もジャージの腰に道具袋を下げ、手には照明配置図を持っている。
「よう、お疲れ」
朋は私の隣に腰を下ろすと、無断で私のペットボトルを取って、美味しそうに喉を鳴らして中身を飲み干していく。
「いやいや、一言断ってもよくない?」
私が指摘すると、朋はこちらに視線をよこすが、ペットボトルからは手を放さない。
「ん? あぁ、悪い悪い。飲んでいい?」
「もう飲んじゃってるじゃん……」
「悪かった、悪かったよ。道具作りで汗かいちゃって喉乾いてたから、つい、な」
「ついじゃないよ。すぐそこに自販機あるんだから、自分で買ってきなよ」
朋は悪びれる様子もなく、中身を喉に流し込んでいく。
よく見ると、朋の首筋や額にはうっすらと汗が浮かんでいる。頑張って作業していた証拠を見ると、責める気持ちが消えていった。
彼女たちが協力してくれなければ公演を行うこともできない。気持ちよく作業してもらうためと考えれば、ドリンクの一本くらい安いものかもしれない。
「調子どうよ? 今回は準主役狙いだっけ? なかなかセリフ多いみたいじゃん」
ペットボトルを空にした朋は、私の台本を手に取ってペラペラとめくり始めた。
「新人の子が主役に立候補してるからね。去年は先輩方が譲ってくれたし、今年は私の番かなって思って」
「おっ、さすが先輩っすね。マジリスペクトっすよ」
茶化すような口調で言われて、私の頬がカァっと熱を持つ。
「ふふふっ、素直な反応しちゃって、かわいいよ」
朋はからかうような口調でささやくと私の頭をガシガシと乱暴に撫でまわし、楽しそうに大きな笑い声を上げた。
彼女は私がうろたえたり赤面したりする反応が楽しいらしく、一年生のころから何かというと私のことをからかって遊んでいるのだ。
「亜希子さんの名演には、アタシも期待してますから、マジ頑張ってくださいよ。こっちもマジでいいもの作っておくっスから」
わざとらしく敬語で言うと、空になったペットボトルを拾い、裏方の生徒が作業をしている場所へ戻っていった。
一人になった私は、しばらくの間台本を眺めていた。
「次、藤野! 藤野亜希子!」
鋭い声に呼ばれ、台本をもって先生のもとへと駆け足で向かう。
先生は長机に大判のノートを広げ、三色ペンを弄んでいた。
先生の前に立つと心臓が大きな音を立て始めた。自分の弱点を言い当てられる講評の時間は、何度経験しても慣れるということはない。
「来たか。それでは、お前の役についての講評だが……そうだな、中々厳しいことを言わなきゃならない」
眼鏡越しにじっと見つめられ、じっとりとした汗が背中を湿らせる。
「まず指摘しなければならないのは、全体的に落ち着きがない。心が浮ついて人間の魅力が感じられない。人間の心を表現できないからうわべの技術を見せようとしてしまうんだ」
「はい……」
口の中が乾き、普段とは違って、かさついた細い声しか出てこない。
先生は私の様子を見て一瞬目を泳がせる。二、三度瞬きをすると、先ほどと同じ鋭い視線を私に向ける。
「……はっきり言わせてもらうが、このままの演技では、お前のことを公演に出すわけにはいかない」
「なっ……」
予想外の言葉に、私は半ば呆然として絶句してしまった。
「お前には悪いが、今の演技を後輩たちの手本として見せるわけにはいかないんだ」
「……は、はい……わかり……ました……」
先生の口調に責める気配はなく、事実を淡々と述べているようだった。それだけ説得力が強く、私は胸が締め付けられるように感じた。
「まだ、正式決定ではない。が、このままだと考えなければならない。私が言いたいことはわかるな?」
「はい……。わかり、ます……」
鼻の奥がキュっと痛くなって口の中が酸っぱくなったのをごまかすため、区切りながら返事をすると、先生は小さくうなずいた。
「しばらく後にもう一度チェックするから。その時までに改善することを期待する。私からは以上だ」
「はい……ありがとう、ございました……」
頭を下げた拍子に涙腺が決壊した。
一筋の涙が顔を伝って、途中でポトリと床に落ちた。私は、それ以上涙があふれてこないように、下唇をギュッと噛んで稽古場へと戻った。
その日はほとんど上の空で、気づけば部活が終わっていた。
自分の体が透明な膜で覆われているようで、周りの景色や喧騒がボンヤリとしか伝わってこないように感じた。
それからボーっとしたまま時間が飛び飛びになっているようで、気づけばジャージから制服に着替えて靴を履き替え、校門を通り過ぎていた。その後、どの道をどのように通ったのかわからないまま家に帰りつき、学校の制服を着たままで自分の部屋のベッドで布団にくるまっていた。
「……着替え忘れてたんだ……」
しわになってしまうことを考えたが、面倒くさくてそのまま転がってしまう。見苦しいほど乱れてしまったとしても、予備の制服を着ていけばいいだけの話だ。
「……今、何時だろ……」
学校を出たときにはオレンジ色だった空が、深い藍色に変わっていた。冷たい夜に押しつぶされるような気がして、気持ちがさらに滅入ってしまう。
半分寝ているような頭の中で、先生の言葉が何度も繰り返し再生され、悔しさと悲しさが胸の中でグルグルと渦巻く。
自分はできているはずだという自信と思い上がりを真正面から指摘されたから、こんなに傷ついているのだろうか。
頭までシーツをかぶって目を閉じてみるが、瞼の裏にこびりついた光景が消えることはなく、眠りに逃げこむこともできなかった。
ここで寝っ転がっていても何も解決するはずはないとわかってはいたけれど、布団から出る気が起きなかった。布団の上でゴロゴロしていると、部屋の扉が開いて廊下の灯りが差し込んできた。
「亜希子ー。起きてる?」
「……お母さん、入ってくるならノックしてって言ってるじゃん……」
「はいはい。悪かったね」
お母さんの口調には、全く悪びれた様子がない。部屋に入ってくると、照明のひもを引いた。蛍光灯の白い光が目に飛び込んできて、視界が何度か明滅した。
「あんた、着替えないで寝てたの? よっぽど疲れてたのねぇ」
「んー……別に……」
何度かまばたきをして視界をはっきりさせる。目の前に立つお母さんは、心配そうな表情を浮かべている。
「あんた、何か嫌なことでもあったの? 黙って部屋に入って行って、呼んでも来ないから心配しちゃったよ」
「……別に何でもない……。それで、何か用? まだご飯の時間じゃないでしょ?」
「おでんと炒り鶏たくさん作ったから、おばあちゃんにもおすそ分けしようと思ったのよ。悪いけどおばあちゃん家まで届けてくれない?」
祖母の家は歩いて十分ほどの距離だから、特に大変なことはないのだけれど、今は外に出て誰かに会いたい気持ちにはなれなかった。
「えぇ……。一応私今悩んでるんだけど……。悩み多き思春期の娘のことを心配してくれてもいいんじゃないの?」
「心配してるわよ。ここでゴロゴロしているよりも、少し歩いてきたほうがスッキリしてくるんじゃないかと思って」
「絶対今考えたでしょ……。大体お母さんが届けて来ればいいじゃん」
私の幼稚な反論に怒るでもなく、目じりを下げて小さく息を吐く。
「それがね、これから町内会の人が来ることになってて、留守にできないのよ。お願いよ。少しだけどお駄賃あげるから、ね?」
用事があるのなら仕方がない。ここでケンカしても何の意味もないため、引き受けることにした。
「……わかったよ……。顔洗ってから行くからちょっと待ってて」
二つのタッパーを保温バッグに入れて外に出ると、夜の空気はひんやりと湿っていた。
冬が終わり暖かくなってくる期待感に満ちた、思わず背伸びをしたくなるような涼しさではなく、これから冷たい白さに閉ざされていく閉塞感を予感させるような涼しさだ。
祖母の家に近づいたところで、手鏡を取り出して自分の顔をチェックしてみる。優しい祖母には、疲れた顔や悲しい顔を見せたくなかった。
「表情よし。声よし。笑顔よし」
鏡の中の自分に言い聞かせて、玄関のインターフォンを押す。
少し待っていると、家の奥から玄関に向かってくる足音が聞こえて、カラカラと音を立てて引き戸が開いた。
「あらあら、亜希子ちゃんでねぇの。よく来たねぇ」
海の近くで育った祖母の言葉は、強くなまっている。田舎風の服装も相まって、祖母と話していると優しく包み込まれるように感じる。
「おばあちゃん久しぶり。お母さんがおかずたくさん作ったから持って行けって」
「あらー、ありがとうね。こういうのはたくさん作っても余らせるし、一人分作ってもおいしくならないからねぇ」
祖母は優しい笑顔を浮かべて出迎えてくれたが、すぐに顔を曇らせた。
「亜希子ちゃんどうしたの? なんだか元気なくて悲しい顔してるよ。まんず上がって上がって」
祖母が一目見て私の変調を感じ取ったことに、恥ずかしさ半分嬉しさ半分で顔が熱くなった。
「えっと……私はおかず届けに来ただけで……」
「ええがら、ええがら。ばあちゃんもお話ししてえのだから少し休んでいぎなさい」
祖母は、私の腕をとって、半ば無理やり家に招き入れた。祖母の家は暖房が効いていて暖かく、秋の夜に冷やされた私の手や顔にじんわりと血液が流れていくのが分かった。
「年とって、寒さを強く感じてしまうから暖房付けてるのす。暑かったらごめんね」
祖母は節くれだった細い手で私に座布団を渡すと、保温バッグから取り出したタッパーを台所へと運んで行った。
普段は自分の部屋でも教室でも椅子に座っているため、座布団に座るのは、お腹の下あたりが圧迫され目線も低くなって、何となく落ち着かない。
座布団を敷いてどんな座り方をすればいいか考え、女子として胡坐をかくわけにもいかず、脚を横に流して座る。
机の上に手を伸ばすのにもその場から動くのにも不便な姿勢だけど、足がしびれることもないし、バランスが崩れることもない、一番楽な座り方だった。
しばらく居間の様子を眺めていると、祖母がお盆をもって戻ってきた。
「お待たせ。亜希子ちゃんはジュースが好きかもしれねぇけど、ばあちゃんは普段飲まねえから、コーヒーしかねえけども、それでえがんすか?」
「ええっ、悪いよ。私すぐ帰るし、そんな気を使わなくてもいいのに」
「ちょうどばあちゃんも飲みたかったところだから、ええのよ。お砂糖はどうする?」
「うーん、ブラックでいいかな」
カップを受け取りながら言うと、祖母は優しく微笑んだ。
「そう、亜希子ちゃんは大人なんだね。ばあちゃんは子供だはんで、お砂糖もミルクも入れちゃう。……またお医者さんに怒られてしまうな」
祖母のいたずらっぽい口調とコーヒーの温かい湯気で、気持ちがフっとゆるんでいく。
祖母はカップに砂糖を入れると、机の角を挟んだ向こうに腰を下ろす。自宅だというのに、きっちりと膝を折り曲げて背筋を伸ばした正座をしている。立っているときは見下ろしていた祖母の顔が、座った時には私より頭一つ分くらい上にきていた。
そういえば、意識してみたことはなかったけれど、祖母はいつでも正座をしていた。私が小さな頃から、遊び相手になってくれているときも、洗濯物を畳んでいるときも、同じ部屋で本を飲んでいるときも、長時間の時も短時間で立ち上がる時もスッと背筋を伸ばして姿勢を正して座っていた。
今も私の目の前でキッチリと座っている様子を見ると、足を崩している自分がだらしなく思えた。
祖母は、何かをたずねてくるわけでもなく、私と一緒にカップを傾けていた。互いに口を開かず、無言でコーヒーをすすっているが、不思議と気まずい感じはせず、心が日に干した布団のように柔らかくほぐれていった。
「ねえ、おばあちゃん……」
「んー? どうした?」
祖母は、私を刺激しないようにしているように、のんびりとした声で答える。
「……私って、落ち着きなく見える……?」
「んー? 誰かに落ち着きがねえって言われたのか? それで悲しそうにしていたの?」
「うん……」
私はつかえながら、今日の部活であったことを祖母に伝えた。
祖母は、私の話を遮ることなく、聞いてくれた。時折相槌を打ちながら、私の言葉が途切れるまで辛抱強く聞いていてくれたため、私は自分の気持ちが暴発しないように落ち着いて話すことができた。
「……なるほどなぁ。悔しくて悲しい思いしてたんだな」
「うん……。おばあちゃん、私どうしたらいいのかな? このままじゃいけないんだけど、どうしたらいいかわからなないの」
祖母はカップを少し傾けてから、少し考えるようなしぐさをして、一つ息を吐きだした。
「そうだねぇ……。ばあちゃん演劇って言われてもよくわからねぇからなぁ……。わからねぇのに、無責任にあれやこれやと言うわけにもいかねぇと思うな」
「そっかぁ……」
私は自分が勝手に期待していただけなのに、アドバイスの言葉がないことに内心がっかりしていた。そんな簡単に解決する話ではないと分かっていたはずなのに。
祖母は私の様子を見て、何か思い出したように手をポンとたたいた。
「そういえば、あの子も相談してきたっけねぇ」
「あの子?」
「亜希子ちゃんのお母さんのことだよ。落ち着きがねえから、どうしたらいい? って、聞きに来てたなぁ」
「へ、へぇ……。そうなんだ……。お母さんも……」
あまりうれしくない特徴も、母からしっかりと受け継いでしまっていたらしい。
「それで、おばあちゃんはお母さんの相談になんて答えたの?」
「落ち着きてぇなら、まんずはぁ、しっかりねまれじゃ」
「は……ねま……? どういうこと?」
突然祖母のなまりがキツくなって、聞きなれない言葉に思わず聞き返してしまった。
祖母は少し残念そうな表情を浮かべたが、すぐに優し気な微笑みに戻った。
「そうか、亜希子ちゃんたちの年代だば、方言使わないものねぇ。ばあちゃんの地元岩手の言葉で『ねまる』は座るってことよ。じいちゃんの地元北海道だと、おっちゃんこって言ったりもするらしいよぉ」
「へぇ……。おっちゃんこってなんかかわいいね」
小さなおっちゃんがチョコンと座っている様子を想像して、吹き出しそうになった。
「心を落ち着かせたいなら、きちんと座ることから始めなさい。ばあちゃんのばあちゃんから教わったことだよ」
そう言われて、改めて祖母と自分の姿勢を見比べて見る。
きちんと膝をそろえて背筋を伸ばしている祖母は、体に一本芯が通っているように見えた。一方の私は、重力にあらがえずにダラっとして、背筋もぐにゃぐにゃと色々な方向に曲がっている。座り姿だけ見たら、私のほうが年をとっているようだ。
「きちんと座りなさい、かぁ……」
「はじめは少し窮屈かも知れねえども、慣れたらこんなに楽な座り方はないんだよ。腰もぐらぐらしないから、本読むときも仕事するときも動きやすいし、必要な時にはすぐ立ち上がって動けるべ?」
祖母は、説明しながら一度立ち上がり、もう一度腰を下ろして見せた。
「正座させるのは躾のためだとか、お仕置きのためだとかって言われることもあるども、ばあちゃんはそうは思わねぇのよ。そんたなことのために続けるほど昔の人も暇じゃねぇべ」
なるほど、足の指を立てれば一息で立ち上がることができて、座るときも腰を下ろす動作の延長線でキチンとした姿勢になっている。座った時にお尻が定位置に収まることで、上半身がぐらつかないのもよく分かった。長い間廃れることなく続いてきたことには、それなりの理由があるのだと思わされた。
祖母の姿を見ながら私も一度腰を上げ、体の横に放り出していた足をお尻の下にしまい込んだ。
「うっ……」
正座なんてしたのはいつぶりだっただろう? なれない姿勢をとるのは正直かなりキツい。太ももが突っ張り、ふくらはぎが圧迫される。お腹の下あたりが少し苦しい感じがして、お尻が乗って体重がかかり足首が少し痛くなる。
「くぅ……結構……きついかも……」
すぐにしびれが切れ始めて、うめき声をあげてしまう。
「無理しねぇんだよ。特に若い人は慣れてねぇだろうし」
「う、うん……」
ものの数分で再び足を崩してしまった。足の裏がジンジンとしびれて、すぐには立ち上がれそうもない。
「慣れたらこんたに楽な座り方ねぇども、それまでは少しつらいかもしれねぇな。ま、気が向いたら試してみるといいよ。くれぐれも無理しねぇでな」
「うん、わかった。ありがとうねおばあちゃん」
「なんもなんも。何かあったらいつでも来ていいんだから」
しびれが収まってから立ち上がり、祖母の家を後にした。おかずのタッパーを届けるだけのはずが思わぬ長居をしてしまった。
外の空気は相変わらず冷たかったが、来た時に感じていた追い詰められていくような感じは薄れ、幾分気持ちが楽になっていた。
自分の部屋に戻り、部屋着に着替えた私は、ベッドの上で正座をしてみた。
「うーん……やっぱりちょっと苦しいなぁ……」
祖母の家で正座したときはスカートだったから、あまり感じていなかったが、長ズボンの部屋着だと、生地の伸縮性にも限度があり、太ももが締め付けられる感触が、強く感じられた。すぐに足がしびれてきて、落ち着く間もなく足を崩してしまう。
「本当に落ち着くことなんかできるのかなぁ?」
脚を伸ばして、ストレッチしてみてもなかなかしびれは取れず、集中なんてできそうになかった。
「こんなことしてて、本当に意味あるのかなぁ……」
疑問が浮かんでくるが、私はただ落ち込んでいただけで、何も思いつかなかったのだ。せっかくアドバイスをもらったのに、ろくに試しもせず結論を出すことはできない。私はもう少し続けてみようと思った。
2
「……あいたたた……」
数日間正座の練習を続けた私は、相変わらず足がしびれてしまうけれど次第に長い時間座っていられるようになった。
座っていられる時間が長くなるにつれて、祖母の言っていたことが少しずつわかってきた気がした。
姿勢を正して座っていると、何か動いていなければならないと自分の内外から追いかけられているような焦りや不安の気持ちが薄くなって、心が静まっているように感じられるのだ。
膝を折り曲げて、お尻をペタリとおろすと、椅子に座っているときや足を崩して座っているときに比べて自然と呼吸が深くなる。ゆっくりとした呼吸をしていると、頭の中でモヤモヤしているものが消えて、スッキリとしてくるように感じられた。
また、適当に座っているときには、身の回りにある漫画本や携帯電話に手が伸びてしまうが、正座をしていると一度立ち上がってモノがあるところに移動しなければならない。
余計なものに惑わされずに、集中することができるのだった。
「……それじゃあ、そろそろ、脚本を読んでみようかな……」
今までは、とにかく座っていることだけを考えていたが、本来の目的はこれから先だ。しっかりと脚本を読み込まなければならない。
「……こんないい姿勢で本読むなんて、寺子屋ってこんな感じなのかな……」
今までは、部活の時間も家に帰ってからも、こんなにいい姿勢で本を読んだことはなかった。机に向かっているときは前かがみになっていたし、そうでなければ寝っ転がって読んでいることが多かった。
姿勢を変えたところで、書いてあることが変わるわけではない。けれど、何となく今までとは違った読み方ができるのではないかと思えた。
「さてと、どんな感じかな……」
荷物から台本を取り出して目を通していく。
今まで何度も読んできた台本には、色とりどりの書き込みがされて、少し読みづらくなっていた。
「そういえば、人間が表現できていないって言われたっけ……?」
先生に言われたことを思い出したが、頭を覆いたくなるような嫌な感情が薄れていた。お腹の奥までしっかりと息が入って頭がスッキリしていることで、自分の感情をコントロールすることができ、何をすればいいのかを前向きに考えられるようになっていた。
「うーん……人間かぁ……」
私は一行ずつゆっくりと読み進めていく。普段は自分のセリフと動きを中心に読んでいたが、今はどんなに些細なことも見逃さないように、ゆっくりと確実に読んでいく。
読みなれた内容の本なのに、眠くなることも集中力が途切れることもなく読んでいくことができた。
「……なるほど……ここがこうなってるから……」
自分以外の役のセリフや行動の背景を読み進めていくことで、逆に自分のキャラクターが浮き上がっていくように感じられた。
一見関係なさそうだった場面の行動が、後々のセリフのための伏線になっている様子がよく理解できた。自分では読み込んだ気になっていたけれど、ずいぶん甘かったということがよく分かった。
「……こんな状態で、できた気になっていたなんて……」
いい気になっていた過去の自分を張り倒してやりたい気分になったが、それよりも今まで何度も読んできた本の面白さを再確認して、自分の役についての理解が深まった嬉しさのほうが勝っていた。
「……ここで、このセリフが出てくるってことは、こんな感じの話し方になるのかな?」
軽く息を吸い込んで、自分の役のセリフの練習をしてみる。
「あれ? あれ?」
自分の声なのに、予想以上にしっかりとした声が出て驚いた。
どうやら、自然とお腹に力が入っていることと、深く息を吸い込むことができていたことで、意識することなく腹式呼吸をできるようになっていたようだ。
「正座にこんな効能があったなんて……おそるべし正座……」
私は感動すら覚えて、足がしびれていることも気にならなかった。
3
家だけでやるにはもったいないため、私は学校にも小さなクッションを持ってきて部活が始まるまでの時間も、正座をしてみた。
「亜希子、それ何してるの? 先生に怒られて何か反省でもさせられてるとか?」
私の姿を見た朋が、笑いながらからかうように話しかけてきた。
確かに稽古場で正座をしているのは奇妙に見えるだろう。少し恥ずかしかったが、役に立つことをやめる必要はないだろう。
「朋、正座が躾だとかお仕置きだとかっていうのは、短絡的すぎるよ」
「ほーん、そうなの? 私はいたずらしたときに、親父とかじいちゃんに怒られて正座させられた記憶しかないなぁ……。フローリングに直接座るから、膝が痛くなっちゃうんだよなぁ」
朋は本当に嫌そうな顔で正座の思い出を話した。
きっと、他にも正座に嫌な思い出を持っている人は多いのだろう。
同じ動作でも出会い方次第で、印象は変わってくる。私はかなり幸運な出会いをすることができたようだ。
「集中するためにやってるだけで、別に誰かからやれって言われたわけじゃないよ」
「ふーん、確かに正座とか座禅とかって、集中できそうだよね。武士とかお坊さんっぽくてかっこいいし。トラディショナルジャパン的な」
朋は面白そうに言うと、工具をもって大道具の作業に向かっていった。
私は、正座をしたままで静かに目を閉じて、ゆっくりと深呼吸を始める。
鼻から吸い込んだ空気がお腹の奥までストンと落ち、頭に酸素が回っていくように感じて、集中力が増していくように感じられた。部活前のあわただしい雰囲気やザワザワとした声から自分が切り離されていくような感覚が心地いい。
数分間深呼吸を続けた後、今度は声を出す練習を始める。下腹にぐっと力を入れて、発声練習を始める。上半身全体に空気の振動が伝わっていく。
部活の練習が始まってからも、普段と比べて集中することができた。
練習の後半になったころ、顧問の先生が台本やノートを持って稽古場に入ってきた。
「お疲れ。今日は全体稽古の前に個別で演技見ていくから、呼ばれたやつから出てきて」
一瞬心臓がドキリと大きく音を立てた。
今まで集中できていたのに、嫌な気持ちを思い出してしまい、呼吸が浅くなって頭が真っ白になってきた。
「……ダメだダメだ。このままじゃ前回よりひどいことになっちゃう。せっかくもう一度チャンスがあるんだから、しっかりしないと……」
私は稽古場の隅のほうへ移動して、クッションの上で膝を折り曲げた。
すっかり正座にも慣れていたため、座って背筋を伸ばしただけで、気持ちが落ち着いてくる。
ゆっくりと鼻から息を吸い込んで、お腹の奥まで空気を満たしていくと、ドキドキと大きく速かった心臓も次第に落ち着いてきた。私にとっても正座をすることは、すっかり落ち着くためのルーティーンになっていたようだった。
精神的に充実して、虚勢ではない自信が胸の中に満ちている。
「次、藤野。短い期間だったが、良い変化をしていることを期待しているぞ」
「はい。頑張ります」
下腹にグッと力を入れて返事をして、リベンジの舞台に向かって立ち上がった。
指定された範囲を演じ終えて長机の前に立つと、先生は小さく笑みを浮かべて何度かうなずいた。
「まだまだ粗く、稽古の中でブラッシュアップが必要だ。が、前回と比べれば数段良くなっている。公演に向けて、他の役者たちを引っ張っていってくれ。以上だ」
私は、喜びの声を上げそうになるのをこらえ、自分にだけわかる小さなガッツポーズをして、荷物をまとめている場所へと戻っていった。