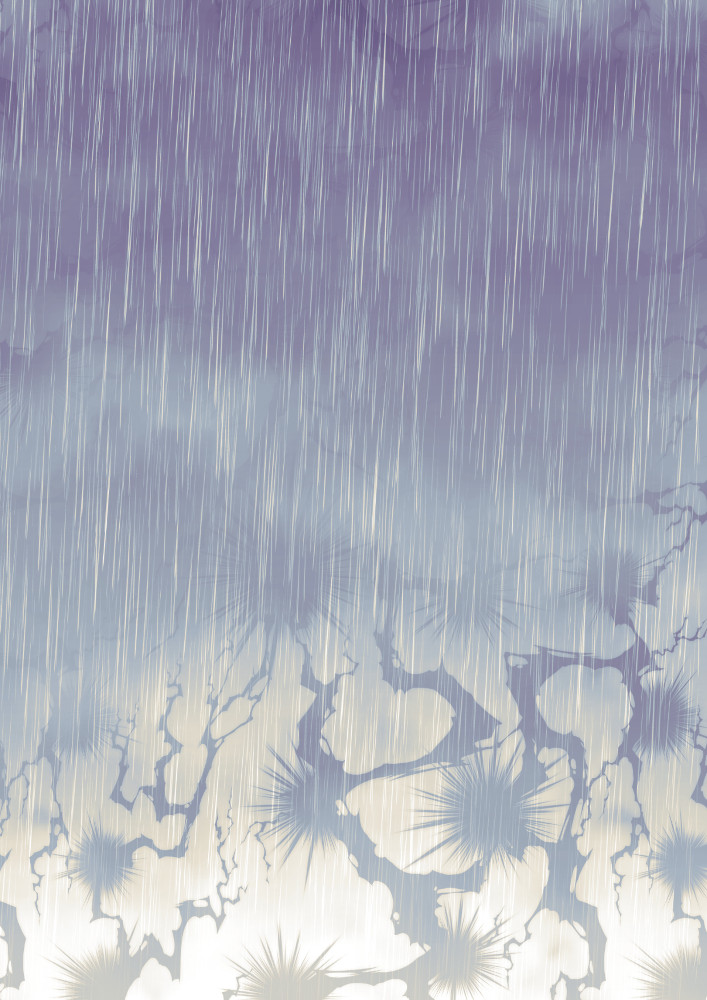[235]婚姻届は正座で書きましょう

タイトル:婚姻届は正座で書きましょう
発行日:2022/09/01
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:52
販売価格:200円
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
山に囲まれた美しい竜床沼(りゅうしょうぬま)には、竜が棲んでいるという言い伝えがあり、神社を建てることになった。絹香は町から山道を歩いてやってきた。婚約者の宮大工、木綿太(ゆうた)が神社の普請に参加しているからだ。
行ってみると木綿太は普請中の神社の屋根の上で正座して、毛筆で婚姻届けを書いていた。
そこへ台風が接近する。さて?
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/4131824

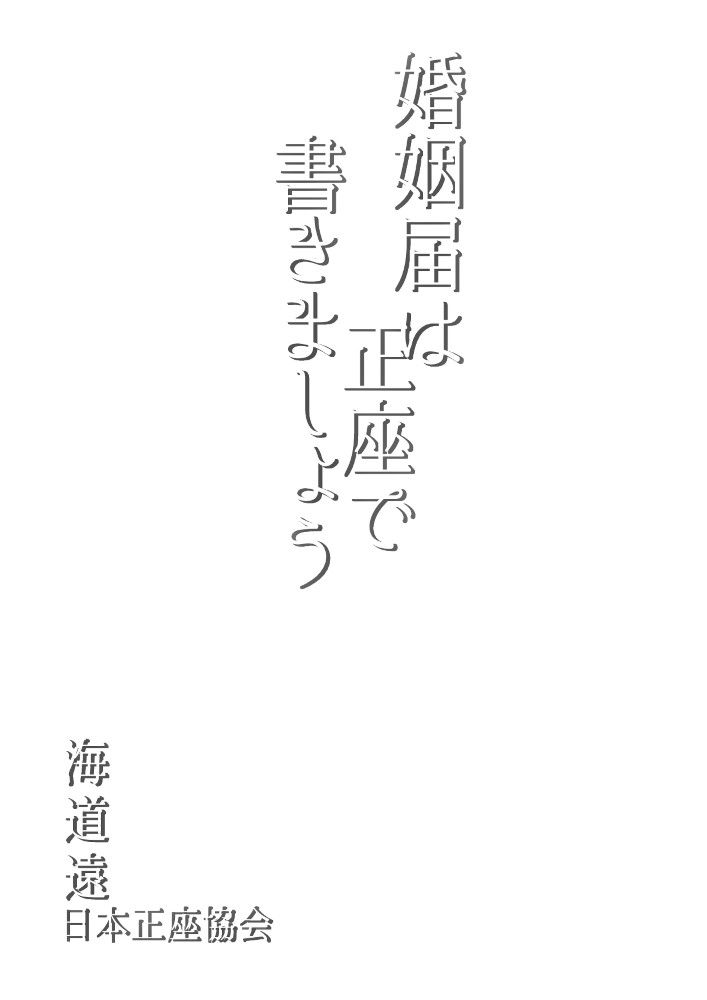
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序 章
なんという神秘的な沼の色だろう。
こんな美しく吸いこまれそうな青色は見たことがない。
周りを囲む山の緑よりも深く濃い青だ。空より深い青だ。青だか蒼だか碧だか、表現できない。
時折、頬を冷ややかな風が通り、
ザザザザザ……。
沼の水面に細かい波が立つ。
(伝説の竜が棲んでいそうな沼の色だわ)
ほとりをぐるりと歩いてきた絹香は思った。なんとなく熱い視線のようなものを感じる。
(静かで誰もいないわ。きっと思い過ごしよね)
ぽつんとあったバス停から三時間は歩いてきただろうか。パンプスで靴ずれができてしまった。目的地の普請中の神社が見えてきた。
第 一 章 屋根の上で書道
「あのう、棟梁さんですか?」
棟梁が振り向くと、建築用の木材やカンナ屑や大工道具がところせましと散らかった中に、パンプスを履いた若い女性が立っている。
「そうだが。何か?」
「ここに松島木綿太さんという大工さんがおられますか?」
「木綿太ならいるが。あんたは? そんな恰好で材木の中をうろうろしてると危ないですぞ」
ゴマ塩頭で角切りの棟梁が言った。
「木綿太さんがいた! 良かった。私は彼の婚約者で若野絹香と申します」
「おお、あんたが木綿太の。えらいべっぴんさん(美女)でびっくりだな、これは!」
周りにいた宮大工たちが視線を向けた。
「あのう、木綿太さんは」
「あいつなら、屋根の上にいますよ」
「お仕事中、すみません」
「いや、今は休憩中だが、屋根の上で習字の稽古をしているよ」
「え? しゅ、習字の稽古ですか?」
絹香は思わず聞きなおした。
村はずれに、とても深いといわれているる竜床沼という沼がある。
秋には紅葉する樹々に囲まれて湖面が青く映え、とても美しい。
昔から竜神様が沼の底で眠っているという言い伝えがあったが、祠も神社も無く、今まで時間が過ぎた。村の会議でやっとこさ、竜神様のための神社を建立することになった。
宮大工が沼のほとりにぞろぞろやってきて、作業を始めた。
土台の工事が終わり、神社の本殿が建てられ、檜皮葺の屋根を葺くことになった。
絹香は以前に、自宅の屋根修理にやってきた職人さんたちにおやつを運んだ時に足を滑らせ、すんでのところで木綿太が助けたのが縁でつきあうようになった。そしてデートを重ねて婚約した。
結婚式の日取りも決まり、後は支度に奔走する日々だったが、そんな忙しい中、木綿太が書道を習いだしたという。
「どうして書道を?」
「木綿太の筆跡は確かに見られたものじゃないがな」
「そうですね」
棟梁と絹香は苦笑いしあった。
「そればかりか、正座まで習いだしたんですぞ」
「正座して書道? どうして?」
共働きになる結婚生活のために料理を習い始めたのならわかるが、木綿太は独身生活が長かったので料理はできる。
「あ、あれかな」
棟梁が手をポンとした。
「婚姻届けの連帯保証人になってくれって言われたから、俺が筆ペンで書いたからかな?」
「ああ、きっとそうですわ。木綿太さんてば、単純なところがありますから」
吹き出しそうになるのを堪えながら、絹香は辺りを見回した。
「すみません、ちょっとはしごを貸していただけますでしょうか?」
「そりゃかまわないけど、お嬢さん、危ないよ」
絹香は手早くはしごを運んできて軒に立てかけ、パンプスを脱いで素足になった。
「木綿太さん、私よ、絹香!」
はしごの真ん中から首を伸ばして叫んだ。
屋根のてっぺんに藍色の法被と足袋姿で座っていた木綿太が、ぎょっとした顔で見下ろして振り向いた。
「きっ……絹ちゃん? どうしてここに? 来るならメールぐらいくれよ」
「聞きたいのはこっちよ。時間ができたからびっくりさせようと会いにきたら、棟梁さんから屋根の上でお習字してるって聞いて。何やってるの?」
「見ればわかるだろ。正座して習字の練習してるんだ」
「そんな座りにくい屋根の上で?」
「書道をする時は正座して書くに決まってるだろ。姿勢からビシッと決めなきゃ、字がへろへろになっちまうから。それに俺は職業柄、屋根の上がいちばん落ち着くんだ。屋根の上で正座して婚姻届けを書くと決めている!」
「なんですって? 婚姻届けを書いてるの?」
さすが職人気質!
木綿太はこうと言い出したら聞かない。
結婚の日取りばかりか、お結納の日はもちろん、婚姻届けを書く日も縁起の良い日でなければならない。それも、絹香の分とばっちり合うように、四柱推命から星占いから数秘術から、すべて縁起の良い日を調べ回ってやっと決めた。
「今日の十九時二十八分に書き上げるんだ」
強行に絹香にも命令した。
「婚姻届けは俺がきれいに書いてから、お前の欄に書け」と。
仕方なく絹香もはしごから降りて、工事現場の片隅に正座して毛筆の稽古を始める。
第 二 章 絹香、風に飛ばされる
「大変だ、棟梁!」
スマホを見ていた大工が叫んだ。
「南の海にあった大型台風が急接近してくるって!」
「なにぃ? ありゃあ、消滅したんじゃなかったのか」
足場を取り外した後なのが幸いだった。神社の普請現場は、たちまち大慌てで台風の備えを始めた。
村でも騒ぎが始まり、住民たちは避難準備を始めた。
普請中の神社の本殿にも近所の住民たちが消防団の案内で避難してきた。皆、防災グッズを持って本殿の床に並んで座っている。
神社の神主さんと神職さんたちは、町内会の人たちの世話におおわらわだ。
「木綿太くん、今日はあきらめなさい!」
棟梁と神主が叫んでも、木綿太は決めた今日の十九時二十八分に絶対決行するという。
雨合羽を着てブルーシートの上で正座し、ボードを広げ、習字の練習を続ける。
「沼の竜神様と約束したんだよ! 婚姻届けは正座して毛筆で書くって。あの男性はきっと竜神様だ。どこか気高かったものな」
「え? なんて言ったの? 竜神様?」
雨が横殴りに降って声が聞こえない。
木綿太は、どうにか屋根のてっぺんに昇るとブルーシートをまたいで正座した。暴風にあおられてふらふらする。
「やめましょうよ、木綿太さん! 落ちて大けがでもしたら、結婚どころじゃなくなるわ!」
絹香が何度叫んでもいうことをきかない。
「正座してあの時間に書かないと、俺たちは幸せになれないんだ」
「木綿太さんてば!」
絹香も命綱をつけて登っていき、木綿太が風で飛ばされないように、腰を持って支えた。
「おう、絹ちゃん、助かるぜ!」
「こうなったら、しっかり書いてよ、木綿太さん!」
棟梁が軒先から叫ぶ。
「もうすぐ台風の目に入るってよ。しばらく静かだから、今のうちに書いてしまえ」
「おう、棟梁!」
今だ! と思った時に、突風が絹香を襲った。叫びが風と共にぶっとんでいった。
「きゃあああああ!」
「なんだ? あっ」
木綿太が気づいた時には屋根の上に絹香の姿はなかった。
夜の闇に吸いこまれるように、絹香は消えてしまった。木綿太の手元にあった婚姻届けも半分、飛んでいった。
一晩じゅう荒れ狂った台風は、夜明けにようやく遠ざかっていった。紫色と暁色の混じった色の雲が速く流れていく。本殿で眠れない夜を過ごした住民たちが、ごそごそ動き出した。
「皆さんはまだ、ここにいて下さい。わしらは、ちょっくら沼の様子を見てくっから」
町内会長と消防団長と棟梁が三人で沼の周りを偵察に行った。
「町から来た娘さんが行方不明になったって本当ですか? 棟梁」
町内会長が沼への斜面を降りながら尋ねた。
「どうやらそうらしい。わしの弟子のいいなずけなんだ。なんとか無事でいてくれるといいが」
「棟梁のお弟子さんのいいなずけですか! そりゃご心配なことだ」
「弟子の木綿太も一晩中帰らんのでね」
木綿太も、一晩じゅう帰らずに強風の中を絹香の姿を求めて捜索したのだろう。
沼は濁った水であふれていた。流れこむ谷川からの木々で湖面がいっぱいになっている。
「あ、あれは?」
沼のほとりから、とぼとぼ歩いてくる男の影がある。
「木綿太!」
棟梁が叫んだ。全身、濡れねずみになった木綿太だった。
「棟梁……、どうしよう……。絹香が……絹香が台風の風で、どこかへ飛ばされちまった……。これのために……」
木綿太の握られた右手には、濡れて半分溶けてしまっている婚姻届けの切れはしが握られている。
「お~~い、誰か毛布を!」
消防団長が叫び、
「君、とりあえず屋根のあるところで温まりなさい。婚約者はわしらも捜索するから」
木綿太は消防団員らに脇を抱えられ、本殿に向かった。
********************
絹香の意識が戻ったところは、とても温かかった。
まるで生まれたばかりで、真綿にくるまれたようだ。
薄く目を開けると絹の布団に寝かされており、少し離れたところに背を向けて正座している人物が見えた。ろうそくの灯りがあり、その人影は岩屋にゆらゆらと映っている。
「あのう、ここは……」
「気がついたか」
背を向けたまま、男は応えた。岩屋に響いた声は、この世の声でないように神秘的に聞こえた。男は腰を越えて長く伸びた銀緑色の髪の毛を、背後の岩の上に巻いて置いていた。
絹香が起き上がろうとすると、身体のふしぶしが痛んだ。
(どうしてだろう。あ、私は必死で屋根にしがみついていたんだ。真っ暗な嵐の中で)
手には、婚姻届けの切れはしが握られていた。
(あ~~あ、破けちゃった! 台風のさなかじゃ無理に決まってるじゃない)
(木綿太は、木綿太は無事だったろうか? 普請途中の神社は倒れなかったかしら。避難してきた人たちは無事かしら………。何より、婚姻届けはどうなったのかしら)
どこかから、風の唸りがかすかに聞こえてくる。
第 三 章 銀髪の男
「どうやら嵐は去ったようだな」
岩屋の奥に座っていた銀色の長髪の男が耳を澄ませてからつぶやいた。
「もう、大丈夫だろう、娘よ」
「でも、木綿太と離れ離れになってしまったわ。木綿太も台風のために婚姻届けを書けずに、どんなにがっかりしていることか」
「婚姻届けだと?」
振り向いた銀髪の男の昏い世界に棲む者特有の美しさをまともに見て、絹香はぞっとして凍りついた。
普通の人間ではない。真っ白の肌、金色の瞳、額に刻まれた謎の模様の刺青……。
「あなたは誰っ!」
「ああ、我か。我はこの沼のヌシ、竜神の幻馬と申す。木綿太という男なら、この沼のほとりで二日ほど前に出会うた。婚姻届けを書くと言うて息巻いておったから、正式な書き方を教えて進ぜた」
「正式な書き方?」
「正座して毛筆で書きなさいとな」
絹香は目を見開いた。
木綿太が急に婚姻届けの書き方にこだわり始めたのは、この銀髪の幻馬とやらいう竜神が教えたのだ。
「あなたのせいだったのね! 木綿太が急に婚姻届けを書きだしたのは」
「どの道、書く予定だったのだろう? 夫婦になるとか申していたから、正座して毛筆で書くと夫婦円満、家内安全、健康長寿になると教えた」
「でも、そのために台風の最中に書かなければならなくなって、風に飛ばされてしまったわ。今頃、木綿太は大けがして病院に運ばれてるかもしれない」
「あの男なら大丈夫だ。多少のかすり傷だけですんだようだ」
銀髪の男は、自分の前に置かれている水晶玉のようなものを見つめて告げた。
絹香は布団からガバッと抜け出し、男の前まで駆けつけて玉の中を覗いたが、何も見えない。
「何も見えないわ! こうしちゃいられない! 私、帰ります! どこから帰れるの?」
「まだ沼の増水が退かぬ。この岩屋は沼の地下にある。地上への道は閉ざされている」
「じゃあ、どうしよう、婚姻届け……。もう一度、保証人の欄に、棟梁さんに書いて下さいって頼まなきゃ」
「なんなら、我が保証人になって進ぜようかな? あの男の持っていたヤワな紙のより、竜のウロコでできた強い婚姻届けが手に入るぞ」
「竜のウロコ? それってロマンチックな柄が描いてある? シンデレラや美女と野獣のような」
「しんでれら……とは何か知らぬが、竜族の縁結びの神からすぐに取り寄せられるぞ。求婚する時は、希少な品を持参するのが習わしだ。ちょうどよい」
絹香は瞳を輝かせた。
「本当? じゃあ、お願いします!」
「ついでに正座の稽古も見て進ぜよう」
「はい、お願いしますっ!」
第 四 章 書き損じ
「違う! 背筋がまっすぐなってない!」
銀髪の幻馬という竜神が、しなやかな鞭を振り回した。
「こ、こうですか? 背筋をまっすぐして……」
「違うと申しておる! 曲がっておる!」
さんざん特訓されて、絹香はようやく、お尻の下にスカートを敷いて、かかとの上に座ることができた。
「よろしい。文机について。筆を持ってよろしい。この婚姻届けは縁結びの竜族の神に急いで送らせた用紙だ。今度こそ替えがないから、そのつもりで慎重に書くこと」
絹香は震える手を一生懸命に固定して、筆に墨をつけ、そっと竜のウロコでできているという婚姻届に署名した。筆を下ろした感じは普通の半紙と変わりない。縦書きになっているのが役所の用紙と異なっているだけだ。息を止めて、どうにか失敗せずに書けた。
「では、保証人の欄に署名をよろしくお願いします」
恭しく幻馬に渡した。
幻馬は文机の前に正座すると、長い袖を左右にさばいて墨を少しすり、筆につけて用紙に向かった。
岩に囲まれた空間の中、ろうそくの火だけが揺れている。
緊張が絹香にも伝わってきた。
「これでよし」
幻馬は落ち着いて言ったが、次の瞬間、なんとも言えない情けない顔になった。
「どうかなさったのですか?」
絹香が尋ねると、
「保証人と婚姻する者の欄を間違えて記入してしまった! 絹香どのが書いた隣の欄に、つい」
「まあ……書きなおせばよろしいではないですか」
「それが、我ら竜族の使う紙は百年は書きなおせないのだ! 破ることもできないのだ」
「じゃ、じゃあ?」
「このまま天帝様のところに提出して――。いったん受理してもらってから離婚届を提出するしかない」
「私たちの世界では結婚してから、半年経たないと離婚できない決まりになってるのですが」
「竜族の世界では、百年だ」
「百年! じゃあ、じゃあ……、あなたと結婚してしまうことになるの! 木綿太とは結婚できないの?」
絹香の唇は、恐れのために震えた。
「最初の恋は失恋に終わるものだ」
幻馬の口の端がニヤリとしたように絹香には見えた。青白いほど白い顔が笑みに歪むとよけい恐ろしい。恐ろしいほど美しい。
(この、人というか、竜神を信じていいのかしら)
「娘、我の話を聞いてくれるか」
冷たい手で手を握られた。かなり強い力なので、とっさに振りほどこうとしたが、びくともしない。
「我を赤子の頃から育ててくれた沼の妖精がおってな。名を瑠璃羽と言った」
(る、るりは? 何を話し始める気? 私たちの婚姻届けはどうなるのよ)
幻馬の眼は絹香の瞳を見つめるうちに、とろりとなってきた。
第 五 章 瑠璃羽
「我は瑠璃羽の真白き乳房を吸って育った。走り回れるわらべとなっても乳房を探して胸をまさぐり、乳を吸って眠りについた」
絹香の脳裏に、美しい天女のような乳母が幼子をあやしている姿が浮かんだ。
「沼の中なら端から端まで泳ぎ回り、我の知らぬことは何ひとつなかったが、我には人間のように『親とか血族』とかいうものが側にいない。頼れるのは瑠璃羽ひとりだけだったのだ」
幻馬の長い指が伸びてきて、絹香の栗色の長い髪を巻きつけた。
「おお、この感触だ。瑠璃羽の髪もこのように極細の絹糸のように細くしなやかで、重く、艶やかで……。我は毎夜、どれだけ、この岩屋の奥で瑠璃羽のしなやかな髪を撫で、白い乳房を愛撫し、白い首筋を吸ったことか。輝くような頬がどんなに柔らかかったことか。地上に咲くバラの花のような唇を吸ったことか」
指先で唇に触れられた時、絹香は思わずビクッと身を退いた。
「あ、あのう……」
「動くな。お願いだから、我の話を聞いてくれ。我の側にはもう誰もおらぬのだ」
「え、じゃあ、その瑠璃羽さんていう妖精は?」
「……」
幻馬はしばらくうつむいて目に手を当てていた。
「千年も側にいてくれた瑠璃羽の命が尽きてしもうたのだ。あれは何百年前であったか。しかし、瑠璃羽は美しいままだった。消えていく瞬間までしなやかな黒髪、バラ色の唇、真白き乳房はそのままだった」
「……命が尽きた……」
「赤子の時から数え切れぬほど愛し合った。岩屋や、時には沼の水中で。青色が熱を持って沸騰するくらい愛し合った。お互いの孤独を満たそうとするかのように」
聞いているうちに頬が熱くなるのを絹香は感じた。
「夢中で抱きしめ、我は乱れて竜の身体になってしまうこともあった。長い身体で幾重にも巻きつけば、絶対に離れはしないだろうと思っていた―――。しかし、運命とは残酷だ」
「瑠璃羽さんは、亡くなってしまったんですね」
絹香がつい、もらい泣きしながらつぶやいた。
「そうだ……瑠璃羽は長い長い年月の果てに消え入るように、霧のように消えてしまった……。でも……」
「……」
「奇跡とは起こるものだな。数日前、湖畔で、我は見てしまったのだ。瑠璃羽とうりふたつの女を……」
幻馬のガラスのような金色の瞳がねっとりと絹香をとらえ、離さない。
「ま、まさか」
両手で顔を包みこまれ、眉間の不思議な刺青が間近に迫った。白い唇が絹香の唇に重ねられた。
「何をなさるの!」
幻馬の白い衣の胸を突き飛ばした。
「その少し前に、宮大工の若者に出会ってな。我は釣り人のふりをして沼の縁に座っていたのだが。宮大工がえらくご機嫌なので、『何か良いことがあるのか? 』と尋ねたら、もうすぐ婚姻届けを書くというではないか。それで、我は書き方を教えてやった。正座して毛筆で書かねば幸せにはなれぬとな」
「あ、あのバカ」
木綿太に一発、ゲンコツしてやらねば。
「練習をして正座して毛筆で書けば、幸せは約束されたも同然だ。幸せにな。おめでとう。そう言って宮大工の若者とは別れた」
「……」
「知っているか、娘。祝福とは呪いだ。……嫉妬する者にとっては」
絹香の全身が凍りついた。
第 六 章 海岸にて
「幻馬……。あ、あなたはもしかして」
唇をわななかせて絹香は尋ねた。
「―――もしかして?」
幻馬の黄金の瞳がまっすぐ向かってきた。
「私たちの結婚を邪魔するために、木綿太にウソを教えたの? 昨夜、台風が来ることも知っていたの?」
「違うな。あの若者にいい加減なことを言ったが、昨夜の嵐は、台風ではなく我が起こしたものだ」
「な、なんですって!」
「瑠璃羽にうりふたつの不思議な娘よ、我を誰だと思うておる。天と海と地を支配する竜神ぞ。嵐のひとつやふたつ、呼べないでなんとする」
黄金の瞳の中に、強風に翻弄される木綿太の姿が見えた。
「ひどいわ! 竜神だかなんだか知らないけど、人の幸せの邪魔をするなんて」
「瑠璃羽をもう一度抱けるのならば、どんなこともしようぞ」
「私は瑠璃羽じゃない。元の世界に戻してよ! 戻るわ」
「戻れるものならな」
「戻ってみせるわよ」
岩屋から上に通じる細い通路を、絹香は必死で両手も使って岩を掘り進み、よじ登っていった。
指に血をにじませ、大きな岩を掘り返した時、光が入ってきた。
「やったわ!」
地上へ出られたと思い、這い出て周りを見回すと、そこは山の中ではなく、水平線の見える海岸だった。雲から天使の梯子の光が何すじかが降り、神々しい情景だ。
嵐が去り、静かに打ち寄せる波の浜に呆然と立った。
「ここは……」
背後に、銀色の長髪をなびかせて幻馬が立っていた。
「この海の向こうに天帝様がおわされる」
「てんてい様?」
「天帝様こそ天界の神。宇宙のすべてを治める存在。宇宙の黄金律の番人。――どうやら天帝様が降りてきたようだ」
幻馬の手には、新郎の欄に書いてしまった婚姻届の用紙が握られている。
雲の間の光から、なにか大きな存在が浜辺へ降りてきた気配がした。幻馬は砂浜に、かしこまった所作で正座した。
「天帝様……」
絹香はただ呆然と眺めていた。
「娘よ。天帝様が保証人になって下さるそうだ。これで我らは夫婦になれるぞ」
「――いや! いやです! 私は人間。あんな沼の底に閉じ込められるなんて真っ平よ!」
かぶりを振りながら、絹香が後じさろうとするのを、幻馬が力強い腕でつかんだ。
「許さぬ。お前は瑠璃羽の生まれ変わりだ。今度こそ一生、添い遂げる運命なのだ」
「イヤよ! 私は木綿太と結婚するのよ!」
キラキラしていた彼方の海面が鈍い灰色に変わった。
「幻馬よ――。その娘がお前の婚約者か」
なんと重々しい声だろう。低い雷鳴のような。
「拒否しておるのではないか」
「ほんの気まぐれです。この娘も我を慕うております」
「そうかのう、竜床沼の普請中の神社に携わっていた若者が、先ほどから熱にうなされながらも、余の心に訴えておるのじゃが」
「え?」
幻馬も絹香も耳をすませた。
「絹香、絹香、とな。その娘のことであろう。このままでは、余が婚姻届の保証人になることはできぬな」
「天帝様!」
「若者が高熱にうなされて娘を呼んでおるのだぞ。すべての世界を統べる余が、一組の恋人たちを引き裂くことはできまい」
「では、私の思いはどうなってもよいと申されるのですか、天帝様!」
「そなたは、聞かん坊なところがあるからのう」
あごひげを生やした初老の男が、海岸に姿を見せた。黄檗色の衣を身にまとっている。
「天帝様……ですね。お願いがございます」
絹香はその場に丁寧に正座して頭を下げた。
「何か武器をお貸し下さい。ちゃんと通用する武器を」
「むむ?」
天帝が怪訝な顔をした。絹香は砂浜に棒切れで小さな絵を描いた。その絵はすぐに波が消していった。
「ふむ、よかろう」
天帝はあごひげを触って頷いた。同時に、絹香の腕の中にはずっしりと重い剣が現れた。
「じっとして!」
絹香の持った剣の切っ先は、幻馬の喉元にぴしりと当てられた。
「私を人間界に戻しなさい。さもなくば」
幻馬のあごの下で剣の刃がぎらりと光った。絹香が砂地に描いた絵は、竜に×印をつけた絵だったのだ。
第 七 章 天帝の声
「しっかりせい、木綿太!」
棟梁の声が聞こえた。
「木綿太さん、大丈夫ですか?」
(ああ、これは誰の声だっけ? そうだ、神社の宮司さんだ)
思った瞬間、木綿太は意識を戻した。
「大丈夫か? 熱は退いたようだが」
「ああ、棟梁」
「お前、台風の最中に神社の屋根で婚姻届けを書くと言ってきかずに、風に飛ばされて一晩中、絹香さんを探しに行き、熱を出して寝こんでおったんだ。ここは神社の社務所の部屋だ」
「婚姻届け……。そうだ、絹香は?」
棟梁は首を振った。
「あの夜から行方不明だ。お前も沼の周りを探したのだろう」
「行方不明のまま……! 絹ちゃん……!」
布団を握りしめて木綿太は悔しがった。
「木綿太さん、ちょっと神社の本殿まで歩けるか?」
宮司さんが言った。
「実は、ご神体の鏡から声が聞こえて、あんたを呼んでいるのだが」
「ええっ? なんと言われました? 宮司さん」
「宮大工の若者、木綿太を呼ぶようにと」
木綿太も棟梁もたまげた。
本殿は、まだ普請途中で完全に出来上がったわけではないが、嵐には耐えて雨漏りひとつしていなかった。
広さは五十畳くらいだろうか。つるつるの檜の床の奥に神棚がある。棚にまん丸の鏡が鎮座している。
「あの鏡から声が聞こえるって本当ですか?」
熱が下がったばかりの足取りだが、木綿太は棟梁と一緒に本殿までやってきた。
嵐から丸二日経った夕方のことである。
「本当に聞こえるんですよ。この鏡は沼のほとりから出土したという古い鏡ですが、磨いてみると新品のようでしょう?」
「本当だ。俺の顔もよく映る」
「私も同じく」
宮司は言い、
「でも、声が聞こえてくるのは初めてなんですよ」
「……」
一同、静かにして耳をすませた。
「木綿太、これへ参ったか」
だしぬけに男の声がしたので、木綿太たちは飛び上がった。棟梁と宮司は素早く、木綿太の背中に隠れた。
「はあ、ゆ、木綿太ですが、あなたは?」
「わしは万物を統べる天帝だ。この度は竜床沼の神社の普請、ご苦労じゃった。ほぼ完成じゃのう」
「は、はあ」
木綿太と棟梁と宮司は顔を見合わせた。
「ところで、そなたはもうすぐ嫁を迎えると知った。婚姻届けを書かねばならぬのじゃろう。わしがそなたの正座の出来ぐあいを見て進ぜよう」
「は?」
「婚姻届けを正座して毛筆で書くのじゃろう?」
「はあ、書いていたのですが、風に吹き飛ばされちまいまして」
「では、もう一度書くのみじゃ」
外から走りこんできた者がいる。
「もう一度、書くことができるのですか!」
絹香だった。屋根に登っていた時のワンピース姿のままで、泥だらけだ。
「絹ちゃん!」
「木綿太さん! 熱が下がったのね」
「絹ちゃんこそ、無事だったんだな!」
木綿太は、絹香の細い身体を抱きしめた。
「嵐でひどい目にあったのよ。ほら、泥だらけでしょう。――それより、天帝様っ!」
絹香は神棚の一番前に、グイと出てきて鏡に向かって叫んだ。
「婚姻届けを間違えても、もう一度書き直してもよろしいのですか?」
「竜のウロコの用紙のじゃろう? 新しいのに書けばよろしい」
鏡の中の声は答えた。
「幻馬という竜神様が、書き直しはきかぬから、天帝様に提出してから離婚届けを出すしか仕方ないと言ってましたが。それも百年経ってからでないと受理されないとか」
「いや、すぐに書き直してもよいぞ。幻馬がそのようなことを?」
「なんですって? 本当ですか、それは。天帝様!」
「まことじゃ」
「あの竜神てば……っ。今度会ったら覚えてらっしゃい! いや、会いたくないけどっ」
絹香の眼が沼の方角を睨みつけた。
第 八 章 瑠璃羽の魂
水がひたひたと押し寄せる沼の汀に、絹香は立っていた。仁王立ちになって大地を踏みしめていた。地面に杖のように差し込んであるのは、天帝からもらった長剣だ。束に瑠璃色の宝玉が埋めこまれている。
湖面には霧が立ちこめていた。
「瑠璃羽よ、本当はあの竜神を愛しているのでしょう。あなたは宝玉の中へ帰らなければならなくなり、しかたなく別れを告げた―――。いい迷惑だわ。幻馬はあなたが恋しくて、私の面影と重ね合わせてしまったのよ」
長剣を地面からグイと抜き、光る刃を目の前に持ってきた。
「おかげで、横恋慕されて婚姻届けのことを騙されるところだったわ」
刃の面に、瑠璃色の衣をまとった美しい女が映った。野に咲く花のように可憐な女だ。眼に涙をためて細い肩を震わせている。
「お許し下さいませ、どうしても宝玉の中へ戻らなければならかったのです。赤ん坊だった幻馬さまの元へおつかわしになった天帝様のご命令です」
「そうだったの。……こんな美しい寵姫を竜神の乳母に気軽につかわすものじゃないわね」
「はあ……」
「幻馬に、はっきり言ってちょうだい。私とあなたは別の魂だって」
「わ、わかりました」
湖面がざわめき、霧の彼方に幻馬が姿を現した。
絹香を見つけて湖面を飛ぶように走ってくる。
「娘、我の元に戻ってくれたのだな」
喜んで抱きしめようとしたが、絹香の手は長剣を竜神の胸に突きつけた。
「勘違いしないで。この長剣に訳を聞いて。私は瑠璃羽ではないわ」
「え……」
くるりと長剣の束を向けられて、握った幻馬は長剣を見つめる。
「そんなに瑠璃羽を愛しているなら、自分で手に入れなさい。そして二度と離しちゃダメよ」
絹香はきびすを返して、神社の方へ戻っていった。
神社の本殿では、木綿太が正座の稽古をしていた。
背筋をまっすぐして膝を床につき、静かにかかとの上に座る。ようやく滑らかに恰好よく座れるようになった。
鏡の中から天帝が見守っている。
「よし、よいじゃろう。婚姻届けの保証人の欄に書いて進ぜよう」
「あ、ありがとうございます」
沼から戻ってきた絹香とふたり、しっかり正座をして頭を下げた。
本殿の奥から、沼からの爽やかな風が吹いてきて、ふたりを取り巻いた。