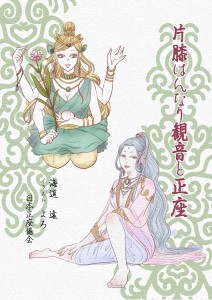[30]ウチの姉ちゃんは正座で化ける
 タイトル:ウチの姉ちゃんは正座で化ける
タイトル:ウチの姉ちゃんは正座で化ける
分類:電子書籍
発売日:2018/01/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:40
定価:300円+税
著者:久木 わこ
イラスト:時雨エイプリル
内容
実の姉が怖い。大学生の圭太は昔から姉に逆らえなかった。
そんな姉と結婚した相手は、善人を絵に描いたような心優しい男。彼が恐ろしい姉と結婚してしまったのはなぜなのか、その理由が正座にあると圭太は考えている。圭太の姉が正座によって得たものとは果たして……。
販売サイト
販売は終了しました。

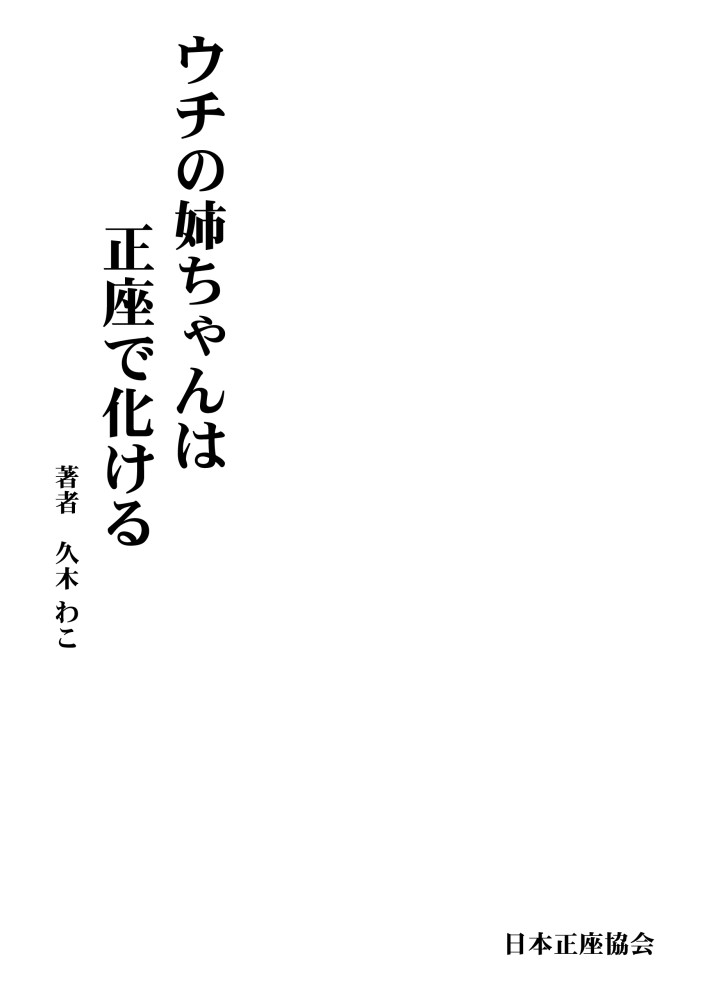
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
俺にはこの世に苦手なものが二つある。一つは歯医者だ。子供の頃からとにかく歯医者が嫌いだった。痛いイメージがあるのはもちろんその通りだが、どちらかと言うとあの音に体が拒絶反応を示している気もする。妙に高く、それでいて鈍いような、なんとも言えないあの音だ。あれはどうにかならないのか。小さな子供を泣かせるための効果音にしか思えない。
甘いものが好きな俺は、幼稚園児だった頃からしばしば歯医者さんのお世話になっていた。そして気づいた時には歯医者イコール怖いというイメージが定着していた。近所にある歯科医院に入った瞬間には恐怖の音を耳が拾う。そのせいで毎回毎回母親を困らせてきた。歯科医院の入口より先へと動こうとしない俺を、どうにかして引っ張っていこうとする母親の姿を良く覚えている。
とにかく怖い思い出しかない歯医者だが、正直なところ現在でも好きではない。歯医者が好きだなどと言う物好きな人間はそもそも滅多にいないだろう。けれど世の中に大勢いるはずの歯医者嫌い達と比べたとしても、俺はずば抜けた歯医者恐怖症であると自信を持って断言できる。それくらい嫌いだ。単なる定期検診の時でさえ、今でも若干足が竦む。大嫌いだ。
しかし俺にとっての苦手なものは歯医者だけではない。いやむしろ、歯医者よりもアレの方が遥かに苦手であると言えるだろう。盛大な恐怖心を俺に植え付けてきた歯医者より、あの恐ろしい音より、アレの方がよっぽど怖い。厳しくて手強くて残酷で、容赦も慈悲もない恐怖の存在。心の中ではこっそり大魔王と呼んでいる。俺の姉ちゃんだ。
「けいたー」
「……なに」
「コンビに行くならついでに梅酒買ってきて」
「…………」
「返事は?」
「……ハイ」
夕食後、急に甘い物が食べたくなった。うちからコンビニまでは歩いて三分で着く。小腹が空いたり甘いものが欲しくなったりした時にはとても便利な位置にある。
俺がコンビニを利用する目的の大半はスイーツだ。大の甘党である俺は酒なんて飲まない。ところがそれにもかかわらず酒を買いに行く頻度は多い。正確に言うと、買いに行かされることが良くある。買ってこいと命じるのは俺の姉ちゃんしかいない。実の姉で、恐怖の大魔王でもある、絶対無敵の理恵子様だ。
俺が成人したのは去年の六月の事。しかしそれよりもずっと前から、姉ちゃんはこうしてしばしば俺を小間使いのように扱ってきた。成人してからもそれは変わらず、むしろパシリにされる内容の中に酒のカテゴリーが増えてしまった。今もまた、姉ちゃんはソファーに座って爪を整えながら、財布を持った俺に向けて当然のように命令を付け足してくる。
「カロリーオフの方ねー」
「…………」
「返事」
「……ハイ」
コンビニスイーツよりも重大な使命を背負わされてしまった。万一カロリーオフタイプの梅酒が店になかった場合、家に戻った時に姉ちゃんから怒られるのはこの俺だ。
気のいい父さんと優しい母さんの間に生まれた俺はごくごく平凡な男に育った。大学は地元の国立大に受かって実家から毎日通っている。一人暮らしの願望がなかった訳でもないが、ここからの通学であっても特別大きな不満はない。自分で家事をやる必要がないうえに生活費の心配もいらないのだから、これはこれで有りがたいし悪くないとも思っている。しかしたった一つだけ納得のいかない点を挙げるとするなら、それは六つ歳の離れた姉ちゃんがいつまでも実家に居座っている事だ。
姉ちゃんは二年前に結婚した。それなのにまだ実家にいる。なぜかと言えば、迂闊にも姉ちゃんと結婚してしまった旦那さんがとてもいい人だったからだ。姉ちゃんに懇願されるまま、彼は婿養子となって妻の実家で暮らすことを決意した。決意させられた、と言った方が正しいのかもしれない。
鬼のような姉ちゃんには勿体ない程の優しい男性だ。姉ちゃんの弟である俺にまでいつも気を遣ってくれる。そんな良心の塊みたいな義兄がちょうど目に入ったのは、コンビニへと赴くために玄関の扉を開けた時だった。
「あ、お帰りなさい正行さん」
「ああ、圭太くん。ただいま。コンビニ?」
「はい。梅酒買ってきます」
「ハハっ。理恵子がいつもごめんね」
「いやいや、正行さんはなんも悪くないですよ」
とにかくいい人だ。姉ちゃんと結婚し、俺にとっては義兄となったこの人。今日も真面目に残業をこなしてきた正行さんは、姉からパシリにされる俺を気遣い困ったような笑みを浮かべた。
「俺が行こうか?」
「いえっ、大丈夫です。それよりはやく戻ってやってください。姉ちゃん今日、張り切って晩飯作ってたから。料理教室で習ってきたやつらしいです」
「ああ……急に残業入っちゃったからなあ。怒ってた?」
「そうでもないですね。機嫌いいと思いますよ」
「そっか。よかった」
そう言って正行さんはほっと肩を撫で下ろした。これ以上ない程の見事なカカア天下っぷりだ。正行さんは姉ちゃんに逆らおうとはしない。優しすぎるくらい優しいから、怒って反論する事さえもない。
真面目で優しくて仏のような正行さんだが、女を見る目だけは残念な事になかった。ウチの姉ちゃんは家族の贔屓目を無にしても美人だ。美人ではあるものの、中身に難が多すぎる。そうとも知らずに姉ちゃんと結婚し、この家で生活を始め、二年目ともなればさすがの正行さんも自分の嫁の本性に気づいているはずだ。しかしこの人は嫌な顔一つしない。あんな鬼のような女なのに心底惚れているそうだ。正行さんの心が広いおかげで夫婦仲はいつでも円満に保たれている。
玄関先で正行さんと別れ、俺は一人夜のコンビニへと向かった。なかったらどうしようかと案じていた梅酒はきちんと冷蔵棚に並んでいた。カロリーオフタイプの梅酒を二本手に取って、オレンジ色の買い物かごに入れた後は自分のスイーツを物色しはじめる。
俺は特段カロリーなどと言うものを気にしない。たとえ夜でも、甘いものが欲しくなれば好きなスイーツを買いに来る。しかし姉ちゃんは違う。常に自分の体重と体型を維持する事を心掛けている。だったら家でゴロゴロしていないでコンビニくらい自分で行けばいいのに。カロリーオフのアルコール飲料を選ぶくらいなら、そもそも酒なんて飲まなければいい。次から次へと姉ちゃんに対する不満は溢れてくるが、これを本人に面と向かって言える日はやって来ないだろう。俺は姉ちゃんが怖い。パシリにされても文句なんて絶対に言えないと思うくらい怖い。
俺が実の姉を恐怖の対象とするのにはそれ相応の理由がある。子供の頃から着々と構築されていった上下関係は、大人になった今でも払拭される事無く馴染んでしまっていた。
暴力を振るわれた事はない。幼かった時代も現在も、姉ちゃんが暴力に訴え出たことは一度もなかった。姉ちゃんの武器は良く回る頭と口と、そして有無を言わさぬ鋭い眼力だ。近所でも評判の才女だった姉ちゃんは無駄に頭が良く、幼いころには口喧嘩になる度に論破され続けてきた。口を噤まざるを得ない状況へと徹底的に追い込まれ、まだまだ小さかったあの頃の俺は悔しさに歯を食いしばって涙目になったものだ。
恨みの内容は多岐に渡る。あれはいつだったか、珍しく俺のためにスイーツを買ってきてくれたかと思えば甘いシュークリームの中にカラシが仕込まれていた事があった。夕食時に見たいテレビ番組が対立した場合、リモコン争奪戦で俺が勝てたことはない。姉ちゃんよりも先に俺が風呂に入れば機嫌を損ねる。姉ちゃんが愛用している高いシャンプーを使ってしまった時にはトラウマになるほど激怒された。
幼い時代からいくら記憶を辿ろうとも、俺には姉ちゃんから優しくしてもらった記憶がない。現在の俺は姉ちゃんに刃向う事は一切せず、間違っても口論になる事がないように構えている。姉ちゃんが気まぐれに買ってくるスイーツにはいまだに注意を払うし、夕食時に姉ちゃんの見たいテレビ番組がある時には進んでリモコンをどうぞと差し出す。風呂は姉ちゃんよりも後に入る。姉ちゃんの私物には何があっても触らない。
姉ちゃんに逆らわない。姉ちゃんを怒らせない。どんなに頑張っても姉ちゃんには敵わないから最初から盾をつかない。俺の中に植え付けられた服従精神とその習慣は、この先何年経とうとも変わらずに続いていくのだろう。
大好きなスイーツと興味のない梅酒二本と、ご機嫌取りのために酒のつまみも買ってからコンビニを出てきた。これを持って家に帰ったら、ありがとうとは言われると思う。しかし形だけの礼を口に出されはしても、酒のために支払った分の金を返してもらえる事はあり得ない。
草食系か肉食系かと問われれば、明らかに草食系である自分の性格を恨む。一方の姉ちゃんは問いかけるまでもなく無敵の肉食系だ。実の姉の下僕と成り下がっている現状を踏まえても、俺があの家を出ていかない限りはこの生活を続けていく事になる。
大学を卒業するまであと一年。就職と同時に家を出たい。それまでの辛抱だと自分を励ましつつ我が家に帰ってきた。部屋の中に入ってみれば、そこにはダイニングテーブルに座って遅めの夕食を取っている正行さんが。正行さんの隣には姉ちゃん、姉ちゃんの前には母さんが座り、肩身の狭い状況の中でさえ不満気な表情を浮かべるでもなく、妻の手料理をいちいち褒めちぎっている。
出来た旦那だ。出来た婿だ。正行さんの健気な姿に同じ男として悲しくなってくる。自信作の料理を正行さんに褒められた姉ちゃんは、機嫌の良さそうな顔つきで俺を見上げてきた。
「お帰りー。あった?」
「うん」
「そう、ありがと。そっちに入れといて」
「……うん」
冷蔵庫を指されて頷き、梅酒二本だけをそこに入れてからリビングへと足を向けた。テレビの前のソファーには父さんがいる。その隣に俺も腰を下ろし、コンビニ袋の中からお気に入りのカップケーキを取り出した。
袋の中には姉ちゃんのために買ってきた酒のつまみが残っている。それを横から父さんが覗き込んできた。
「柿の種か?」
「うん。姉ちゃんの」
「……そうか」
父さんの残念そうな声を聞いた。悪い事をした。もう一袋くらい買ってくればよかった。
女同士だからという事もあるのか、うちの中で唯一姉ちゃんと対等に接する事ができるのは母さんだけだ。しかしそんな母さんの人柄は温厚そのものだから、必然的に家の中で最高権力を握るのが姉ちゃんになっていた。
仮に姉ちゃんが毎日遊んで暮らしているような怠惰な女であれば、俺達男性陣にも反論の余地はあっただろう。ところがこれまた残念なことに、姉ちゃんの家事スキルは主婦歴の長い母さんにも負けず劣らず。結婚する前に勤めていた会社は名の知れた大きな会社だったし、会社員を辞めた今でも空いた時間でパートに出ている。そのうえ料理の腕を磨くために近所の教室にまで通っているときた。
寛ぐときには思いっきりぐうたらする女であるが、基本的にはアクティブで良く働くから文句の付けどころが見あたらない。姉ちゃんの怖さはこういう抜かりのない所にもあると思う。
そうやって実家で天下を取っている姉ちゃんだが、外に一歩出れば周囲からの評価は最上級のものばかりが聞こえてくる。ご近所さん達の間では、昔から礼儀正しい才女として評判だった。いつも姿勢が良く気品もあり、言葉遣いも振る舞いも丁寧な女の子だとかなんとか。大人になった今でもその評価は依然として変わらず、それどころか少女の時代を終えたことによりますます美人になっていくとまで。
そもそも正行さんが姉ちゃんと出会って結婚に至ったのも、姉ちゃんの外面の良さにまんまと引っ掛かってしまったことが原因だった。姉ちゃんが正行さんと出会ったのは三年前。二人が初めて顔を合わせた当時、俺もその場にいたから良く覚えている。
近所にある華道教室で、体験講座が実施されていたあの日。正座による足の痺れを抱えながら、二人が言葉を交わすのを聞いていた。姉ちゃんを前にして呆気なく恋に落ちた正行さんの照れた顔は、三年経った今でもまだはっきりと記憶に残っている。
2
「生け花って結構難しいですよね」
「そうですね……まさか自分でやる事になるとは……。俺は今日、姉の付き添いで来たつもりだったので……」
「あら、それなら私の弟もです。同じですね。ねえ、圭太?」
そう言ってふわりと笑いかけてきた姉ちゃんに、三年前の俺は声も出せずに頷く事しかできなかった。
顎で弟を使っている時の姉ちゃんとは百八十度人格が違う。凛とした正座姿は殊更に美人に見えた。花の前で淑やかに背筋を伸ばし、静かな所作で活けていく様子からは気品が漂う。弟の俺が言うのもなんだが、姉ちゃんほど正座の似合う日本女性はなかなかいない。顎を引いて手元に目線を落とす姿は、文句なしの大和撫子だ。家に帰ればソファーの背凭れに寄り掛かかり、堂々と足を組んでいるような女だとは到底思えない。
偽りの清楚系女子であるとも知らず、姉ちゃんの目の前でぎこちなく話していたのが正行さん、その人だった。少なくともあの時の彼は、三年後の自分が妻の家の婿養子になるとは想像もしていなかっただろう。
華道の体験教室には床一面に畳が敷いてあった。背の低い長テーブルの前に座布団が用意され、正座をして花を活けていく小一時間。正座なんて俺にとっては苦痛でしかなかったが、その間に姉ちゃんと正行さんは運命の出会いを果たしていた。
向かい合うようにくっつけられた二つの長テーブルに、俺達姉弟と正行さん達姉弟が一緒に座ったのはたまたまだ。俺の右隣には姉ちゃんがいて、姉ちゃんの正面には正行さんがいた。俺の正面には正行さんのお姉さんが座っていたのだが、女同士ですぐに打ち解けたのは見て取れた。
教室内で肩身が狭かったのは俺と正行さん。男の参加者は俺達しかいなかった。しかし正行さんがずっと居心地悪そうにしていた原因は、男性率の低さによるところではなかったはずだ。姉ちゃんとはなかなか目を合わせようとせず、俯きがちに照れている様子が嫌でも分かった。それを見た俺は心からげんなりした。この人は姉ちゃんの正座姿に騙されている。更に姉ちゃんはそんな男性を仕留めようとしている。そう確信した。
はっきり言って正行さんは姉ちゃんの理想そのものだ。顔はどちらかと言えば地味だし背格好も標準的だが、物腰は柔らかくて優しそうだし真面目そう。そして何より人が良さそう。かねてより姉ちゃんが理想の旦那像として公言していた通りの人物だった。
姉ちゃんは外堀から埋める事にしたのかなんなのか、正行さんのお姉さんからも早々に好印象を勝ち取っていたようだった。正行さん本人にも控えめながら愛嬌を振り撒き、着実に落としにかかりながら花を活けていた。
姉ちゃんが正行さんの目を決定的に奪ったのは、体験講座を終えて立ち上がった時だと思う。一時間ほどずっと正座をしていたにもかかわらず、姉ちゃんは淑やかな様子で滑らかに腰を上げた。スッと綺麗に立ち上がったその姿を、正行さんは半ば呆然としながら座ったまま見上げていた。そんな正行さんを急かしたのは彼のお姉さんだ。何ボサッとしてんのよと、少々きつめの小言を食らっていた。どこの家でも弟に対する姉の態度なんて似たようなものだ。俺と同じく姉に逆らえないらしい彼は慌てて立ち上がろうとしたものの、しかし途端に足元をふらつかせた。
どうやら相当に足が痺れたらしい。赤くなった顔を苦痛にゆがませ、あせあせしながら姉ちゃんに向けてぎこちなく笑いかけていた。
「あ……ハハ……。すみません……」
「ふふっ。正座に慣れていないと痺れちゃいますよね。大丈夫ですか?」
姉ちゃんがふふっと笑った事に俺は引いた。正行さんに差しのべられた姉ちゃんの手は、決して優しさに満ち溢れたものではない。あれは計算高い女が将来の婿候補を捕獲しようとしている手に違いなかった。
いい女は正座をしても足が痺れない。いつだったか聞かされた姉ちゃんの名言だ。正座をするような場に赴く時、姉ちゃんはできる限り膝下丈のフレアスカートを履いていく。座る時には尻の下にスカートを敷くように、軽く手で押さえながらゆっくりと腰を下ろす。その振る舞いは誰が見ても文句のない上品なものだ。外から見えないスカートの下では膝と膝の間に多少の間隔を開け、周りに気付かれる事無く時折重心を片足ずつ移している。そうすれば痺れないらしい。
正座をしている時も、正座を長時間続けた後に立ち上がる時も、最初から最後まで凛々しく美しく、花のように清楚であるべき。周りを化かしにかかる姉ちゃんによる恐ろしいモットーだ。正行さんは見事に落ちた。
3
姉ちゃんが正座を完璧にマスターしたのはずいぶん幼い頃だった。俺も母さんから聞いた話だが、法事に連れて行ってもお稽古事を習わせてみても、姉ちゃんが正座を嫌がる事は一度たりともなかったらしい。
自分がどうあれば周りからの印象が良くなるのか、姉ちゃんは幼少期のうちから心得ていた。というのはさすがに言いすぎであり、実際のところがどうなのかは俺にも分からない。しかし少なくとも高校生の頃には、正座姿が周りから良く見られているという事実に姉ちゃんも自分自身で気づいていたはずだ。
正行さんとの出会いのきっかけともなった華道だが、実は姉ちゃんは初心者ではなかった。高校の時に三年間、華道部で活動していたのだ。
姉ちゃんが通っていた高校は頭のいい人間が集まる共学の進学校で、勉強も然ることながら部活も熱心に取り組んでいるような所だった。部活動のために用意された教室もいくつかある。和室はその一つだ。姉ちゃんが入っていた華道部では毎日畳の敷いてある教室で活動をしていて、文化祭などの催し物がある時にも和室を展示場として使用していた。
姉ちゃんが高校生の時、俺はまだ小学生だった。けれど今でも記憶の中にしっかりと残っている。女子高生時代の姉ちゃんが、周りの人間達から惚れ惚れとした注目を浴びていた光景を。
姉ちゃんの高校で、一般にも開放される文化祭が行われたのはとある日曜日だった。母さんと一緒に俺も遊びに行き、もちろん姉ちゃんが活動している華道部のブースにも足を運んだ。華道部では作品の展示以外にも、実演公開をしたり体験コーナーを設けたりしていた。
俺と母さんが華道部の教室に行ったのは、ちょうど姉ちゃんが生け花の実演をしている最中だった。文化祭と言う事もあり、部員はみんな和装をしていた。
着物姿で正座をしつつ、観衆がいる目の前で丁寧に花を活けていた姉ちゃん。いつもの姉ちゃんではなかった。華道部なんて地味だし目立たないとばかり思っていた俺のイメージも同時に払拭された。なぜなら皆が姉ちゃんを見ている。部室に集まる観客の多さと言ったらない。男子生徒も女子生徒も、正座で花を生ける姉ちゃんに沢山の人が注目していた。衝撃的だった。
姉ちゃんが家で正座をする事はほとんどない。リビングではソファーに寝そべるし、ダイニングではテーブルとセットの椅子に座るし。洗濯物を畳むときでさえ、ソファーに座ってテレビを見ながらだ。
親戚が集まる時には俺も姉ちゃんも正座をするが、こうもまじまじと姉ちゃんの正座姿を目にしたのはおそらくこの時が初めてだっただろう。観衆が見惚れるのも頷ける。着物の効果も相乗し、姉ちゃんはとにかく綺麗だった。着物と正座の相性がいいのはもちろんで、姉ちゃんの所作もそれに見合うものだ。だから尚のこと、花と姉ちゃんと着物と正座は全部まとめて上質な光景に見えた。
元々極めて外面の良い女ではあるが、正座をする事によって姉ちゃんは人を化かしている。もはや妖怪か何かに思えた。それくらい衝撃的だった。家の中では男よりも気が強く、弟の俺を下僕扱いしているくせに、ひとたび正座をしてしまえば完璧な大和撫子に成り代わった。
4
「正行さんは姉ちゃんのどこに惚れたんですか?」
「えっ?」
姉ちゃんと母さんは朝から二人でショッピング中だ。父さんは仕事仲間と趣味のゴルフへ出かけている。他の家族が出払った休日の正午過ぎ、正行さんと一緒に昼飯を食べながら何とはなしに問いかけた。
正行さんは俺の唐突な質問に箸を止め、照れたように笑っている。結婚して二年経ってもこの調子なのだから、この人が姉ちゃんに逆らえないのも仕方がない事なのかもしれない。惚れた弱みと言う奴だ。あんな恐ろしい姉でも、良い旦那さんに恵まれた事は弟として素直に嬉しい。
「姉ちゃんのこと、怖くないですか?」
「うーん……。どうだろうね。全部含めて理恵子だからね」
模範回答が返ってきた。正行さんの場合は決して上辺ではなく、本心で言っているのだから尊敬する。こんなにいい人を婿にするとは、姉ちゃんはよっぽどの目利きなのだろう。
「姉ちゃん割となんでもできるけど性格がいいとは言えないと思うんですよ。正直なとこ、あの顔に惚れた感じだったりします?」
「カオ……ああ……まあ、美人だからなあ。でも俺はどちらかと言うと正座姿が……」
「正座?」
聞き返すと、正行さんは懐かしそうな顔を浮かべた。俺の脳裏にも昔の記憶が蘇る。三年前だ。姉ちゃんと正行さんが初めて会ったとき。背の低い長テーブル越しに、正座で向かい合っていた二人。
「あんなに綺麗な正座ができる女性を生れてはじめて見たからね。大和撫子は実在したんだって、あの時は本気でそう思ったよ」
「…………」
「うん。いいよ、笑って。すごく単純だよね。自分でも呆れる」
「あ、いえ。なんか……ありがとうございます。姉ちゃんと結婚してくれたのが正行さんで良かった」
「そう?」
嬉しそうにニコリと笑った正行さん。こう言ってはなんだがチョロすぎる。正座からすくっと立ち上がった姉ちゃんを見上げていた時の、呆けたような正行さんの表情は恋に落ちた瞬間の男の顔だった。
姉ちゃんはやはり魔王であり妖怪だ。正座一つで人の目を騙し、化かした相手を婿に引き入れる事まで成し遂げる。
丁寧な振る舞いと、それを引き立てる正座は姉ちゃんの武器だろう。あれから三年経ってもなお、旦那の心を掴んで離さない。
「洗濯物とか畳むときにさ、理恵子は必ず正座するんだよね。その時の仕草がやっぱり綺麗だから、いい奥さん持ったなあって」
「……え?」
さり気なく惚気を放り込んできた正行さん。俺はその言葉に首を傾げた。
洗濯物を畳むときの姉ちゃんは、ソファーに座ってテレビを見ながら手を動かしているイメージが強い。けれど思い返してみれば確かに、姉ちゃんでも時々は家の中で正座をしている。カーペットの上で正座して、膝の上で洗濯物を丁寧に畳む。そんな上品な動作を見せるのはどういう時かと考えると、必ず部屋の中には正行さんがいるような気がする。
「…………」
わざとだ。あの女は全て分かった上でやっている。その事にいま、ようやく気付いた。
「……正行さん」
「うん?」
「姉ちゃんのこと、これからもよろしくお願いします」
「えっ、どうしたの改まって」
俺が急にぺこりと頭を下げたせいで、正行さんはギョッとして戸惑ったような声を出した。俺も実は困惑している。姉ちゃんの中にある女心を、思いがけず知ってしまった。
姉ちゃんが正行さんの前で正座をするのは、正行さんの気持ちを繋ぎ止めておくためだ。正座をすると上品に見える。正座をすれば清楚に見える。正座をしながら洗濯物を畳んでいれば、正行さんが見てくれる。それを理解している姉ちゃんだから、正行さんの前でだけはマメに正座をするのだろう。
「……まさか正座にこんな効果が……」
「なにが?」
「いえ……ひとり言です……」
「……圭太くん、大丈夫?」
心配されてしまった。しかし俺が心配なのは正行さんの方だ。本人が幸せならばそれでいいけど、疑う事を知らない正行さんは妻の策略にも決して気付けないと思う。
姉ちゃんはきっと正行さんを離さない。正座の効果をフルに活用して、いつまでもヤマトナデシコを演出し続ける。姉ちゃんが正座をしている限り、夫婦の仲は生涯に渡って円満であるはずだ。
すごいのは正座だろうか。それとも姉ちゃんの方だろうか。どちらなのかは分からないが、ウチの姉ちゃんは正座で化ける。




![[271]お江戸正座](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)