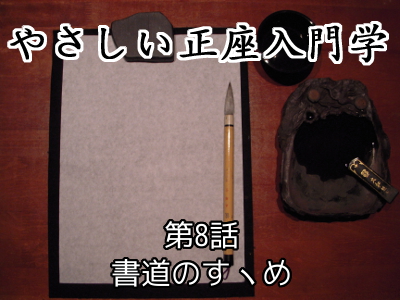[271]お江戸正座
タイトル:お江戸正座
掲載日:2024/01/23
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:1
著者:虹海 美野
内容:
文左衛門は江戸の戯作者としての第一歩を踏み出した。
師の元で学び、生活をしていたが、食事の時に正座で足をしびれさせ、師のお嬢さんを巻き込んで盛大に転ぶという失態を機に、一人暮らしを始める。
そこへ師のお嬢さんの友達のおようがやって来て、文左衛門のこれまでの経緯を聞き、正座を教えてくれる。
自分の情けなさにしょげかえる文左衛門をおようは励ましてくれる。ささやかに心の通じ合った文左衛門とおようだったが……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
文左衛門は茶葉を売る『諏訪理田屋』の七男坊であったが、戯作者を志し、家を出た。
御年十九にしての、一応の独り立ちである。
はじめの頃は師と仰いだ初老の男の元へ身を寄せた。だが、戯作者としての勉強をするため、さまざまの資料を読ませてもらえたり、師と戯作に関する話ができるのはよかったが、居候の身である。師には妻と二人の娘がいて、ちょっと夢のある話なら、その娘と恋仲になり……、という展開もあったかもしれぬが、現実はそう甘くはない。厠を使って出てくれば、娘が迷惑そうな顔をして、庭の花に水やりをしている素振りで待っているし、食事の時には狭い部屋で顔を突き合わせるので、互いの咀嚼も、師のげっぷも全てを分かち合うわけである。師の元で世話になるのが決まった時には、長兄がそれなりの金銭を持たせてくれ、それを文左衛門は全て師に渡した。だから肩身の狭い思いをする必要もなければ、厠を使用して迷惑がられるいわれもないわけである。
まあ、言ってみれば、師の家は居心地が悪かった。
決定的だったのが、膳を前に正座でいただいていた中、いつもより文左衛門の座る場所が狭く、こういう時に限って師が戯作に関する話に長じた折である。ようやく師の話が済み、膳を持って立ち上がった際、足が冷たくなるほどにしびれていることに文左衛門は気づいた。気づいた時には遅かった。茶をすすっていた師の娘にぶつかり、そのまま障子に倒れこみ、障子もろとも廊下から中庭へと転げ落ちた。
即座に師の妻が茶碗が割れたことを嘆く声が聞こえた。
悪い人ではない。
だが、身内の中に他人が入るというしんどさに堪えていた師の家族もまた、辛抱を強いられていたのは間違いなかった。
ああ、出て行こう、と文左衛門はこの時思った。
文左衛門が師の家を出ると申し出て、止める者はいなかった。
師が餞別にと、この先役立ちそうな本をたくさんくれた。それから師に納付した金銭の元の十分の一ほどの額と、米もこっそりと持たせてくれた。
そうして文左衛門は、もう人と近い距離で暮らすのはごめんと、古く小さな家を借りた。窯を入れ、畳を入れ、引き戸の紙を貼り、どうにか文左衛門一人暮らしていける住まいが整った。今後の生活の見通しについては、師が責任を感じてか、通いでよいとの条件で、師の懇意にしている版元で手伝いをする仕事の口利きをしてくれた。その傍ら、版元で書き手が足りぬというので、これまた師の口利きで書かせてもらえるようになった。
ようやく自分の名で本を出してもらえることになり、それならば名をどうするかと師に尋ねられ、文左衛門は迷わずに実家の茶葉を扱う店の屋号である諏訪理田と名乗ることを決めた。こうして諏訪理田という、洒落気も風情もあまり感じられぬ名の戯作者が江戸に誕生した。そうはいっても、まだ作が生まれてはいない。
さて、どうしたものかと文左衛門は昨日米を炊いた窯を覗いた。
おひつに移すのを忘れた窯の飯をどうにかこそげとっているところへ、ごめんくださいまし、と高らかな声がした。
「はい」と文左衛門は顔を上げた。
そして、「あ」と小さく声が漏れた。
師のお嬢さんのお稽古仲間のおようさんであった。
師のお嬢さんは、お稽古仲間などの友達を家に招く際、いつにも増して文左衛門を邪険にした。師や妻にはわからぬように、廊下などですれ違う折に「とっとと出かければいいのに」などと独り言を装って、文左衛門を攻撃する。もともと商いをする家の末子であるから、今こっちへ入ってはいけませんとか、暫くそっちで遊んで待っていなさいなどと言われて大きくはなったが、やはりよそ様と身内とでは、その言葉や内容に温度差があった。だから、なるべく師の娘がお稽古事から帰って来る時刻には師の仕事部屋から出ぬようにし、文左衛門は息をひそめたものである。そうした気遣いがなくなったとせいせいしていたところへ、この来客。どうしたものか……。
そもそも、男一人が暮らす、お世辞にもきれいとは言えぬ家に、妙齢のお嬢さんを上げていいものか。考えあぐねている文左衛門に、おようは「独立されたと聞きまして、お祝いにでもと思ったのですが、粋人の方のお眼鏡にかなうものがわかりませんでしたので、こちらを作って参りました」と、包んだお重を見せる。
ここで暮らしてからというもの、物売りもあまり通らぬ住まい故、買いに出るのも億劫で、文左衛門はここのところ茶漬けばかりを食っていた。そこへ、何やら食べ物を詰めたお重がやって来て、つい、文左衛門は「狭いところですがどうぞ」と、おようを通してしまった。
まあ、隙間だらけの家である。
戸も半ば開けておいた。
おようは「お邪魔いたします」と草履を狭いたたきに揃えると、畳んだ布団を奥に押しやった大層狭い部屋にちょこんと正座した。
「今、茶を淹れます。茶屋の倅だけあって、茶だけは良いものがいくらでもあるのですよ。まあ、私としては茶より腹が膨れるものの方がよいのですが」と、湯を沸かしながら軽口のつもりで言い、「それは丁度ようございました」とおようが答えた時に、まるで催促しているようだと恥じ入った。
座布団もない部屋に古い畳で申し訳ない思いで、湯が沸くまで、文左衛門はじっと、茶を淹れるのにちょうどよい温度になるまでの時間を待っていた。文左衛門はいつもより慎重に茶を淹れた後、たたきのすぐ傍に小さく正座をした。一緒に茶を飲みたいところだが、湯のみはひとつしかなかった。
狭い部屋で向かい合わせになると、おようが「よろしかったら、召し上がりませんか。私が作ったもので、あまり自信はありませんが」と自ら包みを解く。
「ああ、ありがたい」と、文左衛門は欠けた皿と、先が折れて長さの違う箸を持ち、おようが並べてくれた重箱を眺めた。
根菜類の煮物に佃煮はあさりと昆布の二種類、米は白米のおにぎりのほかに、稲荷ずしまである。
「これはすごい!」と目を輝かせる文左衛門に、「それにしても、一体どうしてこちらで暮らすようになったのですか。前の暮らしなら炊事も洗濯も困らなかったでしょう」とおようが言う。
文左衛門は暫し黙り、「正座がいけなかったのです」と小さく打ち明けた。
「正座、ですか」
おようはきょとんとして文左衛門を見る。
「はい。もともと四人で暮らしていたお宅に私が入り、五人での食事になります。そうすると、これまで四人では悠々とした場も、自然と詰めなければいけなくなる。その日、私はいつもより端に座していました。いえ、あのように良くしていただいて、部屋の広さがどうのと言うのではありません。ただ、正座をしていて、その時間がいつもよりも長く、膳を持って立ち上がった際に、もうお詫びのしようもないほどの失態をいたしまして。それで、ああ、これ以上ご厄介になってはいけない、と思い立ったのです」
「はあ……」
おようはわかったような、わからぬような顔をしている。
「つまり、正座をした状態から、何か、文左衛門さまのおっしゃるところの失態をしてしまった、と」
「その通りでございます」
文左衛門は箸をひっこめ、うなだれた。
「今さらながらですが、私、今度お武家様の元へご奉公に参ることになったのです。その前に礼儀作法も心得ておこうと思いまして……」
「はあ」
「私にできることと申したら、それくらいですけれど」
そう言うと、おようは、「戯作者の先生ですから、どうしても前かがみになると思うのですが、背筋を伸ばしてみてください。柱に背をつけてみると、どのくらい普段背をかがめているかわかると思うのですが。それから、脇をしめるか、軽く開く程度で、膝もつけるか、握りこぶし一つ分開くくらい。穿いているお召し物は広げずに、お尻の下に敷いて、足の親指同士が離れぬように。手は膝と太ももの間に、履物の鼻緒のような感じで指先同士が向かい合うような形で置いてください」と、正座について簡潔に指南してくれた。
「はあ、なるほど」と文左衛門は背筋を伸ばした。
茶葉を売る兄や奉公人は客相手で腰は低かったが、確かに猫背ではなかった。
手代たちはお仕着せの羽織に皺のできぬ、よい姿勢であった。
文左衛門は大きく息をつき、しょげかえった。
「私には観察眼というものが足りていない。戯作者として、これほどの痛手はありません」
「そんなことはございません」と即座におようが言う。
「朗らかで、穏やかであることがどれほど尊いか。文左衛門様はご自身の良さに気づいておられぬのですよ」
「はあ」と文左衛門は、よくわからぬ顔で一応相槌を打つ。
「せかせかと動き回り、周囲の顔色ばかりを気にして、それが何になりましょう」
それができなかったから、私は師の家を出たのだ、と思ったが、文左衛門は黙っていた。
「私は、時折文左衛門様とお顔を合わせるのが楽しみでございました。いつも、いいお天気ですねとか、今日は花の香が漂って心地よいですねとか、明日は雨でしょうか、しっとりとした空気ですねとか、そんなふうに自然に五感を向けて目を細めているさまは、まるで猫のようにかわいらしく、高貴で……」
かわいらしく、高貴であるなら、それはおようさんのことだ、と文左衛門は思った。
いいおうちの娘さんで、豪奢な着物に髪をきれいに結い上げているが、鼻にかけることなく、むしろそれを消し去るような、清廉で、邪気のない美しさがある。生まれながらに気品を備えた猫のようである。
それをどう伝えたものか、と文左衛門はもじもじした。
「長居をいたしました。そろそろお暇いたします」
そう言うと、おようは文左衛門の淹れた茶を飲み、「おいしい」と呟き、「文左衛門様と今日お話できたこと、こうしてお茶を淹れていただいたこと、おようは忘れません。お武家様の元で精進いたします」ときれいな正座に三つ指揃えて、目を伏せた。
文左衛門が「なんのお構いもできませんで」と、頭を下げると、おようはそっと立ち上がり、文左衛門の家を出て行った。
文左衛門は暫しぼんやりとしていた。
2
おようが持って来てくれた大層おいしい差し入れを二日かけてありがたくいただき、文左衛門が湿った布団で寝ていると、「さっさと起きなさいよ」と鋭い声がした。
嫌な記憶が甦る。
顔を上げると、勝手に引き戸を開けてそこに立っていたのは、やはりおようの友であり、師の娘、その人であった。
「この前、おようちゃんが来たでしょう」
文左衛門は「はあ」と頷く。
「おようちゃん、明日にはご奉公に行くから。その前に重箱を返しに行ったら?」
ここでようやく、文左衛門は師の娘としては悩みの種であっても、おようの友達としてはこの娘は優しいのだと気づいた。
「おようちゃんの家は、うちがお世話になっている版元の二軒先よ」
それだけ言うと、師の娘は踵を返して去って行った。
文左衛門は慌てて床から抜け、戸口から「お嬢さん、ありがとうございます」と声をかけた。師の娘は一度だけ振り返り、大層嫌なものを見たといった顔ですぐにそれを逸らした。ふと自分の着物の下をみれば褌がよく見える状態であった。
文左衛門は身なりを整え、途中で櫛と花を買い求め、おようの家を訪ねた。ただ文左衛門と名乗るのは心もとなく、師の名を借り、その弟子だと名乗った。
師の信用とともに、師の娘とおようが親交があることを知るおようの家族は、師の娘からの用事を頼まれ、お遣いで文左衛門がやって来たと思ったのか、すぐに茶の間に文左衛門を通してくれた。
驚いた様子で茶の間に来たおようは、「文左衛門さん……」と、その名を呼んだ。
文左衛門は「背筋を伸ばし、脇はしめるか、軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は鼻緒のようなかたちで太もものつけ根と膝の間に置く。足の親指同士が離れないようにする、穿いているものは広げずにお尻の下に敷く、でしたね」と正座をして、おように話しかけた。
「ええ……」
「この度は、お武家様へのご奉公が決まり、おめでとうございます。ご奉公が明けて、もし、茶が必要でしたら、いらしてください」
お武家様に奉公する娘の嫁ぎ先は、大きなお店や裕福な家と相場が決まっている。少しでもよい嫁ぎ先を探すための奉公と言っても過言ではない。そんな娘が寂れた家に住む戯作者の元へ来るとは思えなかったが、文左衛門はそう告げた。茶が必要ならば、文左衛門の実家でも、ほかでもいくらでも手に入る。それでも、一縷の望みを託し、文左衛門はそう告げた。例え、今文左衛門と心が通じても、奉公明けのおようの心が同じではないかもしれぬことも重々承知である。
だがおようは、「はい、伺わせていただきます」と答えた。
目を上げた文左衛門をおようはしかと見つめ、「必ず」と続けた。
3
文机を前にした文左衛門は筆を取った。
作の題名は『娘と花と猫』。
一人住まいの寂しい男の元へ、ある日お重のご馳走が届く。
そこに人の姿はなく、ちょうど高貴な風情の猫がいて、男はまさかといぶかしながら、自身に同情した猫が、どこからかご馳走をくすねて男の元へ届けてくれたのではと考える。
そうして、男は家の軒先にご馳走の詰められていた重箱、それに花と煮干しを一つづつ置いた。
かたり、と音がして、男が引き戸を開けると、そこには煮干しをくわえた先日の猫だけがいた。
男が下駄も履かず、町までの道を走ってゆくと、そこに花と重箱を手に歩く、可憐な娘がいた。
そんな話である。

![[336]お江戸正座20](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)