[303]水占師と水車の繰り女(くりめ)の正座
 タイトル:水占師と水車の繰り女(くりめ)の正座
タイトル:水占師と水車の繰り女(くりめ)の正座
掲載日:2024/08/07
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
山深い水郷。毎日、河に舟を漕ぎ出す青年と少女の姿があった。
青年は川面に形代を浮かべて占う水占師(みずうらし)の翠嵐(すいらん)。流里鈴(るりりん)という女の子はどこの子だか、いつの間にかついてくるようになった。農夫の牛の背中にも綺麗に正座する。ある日、澄んだ河の水が真っ黒になっていた。

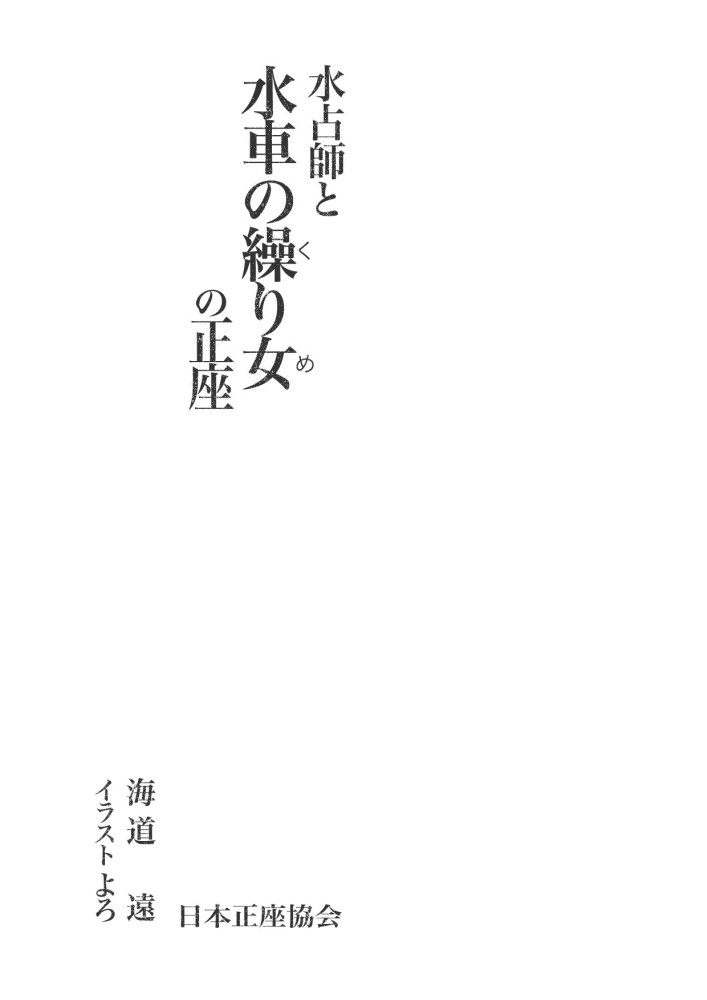
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 水占い
緑の高い山々に囲まれた水郷。
白い鷺が河面をすれすれに滑空していく。まだ太陽は昇りきらない。
霧が立ち込めた船着き場が見える。
水占師の青年が長い髪を垂らし、青く長い衣を引いて提灯を掲げ、いつものように少女を連れて河に向かう。
老農夫が煙草をふかしながら、牛の背から声をかける。
「ご苦労さまですのう、水占師さま」
「……私にできる、ささやかな務めですから」
人々が託していった形代(かたしろ)の紙片が、数枚ばかり青年の手に握られている。
「時に、後ろにいつも連れていなさる小さなおなごは妹さんかい? 娘っ子かい?」
水占師の腰くらいの背丈の女の子が、チラリと老農夫に目をやる。前髪の下から覗く黒目がちな瞳は、少女のものと思われない強い光を讃えている。
「……どこの子か知らないのだが、かなり前から私の後をついてくるのだ」
「ほう、知らない子……」
老農夫は、白い眉毛の下の小さい目を見開いた。
「おじいさん、牛の上で正座ができる?」
「正座?」
女の子は牛に飛び乗って、藁座布団の上でまっすぐ立ち上がり牛の背に膝をつき、着物をお尻に敷き、かかとに座った。
まるで、牛の上にお人形が座ったようだ。
「こりゃあ、たまげた。デコボコの牛の背によくぞ座れることだ」
女の子はツンとして、
「水占師さまが小舟に座る時の真似しただけよ」
「流里鈴(るりりん)、行くぞ」
水占師が声をかけると、女の子は牛の背から飛び降り、
「おじいさん、あたいの祖父ちゃんに少し似ているわ」
言い残し、子犬のようにころころと駆けていった。
「河は静かに見えても恐ろしく深く、いつ氾濫を起こすかもしれん。気をつけて参られい」
背後で老農夫の声がした。
小舟に正座した水占師は、河面に浮いた水草(みずくさ)に形代を乗せようとして異変に気づいた。
「どうしたことだ、これは。いつも澄み切っている水が墨を流したように真っ黒とは……」
「きゃあ! すっごく冷たいね。凍っているよ!」
流里鈴も河の水に指先を入れて叫んだ。
第二章 繰り女の洞穴へ
水占師の務めは河に小舟を出し、水草に形代を浮かべて占いをすることである。形代に息を吹きかけ、願い事を念じる人々の形代を水草に絡めて占い、願う。
形代とは、紙で作られた人のカタチをした人間の身代わりである。
子どもの病を平癒祈願する親。
親の病を治してやりたい子。
干ばつや冷害に苦しむ農民が農作物を作れるようにとの願い。
弟子入りしても、うまくいかない人が道を見つけたい願い。
水占師は、それらの願いを込めた形代を水草に絡めて占う。
しかし、河の水が黒くなり凍ってしまったのでは占いができない。
「原因を突き止めるために、河の上流の繰り女のところへ行く」
水占師は言い、支度を始めた。
「繰り女って?」
「会ったことはない。話に聞いただけだが、この河の源には大きな水車があり、大昔から廻しているのが繰り女という女だ」
「あたいも行く!」
「険しい山の上の洞穴の中にいると聞く。お前には無理だ」
「あたいも行く! 絶対、行く!」
流里鈴は言い出したらきかない。
「好きにしなさい。その代わり、途中でへばっても置いていくぞ」
水占師は、ひとりでさっさと支度を始めた。
繰り女が水車を廻している場所。
それは峻険な崖の連なる山々の、そのまた奥。仙人の住まうような墨絵の世界だ。
最も高い山の洞穴の奥深く進んでいくと、巨大な水車があるという。原始の神が作ったと言われる巨大な水車だ。
かたわらでは繰り女が、まるで手元の糸車を廻すように座りこんで、軽々と取手を廻している――という話だ。
水占師は山登りの装備に身を固め、慎重に一歩ずつ岩山を登っていった。流里鈴もがんばってついていく。
かなり高い位置に昇ると、ぱっくりと獣が口を開けたような洞穴の入口に行きついた。水占師は肩で息をしていた。
「ここだ……」
流里鈴は意外にも、少しも息を乱さずついてきた。
「お前はいったい……」
「山や野原を駆けまわっているから、ちっとも苦しくないよ。水占師さまこそ、大丈夫? 汗びっしょり」
「放っておけ」
本来なら洞穴の入口から巨大な滝が落ちているのだが、この水がいつもの船着き場に通じている。案の定、真っ黒になって氷の柱になっている。まるで黒曜石(こくようせき)の原石が尖って光っているように見える。
洞穴の中へ入り、提灯を灯して奥へ進みはじめた。
「繰り女はどこ?」
流里鈴が尋ねる。
「洞穴の突き当りに大きな水車があって、そのかたわらに正座しているはずだ」
「正座って、水占師さまと同じ座り方だね」
「正座して小さな取手を廻しているはずなのだが、水車も凍りついてしまっていることだろう」
どのくらい歩いたか……。
「そろそろ、水車の真上に空いた穴から光が入ってきてもよさそうなのだが……」
「薄暗いままだね。さっきから岩につまずいてばっかりだ」
流里鈴がぐちを言う。
ほどなく前方が仄(ほの)明るくなってきた。道が開けて広場のようになった。真ん中に巨大な水車が見える。かなり大きい。杉の木より高いのではないだろうか。
「思ったより暗い。何ゆえ薄暗いのだ。太陽の光が燦燦(さんさん)と降りそそいでいるはずなのだが」
ついに、ふたりは水車のすぐ側に行きついた。
水車は水と共に黒く凍りついて止まったままだ。
「おおい、誰かいないか!」
水占師が叫ぶ。
第三章 繰り女
水車のかたわらに大木が生えていて、幹から丸いひと抱えもある宿り木が茂っているが、赤茶けている。
丸く繁った葉をかき分けて、頭髪がボウボウの男の子が現れた。アカネ色の着物を着ている。
「お前は?」
水占師が尋ねると、男の子は唇を尖らせた。
「あんたこそ誰だよ」
「私は麓の村の水占師で、翠嵐(すいらん)という」
流里鈴は目玉を丸くした。
(水占師さまの名前は「翠嵐」っていうんだ! 初めて知った!)
「俺は宿り木の妖精でヤドリってんだよ」
「なぜ、赤茶けた着物を着ている? 宿り木は常緑樹で、妖精も緑色のはずだが」
「天井からのお日様の光が弱まったから、宿り木の葉っぱが赤茶けてしまって、この通りさ」
「どうして、また――」
「繰り女が、水車を廻す時の正座をサボったからだよ」
「正座をサボっただと――?」
「そうさ。それで天の神様がお怒りになったんだろうよ。天井からの光が弱まってしまった」
「繰り女はどこにいる?」
「水車の側にうずくまっているよ」
水占師が目をこらすと、巨大な水車の側の岩の上に人影が見えた。急いで近寄ると――。
ボウボウの白髪をそのままにして、みすぼらしい着物を着た老婆が石のようにうずくまっているではないか。
気配を感じたのか、白髪の間から覗いた眼は、黄色く濁って生気がまったく感じられない。
「繰り女とは、このような老婆だったのか?」
思わずひるんだ水占師に、繰り女は顔を上げた。
「このような老婆とは、なんたる言い草か! おぬしの眼はどこにくっついている!」
流里鈴が、ふところから小さな手鏡を出して、繰り女に示した。
「これ、見てみて」
手鏡を受け取った繰り女は薄暗がりの中で、しばらくまじまじと見つめてから悲鳴をあげた。
「こ、これは! わ、私はいつの間に老いてしまったの? 手までシワだらけじゃないの!」
ヤドリがため息をつきながら、
「繰り女、気がつかなかったのかい? 水が黒くなって水鏡が映せなくなったから仕方ないか」
「どうして、こんなことに――?」
「あんたが正座をサボったからだよ!」
ヤドリが言い放った。
「ああっ!」
繰り女は、自分の膝に目を落として驚愕(きょうがく)する。
「本当だわ! 正座が崩れている! それで、天罰が当たって老婆になってしまったんだわ! 何故、正座が乱れてしまったのだろう?」
絶望的に泣き始める。
「ああ、どうしよう、正座は崩れるわ、そのせいで老婆になるわ、天からの光が弱まるわ、宿り木は赤茶けてしまうわ、水車の水は黒く凍ってしまうわ――」
「繰り女、落ち着け。すべてお前のせいかどうか、まだ分からない」
水占師は口下手ながら、なだめた。
「そりゃあ、こんなに固い岩の上で長く正座していれば崩れもするだろう」
「でも、決して崩してはいけなかったのです。水車が止まると水の流れが……。ああ、どうすれば……」
繰り女はますますひどくうろたえる。水占い師も途方に暮れた。
ヤドリ少年が、手のひらにポンとこぶしを打ちつけた。
「こういう時には、正座のお師匠さま、万古老師匠を呼ぼう!」
「万古老師匠だって?」
「うん。正座の名人で師匠。仙界では、お世話になった方は多いと思うぜ」
「坊主、早くそれを言わんか。さっそくその、万古老師匠というのを呼べ!」
水占師に言われて、ヤドリはしぶしぶ、
「みんなで正座修行させられてもいいんならね」
何やら念じて、万古老師匠を呼んだ。
しばらくすると、天井の穴から老人が落ちてきた。宿り木の上にふわりと着地する。
「誰か呼んだかの?」
第四章 万古老師匠
白いヒゲを生やした仙人のような万古老は、繰り女のだらしない座り方を見るや怒鳴りつける。
「神聖な水車を繰る身で、そのだらしない座り方は何じゃ!」
「理由が分からないのです。知らない間に正座が崩れてしまって……。気がつけば、天井からの光が薄暗くなっていました……」
泣くばかりだ。
「ううむ、何ゆえ天井からの光が薄暗くなったかは判らぬが、水車を廻す手元まで狂うようでは非常に困る! 薄暗い中でも正座を崩さぬよう稽古あるのみじゃ!」
「は、はい」
「こうなったら、皆で基本から正座の所作のおさらいをする!」
「えええ~~、おいらも?」
ヤドリが露骨にイヤそうな声を出す。
「そうじゃ。皆、岩の上に並んで」
万古老は、水占師、繰り女、ヤドリ、流里鈴まで並ぶように指図して稽古を始めた。
繰り女は、懸命に正座の所作と心構えを自分のものにしようとしている。
そのうち、万古老が流里鈴を見つめ始めた。
「お嬢ちゃん、いつだったか、黒か白の龍神さまと一緒にお稽古したことがあるのではないかえ?」
「し、知らないわよ。あたいはお稽古するのは初めて。正座は水占師さまの所作を見よう見まねしてるだけよ」
流里鈴の口ぶりは、やや慌てていた。
「そうかえ?」
万古老が遠い目をして、
「あれは……白い龍神さまの方じゃったかのう? それとも黒い龍神さまの方かのう? 最近、昔の記憶があやふやになってしもうて……」
水占師のこめかみが、苦いものを咬み砕いたようにピクリと動いた。
ヤドリが、膝を乗り出した。
「龍神さまに白と黒があるのか?」
「あんた、ヤドリギのくせにそんなことも知らないの?」
流里鈴は舌打ちしてヤドリを睨んだ。
「まあまあ、お嬢ちゃん、そのような物言いをするでない。ちゃんとお稽古ができたら、何ぞかご褒美をあげるからの」
万古老がなだめて稽古は続けられた。
「繰り女や。天井からの光を浴びているつもりで背を正して下腹に力を入れて地面に膝をつき、着物はお尻の下に敷いて、かかとの上に静かに座る。両手の力は抜くのじゃ。自らの心臓の音を聞こうと集中して……」
繰り女は五感を全集中して正座の稽古に打ちこんだ。
数時間後、ついに万古老がうなずいた。
「うむうむ。その所作とカタチで良かろう。後は心穏やかに深く呼吸をして持続するのじゃぞ」
「はい。万古老さま、お稽古ありがとうございます」
「さて、次は天井からの光を元に戻してもらうために、龍神さまに繰り女の正座をご覧いただかなくてはならぬ。白と黒、どちらの龍神さまかな?」
水占師が、ぼそりと、
「白い龍神さまなら、面識があるが……」
ヤドリが眼を輝かせた。
「うわ、水占師さま、すげ――! 龍神さまって、やっぱクネクネとしていて長いの?」
「お会いした時には、人型になっておられたが」
興味津々のヤドリに苦笑して答えた。
――正座の稽古が終わっても、流里鈴は小さな唇をゆがめて不機嫌極まりなさそうだ。
第五章 白い龍神さま
万古老師匠は、とりあえず白い龍神を呼ぶことにした。
ヤドリ少年から髪の毛を一本抜く。
「いてっ」
髪の毛は細い枝に変わった。万古師匠はそれを頭上に掲げて、
「純白の龍神よ。この宿り木の枝を目印に、洞穴の水車に降りてこられませ!」
しばらく静寂が訪れた。――やがて、天井の穴の真上辺りに強い風が吹く気配がし――。
「呼んだか? 万古老師匠」
荘厳な声が穴から響いた。
次の瞬間、水車の横に、純白の着物を着た長身の男が立っていた。
「おお、白い龍神さま! お越しいただき恐縮でございます」
「正座の師匠、万古老がお呼びとあらば、地の果て海の果てへでも参りましょう」
清々しい面(おもて)の白い龍神は、万古老の手を握りしめた。
「私に何のご用でしょうか?」
さっそく美しい所作で万古老の前に正座した。
流里鈴が、そっとその場を離れ岩陰の向こうへ行くのを、水占師は見届けてから、
「お久しゅうございます。白い龍神さま」
「おお、そなたは翠嵐。久しいな。以前はよく万古老師匠の元で正座の所作の稽古を共にしたものだな」
「はい。その節はお世話になりました」
「で――、そなたもいるということは、水車や河に何か異変が起きたのだな」
白い龍神の眼がキラリと光った。
「お察しの通りです。天井の岩盤に空いた穴から射しこんでいた光の力が弱ってしまいました。そのせいで、水車を動かす繰り女の正座が乱れてしまい、水が黒く凍ってしまったのです」
水占師が説明した。
「うむ。ここへ降りてくる際に見下ろした河が黒くなっているので、気に留めた」
万古老が説明を引き継いだ。
「何ゆえ、天井からの光が薄暗くなってしまったのか、白い龍神さまならご存知かと思い……。それと、繰り女の正座を稽古させて、元に戻りましたのでご覧いただこうと思いまして」
繰り女が龍神さまの前に進み出て、正しい所作で正座した。
「繰り女でございます。白い龍神さまにまでお越しいただきまして申し訳ございませぬ。気合が足りず正座が乱れておりましたが、万古老師匠さまのおかげで再び正座ができるようになりました」
肩にかかる白髪をそのままに、丁寧に頭を下げた。
「はて――」
白い龍神は、純白の扇子で自分の首すじを軽くたたき、
「困ったのう。そなたは今、『気合が足りず』と申したが、そのせいで正座ができなくなったのか? また、私がそなたの正座を見届けたところで、天井からの光は元には戻らぬぞ。まったく私のあずかり知らぬことゆえ――」
「えっ」
万古老が、
「天井からの光のことを何もご存知ないのですと?」
「うむ。とんと見当がつかぬ」
「では、いったい何が原因で――」
万古老は、水占師に視線を向けた。
「ということは――、常闇の龍神が存じておるのかの?」
白い龍神が、慌てて万古老の口元に両手を当てて耳うちした。
「万古老師匠、水占師に、その名前は禁句ですぞ」
「え?」
さらに、急いで岩陰に連れてきた。
「水占師の翠嵐は、あるおなごをめぐって常闇の龍神と敵対関係にあるのです」
「敵対関係ですと?」
「しっ、お声が大きいです。翠嵐は常闇の龍神の恋敵なのです。つまり三角関係です」
「わ、わしゃ、知りませんでしたぞ! あるおなごとはいったい?」
「か弱い水の精だとか」
「うむむ……。それでは、水占師に常闇の龍神を会わせてはまずいですな」
対面の岩陰から、流里鈴が飛び出してきた。
「万古老さま、常闇の龍神さまには、あたいがお会いします!」
「なんじゃと、お嬢ちゃんが?」
万古老は口をあんぐり開けた。
第六章 少女と常闇
流里鈴は、常闇の龍神とふたりきりで会うと言い出した。
「あたいは、常闇の龍神さまとは正座のお稽古でご一緒したことがあるのです」
「やはりそうか。では、常闇さまとお話できるのじゃな」
「万古老さまと水占師さまの代わりに、しっかり繰り女さんの正座を見ていただきます!」
「では、頼むぞ」
万古老はしぶしぶ許した。
後に残るヤドリに、流里鈴と常闇の龍神の様子を見届けるように頼んだ。
「ガッテンだ! ちゃんと知らせるよ」
「ヤドリ。お前は正座がよくできたゆえ、きっと宿り木も瑞々しい緑に戻ると信じておるがよい」
「流里鈴を残していく?」
驚く水占師に、万古老師匠は、
「繰り女と共に正座のお稽古のおさらいをさせるだけじゃ。ささ、早く山を下りよう。ひと雨来そうじゃ」
「しかし……」
「後でワシが送り届けるゆえ心配はいらぬ」
ぎこちなく言いくるめ、水占師を連れて水車の洞穴を後にした。
やがて、大粒の雨が落ちてきた。
ヤドリが宿り木の茂みから様子をうかがっていると、天井の穴から漆黒の着物を着た男が、大コウモリのように雷と共に降りてきた。
凄まじい音響と、目も開けていられない風雨がヤドリの顔面に吹きつけた。
「常闇さま!」
流里鈴が迎えた。頭には黒い角が二本、肌には黒く光ったウロコが見える。暗黒の眼窩も狂暴な常闇の龍神である。
ヤドリは震えあがった。
流里鈴は常闇を水車から離れた洞穴内の小山の向こうへ導いた。
「お前か、わしを呼んだのは」
「はい。常闇さまが天井からの光を暗くしてくださったおかげで、繰り女は老女の姿になりました」
「八百年前、家や家族を河の水に流された怨み、少しは晴らせたか」
「少しは。流されたおとうやおかあたちは戻ってこないけど……」
うつむいて、流里鈴は下唇を噛みしめた。
「でも、正座師匠のおじいさんが来て、繰り女の正座を復活させてしまった」
「少女よ。もっともっと繰り女を憎め。復讐すると誓ったことを忘れるな。そうすれば、繰り女は再び正座ができなくなるだろう。水車をよけいに廻す間違いを犯して人々から憎まれるだろう」
常闇の爬虫類特有の瞳が、ごうごうと燃え盛り、少女の瞳の中に飛び火した。
「はい。あたいの家族や家を奪った繰り女……。もっとひどい目にあわせてやります」
岩山の陰に身を潜めて、ふたりの会話を聞いていたヤドリは、足をガタガタ震わせた。
(なんてこった! 繰り女の正座を乱したのは、常闇っていう黒い龍神で、流里鈴は常闇の命令をきいていたのか!)
(おかげで、おいらまで着物や頭の毛が赤茶けてしまって……)
ヤドリは足を踏ん張って顔を上げた。
(それどころじゃねえ! 天井の光を暗くして、繰り女にヘマをさせて河の水を黒く凍らせたのは、常闇の仕業だったんだ! 早く万古老師匠に知らせなきゃ!)
頭の中を整理して、懸命に万古老に教えてもらった通りに正座した。デコボコの岩盤も痛くはないくらい集中して――万古老に思念を飛ばせた。
第七章 流里鈴の企み
(どうやったら、もっと繰り女を苦しめることができるだろう)
流里鈴は考えた。
(そうだ! 愛する人を苦しめれば人は悲しむ。繰り女の愛する人を突き止めればいいんだ!)
常闇の龍神が去った後、流里鈴は水車を廻し続ける繰り女に近づいた。黒い氷は溶け始め、色も澄みはじめている。
「繰り女さん」
流里鈴の声に、取手を廻す手が止まったが、またすぐに廻しはじめる。
「さっき、一緒に正座のお稽古した流里鈴よ」
「何かご用ですか? お嬢ちゃん」
しわがれた声のままだ。
「ねえ、繰り女さんは水車の側でお務めしていて寂しくないの? ずっとひとりで平気?」
「さあ。長い間、正座して水車を廻すことで一生懸命なのでねえ」
「家族はいないの?」
繰り女は視線を伏せたまま、首を横に振った。
「じゃあ、友達は?」
「いませんよ」
「繰り女さんの一番、好きな人は誰なの?」
「好きな人?」
繰り女の手の動きが再び止まる。
「そう、好きな人よ。繰り女さんの黒髪がツヤツヤしていた頃に、誰かいたでしょう?」
小悪魔の目つきで、流里鈴が迫る。
「好きな人……思い浮かべただけで胸がじ~んと熱くなる人……」
「そうそう、その人の名前は?」
「胸が熱くなる人の名前……。青緑の面影……。水をたっぷり含んだ空気を感じさせる、あの人の名前は……」
「名前は?」
「翠(すい)……。あの人の名前は『翠嵐』……」
白い前髪に半分隠れた瞳が生き生きと輝いた。
「翠嵐ですって!」
流里鈴は繰り女から飛びすさった。
「水占師の翠嵐のこと?」
「ああ、水占師の翠嵐さま……。河の流れの中で出会い、すくい上げて愛しんでくださった方……」
繰り女の表情が少女のようにうっとりとなった。
第八章 水草の反乱
牛を連れた老農夫が水占師を見かける。
「また、占いができるようになって良かったですのう」
「ああ、水が元通り透きとおったのでな」
「おや、いつもの女の子は?」
「しばらく正座の道場にあずけてある」
「正座の道場?」
水占師は船着き場に歩いて行くと、舟を出し、形代を河面に浸して占いを始めようとしたが――。
異変を感じた。水草がどんどん腕に登りついてくる。根は粘つき(ねばつき)、腐臭を放ちながら腕から肩へ伸びてくる。
「これは……!」
必死で抵抗するが、動きがとれない。
水車のある洞穴では、流里鈴が水占師の様子を地面の水鏡を通して、繰り女に見せている。
「す……翠嵐、どうしたの? 水草にまとわりつかれて……」
「繰り女さん、翠嵐のことをはっきり思い出したのね。どう? 愛する人が苦しむ様子は」
流里鈴が薄笑いを浮かべながら、繰り女の戸惑う様子を楽しんでいる。
水草は水占師の首にまで巻きつき、締めつけ始めた。
「やめて~~! 翠嵐が黄泉(よみ)の世界へ行ってしまう!」
「そうなったら、あんたはどんなに悲しいかしら?」
流里鈴の顔に残虐な色が浮かぶ。
「あたいは、あんたのせいで、おとうもおかあも、祖父ちゃんも祖母ちゃんも、失ってしまったんだよ!」
「あなたは……」
「繰り女。あんたの八百年前のヘマで大洪水が起きたのを覚えている?」
「……!」
「あの時の被害者のひとりなのさ、あたいは」
繰り女は蒼白になった。
「ゆ、許してちょうだい。私の命で償えるなら、そうしてください」
「あんたの苦しむ顔が見たいんだよ」
面差しに、常闇の龍神のどす黒さが宿っている。
水草に全身を絡みつかれた水占師は、小舟から河に転落してしまった。
(いかん、私としたことが、水草に絡まれるとは! い、息ができない!)
もがき苦しむところへ……。
水中から白い閃光が差しこみ、水草は次々と剥がれていく。
「翠嵐、大丈夫か?」
小舟の上に逞しい腕で救い上げられた。
「白い龍神さま……」
「間に合って良かった! 万古老師匠が宿り木の子から知らせを受け、知らせて下さったのだ。お前が危ないと」
「私が溺れそうになるとは。……いったい?」
水占師は小舟の上で咳きこみながら、水草を取り去った。
「お前の連れの女の子は、常闇に魂を憑りつかれている。家族を失った悲しみに付けこまれたのだ」
「流里鈴が」
「あの子は繰り女さんを憎んでいる。いや、常闇が憎ませているのだ」
「常闇の龍神が……。流里鈴に繰り女を憎ませようとしていると? いったい何故?」
「お前たちふたりを苦しませるためにだ」
「……?」
白い龍神は、水占師の襟元をつかんだ。
「まだ分からんのか、鈍い男だな、翠嵐。繰り女はあんたの大切な水の妖精、滔々(とうとう)だというのに」
「繰り女が、滔々だって?」
(白髪になってしまった、あの老婆が?)
「滔々は、大昔に行方知れずになったままだが……」
「すべては常闇の仕業だ。あやつが嫉妬して水車を廻す繰り女にして洞穴に閉じこめたのだ。そして今また、天井からの光を暗くして河の水まで暗黒にしたのだ」
「なんてことだ! 滔々の気配に気づかなかったとは」
「行こう、翠嵐! 水車の洞穴までひとっ飛びだ!」
水占師に肩を貸すや、白い龍神は龍の長い姿となって天高く舞い上がった。
一部始終を見ていた老農夫の手から煙管(きせる)が落ちた。牛と共に口を開けて空を見上げていた。
第九章 再会
水車のある洞穴へ飛んでいく。
水占師が白い龍神に運ばれて水車の側に降り立つと、流里鈴が繰り女に水鏡を見せていた。
「滔々! 無事か、滔々!」
繰り女は、ハッと顔を上げた。
「その声は……」
「私だ、滔々! 水占師の翠嵐だ!」
「す、翠嵐……」
繰り女は水占師に駆け寄った。が――。
「無事か、滔々。よく生き延びていてくれた」
次の瞬間、繰り女は、広い胸板を突き飛ばした。
「よ、寄らないで!」
「どうした、滔々。長い間、探したのだぞ」
「今の私は年老いた姿です。お願い、顔を見ないで」
「くくく……」
流里鈴が低く笑った。
「苦しめ、苦しめ、ふたりとも。あたいの苦しんだ八百年分を苦しむがいい」
いつもの愛くるしい流里鈴はどこへいったのか、眼は墨を流したような暗黒に化している。
「翠嵐どの、幼女の中に常闇が入りこんでいる。気をつけられよ」
人型に戻った白い龍神が忠告する。
水占師は、親鳥が雛を包みこむように、ふわりと滔々を抱きかかえた。
「滔々よ、醜いなどと思いはせぬ」
「翠嵐……会いたかった……。頭に霧がかかったように、暗くなってからはっきり思い出せなかったの。今はあなたのことが分かるわ」
滔々の眼から涙がほとばしった。
流里鈴がしわがれた声で、
「再会の喜びは満喫したか? では……繰り女を仲間にしてやろう」
言うが早いか、ウロコに覆われた手で滔々の首根っこをつかんで地面を蹴った。
「ああっ!」
滔々は流里鈴に引きあげられて空へ昇っていく。
「滔々~~~!」
水占師はふたりに追いすがった。
流里鈴は、すでに常闇の龍神の長い姿になっている。
「いかん!」
白い龍神が正座で座りこみ、目を閉じて念じた。
水占師と滔々の姿は上昇しながら白く長い姿に変身した。黒と白の三匹の龍は、もつれあいながら更に高く上昇していく。
第十章 少女を奪還(だっかん)
ヤドリが駆けつけてきて彼らを見上げた。
「白い龍神さま! 水占師さまと繰り女さんを龍に変えたのですか?」
「龍に変身した方が、常闇には手を出せぬゆえな」
「あの女の子はどこへ?」
「常闇に身体を乗っ取られているが、やつの憑依の力に勝てば元の姿に戻るだろう。どれ、私も加勢してくるとしよう」
白い龍神は立ち上がり、天井の穴へ向けて飛び立とうとした。
「待って! これを!」
ヤドリが細い枝を渡した。宿り木の真珠のような実が鈴なりについている。
「神聖な木の実だから、常闇のやつらは苦手なはずだ」
「おお、助かるぞ、ぼうず」
白い龍神は枝を口にくわえると、三匹の龍を追って舞い上がった。
足元には小さくなった島国が見える。
濃い藍の空で三匹の龍がからんでいるところへ、純白の逞しい龍が昇ってきた。龍が朗々とした声を発する。
「常闇の龍神よ、いい加減に諦めよ。お前の小細工など破れる運命にあるのだ」
「白い龍神め、小賢しいことを!」
常闇の龍はうめいた。
「宿り木の実をくらうがよい!」
白い龍が、常闇の目元へ宿り木の真珠の実を落とした。実ははじけて、白い果汁が常闇の両眼に降りかかった。
「ぐわあああああ」
常闇の龍は、二匹の白い龍を離した。
「翠嵐、今だ! 少女に話しかけるのだ」
龍と化している白い龍神が叫んだ。
水占師は、うねうねと空を飛び、常闇の龍を追った。
「流里鈴、お前の身体に憑依(ひょうい)しているのは常闇の龍神だ。繰り女の手元を狂わせ、水車の水を大量に流した張本人だ。すぐ、そやつの身体から離れよ!」
常闇の龍は両眼から宿り木の果汁を振りはらおうと、苦しみもがいた。浮遊を止め、小さな人間となって落下を始めた。
「流里鈴、よく聞き分けてくれたな」
白い龍神が、素早く少女の身体を口で受け止めた。
終章
気がつくと、水占師はいつもの霧深い河の船着き場に、女と立っていた。
「滔々……だな?」
「翠嵐……」
振り返った女は、黒髪につやつやとした肌の姿に戻っていた。
「滔々! かつての姿だ」
「翠嵐、私たち、助かったのね」
ふたりは、二度と離れまいと固く抱きしめあった。
船着き場に、万古老師匠と流里鈴の姿があった。
「これこれ、いつまでもくっついていないで、白い龍神さまにお礼を申し上げ、正座の修行を再開するのじゃぞ」
「万古老師匠……」
「流里鈴の魂はワシが預かって、極楽にいる家族の元へ送り届けるゆえ、心配せぬように」
流里鈴が水占師の元へ駆けてきた。
「あたい、なんだか悪夢を見ていたみたい……。分かるのは、昔の水害は繰り女さんが悪いのじゃなかったってこと。黒い怖いものがあたいに憑りついていたこと」
「それを分かってくれれば充分だ。二度と常闇の龍神と関わってはならぬぞ」
水占師は流里鈴の頭を撫でた。
「繰り女さん、苦しい目にあわせてごめんよ」
滔々にぺこりと頭を下げ、水占師に向き直った。
「水占師さま、ありがとう。八百年間も側にいさせてくれて」
「お前のおかげで孤独ではなかったぞ。二度と常闇に憑依されぬよう、お前の形代を念じて河に流してやろう」
「ありがとう。水占師さま」
にっこり笑って、ふたりは別れを告げた。
「私が繰り女の役目を下りたら、水車を廻す者はどうなるのかしら?」
滔々がもらした。
「それなら、正座ついでにワシがやることにしたから、心配ご無用じゃ。小遣い稼ぎにちょうどよい」
万古老師匠が答えて、わっはっはと笑った。







