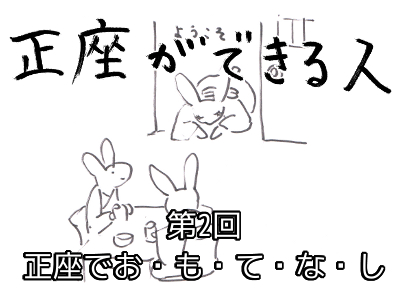[307]お江戸正座11
タイトル:お江戸正座11
掲載日:2024/09/12
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:11
著者:虹海 美野
内容:
秋由(あきゆう)は、札差の三男である。しつけの厳しい家で育てられ、それが鬱陶しく、合わなかった。
家のしつけや方針に従順な長兄とはもめることも多く、何かと不満を抱く秋由。
だが、札差仲間との交流のために習うお三味線などは得意で、歌や戯作も好きであった。
ある日、花見に行くとそこで歌をそらんじている娘に会い、趣味が同じだとわかると少し話しませんかと誘われ、敷物に座る際にいつものように正座した秋由だが……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
秋由(しゅうゆう)は、札差の三男であった。
今名乗っている秋由という名は、俳句を始め、その句を歌集に載せてもらえると決まった暁に師と相談し、決めた。もう四十を過ぎ、己の年齢を秋に例え、読む歌がのびやかであるようにとの思いからである。
秋由は、二十三の時に口入屋に婿入りし、後に婿入り時の持参金を遣い、管理する貸店舗を増やし、口入屋を子どもに任せた後は増やした店舗の賃料で暮らしている。
長兄の継いだ札差は今でも大きなお店で安泰で、次兄も秋由と同じように店舗をいくつか預かり、そのうちのひとつの表店で器を扱う商いを始め、裏長屋の家主と併行し、店舗の管理もしているが、そのほとんどを所帯を持った子に任せ、今は商いと裏長屋の住人の世話役をしている。
次兄、秋由ともに家を出るのに際し、それなりの額を持たせてもらった。
秋由がこの時の持参金を元手に、今手広く店舗を貸し出していることから、札差の息子は婿入りしても、主を退いても左団扇で、とやっかみ半分に言われることもあるが、そもそも持参金を引退後の資金運用に充てること自体が至極手堅いわけで、周囲がそのあたりをどう捉えているかはわからぬし、内情を説明してもらいたいと思って言っておらぬことも承知であるから、秋由はおかげさまで、と適当に流している。そうすると、相変わらず、あの人は腹では何を考えているかわからぬ、と囁かれる。囁くのはそれぞれの自由だから、いちいち目くじらを立てる気も起きぬ。妻も子も、秋由同様に「おかげさまで」と微笑むだけである。だから、あそこの口入屋は婿養子の前は感じがよかったが、どうにも婿入りの旦那以降は面倒だ、だが、お商売に関しては一切手を抜かぬから、ここぞという時は絶対にあそこに頼むのがよい、おまけにあそこの旦那は札差の息子で金に困ったことがないから、あこぎな商売はしないと、悪口なのか褒めているのかわからぬ評判をあちこちで言うのがたまに聞こえるが、その時は「ありがとうございます」と言っておく。
秋由はこうして今日も飄々と、ちょっと洒落た好みの着物に巾着なんかを提げて、思いのままに過ごしている。
秋由の家は先述の通り札差で潤っており、住まいや飯が豪勢で、髪結いはもとより、反物、掛け軸など、さまざまな商い人が出入りし、家はそうした商い人にとって上客であった。
つまり、贅沢な暮らしをさせてもらっていた。
だが、札差というのは、数多あるお商売の中でも、兎にも角にも世間からの評判、信用を重視する。
だから、とにかく装いは身ぎれいを第一に。
これが娘でもいれば、きれいに着飾って可愛がられたのかも知れぬが、息子三人の家である。父の札差の仲間には羽振りよいままに、いろいろと散財するお人というのもあったが、父は質素、実直な人柄で、そうしたことを好まなかった。多くの商い人が出入りすれど、本当に必要なものだけを厳選して買っていた。家族、雇っている人間に必要なものはけちらずに求めるが、世で所謂道楽と言われるものには、一切興味を示さなかった。お店にとってそれはよいことであり、秋由もそうした父を尊敬してきた。だが、自身を律すると同時に、子どもらへのしつけもまた、うるさかった。
正座から作法の所作に至るまで、それはそれは厳しかった。
長兄も次兄も、そうした厳しい家の方針に従い、また卒なくこなしていた。
ただ、秋由だけは、それが馴染めなかった。
それぞれの息子に目をかけて育てる父は、暫し、秋由に苛立ち半分、諦め半分の目を向けた。
正座は背筋を伸ばし、膝はつけるか、握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか、軽く開く程度、穿き物は尻の下にきれいに敷き、足の親指同士が離れぬように気を付ける。手は太もものつけ根と膝の間で両の手の指先同士が向かい合うように揃える。
その姿勢で帳場はもちろん、客に接する手代も番頭も常に働き、膳を前にした時にもそれは同じであった。
仕立のよい着物を母はいつも着ていたが、決して派手な柄が入ったものや、きつい色合いのものは選ばなかった。きりっとした整った顔立ちで、すらりとした長身なのだから、少し色味の濃いものや、派手なものも着こなせそうだと思ったが、反物を取り寄せて選ぶ時は父も顔を出し、母の選んだ反物を必ず確認していた。
「お母ちゃんには、こういうのも似合うのに」と言う秋由に、母は少し嬉しそうで困った顔をし、「お母ちゃんにはちょっと合わないわ」と返す。
「本当にそう思っているの? 好きなものを選べってお父ちゃんが言うんだから、そうしたらいいんだよ。せっかく仕立てるんだから」
そう真剣に言う秋由を、長男がいつも「いちいち余計なことを言うな」と遮る。
その遮り方も気に入らなかった。
父に叱られるのには道理がある。
だが、この長兄の父に似せた口調は、本人は正義感からであっても、根本的には秋由が気に入らぬという思いが含まれている。
「兄ちゃんは算術はできるけど、てんでこういう洒落事には疎いんだから黙ってなよ」と秋由が言い返せば、「うるさいんだよ。札差で算術ができるのに文句を言うな。末っ子の分際で」と兄がむっとした顔で睨む。
そんなことで怯むと思うのか。
末っ子の分際で、と言うが、これは本人の力の及ばぬところではないか。
ほかに俺に対して言えることがないのか。
だったら、その末っ子の分際で言い返す
「末っ子の俺に言い返されて面白くないのか。ご長男様」と言葉を重ねる。
次兄と母が小さく吹き出し、口を閉じ、畳の目に視線を落とし、笑うのを堪えている。
「なんだよ」と長兄が本気で怒り出し、殺気だった目を向ける。
今にも手が出そうな勢いである。
腹は立てているが、その割に返ってくる言葉はお粗末であると思う。
「これ、おやめなさい。みっともない。あなたたちは、この反物に決めたのね」と、母は、至極まっとうな口調でその場を収める振りをし、息子三人に仕立てる反物を確認するのだった。
2
お茶をいただく席で、兄弟三人は並び、祖母が茶を点ててくれる。
こうした嗜みは、普段から身に着けるのがこの家の方針であった。
床の間に飾る花を買い、掛け軸は祖父があちこちの店を歩いて買い求め、日に応じて掛けかえる。
まだ幼い兄弟は着物をきちんと着て、着物を尻の下に敷き、背筋を伸ばし、膝をつけるか握りこぶし一つ分開く程度、脇は締めるか軽く開くくらい、手を太ももと膝の間で両の手の指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士をつけ、菓子とをいただく。
これもいいけど、もっと大きな饅頭を寝転がって食べた方が好きだ、と秋由は思っていた。
茶をいただいた後、縁側で足をぶらぶらさせている秋由に、次兄は、「お前、もうちょっとうまくやれよ。いちいちもめて、疲れるだけだろう」と言う。
「疲れるって理屈で、本当のことも言えないのは願い下げだね」と、幼い秋由は言う。
「わざわざ疲れるようなことをしなくても、大人になれば、そういう機会はいくらだってあると俺は思うけどね」と、次兄は冷めた口調で返す。
「その時はその時で考える。それくらいの知恵はある」と秋由は言い、畳に色とりどりに広がる反物を思い出す。
先ほどの反物だって、秋由が「これがいい」と最初に言った反物は一見地味で、長兄は「そんなのがいいのか」と笑ったが、呉服屋には「お目が高い」と褒められた。「これはなかなか手に入らぬ貴重な品です」と続ける。それに長兄は面白くなさそうな顔をし、母が「まだ幼いですし、この子にはこちらを」と兄たちと似通った色味の他の反物を選んだ。まあ、お母ちゃんがそう決めるのなら、仕方ない、と秋由は思った。次兄は、そんな様子をいつも黙って見ている。
厳しい父と、しっかりものの美しい母の間に、秋由たちは生を受けた。
もともと気が強く、負けん気の強い長兄、そこそこに頭の回転が速く、冷めた物言いをする次兄、そうして思ったことは主張しないと気の済まぬ三男の秋由。
そうした息子三人が同じ家で常に一緒にいるのは、なかなかに大変なことであった。当人同士というよりも、その周囲にいる大人が苦労したといったところか。
往々にして、長兄は父に気に入られていた。
否、正確には馬が合った。
このあたりは、本当に些細なことであるかも知れぬが、一家、そして店を取り仕切る人間と、毎日顔を合わせる中で、馬の合わぬ息子である秋由には居心地の悪いものであった。ある意味、他人であれば諦めもついたのかも知れぬ。
ああ、こういう人だ、と割り切れもしたかも知れぬ。
まあ、そうなってみなければわからぬが……。
兎にも角にも、父のことを尊敬し、何の疑念も反抗も抱かずに、真っすぐに父を見つめ、育っていく長兄と、いつも腹の中で何やら意見とか、疑問とか、そういうものを抱いて、なんとなくおさまりの悪い気分で俯き、箸で豆なんかを一粒二粒つまんでいる秋由とでは、やはり父からの覚えにも差は出ても仕方あるまい。
仕方あるまい、と思いながら、それでも己の我は、幼い秋由には己でもどうにもできなかった。
そんな秋由を家族や店の者の前ではなく、それとなく周囲に人の居ぬ時にかわいがってくれたのが、離れに住む祖父母であった。
お前は周囲に左右されない、正直で、しっかりした心を持っている。
従順であることはよいことだが、それだけがよいわけではないのだよ、と祖父は言った。
祖父はやはり札差の跡継ぎ息子で、お商売を第一にやってきた人であるが、趣ある調度品を集めるのが好きであった。
そうして祖母は、よく歌集や戯作を読んでいた。店のおかみさんであった時には、そうした時間はなかったが、今はゆっくりと書物を広げられると言っていたのを覚えている。
秋由の家では、息子三人に勉学、芸事、剣とを仕込むから、それ相応に忙しい日々ではあった。長兄は真面目に勉学に励み、家の庭でも竹刀を振っていた。
その一方、次兄は祖父の調度品を眺め、次第に一緒に調度品を見にあちこちの店を歩くようになり、秋由は祖母の横で書物を読んでいた。
長兄の真面目な行いに父は目を細め、下二人の息子には溜息をついた。
札差の息子が何をしていると、怒鳴るところなのだろうが、その先にいるのがこれまで店を守ってきた両親とあり、堪えているようだった。
今にして思えば、次兄とともに財産ももらって家を出たが、昔から付き合いのある札差の家への婿入りや、暖簾分けの話は出なかった。札差にならぬことを次兄も秋由も望んでいると父は見越していたのだろう。
そうしたわけで、手習いを終える頃には、兄弟の生まれた順だけでなく、その能力や適性から、長兄が店を継ぐことは決定しており、次兄と秋由は、いずれ家を出るにしろ、それまでの間ということで、暫く見習い、そうして手代になるまでの間を実家で過ごした。
秋由が手代になり、二年ほど経った頃だろうか。
札差のお三味線仲間から花見の誘いがあった。
この頃には、呉服屋が持参した反物から、そこそこに好みで、父や兄が目くじらを立てぬものを選ぶ知恵もついていた。だから、外出の際の羽織なんかも、品あり、控えめでありながら、あまり周囲と似通らぬものを選んだ。出かける用事というのも大概は、お店に関することで、そうなるとお店を出ても札差の仕事の一環のくくりになるから、着物なんかはやはり父の意向を外れぬもの、という認識も十何年かの間に秋由は得て、それなりに自身の趣向との折り合いをつけるようになった。
この近辺の札差仲間が集う行事というのはさまざまで、お三味線もその集いのひとつであった。まあ、継続的な関係を築く一環であり、前回までは先代と旦那が出席していたが、最近はそこの旦那だけが来るようになったとか、旦那とともにそこの息子が来るだとかいうのも多かった。
多忙な父が、といってしまえば、聞こえはよろしいが、如何せん、芸事には不向きであるらしい父に代わり、秋由が行くようになった。同じような理由で、歌の方も秋由が出向き、茶や香といった席には次兄が出た。商いの話し合いの時には父と長兄が出向いた。
とにかく、この日はお三味線での集まりで、秋由が出向いた。
桜が見頃で、この日もお三味線のお仲間で花見と洒落こむ。
いつも顔を合わせる、うりざね顔にやたらと洒落た小物をちらつかせる幼馴染は、札差の次男で、近々婿入りするのだと言う。あんなのがやって来たのでは、あちこちからこれは珍しい、高価だ、貴重だと揉み手しながらやって来る商人を一緒に呼び込むようなもんだと秋由は思った。思ったが、本当は少し、うらやましくもあった。あの浪費息子が、と散々旦那さんは嘆いてみせたが、実際のところは洒落者の息子がかわいくて仕方がない。だから、あのうりざね顔にすっかり夢中のお嬢さん、そしてその娘に大甘で、多少の浪費はよしとしてくれるしっかりとした婿入り先を探し、着々と見合いを進め、見事婿入りに至った。
いい親父さんじゃないか、と思う。店を継がせないし、同じ家に住み続けるわけでもない。だが、このうりざね息子が幸せにやっていける、大事にしてもらえる、そういう場を用意した。大の大人である息子に、と言う人もいるだろう。実際に自分の力では何も得てはおらぬ、と言う人もあるかも知れぬ。
……それでいいじゃあないか、と秋由は思う。
親が用意してくれたものだって、くれるというのなら、自分のものだ。
そんなことを言ったら、手習いに行く時に持参した文机だって親が用意してくれて、これは俺の机だ、と言う。まあ、子どもの頃のことを同列にするのは、それこそ大人気ないというものか……。
延々と己の中でそのようなことを考え、じゃあ、俺だったら、何をお父ちゃんに頼みたいのか、と問えば、それはわからぬ。
この年になって、一体俺はお父ちゃんに何をしてもらいたいんだ。
うりざね息子を素直に祝えない思いは何なのか……。
約束の場に皆が集まり、注文しておいた弁当を抱え、花見に向かう。
土の暖かな匂いに、小鳥のさえずり、満開の桜。
なんとうららかな世だ。
ひとつ、ふたつ、とこの頃読んだ戯作や歌のことを思い出す。
するとふと、まるで小鳥のように明るい声で、たった今、秋由が思い浮かべた歌を誰かがそらんじた。
顔を上げれば、なんとも美しい打掛が木にかけられている。
赤い珊瑚のように見えたかと思えば、青みがかっても見える。
これは、光の当たり具合によって、さまざまな色味になる手の込んだ織物だと、秋由はすぐに思った。ほかの娘の打掛も、この時期はあちこちの木にかけられているので、お嬢さん方の自慢の打掛のお披露目会のようでもあるのだが、この打掛はほかと違う、と思った。
そうして、今、歌をそらんじた声の主を知りたいと思った。
二つのことが重なった時、なんの偶然か、風が吹き上げた。
打掛が大きくひるがえり、緋色の敷物に座っていた娘が見えた。
目が合った、と思った時には、打掛が枝から外れ、大きく空を舞った。
弁当を抱え、うりざね息子に「いやあ、本当におめでとう」と呑気に言う、やはり札差の次男の横を通り、軽く跳んでその打掛を捕まえた。
美しいこの織物は軽く、柔らかい。
そうして、腰を上げかけたその娘は、漆黒の豊かな髪を結い、先ほど合った、大きな目を見開き、秋由を見ていた。
「これを……」と秋由が言うと、「ありがとうございます」と、赤い紅の大層似合う小さな口から、初めて秋由に向けた言葉を発した。
これが、秋由と妻の出会いであった。
今でも秋由は、この日の妻の姿を覚えている。
こんなにもあでやかな娘がいるのか、と思った。
名をおうた、と言った。
口入屋の長女で、結論からいうと、秋由はこのおうたの家に婿養子に入り、この口入屋の家業を一度は継いだが、それを子に託すと、口入屋の持ち物である貸店舗の管理をし、その賃料で暮らすようになった。
3
話を戻す。
打掛を渡し、一度はそのまま離れた秋由とおうたであったが、花見の折、「よろしかったら、こちらのお重もいかがですか」と互いへの行き来をした。
おうたの方はお稽古仲間のお嬢さんたちとであったが、先ほどの弁当の箱を抱えた札差の次男と店が近かかったことや、その仲間というのが信用につながったようだった。
これまでで一番、札差仲間の集まりに参加してよかった、と思った出来事かも知れぬ。
そのうちに、お重を持って行った者に手招きされ、行ってみると、そこでおうたが「よろしかったら、こちらで少しお話なさいませんか」と言う。
「おうたさんは、戯作や歌がお好きなのだそうだ」と、札差仲間が間に入って会話をつないでくれる。
「……そうですか。先ほどの歌は……」と、気が逸る秋由に「どうぞ」と、おうたは座ったまま手をつき、横を開けてくれた。
「少しだけ、失礼します」と秋由はやや躊躇ったが、礼をし、草履を揃えると、正座した。
緊張していたが、背筋を伸ばし、脇を締め、膝をつけ、足の親指同士も重ねた。手は膝と太もものつけ根の間で指先同士が向かい合うように揃え、穿いているものをきれいに尻の下に敷く。
「所作が美しいのですね」とおうたは言った。
「なんだか、すぐお近くにいるのに、遠い人のよう」
「ちょっとおうたさん、私も札差の息子ですよ。昔から知っているでしょう」と、話をつないでくれている例の弁当の男が言えば、「まあ、そうでした。ですが、札差のおうちの方、というよりはなんでしょうね……」と、首を傾げる。
秋由は、「うちは父が厳しいもので。長兄だけならわかるのですが、次兄にも私にも厳しいのですよ」と言い、その時おうたは「よいお父様なのですね」と言った。
よいお父様……。
今度は秋由が首を傾げた。
あの実直な、うるさいお父ちゃんが?
「お作法のお稽古だけでは、とてもとてもここまでは追いつきませんものね。とにかく所作や正座は日々の心がけと、教えられますし、本当にそう思っております。言う方だって、きっと大変ですよ。お商売をされていて、ご自分のこともあって、それでも『厳しい』と言ってもらえるほど、いつも子に目を向けられるのは、なかなかできることじゃあないと思うのです」
はらはらと降る花弁を見つめ、それからおうたを見た。
今のこのおうたの話を聞いたら、お父ちゃんはなんと言うか。
こんなふうに言ってくれる娘でもいればよかったのか。
それはわからぬ。
ただ、この時、漠然とお父ちゃんにありがとう、と秋由は思った。
いつもいつもうるさくて、鬱陶しく思っていたお父ちゃんの、お父ちゃんなりの子への思いというのを、今、ようやく知った気がした。
「ありがとうございます」と秋由は言った。
おうたに向けて、そうして、お父ちゃんに向けて。
4
おうたと秋由の縁談はすぐに決まった。
おうたの家は娘だけで、おうたは長女だったので、秋由が婿入りすることになった。おうたの家は、この辺りで評判の口入屋であった。つい先ごろ縁談の決まったうりざね息子の家も、なんとこのおうたの家の口入屋に見合いを頼んでいた。おいおい、将来俺はうりざね息子の娘だとか息子だとかの縁談の世話をするようになるのか、と秋由はふと、思ったのだった。
祝言の準備をし、明日にはおうたの家へ婿入り、という日、秋由は父の元へあいさつに行った。
「失礼します」と言い、この日は障子の前に正座し、父の返事を待って手を揃えて障子を開け、そこで一礼した。
「入りなさい」という声に、習った通りの作法で丁寧に障子を閉め、勧められた父の向かい側に正座する。
背筋を伸ばし、着物をきれいに尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬよう、膝をつけ、脇を締め、手を太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃える。
そういえば、いつも父は判を押したように、きちんと正座していた。
疲れている時でも、否、酒の席ですら、そうではなかったか。
こんなにいつもいつも礼を心掛けていて、何が楽しいのか……。
「このたびは、私の婿入りのため、多大なるお祝いをいただき、ありがとうございました。これまで育ててくださった御恩、生涯忘れません。これからはおうたの家のため、精進いたします」
一応考えておいた決まり文句であり、また心からの謝辞でもあった。
「うん」と父は小さく頷いた。
この後、長い沈黙が流れ、そのまま「では、失礼します」と秋由がぼそり、と言い、「うん」と父が返し、そうしてまた丁寧に障子を開け閉めし、秋由は父のいる奥座敷を後にしたのだった。
5
「お前、お父ちゃんにきちんとあいさつはできたんだろうな」と、廊下にいた長兄に呼び止められた。
様子を見ていたのか。
念願の若旦那になって気を抜いているのか、と秋由は長兄を見た。
「ああ」といやいや返事する。
「順番からいえば、俺が先だったんだ」
どうせ、なかなか相手が決まらぬのだろう。
こんなに面白味のない男のところへわざわざ来るもの好きがいるのか。
俺が婿入りした後、最初の仕事がこの兄の縁談というのは勘弁してほしい。
否、待て、この兄だから、お父ちゃん、お母ちゃんもそのへんはわかっていて、ずっと前に相手を決めているのか。
そんなことを腹の中で思っていると、「お父ちゃんが、お前の好きにさせてやれと言ったんだ。ひねくれたお前からしたら、自分が婿入りするのに親の許可が必要かと突っかかるんだろうが、あの規律に厳しいお父ちゃんが、末息子のお前にしてやれることは、お前が自由で幸せであることだと言ったんだ。そのための教養をつけ、持参金も少しだが用意してやる、そう言っていた」と、長兄が続ける。
帳場から「若旦那、お客さんです」と声がかかり、「今行く」と長兄はすぐに返事し、仕事に戻って行った。
秋由は踵を返し、奥座敷に戻った。
「どうした」と驚いた顔をしている父を前に、秋由は再度正座をした。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝をつけ、脇を締め、足の親指同士が離れぬようにし、手を足のつけ根と膝の間に指先が向かい合うように揃える。
「お父ちゃん、……本当にこれまで、ありがとう。ずっと、うるさく、いや、しつこく、そうじゃなくて、辛抱強く、いつもいつもしつけてくれたのは、とても大変だったよね。それがいかに大変で、お父ちゃんがいいお父ちゃんかと言ってくれたのは、おうたさんだったんだ。お父ちゃんのこと、あんまり好きじゃなかったし、鬱陶しいと思ったけど、それだけじゃなくて、そういうふうに言ってもらって、俺はとても嬉しかった。ありがとう」
「うるさくて、しつこくて、鬱陶しくて、済まなかったな。向こうのお父さんには、きちんとした言葉を選んで話しなさい。息子に嫌われてまでしてきた努力が無駄になる」
そう言うと、父はすくっと立ち上がり、部屋を出て行った。
ああ、またやらかした……。
そう思って庭に面した縁側で菓子器から出した饅頭を食っていると、隣にお母ちゃんが座った。
「ずいぶん立派なあいさつをしたようじゃないの」と言う。
「とんでもないよ。またやらかした」と秋由は小さく笑った。
「そんなことないわよ。お父ちゃん、あいつも大人になったもんだなって、言いながら、泣いてた」
何かの間違いじゃないか?
「今だから言うけど、お父ちゃん、あいつは大したもんだ。よいものを見極める力があるって、いつも言ってた。お父ちゃん、昔はお三味線なんかも札差仲間の付き合いの一環だからって、頑張って練習していたんだけど、ちいっとも上手にならなくて。だから、あんたがお三味線の筋がいいってお師匠さんに褒められた時には、まるで自分が褒められたみたいに喜んで帰ってきてね。うちの息子で、それで長男でなくてよかったって」
「なんでお母ちゃん、それをもっと前に言わなかったんだ?」
秋由が尋ねると、「だってお前、そうすると、すぐ兄ちゃんたちとの喧嘩の時にそれを持ち出すでしょう? それじゃあなくっても、もめることが多かったからねえ。だけど、私はちゃんとあなたたち三人をほめてかわいがって育てましたよ。ええ」と言う。
まあ、わからないではないが……。
毎回、正座だ行儀だと言うなら、少しくらい、言ってくれたっていいじゃないか……。
だから、おうたに言われるまで、お父ちゃんからの恩義に気づけなかったんだ。
気づかなかった俺もよくないが……。
6
こうして、秋由はおうたの家に婿入りした。
持参金はおうたの父が受け取らず、結局それに世話になったのはかなり後のことであった。口入屋の商いも十二分に学び、何年かかけていくつかの店舗を買い、その賃料を元手におうたとの今後の生活に充てることにした。お父ちゃん、お父ちゃんたちが暮らしてゆく資金くらいこっちで出させておくれよ、と子どもたちがありがたいことを言ってくれたが、秋由は自身の考えを曲げなかった。
こういう桁違いに生真面目なところが、やはり父に似ていると秋由は思う。
口入屋のお商売を学び、札差の息子である時から更に人付き合いは広がったが、そうした中で、一見礼儀正しく、きちんとし、また柔和そうに見えるが、結構な理詰めの、ちょっと面倒な性格だと言われるようになっていた。腹の中で何かを思うのは昔からだ。何を今さらと、思う。
しらっとした顔でいる秋由だが、昔からの馴染みの呉服屋が来る時は少し違う。向こうは父から店を継いだ息子で、代替わりした時にはあいさつに来てくれた。ここで今は思い思いの反物を選ぶ。おうたにも好きなものを選ぶように言うが、つい一緒に反物を見て、これはどうか、あっちもいい、と述べる。お父ちゃん、お母ちゃんに好きなのを選べって言ったのに、という、かつての自身の言葉を思い出し、心の内で苦笑する。
呉服屋の息子は、やはり家でのしつけが厳しかったのだろうし、本人がもともと所作に気遣う性格だったのかどうかまではわからぬが、いつもきれいに正座している。
背筋を伸ばし、着物をきれいに尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬようにつけ、隙のない所作で、柔和な笑顔を作り、品を見せる。
そうして、この呉服屋は、かつて定期的に顔を合わせた札差のうりざね息子、今は札差の旦那(否、大旦那になったか)の元にも通っている。相変わらず値の張る洒落たものを好んでいるようで、変わらぬ、と思いながらも、昔ながらの友の様子を聞けるのは嬉しいものである。そうして、お三味線の会に時折顔を見せるこの友と一言、二言話せば、何やら昔のような心持になる。どちらも婿入りした立場だが、ご新造さんを想い、想われ、お商売に精進し、幸せに年を重ねているのも、喜ばしいことであった。
書物を開き、俳句を詠み、そうしておうたと季節ごとに花を見に行き、祭りに行き、楽しい日々を過ごしている。おうたを俳句などにも誘ったが、私は誰かの作ったものを楽しむ方が合うようですと言う。
そうしてある日、おうたが読んでいた本に新たな戯作者を見つけ、同じ名の茶葉を扱う店に入ったのは、また後のことである。

![[360]お江戸正座27](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)