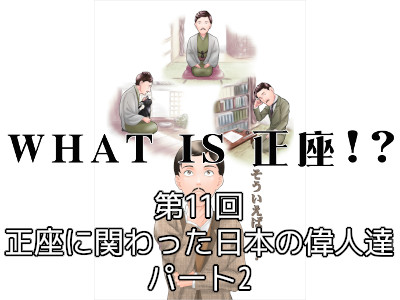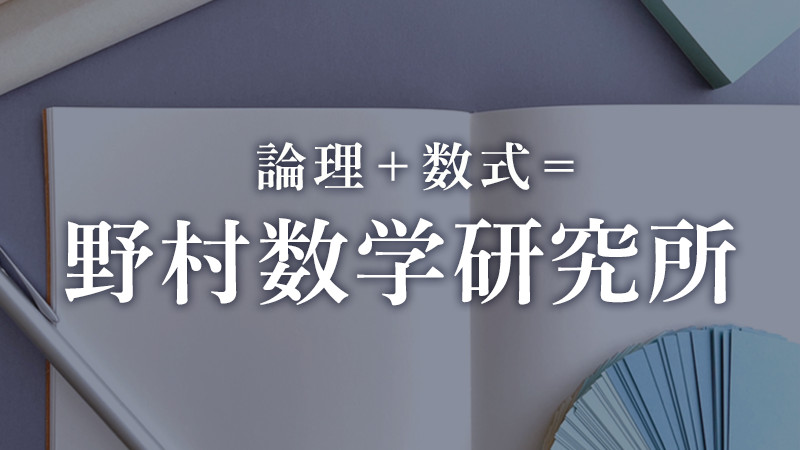[339]お江戸正座21
タイトル:お江戸正座21
掲載日:2025/02/20
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:21
著者:虹海 美野
あらすじ:
善太と善次郎は料亭の二代目兄弟である。兄貴分であった板前の佐久造が暖簾分けで店を出た。
真面目に料理に邁進する兄弟だが、自信が持てぬ。
そんな折、新しい昆布を使って合わせ出汁を作り、つみれ汁に使えるように考えよ、と父から言われる。
弱り切った兄弟だったが、偶然札差に嫁いだ妹のお付であるおきぬに会い、おきぬの言葉から、出汁の味見をしてもらおうと思いつく。
膳を前に正座するおきぬに、兄弟は緊張の面持ちで……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
善太は、料亭の二代目である。
父は一代で小さな貸店舗の飯屋から始め、今の大きな料亭を築いた。
そうして、そこに欠かせないのは、父にとっての一番弟子、佐久造であった。佐久造はまだ善太が物心つく前より、飯屋の板場を見に来ており、善太の弟の善次郎が生まれる頃には買い出しなんぞについて行くようになり、善太の妹のおつたが生まれた頃には手習いを終え、飯屋の下足番を始めた。
ちょっとした珍しい食材や高価な調味料なんかが手に入ると、善太の両親は、それを佐久造にも必ず分けた。佐久造の家は、善太が幼い頃に住んでいた店舗兼住まいの近くにあって、三度の飯もそっちで食べていたから、佐久造が食べるのに困る子どもでなかったのは確かである。佐久造が下足番になる以前は、時折佐久造のお父ちゃんやお母ちゃんが、こちらに入りびたりでご迷惑をおかけしてはいないでしょうか、と顔を出し、幼い善太や善次郎、おつたにと玩具を買ってきてくれたものだ。
この頃は、独り身の男ばかりが客で、店は騒がしいというか、時には酔った客なんかもいたが、そうした中で、飄々と通うお客が何人かいた。質屋の大旦那もその一人で、まあ、当時は質屋の旦那だったのだろうが、こじゃれた装いで、店に通ってくれていたのを覚えている。
膳を前に、この質屋の旦那、大層お行儀がよろしかった。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、足の親指同士が離れぬようにし、膳が来るまでは手を太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃えて正座しておられる。
箸遣いもきれいであった。
そうした様子を、善太はそっと見ていた。
お代は同じでも、人の所作とは違うらしい、と思った。
そうしているうちに、自然と手習いでも、行儀よくするようになった。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、足の親指同士が離れぬようにして正座し、机に向かう。そうしていると、文字が美しく書け、算術も集中できるような気がした。これは、手習いを終えた後に、かなり役に立った。帳面のつけかたや、勘定の計算、その見やすさや正確さが商いには欠かせぬ。弟の善次郎も字は丁寧だし、算術も滞りなく習得した。
息子二人が手習いに通っている間に、店は評判が評判を呼び、長い列が連日できるようになり、とうとう大きな店に移った。店は小さな飯屋ではなくなり、いつしか商家の旦那衆や粋人の集まる場になった。店の間口はもちろんのこと、板場もぐんと広くなり、客間もこれまでの数倍になり、そのほとんどが個室になった。
ここでお父ちゃんが最も恐れたのは、今の状態に胡坐をかくことであった。
小さな店舗の時より、お父ちゃんは銭勘定と折り合いをつけながら、質よく身体に馴染みやすい食材を厳選してきた。その努力が伝わったのか、自然と客が二度、三度と訪れるようになった。それが大きな店構えに頼って、努力を怠るようになっては、きっと客は一度目、二度目と来ても、三度目はなくなる。それをいつも肝に銘じている。
だから、善太と善次郎は、料亭の二代目だからとすぐに板場には入れてもらえなかった。まずは下足番から学んだ。丁稚で入った、自分よりも年下の少年に仕事を教わった。少年の方が年下ではあるが、仕事を教えてもらう身、言葉、態度に気を付けるようにお父ちゃんに言い遣って、店に入った。
朝誰よりも早く起き、店の掃除や水汲み、そうして、帳面の付け方、食材の買い付けと順を追って、料亭のお商売を学び、お運びや、部屋の後片付けもした。
その間、とにかくお客がいてもいなくても、所作を気遣うことをきつく教えられた。
背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、足の親指同士が離れぬよう正座する。それを基本に動いていれば、客間の障子を開け閉めしている時などに、客が手水場へ向かうのに出くわしても、焦ることがない。一見お父ちゃんの仕事の教え方は厳しいように思われたけれど、実際にお店の全ての仕事を学び、把握し、そうして所作に気を付けていれば、なんら店の中で困らぬ。いつ、なんどきでも、対応できる。そういう力をつけてくれたのは、優しさであろう。
末子の妹、おつたは物心つく頃には大きな料亭のお嬢さんであった。おつたが着飾り、お稽古事に精を出していた頃、善太と善次郎は板場で料理を学んだ。
2
板場を仕切るお父ちゃんと佐久造は、とにかく手際がよかった。
そうして、舌が鋭い。
ちょっとした季節の変わり目の湿気や気温の変化で、食材の風味が変わるのにいち早く気づく。旬の食材も、どうすると最大限に活かせるか、一緒に使う食材を思案し、味付けは果実の皮を薄切りにして添えたり、絞汁を使ったり、出汁は絶妙の頃合いを見極め、包丁の手入れを欠かさない。
これは、言われた通り、間違ったら素直に謝る、というこれまでの仕事とは幾分か要領が違った。
おおよそのことは教えてもらえるし、真面目に見ていれば覚えられる。
だが、ここだ、という勘のようなもののつかみどころで戸惑う。
帰り際の客の声は、板場に届くこともある。
風味がよいとか、のど越しがよいとか、香りがよいとか、深みがあったとか、もう、お客によって、さまざまな言い方がある。
「ありがとうございます」と板場で見習いをしながら、否、それ以前に下足番を始める前、昔の店舗の奥の座敷で遊んでいた頃から、善太はそれらの声を聞いてきた。
だからかはわからぬが、料理をすると、その客らの声が甦る。
自分の作ったものは、それに相応する味なのか。
考えるとわからなくなる。
それは、善次郎も同じなようで、善太も善次郎も、最後には佐久造に味の確認をしてもらう。
もう、何べんも大丈夫だ、と言われても、今一度、と頼む。
佐久造は少々言葉や所作が荒いところがあるが、この時はいつも優しく、大丈夫だ、と必ず言う。
もっとも、正式にお墨付きをお父ちゃんにもらったのも、結構前のことであった。
客に出すのと同じ膳、皿に盛りつけた料理は一から作り、そうしてそれを、お父ちゃんの待つ部屋へ運んだ。
お父ちゃんは大きな料亭の主になって、いい着物をお母ちゃんに選んでもらうようにはなったが、根っからの料理人である。
もともと食材にこだわりのある人だが、今の店になってからは、食材を選ぶのに、昔ほど勘定に悩むことがなくなった。望むのにより近い食材を選び、出せるようになった。そうしたこだわりからか、お父ちゃんは年のわりに肌がきれいで、身体に緩みや衰えが見られぬ。それは、この家の家族、料理人も同じであった。ただ値の張る食材を、というのとは違って、混ざりもののない食材や調味料を基盤に、魚であれば鮮度、野菜であればその育ち方をよくよく観察して選ぶ。
そうして、その厳選した食材で、料理人の技と味覚を最大限に活かした料理を出す。
その生き方が、お父ちゃんという人の身体と心を培っている。
膳を持って入った部屋で、お父ちゃんは正座して、善治を待っていた。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬように。
いつもの、姿勢であった。
もっとも気の抜ける、楽しみである食を前に、お父ちゃんはとても厳かな顔をしている。
そうして、この日はまた、特別にそうであった。
お出しした膳にお父ちゃんは手を合わせ、「いただきます」と目を閉じて言った後、汁物から手にとった。
それは、それほど長い時間ではなかったのかも知れぬ。
だが、善太にとって、気を失うのではないかと思われるほどの緊張を要した。
お父ちゃんの前で背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬように正座し、脇は締めるか軽く開く程度で太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃えた手は、震えていた。
どのくらいの時だったろうか。
「ご馳走さまでした」と、箸を置く音がした。
はっとし、顔を上げる。
「よく、ここまで頑張ったな」
お父ちゃんの目に嘘はなかった。
善太は知らず知らずに浮かんだ涙を落とさぬよう、瞬きを堪え、「ありがとうございます」と、手をついた。
あの時、確かにお墨付きをもらった。
それなのに、未だにどこかで自信が持てぬ。
3
そんな善太に、転機が訪れた。
いつまでもこのままではいけぬ、とまるで囁かれたかのような出来事であった。
一つ目は、妹のおつたの結婚が決まった。
嫁ぎ先は、札差であった。
少し前から店を時折訪れていた札差の長男と、いつの間にかおつたは心を通わせていた。
大きな料亭の娘、といえば、まあ、そうで、お嬢さんと言われれば、それも本当であろう。
だが、如何せん、何代続いているのかはわからぬが、札差の家の跡継ぎと一緒になる。
お稽古事に通い、中でもお琴やお三味線が好きで、きれいな着物を着て楽し気にしていた妹のおつたに、果たして札差のご新造さんが務まるのか……。
幼い頃、面倒を見ていた折の、よだれで濡れた小さな手や、温かく、眠ってしまうとずっしりと重く感じた妹が思い出される。
そうして、もう一つの転機は、佐久造の暖簾分け話であった。
店の方は、いずれ善太、善次郎が継ぐのはわかっていた。
だが、どこかで佐久造がずっと店の板前でいてくれると思っていた。
いつまでも味の確認を佐久造に頼むとは考えてはいなかったが、いずれは、というくらいで、すっぱりと佐久造がこの店を出る、ということを考えてはいなかった。
まあ、いってみれば、善太の考えが甘かった。
いつかは、と思いながら、それを先延ばしにして、何の心構えもしていなかったのは、矢張り二代目の甘えか……。
はあっと、善太は溜息をつく。
「兄ちゃん、どうした」と、善次郎が訊ねる。
今日は佐久造が、どこぞの戯作者の先生のもとへ弁当を届けに行く日だとかで、昼の板場が一段落すると、早々に出かけた後である。
ほかの人間も夕刻まで一休みといったところだ。
二人は賄いのおにぎりに香のもの、魚のアラを使った味噌汁を前にし、向かい合った。
共に、疲れた時でも、膳を前にし、所作に気を付ける。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬように正座して、手を合わせる。
「兄ちゃん、そういえば、昼用の刺身は使い切った?」と善次郎が訊く。
「ああ、全部使ったよ」と善太は頷いた。
刺身にする魚は、買ってきて、時間が経つと風味が落ちる。まだ悪くなっていなくとも、風味が落ちたものは出してはいけない、と佐久造に教わった。佐久造は言葉で教えるだけでなく、寒い時期に、実際に買ってきたばかりの魚を捌いた刺身と、前日の夜の残りの刺身とを善太、善次郎に食べさせ、その味の違いを教えてくれた。
客がこの刺身の味を求めて来たのに、こっちの刺身が出てお代が同じなら、どうだろうか。がっかりするか。もう来ない、と思うか。
そんなふうに教えてくれる。
味の違いは理解できる。
だが、それを断言できるだけの自信がいつも善太にはない。
善次郎も同じか……。
米も然り。
同じ米であっても、研ぎ方、水加減、炊き方で、ずいぶんと異なる。
今日米を炊いたのは、善太だ。
正直なところ、客云々ではなく、佐久造を意識し、随分と気を付けて米を炊いている。
師である佐久造が、善太にとっては全てであり、それで店の味は保てているが、どこか本末転倒といった気がするのだ。
「ねえ、佐久造が暖簾分けしたら、私たちは大丈夫なんだろうか」
よく炊けた米は、冷めてもうまい。
米の味をかみしめながら、善太は善次郎を見た。
弟も、不安そうな顔をしている。
「お父ちゃんに佐久造の代わりをしてもらう?」
「ここまで頑張ったお父ちゃんに、そんなこと頼めないよ」
「だけど、店にお客が来なくなったら、お父ちゃん、お母ちゃんの隠居生活だって、保証できないよ」
「……嫌なことを言うねえ……」
周囲から見れば、大きな料亭を担う息子が二人。
将来は明るいばかりに見えるだろうが、この兄弟の心は暗かった。
4
おつたの祝言は、嫁ぎ先の札差の家で行われる。
そこで振る舞われる祝い膳は、佐久造に任された。
善太、善次郎も向こうの台所で腕を振るうつもりであったが、妹の祝言であり、信頼できる料理人がいるのだから、ここは佐久造に頼もうとお父ちゃんが言った。確かにそうなのだが、ほかにも佐久造がこの店を離れる前の最後の大仕事といったところか……。
祝言の前夜、いつものお商売が終わると、佐久造は翌日に備え、早々に引き上げた。
その後、どちらともなく善太と善次郎は板場に残った。
「兄ちゃん、もうじき、佐久造は暖簾分けでここを出るんだな……」
「ああ、そうだ」と善太は頷く。
これから店を探したり、いろいろと準備もあるだろうから、まだしばらくは居るだろうが、一年、二年といるわけではない。
「もし、私たちが娘だったら、佐久造はこのまま店にいたのかな……」
「そうかもな。商家では、番頭と娘が一緒になるっていうのが結構あるからね。料亭ともなれば、店の味もあるんだし、やっぱり頼りになる料理人と一緒になるんだろうな」
広々とした板場は、隅々まで片づけられ、料理道具は手入れが行き届いている。
その様子を善太は眺める。
「いっそのこと、私も娘だったらよかったのかも知れないねえ。この料亭を受け継ぐ器だと、どうしても思えないんだよ」
「それを言うなら私だってそうだよ。言われたことは、本当に頑張ってできるようにしてきたよ。だけど、もともと料亭の子でもない佐久造のように、自分でその道を決められたかって訊かれると、さっぱり自信がないんだよ」
善太と善次郎は溜息をつく。
「てことはあれかい? 兄ちゃんが娘だったら、兄ちゃんが佐久造と一緒になるってことになったのかい?」
「えええ、それは勘弁してもらいたいよ。だったら、おまえが佐久造と一緒におなりよ」
「いやいや、そこはさ、やっぱり、上の子に譲らないとね」
仮に娘だとしても、佐久造と一緒になるのはご免だ。
料理人としては天賦の才があるが、如何せん、気が荒い。
見た目はそこそこだが、仮に自分が娘だと考えて、どう思うかと問われれば、ちょっと自信がない。だったら誰がいいのかい? と訊かれてもわからぬ。
全ては仮の話だ。
5
そうして、翌日、粛々とおつたの祝言は挙げられた。
今さらながら、札差の家のご新造さんに妹がなるのは心もとない、と善太は思った。
だが、もう決まったこと。
そうして、善太たち兄妹は、お父ちゃん、お母ちゃんにしっかりと育ててもらった。そのことに一点の疑いもない。ならば、堂々としていよう。
お父ちゃんお母ちゃんに並び、善太は背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬようにし、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃え、正座した。
おつたが嫁入りすると、あちらで「おつたさま」と、かわいらしい娘が妹に付き添ってくれた。なんでも、おつた付きの女中なのだとか。いやはや、札差の家というのはそういうものなのか。本来なら、うちからそうした女中を行かせるものなのか……。わからぬが、おつたが、その女中を妹のようにかわいく思っているのが伝わってきたので、ああ、もうお任せしてよいのだろう、と思った。それに、なんにしろ、一緒になる札差の長男とおつたは、人前とあってさほど言葉を交わさぬが、互いに想い合っているのがわかる。
そうして、佐久造が心を込めた祝い膳を、座敷でいただいた。
考えてみれば、こうして客のような立場で、膳を前にするのは初めてであった。
なんと、それは贅沢なことなのだろう。
味や盛り付けなんかは、もちろん、普段の仕事を思い出さずにはいられぬが、それでもこうしておめでたい席で、ただ、出て来るものをいただく、というのは別格である。
善太は、今日は何も考えずにいただこう、と決めた。
せっかくの目出度い席。
佐久造のおつたへの贐(はなむけ)。
ならば、それはただただいただく、そこに徹しよう。
当たり前だが、料理はどれも大層旨かった。
ああ、店に来るお客というのは、こういうものなのか、と思った。
ただ、腹が減るから来る、というだけでなく、この味を、この場所で、という思いや、人付き合いの席で喜んでもらえるものを頼める店、という意味もあったのかも知れない。
己がこれまでひたすらに作り続けたものが、どのように迎えられていたのかを、善太は初めて知った。やはり、同じ思いなのだろうか。隣にいる善次郎も「旨いなあ」とかみしめるように言った。
これで大丈夫か、と散々おろおろしていた善太だったが、ここでようやく、その迷いが消えたのだった。
6
季節が移るのは早い。
桜の花見に始まり、川開き、と弁当の注文が数多入り、板場はいつも以上に忙しく、お父ちゃんも朝から板場に立つ日が続いた。
そうして、紅葉狩りまで行楽用の弁当注文が一段落といったところで佐久造は暖簾分けをし、店を出た。
佐久造は江戸の外れに、店を出すという。
善太たちの店とは違い、一人で切り盛りする、小さく、値段も安い飯屋にすると言っていた。場所が離れているから、こちらの店のお得意様が佐久造の店にそう頻繁に通えぬことは承知だが、それでも繁盛するだろうことは明らかである。
これまで兄のように慕い、そうして兄弟子として毎日会っていた佐久造と離れるのは寂しいが、それも仕方のないことである。
行楽弁当の注文にかこつけて、定期的に実家の方へ顔を見せられるようにしてもらっているおつたも、そのお付のおきぬという娘も、佐久造がこの店を出ると聞いて、大層寂しそうであった。
7
佐久造が去った後も、善太、善次郎は板場でなんとかやっていた。
味が変わったと言われたとか、常連が来なくなったといったことも今のところ起きてはおらぬ。
だが、やはり佐久造がいた時の状態を維持し続けるだけ、というわけにはいかぬ。守るべき味と、新たに提供していく味とが、店には必要だとお父ちゃんは考えている。
ある時、出入りの乾物屋がよい昆布が入ったと荷をほどきながら言った。
これまで使っていたものもよいですが、これも試してはいかがでしょう、ずっと使うかは追い追い決めていただいて構いません、少しお安くすしますからと言う。
こういう時、自分たちだけで判断のできぬ善太、善次郎はお父ちゃんを呼んだ。
お父ちゃんは勧められた昆布といつもの昆布の両方を買い、商人が帰った後、善太と善次郎にかつおとの合わせ出汁を完成させ、これからの季節のつみれ汁に使えるようにしろと言い置いた。つみれ汁は、昆布だしでも十分旨いが、この店ではお父ちゃんの代からかつお節との合わせ出汁だ。
店で使う昆布もかつお節なかなかに高価な材料であるから、無駄にはせず、それでいて納得できる味ができるまで合わせ出汁を作らなければならぬ。
二人して、店が終わった後に、あれこれと試し始めた。
だが、正直、どれも旨いのだ。
これがいい、と言われれば、これがいい。
だが、こっちもいいのではないか、と言われれば、そうだ、というふうにも思える。
二人して試行錯誤を続ければ、続けるほど、わからなくなってくる。
それでも店は昼と夜に開けるから、その用意もあるし、ほとほと参ってしまった。
「私は、弟のあんたがいてよかったよ。一人じゃあ、とても無理だ」
「私だって、兄ちゃんがいてよかった。一人で何かを決めるって器じゃないんだよ」
二人して、昼の店が終わると、はあ、と座り込んだ。
「なんだ、お前たち、辛気臭い顔して」
顔を上げると、お父ちゃんがいる。
家族とはいえ、店では主と板前。
さっと立ち上がる。
「少し外に出て来い。歩いて、腹空かせて、また考えた方がまだましだろう」
一向につみれ汁の合わせ出汁が決まらぬことに気づいていたお父ちゃんにそう言われ、立派な大人の兄弟は言葉なく、店を出た。
「これは、誰かに訊いた方がいいんじゃないか?」
ぽつり、と善次郎が言った。
二人はいつしか店を離れ、川沿いを歩いていた。
花の見ごろは過ぎたとはいえ、まだいくつかの花が優雅にその花弁を揺らしている。
「おや、あれは」と、善太は向こうにいる娘に気づいた。
おつたのお付女中のおきぬである。
まだ幼いが、しっかりとした娘で、だが、それを本人が自覚しておらぬのか、もともとの性格なのか、優しく、柔軟である。この娘がおつたに付いてくれる、ということに、善太は随分と感謝している。
今日はおきぬ一人である。
「おきぬさん」と声をかけると、おきぬは二人を認め、さっと頭を下げる。
「今日はどうしたんだい?」
「おつたさまは、若旦那さまと今日おでかけなさって、私は付いて来なくてよい、と仰せつかりましたので、お店の方の遣いに行ってきたところです」
おつたの面倒を見なくてよい日でも、この娘は自らほかの者の仕事を肩代わりする性分らしい。
えらいねえ、と善次郎が呟く。
「おつたは迷惑をかけちゃあいないかい? まあ、私がこう聞いても、おきぬさんは『はい』とは言わないんだろうけどねえ」
苦笑交じりに善太が言うと、「とんでもございません、おつたさまには、本当によくしていただいております。おつたさまに付かせていただいてすぐ、お店でお茶とお菓子を私の分も頼んでくださったんです。初めていただいたもので、どう美味しいかはわかりませんでしたが、そんな私でも、口や鼻から抵抗なく身体に入りやすいものというのは、美味しいのだとわかりました。おつたさまは、そうしたことも教えてくださいます」と言う。
最初は、そうか、そうか、と頷いていた善太だったが、後半で、ふと顔を上げた。
善次郎も善太を見ている。
善太と善次郎は頷き合った。
そうして、おきぬに頼みがある、と言い、店へ連れて行った。
道草を食っていると思われてはおきぬが気の毒だから、店の者にこちらで少しおきぬに用があるので、おきぬを借りたい、それほど時間は取らせず、帰りは店の者に送らせるという旨を書いた文を、おつたの嫁ぎ先であり、おきぬの奉公先である札差に持って行かせた。
おきぬは板場での手伝いと聞き、水汲みや掃除、皿洗いだと思っていたらしい。
だが、善太と善次郎が「ちょっと夕餉前までここの一室を借りるよ」と断っておきぬを連れて行ったのは、客間の一室であった。
そこの座布団を指し、「悪いが、ちょっとここで待っていてもらえるかい?」と言い、女中に茶を出しておくように伝えた。
おきぬは、「私がこの豪華なお部屋にでございますか?」と目を白黒させている。
「ああ」と頷き、善太は「内緒の話だが、おきぬさんは、ここのお客より重要だ。何せこの店の将来がかかっているからね」と付け加えた。
「一体どういう……」
「まあまあ、難しいことじゃあないよ」と、善太はなんとか言い置く。
おきぬは「左様でございますか」と神妙な顔で首を傾げ、ようやく腰をおろした。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃え、足の親指同士が離れぬように正座する。
着ているのは木綿だが、どこぞのお嬢さんのような気品があった。
もともとかわいらしい娘ではあったが、なるほど、あの札差のお内儀さんが、嫁のお付に選んだだけのことはある。
いや、感心している場合じゃあないよ、と善太は板場にとって返す。
この千載一遇の機会、絶対に逃せぬ。
善太と善次郎はいくつもの小鍋に入っている合わせ出汁を、まず小皿に入れ、味を見る。
どれもいい。
その時、おつたの顔が浮かんだ。
おきぬを連れて来たからであろう。
「つみれ汁、おつたが好きだったなあ」と善次郎が言う。
「ああ、よくお替りをしていた」と善太も言う。
今ほどよいかつおや昆布が使えていたわけではなかった。
だが、家族のためにお母ちゃんが作るつみれ汁は、角のない味で、それこそ先ほどおきぬが言ったように、口や鼻が抗うことなく、身体に入った。
二人は一通り小鍋の出汁を味見した後、どちらともなく、「これか」と同じ小鍋を指した。
そうした後、何度か候補に挙がったものふたつの出汁で、三つのつみれ汁を作り、膳に載せて、おきぬのところへ持って行った。
おきぬが緊張するとわかっていつつも、善太、善次郎ともに、おきぬの前に正座した。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、足の親指同士が離れぬようにし、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃える。
「いただきます」と、おきぬは行儀よく、箸を持つ。
小さなおきぬに、朱塗りの椀がどんぶりのように大きく見える。
知らずに善太は手に冷たい汗をかき、善次郎は全身に力を入れていた。
「ごちそうさまでした」とやがておきぬは、全ての椀を空けた。
「どう、でした」と善次郎が訊く。
「どれもとても美味しかったです。ありがとうございます」
「その中で、特に気にいったものは?」と善太が訊く。
「私なんぞが言っていいのかわかりませんが」とおきぬが少し戸惑う。
言ってくれていいんだって、と善太は焦れる思いで次を待つ。
「高級な味というのでしょうか、そう思うのはこちらの椀、風味と味が強いからだと思います。そうして、うちの大旦那さまがお好きなのはこちらの椀、あっさりとした味で塩気をあまり感じず、ほかの香のものや塩を振った魚の切り身と一緒にいただいた時に食べやすいと思います。最後にこちらの椀は、おつたさまが恐らくお喜びになる味かと。しっかりとした風味に優しい味で、最初の椀と二番目の椀のよいところを揃えたものだと思いました」
なんとまあ、聡い娘だと善太、善次郎は目を見張った。
そうか、そういうことか……。
散々悩んだが、その答えは、たまたま道で会った娘の意見によって、あっさりと導き出された。
いやいや、悩み過ぎてちょっとわけがわからなくなったのかも知れぬ。
……まあ、味は完成した、ということだ。
このまま誰かに頼りっきりの料理人兄弟というわけにはいかないが、今回は味を完成させられたからよしとする。
そうして、この味は、試行錯誤して到達したから、出汁を取るのに、誰かに確認を取ることはない。
少しづつでも前進できればいいじゃあないか……。
善太と善次郎はお互いを見遣り、頷き合った。
まだ明るいし、一人で帰れますと言うおきぬに手代をつけて送る際には、善太、善次郎は深々と頭を下げた。
今日の夜にでもお父ちゃんにつみれ汁の出汁をみてもらうつもりだが、おそらくもう答えは出ている。もし仮にお父ちゃんが何かを言ったとしても、この味で、というだけの自信が今の善太、善次郎にはあった。
おきぬへ改めて礼をしたいが、多分あの娘は何も受け取らぬだろう。
だとすれば、おつたが来る時に出す昼餉とでも口実をつけて、おきぬにお礼の膳を出そうか。今日のつみれ汁を添えて出せば、きっとその意味を汲んでくれるに違いない。

![[357]お江戸正座26](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)