[306]オダマキの正座おやつ
 タイトル:オダマキの正座おやつ
タイトル:オダマキの正座おやつ
掲載日:2024/09/07
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
傀儡子の少女、オダマキの人形劇は繁盛している。
最近、誰に言われたわけでもないのに、見物に来る子どもたちが、ちゃんと正座している。どうやら傀儡子仲間がお付き合いしている九条家の薫丸(くゆりまる)がお世話になっている、正座師匠の正座の所作をマネしているらしい。オダマキは、お利口な子どもたちに何かお礼をしたい、と親方に相談する。

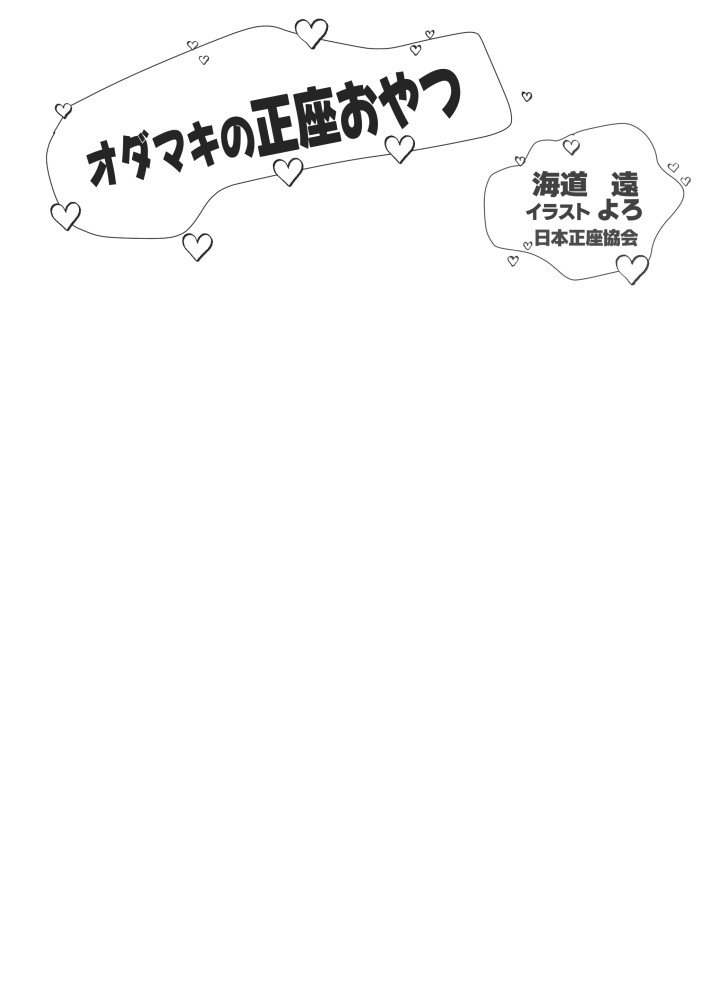
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章
【人形の会話】
「さあさあ、おやじさん、ここらで休憩して食べていかんかね」
赤い前掛けをつけた娘っ子が声をかけた。
「おお、こりゃあ、美味そうなダンゴだな。一皿もらおうか。なんていうダンゴだ?」
「桃ダンゴというんだよ。外側は油で揚げてあるから茶色いが、中は桃色で美しい」
「わしゃあ、ダンゴは美しいよりうまい方がいいのう」
「はい、じゃあ、今日はここまで!」
傀儡子のオダマキが言いながら箱の中に人形を仕舞いかけると、子どもたちは残念そうに立ち上がり、ひとりずつザルに野菜や豆の入った袋を入れていく。
「はい、ありがとうね」
子どもたちはシャンと立ち、むしろの上に膝をついてお尻の下に着物を敷いて座ってから、かかとの上に座った。そして、いっせいに頭を下げた。
「オダマキねえちゃん、ありがとう。また続きを見に来るね!」
「はいよ! 待ってるよ!」
最近、誰に言われたわけでもないのに、オダマキの演じる人形劇を見る小さな子どもたちが正座しはじめた。
まだグラグラしたり、しびれるとすぐに立ち上がったりしているが、万古老師匠から正座のお稽古を受けた、九条家の若君、薫丸や傀儡子仲間の半夏(はんげ)にいさんが見物する時の正座をマネしているらしい。
「ねえ、親方。この子たちにあたいの人形劇を見てくれるお礼に、おやつをあげたいんだけど……」
黒い口ひげを生やした親方に相談してみる。
「おやつ? 甘いものか? 貴族様しかお口にできない高級品だろ」
「だから、菓子職人のリ・チャンシーさんから余りものでも削りカスでもいいからもらって……」
「ああ、唐から時々やってくる菓子職人のにいさんかい?」
「そう。この前、薫丸(くゆりまる)からもらった飴がとっても美味しかったから、あの子たちにも味合わせてやりたいんだよ。作り方、リ・チャンシーさんは教えてくれないだろうか?」
「おそらく高い原材料がかかるぞ。その分はどうするんだ?」
「あたいがリ・チャンシーさんのお世話係をして賃金もらって、その中から支払うっての、どう?」
薫丸に頼んで、九条家に滞在中のリ・チャンシーに会わせてもらうことにする。
オダマキはもじもじして、真っ赤な顔になってやっとお願いする。
「え? 子どもたちに正座のご褒美のおやつを配りたいだって?」
リ・チャンシーは白い歯を見せて清々しく笑った。快く引き受ける。
「原材料って高いんでしょうね?」
オダマキがおずおずと尋ねると、彼は、
「まかしとけ!」
と自信満々だ。
「手伝いしてる間、傀儡子の人形劇はどうするのだ?」
「やるよ! 1日3回。それ以外はリ・チャンシーさんの手伝いするよ」
「菓子作りならひとりで十分だ。私の着物の繕いものでもしてくれた方が助かるよ。できるかな?」
「まかしといて! 人形たちは、あたいが作ってるんだから縫いものならバッチリだよ」
「じゃあ、商談成立だね」
オダマキは大喜びで、親方に報告する。
「ぎぶアンドていくだな」
親方は片目をつむってみせる。
万古老の用事で九条家に来た百世(ももせ)は、薫丸からおやつのことを聞き、裏口で仲良く話しているリ・チャンシーとオダマキを見かけた。なんとなく面白くない。
「オダマキ、あんた、もしかしてリ・チャンシーさんのことを好きなの? それで弟子入りなんか思いついたんだね」
百世がトゲのような視線で尋ねた。
「そ……」
「そうなんでしょう。あたいよりひとつ上なのに、全然、胸が無いクセして! 女のカタチしてないじゃないの! あたいの方が、ほら、『鉢かづき姫』の鉢より大きいんじゃないかな?」
百世は得意げに豊満な胸を揺らせた。
「あたいだって、そのうち大きくなるわよ!」
「へええ、いつ? 証拠を見せてもらおうじゃないの」
「威張らないでよ、胸が大きいからって、和歌が上手に読めたりお琴が上手なわけでもないようだから!」
ふたりはにらめっこの体制になった。
「こ、こら、オダマキ、はしたないぞ」
薫丸が中に入った。
「百世もやめなよ、みっともないぞ」
山から迎えに来ていた、百世の兄弟弟子の流転(るてん)も引き止めた。
「帰るぞ!」
ふたりは引き裂かれるように、互いの迎えに引きずられていった。
オダマキは、人形の箱を持って一座の泊まっている古寺のお堂に戻った。
一座の連中は、酒が入っていたヒサゴなど取り散らかしたまま、高いびきで寝ている。
オダマキの耳の奥で、さっき百世が言った言葉が反響した。
『リ・チャンシーさんのことが好きなの? それで弟子入りなんか……』
オダマキは顔をブンブン左右に振った。
「それじゃ、人形劇を観てくれる子どもたちを利用しようとしたみたいじゃないの! そうじゃないわ! あたいは心からお礼におやつをあげたいだけよ!」
第二章
「ンモオォ~~~!」
まず、オダマキはリ・チャンシーについていって、農家の乳牛をおっかなびっくり借りてきた。
「でっかいお乳だねえ。……羨ましいくらい」
オダマキは自分の胸と見比べてもらした。
リ・チャンシーは牛から絞った新鮮な牛乳から、子どもたちに配る飴を、牛乳を茶色まで煮詰めて作ってくれた。貴重な砂糖も、クルミも入れてあるから甘くて美味しい。
「すごい! こんなにたくさん、甘いのを!」
オダマキは丁寧にお礼を言った。
その日も、オダマキの人形劇を見ていた子どもたちは、可愛い膝小僧を並べて正座していた。
人形劇が終わり、親から預かってきた畑の作物を渡す。痩せた菜っ葉や大根だが、引き換えにオダマキは、リ・チャンシーが作った飴をひとりずつの口の中に入れていく。
「なんだ、これ? 甘い!」
「正座して見てくれたご褒美だよ」
大喜びしている子どもたち。
そこへいきなり、やってきた百世が飴を取り上げて、怖い顔で子どもに叱りつける。
「褒美なんてまだ早い! あんなひょろひょろ正座!」
「百世ちゃん……」
オダマキは呆然とする。
「どうしたの? いつもの優しい百世ちゃんらしくない」
「子どもたちがつけ上がるだけさ! 人形劇を見物したら、あんな高級な飴をもらえるってね。リ・チャンシーさんの好意に甘えすぎちゃいけないよ」
「リ・チャンシーさんのご好意に甘えすぎ……あたい、そんなつもりじゃ……」
オダマキは唇を震わせた。
「甘えすぎだよ! あんなおやつ、貴族にしか口にできないんだよ」
「それは……薄々、分かってはいたけど……」
オダマキの瞳から、飴玉に負けないような大きな涙が落ちた。
「おい! 何やってんだ」
駆け寄ったのは、薫丸だ。
「百世! オダマキはリ・チャンシーさんの身の回りのことさせてもらって給金もらってるんだ。その中から飴代を支払ってるんだから、文句ないだろ」
「オダマキにどれだけ働きがあるのさ」
「これくらい」
背後から現れたリ・チャンシーの手には、金ピカの大判が握られている。
「オダマキ、今日の給金だ」
「ひゃあ〜〜!」
大人の手のひらよりデカい大判に、薫丸も百世も、子どもたちも目を見開いて叫び声を上げた。
「キンキンピカピカだ!」
「こんなデカい金、初めて見た!」
「今日はよく働いてくれた。私の繕いものを全部きれいにしてくれて部屋の掃除や洗濯も。はい、この中からおやつの原材料の費用を払ってくれればいいからな」
オダマキの頭を撫でながら言った。
「これでいいんだろ、百世ちゃん」
「オダマキの給金がこれ?」
「そうだよ」
「そ、そんなバカな! リ・チャンシーさん、どうかしたんじゃないの?」
「いや、妥当な給金だよ。よく考えて決めた。オダマキの人形劇を正座して見ている子どもたちに感動したんだ。そしてその子たちにご褒美をあげたいというオダマキの心にね」
百世は口をモゴモゴさせてから、プイと横を向いた。
第三章
「オダマキ、今日の仕事は終わったか?」
「はい! 今日も子どもたちが正座して観てくれました! 先生の作った桃団子、好評でしたよ」
「そうか、良かった。じゃあ、今日は『龍のふずく』っていうのを作ってみよう」
「『ふずく』?」
「ふずく」を作るために、リ・チャンシーは薫丸の九条家の屋敷の台所を借りた。彼が調理用白衣を着るとバリッとして、とても似合っている。オダマキは改めて見惚れた。
「蒸し菓子の一種だ。米粉にアマヅラ煎(蔓から採った甘味料)とほんのり色のつく粉を混ぜて丸太状に作り、布巾で包んで蒸す。蒸し上がったものを切ってそろえる。涼しいところに置いて冷えるのを待つ。ペロンペロンになったら出来上がりだ」
リ・チャンシーさんは手際良く「ふずく」をカタチ作り、オダマキと腰かけて待った。
「どうして『龍のふずく』って言うの?」
「さあ、何故かなあ、出来上がってからのお楽しみだ」
庭の奥から鹿威し(ししおどし)のいくつかめの音がカコーン! と響き、オダマキとリ・チャンシーは笑顔を見合わせた。
「100! 鳴った! 『ふずく』ができてるかしら?」
ふたりは、それっ! と井戸端へ走っていった。鶴瓶を巻き上げるのももどかしく桶を引き上げた。
中には月桃(げっとう)の葉で包んだ「ふずく」が冷えている。
葉を広げたオダマキが、
「わあ〜〜きれい!」
と叫んだのも無理はない。「ふずく」の中には細かい金色の粉がキラキラしていたのだ。
「なんでこんなに金色にキラキラしてるの?」
「ははは、ナイシヨだよ。それより食べてみなさい」
オダマキは一口食べた。
こんなにちゅるんとして、甘くて喉越しの良い食べ物は生まれて初めてだ。
「じゃ、明日、人形劇が終わったら、子どもたちにくばってあげなさい」
「はい!」
第四章
いよいよ次の日、人形劇が終わって、子どもたちの代表、ともりという女の子が丁寧に正座の号令をかける。
「はい、みんな、真っ直ぐ立ちましょう。それから、床に膝を付き、着物をお尻の下に敷きながら、かかとの上に座りましょう」
「はぁい」
可愛い手を挙げて、皆、上手に正座ができた。
オダマキとリ・チャンシーさんが九条家の井戸から桶を運んできた。
中には月桃の葉の包みが、たくさん入っている。オダマキはひとつずつ取り出して、子どもたちに配っていく。
さっそく葉を広げた子どもらは、中身にかぶりついて、
「わ〜〜、ちゅるんちゅるんだ!」
「甘い! 冷たい!」
「美味しいね!」
子どもたちがひとつでもたくさん取ろうと殺到する。
ひとりの子が混乱の中で「ふずく」を地面に落として、踏んでしまった。
「あ~~ん、あたいのおやつが~~!」
すると、その子の兄らしき子が、妹の「ふずく」を踏んだ子の分を取り上げて地面にぶつけた。
「何すんだっ」
「最初に踏んづけた子が悪いんじゃないかっ。こんな貴重なおやつを!」
「なんだって、おかみさん、うちの子が悪いってのかい?」
「そうだよ。しつけがなってないってんだよ!」
大人まで怒り出し、つかみ合いのケンカまでする始末だ。
見物人全部を巻き込み、正座したまま「ふずく」の投げ合いまでやってしまい、ついには優しいリ・チャンシーから、
「食べ物を粗末にするとはどういうことだ〜〜〜!」
カミナリが落ちた。流転も珍しく本気で怒る。
「正座したまま、なんてことを!」
リ・チャンシーが通力で万古老師匠にも知らせ、かけつけてきて改めて正座の意味を諭した。
「親御さんたち、落ち着いて。正座とは相手をうやまう態度だ。せっかく子どもたちが自分から正座を始めたというのに、子どもによくある争いを目撃したからとて、心を乱してはいかん。食べ物はとても貴重だ。リ・チャンシーどののお菓子も、もちろんな」
一同、正座して頭を下げ、一座の親方も平謝りした。
第五章
夜になって、百世がそっとリ・チャンシーの部屋に行くと、書き物をしていた。
その後、リ・チャンシーが席を立った隙に机の上を見てみると、普通の文字ではなく「龍文字」であることが百世には分かった。
「あ、これなら読めるわ」
仙界の者だけが読める文字で、サッと目を通すとどうやら愛おしい妻に当てた手紙だ。
昼間のことをちゃんと謝ろうと思った、オダマキもやってきて手紙を見るがさっぱり読めない。
「なに? こんな文字、初めて見るわ」
百世が手紙を手にした。
「これはリ・チャンシーさんが奥さんに当てた手紙だよ。……子どももいるようなことが書いてある」
「リ・チャンシーさんに奥さんと子ども……!」
オダマキはへなへなとなるが、百世は、
「本妻がなによ! 2番目でも3番目でもかまわない! そのうち順番を抜いてやる」
萎れるどころか意気揚々となって、百世は大股でその場を後にした。
一方、オダマキはショックのどん底だ。
(リ・チャンシーさんに奥さんと子どもがいたなんて、考えてもみなかったわ……)
龍文字というのが書かれた紙を見つめて涙した。
「何をおマセなこと言ってるんだ、オダマキ」
背後から声をかけたのは、薫丸だった。
「薫丸……」
「お前なんか、まだまだ子どもじゃないか。リ・チャンシーさんは立派な大人だ。似合わないよ」
「ひどいわ……。あたいだって後2、3年もすれば誰かと世帯を持ったっておかしくないトシよ」
平安時代の婚期は、オナゴなら12〜18くらいだ。オダマキが怒るのも無理はない。
「あ、あ、俺が悪かった! つい……俺もびっくりしたんだよ。オダマキがいつの間にか、こんなことで悩む女の子になっていたなんて……」
薫丸がなんとか言い繕った。
そこへ、リ・チャンシーさんが帰ってきた。ふたりは慌てて何事もなかったように部屋を片付けている風をよそおった。
「やあ、オダマキ。今日も頑張ってくれたようだな。はい。今日の給金」
金ピカの大判を差し出した。
「また、こんなに沢山! ありがとうございます」
オダマキが受け取った後、リ・チャンシーが頭を押さえてふらふらしているではないか。
「あれ? リ・チャンシーさん、顔色が良くないんじゃないですか?」
薫丸が言うと同時に、リ・チャンシーの身体はぐらりと傾き、オダマキの肩にもたれかかった。
「チャ……リ・チャンシーさん?」
オダマキが支えたリ・チャンシーの肩には、血が大きく滲んでいるではないか。
「大変だ! うちのかかりつけの薬師を呼んでくる!」
薫丸が飛び出していった。
第六章
リ・チャンシーは青い顔をして横になっていた。
薬師は曇った顔で、駆けつけてきた万古老師匠を廊下に連れだした。
「出血は大したことはないが、あの青年は人ではありませんな」
「やはり、お分かりになりましたか」
「私とて大陸に渡って医術を学んだもの。天部のもののことも、それとなく分かります。青年はウロコを無理に剥がしたようですな」
「ウロコを……」
万古老が首をかしげた時、廊下に飛び出てきたオダマキが金ピカ大判のものを持ってきた。
「もしかして、これのことかな?」
「オダマキ、これは?」
「リ・チャンシーさんがあたいにくれた給金!」
「ひえっ! 換金すればいくらになると思うておるのじゃ?」
「さあ?」
「城がひとつ建てられるぞ! リ・チャンシーどのは我が身を削り、この子に給金を……これではまるで『ツルの恩返し』ではないか」
万古老は目元に袖をあてた。
薫丸も廊下に飛び出してきて、
「オダマキ、お前、何かリ・チャンシーさんに恩を売った覚えでもあるのか? 冬に何かの命を助けたとか」
「恩? ううん、べつに……。そ、そう言えば」
「なんだ?」
「いつぞや、一座の皆が池で龍すくいした時に、一匹だけ黄色いのがいたから、逃がしてやった!」
「それだ、きっと。黄色い龍がリ・チャンシーさんの子どもの龍だったに違いない!」
「ええ?」
「そうでなければ自分の身体を傷つけてまで、オダマキの願いを叶えてやるなんてことはしないだろう」
万古老とオダマキは考えこんだ。
「と、とにかく、これ以上、リ・チャンシーどのには負担をかけさせぬようにの!」
薬師は言い置いていった。
リ・チャンシーが寝込んでいる間に、オダマキは先日の「龍のふずく」を練習して、ばっちり作れるようになった。
色と味を変えて、毎日「ふずく」を作った。
金粉を散らして中に入れたので、光が当たるとキラキラと美しく反射する。
一座の曲芸師が、元気よく新しい稽古をはじめた。
桶を締める大きなタガの輪を太くして、その中を子どもにピョンと跳んでくぐらせる。
親方がやってきて、
「新しいワザかい?」
「ああ。この前、お菓子の投げ合いがあったろう。それから考えついたんだ。うちの小さい子に代わりをさせ、空中で一回転させるんだ」
曲芸師の父親が張り切って答えた。
「そりゃすごいワザだが、くれぐれもケガさせぬよう気をつけろ」
親方は念を押した。
第七章
「いいか、頑張れよ」
曲芸係のベン吉が弟に言い聞かせている。
「俺はもう、身体が大きくなっちまってできないが、お前ならできる」
「うん! にいちゃん! で、今日のおやつは?」
「知るかよ、お菓子職人が寝込んでるそうだから、おやつはナシだろ」
「ちぇっ、つまんねえの」
ベン吉の弟は舌打ちしてションボリした。
しかし、興行は大盛況だ。
火のつけられた桶の輪をくぐり抜け、一回転して着地するベン吉の弟、ブン太の身軽さに、皆はやんやのコーフンだ。
ブン太は3回めに挑戦して、
「やった―――!」
と思った瞬間に、天の月が薄闇に覆われて赤黒くなった。なんとも背筋をゾクリとさせる血のような色だ。風が生ぬるい。
「さっきまで昼だったのに、急に夜になったわ!」
「いったい、これは?」
見物人たちがさわいだ。
瞬間に、輪の炎がブン太の着物にボッと燃え移った。
「ギャ――ッ!」
仲間がとっさに防火用水をぶっかけ、ブン太の火は鎮まった。
次の瞬間、赤黒い月の方角から得体の知れない黒い巨大なものが飛び出してきた。
翼がバサバサする音がする。
「きゃ――!」
「助けて!」
ベン吉と弟のブン太が得体の知れないものに捕まったようだ。
「ベン吉~~~! ブン太!」
駆けつけたのは薫丸だ。
「お前は、人を食う悪魔、赤闇(あかやみ)!」
「赤闇?」
「ああ! リ・チャンシー先生の中国の書物に書いてあった。人が嫉妬心や敵対心、虚栄心を持った時、惹かれて姿を現すと」
薫丸が弓をつがえて矢を放ったが、赤闇とやらの薄い翼を突き抜けただけで勢力は衰えていない。
今度は一座の仲間に襲いかかって、ひとりの男を背後から捕まえた。真っ赤な爛々とした眼、血のしたたるような赤い口腔だけが見える。
半夏が大股に駆けてきて、強弓(ごうきゅう)を構えた。
が―――、赤闇の口が、飛んできた矢を難なくくわえ、噛み砕いてしまった。
「わ〜〜! 半夏さまの矢が!」
「このままじゃ、みんな喰われてしまう!」
第八章
そこへ、
「そうはさせないよっ!」
オダマキが両手に桶を持って駆けてきて、中のものを赤闇に向かって投げつける。
それは赤闇の身体にベタベタと張り付いていき、獲物の男を獲り逃がした。
「オダマキ、これは?」
「薫丸! 半夏さん! 屋敷からもっと桶を持ってきて!」
「おう!」
ふたりが桶を運んできて、赤闇に隙を与えないほどベタベタしたものを投げつけて動きを封じた。
「これは、おやつの『ふずく』じゃないのか?」
薫丸がひと口食べながら言った。
「そうよ。龍の金箔入りだから、魔物は動きがとれなくなる」
「いいのか、リ・チャンシー先生から叱られるぞ! 食べ物を投げつけるなんて!」
赤闇は両目に「ふずく」を貼り付けられて、何も見えなくなるわ、手足にも投げつけられて身動きができなくなるわで、よろよろと立ち上がると、赤い月に向かって飛んでいった。
「オダマキちゃんっ! ありがとう、弟を救けてくれて」
ベン吉が、オダマキに正座して頭を下げた。弟のブン太も同じように頭を下げる。
ふたりの親の曲芸師のオヤジも、子どもたちと同じように正座して礼を言った。
「ふたりとも無事でよかったわ」
「オダマキ! 大丈夫か~~!」
リ・チャンシーも駆けつけた。
薫丸が、
「リ・チャンシー先生、食べ物を投げて、こんなに散らかしてしまいましたが、どうかオダマキを叱らないでやってください! みんなをあの化け物から助けようと一生懸命だったのです」
「はは、わかってるよ。『ふずく』を投げつけるように言ったのは私なのだ」
「ええっ?」
「横になっている間、机の上の小さな渾天儀(こんてんぎ)を見ていて、月食の日にちを予知していたのだ。月食には赤闇が現れやすいという伝承も読んでいたのでな」
「それで、あたいにたくさん『ふずく』を作るよう支持されたんですね」
オダマキは合点がいってもらした。
「~~ってことは、また、金のウロコを使ったのですかっ」
正座師匠の万古老が駆けつけてきた。
リ・チャンシーは膝を整えて万古老に頭を下げた。
「申し訳ありません。万古老師匠。あれほどお気にかけてくださった約束を破って起き上がってしまいまして……」
「い、いや、リ・チャンシーさんから丁寧に正座して謝られると、ワシも困りますが」
「困るのは私の方です」
ふたりとも互いに正座で頭を下げた。
第九章
「そこにいらっしゃるのは万古のお師匠さまですか?」
顔面に「ふずく」を貼り付けたまま、手探りで百世がよろよろと歩いてきた。
「百世、心に醜い感情が湧いたことを認めるか」
万古老師匠はいつになく厳しい声音で言った。
「『嫉妬』や『悪口』を言うたのではないか?」
百世の心にズキンと来るものがあった。
「それに、己の自慢をして、人を貶めることをしたのではないか? 赤闇はそういう悪い精神が大好きで寄ってくるのじゃ」
百世は唇を噛み締めた。
オダマキにさんざんひどいことを言ったあげく、自分の胸を自慢したことはよく分かっている。
「も、申し訳ございません、お師匠……」
正座して頭を下げた。
「謝る相手はワシではなかろうが」
百世はハッとして立ち上がり、
「薫丸! 確かそこにいたね! オダマキはどこ?」
「あたいならさっきからお師匠の隣にいるよ」
「ああ、オダマキ、あたい、ひどいことを言ってしまったね! ごめんよ、許しておくれ!」
地面についた両手にオダマキの手が覆った。
「百世……。あたいも、正座してくれる子どもたちにお菓子を振る舞ったりして。自分の人形劇を見せびらかそうとした……きょ……きょ……」
「虚栄心じゃ」
万古老が助け舟を出した。
「そう! その虚栄心を満たそうとしていたよ。ごめんなさい」
「百世……」
オダマキが手拭きで百世の顔をぬぐい、ふたりは泣き笑いして仲直りした。
「じゃあ、私は何が原因なのです?」
顔面に「ふずく」を貼り付けたまま、ふらふら歩いてきたのは、九条家の女房のひじきだ。
「気の毒じゃが、それはただの『とばっちり』ですな」
万古老が笑いをこらえて言った。
第十章
「ああ、これは……」
リ・チャンシーさんが辺りに散らばっている「ふずく」を、つくづく見渡して絶句した。
「張り切って作りすぎたかしら……」
「いや、皆が無事ならいいんだよ」
懐から布巾を出して、ひじきの顔を拭いてやった。
目が見えるようになって、リ・チャンシーに顔を拭いてもらったと知ったひじきは、真っ赤になった。
「こ、これはリ・チャンシーさん、お手を煩わせまして! でも、おかげさまでリ・チャンシーさんの好い香りが、鼻の奥まで染みとおりましたわ!」
「リ・チャンシーさんの好い香りですって?」
百世とオダマキが振り返った。
「私も拭いてください!」
「私もこれから塗りつけますから、私も!」
オダマキは落ちていた「ふずく」を拾ってまで顔に貼り付けている。
ふと気づくと、落ちていた「ふずく」を拾い集めている人々がたくさんいるではないか。まだ夜中なので、提灯など持ってきた者もいる。
「ふずく」には金粉が混じっているので換金でもするつもりなのか。
万古老は、やれやれと大きなため息をついた。
「これでは、赤闇もいつまでたっても忙しいわけじゃのう」
「緊急時とはいえ、私も自分のウロコなんぞを使ったのが悪かったのです」
リ・チャンシーが頭を下げた。
「皆さま、ご覧あれ。この青年の謙遜(けんそん)した態度を!」
「万古老師匠、私は、子どもの命を人間さまに助けていただいたことがあるのです。こんなウロコくらいどうということはありません。が、争いの元になるのなら本末転倒ですから、もういたしません」
髪の毛、一糸乱れぬ髷(まげ)の頭を下げて、地面に正座して丁寧に謝った。
「ううむ、さすがはリ・チャンシーどの。謝る座礼にも心がこもりすぎて、こちらが恥ずかしくなるくらいじゃ」
万古老は感じ入った様子だ。
暗闇の中で「ふずく」を拾っていた者たちも、手を止めて正座し、頭を下げた。
「あたいが一番に拾いはじめたのです」
オダマキが、念の入った正座をして謝った。
「オダマキよ、もうよい。誰が悪いかというと、こんなにモテるリ・チャンシーどの自身が良くないのじゃ! のう、リ・チャンシーどの!」
「ば、万古老師匠さま……」
万古老師匠は、かっかっかと笑った。
やがて、夜がしらしらと開けてきて、バサバサと翼の音がして遠くなっていく。赤闇とやらいう魔物が去ったのだ。
「さあ、新しい一日の始まりだ。顔を洗って、今日も労働にはげもう!」
リ・チャンシーがオダマキに優しく、力強く言い、オダマキは強くうなずいた。


![[6]ざぶにゃんスタンプ](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)





