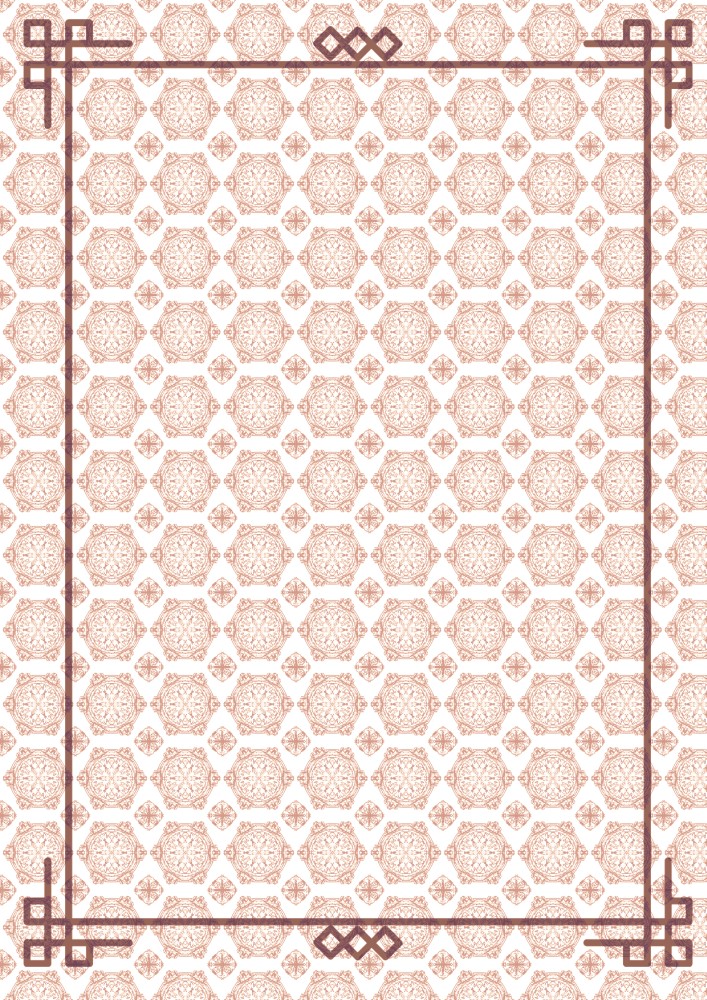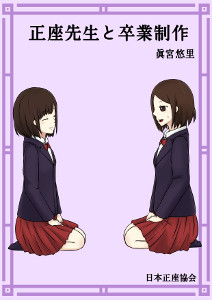[314]黒い瞳のうさぎと黒い座玉(すえたま)
 タイトル:黒い瞳のうさぎと黒い座玉(すえたま)
タイトル:黒い瞳のうさぎと黒い座玉(すえたま)
掲載日:2024/10/22
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
奈良時代のこと。丹後地方の籠(この)神社には、守護役の海都(かいづ)一族が仕えている。宮司の娘、倭光姫(わこうひめ)が奥宮の真名井神社の磐座(いわくら)の湧き水を増やすため、天帝からご神水を授けていただき、愛兎の真珠丸と共に帰った。
山城国の伏見御香宮(ごこうのみや)にもご神水を分けるために旅立つことに。一族のお転婆少女もえぎも同行を命じられ、黒い座玉(すえたま)を持ち、うさぎのコタタと共に旅立つ。


本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序章
うさぎの目は赤い?
赤い子がよく知られているが、倭光(わこう)姫が抱いているうさぎの瞳は黒曜石(こくようせき)のように深い黒色だ。真っ黒でピカピカのお目目は何を見ているのか? まったく穢れがない。
生まれてまもない赤ん坊の瞳のようだ。きょろきょろして、世の中のあらゆるものを見ようとしているかのように俊敏だ。
籠(この)神社の奥宮、真名井神社の水を天帝から授かり受けてきた姫は、黒い瞳のうさぎをいつも綾絹の衣のふところに抱いている。
第一章 人ちがい
「あ~~あ、よく働いた! お腹すいた!」
もえぎは、草原にドサッと腰を下ろし、粟(あわ)と稗(ひえ)を半々に炊いた握り飯をふところから取り出した。男が食べるおむすび並みにでかい。
袖口から、うさぎのコタタも元気よく飛び出してきた。真っ黒のつぶらな瞳でもえぎを見つめる。
「おっと、これはあたいの分だよ。あんたはその辺のたんぽぽでも食っときな!」
コタタは大好物のタンポポを見つけてむしゃむしゃ食べはじめた。
大きな握り飯を食べ終わったもえぎは、筒から水を一気飲みして腕で口元をぬぐう。
「まったくこんなか弱い女の子を港の船の荷下ろしにコキつかうなんて、あんまりだよな。……あ、こんな時、お上品な女の子は、ちゃんと正座して、おにぎりをいただくんだろうな」
ようやくお腹がふくれてひと息つき、新緑の季節の心地よい風に吹かれた。
丘の下から、人声がした。
「いたいた、あの娘だ! 黒い目のうさぎを抱いているだろ」
「本当だ! あのうさぎの目は真っ黒だ。倭光姫に違いない!」
農民らしき男や女将さんが、丘を登ってくるなり、もえぎのところへ走り寄った。
「倭光姫さまでございますね? この度は類(たぐい)まれなるご大任を果たされ、ご苦労様でございます」
「わこう姫? ご大任? 何のことだ?」
もえぎは草原に尻もちをついて後じさりしたが、農民たちはどんどん押し寄せて迫ってくる。
「どうか、われら庶民にもご神水をお分けくださいまし」
「ご神水を飲むと、福を授かり病人は病が治り、田畑は豊作になるというではありませんか。それに、正座が上手になって心が穏やかになれるとか」
「ご神水って何のことだか、あたいには……」
「後生でございます、倭光姫さま!」
もえぎが困っていると、
「お~~い、もえぎ!」
一族の青年、ツバクが丘を登ってきた。
「碧王丸様がお呼びだぞ!」
「ぺき様が?」
「お前にお客人と命令だ!」
碧王丸とは、もえぎの属する、丹後地方で長い歴史を持つ籠(この)神社の警護を受け持つ、海都一族の頭領のことである。まだ年若い少年で、もえぎは常日頃「ぺき様」と呼んでいる。
「コタタ! 帰るぞ!」
もえぎは素早く褐色のうさぎコタタを抱くと、脚絆を巻いた足で少年のように森の中にある一族の屋敷へ走った。
第二章 倭光姫
「おや?」
海都一族の屋敷の裏手に林がある。
夕暮れの木陰に混じって数人の怪しげな男たちがたむろしているのを、もえぎは見た。
(何者だろう? お客人の護衛の者かな)
海部一族のウミガメの紋が焼き付けられた木の門をくぐる。
屋敷に戻ると奥座敷に、碧王丸がちゃんと正装をして正座していた。その対面には、この世のものとも思えないほど可憐な少女が薄紅の衣をまとって座っているではないか。眉間と両方の唇のハシに薄紅の花鈿(かでん)まで描いて、髪はふたつのまげに結って桃の花を飾っている。花の精のようだ。
もえぎは、あまりの愛らしさに魅せられて、うっとりとしてしまった。
「これ、もえぎ。お客人をお迎えするというのに、その格好は何だ?」
頭領の碧王丸が叱りつけるのも無理はない。
袖の無い、男と同じ作業用の衣、脚絆を巻いている手足は汚れ、髪はテキトーに荒縄で縛ったまま。まるで山猿だ。
碧王丸の側仕えの女房がすぐに別室に引っぱっていき、とりあえず恥ずかしくない着物に着替えてきた。
「お待たせいたしました。どのようなご用でしょうか」
碧王丸は「ふむ」とうなずき、
「こちらは、天帝からご神水を黄金の器にて真名井の磐座(いわくら)まで運んできてくださった、倭光姫だ」
「へっっ? 天帝様から?」
真名井の磐座とは、籠神社の奥に鎮座する大きな岩である。岩そのものが神と崇められているが、昔から湧いていた湧き水が少なくなってきたので、天帝さまにお願いの使者に立ったのが、神社から遣わされた宮司さまの娘、倭光姫だそうだ。
(籠神社の宮司さまの姫さま? そういえば拝見したことなかったな)
倭光姫は、もえぎの緊張する様子を目にして微笑んだ。ふところから純白で真っ黒な瞳のうさぎが顔を出す。
「おお! なんてきれいなうさぎだ!」
(それにくらべて、褐色のコタタは同じ黒い目でも大違いだな)
「ああ、それで、さっき田畑のおじさんや女将さんに囲まれたのか。そりゃ、豊作になるんなら欲しい水だな」
倭光姫が、
「高千穂の地にも、お水をお分けしてまいりましたの」
「高千穂というと、九州の高千穂のことですね」
「それともう一か所、山城の国にある神宮皇后(じんぐうこうごう)さまを主神とされるご香宮(ごこうのみや)にも水をお分けしたいと思いまして」
「おお、神功皇后さまをお祀りしてある宮ですか」
神宮皇后といえば、お腹に子を宿しながら、男装して大陸の半島の三韓征伐を成し遂げた偉大な皇后だ。
「山城のご香宮の湧き水は安産に効くと言われています」
天の水を神功皇后の祀られている山城の国のご香宮にも分けてさしあげるという。
「それと、ご香宮の湧き水を産湯に使った赤ん坊は、正座の名手になれると言われているのだ」
碧王丸が言い足した。
「もえぎ、そなたは山城の国まで倭光姫の供をするよう命ずる」
最初は、そんな大任困るな……と思ったもえぎだが、以前からおなごでお腹に子を宿しながら、男装して三韓征伐に向かい、見事に勝利をおさめた神功皇后の逸話に憧れていたことでもあり、お供に加わることにした。
(神功皇后みたいに戦いに行くわけでなし、神水を届ければいいだけじゃないか)
籠神社からの供十人と、海都一族の若衆の従者十人、その中に頼れる仲間、ツバクも同行するという。
倭光姫の侍女十数人も共につく。担がれる台に乗っていくと目立つので徒歩(かち)で行く。ご神水は、共の侍女が黄金のひさごに入れて、抱きしめるように持つ。
籠神社からの使者であることを証明するために、もえぎは奥殿の欄干に座えられている五色の玉のうち、黒い玉を持っていくことになり、倭光姫の侍女に預けた。赤、黄色、白、青、黒のうち、「黒」が「水」を表すのだ。
「ああ、きゅうくつ、きゅうくつ」
普段から、長い手足を惜しげなく出した丈の短い衣で動き回っているので、使者らしいちゃんとした衣に、複雑に結った髪では窮屈で仕方がない。
第三章 御香宮
山城の国へは、二泊の旅である。
山道を登ったり下りたりの旅を続けて、ようやく山城の国へたどり着く。
気候は温暖そうで田畑も豊か、人々も温厚そうだ。
もえぎたちは御香宮に到着した。そこそこ大きな鳥居に、清潔な境内で感じのよい神社だ。
宮司さまや神職の方々の丁寧な出迎えを受ける。若い神職の方々の視線が、倭光姫に集中している。
(失礼な人たちだねぇ、ここにも若い女の子がいるってのに)
もえぎが文句を言っていると、ツバクが笑いをこらえながら、
「そりゃあ、馬子にも衣装のお前とは月とすっぽんだもんな」
もえぎは、ツバクのみぞおちに思いきりひじ鉄砲を食らわせた。
御香宮の奥殿に通され、侍女が大事に持ってきたひさごを宮司さまに差し出しながら、
「この水を湧き水の源に注げば、水脈が甦ります。ご懐妊中の女人がお飲みになれば、ご安産間違いございません」
倭光姫さまがお渡しして、宮司さまは恭しく受け取った。
もえぎが言い足す。
「宮司さま。この水の効能はもうひとつ、正座が上手になることです。これを飲み、お稽古なされば……」
宮司さまは不思議そうな顔をした。
「正座? それはいったい……」
「百年ほど前に、唐土(もろこし)の地より伝わった正式な場での座り方です。所作をお見せいたしましょう」
もえぎはその場に真っ直ぐ立ち上がった。カキツバタの花が一本、凜として立ち上がった感じがした。そして膝をつき、衣は手を添えてお尻の下に敷き、かかとの上に座る。両手は静かに膝の上に乗せる。
「これが、『正座』の一連の所作です」
「ほほう、丹後の国や平城の都では高貴なお方は皆、この座り方でございますか?」
「はい。高貴な方ばかりではなく、庶民にも改まった席では広まりつつあります」
「ほほう、身どもの方では神事の時は正座ですが、庶民にまではまだそこまで定着しておりませぬ。お恥ずかしゅうございます」
宮司さまが申し訳なさそうに言うと、倭光姫が、
「この度、お持ちしたご神水は、主にご安産の効能のためにお持ちしたのです。正座のことはお気になさいませずとも……ほほほ」
愛らしい瞳が、ほんの一瞬、昏い(くらい)色を含んだような気がした。
ツバクが急いで耳うちした。
「もえぎ、黒い座玉は?」
「しまった、忘れていた! 倭光姫の侍女どのに預けたのだった」
急いで黒い座玉を持つようお願いした侍女を探し出して、宮司さまにお渡ししてみせるよう言うと、
「はあ? そのような玉をお預かりした覚えはございませんが」
「そんなはずないわ。あなたよ。お預けしたのは」
しかし、侍女は「知らない」の一点張りだ。
(黒い座玉を失くしたら、どうしよう――!)
もえぎは、自分の荷や、共の者の荷まで頼み込んで探してみた。が、見つからない。
がっくり力が抜けた。籠神社の秘宝ともいえる五色の玉のひとつを失くすとは!
肩を落として神社の奥座敷に戻ると、倭光姫が、ちょうど宮司さまに木箱を渡すところだった。
「これなるは、籠神社の奥殿の欄干に座えてございます五色の座玉のひとつ、黒い玉で、『水』を意味するものでございます。我ら一行の身の証に御目文字のため持参いたしました」
(何ですって?)
もえぎは木戸のすき間から思わず覗いた。
宮司さまが木箱の蓋を開けて取り出したのは、膝の上いっぱいくらいの大きな座玉――、まさしく奥殿の欄干の五色玉のうちの黒い座玉ではないか。
「ちょっと、あんた!」
もえぎは勢いよく扉を開けるなり、倭光姫の真正面から指差して言った。
第四章 悔し涙
「侍女にウソつかせたね! あんたの侍女に黒い座玉を預けたのに、知らないって言ったんだよ! たった今、宮司さまに渡したじゃないよ! その黒く輝く玉が、座玉でなくて何だっていうの?」
和光姫は、まつ毛をパチパチさせた。
ツバクが飛びこんできた。
「もえぎ、姫さまになんて口の聞きようだ! こっちへこい!」
嫌がるもえぎを簀の子に引っぱっていった。
簀の子をドスドスと別棟へ歩いていき、やっと手を放した。
「いたた、腕が抜けるかと思ったじゃないよっ」
「腕の一本くらいなんだ! 打ち首になるよりマシだろ」
「……」
「いいか、あの姫は、本当は籠神社の宮司本家の娘なんだぞ。逆らったら命はない!」
「それは聞いているけど……」
「身分を隠して、神話のように天帝さまからご神水を黄金の杯で授かってきたことにしてあるんだよ」
「どうして身分を隠して……」
「由緒ある神社の宮司の娘が、地方を旅してるなんてことが知れたら、身が危ないからだろう」
「……」
「だから、どんなにバカにされても、あの姫に逆らうんじゃない。お前には、はらわたが煮えくり返るほど悔しいことだろうが」
「むむむ……確かにね。ちょっと庭に降りて夜風に当たってから、宿所に帰ることにするわ」
「大丈夫か?」
「うん……ありがとう」
本当はツバクでも誰でもいいから、胸にすがって大声で泣きたいほど悔しいもえぎだった。足元にうさぎのコタタがやってきて、汚れない黒い瞳で見つめた。もえぎは抱き上げて声を抑えて泣いた。
御香宮の湧き水はご神水のおかげでよく湧くようになり、宮司さまや庶民は喜んだ。神職の方々も倭光姫に深く感謝した。
もえぎたち一行は無事に務めを終え、帰途につくことになった。
途中、丹波の国の大きな農民の家に一泊をお願いした。精一杯のもてなしを受け、湯まで沸かしてくれたので、手ぬぐいを浸して旅の汚れを落とすことができた。
もえぎが身体を拭いてさっぱりして、部屋に戻ろうとすると、奥から人の気配がした。
(この部屋には誰も泊まっていないはず)
木戸の隙間から倭光姫の後ろ姿が見えた。下着姿で、よく見ると正座の所作の稽古をしているではないか。
しかし、膝をついてかかとの上に座る段になると、床に倒れてしまう。何度やってもそうなってしまう。
「大丈夫でございますかっ」
もえぎは思わず部屋へ入って助け起こした。
倭光姫は驚いて、もえぎを突き飛ばした。
「放っておいて!」
「姫さま……」
「そ、そなたであったか」
もえぎは姫の足首が不自由なことに気がついた。
「ふふ……可笑しいでしょう、正座を薦めている神社の娘が、正座ができないなんて」
「……」
「乗馬はじめの折に、落馬して足をケガしてしまったのです。だから、わらわには美しい正座をすることは無理なの」
濃いまつ毛の先に溜まった真珠は、ポトリと膝の上に落ちた。
(正座の話題にふれた時の昏い瞳――そういうわけだったのか)
もえぎは倭光姫を気の毒に思った。
「先日、山城の御香宮でそなたがやってみせた正座の所作は美しかったわ。特に真っ直ぐに立った時は、カキツバタの花が一本立っているような凛々しさだった」
もえぎは、その場に正座した。
「お褒めいただき、ありがとうございます。しかし、姫さまもお諦めになることはございません。あたい――私は乗馬には幼い頃から精通しております。姫さまのお怪我を診せていただけたら、治せるかもしれません。お歩きになるお姿は美しいのですもの」
「そなた……もえぎと申したな」
「はい」
「今までわらわの周りには、この怪我のせいで心ない言葉で責める者ばかりであった。そなたは人の心を思いやれる優しいおなごじゃな」
涙を浮かべた。
うさぎのコタタも、姫の愛兎の純白のうさぎも、ふたりに寄ってきた。
「おお、真珠丸。おいで。もえぎのうさぎと仲ようするとよいぞ」
「姫さまの愛兎は、真珠丸さまと申されるのですか? ぴったりのお名前ですね」
「そうか? コタタもかわゆい子じゃのう」
ふたりは、涙まじりの微笑みを交わした。
次の瞬間――、部屋の灯りが消えた。ふたりはしがみつこうとした時、口元を大きな布でふさがれた。
(ツバク、助けて!)
思わず心の中でもえぎは叫んだ。
声を出すこともできないまま、何者かに拉致(らち)されてふたりは運ばれていった。
第五章 海都一族の会議
丹後の国、籠神社の警護に就く海都一族の屋敷には、ものものしい空気が満ちていた。
当主の碧王丸の唇は引き結ばれ、わなわなと震えていた。
「帰途の丹波の国で、姫さまともえぎをさらわれたと申すかっ」
座敷の下座で土下座していたツバクは、もっと下の座へ下がった。
「は……私めがついておりながら、この不始末、いかようにでも罰はお受けする覚悟にございます」
「お前に罰を与えたところで……」
いきなり配下の者が入口で一礼するや、碧王丸に素早く近寄った。
「このような矢文(やぶみ)が、たった今、玄関の扉に!」
碧王丸が急いで文を開く。
「敵は、何と?」
「うむむ……、女共を返してほしくば、奥殿欄干の五色の座玉を全て持参せよ、持って来なければ、手元にある黒い座玉と女ふたりの身柄は渡さん――と」
「いったい、敵は?」
ツバクをはじめとする男衆がいきり立った。
「いったい、何もの?」
ツバクが叫ぶように、
「ぺき様! 碧王丸さま! 俺は責任を取ってこの命を差し出します!」
「お前が命を差し出したところで何も解決せん! して、お前が部屋に駆けつけた時には、誰も残っていなかったのだな?」
「は、はあ。うさぎが二羽残っていただけです。倭光姫さまの愛兎と、もえぎのコタタが」
「二羽とも怪我はないか?」
「はい。しかし、両方とも何かにかみついたらしく、布の切れ端が歯に引っかかったまま、取れないのです」
「うさぎを二羽とも連れてまいれ」
碧王丸の膝元に二羽のうさぎが連れてこられた。
「コタタ! 無事で良かった。して、お前のご主人のじゃじゃ馬はいずこへ」
碧王丸はコタタを抱き上げて顔を付き合わせて、瞳を見る。それから純白の真珠丸の瞳を覗きこんだ。
真珠丸の瞳には、倭光姫が繰り返し正座の所作の稽古をする様子が映っている。
今度はコタタの黒い瞳に、ひとりの黒装束の男がもえぎを肩に担いで部屋を出ていくところが映っていた。
「ぺき様、これは? なんと不思議なものが見えますな」
「コタタの瞳には、過去に見たものが映し出されるのだ。真珠丸ももしかしてと思い、見てみたら……」
「では、これは、姫さまともえぎが連れ去られた時の――。うさぎとは、なんとも神秘的な生き物でございますな」
ツバクはうさぎたちに顔を近づけ、念入りに見た。それから、コタタの口から布切れをつまみ出した。
「この黒い布は?」
「待て、ツバク。見せてみよ」
指先にかろうじて乗るくらいの小さな布切れを、碧王丸は何度も裏返したりしながら眺めた。真珠丸の口からは別の布が見つかった。
「これは、瞳に映っていた黒装束の者の衣ではないか。そして、真珠丸の口のハシから垂れていた布は、金糸銀糸を織った豪華な布だ。どこかで見たような柄だが……」
しばらくじっと眺めてから、
「あっ」
碧王丸は急いで文机を持ってこさせ、自分も部屋から一枚の衣を引っぱり出してきた。
古びた衣だ。文机の上に、真珠丸が咬んでいた小さな切れ端と古い衣を広げてみた。
人ばらいをして、碧王丸の他はツバクとうさぎ二羽が残った。
隠居して普段は一族の集まりには顔を出さない、呼吟(こぎん)爺やが珍しくやってきた。
「碧王丸さま、この衣は……」
「もっと灯りを近づけよ」
「呼吟爺や、この紋様は本家の繋がりの……」
「間違いございません。宮司さまのご令弟(れいてい)さまの神紋でございます」
矢文の矢の先に彫ってある紋も同じものだ。
「……?」
ツバクは、訳の分からないまま見守った。
碧王丸が神妙な口調で説明する。
「籠神社ご本家の現、宮司さまがお跡継ぎになられる時に、跡目争いから脱落されたご令弟さまが、六芒星の神紋を掲げて一旦は去られたのだという」
ツバクが尋ねる。
「一旦はということは、ご令弟さまはいつか再び、宮司さまの座を望んでおられるということでしょうか?」
「うむ。おそらくは。この衣は私が幼少の頃、ご令弟さまから賜った品だ。そして、真珠丸が咬みついた小さな端切れにも、同じ紋様の六芒星を織り込んだ模様が見える!」
「では、宮司さまのご令弟さまの一派が、倭光姫ともえぎを連れ去ったということでしょうか!」
碧王丸と爺やとツバクは、唾をごくりと飲みこんだ。
第六章 敵の正体
ふたりはうなずきあった。
本社の宮司さまに報告しなければならない。何せ、宮司の娘である倭光姫と海都一族の一途な少女、もえぎの命がかかっている。
すぐに面談に応じるとの返事が、宮司さまから返ってきた。
夜が更けた頃、本社の奥座敷に宮司さまと、先に来ていた呼吟爺やは待ち受けていた。
碧王丸とツバクは、御前に正座した。
「碧王丸、しばらく会わぬうちに逞しゅうなったな。我が籠神社の守護の頭領の務めを手堅く務めてくれてご苦労である」
宮司さまは初老に近い。銀髪の上に頭巾を被り、精悍な感じは以前と変わりない。
碧王丸も恐縮して、頭を下げた。
「宮司さまもお変わりなくご健勝のご様子。何よりでございます」
「大方のことは呼吟爺やから聞いた。実はな、内密にしていたが、我が弟は三年前、急な病を得てみまかったのだ」
「えっ、ご令弟さまが!」
宮司さまと実弟とは、元々、仲が良くなかったところへ継承問題で決裂してしまったそうだ。ツバクも死去されていたことは知らずにいた。
宮司さまは表神紋を、実弟は裏神紋の六芒星紋を使っていた。
「そういう事情から、今回のことは裏神紋を使って、実弟側についた者どもの残党がやったことではないかと思われる。今、検非違使(けびいし=警察)に、彼らの根城を捜索させている」
碧王丸とツバクは、意外な事実に呆然として、一族の屋敷に引き上げた。
第七章 うさぎの瞳に
(検非違使からの報告を待つしかないのか?)
ツバクが一族の屋敷でイライラと歩き回っているところへ、コタタが足元にじゃれついてきた。
「これ、コタタ。お前のご主人の身が危ういかもしれんのだ。おとなしくしないか」
抱き上げたところ、コタタのつぶらな瞳と視線が合った。
「おやっ? コタタ。じっとしな。もう一度顔を近づけてくれ」
コタタの黒い瞳に、知らない屋敷でもえぎたちが男たちと立ったまま真剣に向き合っているところが見えた。
「こ、これは?」
ツバクは急いで、
「真珠丸! お前もこちらへおいで。たんぽぽをやろう、ほら!」
真珠丸は喜んで跳ねてきた。ツバクがすかさず捕まえ、
「ちょっとお前の目も見せてくれ」
一族の男衆が集まってきて、コタタと真珠丸を抱き上げ、奪い合いながら瞳を覗いた。
黒い座玉が置かれた側で、もえぎが何かしゃべっている。
「これは、どういうことだ? 何故、うさぎの瞳に……」
「分かった!」
ツバクが叫んだ。
「あっちで黒い座玉に映ったものが、うさぎの瞳を通して見えるんだ!」
「本当だ! なんて不思議なことだ!」
「もえぎは何を話しているんだろう?」
ツバクがポツリポツリ話しはじめた。
「あなた方……、本社の宮司さまの……ご令弟の配下だったのなら……、心の底では宮司さまも本社も大切なはず……」
「ツバク! もしかして、もえぎの唇を読んでるのか?」
仲間たちは、うさぎの瞳を見つめながら話すツバクに、やっと納得した。
「さすがツバク! 命より大事な、もえぎだもんな」
「う、うるさいっ、静かにしろ!」
ツバクは真っ赤になってから、深呼吸をして再びうさぎの瞳を見つめた。
「倭光姫さまは……、そなた方が味方したご令弟の姪御さまにあたられるのですよ。一刻も早く……帰してさしあげなさい」
黒装束の男たちは、もえぎの迫力にタジタジとなっていた。
「これから、あたいと『正座勝負なさい』」
「『正座勝負』?」
「この座り方を長く続けた者が勝ち。勝った方の言うことをきくこと!」
もえぎはさっさと抜かりない所作で正座をした。男たちも、仕方なくノロノロと同じように座った。
ツバクと一緒にうさぎの瞳を見ている仲間たちも、ツバクの言葉を聞いて応援しはじめた。
「いいぞ、もえぎ! 正座を頑張れ!」
「そんな輩、負かしちまえ!」
しばらくして――、男たちが足を押さえてひっくり返りはじめた。
「いててえ!」
「たまらん、ジィ~~ンとしてきて……」
床の上で男たちがのたうちまわっている時に、ちょうど検非違使たちがやってきた。男たちは次々にお縄になっていく。
うさぎの瞳を見ていたツバクたちが、
「やった――!」
「よくやったぞ、もえぎ!」
勝鬨(かちどき)の声をあげた。
「よし、もえぎと姫さまを迎えに行こう!」
ツバクたちも大喜びで、もえぎたちを迎えに行く支度をはじめた。
「今、少し待て」
碧王丸も、いつの間にか皆の背後に来ていて声をかけた。
「どうなさったのですか、ぺき様、早く姫様方を迎えに……」
「待て、これを見よ」
碧王丸が晴れ晴れとした顔で、真珠丸をヒョイと抱いてツバクに渡した。
真珠丸の瞳からは、男衆に「正座の所作」を教えているもえぎが見えるではないか。
「だめだめっ、やり直しだよっ」
怒鳴りながら、何度もやり直しさせている。
「うわぁ、あいつの稽古、おっかねぇ~」
「口だけだ。あいつは絶対、正座の稽古に関してお仕置きしたりしない」
ツバクが胸を張った。
やがて、正座の稽古は落ち着いて行われ、もえぎが倭光姫に優しく繰り返し教えているところも見てとれた。
第八章 海岸で
「こらこら、おとなしくしていないと迷子になるぞ、二羽のうさぎよ」
「コタタと真珠丸を抱いて、船着き場まで迎えに来たツバクが、うさぎ二羽を抱き上げるのに、四苦八苦している。
「ツバク、コタタを貸すがよい」
碧王丸がコタタを預かった。
「ほら、コタタ。もうすぐ、もえぎがあの舟に乗って帰ってくるからな」
検非違使から知らせが来た。
和光姫ともえぎを、神社の宮司ご令弟の配下の根城から助け出した役人が、海岸に舟で到着すると。
残党の根城は岬の裏側の無人島に発見されたのだ。
波に揺られてきた舟が、船着き場に二艘到着した。
一艘は手首を縄で縛られた男たち十人あまりが乗り、もう一艘から女人ふたりが手を貸し合いながら降りた。
「コタタ!」
「真珠丸!」
もえぎは碧王丸から、倭光姫はツバクから、それぞれ愛兎を受け取った。
「元気だったかい?」
「会いたかったわ、真珠丸」
二羽のうさぎは真っ黒な目をいっそうピカピカさせて、ご主人の胸で甘える。
もえぎは碧王丸の御前に改めて正座した。
「ぺき様、ありがとうぞんじました。お陰さまで無事に帰って来れました」
「不思議なうさぎたちの瞳と黒い座玉のおかげだな」
もえぎと碧王丸は、役人の持ち帰った黒い座玉から目を離せないでいた。
「あっ!」
もえぎは受け取ったばかりのコタタを碧王丸に返すや、小舟に駆け戻った。手首と足を縛られた男たちが、砂浜をのろのろ歩いているところだった。
「あんたたち、半分が途中で正座から横座りに変えたでしょう。ちゃんと見張ってたんだから、もう半刻、舟底で正座していなさい!」
「うへっ!」
「怖い方のねえちゃんにバレてた!」
男たちは「ぎゃふん」と言わんばかりだった。
「もえぎさん、許しておあげなさい」
倭光姫がゆっくり歩いてきて、苦笑いしながら言った。
第九章 表神紋と裏神紋
浜辺には、呼吟爺やの姿もあった。
倭光姫のことが心配で矢も楯もたまらず、迎えに来たのだ。
「おひい様、よくぞご無事で……。お怪我はありませぬか!」
「爺や、心配かけた。わらわはこの通り無事じゃ。もえぎさんが正座のお稽古と足を揉みほぐしてくれたおかげで、ほら」
姫は、草地に所作正しく美しい正座をしてみせた。
「おお……」
爺やのシワの奥の瞳から涙があふれた。
「もえぎどの、感謝する。この爺や、なんとお礼を申し上げればよいか」
「爺やさま、お顔をお上げくださいまし。これはきっと姫さまご自身が天帝さまから賜ったご神水のおかげですよ」
もえぎは照れた。
「それと」
胸に抱いていた漆黒の玉を示した。
「座玉の表面には、籠神社の表神紋と裏神紋の両方が彫られています」
表神紋は三つ巴の紋様、裏神紋は六芒星が彫られている。
もえぎと倭光姫はそろって左腕を差し出した。腕の内側に、倭光姫には表神紋、もえぎには裏神紋の刺青がなされている。
「裏神紋をよう見やれ。三角がふたつ重なった六芒星の紋は、ウミガメの身体を表しているであろう」
爺やがしげしげと眺めて説明した。
「宮司家を守る海都一族の真の印じゃ。……もえぎどの、これからもおひい様をよろしゅう頼みましたぞ」
「はい。倭光姫さまは一目拝見した時から、ずっと仕えさせていただくお方と感じました」
「もえぎさんは、わらわに正座ができるよう、導いてくださいました。決して離れませぬ」
真珠丸に引けをとらない漆黒の瞳を輝かせて、姫が答えた。
波打ち際に放たれた二羽のうさぎたちはぴょんぴょん跳びはね、乙女たちはきゃっきゃと声を上げてはしゃぐのだった。