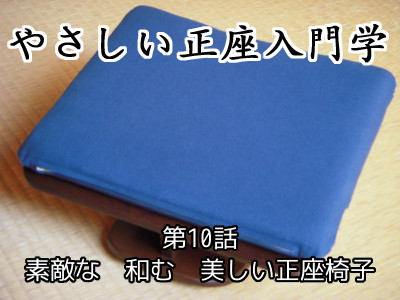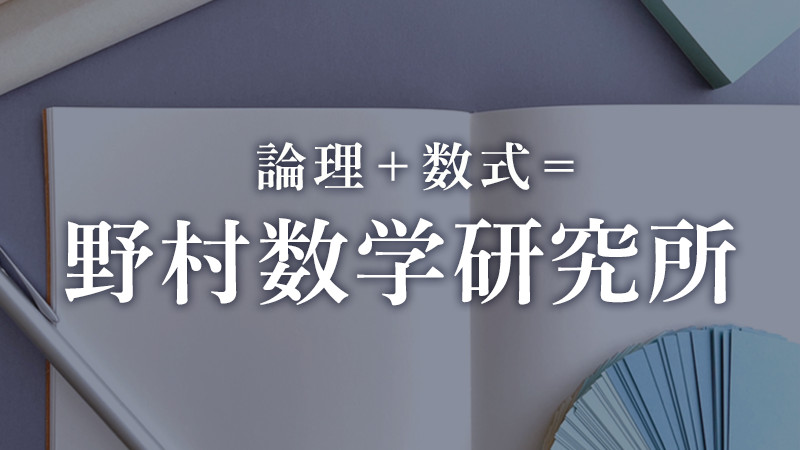[325]お江戸正座16
タイトル:お江戸正座16
掲載日:2024/12/12
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:16
著者:虹海 美野
あらすじ:
良次は札差の次男である。ある日、嫁入りした妹のおりつが良次を訪ねて来た。
幼い頃に、兄たちの玩具のちゃんばらを勝手に使い、良次が花を活けて飾っていた花器を壊したことを詫びに来たのだと言う。
花器を買って贈りたいと言うおりつの申し出で、義弟の営む陶器店を訪れた。
この縁で、良次は義弟が昔から親しい札差仲間の通う師の茶会に誘われる。
心配になる良次だが、茶の席で正座をし、菓子を前にふと幼い頃のことを思い出す。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
良次は札差の次男である。
少し前に三人兄妹の末子であるおりつが、札差の長男のもとへ嫁いだ。
男の子二人の後に生まれた札差の家の女の子となれば、着飾り、お琴やお三味線、踊りとお稽古に励み、家族中の庇護のもと育つものだと思われたが、妹のおりつはとんでもなく強かった。剣術は長年真面目に稽古に通っていた長男の良太をまだ幼い頃に打ち負かした。最近兄から聞いた話だが、実はおりつは嫁ぐ前に偶然剣術の道場で知り合った夫となるお人とも互角に戦うほどの腕前なのだと言う。おりつの夫、義理の弟となる人とは顔を合わせたことがあるが、立派な体格で、剣術のお師匠によれば、子どもの頃より大層筋がよいと言う。いやはや、我が妹ながら、どう育てばあれだけ強くたくましくなるのか。同じ家で同じものを食べて育ってきたはずである。
そうして、長男の良太は剣術も勉学も真面目に取り組み、しかも聖人君子の如く、子どもの頃から人格者であった。手習いでちょっかいをかける子どもに着物を汚されたり、筆を駄目にされても、それを親に言うこともなかったし、相手を責めることもなかった。つい先日、その時の男が、当時のことを詫びにやって来て、いつの間にか仲を深めている。これまでお商売だけに励んでいた兄が、最近ちょくちょく、おりつの夫、義理の弟に連れて行ってもらった店を訪れるようになった。酒をほとんどやらぬ兄だが、果実酒が大層おいしいのだと言う。
良次から見れば聖人君子のような兄、良太であるが、本人はこれまで自信がなかった、と打ち明けた。打ち明けたのは、例のひとつ覚えの義理の弟に教えてもらった料亭に良次を誘った席でのことである。
しつけに厳しい家であったことと、もともと大人しい性格の二人は、酒が出る席でも、正座をする。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬようにし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか、軽く開く程度。手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うようにして揃える。
確かに果実酒が美味しいし、料理の味も盛り付けも品があり、よい店である。
ただ、正直なところ、良次は面白くない。
この店が妹、おりつの夫からの紹介、という点だ。
おりつは妹で身内で、言うまでもなく大切な存在である。
かわいい、と言われれば、かわいいに決まっている。
だが、もし同じ家の子でなく、妹でなければ、仲良くしたいか、かわいいと思うかと問われれば、素直に頷けない。
しつこいようだが、おりつは昔から、とにかく強かった。
傲慢なわけではない。
だが、生まれ持った強さというのは、それを持たぬ良次からすると、どうにもやりにくさを感じる。
庇護したい、と本能的に思うし、周囲もそう教える。
かわいい末の妹なのだから、と。
だが、実際のところ、おりつは長男の良太より、次男の良次よりも、強かった。
剣術の腕だけではない。
小柄な娘のくせに、力があり、また自身の身体の動かし方というものを本能的に心得ていた。
だから、幼い頃、ふざけて相撲を取っても、おりつが勝つことがあった。
無邪気に喜ぶさまに、手放しで喜んでやれるほど良次は大人ではない。
なんとなく、腹立たしさを抱いた。
そうして、決定的な事件があった。
春の節句の折、良太と良次はちゃんばらのおもちゃを買ってもらった。
おりつも欲しがったが、おりつは三月にひな人形を買ってもらっていた。
いちいちなんでも欲しがりやがって、と内心良次は毒づいた。
本当のところ、良次はおりつのひな人形が少しうらやましかった。美しい着物を着た、その小さな夫婦の人形は精巧なつくりで、いくら見ていても飽きなかった。だが、おりつは一応喜びはしたものの、飾ってあるひな人形の前を素通りしていた。
そうして、ちゃんばらである。
ただ、良太、良次の目を盗み、ちゃんばらで遊んだだけなら、まあ、許してもいい。
だが、あろうことか、おりつは良次が違い棚に飾った花器を割った。
わざとではないのだから、と周囲の大人は言い、誰もけがをしなくてよかった、とその場を丸く収めたが、良次はそれが解せなかった。
粉々に散ってしまった花器は戻らなかった。
祖母の部屋にあった小さな花器が美しく、あっちの部屋の違い棚に飾ってもいいか、とせがんだのは良次だった。
美しいものが身近にあるというのは、大層幸福なことである。
それを全く理解しない上、勝手に兄のおもちゃを振り回し、花器まで壊した。
おまけに、おりつの見合い相手であった義弟と母上が家に来た際に、父は装飾の類が家に置いてないのを、幼い頃の良太と良次のせいにした。
まあ、大事な見合い相手を前に、正直に話す必要もないが、だったら、装飾の類は置かぬと言えばいいではないか……。
普段からそれほど良太と話す方でない良次が、口数少なく箸を進めていると、「そういえば」と、良太は前置きし、まるで良次の心中を読んだかのように、父が見合いの際に装飾の類を置かぬことを良太と良次のせいにしたことを詫びていたこと、そうして、おりつの嫁ぎ先の母上はそうしたことを気にするお人ではないし、義理の弟はわかっているだろうと続けた。
ああ、そうなのか……。
許せるかどうかは別とし、周囲がわかっていた、そうして心に留めていた、ということは、ひりつく擦り傷に薬を塗ったように、過去を少しだけやわらげたのだった。
2
ごめんください、と聞き覚えのある声がしたのは、兄と料亭に行ってから三月ほどのこと、ちょうど長く続いた雨がようやく止んだころであった。
店の上がり框のところに立っていたのは、嫁いで以来のおりつであった。
「おりつ、どうしたんだ」と、良次は慌てた。
こういう日に限って、兄、両親ともに出払っているときた。
兎にも角にも、おりつを奥の座敷へ上げる。
からりとした日ではあるが、汗をかく日だったので麦湯を持って来るように言いつけ、おりつと向かい合う。
互いに正座し、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、親指同士が離れぬようにし、膝けるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、足の親指同士が離れぬようにし、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃える。
「一体、どうしたんだ。まさか、嫁入りに持ち込んだ竹刀で、夫を正面から打ち付けて追い出されたのではないだろうな。ああ、それとも、家の中で大立ち回りでもして、家宝の壺でも割って、逃げ出して来たのか。どちらにしても謝ろう。私も一緒に行く。そうしよう」
言っているうちに涙目になる良次の額を、おりつはぴしり、と叩いた。
「いたっ」と、良次は声を上げる。
嫁入りし、改心したかと思ったが、相変わらずである。
ああ、やはり嫁ぎ先でまずいことになったのだ。
いよいよ頭を悩ませる良次に、「もう帰る」と、おりつが立ち上がる。
「待て待て。どこへ行く気だ」と、良次は止める。
冷ややかな目でおりつは良次を見おろした。
そうして、また元いた場所に戻り、座る。
様子を見ていた女中がおずおずと麦湯を置いて、すぐに出て行った。
おりつが幼い頃よりこの家にいる女中頭だから、おりつが立腹すると大事になるのを知っているのだ。とばっちりはご免、といったところか。
「嫁ぎ先で何かやらかしたわけでないのならいい。先走ったのは悪かった。謝る。心配してのことだ。許せ」
「私もつい、手が出てしまいました」と、おりつは麦湯を飲み、息をつく。
つい?
おりつ、お前の『つい』はどれほどの頻度で出るのか。
だが、しおらしい様子に戻ったところを見ると、今はこれがいつものおりつということらしい。無理をしていないか、と別の方面でも心配になってくる。
「それで、どうしたんだ。お父ちゃん、お母ちゃんが帰って来るまで待つか?」
そう訊くと、おりつは首を横に振り、「今日は良次兄ちゃんに会いに来ました」と言う。
「それは珍しいな。どうした?」
おりつは畳に視線を落とし、「実は私、子を授かりました」と言った。
「えええええっ」と、良次は大声を上げた。
「もうか? それは早くはないか? 本当か?」
「良次兄ちゃん、落ち着いて」
「いや、だって、おりつ、そんな時に一人で出て来て大丈夫なのか。ああ、それより、ここまで、駕籠を頼まず来たのか?」
ちいとも落ち着かぬ良次に、おりつは溜息をつく。
「良次兄ちゃん、もう一発お見舞いしたら、少しは落ち着く?」
そう言って、おもむろに自身の手を見つめるおりつに、「いやいやいや、大丈夫だ。落ち着いた!」と良次は正座したまま、後退した。
「そう?」
冷ややかなおりつの目に、更に良次は後退する。
「ああ、大丈夫、大丈夫だ」
両の手のひらを面前に出し、作り笑いで良次は応じる。
「実家に行くと、旦那さまにも、お義父さん、お義母さんにも伝えてまいりました。駕籠で行くようにと仰せつかり、お付もと言われましたが、お付は断りました。駕籠で以前通っておりました、うちの近所の剣術の師匠宅へ寄り、あいさつをしてきましたので、駕籠はそこでおり、師匠宅から歩いてまいりました」
「……そうか。師匠宅からなら、すぐだからな。安心した。それに嫁ぎ先の手厚い心遣い、兄からも感謝しないとな……」
まだ驚きを沈められぬまま、良次は大きく頷いておりつの説明に応じた。
子を授かったことを話しに来るのであれば、お母ちゃんに報告するのがよかったのではないか。なぜ、あろうことか、この自分に……。
そんな良次の顔をまじまじと見つめるおりつが、「それで本題に入ってもよろしいですか」と尋ねる。
「今のが本題ではなかったのか?」
驚く良次に、「なんでそう、良次兄ちゃんは、いくつになっても落ち着かないの」と言う。
……いや、妹が子を授かったと聞けば、驚くだろう。
それとも、世の人というのは、夕餉の膳を前にした時と同じような表情でいるのだろうか?
そんなことはあるまい。
「子を授かって、お義母さんが言うには、人によって暫く床に臥せったり、食が細くなったり、とにかくまあ、これまで通りにはゆかないことがあるそうなの」
「お前、子を授かったんだよな。今も、そういうことはないのか?」
おろおろと良次が訊くと、「そうなっていたら、来るわけがないでしょう」とこれまたきっぱり言う。
「それで、まあ、兎に角、その前にやっておきたいことがあって、ここへ来ました」
「なんだ、打ち合いか? いくら心置きなく打ち負かせると言っても、それで私のところに来るのはひどいとは思わぬか?」
「良次兄ちゃん」
はっと、良次は我に返る。
「良次兄ちゃん、私に打ち負かされたいのですか? 子を授かったと、たった今、申しましたよね?」
据わった目でおりつがこちらを見ている。
「そう、大事な時だ。ははは、誤解するな。おりつを思ってのことだ。大事にしないと。そうそう、話を続けてくれ!」
おりつが息をつく。
「『何か今のうちにやっておきたいことはあるか』と旦那さまに訊かれまして、やりたいことではないけれど、ひとつ、やっておかねばならぬことがあると申しました」
「うん」と良次は頷く。
久しぶりにお母ちゃんと一緒に寝たいと思ったのか。
里心というやつか。
「良次兄ちゃん、昔、花器を壊してしまったこと、謝ります」
そう言うが早いか、おりつは座布団を外し、座礼した。
大層きれいな座礼であるが、子を授かった身でそれは大丈夫なのか。
そうして、よくもまあ、そんな前のことを覚えていたものだ、と感心した。
「わかった。わかったから、もういい。来てくれてありがとう。駕籠を呼ぼう。気を付けて帰りなさい」
良次はおりつに顔を上げさせた。
すると、おりつは「まだ終わっておりません」と言う。
「なんだ、私を相撲で投げ飛ばした時の詫びか? それとも私の分の饅頭を食った詫びか? 後はなんだ?」
そこで良次は、またしても据わった目のおりつに気づき、はた、と黙った。
「同じ花器はないと思いますが、旦那さまの弟さんが陶器を扱う店を商っております。そこの店でなければ、ということではございませんが、好きなものを選んでくださいませんか。それを私に贈らせてください。いえ、旦那さまが是非ともそうしろとおっしゃってくださいましたので、旦那さまから、ということになるかもしれません」
いやはや、義理の弟はできたお人だ。
なんだってまあ、結婚する遥か昔の妻のやらかしまで、あの人は面倒見るんだか……。
そう思ったが、これ以上おりつを怒らせたくはない。
心持で、身体によくない場合もあるかもしれぬ。
3
子を授かった身なら駕籠がよかろうと良次は思ったのだが、普段からよく身体を動かすおりつは、具合のよい時は歩いたほうがようござんす、と言う。
だが、心配である良次も引けぬ。
そこで、ここから比較的近いという義弟の陶器店まで歩き、そこで駕籠を呼び、おりつを乗せて帰すことにした。
くれぐれも無理はするな、と言い、おりつの夫の弟君の商っておられる店へと向かった。
おりつの夫の家は、おりつの夫が札差を継ぎ、二番目の弟君が陶器店を妻と営み、三番目の弟君が口入屋に婿入りしたのだそうだ。
なるほど、自分もいずれは家を出る。
その時はどうしようか、と良次は考える。
こんなに強い妹とともに育ったから、一緒になるなら、優しい人がいい。できればはんなりとした、かわいらしい人がいい。
そんなことをぼんやりと考えていると、「良次兄ちゃん、ここ」とおりつに呼び止められた。普段来ない方面であるが、確かにさほど遠くはない。
まだ新しい店構えであるが、店の中は多くの品が整然と並んでいた。
そうして、安価ではあるが、どれも心引くものばかりであった。
本当にちょっとしたことだが、曲線やかたち、描かれた絵の小花や小鳥、そうしたものが優しく、品がある。
これは……。
もう何年も、こんなに心躍る場に来たことがなかった。
兄と行った料亭も悪くはないが、こうした美しい、それでいて身近に感じられる品というのは、なんと心に優しいのか。
あれも、これも、心を引く。
自然と顔がほころぶ。
「ずいぶん、良次兄ちゃん、楽しそうね」と、おりつが言う。
「だって、お前、こんなにかわいらしい花器を見たことがあるか? これもいい。この柔らかな曲線と色合い。こんな素晴らしいものに囲まれて暮らせたら、本当に日々は明るく素晴らしいだろうなあ」
「お気に召したものはございましたか」
店主に声をかけられ、振り返ると、ああ、おりつの婚礼の折に顔を合わせた、義理の弟君である。
「これは。不義理をしておりました。本日は妹のおりつともに伺いまして」
頭を下げると、「いえいえ、こちらこそ。まだ新しい店ですが、妻の実家の商いを引き継ぎましたので、品を卸しているのはしっかりした窯元です」と言う。
品のある佇まいと、しっかりとした口調。
お商売に向いている、聡いお人だと思った。
店主とひとしきり話し、あれこれ迷って、最初に心引かれた手のひらに載るほどの大きさの花器を選んだ。
財布を出すおりつに、「いいから」と小声で言う。
「旦那さまにきちんと渡されてきましたから」と言うおりつに、「子を授かると腹が減るらしいから、その時に好きなものでも買ったらよかろう。その時の私からの差し入れだと思えばそれでいい」と納得させた。
店主と親しくなり、今後もぜひお付き合いをと約束をした。
駕籠を呼びに行く間、おりつを店で待たせてもらおうかと良太は考えていたが、すぐ先に駕籠屋があるらしい。
ここで別れて帰るとおりつは言うが、心配で、駕籠屋まで送ることにした。
駕籠屋へ向かう道すがら、おりつは「良次兄ちゃんはすごいね」と言った。
「何がだ?」
おりつが花器を買うという申し出をうまく断ったことか?
「さっき、ずいぶん花器について話していたけど、私にはちいともわかりません。大きさとか、色とか、そういうのはわかるけど、どれがどういいとか、趣があるとか、言っていること自体はわかるのですが、それを聞いていても、『ああ、そうなんだ』と思うばかりなのです。実は、うちの旦那さまも同じなのです。私のお琴の出来がひどかったのは、良次兄ちゃんも知っているでしょう?」
「ああ、まあ」と、良次は曖昧に頷いた。
先生のところに通っていたが、おりつのお琴は全く上達しなかった。
剣術に於いては、兄や良次よりずっと遅くに稽古に通ったにもかかわらず、思わぬ実力を発揮したのだが……。
兄の良太も、おりつ本人には言わなかったが、「もう少し、お琴というのは趣ある弾き方をするのではないか。こう、曲によって優美であったり、悲哀があったりと……」と言っていたことがあった。
「私にとって、それはずっとずっと負い目というか、弱みだったけれど、偶然、旦那さまもそうしたことがあまり得意でなくて。夫婦として、どちらも芸事に不向きなのは好ましくないのかもしれないけど、私はとてもとても、それが嬉しかった。剣術で手合わせした時から、とてもお互いを尊重し合えた、わかり合えた、という思いがあったの」
「それはよかった」と良次は頷いた。
おりつがそこまで考えていたとは思わなかった。
ただただ、おりつが竹刀を持つと、相手をさせられるのでは、とひやひやした記憶しかない。
「それでね、旦那さまと一緒に過ごして、ああ、良太兄ちゃんや、良次兄ちゃんにとっての大切にしていることや、好きなことを私は長い間見ていなかったと思った。今になっても、この通り、器の良さもどうもわからないけど、良次兄ちゃんにとって大切なものを、完全ではないけれど、また手元に置いてもらいたいとは考えるようになりました」
「そうか」と、良次は頷いた。
駕籠屋に着いた。
「ありがとう。おりつ、よい旦那さまと一緒になれてよかった。くれぐれも身体を大事に」
おりつが駕籠に乗り、嫁ぎ先へと帰ってゆくのを見届け、良次は来た道を戻った。
帰って来ていた両親と兄におりつが子を授かったことを伝えると、大層喜び、そうして、あの子が大人しく過ごせるか、と心配し、お義母さんや旦那さんがいるから大丈夫だ、と一番心配そうな顔をする父が話を収めた。
4
大きな花器に活けた花の残りを、先日買い求めた小さな花器に活け、部屋に飾った。最近、良次は散歩がてら花を摘んだり、時には花売りから買い求めたりしては、それを活けて、床の間や自分の部屋に飾っている。
おりつがいなくてすっかり静かになった家だが、常に聞こえる庭での剣術の竹刀の音から、今は良次の活ける花が彩りを加え、時折母がおりつの置いて行ったお琴を爪弾くようになった。
今日は、少し大きな花器を求めに、また同じ陶器店を訪れた。
「またいらしてくださり、嬉しいです」と、義弟は言う。
「最近このような楽しみができて、こちらこそ礼を言いたいところです」
あれこれと陶器を見て、今回は少し大きめの花器を求めた。
そうして、奥でご新造さんが茶を淹れてくれると言うので、お言葉に甘え、少し休んでいくことにした。
通された座敷はそれほど広くはないが、湿度の高くなりがちな今の時期でも風通しよく、風鈴が涼やかな音を響かせ、明り取りの窓の隣にある違い棚には、今の時期の花を活けた花器が飾ってある。そうして、その下に伏せられた盃がある。普段使用のもののようだが、赤い布の上に並んで置かれた様子は、まるで男雛と女雛のようだ。
「一年中飾れるひな人形のようですね」
かがみこんで、対の盃にあいさつするように、微笑みかえた。
そんなふうに部屋を見せていただいた後に、良次は正座した。
背筋を伸ばし、脇は締めるか、軽く開く程度、着物は尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃え、足の親指同士が離れぬようにする。
茶を淹れて部屋を出ようとしたご新造さんがふと、こちらを振り返った。目鼻立ちのはっきりとしたかわいらしいご新造さんを、義弟は、幼い子のように見遣る。
向かいに正座した義弟は、良次に微笑む。
「そのようにおっしゃったのは、良次さんが初めてです」
目を細めた様子から、何やら嬉しそうな思いが伝わる。
「そうですか?」
「ええ、まあ、この部屋にそもそもそれほど多くの人をお通ししませんがね」と、義弟は前置きし、この対の盃は、ご新造さんが幼い頃、その実家の陶器店を義弟が祖父とともに訪れ、そこで二人同時に欲しがった品で、それを義弟の祖父が買い取った上で、一方をこのご新造さんに、一方を義弟に贈ったのだと言う。そうして時が流れ、ご新造さんの一家が親御さんの郷に戻る、という折にご新造さんがこの盃を返しに来たのが、一緒になったいきさつであると語った。
「なんと、麗しい話でしょう」
良次はしみじみと対の盃を見遣った。
「つい、こんな話まで」と、義弟は照れながら笑う。
そうして、「私は良次さんを、兄との縁談で縁者になったからということを別にし、良次さんというお方に大層引かれております」と切り出した。
「私なぞ、取柄もない人間で、勿体ないことでございます」と返すと、「そんなご謙遜は必要ありません」と言う。
そうして、「今度、茶会に行きませんか」と誘う。
なんでも義弟の実家の地域の方で懇意にしていた札差仲間で、時折茶道の師の元で茶会をしているのだと言う。
「あの、大層嬉しいのですが、そんな先代、いや、先々代からのお付き合いのある方々の中に、私などが行っては、皆さん、困惑されるのでは……」
「それはございません」と、義弟は言い切る。
「実は、前回花器をお求めになったことを、茶会の席で話したのです。義兄は、大層趣深い方で、手のひらに載る花器を求めた、と。そうしましたら、師も仲間も、ぜひそういった方とお近づきになりたい、と申しまして。いやはや、断りなく話をしてしまい、申し訳ない。ただ、そんな事情ですので、ご迷惑でなければ、来ていただけませんか」
「はあ」と、良次は半信半疑のまま頷いたのであった。
5
夕餉の席で、良次は茶会の話を出した。
膳を前に、家族で正座しての場である。
お商売で昼間は何かと忙しいが、こうして膳を前にしてはいるが、正座で同じ時を過ごす時というのは、やはり落ち着いて話せる。
おりつが嫁ぎ、膳がひとつ少なくなった席ではあるが、皆、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか、軽く開く程度、足の親指同士が離れぬようにし、箸を進める。
「それはいい話ではないか」と、兄の良太が上機嫌で答える。
「店の方を少し開けることなるが」と言うと、「そう毎日でもないのだし、そういったことも必要でしょう」と続ける。
妹の夫で長男の義弟との仲から、ひとつ覚えの料亭へ行くことが楽しみになったから、弟の昼の用事にも大らかなのか、もともとの性格であったかは、判断がつかぬところではある。
「せっかくだから行ってきなさい」と父も言う。
「おりつには、茶道も華道も長く通わせてみたが、あまり楽しそうではなかったが、お前たちを何度か通わせた時には、大層筋がよく、また楽しんでおられた、と言っていただいた。お商売のことを覚えなければならないから、頻繁には通えなかったが、今からでもよいではないか」
つい、おりつのことを口にし、父は若干寂しそうな顔をしたが、今ここにいる息子二人のことも、一応は記憶にとどめてはくれていたようである。
「はい」と良次は返事をした。
「着物は何がいいかしらね」と、母がそこで思いついたように言う。
「いつものお商売の時の着物では、なんだか味気ない気もするし、昔お父さんに作った着物を出しましょうか。ああ、それとも、昨年作ったもののなかに、良さそうなものはあったかしらね」
そういえば、陶器店の店主である義弟は、さりげなく、洒落た装いをしていた。
これみよがしな華美なものや、値の張るものではないのだが、ふっと心を引く装いだ。粋と言うよりは、趣がある、といったふうか。
6
母があれこれと世話を焼き、そのうちに、新しい着物を買いましょうかと言い出したのを止め、足袋だけは新しいものをおろし、いつもとは違う着物で良太はでかけた。
天気のよい日である。
町中では、早くも冷たい水を売る店が出ており、そこかしこから、風鈴の涼やかな音が聞こえる。
妹の嫁ぎ先の札差仲間の集う茶会とあって、少し距離がある。
途中、船着き場を見おろし、橋を渡り、神社に参拝した。そこではツツジが美しく花開き、その鮮やかな色に心引かれる。
境内を出て一礼し、そこから家も人もだんだんと減り、田畑の見渡せるのどかな場所に、義弟の茶の師匠の住まいがあった。
質素なつくりの家屋であるが、家の前がきれいに掃き清められており、外観から、家主の人柄が感じられた。
「これはこれは、良次さん」と、後方から声がかかる。
振り返ると、陶器店の店主の義弟に、その仲間と思われる二人がいた。
あいさつを交わし、茶の席へと参じる。
ずいぶんと久しぶりの茶の席であったが、茶道のお師匠さまは、穏やかで慈悲深い目をされた方で、良次のことも優しい言葉で歓迎してくださった。
床の間に飾られた掛け軸に、活けられた花は夏の喜びを表現されたのだという。
大人になって暑い、暑い、と嘆くように言う季節になったが、幼い頃は、夏に見られる花や高い空、鮮明な日暮れに、水菓子と、心躍った。
ふいに、それを思い出す。
高揚と安らぎ。
満たされた思いで、茶の席で正座する。
素足で過ごす時期に、おろしたての足袋が少し落ち着かぬが、背筋を伸ばし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うように揃える。足袋を履いた足の親指同士が離れないようにする。
菓子をいただき、茶をいただく。
そういえば、兄と参加した茶の席で、菓子を幼いおりつに持って帰ってやりたくて、懐紙に包んだことがあった。
おりつは大層それを喜んだ。
……忘れていたなあ、と良次は思った。
7
茶の席でご一緒した方々は、皆、すぐに良次と打ち解けてくれ、良次が花も好きだと言うと、この近辺の花の名所をぜひ案内したいと言ってくださった。もちろん、義弟も一緒である。
嬉しい約束ができ、皆と別れた後、気分よく歩いていた良次は、一軒の菓子屋を見つけた。茶のお師匠さまの住まいから近いことから、先ほど出た菓子は、ここで求めているのかもしれぬ、と思った。
自然と足が向き、中へ入った。
思った通り、小ぶりな可愛らしい菓子が並んでいた。
それを良次は土産用に買い求めた。
おりつの嫁ぎ先はここからそれほど遠くはない。
おりつが嫁いでから、花器を買い、花を飾れる楽しみができ、穏やかにやっているが、本当は、ごくごく僅かではあるが、寂しく思っていた。
そうして、お琴が全くうまくならない妹と思いながら、兄妹の中で、否、ほかの男子に引けを取らぬほどに強く、そしてたくましい妹を、実は結構心配し、かわいいと思っていたことに気づいた。
そんなことを直接言うつもりはさらさらないが、嫁ぎ先の迷惑にならぬ範囲で、こうしたついでの機会にでも、ささやかな好物を持参しよう、そう思った。

![[339]お江戸正座21](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)