[250]安楽椅子は茶席にいらない
 タイトル:安楽椅子は茶席にいらない
タイトル:安楽椅子は茶席にいらない
掲載日:2023/03/05
著者:神崎 七海
イラスト:神崎 七海
内容:
広幡梅子は、部員三名の茶道部の部長。現状の活動内容は、お茶を点てる練習をしながら、茶室で座ってお喋りをするだけ。
部員のひとり、藤麻が持ち込んだ話によると、最近消しゴムの裏に数字を書く恋のおまじないが流行っているらしい。
噂話に花を咲かせる中、突如鳴り響くパトカーのサイレン、そして持ち物検査の実施を呼びかける校内放送!?
色々不可解なこの状況の謎。梅子は清らかな正座の姿勢で茶を点てながら、淡々と謎解きを始める……。

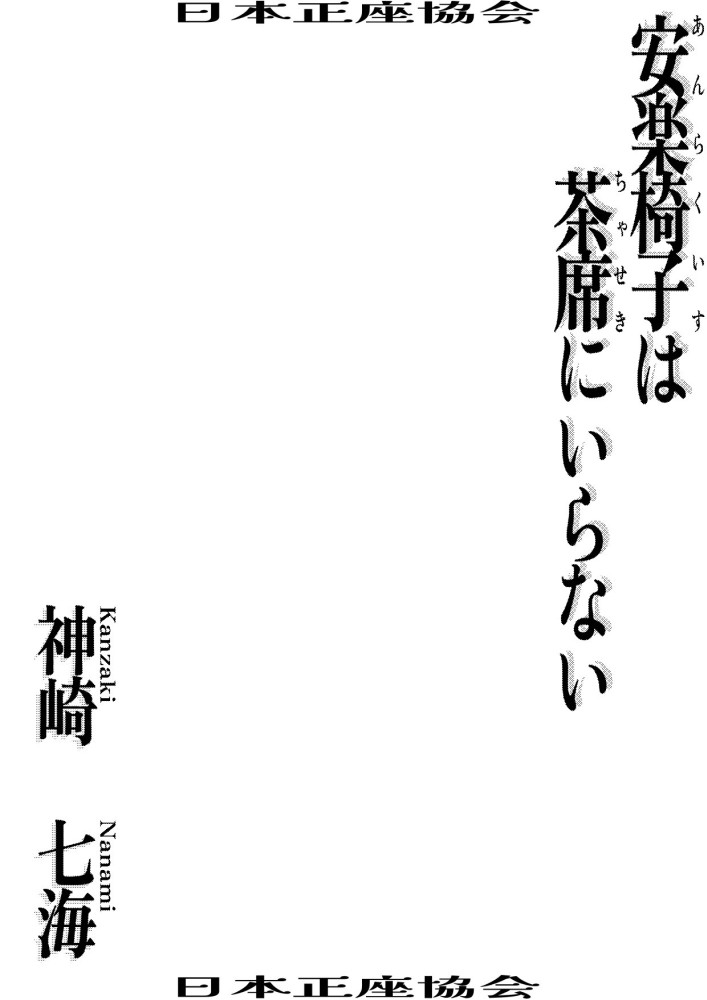
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
「正座の姿勢は、ふくらはぎを圧迫することから血流の悪化に繋がるほか、膝の故障に繋がるおそれがあることから、医学的に良くない姿勢であることが現代では科学的に証明されている」
飾りと呼べる飾りは、今は亡くなった祖父とその息子である父親が、二代かけて仕上げた雄大な盆栽。あとは、茶道の師であり書道家でもある母親が手掛けた掛け軸と、同じく母作の生け花くらいしかない、だだっ広い和室。
その中央で、丁度良い登校時間までにはまだ2時間弱もある朝6時から、簡易的な和服に着替えて正座の姿勢、茶を点てる準備を整えている私。
それを、和室の引き戸から一歩踏み込んだところから、憐憫と嘲笑と侮蔑でちょうど三等分できそうな目で見下しているのは、スーツ姿の私の兄。
「兄さん。畳縁は踏まないよう……」
「ふん。バカ親譲りの、時代遅れのマナー講座かよ。染まりきってんな、可哀想に」
茶道具を並べ終わり、茶杓を右手に取る。抹茶を容れ物から掬いとって茶碗に入れるための匙、ようはスプーンだ。
兄は今年の春から銀行に就職した。ほんの数年前までは大学にも和装で登校していたのが嘘であるかのように、左腕にはギラついた輝きを放つ腕時計。ネクタイ、ソックスなどは、私には知る由もないような海外のブランド物。
自分と違う妹が憎たらしくて仕方がないのだろう。さっさと通り過ぎればいいものを、私の朝の自主練習と出社時間が被ると、兄はわざわざ立ち止まり、嫌味を言いに入ってくる。
「現代医学で体に毒だと証明されている姿勢を強制するような文化が、文化、それも伝統としてこの国で認められているのが異常なんだよ」
「…………」
「黙りこくって茶道具と遊んでないで、何か言ったらどうなんだ、梅子」
「……お時間は、よろしいのですか」
私は兄の方に首を向けもせず、何なら少し顔を背けながら言った。
兄のことが嫌いなわけではない。兄に反感を持っているわけでもない。家業を継がず、しかし家を出ていくわけでもなく居座りながら悪態をつく兄に思うところがないわけではないが、私の方がおかしく、兄の価値観の方が至極真っ当なのであると感じている。デジタルな令和の若者にとっては、茶道も書道も盆栽も、ふつう人生をかけるほどのものではない。
ただ、私は兄が怖いのだ。
私の言葉を皮肉だと受け取ったのか、兄は少し眉間に皺を寄せて口を開きかけ、しかしすぐに冷ややかな真顔を残すように廊下を歩き去っていった。
独り残された私は、朝の鳥の声を聴きながらいつも通りに茶を点て、自分で飲んだ。
「……甘味が欲しいですね」
というか、朝にはやっぱりコーヒーだろう。
2
「恋のおまじないが流行るなんて、ウチの高校は小学校かってのよ」
茶道部副部長であり、風紀委員のひとりでもある吉田藤麻(よしだ とうま)ちゃんは、あぐらをかいた状態で両膝を羽のようにぱたぱたさせながら気だるげに言う。
うちの高校には、この令和の時代には珍しいことに、未だにクラスに一人風紀委員なるものが置かれており、主に朝の服装検査やあいさつ運動に駆り出されている。他の高校で言うと、生活委員とか美化委員とかが当てはまるのかな。
その活動のひとつに持ち物検査というものがあって、学業に不要なものを持ってきていないか、月に数回、不定期に、カバンや筆箱の中をざっとチェックするというものだ。そこで、何人かの生徒が消しゴムに図柄やら数字やらを描いたものを持っていた。
もちろん違反というわけではないが何となく気になったので聞いてみたところ……その答えが、『恋のおまじない』だったということ。
そんな話を私たちにした後で、藤麻ちゃんはやれやれと心底呆れた様子でかぶりを振る。
「別に校則違反でもないし、人の勝手だけど。それにしたって、今日の検査だけで6人よ、6人。他のクラスでもあったらしいし。何て言うか、もう肩の力が抜けちゃったわ」
「まぁまぁ。誰かに迷惑かけてるわけじゃないしさ。可愛くていいじゃん」
「可愛くて、ねぇ。その6人のうち4人は男子だったんだけど」
「え」
「同じこと、言える? 亜麻奈」
それはちょっと、さすがに、アレかも。これ以上先の感想が口から出る前に、私は自分の茶碗を口に当てて、綺麗なお茶で汚い言葉を流し込んだ。
亜麻奈とは私のことだ。中島亜麻奈(なかじま あまな)。藤麻ちゃんと違って茶道部員以外に肩書きを持たない、普通の高校1年生。
「……恋のおまじない、ですか」
「あれ。梅子、こういうの興味ある?」
「興味、と言いますか。そういった、オカルトチックな物事に明るくないもので……どのような内容なのですか、そのおまじないは」
広幡梅子(ひろはた うめこ)さん。私たちと同じ1年生ながら、この茶道部の部長を務める和風美人は、上品に口元に手を当てて少し恥ずかしそうにはにかんだ。
梅子さんの家、広幡家は古くから茶道の名家らしく、部活動だけでなくお家でも毎日茶道のお稽古に励んでいるそうだ。失礼だけど、今どきそんな女子高生がいるのか、なんて最初は思ってしまったが、彼女がさりげなく見せる美しい所作のひとつひとつを見ていると、彼女は正真正銘の名家の娘なのだと納得させられる。
今もそうだが、茶道部の三人の中で綺麗な正座が出来るのは梅子さんだけだ。私は正座から崩した、いわゆる女の子座り。藤麻ちゃんはあぐら。スカートが心配になってしまうが、彼女曰く「短パン履いてるし、そもそも女子しかいないんだからいいでしょ」とのこと。こういう所にも性格が出てるなぁと思うし、やっぱり梅子さんは凄いなぁと思う。いつも同学年相手でも綺麗な敬語の言葉遣いで話すし。
私が藤麻ちゃんや他の女の子はちゃん付けで呼ぶけど、梅子さんだけはさん付けで呼んでしまうのは、そういうところに理由がある。
「おまじないの内容、ねぇ。なんか、消しゴムの裏に何か描くらしいけど」
「私のクラスでもちょっと噂になってたよ。たしか、好きな人の誕生日と星座を書くとか。消しゴムを三つ用意して、ひとつには生まれ月、ひとつには生まれた日、ひとつには12星座の番号」
「星座の番号ですか……。牡羊座が1、牡牛座が2、のような?」
「あ、そうそう。それを描いて使い切ると、好きな人と結ばれるんだよって。やってる子は、なんか懐かしいし可愛いからーって言ってたけど。ホントに信じてるって感じじゃなさそうだったねぇ、さすがに」
「まぁこの歳になって本気でそんなもの信じてるヤツはいないでしょ。面白がってやってんのよ」
それを言っちゃおしまいだよ、と言いたいが、実際のところそんな感じだ。何となく、周りで流行ってるらしいからという理由でやっているだけで、みんな本気にはしていないだろう。
藤麻ちゃんはまた溜め息をひとつ吐いた後で、お茶に口をつけようとして、「あ、でも」と茶碗を口から離した。
「噂が、伝言ゲームみたいになってるせいなのかしら。今亜麻奈が言ったそれ、ウチのクラスの男子がやってた内容とちょっと違うのよね」
「あれ、そうなんだ」
「違うっていうか、ちょっとルールが増えてるっていうか。その3つの消しゴムとは別に、好きな子の血液型が書かれた消しゴムと、上・下のどっちかが書かれた、もしくは何も書かれていない消しゴムを用意するんですって」
「……血液型は、私でも分かる気がしますが。上・下と何も書いていない消しゴムとは……?」
「好きな人が、自分よりも年上なら上。年下なら下。で、同い歳なら何も書かないってこと」
「へえ……なんか、思ったより面倒だね」
「あと細かく言うと、誕生月は漢数字、誕生日はアラビア数字、星座の番号はローマ数字で書くとかね。九、1、Ⅵとか、二、3、Ⅸ。六、9、Ⅳって具合にね」
面倒だと思いつつ、私はこのおまじないを考えた人の真意を考える。
このおまじないを実践するためには、好きな人から誕生日や星座や血液型を訊く必要がある。要するにこれは、おまじないと称して、好きな人と話すことで距離を縮めるための会話の糸口になるようにと考えられたものなんじゃないだろうか。
そう考えれば、5つも消しゴムを用意しなければならないこのおまじないも、信じる信じないの次元ではなく現実的に有用なものだと思えてきた。
どっちにしろ面倒だが。
「ご説明ありがとうございます。おまじないとは案外可愛らしいものなのですね」
「そりゃ小学生女子がやってれば可愛いけどさ。高校生男子がこんなことやってるの、普通にキモいけどね。真正面からアプローチしなさいよ、って感じ」
「あはは。藤麻ちゃんはおまじないとか信じなさそうなタイプだよね」
「占いとかは好きだったんけどね。手相占いの本買ったら、私の生命線が短いことが分かっちゃったから、その瞬間から占いアンチになったんだけど」
「……まぁ、信じたいものを信じたいように信じるのがいいと思うよ」
良い意味でも悪い意味でも極端なところが、藤麻ちゃんの良さだと思う。
話がひと段落して静かになると、7月の、水分を少し多めに含んだ暑さが段々と鮮明に感じられてくる。
「……暑いねぇ」
「そうですね……部員がもう少し増えれば、部費をもらって、扇風機くらいなら置けるかもしれませんが……」
私たち茶道部の活動場所である和室には、エアコンが設置されていない。今でさえとても快適とは言い難い環境で活動を行っているので、8月に入ったら、梅子さんはともかく私と藤麻ちゃんはぐったりしながらお茶を点てることになるだろう。
「一年生の私たち三人だけだもんね。去年、三年生しかいなくて、全員卒業しちゃって部員がゼロ人になって……一応、私たち三人が入部したから、部の存続はできてるけど」
「たしか、文芸部もそんな感じじゃなかったかしら? あっちは五人入ったから、そこそこな部費ももらえてるらしいけど」
「そうなのですか?」
「うん。でもムカつくわよね。私たちは一応ちゃんと活動してるけど、文芸部のヤツら、部室内に友達や先輩を呼んで遊んでるって噂よ。他に部員がいないのをいいことに、部室を秘密基地にしてるだけよ。アイツら」
たしかにそれはどうかと思うけど。まるまる一部屋使える自分たちの秘密基地を学校内に手に入れて、やることが友達を呼んで遊ぶだけって。他にもう少しやることがあるんじゃなかろうか。
「あくまで噂なのですから、よそ様のことをそんな悪し様に言うものではありませんよ。吉田さん」
「はいはい、すみません」
まるで母親と娘だなぁ。不意に笑みがこぼれる。
私たちはいつも、茶道の練習を一時間くらいかけて行い、その後の時間はずっとこんな風にお喋りに興じている。
おそらく、梅子さんが茶道のいろはも知らない私たちに気を遣ってくれているのだろう。私と藤麻ちゃんは、入学して早々ひょんな面倒事に巻き込まれ、それを梅子さんに解決してもらったという縁から茶道部に入部した。
梅子さん本人は、「家でお稽古はお腹いっぱいですから。学校でくらい、友達と、ゆるりと楽しみたいのです」と言ってくれているが、茶道の素人である私たちが楽しく過ごせるように、ゆるい雰囲気を作ってくれているんだと思う。
その甲斐あって、私も藤麻ちゃんも、これまで活動日に欠席したことは一度もない。茶道部でのこの時間を楽しいと思っているし、この和室は、とても居心地が良い。
梅子さんが点ててくれたお茶と、やわらかな夕暮れ前のひと時を楽しんでいた、ちょうどその時だった。
ピンポンパンポーン……。学内放送の、アナウンス音が響く。
『一年二組の大島、花崎、西山、高田。すぐに職員室まで来なさい。繰り返します、一年二組の……』
何やら、穏当ではなさそうな声色の、男性教師による呼び出し。
私たちはお互いのきょとん顔を見合わせる。
「たしか今の四人って、文芸部のメンバーだったよね?」
「噂をすれば、って感じね」
文芸部のメンバーは、一年生の中では目立っているので、他クラスの私でも苗字くらいは把握している。
目立っているというか、悪目立ち。入学当初から様々な問題を起こしている不良グループで、他の生徒たちからは怖がられたりしているのだ。私も遠くから彼らの集まりを見たことはあるけれど、あまり積極的に関わりたくないグループだ。
「……そういえば、今思い出したんだけど。今呼び出された文芸部のメンバー……全員、あの消しゴム持ってたわ」
「えっ? さっきの、おまじないの?」
「うん。関わり合いになりたくない人種だし、落書きしてある消しゴムくらい取り締まりの対象にはならないし。特段、気にしてなかったんだけど……他のおまじないをしている子たちと違って、筆箱を触られるのを少し嫌がっていたような気がする」
ははあ。それは、なんとも……。
不良さんだと思っていたが、案外可愛いところがあるのかな? 男子がそんなことしてるなんて知られたくなくて、恥ずかしがっていたんだろうか。
「何かしたのかしら。いや、ていうか、何かしてそうな輩ではあるけど」
「呼び出しの声、中西先生だったよね?」
中西先生は強面の体育教師で、一年生の学年生活指導も兼ねている。時代があと20年ほど違えば確実に竹刀を持ち歩いていたであろう、というのは私の偏見だけど、ウチの高校の生徒ならみんな頷いてくれると思う。
その中西先生が、怒気を孕んだ声で文芸部の四人を呼び出している。これは、彼らが何かやらかしたと考えない方が不自然だ。
「あれ? 何か聞こえない?」
私がそう言うと、藤麻ちゃんが和室の外を見に行ってくれた。数秒後、興奮した顔を引っさげて戻ってきて、
「外! 外に、パトカー来てる!」
「えぇっ?」
にわかには信じ難い報告。しかし、さっきまでうっすらとしか聞こえてこなかったサイレンの音が、徐々に鮮明に聞こえてきて、信じざるを得なくなる。
「タイミング的に考えて、まず間違いなく、文芸部のヤツらよね?」
「何したんだろう……部室内で、何か悪いことしてるのが見つかったとか?」
「あっ。今日の朝礼で言ってたカツアゲの犯人が、文芸部のヤツらだったとか?」
カツアゲ……たしか、一年の男子が被害に遭ったとかで、朝礼で注意喚起されてたっけ。
定期を更新するために、財布にいつもより多めに入れていたお金を奪われて、定期も帰りの切符も買えなくて帰れなくなったその男子が、職員室に駆け込んだことで発覚した……とか。何とか。
「物騒だねぇ。あぁ、でも……昨日、物理の小テストの再テストがあって、私、放課後残ってたんだけど。その時、職員室の前で先生と話してる男子、うちのクラスの子だったんだよね」
「その生徒が、カツアゲの被害者?」
「タイミング的にそうなんじゃないかな。『気を付けて帰れよ』とか聞こえてきたし……あれ、でも、たぶんあの男子、文芸部の人たちと仲良さそうだったよ。よく昼休みつるんでるところ見るし」
「ふぅん。じゃ、カツアゲの線はなさそうね。他になんかあるかしら、あの連中のやらかしそうなこと」
浮き足立つ私たちとは対照的に、梅子さんは正座の姿勢を崩さぬまま、両手で包むように持った茶碗の水面を見つめて、何やら考え込んでいる様子。
さらにこの状況に追い打ちをかけるように、ピンポンパンポーン、二度目のアナウンス音。
『只今より、緊急の持ち物検査を実施します。今現在学校に残っている生徒は、全員、体育館に集合するように。繰り返します、今現在学校に残っている生徒は……』
……何だ、いきなり大事になってきたけど。
「持ち物検査って。何でしょうね一体」
「……とにかく従いましょう。お二人とも、カバンを持って」
「う……うん」
3
「思ったよりあっさり終わったねぇ」
「全員何事もなく、安心しました」
ものの15分くらいで検査は終わり、私たちは再び和室へと帰ってきて、体育館に向かう前と寸分違わぬ位置に座り直す。
体育館ではバスケ部の練習が急遽中断されたようで、壁際に部員たちの荷物がまとめられていたり、ボールのいっぱい入ったカゴが隅っこに放置されたり、雑然としていた。
部活などで校内に残っていた生徒たちがまばらに体育館へ赴く中、教職員が10人くらい大集合していて、それにおののきつつ体育館に入った瞬間、まだ授業などで接した機会のない上級生担当の男の先生に呼び止められ、その場でカバンの中、筆箱の中、メイク道具入れの中を簡単に検査された。
メイク道具は暗黙の了解で認められてはいるが、厳密には校則上アウトなので、怒られるんじゃないかと震えながら目の前で荷物がまさぐられるのを見つめていると、「はい、戻っていいよ」とあっさり解放。
結局あれはなんだったんだろうか。ぼんやり考える私と梅子さんに対し、藤麻ちゃんは、何か深く考え込んでいた。
「うーん、あの子たちって……」
「どうしたの?」
「いや。私たちも含めて、大体みんなサラッとカバン・筆箱・ポーチを漁られて、すぐ解放されてたじゃん?」
「あぁ……何人か、すぐに解放されず、先生方に何か説明していらっしゃる方がいましたね」
あー、そういえば。私も見たっけ、女子生徒が先生相手に何か怒り気味でまくし立てていた。一緒に来ていた友達も加勢して擁護していたみたいだが、周りがざわざわしていたのもあって、あまりよく聞き取れなかったけど……。
「あの子たちがどうかしたの?」
「うん。あの子たち、私と同じクラスなんだけどね。さっき話に出た、おまじないの消しゴムを持ってた子たちだったの」
「……あの消しゴムを?」
それはまた、奇妙な符号というか……。
順当に考えれば、放送で名指しで呼ばれた文芸部と同じように消しゴムを持っていたのだから、持ち物検査で引っかかった物品は件の消しゴムだと考えるべきなのだと思う。
しかし……。
「あの消しゴムに、何かマズイことがあるとは思えないわよね」
「うん……消しゴムに何か書くおまじないなんて、それこそ、小学生だってしてるわけだし」
「………………」
その時、ふと、目の前に座っている梅子さんがずっと目を瞑っているのが気になった。
「梅子さん? どうかした?」
「……いえ。文芸部の方々が、何故職員室に呼び出されたのか。何故、警察の方が出向くほどの事になっているのか……少し、思い付くことがあったかもしれません」
「えっ、本当?」
私と藤麻ちゃんは顔を見合わせる。
梅子さんは、以前、私たちが茶道部に入部するキッカケになったとある事件で、同じようなことを言って、見事にその事件を解決してみせてくれたのだ。
二人とも少し不謹慎にワクワクしながら、向かい側に座る梅子さんに詰め寄る。
「何なの? 文芸部、何したの?」
「落ち着いてください。お二人に、きちんと説明するためには……少々、考えを整理する必要がありそうです」
梅子さんは、正座の姿勢から一旦立ち上がり、一度片付けた茶道具を自分の前に並べ直してから、もう一度綺麗な正座に直った。
「そろそろ下校時間も迫ってきております。非常に簡易的にはなりますが……どうぞ、お茶を飲みながらお聞きになってください」
4
――茶道とは、おもてなしの文化なのです。
入部初日に梅子さんから聞かされたこの言葉、私は練習の時にいつも心がけているし、梅子さんのお茶を点てる動作を見る度にいつも思い出す。
茶碗も茶杓も、道具は全てさっき使い終わった後に洗浄を済ませたものだ。それでも、茶道ではお茶を飲んでもらうお客様の目の前で、もう一度改めて清めるという手順を踏む。道具は本当に綺麗な状態なのか、そんな疑いを持つことなくお茶を楽しんでもらうための、最初のおもてなし。
最初に簡易的に済ませると言った通り、本来は茶釜からお湯を汲むところを、梅子さんはすぐに湧かせる電気ポットから柄杓でお湯を汲んだ。それを茶碗に注いで、柄杓を置き、茶筅に持ち替えて三人分の茶碗の中の湯をかき混ぜる。熱いお湯で茶碗と茶筅を清めるのだ。
「まず……お二人は、警察の方が来た理由はどのようなものだとお考えですか?」
茶筅で湯を混ぜながら、梅子さんは尋ねる。
数秒考えて、私は首を横に振った。
「……分からないかな。文芸部の人たちが何かしたのは間違いないんだろうけど、学校内のことで警察が出向いてくるようなことって……」
「私は、何か、薬物とかの取引でもしてたんじゃないかなって思ってるわ」
「や、薬物?」
声が裏返ってしまった。
自分のこれまで生きてきた世界の丸っきり外側に存在する言葉。それに驚く私に、藤麻ちゃんは顎に手を当て、憂いを帯びた顔で続ける。
「もちろん、根拠なくこんな事は言わないわ。まず第一に、文芸部の外部の人たちがしょっちゅう出入りしていたという点。そして、これは一般の生徒はあまり知らないかもしれないけど……この町では今、半グレ集団が高校生を狙って、薬物の運び屋をさせるのが流行ってるんだって」
私はそれを聞いて、なるほどと首肯した。藤麻ちゃんの父親は警察官だ。そんな物騒なことが流行っているんだとしたら、娘に気を付けるように言っていたとしてもおかしくはない。
それに、文芸部の人たちはけっこう夜にヤンチャをして補導されているようだし。半グレがどういう人のことを指すのかは分からないが、そういう人たちとの繋がりを持っているというのは十分考えられるだろう。
梅子さんは全ての茶碗のお湯を建水代わりの大きめの茶碗に捨てながら、なるほどと頷いた。
「たしかに、有り得るかもしれません。ですがそれでは、おまじないの消しゴムを持っていた方が検査に引っ掛かっていたことに説明がつかないかと」
「そうね、それは謎のままだわ」
「……薬物取引の会員証みたいに使われてたとかかな。ほら、中学の歴史で習った、朱印船貿易みたいな」
「オシャレで面白いけど。仮にも薬物取引してるヤツらが、そんないくらでも偽装の効く方法で仲間の見分けをつけてるかしら?」
そりゃそうか。うーん、大人しく他の可能性を考えた方がいいのかな。
袱紗で清めた茶杓で、抹茶をすくって茶碗に移しながら、梅子さんは口を開く。
「私が思うに……文芸部と、そこに出入りしていた方々は、賭博に興じていたのではないでしょうか」
聞き慣れない言葉に、一瞬頭が理解を諦めた。
「賭博? ギャンブルってこと?」
藤麻ちゃんが言い換えてくれたことで、私はようやく梅子さんの言葉を理解する。
なるほど、たしかに賭博は日本では犯罪だ。国に認められた公営のギャンブル以外、金銭やそれに準ずるものを賭けてゲーム等をすることは、禁じられている。けど……。
「そりゃ、高校で真っ昼間から学生がお金を賭けてギャンブルしてたら、警察は動くだろうけど」
「数ある犯罪の中で、賭博罪って。またどうしてなの?」
「それを説明するには、まず、おまじないの消しゴムについて話を進めた方が良いでしょう」
梅子さんが話をもったいぶるなんて珍しい。いや、彼女のことだから、多分本当にもう一つの謎を先に解いた方が話が分かりやすいんだろう。
抹茶を入れ終えたら、いよいよお湯を注いで茶を点てる段階。限りなく無駄の少ない洗練された動きでお湯を注ぎ入れながら、梅子さんは話を続ける。
「吉田さん。おまじないの説明の時におっしゃっていた、誕生月、誕生日、星座の番号の組み合わせを、もう一度お願いしてもよろしいでしょうか」
「え? あぁ。えっと、九、1、Ⅵ。二、3、Ⅸ。六、9、Ⅳ。この三つだったかな」
「ありがとうございます。違っていたら申し訳ないのですが、吉田さん。こちらは、吉田さんが風紀委員の持ち物検査で実際に見た組み合わせではありませんか?」
「あぁ、うん。そうだよ。文芸部のヤツらの消しゴムだね。あと一人分はたしか、七、8、Ⅱだったかな……」
たしかに、例に出すなら一、2、Ⅲとかでいいだろうに、妙に具体的だなと思ったんだ。藤麻ちゃんが実際に見た組み合わせだったのか。
「吉田さん、中島さん。今の数字の並びで、何か気が付くことはなかったでしょうか」
二人揃って、首を捻る。何か共通点でもあっただろうか、それとも暗号?
私は早々に両手を挙げてギブアップを宣言。一方の藤麻ちゃんは、まぁ違うだろうけどという苦笑顔で、
「えっと。4人とも、みんな、誕生日が妙に上旬に偏ってるなぁ……とか?」
「それも正解ですね」
「正解なの!?」
私も驚いたが、考えを述べた藤麻ちゃんが一番驚いていた。
梅子さんはさらに続ける。
「正解ですが、もっと明確な矛盾があります。中島さんはたしか、お誕生日が七月八日でしたよね?」
「うん、そうだよ」
「えっ! 私が最後に言った消しゴムの組み合わせと一緒じゃない! もしかして……?」
「い、いやいや。有り得ないから。そもそも私、あの辺の人たちと喋ったことないし!」
私が慌てて否定すると、藤麻ちゃんはけらけらと笑いながら両手を合わせて、ゴメンのジェスチャーを返してきた。
もう、からかわないでよ。
「七月八日の星座は、何座でしょうか」
「かに座だね。……ん?」
私も、小学生の頃は占いの本をよく好んで読んでいたけど。牡羊座を『Ⅰ』番とするなら、かに座は『Ⅳ』番にあたるはずだ。
「おかしいな。藤麻ちゃんが最後に言ったのって、七、8……『Ⅱ』だったよね?」
「あっ、ホントだ」
「星座の番号に当てはめると、Ⅱ番は牡牛座です。七月生まれの方は、かに座か獅子座しか有り得ないはずなのに……」
よく考えればそうだ。二月生まれでⅨ番目の射手座っていうのも有り得ない。
「また、吉田さんがおっしゃったように、いずれも誕生日が一桁ばかりであるのも気になります。誕生日が一桁である確率は1/3以下。四人とも誕生日が一桁である確率は、その四乗で1/81以下。約1.2%です。
また、全員誕生月も一桁なのです。こちらは、確率は3/4以下ですが、四人とも誕生月が一桁である確率は81/256……約32%以下です。
そのどちらもを満たす確率は、二つを掛け合わせて、単純計算、0.39%。有り得ない可能性ではありませんが、かなり低い確率です」
「えっ……今の。暗算でやったの?」
「梅子さんすごい……」
「……お褒め頂き光栄ですが、続きを話させて頂きますね」
少し頬を紅く染めた梅子さんは、茶碗の中でお湯と抹茶をシャカシャカと混ぜ合わせながら、続きを話す。
「今お話させて頂いた確率の話、そして星座の番号の矛盾を踏まえると、噂を聞いておまじないを実践していた方々はともかく。文芸部の方々は、おまじないなどではない、何か別の目的で消しゴムの裏に数字や図柄を書いていたことになります」
五種類の消しゴム。誕生日の月と日と星座を表す一桁の数字が三つと、血液型を表す文字が一つ、年上か年下か同い年かを表す文字が一つ。
これを、別の目的で使うってどういうことだろう。梅子さんは、文芸部は賭博を行っていたって言ってるけど、賭博に関係あるのだろうか。
三人分のお茶を混ぜ終わった梅子さんは、私たち二人の前に、絵柄がいちばん綺麗に見える向きにして茶碗を差し出す。
「お菓子もありませんし、かなり手順を省いた粗末なものではありますが……どうぞ、お召し上がりください」
私たちは、左手で茶碗の底を支え、右手を側面に添える……一連の作法を頭の中で反芻しながら、ゆっくりと一口目を頂いた。
梅子さんの美しい所作を思わせる、優しくまろやかな苦味が、口いっぱいに広がる。私たちがお茶を味わうのを満足気に眺めて、梅子さんはひとつ頷いてから、
「……それでは、結論をお話しましょう。
文芸部では、おまじないに偽装した消しゴムを使っての、賭け麻雀が行われていたのです」
……聞いた私たちの口を永遠に半開きにしてしまうような結論を述べた。
「……賭け麻雀……?」
「お二人は、麻雀という遊びはご存知ですか? たしかに高校生では馴染みがないかもしれませんが、よくある話ですと、正月の親戚の集まりで……とか」
「いや、知ってはいるわよ。やった事ないけど」
「私も知ってるけど。何でいきなり麻雀が出てくるの……」
と言いかけて、私の頭の中で、二つの像が重なった。
消しゴムと、麻雀の牌。
そして、おまじないに用意する五種類の消しゴムと、麻雀牌の種類……。
「あぁっ! なるほど、たしかに!」
「えっ? 何よ、分かってないの私だけ?」
「吉田さん。麻雀の牌の種類はご存知ですか?」
えーと、と目を上に向けながら、藤麻ちゃんは指折り数える。
「お父さんがやってたから、どんな牌があるかくらいは知ってるわ。漢数字が書いてるやつと、青い玉が並んでるやつと、竹が並んでるやつ、あと東西南北、なんも書いてないやつ、発みたいなやつ、中って書いてるやつ」
「それぞれ、漢数字が書いているのは萬子、青い玉が並んでいるものは筒子、竹が並んでいるものは索子。これら三種はそれぞれ1から9まであります。一種少ないですが、トランプの絵柄と数字のようなものと考えて頂けると分かりやすいでしょうか。
東西南北はトンナンシャーペー、そして何も書いていないもの、発に似た漢字が書いてあるもの、中が書いているものは三元牌や役牌と呼ばれます。
さて、そろそろお気付きになられたのではありませんか?」
「消しゴムの種類と牌の種類、完全に一致してるじゃない!」
聞かれるよりも早く、藤麻ちゃんは答えた。
頷いて、梅子さんは続きを話す。
「漢数字で書かれた誕生月は萬子、アラビア数字で書かれた誕生日は筒子、ローマ数字で書かれた星座の番号は索子。
血液型四種は東南西北。年上か年下か同い年かを表す三種は白發中の三元牌。
この高校では、不定期に持ち物検査が実施されます。文芸部室を麻雀の賭場にしようと企んだ文芸部員たちですが、真正面から麻雀牌のセットを持ち込んだのでは、リスクが高い。そこで彼らは思い付いたのでしょう……おまじないに偽装する形で、麻雀牌代わりの消しゴムを持ち込む計画を」
文芸部とそこに出入りしている友人たち、麻雀の卓を囲むメンバーは、各々協力して消しゴム牌を作り、何回かに分けて学校に持ち寄ることでゲームに必要な牌を揃えた……ということか。
「その証左として。吉田さん、彼らの持っていた消しゴムに、使われた形跡は少しでもありましたか?」
「いや、なかったよ……そうか、形が少しでも違ってしまったら、イカサマができちゃうってことね」
「また、先ほど体育館で行われたものではなく、本日クラス単位で行われた風紀委員による持ち物検査の話で、吉田さんは、『今日だけで』と仰いましたね。前回の持ち物検査でも同様の消しゴムが見つかっているのでは?」
「その通りよ。……まるで、見てきたみたいね」
藤麻ちゃんは、驚くのを超えて、もはや怖がってすらいるみたいだった。
「昨日、金銭を巻き上げられたと職員室に駆け込んだ二年の男子生徒。彼はおそらく、文芸部の賭け麻雀で素寒貧になってしまい、しかし賭博で失ったなどと言うわけにもいかず、ありもしないカツアゲ事件をでっち上げたのでしょう。
もしも本当にカツアゲに遭ったのだとしたら、相手の顔は見ているわけですから、朝礼で注意を呼びかける必要もありません。カツアゲの犯人を呼び出して、何なりと処分を言い渡せば良いだけです。そうならなかったということは、彼は先生方に対しては、顔を隠していたとか口止めされているとか言ってはぐらかしたのかもしれません」
「……ここにきて、カツアゲ事件とも繋がってくるなんて」
梅子さんは、未だに自分のお茶に口をつけない。もう少しでこの推理の披露は完了するということだろう。
長く話して乾いてきたのか、ひとつ、唇を舐めて潤す梅子さんの仕草は、いつものお淑やかな彼女の所作と違って、どこか妖艶だった。
「昨日のその事件、麻雀牌の構成に酷似したおまじないの消しゴム、そして普段の文芸部の素行。数々の要素から疑惑を持った先生方は、昨日文芸部員たちが下校した後、文芸部室の捜索に踏み切ったのでしょう。そこで、賭博の証拠となる何らかを発見した。具体的にどのようなものだったかは図りかねますが、おそらく、金銭のやり取りが明白となる点数計算表などでしょうか。
そして、今日。風紀委員による不定期の持ち物検査の実施。吉田さんは、おまじないの消しゴムなんて校則違反には当たらないからと、注意はしなかったようですが、先生方はもしかしたら、それをこそ報告してほしかったのかもしれませんね。賭博の参加者を見つけ出すために……。
おまじないの噂は、文芸部員たちが消しゴム牌の存在を隠すカモフラージュとして流したものなのか、それとも元々あったものなのか。それは分かりませんが……何も知らずに噂を真似して消しゴムに数字を書いてしまった方々は、先ほどの持ち物検査で疑いをかけられて、災難だったでしょうね」
呆気に取られる私たち。
梅子さんは、ふう、と蝶の羽ばたきのような一息を漏らすと、自分のお茶を一口飲んで、
「……大変良く点ちました」
そう締めくくった。
5
「また飽きもせず、母親の言いなりになってこんな朝っぱらから自主練か。殊勝なことだな」
だだっ広い和室、登校時間の二時間前。
いつものように茶道の自主練に励んでいる私、いつものようにそれにいい顔をしない兄。
いつも通りの朝の時間。代わり映えしない毎日の中でも、とりわけ一層変わらない、ルーティンをこなすだけの準備期間。
変わったことと言えば……今日は、兄が室内に入ってきて、私の正面に座った。
胡座をかいて座る兄の姿に、数年前の兄の綺麗な正座を重ねて、少し寂しくなる。
「……なぁ。親父が俺に言ってたよ。『梅子は先月の模試でも県内トップ10だったのに、お前と来たら三流銀行で……』ってな」
「それは……ごめんなさい。私のせいで不快な思いをしたみたいで」
「違う、悪いのはお前をダシに俺に嫌味を言った親父だろ。俺が言いたいのは、お前はいつまで畳の上に正座してるつもりだってことだ」
そろそろ立て……とか、そういう話ではなさそうだ。
「令和になっても、未だ男女の格差はあるが、お前ほどの能力と成績があれば、女性でも良い大学に進んで、良い会社に就職して……いや、自分のやりたい道なら何だって進めるはずだ」
「私にとっては、茶道というこの道が、進みたい道なのです」
「それが洗脳じゃないと言い切れるか?」
後から思えば、痛い所を突かれたのだろう。図星だったのだろう。
「兄さん!!」
はしたないほど顔を強ばらせて、私は怒鳴っていた。
自分で言うのも何だが、私が感情を露わにするのは相当に珍しいことで、兄も一瞬面食らったようだった。しかしすぐに取り直し、言葉を続ける。
「俺たちは子供の頃から、朝は茶道、昼は学校と帰ってきてからまた茶道、空いた時間に書道……友達と満足に遊ぶこともできないまま、フォアグラのガチョウみたいに、親の言う事だけを絶対として詰め込まれてきた。
俺の洗脳が解けたのは大学で色々な経験を積んだ後だった……だけど、それじゃ遅すぎる。遅すぎたんだ。お前には、こんないつか滅びゆく錆びた文化のために、貴重な高校生活という青春を無駄にしてほしくないんだ」
滅びゆく、錆びた文化。
変わってしまったものだ。数年前までの兄なら、絶対にこんなことは言わなかった。他所の人間から同じことを言われて、憤りすらしたはずだ。
人間でさえ簡単に変わる。ならば、文化を変わらず保ち続けることに、何の意味があるのだろうか。文化を営む人間は目まぐるしく変化を続けているというのに、鎌倉時代に始まったこの文化を、私たちはいつまで――。
「しかし、兄さん」
考えなければいけない悩みは山積みで、向き合わなければいけない問題は私の四方八方を塞いでいるようだけれど。
私は、昨日、文芸部のアナウンスの謎を解いたあと……中島さんと吉田さんと話したことを思い出す。
家に帰らなければならないという段になって、昨日朝の兄との会話を思い出し、少し憂鬱になっていた私は、お二人に、変な質問をしてしまったのだ。
――お二人は、茶道の堅苦しさが、息苦しくはありませんか?
部の仲間として、こんなろくに世間を知らない私とお付き合いしてくれる友人として、お二人にはできるだけ、部活動で息苦しさを感じてほしくない。茶道の正式な手順を覚えられなくても、表千家と裏千家を混同したままでも、正座が長時間できなくても、私のわがままで茶道部の存続に協力してもらったお二人に、せめて楽しい時間を過ごしてもらいたい。
そんな想いから出た質問だった。質問を受けたお二人は、どういう意図での質問かと顔を見合わせ、少し考えた後。
――多少堅苦しいとは思うけど、息苦しくはないわよ。まだ正座はできる気しないけどね。
――私も、まだ茶道のイロハすらよく分からないけど。ただ、なんていうか……全然答えになってないと思うけどさ――
「私の茶道部の友人は、こう言ってくれました。
『梅子さんの正座姿は、とても綺麗だと思うよ』」
これもまた、中島さんが言ったのと同じく、全然兄さんの言葉に対する答えにはなっていませんが。
「……良い友達は、持ったみたいだな」
「そこは、普通に『友達を』でよいのではないですか?」
「『は』だ」
そう言って、兄は私の点てたお茶をぐいっと一気に飲み切って、立ち上がった。
「苦い。じゃあな」
ビジネスバッグを担いで、忙しない足取りで廊下へと消えていく兄を座したまま見送り、私はゆっくりと自分のお茶を飲む。
「……うん」
やはり、自分にはお茶が性にあっている。








