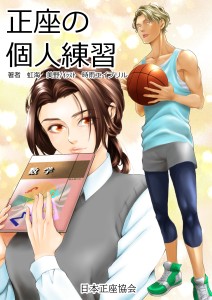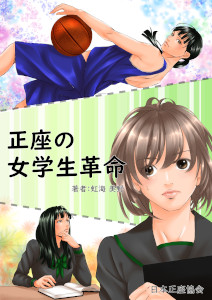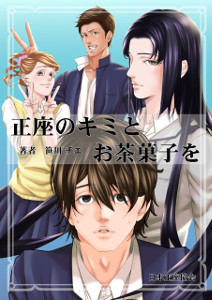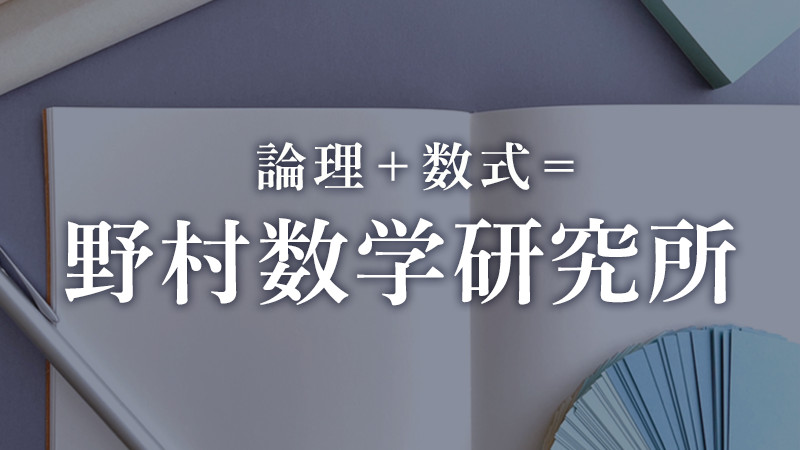[344]正座の屋外研修
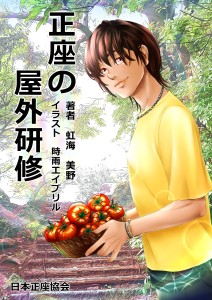 タイトル:正座の屋外研修
タイトル:正座の屋外研修
掲載日:2025/03/29
シリーズ名:某学校シリーズ
シリーズ番号:32
著者:虹海 美野
イラスト:時雨エイプリル
内容:
実土利ユタカは某栄富高校に入学して間もない。
学校では一年時に学校の施設である自然体験施設を用いて一泊研修を行う。
研修場所が学校であるのは気楽だと思ったユタカだが、学校傍にある山の湧き水を使ったお茶を点ててもらい、いただくのだという。
和室での正座にやや憂鬱になるユタカだが、研修では交流の少なかった生徒達とも木工体験や慣れない料理をする中で、次第に打ち解けていき、お茶の前には正座についてほめられ……。
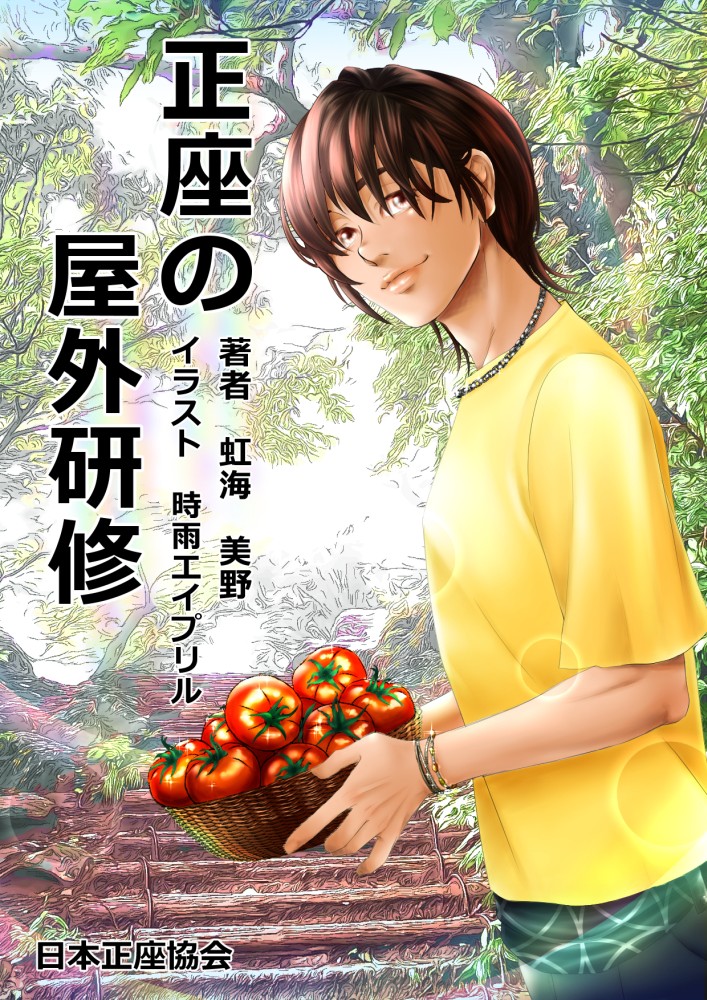
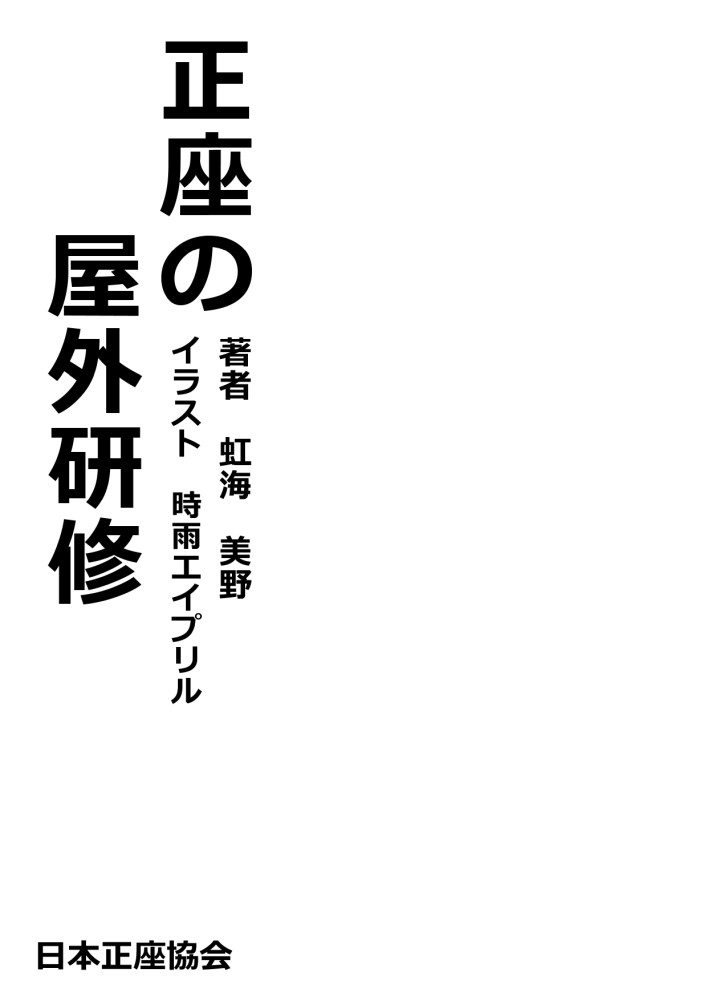
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
実土利(みどり)ユタカの通う某栄富(えふ)高校は、山裾にある高校である。
電車は下りで、朝の通勤通学の時間帯も空いた車両で通学し、駅のロータリーからは、某栄富高校のバスが運行している。公共のバスも某栄富高校経由があり、学校までのアクセスが便利である。そこからは駐車場や家庭菜園なんかがある庭の奥に大きな平屋の住宅があり、それもだんだんと距離が開き、畑や果樹園、釣り堀なんかもあり、もう山の入り口かと思うようなところに、某栄富高校の門がある。
学校は自然を活かし、乗馬クラブだとか、木工だとか、自然体験だとかができ、近隣の幼稚園や小学校にも敷地内の施設を開放しており、地域とのつながりも深い。
実際、ボランティアなんかで花壇の手入れをしに来てくださる地域の方がいつも校内にいて、小さな流しがある生徒の休憩室には、クラスごとにマグカップを置く棚まであって、そこには、そうした地域の方ご自慢のおいしいお菓子や、採れたての果物なんかがご自由にどうぞ、と置いてある。
さらに、校内には地域猫やら、リクガメ、アヒルやらいて、定期的に馬術部の馬を診に来る獣医さんが、時折動物の様子を見に来てくれる。
限られた同世代以外に関わらぬ中学生だったユタカだが、この某栄富高校に入学し、自然とさまざまな世代や職業の人と接する機会が増えた。
特に花壇の手入れで来てくださる地域の方は、ユタカのようなあまり人懐こくない生徒にも、ごくごく自然に接してくれる。にこやかで、穏やかで、多くを話しかけぬが、あいさつや、差し入れをしてくれる。緊張気味に「ありがとうございます」と言うユタカと、「わあ、嬉しい!」と、明るく返す子とに、同じように「どうぞ」と言う。
そうした大人の人の見本とでもいうのか、なりたいと思える人間像というものを、ユタカはこの学校でまず学んだと思う。
ほかの生徒に比べれば、うまく交流できている方ではないが、それでもユタカなりにこの学校にも、ほかの年代の方にもなじんできたと感じる今日この頃である。
入学早々の行事では、簡単かと思って引き受けた係で、正座を学んだ。
背筋を伸ばし、穿いているものをお尻の下に敷いて、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか、軽く開く程度。足の親指同士が離れぬようにし、手は太もものつけ根と膝の間でハの字にそろえる。
まあ、この時限りのことだろうと思ったが、意外と正座の機会は多かった。
2
「なんで屋外研修にお茶?」とユタカは配布された行事予定を二度見した。
配布されたのは、予定表に加え、事前の医療相談のお知らせ、その時提出する体調、体質に関する細かな記入表が添付されている。入学してすぐの頃にも、似たような提出書類と検診はあったが、この学校はこうした飲食を伴う泊りがけ行事前には医療相談を全員が行うらしい。入学の時には、確かこの学校は希望者に給食があること、ボランティアの方が野菜やお菓子を差し入れしてくれる点、学校の環境と教育理念から校内には馬術部があり、保護猫やリクガメなどがいること、地域のボランティアの方の協力を得ている点も記されていた。某栄富高校は、生徒の保護者などからも、ボランティアへの協力は募集しており、一応無償ではなく、一律に謝礼は出ているのだそうだ。当初そうしたことをユタカは知らなかったが、知って、少し気が楽になったようなところもあった。善意でしていただいているとはいえ、一学生でお返しできることも浮かばず、いつもありがとうございます、と感謝するだけでいいのだろうか、と思っていたが、そうしたことが学校側と有志の方との間で納得できる状態であれば、感謝を伝え、勉強以外で教わる味覚や、見習いたい姿勢を一身に享受するまでである。
配布された行事予定は、研修のお知らせであった。
自然豊かなこの某栄富高校では、一年生は夏前に一泊二日の研修がある。
研修といっても、この学校が所有する校舎裏の山にあるキャンプ施設の調理場で自炊し、寝るのは校舎内の施設で男子が武道場、女子がトレーニングルーム、シャワーは学校の更衣室に併設されているものを使用という、かなり低予算なものである。それはよいのだが、自炊、片づけの後、シャワールームを一度に使えないための時間調整か、先にシャワーのクラスと、後にシャワーのクラスとが、それぞれの空き時間にお茶、とある。場所は和室。某栄富高校は一学年三クラスと少ないので、シャワー、身支度が済み次第各自布団受け取り、お茶、の三段階をクラスごとにスライド式に行うようだ。
まあ、学校によってはバスをチャーターして避暑地や観光地で研修を行うが、某栄富高校の場合はいつもより通学時間が遅く、スクールバスもそれに合わせて運行し、布団は学校がレンタルを手配、持って行くのは洗面用具とタオルに着替え、常備薬くらいで学校指定のスクールバッグに悠々と収まる。ジャージは学校のロッカーに入れてあるし、別の場所からの出発でもないので、いつもの定期だけで交通費の用意がないのも気楽だ。
だが、その中で、お茶……。
この日ユタカは学校の給食を頼まずに、弁当持参で休憩室にいた。
弁当を食べた後、ほかの生徒は地域猫と遊びに行ったり、職員室や図書室に行くと、早々に出て行き、ユタカだけがぼんやりと休憩室に残っていた。
そこへ、いつものように、ボランティアの札を提げたおばさんがやって来た。
そうして「よかったらどうぞ」と、輪切りレモンの何枚も入ったお茶の大きなボトルを置いた。
「いただきます」と、ユタカは棚からカップを出して、それを注ぐ。
冷たいのもあるが、とにかく美味しい。
「なんでこんなにおいしいんですか」と尋ねた。
おばさんはちょっと間を置いてユタカを見た。
ああ、こんなふうに質問をしたのは初めてだった、と気づく。
おばさんはにこやかに、「昔からの淹れ方で、レモンと黒糖と、濃いめに淹れた紅茶に氷を入れて作るからかしらね」と言う。
それから「知っていると思うけど、ここの学校のすぐそばに市で管理している湧き水があるでしょう? そこのお水を汲んで、それを使っているの」と続けた。
「湧き水、ですか」
「そう。知らない? ここの山の麓からの湧き水。市で管理しているから、安心して使えるし、おいしいのよ」
「へえ」とユタカは頷く。
湧き水を飲んだことがないと思っていたが、知らぬ間に、こうして振る舞っていただいたお茶で飲んでいたようだ。
「ほら、今度ある研修、そこでね、毎年新入生みんながここの湧き水を飲む機会をってことから、お茶の時間ができたらしいわよ」
「え、そうなんですか」
「ええ」とおばさんは頷き、「お茶、よかったらまだあるからね」とボトルを置いて、花壇の手入れに行った。
確かにこのお茶はおいしい。
でも、だったら、こうやってここで淹れてもらったのを飲むのでいいと思うんだけど……。
ひんやりしたテーブルにユタカは腕を伸ばし、顎をつけた。
そうして溜息をつき、椅子の上で正座をしてみた。
背筋を伸ばし、スカートも、ズボンももちろん尻の下に敷き、足の親指同士をつけ、膝はつけるか握りこぶしひとつ分開けるくらい、脇は締めるか軽く開く程度。
結構一度身に着けたことは忘れないものだ。
まあ、大丈夫だろう……。
3
そうして、研修の日がやって来た。
登校後、ジャージに着替え、釣りやアスレチック、木工など、各々に好きなことをやる。某栄富高校は一学年ごとの人数が百名と少ない。その少なさ故か、いつも誰と誰が一緒にいるといった構図がなく、性格や趣味の違いがあっても、わりと皆仲良く温和にやっている。だから、この自由な時間に何をするかは、誰かと相談することなく、やりたいことを選ぶ。
ユタカは木工を選んだ。
何をするかは当日に選んでよいということだったが、木工キットが足りなくなる場合はないのだろうか、と思っていた。そうしたら、その時は釣りかアスレチックかと考えていたところ、用意されていたのは、木工を行うログハウスにテーブルとイス、そうして適当な大きさに切った豊富な木材の入った箱と、工具、ボンドや、着色やニスを塗るための道具が置いてあった。みんな暫く材料の木材をあれこれ選び、決まると工具を手に作業に入る。ユタカも暫く材料を手に取り、いろいろ思案してから、作業に入った。学園長先生が様子を見に来て、「糸ノコを使いたい人は言ってくださいね」と言う。ユタカはその言葉に「学園長先生、ここ、糸ノコ使いたいんですけどいいですか」と尋ねた。
まだ作業を始めたばかりだが、学園長先生はユタカが何を作ろうとしているのか分かったようだった。
「実土利くん、これはお庭にでも置くんですか?」
「学園長先生、そのことなんですけど、これ、ここの森で使ってもらえますか?」
そう思い切って尋ねると、学園長先生はちょっと細い目を見開き、それからじんわりと笑った。
「ええ、ぜひ」
作業中の生徒が「実土利くん、何作ってるの?」と訊く。
「小鳥の巣箱」
「へえ、ここにうってつけだね」
「これから小鳥も卵を温める時期ですからね」と学園長先生が言う。
そして、「じゃあ、設置しやすいように、この上のところに紐をかけられるようにしていいですか? そうすると、ちょうどいい枝のある木にかけられますから」
「あ、はい、お願いします」
「仕上がったものに、後で私が設置できるよう手を加えて構いませんかね」
「ありがとうございます。お願いします」
そんなやり取りの後、ユタカはほかの生徒の制作を見遣る。
「そっちは何?」
「ティッシュケース」
「ペン立て」
「学園長先生、ティッシュケースの真ん中のとこ、糸ノコ使わせてください」
そんな会話をしながら、だんだんと距離が近づく。
友達というほどではないが、外で会えば軽くあいさつするくらいの間柄だ。
ユタカは友達をたくさん作りたいと強く希望していないが、こうした中での会話が、無理なく、優しく感じられる。
ユタカは着色の必要がないので、糸ノコで小鳥の入る部分を取ると、丁寧にやすりがけをし、後は釘打ちと木工用ボンドの接着で終わりだ。ボンドが乾く間、着色をするほかの生徒の様子を眺めていた。研修の一環の木工と軽く見ていたが、結構個性的で上手な仕上がりである。色を塗って乾かしたところに、油性マジックで躊躇いなく絵や文字を描いたり、見事なグラデーションの着色をしたりで、じっとその工程を見ていた。
「将来、こういう仕事をするの?」と真剣に訊くユタカに、「まさか。えー、褒められると少し考えるな」と答える生徒はなんだか嬉しそうで、そのうちに出身の中学とか、どうしてこの学校にしたかとかいう話もした。
着色した木工作品は明日の帰りに取りに来ることになっており、ユタカの作った巣箱は、明日の朝の山の散策の時間に学園長先生が設置してくださると言う。
近くのアスレチックからははしゃぐ声が聞こえて来るし、そのうちに学校の裏山を下った先にある渓流釣りに、担当の先生と出向いていた生徒たちが、釣った魚をクーラーボックスに入れて戻ってくる。川魚は昼食の時に塩焼きにするのだと言う。
某栄富高校は、場所柄と、一学年百名、全校で三百名ほどという人数から、希望者は事前予約で給食を食べる。給食を希望しない生徒は隣のソファのある部屋で、弁当や、朝買って来た昼食を摂る。この学校の給食はユタカも何度か食べたが、近くで採れた川魚とか、有機菜園で育てた野菜が頻繁に登場する。給食を頼んでいなくても、ソファのある部屋には流しもあり、そこにはボランティアで出入りしている地域の方が、自宅の畑で採れた果物や、差し入れなんかを提供してくださるので、そうした食材にはすっかり慣れていた。
今回の研修での昼食も、トマト、玉ねぎ、キャベツを使ったスープ、新じゃがをふかしてバターを溶かしたもの、ナスやピーマンも入ったスープカレー、炊いたごはん、チーズをたくさん載せて焼いた窯焼きのピザ、それに採れたての川魚の塩焼き。好きなものを選んで食べられるのも、この学校の良さだ。ごはんの横には、ラップ、おにぎりにして混ぜるふりかけや海苔が用意してある。
窯焼きのピザは、学園長先生の奥さんの得意料理だそうで、作り方を教わりたい生徒が集まる。
調理場で下ごしらえ、そしてそれぞれの料理をした。
それぞれ料理、といっても、普段作ってもらい、食べるばかりのユタカである。
ああ、何をしようと、始めはうろうろしていた。
てきぱきと動くクラスメイトに「あの、何か僕ができることある?」と訊くと、「スープカレーに入れる牛肉を今切ったところだから、フライパンで表面を焼いてくれる?」と役割が回ってきた。
早速取りかかったが、プライパンの油がコンロを点けるとすぐにはね始め、そこに大きなボウルいっぱいに入った厚めの牛肉を入れようと持つと、結構な重さで、両手で抱える。
「ここにトングあるから……、え、うわ」
牛肉を切るのに使ったビニールの調理用手袋を取ってこちらを見たクラスメイトの驚く声とほぼ同時に、フライパンにボウルに入っている牛肉を三分の一ほど重力に従い入れた。
当然のことながら油が更にはねる。
「うわ、あち」
フライパンに山盛りの牛肉は菜箸では到底太刀打ちできなかった。
慌てるユタカを見兼ね、「代わろうか?」とクラスの男子が申し出てくれる。
「え、あ、うん、ごめん」
うろたえながら後ろに下がると、まず火力を落とし、入れ過ぎた牛肉をトングでボウルに半分以上戻し、再び火力を上げると慣れた手つきでフライパンを振り、折を見て塩、コショウをする。それを大きなバッドに入れ、次を同じ要領で焼いていく。
やることがなくなり、野菜を切っている女子のところへ行った。
「あの、僕にできることあるかな。あんまり上手じゃないから自信ないんだけど」と言うと、「え、じゃあ、ふかす新じゃがが、ざるにあるから、それをよく洗ってくれるかな。それが終わったら、トマトは切れる?」
この中で、恐らく簡単な作業を割り振ってくれたようだ。
「ありがとう。頑張るよ」
「いや、そんなに頑張らなくてもできると思うけど……」
加減のわからぬユタカは、じゃがいもをぴかぴかに洗い上げ、「え、もう十分、十分」とほかのクラスの男子が「じゃあ、後はこっちでピーラーで芽を取ったりして、ふかしに持っていくから」と言うまでじゃがいもを洗い、その役目が終わると、トマトを切った。じゃがいもについてユタカができそうと判断されたのは、洗うところまでだったらしい。トマトは野菜スープに入れるものだから、かたちにそれほどこだわらなくていいと言ってもらえたのが、大層心強かった。
ユタカが肩に力を入れてこの二つの下ごしらえをしている間に、手際のいい同学年の生徒がどんどん動いてくれて、昼食が完成していく。後は調理器具を洗うくらいだ。
手を動かしながら、ユタカはここ最近の食事について考える。
手元のトマトを見ながら、そういえば、と思い出すことがあった。
この前流しの横に、大きなボウルに氷水を満たした中にたくさんのトマトが入っていて、『採れたてです。よかったらどうぞ』と小さなホワイトボードにボランティアの方の名前があった。体育の持久走の後で喉の渇いていたクラスメイトとともに、そのまま手に取っていただいた。ごくごくと何かを飲むのとはまた違った、身体の隅々に染みて、行き渡るような感覚が大層心地よかった。ただ、直接トマトを食べ慣れておらず、その対応を考えていなかったユタカは白い体操着をトマトで盛大に汚し、周囲は笑うのを暫し堪えていたが、結局大笑いし、体操着はユタカと似たような状態になった。
某栄富高校は普通科だが、こうした新鮮な食材をいただく機会が多く、その食育もかなりのものだとユタカは思う。食育とは少し違うだろうが、先述のトマトの件も、切ってお皿に盛ったものを食べている間は、まず起こらないことだろう。
調理器具を洗い終わると、「ああ、ごめんね、全部やらせちゃって」と、同じ学年の何人かが来て、拭くのを手伝ってくれた。それを仕舞に行ってくれると言うので、またやることがなくなり、テーブルを拭いているクラスメイトに気づき、ユタカもクラスメイトから離れた場所からテーブルを拭き始めた。
そこへ先生が水とコップを持って来た。
今、テーブルに等間隔で配置してあるペットボトルの水も、湧き水なのだろうか。
「先生、この水、学校のそばの湧き水ですか」と、ユタカは担任の先生に訊いてみる。
「水? 材料を頼んだ宅配サービスで一緒に買ったのだよ」
「え、あ、そうですか……」
先生は、「ピザ焼けたそうです。ほしい人はそっちに並んで」と声をかけに行った。
それぞれに片づけの済んだ生徒が、各々の料理の前に並び始める。
テーブル拭きを終えたユタカも、どうしようかなと思いながら、ちょっとあちこちを見てから、ピザの列に並んだ。
カットしたピザをお皿に入れてもらい、一度席に戻り、それから川魚の塩焼きとごはんをよそって戻る。
周囲の席では、スープカレーとピザを選んだり、自分でおにぎりを三つくらい作ったものと野菜スープにしたり、スープカレーにごはんを入れたりと、いろいろな食べ方をしていた。
「ピザおいしい?」と隣の席のクラスメイトに訊かれ、「うん、このちょっとへりが焦げてるところとか、すごくおいしいよ」と答えると、「もらって来よう」と席を立つ。
「ピザはこれからまだ焼きますから」という学園長先生の奥さんの嬉しそうな声がする。
そんなに食事で張り切らないユタカだが、隣の席のクラスメイトの食べ方がおいしそうで、スープカレーにごはんを入れに行き、その後、新たに焼けたピザをもらいに並んだ。
クラスメイトの女子が「あれ、実土利くん、新じゃがや野菜スープは? 自分で作ったもの、全然食べてないじゃん」と声をかける。
「え、ああ、そうなんだけど。みんなが作ってるのを見たカレーとか、ピザがおいしそうで、そっちでもう十分かなって」と答える。
「え、さっき新じゃが、バター載せて食べたけど、最高だったよ。野菜スープも薄味だけど、野菜の味がしっかり出てて、おいしいよ。身体にもよさそう」
何気ない話なのだろうが、本当に同学年とは思えぬほど、みんな会話力、対人関係を築くのに長けている。
ユタカはそれに応じるのに精いっぱいである。
きっとユタカがあまり交流を深めるのが得意でないのは、周囲もわかっていて、お互い無理のない話をするのだろう。
こうして接することをこの学校の同級生、否、上級生も先生もボランティアの方も、みんなが知っているようだ。なんとも歯がゆくもありがたいものだ。
まあ、ユタカが牛肉を焼くのに失敗したことについては、もう忘れているのか、敢えてふれないのかは、よくわからなかった。
こうして昼食を終え、後片付けをすると、もう夕刻である。
その後、クラス委員のくじ引きで、ユタカのクラスは最初にシャワー室、そして身支度に布団受け取り後、和室集合になった。つまりお茶の時間は学年で最後だ。
シャワーを終えて着替え、男子は寝る時に使う武道場、女子はトレーニングルームで布団を受け取り、敷く場所を決める。シャワーを終えて布団を受け取るだけならそれほど時間は必要ないが、実際のところは女子が髪を乾かしたりする身支度に充てられ、男子は自由時間のようなものだ。
もうお茶の時間を終え、シャワー待機のほかのクラスの男子によると、学園長先生の奥さんとボランティアの方がお茶を点ててくださるのだと言う。
お水はこの学校のそばにある山の湧き水を使って、それを沸かしてくれるのだそうだ。
小さめの和菓子の入った入れ物があって、そこからお茶をいただく前にひとつづつ取って食べていいのだとか。
本当はそこでも、懐紙というのが必要だったり、畳のへりを踏んではいけないとか、白い靴下でないといけないとか、まあ、いろいろと作法があるらしいが、今回はこの学校のそばの湧き水で淹れたお茶を、同じクラスの仲間といただく、ということが目的なのだという。
「でも、正座くらいはするんだよね」と誰かが訊いた。
「そうそう、そこはね」と教えてくれる。
……背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分ひらくくらい、脇は締めるか、軽く開く程度で。足の親指同士が離れぬように、手は太もものつけ根と膝の間にハの字で揃える。スカートはお尻の下に敷く。
こんな感じか、とユタカがやると、「すげえ、実土利くん、準備万端じゃん」と、周囲にいた同じクラスや、ほかのもうお茶を終えたクラスの男子が笑う。
「そんなんじゃないけど……」
「実土利くんには、もっと自分ができることとか、好きなこととか、言ってほしいよ」
「まあ、実土利くんのそういうところもいいところだとは思うんだけどね」
「せっかく同じ学校になったし、これから先、同窓会とか、クラス会があったとして、全員集まれるかはまだわからないしさ。今回の研修、全員参加してるんだって。そういう機会っていうのもあるしさ」
今、ここにいるメンバーは、確か一人は馬術部で大会にも出ていると言う。それと、手話ができるクラスメイトと、今日川魚を釣ったクラスメイト。
それぞれにできること、大切にしていることがある……。
自分ができることは、とユタカは考える。
4
クラス委員が武道場にやって来て、「女子の用意終わったってさ。和室に集合」と声をかけてくれた。
和室に行くと、それぞれの私服に、髪をきれいに整えた女子がもう正座をして待機していた。
女子は事前に担任の先生に教わったのか、膝をつけ、背筋を伸ばし、手を太ももと膝の間でハの字に揃え、穿いているものをお尻の下に敷き、足の親指同士をつけている。
座敷に入った来た男子も、さっきのユタカの正座を参考にしており、担任の先生が「なんだ、もうできてるな」と言う。
「実土利くんが教えてくれました」と、誰かが言い、「そうか、実土利くんいい先生だね」と、担任の先生が言う。
本来なら制服で臨むような場だが、ここは某栄富高校ということか。
それでも皆、リラックスできる部屋着でも正座の姿勢は美しい。
ユタカは学校が始まって早々、お茶の席の助手をしたので、おおよその様子はわかるが、やはり新鮮な気がする。
「みなさん、今日はどうでしたか? お昼はおいしくいただけましたか」と、学園長先生の奥さんがやって来た。それに続き、以前ボランティアでお茶の先生をしてくださったユタカの顔見知りのおばさんと、そのお仲間というおばさんたちが「こんばんは」とやって来る。
お茶のお道具の横に大きなボトルに入っている水があって、今度のは湧き水なんだろうな、とユタカは思う。確かそのためのお茶の席なのだが、どうにもお茶の席という不慣れた方に気がいく。それを用意してある窯で温め、器を丁寧にふいていく。ひとつひとつの動作にどのような意味が込められているのかはわからぬが、美しい所作であった。
「それでは、お茶を点てますね。みなさん、このお菓子を召し上がっていてくださいね」
そう言って、向かい合って座っている三十名の前に、学園長先生の奥さんらが手分けして、五人にひとつくらいの割合で、小さな黒い箱を置く。
顔を見合わせながら蓋を開けると、小さな餅菓子が入っていた。
一日の大半を外で過ごし、疲れた身体に甘い小さな和菓子は顔がほころぶようなおいしさだ。
その間に、学園長先生の奥さんたちがそれぞれにお茶を点てる。
手際よく、きめ細かい動きだった。
そうして、どうぞ、とそれぞれの前に出してくださる器のお茶を、いただく。
和室がとても静謐な空間になる。
苦くてさぞかし飲みにくいのだろうと思ったが、全くそんなことはなかった。
お茶というのはこんなにおいしいものなのか……。
ほっとした雰囲気が漂う。
ああ、この時間を持つための研修だったのかも知れない、とユタカは思った。
多くを話さないが、なんとなく、通じるものがクラスの中にあって、実際のところはわからないけれど、困ったことがあったら、ここにいる仲間に話せそうな気がした。
5
夕飯は、近所のお弁当屋さんで注文したものを、給食を食べる広い食堂で一学年全員でいただいた。
大きなハンバーグやエビフライ、目玉焼きにスパゲッティ、ぎっしり入った白米。
学園長先生も、奥さんも、先ほどお茶を点ててくださったおばさんたちも、嬉しそうにそれを食べている。今思えば、学園長先生の奥さんと、あの先生たちは三クラス分のお茶を点てて、それももちろんあるが、その間、ほぼ正座をしていたことになる。お茶の所作はよくわからぬが、とても整い、美しかった。そうして正座もまったく崩れてはいない。足の親指同士はもちろん、背筋を伸ばし、膝をつけ、穿いているものもきれいにお尻の下に敷いていた……。
誰かが、「学園長先生、いつも野菜中心だと思ってたけど、こういうのも好きなんですね」と話しかけると、「ああ、大好きですよ。僕がね、学生の頃からあるお弁当屋さんで、ぜひみんなにも食べてほしいと思ってね。だけど、みんなが通学する時間には、ここのお弁当屋さんは開いてないから、こういう機会にと思って、高校生がおなかいっぱいになるメニューで頼んだんですよ。どうですか?」と言う。
「今度帰りに家族にも買って行ってあげたいです」と言う生徒に、「ああ、じゃあ、先に予約しておくと、待たないで受け取れますよ」と言う。
有機野菜に川魚、湧き水で点てるお茶、と思ったら、思い切り高カロリーのお弁当。
学園長先生についても知る機会であった。
6
翌朝は早朝に学校の敷地である山の散策をした。
もう半袖でいい時期だと思ったが、ひんやりした空気で、腰に巻いていたジャージの上着を羽織る。
小鳥を身近で見たり、朝露に濡れた樹木の匂いが鼻腔を満たしたり、踏みしめる腐葉土がとても柔らかかったり、いつもすぐ横の校舎にいるのに、まるで別の場所のようだった。
散策の途中、学園長先生が「実土利くん、巣箱はここに設置したいと思うけど、どうかな?」とわざわざ聞いてくださる。
「あ、はい。お願いします」とユタカは頭を下げた。
「実土利くんの作ってくれた家に入るのは、どんな鳥でしょうね。ムクドリ、シジュウカラ、ほかは……。楽しみですね」
「学園長先生、スズメはどうですか?」
「そうですね。スズメにもいい大きさですね。ただまあ、山の中ですからねえ、どうですかねえ」
穏やかな学園長先生の声と、楽し気な生徒たちの明るい声との話題の中に、自分の作ったものがあることが、ユタカにはこそばゆかった。
そうして散策から戻ると、手を洗い、各自で昨日の昼同様に自炊開始である。
朝食は昨日の昼食作りをしたキャンプ場にある調理場に移動し、屋根の下、ごはんを炊き、葉物や根菜類の入った味噌汁を作り、卵をゆで、フランクフルトを鉄板で焼いた。クーラーボックスからヨーグルトを出し、バナナとともに配布する。前日のことがあったので、ユタカは率先して、テーブル拭きとバナナ、ヨーグルトの配布をやった。
それらをいただき、片づけを終えると、研修は終了。
解散だ。
時間はまだ十時半。
スクールバスを降り、駅に向かうと、「実土利くん、この後ちょっと遊んでいこうってみんなが言ってるんだけど、どう?」と声をかけられた。
同じクラスだけでなく、昨日武道場で少し話したメンバーだった。
いつもなら、断っていたかも知れない。
けれど、自然に「うん」とユタカは返事をしていた。
「で、どこに行くの?」と訊くと、「今出てるのが、猫カフェ、カラオケ、ラーメン屋、ボウリングなんだけど」と言う。
どれがいいか……。
まあ、どれでもいい。
投げやりなのではなく、この顔ぶれなら、それぞれに楽しそうだ、とユタカは思った。