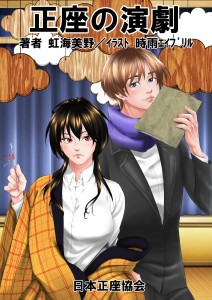[223]正座のホームステイ
 タイトル:正座のホームステイ
タイトル:正座のホームステイ
発行日:2022/04/01
シリーズ名:某学校シリーズ
シリーズ番号:21
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:52
販売価格:200円
著者:虹海 美野
イラスト:時雨エイプリル
内容
某善位高校(ぼういいこうこう)普通科一年の味子(あじこ)の家に留学生、ミアがホームステイすることになった。
ミアは大人しい感じの女の子だが、自身の意見を授業中にハッキリと言い、クラスの姿勢を前向きに変える。
一方でなかなかミアと打ち解けられない味子と、日本食に不慣れなミア。
しかし、ミアは正座の仕方を学びたがり、日本の漫画や映画にも興味を示した。
翌日、日本料理店を営む祖父宅で、ミアの歓迎会が行われ……。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/3762956
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止します。
1
某善位高校は、多くの専攻学科があり、その専門的な設備を整え、一学年で軽く二千人を超える大規模な学校である。
その某善位高校の普通科一年に在籍する、正向味子は、至極普通の女子高生だ。
そんな味子に、毎年恒例で迎える数人の留学生のうちの一人のホームステイ先として白羽の矢が立ったのは、味子の母、さらの実家が味子一家の住まいのほど近くにある老舗の地元では有名な日本料理店という点にあった。
もちろん入学時に、学校内での広報撮影の際に生徒が写ることに始まり、大人数の学校故、運営を円滑に行うための事前書類内に、留学生の家庭での受け入れを希望するか否かの欄があり、正向家では両親が、まあ、来てもらえるのであれば、というくらいの考えで、『希望する』を丸で囲って提出した経緯がある。しかし、入学して一ヶ月が経過し、その間に、運動部の都大会の応援に出向いていた味子は、すっかりそのことを忘れていた。つい先日の土曜日にも、女子バスケ部の大会に、学校で配布された応援グッズを持って行ってきたばかりである。さまざまな分野で将来有望な生徒が多数在籍する某善位高校では、一般の生徒の応援も日常化しており、事前に応援に参加できるかの、いわば出欠確認を行い、この参加も生活態度のひとつの目安になるらしい。当初はやや面倒な気もしたし、部活のある子は堂々と欠席します、と言えるあたりが羨ましく思えたが、親しくなりかけの友達と駅で待ち合わせをし、普段は廊下でもすれ違うかどうか、というくらい接点のないスポーツ特待生の活躍を間近で見て応援し、帰りにちょっと洒落たお店でランチをして帰って来るというのも楽しくなってきた頃だった。
生徒が多すぎるので体育館ではなく、教室ごとにテレビ画面に映し出された校長先生の話を聞く朝礼の後、味子は担任に封筒に入った書類を渡された。
何だろうと思ったら、ホームステイのお願い、と書いてある。
親に渡す前に、味子はざっとその内容を見た。
簡単に言えば、一週間、学校で過ごす以外の時間を味子の家で留学生をお預かりする、という内容だ。
留学生は、オーストラリア在住の十五才の女の子で、ファーストネームはミア。
顔写真はなかったが、味子にとって、書面で知る数少ない情報から想像するのは、きらきらとした、ネットで見る海外映画に出て来るハイティーンだった。
あいさつは、教室にいる仲間に後ろから「ハアイ」という声かけ。仲間内で、少し前方にいる同じようにきらきらした男の子に視線を送り、その男の子が振り返って、「やあ」と片手を上げ、「今度の日曜、何してる?」、なんて訊いたりして……。
きゃー、と一人興奮する味子だったが、ここは日本の高校で、オーストラリアでキラッキラのスクールライフを送るハイティーンには、あまりにそぐわない地味な場所に思えた。
否、日本のこの高校だって、キラッキラの時間の中にいる人はいるが、まず自分は除外だ。
おまけに、キラッキラのハイティーンの自宅というのは、偶然帰りが一緒になった友達が突然訪れても、広い住まいはソファセットとダイニングのおしゃれなテーブルのセットが配置されていて、テーブルには花なんかが飾ってあって、ソファには品のあるクッションが無造作に置いてあって、何一つ不都合なものはない。決して、玄関に翌日に出す雑誌の束が置いてあったり、テーブルに新聞やお菓子や飲みかけのペットボトルなど放置されておらず、取り込んだ洗濯物の家族みんなのパンツなんかが山積みになっていることなどない。
味子は思わずその場に座り込んだ。
一週間……。
短いようでいて、そこそこに長い期間である。
例えば友達が二、三時間遊びに来るのであれば、居間と自分の部屋をざっと片付けておけばいい話だ。
実際にそういった時、味子は両開きのクローゼットに、ベッドや床に散らばっている衣類をまとめて放り込んで、さもいつもきれいにしています、という顔で友達を招き入れていた。しかし、一週間となれば、ずっとクローゼットを開けないわけにはいかない。いずれ、丸まった衣類の山が転がり出てくるところを目撃されるだろう……。
嗚呼、どうしたものか、と味子は困った。
困って、帰宅した後、夕飯を作っている母、さらに書類を手に、どうしたものかと言ってみた。
母、さらは、フライパンをかき混ぜる菜箸を一瞬止め、「片付けましょう」と笑顔で言った。
母、さらの実家は老舗の日本料理店で、個室がいくつもあり、日本庭園には年に何度か古い付き合いになる造園会社に入ってもらっている、いわば格式高い店である。ランチと夜のコースがあり、お祝い事や、会食で予約が埋まることが多く、客室には年代ものの掛け軸や壺が置かれ、花器に生けた花が飾られている。そんな老舗の店は現在、母、さらの兄、大器伯父が引き継いでいるが、祖父は調理場で、祖母は客室係りでかくしゃくと働いている。そんな家で育った母は、それなりに厳しいしつけをされて育ったと言っている。
朝食は全員がきちんと正座をし、それでも、背筋が伸びていないとか、スカートが広げられていてお尻の下に敷かれていないとか、そんなことを注意され、ようやくそれが整うと、父の「いただきます」の合掌に倣い、父が箸をつけた後に食事が始まるのだという。
通常であれば、それを母さらが引き継ぎ、子どもたちにもそれを教えそうなものだが、長女の箸子伯母、長男の大器伯父、と二人の姉兄の後に生まれた母さらは、厳しくしつけられる二人を見て育ったため、守るべきしつけは身につけはしたが、息の抜き方も心得ていた。その結果、といっては何だが、箸子伯母は現在高校で歴史の教師をしているが、調理師免許を取っているし、大器伯父も高校で調理科に進み、十代の頃に店の調理場で働き出したのに対し、母さらはたまに実家に顔を出すついでに店を手伝いはするが、調理に関しては全くの素人である。本人曰く、米研ぎと味噌汁作りは子どもの頃から自発的にやっていた、ということだが、ほかのおかずは良くも悪くもない、と味子は思う。たまに祖父母宅に遊びに行き、そこで落ち合った箸子伯母が何かを作ってくれることがあって、「何がいい?」と訊かれると、味子は「卵焼き」、「煮物」と答えることが多かった。箸子伯母は、「味子ちゃんは、おいしいものをよくわかっている子ね」と、いつも味子を褒めて、丁寧に出汁を取り、その様子を味子は横から見ていたものだ。
おまけに、結婚を機に家を出て、親の監視下から卒業した母さらは、片付けということに全く重きを置かなくなった。
実家では考えられなかった、寝転がりながらテレビを見て、お菓子の入った袋に直接手を突っ込んで食べ、時々は、そのまま眠る、ということをしている。母さらにとって、それが最高の贅沢なのだと言う。
要するに、学校側としては、由緒正しき日本の姿をオーストラリアからはるばるやって来る学生に見てもらおうという期待から味子の家を選択したが、とんだ誤算だった、ということだ。それが白日のもとに晒される前に、何とかしよう、否、何とかしなければならない、というささやかな危機に正向家は直面していた。
2
正向家がそれから、留学生、ミアが来る前に準備したのは、食器一式、それに学校へ持って行くランチボックス、客用布団だった。それに加え、トイレや洗面所にかけてあったタオル、スリッパを新調した。室内の片付けもこの際しようということになったが、ここまで捨てなかったものには、正向家の家族それぞれの理由があって、それを聞いていると、全く片付けは進まなかった。この漫画、随分読んでいないから捨ててもいいんじゃない? と誰かが本棚に手をかければ、「それ、感動する場面があるから駄目」だと誰かが止めに入り、「このDVDの山、片付けてよ」と誰かが言えば、その場に座って一枚一枚を確認し始め、「あ、これここにあったんだ。後で観よう」と言い出す始末だった。仕方がない、ここは私たちの家で、ここにある物は家族の誰かしらが大事にしている物なのだから、という結論に達した。つまり、片付けは挫折に終わり、新調した物と入れ替えに捨てればいいと思われたタオルやスリッパすらも、「何かあった時に使えるでしょう」と、もともと定員ぎりぎりの収納棚に押し込んだので、捨てたもの、手放したものは皆無だった。
ただ、一応、正向家としては、家にあるものを改めて見直したので、崩れかけたDVDの山が三つに分けて置き直されたり、漫画が入ったままだった本棚の埃を払ったり、ということはした。味子の部屋に散らかっている物は箱に入れ、一時的に和室の隅に置くことにした。
こうして留学生、ミアを迎える日がやって来た。
ミアは、担任とともに、転校生のように朝の教室にやって来た。
ミアは濃い茶色の髪と目をしていて、背はそれほど高くなく、ほっそりとした女の子だった。
すごく大きなジェスチャーで笑いの絶えない子を想像していた味子は、自分にとっては親しみやすい感じの子だと勝手に思った。
自己紹介をミアは日本語でした。
味子の通う高校の子は大抵英検準二級くらいは中学生の間に取得しているし、文系の特進コースの子になれば、幼稚園の頃から英会話教室に通っているとか、帰国子女であるとかいう子が珍しくなかった。だから、英語での自己紹介でも簡単な内容であればわかるのだが、助詞がやや拙いミアの自己紹介は心にしみた。また、ミアは控えめに「日本の漫画が興味あります」と趣味について触れた。
温かい拍手で迎えられたミアは、留学生用の教卓斜め向かいの一列目の席に着いた。
そうして授業は開始されたが、控えめな子だと思われていたミアは、積極的な授業態度でその印象を一変させた。
教師の問いかけにも、ほぼ無言の教室で、真っ先に答えるのがミアだった。
政治経済の時間には、ミアの意見が貴重だと教師が、いつもの内容を変更し、国際情勢について意見交換の時間を設けた。
初めはうつむいていた生徒が、ミアの発言から、政治経済を教科のひとつ、テレビニュースで語られる一方通行の世界から、ごく身近なものだと意識し始め、ぽつり、ぽつりと発言した。
味子自身も、受験で勉強した歴史というのが、こういう話し合いの時にいかに必要であるかを知ったのだった。
そしてもうひとつ、ミアは、周囲の反応というのをあまり恐れていない気がした。
ミアについてはまだ知らないことばかりなので、実際のところはわからないが、自分の意見を述べるミアは堂々として、周囲の反応を見て匙加減をするような様子は見られなかった。小柄でも、真っすぐ背筋を伸ばし、拙い日本語ながら、はっきりと自分の考えを述べる姿に、味子は感銘を受けた。ああ、同じ年の女の子でも、この世界にはこんなにも自信を持って思ったことを言う子がいるんだ、と。味子自身、まだ学校生活が始まったばかりとあり、周囲は仲良くしつつも、この先も仲良くできるようにと慎重に、そして臆病になっていた。その突破口のようにミアは現れた。
この日のランチは、クラス委員の二人が付き添って、学食へミアを連れて行った。
大きな学校故、学食も広いが、試合前で練習に忙しいスポーツ推薦のクラスの生徒専用の席や、教員のための席は用意されていて、ミアもこの日は来賓用の席を使えたらしい。
しかし、翌日からは一般生徒と同じ扱いだ。
一般の生徒はもちろん、各自で席を確保する。
その競争がなかなかのもので、味子は最初の日にすでに音を上げてしまい、弁当持参で教室で食べるようになった。
たまに学食に行きたい時には、早めに授業が終わり、確実に席を取れる日を選び、友達と事前に約束して、弁当を持って行かないようにしている。
昼食後、この日は二限の授業で終わった。
特進クラスになると、昼食後も三限まで、つまり午前の授業と合わせて七限あるのが通常で、スポーツ推薦のクラスの子は寮生活を送っているので、校内はまだまだ騒がしい時間帯であった。
それまでミアに付き添っていたクラス委員が味子のところへやって来て、ミアと味子を引き合わせ、帰って行った。
本来なら、朝ミアが教室に入って最初の授業が終わった後に味子から声をかけるべきだったが、なんとなくその機会を逃していた。
ミアの背負っていた大きなリュックと通学用のバッグを見た味子は、「アイ ハブ ラゲッジ」とミアの荷物を持つように言ったが、ミアは「イッツ マイ オウン」と、私のだから大丈夫というような趣旨のことを言って、笑顔でそれを断った。本場の英語は、味子が普段授業で聞くのとは違い、また週に一度来てくれる外国人の英語の先生のようにゆっくり話すわけではないので、聞き取り、その意味を呑み込むのに、短い会話でも少し時間がかかった。
弱気になった味子は、「ヒア」と、家の方向はこっちという意図で時々行先を示し、自宅まで言葉少なにミアと連れ立って歩き、これから一週間もどうしようと途方に暮れた気持ちになった。
3
自宅に戻ると、母、さらが笑顔で迎えてくれた。
いつもは味子が帰って来ても、奥の部屋から声だけ「おかえり」と言う、ちょっと横着な母であるが、この日は母なりの小ぎれいな装いで、部屋も物は片付けられなかったが、掃除は隅々までしたあとが見て取れた。
そして、母は「ウェルカム テイク ユア タイム」とミアにようこそ、ゆっくりしていってね、と、中学校の時に教科書を読むような発音で歓迎の言葉を伝え、さりげなく荷物を受け取り、味子の部屋に運んだ。
「ウォッシュ、ハンド」、と味子は両手を広げてミアに見せ、洗面所へ促した。
味子の言葉少なでやや無理をした笑顔を感じ取ったのか、ミアは「サンキュー」と、最小限のお礼を言うに留めていた。
味子の部屋に行くまでの間も、最小限の会話しかできなかった。
その気詰まりを一気に押し流すように、インターフォンが鳴ってすぐに母と伯母、箸子の楽し気な声が聞こえてきた。
どうやら、ミアの歓迎会の食事の助っ人に来てくれたらしい。
「あら、まだこの雑誌片付けてないの」と言う箸子伯母と、「これはうちの大事なインテリアだから」と言い返し、「店の壺と同じ。お姉ちゃん、お父さんにこの壺古いのにまだ捨てないのって言わないでしょ」と続け、「それ、お父さんに言ってごらん」という箸子伯母が言うのが聞こえた。
「マイ、アント、ハシコ」と、味子は片言の英語でミアに伝えた。
荷ほどきを始めたミアは顔を上げ、居間の方を見ている。
「ゴー?」と、早くもきちんとした英会話を諦めた味子が短く訊くと、ミアは頷いた。
箸子伯母は高校の歴史の教師であるが、勤勉な人であるため、英語も現役学生の味子よりよほど達者で、ミアととても国際的でフレンドリーなやり取りを始めた。
二人の会話を傍で聞いていると、結構味子が中学校で勉強した文法が多く活用されている。
へえ、そうやって話すのか、と感心しながら、端々は理解できる二人の会話に耳を傾けていた。
その会話の中に、耳慣れた日本の作品が次々に登場し始め、箸子伯母がそれを受け、部屋の隅に積んであるDVDや本棚の本を指した。
ミアは一気に顔を輝かせ、それらを見て、「アメイジング」と繰り返した。
なんだかわからないけど、家にいる時にそれらを好きに見ていいよ、というふうに味子や味子の母が簡単な英語で説明すると、ミアは味子と味子の母を順に熱くハグした。
……片付けられなかった漫画やDVDがこんなに役立つ日が来るとは、と味子も味子の母も、そして伯母の箸子も面食らった。
食事は、残念ながら、箸子伯母の作ったちらし寿司や煮物はあまりミアには合わなかったようだ。
一応口にはしたが、味子の母が作った牛肉を焼いて市販のソースをかけたものや、果物を一口大に切って出したものをミアは好んだ。
そしてふと、ミアは箸子伯母の座り方を尋ねた。
ワット・・・・・・、と最初の単語しか味子には聞き取れなかったが、ミアは、その座り方はなんですか、というふうに訊いたらしい。
箸子伯母は、これは正座です、というふうに説明した。
さすがに箸子伯母の発音で「ディス イズ セイザ」は理解できた。
その後、箸子伯母は、英語を交えて、正座の指導をした。
「背筋は真っすぐ。膝はつけるか、にぎりこぶし一つ分開くくらいで。親指同士は離れないように。手は太ももと膝の間にハの字で。脇は軽く開くか、閉じて」ということを伝えるが、これはなかなかに難しい指導だった。さすがに箸子伯母も「背筋」という言葉がわからなかったり、「親指同士離れないように」というのを伝える際には、箸子伯母が正座をし、自分の足の親指をつけて見本を示していた。
おまけに小柄ではあるけれど、真っすぐな膝の、脚の長いミアが初めての正座をするのである。
ハの字というのも、箸子伯母が手を添えて教えていた。
「ドント オーバー ドゥー イット」と、無理はしないで、と加え、ミアは足を崩したが、大層日本のお作法に興味を持ったらしく、箸の持ち方や、日本の食事作法についても知りたがった。
来日前に一応日本の作法は学んだというが、それは玄関で靴を脱ぐとか、お風呂の湯船に入る前にかけ湯をするとか、そういった初めて触れる日本の生活文化に於いて止まりで、そこから先は日本で見て学ぼうと思っていた、ということだった。
それを聞いた箸子伯母は、お箸の持ち方や、汁物のいただき方など、自身が見本を見せ、細かに教えていた。
言葉や文化の違いから、なかなか箸子伯母も大変そうではあったが、楽しそうでもあり、本当にこの人は、誰かに何かを教える、尽くすということが好きなのだと味子は思った。
その後ネットでミアの家族と、味子一家、箸子伯母は対面し、短い自己紹介と交流を果たした。
味子の母は、事前に調べて書いておいた英文を出し、「アイ ウィル テイク グッド ケア オフ ミア」と読んだ。
恥ずかしいくらいの本来の英会話とはかけ離れた発音だったが、ミアを大切にお預かりします、という母の言葉が伝わると、「よろしくお願いします」と、ミアの両親はぎこちない日本語で応えてくれた。
ミアとそれぞれに似たところのあるミアの両親は、大きなソファに並んで座り、温かく、しっかりとした眼差しをミアに向ける。
……もし、私が単身でこのおうちにホームステイすることになったら、と考えると、味子は全くもって自信が持てない。
ここまで来て、初対面の子の家でその家族と食事をし、一週間寝泊りすることを含めて日本に学びに来たミアの向上心と勇気を味子は今更ながらに思った。
4
翌日、母が味子とミアに持たせてくれたお弁当は、いつもと違い、サンドウィッチとサラダ、果物だった。
サラダの入った新しいランチボックスと、お箸、フォークとスプーンの入ったセット、そしてランチバッグにミアは感激し、「クール!」を連発した。
そして、味子といつも一緒にお弁当を食べている子のランチボックスを見て、ごはんにおかず、彩りの野菜の入っているのがオーソドックスな日本のお弁当なのか、と尋ねた。
友達が頷き合って答え、ミアに食べやすく、味子のママがサンドウィッチのお弁当にしてくれたのではないか、と言うと、ミアは「ありがとう」と何度もお礼を言い、目の端を拭った。
「慣れてきたら、ごはんのお弁当にする? でも無理はしないでね。時々、うちはサンドウィチの日があるから」と味子が説明すると、全ての意味は分からなくとも意図は読み取れたミアは大きく頷いた。
「大丈夫かどうか、ちょっと食べてみる?」と味子の友達が、お弁当の蓋に卵焼きを置き、もう一人の友達がアスパラの豚肉巻を置いた。
「いただきます」とミアは箸子伯母に教わった通りに丁寧に合掌すると、それらを食べ、「おいしい」と頷いた。
「じゃあ、明日のおかずは、卵焼きとアスパラの豚肉巻で頼むね」と味子が言うと、ミアは「ありがとう」と笑った。
この日、味子は帰宅前に祖父母宅に寄った。
「グランパ、グランマ、ハウス」と家を差す。
「アメイジング!」とミアは目を輝かせた。
味子の祖父宅は日本料理店の隣にある。その自宅も、店同様の立派な日本家屋である。
シャッターつきの門の上には手入れされた松が枝を広げ、庭に入れば、桜や橘、ツツジ、紅葉が植えられ、玄関まではきれいに刈られた芝と隔てられた白い砂利道だ。 今日は店の定休日で、箸子伯母、大器伯父の家族、祖父母とが集まり、ミアの歓迎会を行う予定だ。
もう味子の母も来ていて、箸子伯母の旦那さんである伯父と、味子の父は仕事が終わったら来ることになっている。
門をくぐったところで、後ろから賑やかな声が聞こえてきた。
「漆ちゃん、そのアメリカの子って英語で話すの?」
「間場さん、先生、オーストラリアって言ってたよ。しかもこれ、三回目」
「ああ、そうだっけ?」
その声とともに、シャッターの門の横、手で開ける戸が乱暴に開けられる。
そこにいたのは、箸子伯母と、黒いズボンに白いポロシャツの男子高校生と、膝上二十センチくらいの短い黒のスカートにだぼだぼの半そでのパーカーを着た女子校生と思しき女の子がいた。女の子の半そでパーカーはサーモンピンクで、パーカーの紐の先についた大きなポンポンと中央のポケット、裾の部分がスカイブルーだった。ソックスは何かのブランドでピンクに白い横線の入ったもので、スニーカーはハイカットのイエローだった。なんとも騒々しい服装で、味子の高校なら門で足止め間違いなしだ。状況的に箸子伯母の生徒と思われた。箸子伯母の勤務する高校は、某出井高校と聞いている。実際に行ったことはないが、こうしてみると、あんまり関わりたくないと正直思う。しかし、ミアは「クール!」と目を輝かせた。そして、どういうわけか、味子より全然英語のできなさそうな、この派手な身なりで、味子の伯母を「漆ちゃん」と呼ぶ(多分、伯母が結婚後変わった名字の漆左からきているのだろう)子と、ミアはあっという間に打ち解けてしまったのだった。この日、歓迎会の料理は祖父と大器伯父とが店の厨房で用意してくるので、その前にミアは今日のお礼にと、ミートパイとパブロバというデザートを振る舞いたいと言い、その材料を買ってから行こうかと話していたところ、箸子伯母が、勤務先の高校から祖父母宅までの間にお店で懇意にしている農園と、品ぞろえのいいスーパーがあるのでそこで調達してきてくれる、と申し出てくれていたのだった。その買い物に同行してくれたのが、箸子伯母が紹介してくれた、丁太君と、宝ちゃんなのだそうだ。
広い祖父母宅に入ると、早速一同は手を洗い、ミアの料理が始まった。
宝はごく自然にミアを手伝っている。
今日は家族がたくさん集まるし、ミアの料理も手伝うから、無理をしないことにしようと、味子は自動翻訳を用意していた。
しかし、そうした構えもなく、初対面で英語力も味子よりかなりなさそうな宝がすぐにミアとの距離を縮めた。
ミアが、まずデザートのパブロバのメレンゲを作ってオーブンで焼くというようなことを言うと、宝は味子の祖父母の家であるにも関わらず、すぐにボールを出し、「漆ちゃん、ハンドミキサー、この家にある?」と訊いている。箸子伯母も、「ええと、確か、そこの棚の下にジューサーなんかと一緒にあったと思うけど」と言っている間に宝は、「ああ、これね」とミキサーを出して、準備を進めている。
宝は、味子の印象とは違い、実に手際がよく、ミアに先にオーブンを温めておこうかと身振りで確認し、メレンゲをオーブンで焼いている間にミートパイを作るのかと確認していた。
なんとなく手持無沙汰になった味子に、「なんか、図々しくてすみません」と小声でそっと言ったのは、丁太だった。
驚いた味子に、「間場さん、ちょっと自由すぎる感じがするけど、あれで結構優しくて、いい子なんだ」と言う。
味子は「いえ、そんな。手伝ってもらって……」と、曖昧に首を横に振った。
二人は付き合っているのか、とふいに思ったが、なんとなく訊いてはいけないような気がして、温かい眼差しを宝に向ける丁太を味子は黙って見ていた。
メレンゲはあっという間にでき、オーブンに入った。
宝は「ミア、パイの型、ここ。オーケー?」と、メレンゲ作りで使った調理器具を洗っているミアに、パイの型を出したことを伝え、それからエプロンを取ると、「ちょっと疲れたから、交代してもらっていい? 味ちゃん」とぽん、とエプロンを味子に渡した。
あ、本当だ、と味子は思った。
ミアがここで馴染むところまで付き合い、そこからはいつも一緒の味子のポジションだと考えていたのだろう。
「すごく、宝さんのこと、わかっているんですね。私もミアのこと、少しの間だけど、わかるように頑張ります」と味子は言い、照れて、何を言ったらいいか困っている丁太に軽く会釈をし、味子はエプロンをしてミアの方へ行った。
宝は、「漆ちゃん、そろそろおじいちゃんのとこのご飯、運びに行く?」と声をかけ、丁太も「じゃあ、俺も行きます」と宝の後に続く。
味子はミアの隣に並ぶと、ミアがパイの中身を作っているところだった。
味子はメレンゲを焼いているオーブンを覗いた後、もうひとつのオーブンの温度を上げておくか、ミアにオーブンのスイッチを示し、訊いた。キッチンを新しくした祖父の家は、もともとある古いオーブンのほかにビルトイン式のオーブンもあるので、料理の同時進行がとてもやりやすかった。
フライパンでパイの中身を煮込むのに時間がかかるというので、その間に、メレンゲに飾るいちごやブルーベリーを袋から出して洗い、いちごをカットする。
ミートパイの中身が出来、それをパイに流し込んで、温めておいたビルトイン式のオーブンに入れる。
それと入れ替わりのように、焼けたメレンゲを出し、今度はデザート作りに取りかかる。パブロバは、クリームに、いちごやブルーベリーをふんだんに盛り付けるデザートで、箸子伯母が調達してきてくれた摘みたてのブルーベリーをそこに載せるという。
ミアと二人、飾りつけをしながら、ブルーベリーをつまんで互いの口に入れ、「おいしい?」と訊き合ったり、残ったクリームをスプーンですくって食べたりしているうちに、短い言葉をいくつも教え合えた。
無事にミートパイが焼け、パブロバにいちごやブルーベリーを飾ったところで、宝が台所に入って来た。
「二人とも集中力があって、すごく似ているね。とても会って二日とは思えないよ」と宝が言い、首を傾げるミアに味子が「仲良し」と自分たちを差し、「グッド フレンズ」とミアが頷き、「ファースト?」と早くに仲良くなった、と意味で言おうと味子が首を傾げると、「早く 仲良し」とミアが意図を汲み、味子が「イエス! そうそう」と答えると、「そうそう」とミアも繰り返し、一緒に笑った。
その後、皆が集まっての食事が始まった。
大御所のご登場という感じで、祖父が食事の場に着く時、一同は無意識に緊張する。
居住まいを正す一同に、祖父はこの日、「オーストラリアからわざわざ来てくださったのだから、できるだけ、楽にしてください」と、暗に正座をしなくてよい、という意志を伝えた。
「おじいちゃんが言うんだから、そうしなよ」と、どうしたものかと迷っているミアに示すように、宝が先に足を崩した。一見お行儀が悪そうに見えた宝は、実際に言動には驚かされるものの、箸子伯母と親しいせいか、意外と料理の手際もよかったし、所作も美しかった。目上の人に敬語を使わない宝に、祖父は慣れているようで、うんうん、と頷いてみせる。
祖父はまずミアの出したミートパイを小皿に取り、食べた後に頷き、味付けなどを尋ねた。
驚いたことに、祖父は味子の同級生よりも流暢な発音で英語を話した。
後で聞いたところによると、外国人のお客様が増え始めた数年前より、祖父は英会話教室に通い始め、今では日常会話程度であれば自由に話せるらしい。
遠慮なく宝が祖父と大器伯父の料理に箸を伸ばし、「これ、おいしいよ」とミアに話しかける。
「おいしい」という言葉を繰り返すミアに、「ヤミー、ヤミー」と宝は言い、ぱくっと食べておいしい、という顔をする。
日本食に慣れていないミアは、その言葉に後押しされるように、だんだんと日本食を食べ進めた。
そして、箸子伯母に向き直り、「昨日の煮物、おいしかったです。緊張していてあまり食べられなくてすみません」と英語で言った。
「ザッツ ノット トゥルー」と箸子伯母はすぐにそんなことはないわ、と否定し、「あなたくらい、しっかりとして勇気のある女の子を私は知らないもの」と箸子伯母が英語で言い、祖父が頷き、丁太に訳してもらった宝が、「漆ちゃん、私は? あの怒り狂った漆ちゃんに、自分の意見言えたの、私だけだったじゃん」と、箸子伯母と宝にしかわからないものの、なんとなく、想像のつくことを宝が言うと、「あれは勇気ではなく、無謀の礼儀知らずと言うのです」と、ぴしゃりと箸子伯母は返した。
ミアのパブロバと水菓子の和洋揃った食後のお茶の席で、ミアは「今日はありがとうございました」と礼をした後に、「私にもここで正座をさせてください」と申し出た。
箸子伯母が、再びミアを指導する。
味子は自動翻訳で今日は箸子伯母の言葉を訳してミアに伝える。
「スカートはお尻の下に敷いて。いつものように背筋を真っ直ぐね。足の親指同士をつけて。膝はつけるか、握りこぶし一つ分開く程度で。脇はしめるか、軽く開くくらい。手はそう。『ハ』の字で。大丈夫?」
「はい」とミアは頷き、皆も居住まいを正したのだった。
5
翌日、母さらは、味子とミアのランチボックスに昨日ミアが好んで食べていた太巻き、それに味子がミアが好きだと言っていたアスパラの豚肉巻と卵焼き、野菜を詰めて持たせてくれた。
きれいにつめられたランチボックスをミアは携帯電話のカメラで撮影する。
母さらは、フォークとスプーンも入ったセットを持たせてくれたが、ミアは箸を使い、お弁当を食べた。
家に戻ると、二人で宿題をした後、ミアが居間にある漫画を読んでいいか、と訊いた。
もちろん、と答えると、ミアは居間の隅に正座し、黙々と漫画を読み始めた。
途中で母がココアを入れて出し、味子がクッションをそれとなく置き、そのたびにミアは小さくお礼は言うが、漫画から目を離さなかった。
そのまま夕飯の時間になり、「ミア、サパー」と、味子の母が声をかけ、ようやく顔を上げた。
そして足がしびれていることに気づき、悶絶していた。
食事と風呂を済ませ、部屋で二人のんびりしていると、味子の部屋に漫画の続きを持ち込んだミアが、「味子」と、味子を呼んだ。
「何?」と味子がミアを見ると、「ずっと言ってないことがある」と言いにくそうにミアが言う。
「え、何?」
味子は慌て、緊張した面持ちで身を乗り出す。
「ホームステイ、私でがっかり?」
「……え?」
あっけにとられる味子に、ミアは自動翻訳を使い、「最初に顔を合わせた時、言いそびれて……。本当は、ホームステイに来る子は、チアリーダーをやっているような子がよかったんじゃない?」と味子に言った。
味子はびっくりして、「そんなことない」と何度も首を横に振った。
味子も自動翻訳を使う。
「私こそ、せっかく来てくれたのに、うまくリードできなくて、うちもなんか、物たくさん置いた家で……」
「ううん、味子のところで本当によかった。ありがとう」
「こっちこそ、遠いところから、うちへ来てくれて、ありがとう」
味子は以前ミアがしてくれたハグを、今度は味子からミアにした。
ミアは驚いたようで、それから「ありがとう」と言った。
その日から、ミアと味子は狭い味子のベッドで二人で眠るようになり、ミアは学校では味子やその友達以外とも積極的に話すようになった。
授業では、初日のミアの姿勢を学び、意見交換が活発に行われるようになった。
そうしてミアが日本に来て五日目、祖父が店に招待してくれた。
家に帰った味子とミアに、味子の母が、昔味子の母や箸子伯母の着た着物を出して着付けてくれ、髪も美容院で結うほどに本格的ではないが、セットして、紅もさしてくれた。
味子が気になり、丁太と宝は呼ばなくていいのか、と母に訊くと、「あの二人は前にもうコース料理を食べたから、大丈夫」と笑い、「みんな一緒もいいけど、今日は二人での時間もいいんじゃない?」と続けた。
6
いつもは入ることのない、店の奥の個室に通されると、ミアは緊張しながらも、「アメイジング!」を連呼し、違い棚や生け花、掛け軸だけでなく、鴨居の彫刻や障子も興味深く眺め、味子は着物姿のミアを前に、何度も携帯のカメラで撮影をした。
驚いたことに、祖母がお運びさんをしてくれ、料理をひとつひとつミアに説明する。
日本料理を三食摂る生活も五日目を迎えたことに加え、味子の家が日本の昔からある料理ばかりだったことから、大抵の材料をミアは学んでいた。
そこに大葉や柚、三つ葉といった日本独自の野菜が加わる。
料理の材料を辿りながら、味子は「ミアの国にもある?」と時たま訊き、ミアは頷いたり、首を傾げたりした。
ミアの国では、何を食べているの? と訊くと、ビーフやマッシュ、それにハンバーガーと答えた。
ハンバーガーはこっちでもあるから同じだね、今度一緒にこっちのファストフードに行こうか、と言いながら、もうそれほど一緒にいられないことに味子は気づく。
ミア、留学生でなくても、こっちに来てね、と味子は言った。
ミアはこくん、と頷いた。
そして、味子もうちに来てね。家族に味子を会わせたい、とミアは言った。
味子は自動翻訳を使い、「うん、英語得意じゃないし、人と仲良くなるの、時間かかるけど、頑張って、いつか行くよ」と答えた。
「楽しみにしているね」と、ミアが笑う。
この日、初めて味子とミアは互いの携帯電話でやっているSNSの連絡先を交換した。
翌日の放課後、一学年の普通科だけが集まり、ミアを含めた数人の留学生のお別れ会が講堂で開かれた。
全国規模で有名な吹奏楽部の演奏、ダンス部、チア部のパフォーマンスと華やかな舞台演出が行われた。
その後、残れる生徒が教室に集まり、ミアの希望で、近所のファストフードでおやつを買った。
皆で写真を撮り、一人ずつ握手をした。
最後のあいさつで、ミアは「今すぐでなくても、高校、大学を卒業した後でも、オーストラリアに来る時には連絡してください。ずっと忘れません。本当にありがとう」と言い、大きな拍手が送られた。
それから数か月後、新たな学年に上がったミアが、日本文化のクラブに入り、日本食の紹介を任されていると、味子に連絡がきた。
一緒に送られてきたアドレスを開くと、ミアが学校の仲間と日本文化について発表している様子がアップされていた。
着物の着方や、日本の漫画や映画のほか、ミアの担当したページでは、日本のお弁当を作ってみる、という企画があり、そこには、味子の母がミアのために用意し、帰国時に荷物でなければ、と渡したランチボックスに詰められた、少し焦げた卵焼きや焼いたお肉、野菜に、おにぎりの入った、味子を懐かしくさせる昼食がアップされていた。