[349]麒麟と黄色い座玉(すえたま)
 タイトル:麒麟と黄色い座玉(すえたま)
タイトル:麒麟と黄色い座玉(すえたま)
掲載日:2025/04/13
著者:海道 遠
イラスト:よろ
あらすじ:
奈良時代、丹後地方の籠(この)神社には、五色の座玉(すえたま)があり、正座した時のしびれに効くと言われている。
神社の警護をする一族のツバク青年は最近、怪しい噂を耳にする。
座玉を使えばしびれは一旦、治るが後で足の病になってしまうというのだ。一族の少年頭領のぺき様と、お転婆なもえぎとツバクは真相を探り始める。そんな矢先、神社の鳥居の前で噂を堂々と口にし、病から逃れたければ、麒麟信仰の祠に供物せよという若い山伏が現れる。

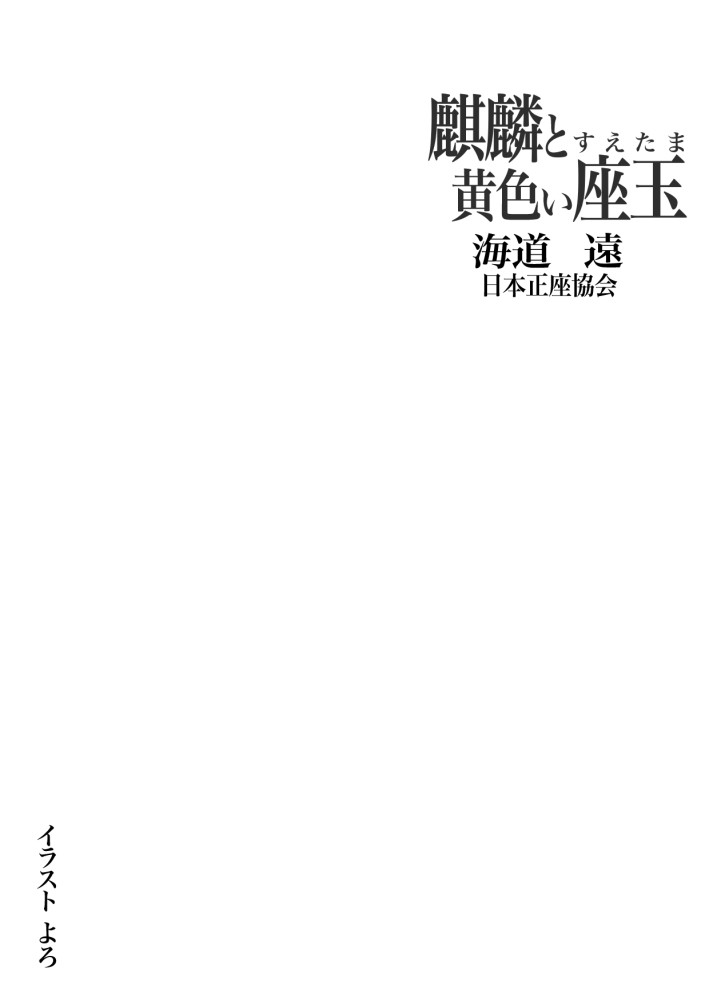
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 怪しい噂
丹後地方の海に長細く続く浜は、天に架かるはしご、または天に昇る龍と呼ばれている。周りの山頂から逆さに望むとそのように見えるのだ。
奈良時代――。晴れた春の早朝、海も空も爽やかな空気に包まれている。
ツバクは馬の足形を天橋立につけて、周りの集落を見回った。籠(この)神社を護る一族、海都(かいづ)一族の中心的な存在の青年だ。
朝の漁から舟が次々に帰ってくる。
子どもの頃から見慣れた風景だが、最近、顔を合わせた村人は、目を合わせないようにすれ違っていく。いつもなら、
「ツバクさま、お務めご苦労様です」
と明るく声をかけていくのに、何かオドオドして、足早にすれ違っていく。
それだけでなく、最近、籠神社の参拝客の数がめっきり減ってしまったのだ。
ツバクは、ここ十日ほど疑問に思っていたことを、漁夫(いさりお)に聞いてみることにした。
浜で網の後かたづけをしていた男たちに声をかけた。が、ツバクを見ると、クモの子を散らすように引き揚げてしまう。
「最近、籠神社のご参拝の人数が減ってしまった。何か心あたりはないだろうか?」
最後に残った男が、ぼそりともらした。
「五色の座玉(すえたま)が恐ろしいとか噂がたって……」
ツバクは耳を疑った。
「だ、誰がそんなことを言っているのだ?」
「皆が言ってますで」
「痺れを治して足を健やかにする座玉の存在が台無しじゃないか。言い出したのは誰だ?」
一族の古い屋敷の簀の子(すのこ)を踏み抜きそうな勢いで、ドスドスと足音が近づいてきた。
座敷にいた「ぺき様」こと、一族の若頭領の碧王丸(へきおうまる)と、一族の女の中で一番の働き手のもえぎは、扉が開くと同時にツバクにどやしつけた。
「静かに歩け! 簀の子が抜ける!」
「そんなことを言ってる場合ではありません、ぺき様!」
日頃、穏やかに警護の任務をこなしているツバクの眉がつり上がっている。
「どうしたのさ、そんな怖い顔して」
もえぎが膝の上のうさぎ、灰色のコタタを撫でながら言う。
「妙な噂が立っている。それも籠神社の氏子一帯ばかりでなく、遠くから天橋立見物にやってくる参拝客まで広がっている!」
「妙なウワサ?」
「正座して痺れを感じ、籠神社の五色玉を膝に乗せて痺れが治った経験のある者は原因不明の足の病になり、歩けなくなると」
「なんだって~~?」
もえぎが勢いよく立ち上がったので、コタタがびっくりして床に飛びのいた。
「それから免れるには、遠く離れている山中の麒麟(きりん)信仰の祠(ほこら)にお詣りして、心をこめて、お米なり金子なりお供えするしかないというんだ」
「な、なんだ、そりゃ」
「座玉を乗せて痺れが治ったという少女が、まもなく足の病になってしまったのだそうだ」
「そんなデタラメ、いったい誰が広めてるんだい!」
「神出鬼没に現れ、まことしやかに語るのは、得体のしれない山伏風の若い男だそうだ」
「山伏風?」
人々は先を争って麒麟信仰の祠を探しに行き、籠神社の参拝客はすっかり少なくなってしまった。
「これは怪しい話だな……」
もえぎ、ツバク、ぺき様は、調べることにした。
しばらくして、もえぎの手元からうさぎのコタタがいなくなった。もえぎは必死で探すが見つからない。
第二章 山伏風の男
山伏風の男が共の者をふたり連れて現れた。なんと、堂々と籠神社の鳥居の足元で人々に話を始めたのだ。どんどん人が集まってくる。
社殿から、禰宜(ねぎ)の青年数人を引き連れて、宮司さまも駆けつけた。
もえぎとツバク、ぺき様は村人にまぎれて聞くことにした。
「皆の衆! ここ、丹後の籠神社の付近に住む村人たちよ!」
話しはじめた若い男は、頭に小さな黒いものを着け、丸い派手な色の飾りのついた帯を前に下げ、膨らんだ袴をはき、手には脚絆(きゃはん)を着けて、山歩きに適した格好で長い棒を持っている。
「ここの奥殿の欄干に据えられている五色の座玉は、正座した時の痺れに効くと言われているが、とんだマユツバ(いんちき)ものじゃ! 痺れに効くどころか、他の足の病を呼び寄せるとんでもない闇の玉なのじゃ!」
「な、何を証拠にそんな!」
もえぎが飛び出しかけたが、ツバクが引き止めた。
「一旦は痺れが遠のくものの、後になって足の病を発症する者、後を絶たず。この事実を村の衆、参拝の皆の衆、知らぬであろう!」
集まって来た者たちは恐る恐る話を聞いている。
「これを防ぐためには、我ら麒麟信仰の祠に行き、お供えをするしかない。皆の衆、目を覚まして祠に向かうがよい」
「そ、その麒麟信仰の祠というのは、いったいどこの国に……」
ひとりの老人が尋ねた。
「探すのじゃ。それでこそ効き目があるというもの」
白い衣の男は顔を上げ、
「我は楽今坊(らっこんぼう)と申す。この中に海都一族一番の美女、もえぎと申すおなごがいるはず。愛兎を返してほしくば、我ら麒麟信仰の祠を捜しあてて来るがよい! 待っておるぞ」
高笑いが響いたと思うと、葉擦れの音だけが響き、男は共の者と消え失せた。
「何? さてはコタタを連れ去ったのは……あの、山伏風の男か?」
もえぎは両足を踏ん張って、上空や木立を見上げた。
「そりゃあ、あたいは海都一族一番の器量よしって評判だけどさ」
側にいたぺき様が、ガクッとした。
「だからって、大切なコタタをさらうなんて許せない!」
「とりあえず、帰って作戦練るぞ」
ツバクがうながした。
第三章 一番の美女
三人は板張りの座敷で、倭国の地図を広げて正座した。
ツバクは噂からいち早く「山伏風の男」と聞いて調べていた。山伏は山岳信仰者だ。中国から文化が渡ってきた。
紀州の山地に山岳信仰が広がりつつあるようだ。険しい山を毎日巡って歩き回り、修行を積み山に祈る。
「今のところ、このくらいしかわからん。この辺には険しい山が無いからな。麒麟信仰というのは初耳だ」
ツバクはため息をついた。
奥から長老の呼吟(こぎん)爺やがやってきた。
「何だ? 今日のあの男は? 厚かましくも、籠神社の大鳥居の脇で宣戦布告をぶちまけおって。『元伊勢さま』と崇拝される由緒ある籠神社を真向(まっこう)から敵に回す口ぶり。宮司さまもたいそうご立腹じゃ」
元伊勢さまというのは、伊勢に鎮座される天照大神が一時期、この籠神社に鎮座されたので、その呼び名が地元民に根づいている。
「呼吟爺やさんも、ずいぶんご憤慨のご様子ですな」
「うむ。ただ、もえぎが一族中一番の美女というのが腑に落ちん。誰かとの人違いではあるまいか」
ツバクとぺき様も、何度もうなずいた。
「な、何よ、みんな!」
一同、シーンと黙りこくった。
呼吟爺やがぺき様と目を合わせてから、
「とりあえず、四国、九州、出雲地方、紀州にも。あらゆる峻険な山岳地方をしらみつぶしに調べさせよ!」
夜遅く、もえぎは奥殿を訪ねた。
欄干には例の足のしびれがなくなるという五色の座玉が据えられている。もえぎは欄干を見上げて真っすぐ立ち、砂利の上に膝をつき、衣はお尻の下に敷き、かかとの上に座った。手前にある紅の座玉を見つめ、順にお祈りしていく。
「籠神社の神様、コタタが無事でいますように。あたいの望みはそれだけです」
第四章 数年前の楽今坊
砂の上を、ザクザクと数頭のラクダと馬が荷を積んで歩いていく。先頭のラクダに乗っている男は、中央アジアの者にしてはヒゲが薄くまだ年若い。
倭国の丹後地方で山伏の格好をしている楽今坊は、数年前、ラッコンと名乗り、大陸の秘境を渡り歩く旅の商人をしていた。
陽が高くなってきたので、少し休みを取ろうと思った時だった。
地平線に、巨大な黄色い生き物が動いているのが目に入った。
ターバンを巻いた手下が、
「お頭、ありゃあ、もしかして伝説の……」
「もしかして、あのデカいのは麒麟……か?」
「わあっ! 麒麟だ!」
「人間に囲まれてるぞ!」
ラッコンと手下たちは、馬を走らせた。
なんという大きさだろう。ヤシの木に届くくらい背が高い。身体は全体に黄色っぽく、大きなウロコに覆われている。頭や首すじ、シッポなどに褐色の毛が生えている。目はぎょろりと大きく、すくみあがってしまう。絵画にある龍の顔そっくりだ。鹿の角のようなものが頭からにょっきり生えている。
首や足に周りの男たちから縄を掛けられ、苦しそうにもがいている。男たちはおそらく野盗だろう。
麒麟はとても心優しい生き物で、肉食などせず草さえ踏んだりしないと聞く。その優しい生き物が声も出せずに首を左右にふっている。
「麒麟は神獣じゃねえか、苦しめるとは許さんぞ!」
ラッコンは馬を下りながら怒鳴りつけた。
麒麟の片脚から血が流れている。
「生きたお宝を見過ごせというのか。市に出せば一生遊んで暮らせるだけの金になる!」
野盗のひとりが言った。言い終わる前に麒麟に掛けていた縄が切られた。ラッコンと手下は素早く岩山へ麒麟を引っぱっていった。
岩山に洞窟が多いのをラッコンは知っていた。ひとつの洞窟にデカい麒麟の身体を押しこめた。
「お頭、さっきのやつらが追ってきやがった」
「入口に岩を置いて麒麟を連れていく! この辺りの洞窟はクモの巣みたいになっていて、地下水も流れているんだ」
「お頭、よく知ってるなあ」
「この辺の道は、空から地下までお見通しよ!」
狭い洞窟の中を麒麟を引いて歩いていくと、地下水の流れがあった。船着き場まである。
「待て。もうすぐ船が来る。わりと大きい船だ」
ラッコンは手下ふたりと麒麟を連れたまま立ち止まった。
「この辺りは吐蕃(チベット)民が地下水路を使っているはず」
わりと大型の船が来た。船首に灯りがついていて、何人かの舟子がいる。
「頭領!」
舟子が叫び、チベットの民族衣装を着た逞しい男が船首まで出てきた。
第五章 バレンとの出会い
「これは……なんと……」
麒麟を見て、驚きのあまり声が出ないようだ。
「生きて、神獣と出会おうとは。……お前たちは?」
「俺は旅商人のラッコン。俺も今日、神獣に出会うとは思いもしなかったさ」
「脚から血を流しているではないか。この先は道が狭まっているから陸からは進めないぞ。この船に乗せて広い水路まで運ぼう」
「そいつはありがてえ」
「私はある一族の地下警備を担っているバレンだ」
チベットの民族衣装を着た男が自分のことを言った。
なんとか皆で力をふり絞り、麒麟を船に乗せることができた。方向転換して船を進ませる。
水路をしばらく行くと、広い地下湖が広がっていた。
皆で麒麟の巨体を岸辺に運ぶ。
「ありったけの清潔な布を用意せよ! キズ薬もだ!」
バレンが叫び、舟子たちは布をたくさん用意した。
麒麟は人間たちが脚のキズを手当してくれる間、鼻息だけを吐き、おとなしくしていた。
「鋼鉄のような素晴らしいウロコだな。いぶした金色だ。鎧を作ったら、千人力だろうな」
「こんな剛毛のたてがみは、見たことがない。さぞかし丈夫な綱が作れるだろう」
舟子たちのおしゃべりを、バレンはたしなめた。
「こらこら、神獣の麒麟は縁起の良い生き物だ」
手当が終わると、バレンは麒麟の前にチベットの織物を敷き、膝をついた。衣はお尻の下に敷き、かかとの上に静かに座る。そして額をつけて麒麟に拝した。
ラッコンが尋ねる。
「その座り方は……」
「正座だ。近頃、唐王朝では正式の座り方だ」
「へええ。俺にも教えてくんな」
ラッコンは真似したが、しばらくすると痺れてきた。
「これを使うがいい」
バレンが碧い玉を差し出した。
「これを膝の上に置くと痺れがおさまる」
「ほ、本当だ。治ってきた」
「この玉は模倣品だそうだが、本物はもっと効き目があるだろう」
「本物はどこにあるんだ?」
「さあな。商人なら探してみるこった」
バレンはラッコンの顔をまじまじ見て、
「お前、大陸の者ではないな。正座の伝わった倭国辺りから、海賊に売られてきたのではないか」
「……」
ラッコンは押し黙った。図星だったからだ。
第六章 雲で倭国へ
麒麟を養うには大量のエサと広い場所が必要だ。
エサは枯草しか食べない。毎日、大量の草を刈り取り、乾かして運ばなくてはならない。その労力をバレンは快く貸してくれた。
また、洞窟の外では正座を知らない近くの集落の人々に順序を教え、痺れて困っている人には碧い玉を貸して治してやっていた。
その賃貸料を、麒麟を養う費用にした。
「バレン! あんた、やるな。警護なんぞやめて商人になればどうだ?」
ラッコンはバレンの商売の手際に驚き、感謝した。しかし、気を許すほど人の好い男ではないのだが――。
ようやく麒麟のケガが治った。
麒麟は雲に乗って移動すると聞いていたが、いざ、出立する時には本当に雲を呼んだので、ラッコンと手下たちは目を飛び出させた。
真白き雲に、麒麟とラッコン、手下ふたりが乗った。三人はおっかなびっくり雲を踏み外さないようにおとなしく乗っていた。
雲は浮き上がり、バレンたちが砂漠から手を振っているのが見えた。
「すごい速さだ! この分だと大陸から大陸までひとっ飛びだな」
「お頭! あれを見て!」
最初に麒麟を砂漠で捕えようとしていた野盗が、しつこく馬で追ってきているではないか。
何より乱暴を嫌う麒麟は本気で怒ったようだ。野盗めがけて炎を吐いて追っぱらった。
雲の行き先は、大陸の奥地に向くはずが倭国へ向かっていた。
「今度こそ、野盗どもに襲われないところに麒麟をかくまわなくては!」
倭国にたどり着いて、険しい海岸沿いに洞穴を見つけた。洞穴の入口に祠を作ってふさいでしまった。
手下に仲間を集めさせ、倭国の山伏の装束に着替えた。最初からの手下を連れて丹後の籠神社に向かった。
「いいか、今日から俺たちは山で修行する山伏だ。人に問われたらそう答えろ」
「問われるも何も倭国の言葉がわからねえよ」
「じゃ、黙っておけ」
バレンから青い玉を見せられた瞬間、座玉のことが思い出された。旅商人をしていると情報には精通する。
痺れをなくす碧い玉は、倭国の籠神社の欄干に据えられている座玉に違いないと、ピンと来たのだ。
籠神社からさらってきた灰色のうさぎを、芭蕉ダンゴを与えて骨抜きにして祠の祭壇に置いた。
「お前ら、そのうさぎをぞんざいに扱ってはならんぞ」
「え? 今夜のメシにするんじゃ?」
「ばかやろう! 絹の衣を着せて風邪をひかさぬよう、お腹を空かさぬよう、よおく面倒みろよ」
「えええ~~?」
手下ふたりは、ぶつぶつ言いながら命令通りにした。
海都一族の中で一番美しい女が大切にしていると聞き、取り返しに来るオトリにしようと思いついたのだ。
子どもの頃、大陸に売られる港で、籠神社の海都一族一番の美しいという女の子が船に乗り換えるのを見たことがある。桃の精のようなその横顔に、ずっと心を奪われてきたのだった。
――やっとあの娘に会える!
――しびれを治す座玉が手に入る!
――生きた麒麟を手に入れた!
座玉は、信者を少なくして神社の力を弱めてから五個ともいただくつもりだ。
ラッコン――いや、楽今坊は幸運に酔っていた。
第七章 祠にて
もえぎはあれ以来、コタタに会いたくて食欲が全くない。おなご衆が心配している。
「あのもえぎさんが食欲がない?」
「コタタをさらわれたんですもの、無理ないわね」
寝込んでいるもえぎのところへ、ツバクがやってくる。
「コタタの居場所が分かったぞ!」
もえぎはガバッと起きた。
「どこ? コタタは元気?」
「西のデコボコした海岸だ。赤い祠が見つかった」
もえぎは大急ぎで身支度を整えた。短めの着物を着て、腕やすねに脚絆を巻いた。
「ラッコンだかラッコだか知らないけど、覚えときなさいよ! コタタ! 待ってて。すぐに助けてあげるわ」
紺碧の海が広がる海岸に険しい岩が切り立っている。ツバクと共に馬で駆けつけたもえぎは下馬してから、岩をつかんで登っていく。
「もえぎ! 楽今坊の手下があちこちに見張っている! 気をつけろ!」
ツバクが叫んだとたんに、もえぎの身体に縄が巻きつけられた。
吊り下げられて持ち上げられたところに平らな場所があり、祠の前に楽今坊が両手を組んで仁王立ちしていた。
「待ってたぜ」
祠の祭壇に、コタタが寝ているのが見えた。もえぎは走り寄って抱き上げたが、でろんでろんになっている。
「コタタ! どうしたの?」
「うさぎのマタタビ、芭蕉だんごを食べさせたから力が出ないだけだ。それより倭光姫はどこだ? お前は侍女か?」
「何のことよ? あたいはコタタの飼い主よ」
楽今坊はポカンと口を開けた。
「このうさぎの飼い主は、倭光姫じゃないのか?」
「寝ぼけたことを。コタタはあたい、もえぎの命より大切なうさぎよ。倭光姫さまのうさぎは真っ白のよ」
「……じゃ、俺様の勘違い……。道理で骨太い女のはずだ。待ちに待って深窓の籠神社の倭光姫さまにお目にかかれると思っていたのに」
楽今坊はガックリと膝を折った。手下がもえぎからコタタを取り上げた。
「コタタを返してもらうよ!」
「そうだ、返せ」
もえぎの背後から、縄に巻かれたツバクも叫んだ。楽今坊は歯を食いしばり、
「姫さまに会えるまではそう簡単に返せねえ」
「何ですって」
「祠の奥には神獣が眠っている。うさぎを気にいってなさるから、勝手に持ち帰ることは許されねえ。ま、俺様の願いを聞いてくれたら返さんでもないがな」
第八章 馬簾王の一行
丹後の港では村人が騒いでいた。
沖に、大陸から豪華な船がやってきていたのだ。
「唐の国から皇帝陛下がいらっしゃったのかい?」
「そんなわけないだろ。大陸の大商人の船らしいぞ」
籠神社の裏方では、更に大騒ぎになっている。もえぎが神社の台所に顔を出してみた。
「何ごとなの? すごいお膳の数を用意しているのね」
「もえぎさん、よいところへ」
おなご衆の一人が振り返った。
「今夜、海都一族のおなご衆にも手伝ってもらえませんか? 神社の者だけでは手が足りないかもしれません。港に来た大陸の商人一行が二十人ほど、座玉見物に来られた後、神社で宴をされることになって」
「座玉見物? へえぇ。分かった。海都の方からも何人か応援するよ」
おなごは、もう一度振り向いて、
「もえぎさん、コタタを捜しに行かれたんじゃ? 連れて帰られたの?」
「まだなんだけど、ちょっと事情で戻ったんだよ。――大陸の商人てのは?」
「ええと、確か『ばれん』さまとおっしゃいましたよ」
「ば、ば、ばれん――?」
「もしかして、チベットの王様の馬簾じゃないだろうね」
もしチベット王の馬簾なら、会ったことがある。
(まさか。馬簾王が海を渡ってくるなんて)
もえぎは顔をぶんぶん振った。
馬簾王の一行二十人が港から上陸して、籠神社に参拝した。チベットの鮮やかな色と模様の衣装を着けている。宮司さまが案内して奥宮の欄干に並ぶ座玉を見物した。
「なんと神々しい玉でしょうな」
一行は、毛氈の上で座玉に向かって正座し、合掌した。座玉の並ぶ欄干の後ろの扉は、神様が出入りすると言い伝えられている。そちらへも正座して地面に頭をつけて礼をした。
もえぎは、杉の木の陰からそっと様子を見ていて、馬簾王の顔を確かめた。チベット王の馬簾王だ。
(どうして倭国まで?)
神社の本殿から、巫女たちの列が近づいてきた。なんと先頭に倭光姫さまが歩いて来られたではないか。漆黒の髪に花びらが散るように飾られたかんざしが白いお顔に映えて美しい。
敷かれた緋色の毛氈の上で、たおやかに正座をしてから馬簾王に梅湯を勧めた。
馬簾王は、たいそう機嫌よく梅湯を味わっている。
日が暮れて、本殿の座敷で宴が始まった。
巫女たちは膳を運ぶのに大わらわだ。もえぎも廊下を走っていたが、曲がり角で突然、腕を引っぱられた。
馬簾王だった。
「や、やっぱり殿下!」
「驚かせたな、もえぎ」
「何故、倭国まで?」
「麗しい花が咲いているとの噂を聞いてな」
扉の隙間から、座敷で接待している倭光姫を示した。
「んまあ、お妃さまに言いつけますよ!」
「しっ! 余は本気だ。 倭光姫を側室に迎えたいのだ」
第九章 乱入
夜ふけの座玉が並んだ奥殿の欄干に、よろよろと千鳥足の人影が近づいた。かなり酒の回った呼吟爺やだった。
宴で正座していて足のしびれた連中が、座玉を貸してくれと言い出したので、拝借しに来たのだ。
(足が痺れても治るとは、重宝な玉だね~~)
鼻歌を歌いながら欄干への階(きざはし)を昇ろうとした時、黄色く光るものが欄干から床に転がり落ちた。
「あやっ? 今のは?」
黄色く光るものは、わずかに開いた観音開きの木戸の中に転がっていった。
突然、宴の席で、ガシャーンと音がした。
男が膳の並んだ中に乱入して、盃や器が散乱したのだ。馬簾王一行は立ち上がり、宮司さまも立ち上がった。
「そなたたちは!」
もえぎたちも急いで座敷に戻った。
乱入したのは楽今坊たちだ。錫杖(しゃくじょう)を持ってわらじのまま、座敷の真ん中に立っている。
「何よ、あんた、まだ言い足りないことでもあるの?」
もえぎが怖いもの知らずな物言いで挑戦した。
馬簾王も、
「ラッコンではないか! その装束は勇ましいな」
「おう、バレン。また会ったな」
楽今坊はにやりと笑った。
「どうやら、俺とあんたの目的は同じようだな」
馬簾王と楽今坊の視線を感じた倭光姫は、もえぎの背中に隠れた。
「倭光姫! 輝くばかりの美しさだな。俺の女になれ! 好きなだけ贅沢させてやるぞ」
宮司さまが姫をかばって、
「下郎、下がれ。我が姫は海都一族の若頭領、碧王丸どのという許婚(いいなずけ)がおられる」
「まだ子どもなんだろう。姫には、俺みたいな逞しい男がお似合いなんだよ」
楽今坊の自信満々な言葉を聞いて、馬簾王が唇のハシに苦笑いを浮かべた。
第十章 姫の気持ち
今にも乱闘が起こりそうな気配を感じた倭国の宴席の出席者は、我先にと逃げ出しはじめる。
海都一族が楽今坊一味を逃がさないよう、周りを固める。
「楽今坊とやら。先日の鳥居前での無礼といい、今夜の乱入といい、倭国の籠神社を何と心得る! 今すぐ神妙に検非違使(けびいし=役人)のお縄にかかれ」
ひとりの権禰宜(ごんねぎ)が言った。
「やなこった! 俺には大きな目標がある。少しでも触れてみろ、まずいことが起こるよな? もえぎの姐さんとやら」
コタタの安全は保障しないという意味だ。もえぎは言葉に詰まり、
「皆さん、楽今坊を捕えるのは、今少しお待ちください」
「もえぎらしくないな」
「どうした」
もえぎは額から冷や汗を垂らし、土下座した。
「お願いしますっ」
伏せたまま微動だにしない。
もえぎは侍女に囲まれている倭光姫の前に進み出て、正座した。
「しばしお時間をください。一族の建物までお願いいたします」
姫はついてきた。
渡り廊下を渡ると、宴席の声が遠くなった。もえぎは別棟の自分の小さな部屋に姫を通した。
「むさ苦しいところで申し訳ございません。急ぎ、姫さまにお答えいただきたき儀がございます」
「な、何かしら」
「姫さまは今日のお客様の馬簾王さまを、いかが思われますか?」
「いかが……とは」
「殿方として、いかがお思いになられます?」
「もえぎさんったら、今日、お会いしたばかりのお方を……。そうねえ、大陸の大商人様なのでしょう? 異国の方でたいそうなお金持ち……。大胆で近寄りがたい方だわ」
泣きたいような小さな声で、姫は答えた。
もえぎは顔を輝かせて、
「では、楽今坊という山伏は? もちろん仮の格好でしょうけど。お嫌ですよね。あのように粗野な方は」
「いえ」
意外にも姫の返事はもえぎの予想と違った。
「あの方、粗野ですが、なんとなく気さくにお話できそうな」
「じゃ、お好きということですか」
「さ、そこまでは」
「馬簾王さまよりは好ましいのですね!」
「そ、そういうこと……になるのかしら」
もえぎは、バタバタと渡り廊下を戻って叫んだ。
「宮司さま! 楽今坊を捕獲すること、しばしお待ちください!」
ツバクが足音を消して、座敷を後にした。
馬簾王はもえぎの表情から鋭く察した。自らの敗北を。しかし、手下に素早く命令を下す。
「倭光姫の身柄を拘束しろ!」
手下は倭光姫の周りにいる侍女らをも囲んだ。
宮司さまが顔色を変えて海都一族に命令する。
「倭光姫を誰にも渡すでないぞ!」
「そうはさせるか」
馬簾王の手下と、楽今坊一味、そして姫を護る海都一族の男衆――三つ巴の睨みあいになった。
「馬簾王、楽今坊! 姫さまは籠神社の神聖な象徴よ。諦めていただくわ」
もえぎが姫の前に立ちはだかった。宮司さまや権禰宜たちも姫を守って囲む。
「今のうちに守りの手薄な座玉を全部いただけ!」
楽今坊が手下に叫び、馬簾王の配下も同じように座玉の欄干へ走った。
第十一章 麒麟の出現
その刹那――、
欄干の内側――木戸の奥から、地響きのような音が近づいてきた。
「な、何だ、これは?」
しばし、静寂があり――、
次の瞬間、扉から黄金の炎の帯(おび)が吹き出し、欄干の外まで飛び出した。人々が吹き飛ぶ勢いだ。
(炎の帯――? 何? あれは……眩しい!)
もえぎが手をかざして目を細めると、巨大な顔をした獣が頭から何かポロリと落とした。黄色い座玉と灰色のうさぎではないか。
(コ……コタタ―――!)
神様の通り道と言われる扉から飛び出してきたのは、黄色い巨大な麒麟だ。
(崖の祠と奥殿がつながっていたなんて――!)
鼻息荒く、目玉をむいて興奮している。巨大な蹄(ひづめ)をカッカと踏み鳴らした。
「コタタ――!」
うさぎは元気に走ってきたが、麒麟の鼻息に吹き飛ばされて地面に転がってしまった。
「おっと!」
ツバクが素早く抱きかかえ、もえぎの手の中に運んでやった。
「良かった~~! コタタ。大丈夫? 怪我はない? 会いたかったよ、コタタ~~~!」
「うしゃしゃ~~~い!」
何度も頬ずりして、もえぎはコタタを抱きしめた。
巨大な麒麟の身体は本殿より高い。二本の角はもっと高い。
背後から現れたのは――。
狩衣を着た少年頭領、ぺき様ではないか。
「皆の者、何をしている。神獣の麒麟さまにご挨拶申し上げないか」
声変わりしていない甲高い声で命令した。敵も味方も我に返って、慌てて正座をして頭を下げた。
「き、き、麒麟さま。此度は、籠神社にご降臨とは」
砂利の上に座礼して、宮司さまが挨拶した。
ぺき様が麒麟の代わりに、
「平和な世がすぐそこに来ているらしい。麒麟さまは瑞獣(ずいじゅう)ですから、感じ取られたのでしょう」
続けて、
「大陸で野盗に襲われた麒麟さまを助けたのは、楽今坊だそうです。また、傷の手当をして食をご用意したのは馬簾だと、心のお声を聞きました。此度のふたりの無礼な所業は許してやるがよい、と」
「ふたりが麒麟さまをそのように……」
宮司さまはふたりを見直したようだ。
「あのう」
もえぎが口を挟んだ。
「倭光姫さまを馬簾王に嫁がせなさるのですか」
「姫さまのお心のままにだ」
ぺき様が大人っぽい口ぶりで言った。
「もえぎ、心配をかけたな。わらわ自身でよく考えます」
倭光姫がしっかりと言ったので、もえぎは引き下がった。
麒麟が残り四つ、紅、碧、黒、白の座玉を舌の上に乗せて出した。
「麒麟さま、座玉すべてをお守り下さっていたのですね!」
神社の者一同は、拍手喝采したいくらい喜んだ。
馬簾王と楽今坊は、悔しさに拳を地面に打ちつけた。
「さて、楽今坊、宴席に土足で乱入した罪は問われぬことになったが、籠神社の権威を失墜させる大ぼらを吹いた罪は、つぐなってもらわないと。ねえ、宮司さま?」
もえぎが言い出した。
「大ぼら?」
「ばっくれてもダメよ。座玉を使うと、足の病になるっていう噂は、あんたが流したんでしょう?」
「そ、そうだった!」
その日から、丹後のあちこちで楽今坊自身が、あのほら話はまったくのウソだったと頭を下げて回ることになったのだった。
麒麟は大きな身体の手足を折り曲げて、コタタと倭光姫の真珠丸から香箱座りを習っていた。
コタタ(そう、足を曲げてお手々も隠すんだよ)
真珠丸(しびれたら丸い玉持ってきてあげるね)
麒麟(ビーズみたいに小さな玉だね)
鼻先に乗ったうさぎ二羽と心で話す麒麟たちは微笑ましかった。







