[88]コンパスの中心に正座して
 タイトル:コンパスの中心に正座して
タイトル:コンパスの中心に正座して
分類:電子書籍
発売日:2020/04/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:48
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:keiko.
内容
マホはお寺の勉強と正座教室で、子供の頃から地球の代わりにコンパスをいじってる女の子。とても活発で、足の不自由な幼なじみ、ヤスキとは仲がいい。
中学、高校と目立つ行動をし始めたマホ。見守り続けるヤスキ。
大人になり、マホは海外ボランティアに参加。アフリカの後進国で活動する中、河野シズルという青年と知り合う。ヤスキとの絆のつもりで持っていたコンパスのために革ケースを作ってくれた。マホの世界巡りは続く。やがて、南の国の子供たちに正座教室を開くことになる。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1940039

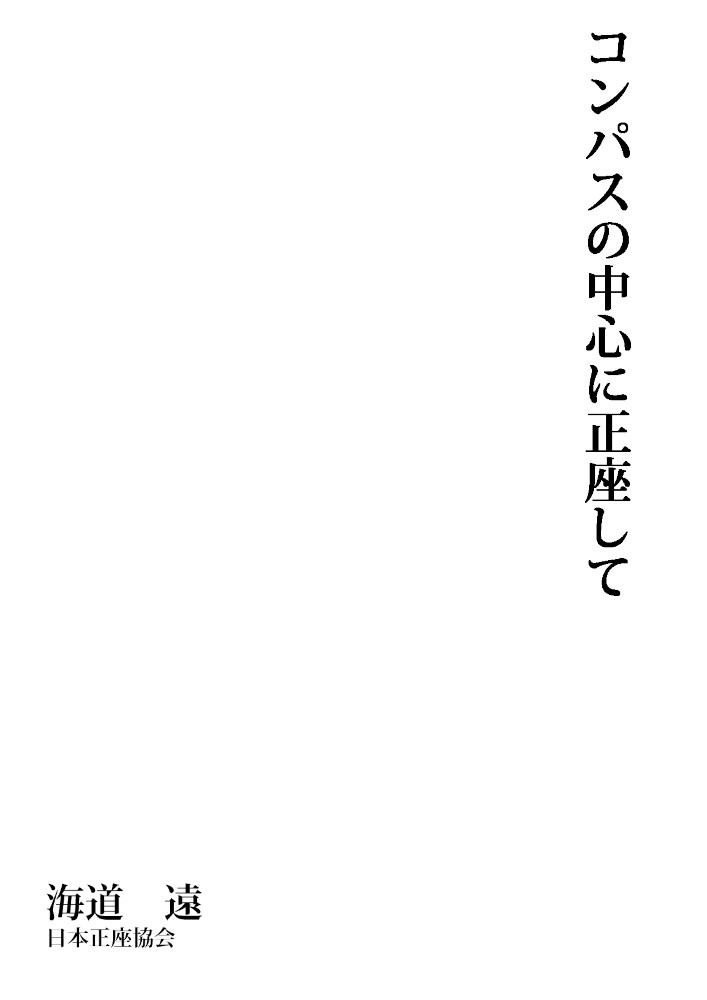
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 寺にて
「コンパスって円を描くこと以外に何ができる?」
コンパスを机の上でくるくるさせながら、マホが言った。
「それ以外に何があんのや」
ヤスキが笑いながら答える。平和な村のお寺の広い部屋だ。
「気がつくまでナイショ」
「ケチやな~~」
その時、廊下から足音が聞こえたので、マホは背をぴしりと正して正座に戻った。廊下から白足袋で静かに入ってきたご住職が咳をひとつして、皆の前に座る。ごましおの有髪であごひげを生やしている。
寺の本堂内の一室、土曜日になるとご住職が小学生を集めて勉強と正座のお稽古の場所を与えてくれるのだ。学校とはまた違う雰囲気で昔話も聞けるとあって、子供たちは寺が大好きだ。
マホとヤスキは小学五年生。一年生の時から、ずっと同じクラスだ。
ご住職は皆に正座の作法も丁寧に教えてくれる。
ヤスキは下半身が不自由で外では車椅子を使用しているが、ご住職は容赦しない。
「背筋を真っ直ぐにして、かかとの上にゆっくり座る。両手は膝の上じゃぞ。女の子はスカートを膝の内側に織り込んで」
「キャッ! ご住職さまいうたら!」
住職がひとりの女の子のお尻をポンと叩いたので、皆が騒ぎ出す。
「静かに! 今、騒いだ者は終了時間、二十分延長!」
「ええっ、そんな……」
皆はピタリと黙り込む。住職も真面目な顔のまま、書物に目を通している。
マホはひとり、ノートの上でお気に入りの、鉛筆を固定させるコンパスを廻していた。針で中心点に突き立て、鉛筆で円を描いていく。コンパスはマホにとって地球の代わりなのだ。
(コンパスを廻す中心に、アイツが正座して見守っててくれるねん)
心の中でつぶやきながら、円を描いている。
ヤスキがチラリと見て、
(マホが大人しくしてるのって、コンパスをいじってる時くらいかな?)
マホはとにかくお転婆だ。狭い町内や、山、川へでも行ったことのない所へ行きたがる。ヤスキは置いていかれる。足の不自由な彼にはマホについていけない。
マホが捜索願を出されたことは一度や二度のことではない。村の人たちを騒がせたことも数知れず。
〇〇岬の先っちょへ行ってみたかったとか、〇〇峠の景色が見てみたかったとか、〇〇校の建物が見てみたかったとか、好奇心だけかと思うと、村のために川筋を調べたり、堤の高さを調べたりしている時もある。
中学生になったら治まるかと思いきや、ますますエスカレートする。体育の時間に一番、目立っているのはマホだ。体育祭のリレーでは、いつもマホがアンカーを走り、優勝に導いた。
かと思うといきなり茶道を始め、先生から「正座がとても美しいですね」などと褒められた。いつものお転婆マホと同一人物なのだろうか、と周りの友達は驚く。こういう時は、内心「えっへん」とドヤ顔だ。
(ご住職様、ありがとさ~~ん!)
住職も、たまにそういう話を小耳にはさむと、
(わしの正座指導もまんざらでもないのう。茶道の先生に褒められたのなら、お転婆マホもしっかり正座が出来てるらしいわい)
と、ニヤニヤしてしまう。
マホは高校一年生の時に日本一周自転車の旅に出かけ、成功。富士山登頂にも成功。三年生の時にはアフリカのキリマンジャロの登頂に成功。
達成する度、お寺に来てはひとり静かに正座して目を閉じている。行ってきた景色を思い浮かべているのか、次の計画を練っているのか。ご住職はそんなマホをそっと見守っていた。
大学は福祉系を選び、海外ボランティアに参加すると言い出した。
もう一方で農学を学び、世界の痩せた土地に作物を作りたいと言う。そして、教育学部も受験し、癖地の小学校で子どもたちに勉強を教えると言い出した。
まるで故郷をコンパスの中心にして、離れた外側で花を咲かせようとするように。
両親は呆気にとられるのに慣れてしまい、娘の好きなようにさせている。
マホは、それらの希望をヤスキに話してから両親に打ち明けた。ヤスキが一番の理解者であると信じている。マホの新しい希望を聞く度に苦笑いしながら、
(さて、台風の目のようなあいつはどこまでやるかな?)
と、車椅子の上で楽しみにしている。
『コンパスの真ん中には、俺が正座して睨んでいるから、戻ってきたかったらいつでも戻ってこい!』
マホと違い色白なヤスキだが、そういう力強さはあった。
第 二 章 海外へ
マホは、二十二歳の時、初の海外ボランティアに参加した。肩まであった髪の毛をショートにした。行先はアフリカの〇〇国。最近まで内乱があり、人々はバラックのような住まいに暮らしていた。仕事もない手持ち無沙汰な男たちと、女性と子供たちがバラックの周りにうろうろしていた。
かろうじて電気が通り始めたが、水道が通っていない。
毎日、生活用水を共同井戸からバケツに汲み上げた。お風呂代わりに井戸水を浴びる。その時には井戸水に敬意をはらうために正座した。
そうすると不安な気持ち、自分は日本人として現地の人々にどれだけ力になれるだろうかと折れそうになる気持ちが治まり、明日からまた、頑張ろうという気持ちが湧いてくるのだった。
ライフラインだけでなく、現地の人々とのコミュニケーションも苦労したが、やがて原色の民族衣装をたくさん身につけた奥さん方が、「マホ、マホ」と言って親しくしてくれるようになった。
ボランティア仲間が新しい井戸を掘り始めたので、手伝ったり濁った水を清潔な水に濾す方法を教えたりした。
後でやってきたボランティアの中に、日本人の青年がいた。
「宜しくお願いします」
はきはきとした物言い、日焼けした顔、真っ白い歯の青年だ。
河野シズルと名乗った。マホより三歳年上だ。一緒に活動するうちに誠実な青年だと分かってきた。
マホがいつもコンパスを腰に携えてるのに気がついたらしく、ある日、
「これ」
と、渡された。黄土色の革細工のケースだった。
「コンパス入れに使って。そのままだと危ないぞ」
「え」
子供の頃からの必需品とでも言おうか、マホは小学校時代からの鉛筆付きコンパスをいつも持ち歩いていた。一緒にコンパスで遊んだヤスキがいつも側にいてくれるような気がしたからだ。
「……ありがとう」
はにかんで受け取った。手作りだ。コンパスを入れてみると、銃のホルスターみたいな感じでぴったりだった。
「器用なんですねえ、河野さん」
「好きなだけだよ。目で測っただけだけど、寸法合っていて良かった」
やがてその地から離れる頃には、シズルと現地の人たちが別れを惜しんでくれた。
マホは一時帰国し、一年間は野菜の栽培について学ぶが、ほどなく土地の痩せた国に行き、農業を指導することになっている。実家に帰ると日焼けしたマホに家族が驚いた。
「まるで男やな」
マホは両親の前に正座し、
「しばらく農業の勉強をしたら、また外国の派遣地へ行きます。行かせてください」
真顔でお願いした。
車椅子で駆けつけてきたヤスキも一緒に頭を下げてくれた。
「ご心配でしょうけど行かせてあげて下さい。僕の代わりをしてくれていると思って応援してますから」
不自由な足ながら、ちゃんと正座してマホと並んでお願いした。マホの両親は、
「反対はしませんよ。マホは言い出したら聞かない子ですから。それに私たちより、ヤスキくんがコンパスの真ん中でしっかり見守ってくれてるしね」
ヤスキは、
「ついていったりはできませんが……」
マホは彼の背中を叩き、
「ヤスキはド~~ンとコンパスの真ん中に正座して待っててくれればええの!」
(ヤスキの見守りがどんなに心強いか)
マホは深く深く感謝していた。
第 三 章 熱病
一年の研修の後、東南アジアのある国で農業を現地の人々に教えることになった。風土に合う作物を研究し、何度も試験した上で実行した。
そこで、アフリカの赴任地でコンパスの革ケースを作ってくれた河野シズルと再会した。
「おや、コンパスのお嬢さん」
マホの腰には相変わらず、コンパスがあることを確認しながら、シズルは屈託なく声をかけてきた。
「河野さん! また一緒になるなんて。コンパスと正座のお嬢さんって呼んでくれたら嬉しいな」
「正座って?」
「正式の正座の作法、今度は河野さんにもお教えさせてね。とっても心が穏やかになれるから」
「へええ。じゃあ、よろしくお願いします。そして頑張って現地の人の力になりましょう」
一日の農作業が終わるとクタクタになったが、出荷場の一隅にむしろを敷き、正座を河野に教えた。
「そうです。静かにかかとの上に座ります。背筋をピンとして、両手は膝の上に静かに乗せる。スカートの場合は、お尻の下に敷く」
「これでいいかな」
日本人であるからには正座は知っていた河野だが、マホから教えられると、改めて正式な方法を知り、毎日稽古するうちに心が鎮まり疲れも吹き飛ぶのだった。
「ありがとう。一日中バタバタしてるより、正座すると心が落ち着くね」
「良かった、お役に立てて」
そんな時、マホは思いがけず熱病にかかってしまった。ジカ熱だ。
ヤスキと両親が飛んできた。
学生時代の友人たちが、ヤスキの車椅子移動の手助けをしてくれた。
「代表の河野さんて方から連絡を受けてな」
両親が、シズルに丁寧にお礼を言ってるのを、夢の中の出来事のようにマホは聞いていた。父親はたまらず、
「日本へ帰るか?」
と尋ねたが、
「お気持ちは分かりますが、しばらくは安静にしないと」
シズルが冷静に言った。
「こんな毒虫や毒蛇がたくさんいるジャングルの中に病の娘を置いて帰れってのか?」
「今、動かしたら娘さんの容態はもっと悪くなってしまいます」
ヤスキも大きく頷いた。
「お父さん、ここは我慢して……」
父親は娘の真っ赤な顔を見て、歯ぎしりしたい表情だったが、拳を握りしめて我慢した。
「マホ、頑張ってくれよ。みんながお前の回復を願ってるぞ」
ヤスキがマホの手を握って声をかけた。
「ありがとう……」
熱にうなされながらも、マホはお礼を言い続けた。
高熱が続き、水分補給を続けた。うなされながら見た夢。ヤスキと一緒に子供に戻って、雨の中、水たまりを長靴でバシャバシャして遊んでいる。
(あれえ、ヤスキ、足が治ったんか。バシャバシャできるやん)
そこで目が覚めたが、どうも現実感のある夢だった。
(あの光景は覚えがある。夢じゃなくて――)
数日後、ようやく熱が下がり始め、マホはしっかりヤスキの存在を確かめた。
「なんだ、台風の目が情けない顔をして」
ヤスキが苦笑したが、ホッとしていた。
「そうかて……今回はしんどかったよ」
「日頃、元気な人がタマに調子崩すと、もうあかんって顔になるからな」
「もうあかんって顔してる?」
「してる、してる。してるけど顔だけで、マホは絶対大丈夫。もうあかん地獄からどうやってでも這い上がってくる」
マホも苦笑いした。
「畑の方はうまくいってるのやろか」
自分が指導した農作物の育ち具合が心配になってきたようだ。
「寝てる場合やないわ」
ガバッと元気よく起きた。
「まったくお前ってやつは。コンパスみたいに回転しながら描く渦巻みたいや」
「できるだけ、いろんなところでいろんな経験せんと気がすまへんのや」
「ええわ。俺が真ん中でどっしり重石になっておいてやるさかい」
「あれえ、ヤスキって私の重しになってたんかいな!」
ふたりは笑い合った。
シズルがマホの住まいへ入ってきた。ヤスキへしっかりお辞儀をしてから、にっこり笑って、
「作物なら、無事に育ってますから安心して下さい」
「ありがとうございます。身内に連絡までして下さって」
「お節介かな、と思ったんですけど」
「いえ、本当にありがとうございます」
河野シズルは頼れる男性だ。マホは「頼れる男性」に好感を持つ自分に驚いていた。
第 四 章 幼い頃の写真
ジカ熱が完治して数か月後、教師の資格試験のため、マホは日本に帰ることになった。
日本へ帰国するのが明日に迫ったある日、焼けつく東南アジアの大地が夕陽に染まる頃である。シズルがいつになく真面目な顔でマホを呼び出した。
「どうしたんですか」
「あの、あの、そのだな……」
「え?」
「あんたがコンパス持ってるわけは分かってる。ヤスキくんがコンパスを使って描いた円の中心で正座して、行動を見守ってるからだろ。ふたりはそれで通じ合ってるんだな」
「どうして、それを」
「分かるよ。君たちを見てると」
マホは呆然としていた。
「邪魔者だとは思うけど、そのコンパス、俺に任せてもらえないだろうか。俺も正座する」
「え……」
「返事は急がないから」
それだけ言うと、踵を返そうとする。
「あ、待って」
自分でも信じられない言葉がマホの口をついて出ていた。
「コンパスはシズルさんが持っていて下さい。正座して待っていて下さい」
「僕がコンパス、持っていいの?」
マホは恥じらいながら頷いた。
マホが日本へ帰った時、ヤスキは別の大学で学んでいた。ある秋の日、彼が欠席していると聞いた。
マホがメールしてみても、
「どうもない、どうもない、ちょっと風邪気味なだけや」
と、返信があるだけだ。その後、数日間大学に復帰したとも報告がないまま過ぎていた。
ヤスキの家を訪問してみた。子供の頃以来だ。
母親が出てきたが、どうも顔色が冴えない。部屋へ行ってみると彼はベッドに横になっていた。
「ヤスキ。寝ていなきゃならないほど、具合が悪いの?」
「そんなに心配せんでもええ」
とは言っても、ベッドの横に置いてある食事はほとんど進んでいないようだし、頬も少しこけたようだ。
窓の外のドングリの実がたわわに実って、どんどん地面に落ちている。
「お寺のドングリ、よく拾ったな」
ヤスキがポツンと言った。その横顔がとても寂しそうだ。
「実は、俺も教師になりたかったんや」
ヤスキから聞く初めての言葉だった。
「小、中学校の理科の教師に」
「理科の先生、それは面白そうやわ。で、その夢は~~」
「結局、車椅子通学になるさかい諦めたけどな」
「そんな。今は車かて運転できるし、細かいことは友達が手伝うてくれるやないの」
「そこまで甘えてええのかなって」
「ええねんよ、ヤスキは友達に甘えても」
思わず言い返したマホの頬に涙が溢れた。
「周りの友達は、皆、ヤスキのことを分かっているさかい、甘えてええのんや」
「ありがとう」
透き通るような優しい笑顔でヤスキは答えた。
居間に降りてくると、ふと古い写真立てが目についた。幼いヤスキとマホが並んで立っている。神社の脇の雨上がり、水たまりの真ん中で。ヤスキはちゃんと立っている!
「あ、」
ヤスキの母親が慌ててそれを取り上げた。
「ごめんなさい、古いから埃が……」
「おばさん、それって、私たちが幼稚園前の写真やね。ヤスキは立って……」
「いえ、さあ、マホちゃんは忙しいでしょ、今日はお見舞いありがとう。ヤスキはそのうちよくなるから心配しないで」
背中から押されるようにヤスキの家を出ることになった。
(さっきの写真……)
確かにヤスキは立っていた。
(足が立たなくなったのは病気のためだと聞いていたけど)
気にならずにいられなかった。
第 五 章 雨あがりの出来事
ヤスキの回復もはっきりしないまま、日本を離れる日が来て、ぎりぎりになって、マホは幼い頃を過ごした寺へ走っていった。
「ご住職さん、ご住職さ~~~ん!」
「はいはい、おや、誰かと思えば、お転婆マホじゃないか」
ご住職は作務衣姿で出てきた。
「どうしたんじゃ? そんなに慌てて」
「教えて下さい! ヤスキの足が不自由になったのは、いつなのか」
「ふむ?」
マホは急いで廊下に上がり、ご住職にしっかり正座して何度も頭を下げた。
ご住職は、
「仕方ないのう、マホもいつまでも子供ではないから」
寺の座敷に上がるよう言われた。小学生だった昔、皆で勉強した部屋だ。
「まあ、お茶でも飲みなさい。落ち着くから」
「教えて下さい。うちの親にも、ヤスキのご両親にも聞くのが躊躇われて……。ご住職さまならご存知かと」
「……」
大きなため息をひとつしてから、ご住職は口を開いた。
「幼稚園に登園してくる時の出来事だったと聞いておる。お前とヤスキがふたり連れでな……」
「で……」
「雨上がりの朝じゃった。お前は水たまりでバシャバシャするのが好きでのう、ヤスキが行こうと言っているのに、いつまでもやっていたそうじゃ。そこへ脇見運転の軽自動車が突っ込んだ……」
「!」
「ヤスキが必死で走って車の前からお前を突き飛ばした」
「え……」
「お前はかすり傷だけで無事、そしてヤスキは」
「ヤスキは?」
「足を怪我して麻痺が残ってしまったんじゃ」
「ああ……」
マホの瞳は空を見つめた。
お寺から帰宅して、マホは自分の部屋に閉じこもった。
「今日の出発はどうするの?」
「延期する!」
夕暮れ、母親が夕飯を告げる声にも微動だにしなかった。机に向かって正座し、本棚を見つめていた。
(ヤスキは覚えていたんだ……。事故のことを)
本棚の間に幼稚園の頃のふたりの写真を飾った写真立てがある。そのヤスキは車椅子に乗っている。
(私が……私が、ヤスキの足をこんな風に……)
真っ暗になるまでじっとしてると、母親が部屋に入ってきた。
「マホ。知ってしもたんやねえ」
「お母さん!」
マホはとっさに母親の胸に飛び込んだ。
「どうしよう、私がヤスキの一生を狂わせてしもたやなんて知らんかった……。私だけ自由なことをやりたい放題やって、世界中、好きなところへ行って。ヤスキはどう思ってたんやろ。私はどうやってお詫びしたらええのん?」
「マホ……。事故やったんや。あんたが悪かったわけやない」
「いくつもやりたいこと、諦めたんやろね……」
「マホ、あんたがお詫びしたりしたら、きっとヤスキくんは怒り出すのと違うかな? お詫びしてほしいなんて思てないとお母さんは思うよ」
母親に泣き笑いしながら顔を覗き込まれて、よけい涙が溢れる。
「それに、事故に遭ってからでもきれいな正座ができるって、ご住職に褒められたそうや。よっぽど心の芯が強いのやろなあって」
「正座を褒められた……」
その言葉を聞いて、心の奥に落とされた重石が少し軽くなったような気がした。
しかし、ヤスキには、もうひとつ伝えなければならない大切なことがある。シズルのことだ。彼とは連絡を取り合って将来のことまで約束している。何も知らないヤスキは、まだマホのコンパスの軸を握っていると思っている。
「私ってなんてひどい人間なの。ヤスキの足をあんな風にしておいて、心まで裏切るなんて」
第 六 章 共に
秋が深まってきたある日、マホの家のチャイムが鳴った。
母親が出てきて迎えてくれた。
「マホ、マホ。ヤスキくんよ! 早く降りていらっしゃい」
急いで降りていくと玄関先の庭に車椅子を止めて、もみじを見上げていた。もみじは紅く色づいている。
「教師の仕事、延期したって?」
振り向くなり、ヤスキは不機嫌そうに言った。
「それより、ヤスキ、身体の具合は?」
「風邪が長引いてただけや。……マホらしくないな。赴任地が南極でも北極でもいっぺん決めたら絶対行くくせに」
何も答えられなかった。ヤスキの足を不自由にさせたのが、自分であったことを知って、赴任地へ行くのを延期したとは。
「私かて鋼鉄人間やない。いつでもスタンバイオーケーやないもん」
「どうした、子供みたいに」
「まあ、ええやないの。中に入りましょ。寒くなってきたわ」
ふたりは居間に座ってコーヒーを味わった。
「私ね、決めたの」
「何を?」
「コンパスの外側へ出かける時も、これからはヤスキと一緒だって」
「ええ?」
「理科の先生になりたかったんでしょ。なら、赴任地へ一緒に行きましょう」
「ええ? ちょっと待って」
コーヒーを吹きそうになって、ヤスキの手元がガシャリと鳴った。
「本気で言ってるのかい? 僕はお前みたいに元気で動き回れないんだよ」
「人間、熱意よ。ハンデがあったってヤスキならやれる。外国の子どもたちにも好かれるわ。教師がやるべきことは知識を授けることより、子供たちと信頼感を持つことよね。ご住職はじめ、今まで出会った先生に教わったわ」
「マホ……」
ヤスキはびっくりした瞳になって、
「気持ちは有難いけど、これから理科の教師免状を取るのは大変だ。どうだろう、僕はご住職に教わったように、日本の正座を外国の子供たちに教えるってのは。床を作って座布団も作ろう。それなら畳の無い国の子だって練習できるだろう」
「ヤスキ! それ、ええやん!」
ヤスキは微笑んだ。
第 七 章 南国の正座教室
それから三か月後、マホとヤスキは東南アジアの小さな島に出発した。思わぬ人物が同行することになった。お寺のご住職だ。
「正座を教えるなら、拙僧も是非一緒に」
ということで、お寺は弟子に任せてついてきた。
首都のジャカルタから遠く離れているため、船を乗り継いでの旅になった。
島に到着する時は、渡し船のように小さな船だ。
一周するのに丸一日かからないような小さな島だが、ジャングルがこんもり繁っている。現地の村人は百人くらいだ。
マホは今まで後進国に行った経験があるが、ヤスキは初めてだ。ご住職も、もちろん初めてだと思っていたら、学生時代、多いにネイチャーを味わったそうで、未開の地が大好きなんだそうだ。カヌーだってお手の物だ。
「まだまだ、お前たちには負けんぞ!」
ボランティアの若者も数人、同行していた。
学校とは名ばかりの、板張りだけで壁がない屋根に大きな南洋植物の葉っぱを乗せたような建物が「学校」と呼ばれていた。
そこへ板が張られて、日本から運ばれてきた「タタミ」という重い敷物が敷かれた。全部で五十枚くらいか。一度は重みで床が抜けてしまった! が、若者ボランティアたちは、あっという間に元通りにして、子供たちを驚かせた。
さて、畳の上に座布団を敷いて、正座のお稽古が始まった。子供たちの最初の反応は、
「ええ? 足を折り曲げて座るの?」
「足の下に足を敷くの? 痛いよ!」
などと不平を洩らしていたが、マホとご住職がゆっくり教えた。
「だんだん出来るようになるよ。背中が真っ直ぐになってやる気力が湧いてくるから」
落ち着かずに足を動かしたり伸ばしたりしていた子どもたちが、だんだんおとなしくなってきた。
南国の正座教室はゆっくり軌道に乗り始めた。子供たちの親たちからも注目され、本島のメディアが取材に来た。
「子供が先生の言うことをきくようになりましてね」
ある母親が満面の笑顔でインタビューに答えた。
「ホホホ。日本の正座がジャングルの中で子供たちに通用するとはのう」
ご住職は誇らしげに笑った。
ちょうどその頃、マホの元へシズルからメールが来ていた。
『今度、お互いが日本に帰ったら式を挙げよう』
マホもそのつもりになっていた。ヤスキには申し訳ない、ヤスキの愛は十分感じている。でも、私はシズルさんと歩いていきたい、と。
第 八 章 コンパスを持つ人
一年後、マホとヤスキとご住職は正座教室を代理の人に任せて、日本に一時的に帰った。シズルも後進国から帰国したという報告が入った。
(幼なじみのヤスキと結ばれると思っているだろうな、周りの皆はどう思うかな)
しかし、自分の心に嘘はつけない。すっかり手に馴染んで古くなった革のコンパス入れを、コンパスごと握りしめた。
シズルが両親に挨拶に来る日がやってきた。
マホは自宅の庭先をうろうろ歩き回りながら、落ち着かなかった。
自惚れにもほどがあるが、このことを知ったらヤスキはどんなに傷つくか……。
シズルの車が近づいてきた。秋の陽の中、幸せを運んでくるように。シズルの屈託ない日に焼けた顔がネクタイを締めて玄関先の車から降りてきた。
「やあ、久しぶり」
「……」
マホは笑顔になれない。
「元気そうだね」
「……」
「ご両親は、家の中? まだ何も話してないよね、僕たちのこと」
「……」
(シズルさんがこのまま家で両親と会って、とんとん拍子にことが運べば……。永遠にヤスキとはお別れ。いつも見守ってくれたヤスキの気持ちは……)
思いつめて、マホは顔を背けた。
(あんなに会いたかったシズルさんじゃないの。でも……でも……)
シズルが玄関に入ろうと二、三歩進めた。
「だめっ」
急にマホは引き留めて立ちはだかった。
コンパスを胸の辺りで握りしめ、革のケースをゆっくり取り去り、シズルに突き出した。
「ごめんなさい。だめなの」
「……」
少し考えて、シズルは苦笑した。
「やはり、僕の負けか」
「ごめんなさい……。私……やっぱり」
この場になってみて、思い浮かぶのはヤスキのことばかりだ。
「いいよ。マホ。謝らなくて。分かっていたことだ」
革のケースを受け取った。
「ありがとう、シズルさん」
頭を深く下げるなり、マホは走り出した。行き慣れたお寺へ。
寺の勉強部屋にはヤスキが凛とした正座姿で机に向かっていた。マホを見ると不思議そうに顔を上げた。
「これの中心で正座して。あなたでなくちゃだめなの。やっと迷いが吹っ切れたわ。コンパスの中心で正座して待っていてくれるのはヤスキだけ」
揺らぐ足で立ちかけたヤスキを抑えるように、その場に今までで一番誇れる正座をして、コンパスを差し出した。小学生の頃から使い込んだコンパスを、ヤスキの大きな手が受け取った。
「ご住職仕込みの素晴らしい正座やな。やっと帰ってきたか」
「帰ってきたよ。ヤスキのところへ」
ヤスキの笑顔が涙で揺らいだ。








