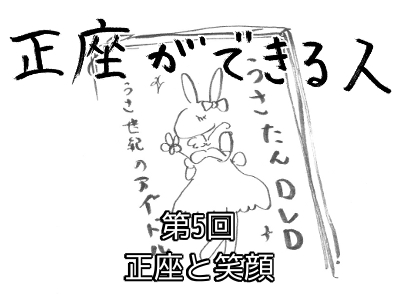[279]笛吹き姫の正座
 タイトル:笛吹き姫の正座
タイトル:笛吹き姫の正座
掲載日:2024/03/18
著者:海道 遠
イラスト:海道 遠
内容:
室町時代の守護大名四家の一家、因幡(いなば)家の当主と嫡男の吉祥丸(きっしょうまる)が、沼の周りを散策中、捨て子を見つけて拾って帰り、吉祥丸の妹として百姫と名づけられた。生まれつき目が不自由で身体の弱い子だった。
やがて吉祥丸は元服して景遠(かげとお)と名のる。百姫が三歳になった頃、見知らぬ笛吹き女が訪れ屋敷に滞在してもらい、笛とそのための正座を習う。

本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序章
緋色の毛氈(もうせん)の上に、篠笛(しのぶえ)が転がった。
「姫さま! 姫さま!」
侍女たちの悲鳴が上がる。
景遠(かげとお)が駆けつけた。毛氈の上にぐったりしている百姫(ひゃくひめ)の細い身体を抱き起こす。
「お百、いかがいたした! お百!」
百姫は兄の腕の中で、白い喉を見せてのけぞったままだ。
「早う、薬師(くすし)(医者)を呼べ!」
家来に腕を引っぱられてきた薬師が、姫の脈を診る。
(先ほどまで凜とした正座をして、笛を奏でていたというのに……)
景遠はじめ、乳母や侍女、家人まで遠巻きにして薬師が口を開くのを待った。
しかし――。
薬師は姫の身体を横たえ、首を横に振るだけだった。
桜色の唇はみるみる白くなっていく。
「お百! お百、しっかりいたせ。この兄を置いていくなどと、許さぬぞ、お百~~~~!」
景遠の男泣きの声が庭全体に響き渡った。
満開の桜が、一瞬にして墨色(すみいろ)に色褪せ(あせ)た。
第一章 百ヶ沼にて
艶やかな糸で刺繍を施された手毬(てまり)が庭の地面を転がる。
「そうれ、お百、手毬がお前の足元へ転がっていったぞ。捕まえてみよ」
「どこ? あ、捕まえた!」
「ようし、よくやった。今度はこちらへ、兄の声のする方へ転がしてみよ」
肩で髪を切りそろえた小さな少女は、花柄の桃色小袖に手毬を抱きしめてから、転がした。
「おお、ちゃんと転がってきた。ようやったぞ、お百」
手毬の相手は前髪のある少年である。
「おじょうずですよ。姫さま」
端で見ている乳母が手を叩く。幼い姫は嬉しそうににっこりした。
座敷からは、父親が見物している。
「吉祥丸(きっしょうまる)、お百、じゅうぶん遊んだであろう。座敷へ戻って休むがよい」
「はい、父上」
少年は父親の言葉に素直に従おうとしたが、幼い姫は、まだ遊び足りない。
「いやじゃ。お百は、もっと兄上さまと遊びたい」
「お百、お前は身体が弱い。汗をかいて、身体を冷やしてはならぬから、父上のおっしゃることを聞いて座敷へ戻ろう」
乳母が姫の着物を整えながらなだめる。
「わらび餅がございますよ。さあさ、お部屋へ戻りましょうね」
「うん。乳母や」
百姫はようやく庭から簀の子(すのこ)(縁側)に上がった。目が不自由だが、草履(ぞうり)を脱ぐ場所や簀の子の位置は分かっている。
兄の吉祥丸が妹姫の両手を布巾でぬぐってやる。
父親が目を細めて、
「吉祥丸はお百が可愛くてならぬ様子じゃのう」
「はい。たったひとりの妹ですから」
前髪の凛々しい少年は、十二、三歳か。甲斐甲斐しく(かいがいしく)姫の相手をしている。
「殿さまも、若君さまも、姫さまが可愛くてならぬご様子。百姫さまは、なんと果報者でいらっしゃるのでしょう」
乳母も兄弟の様子を見て、目を細めた。
室町幕府の守護大名である因幡(いなば)家の裏手には、百ヶ沼と呼ばれる大きな沼が広がっていた。
青みどり色の底には、大きなヌシの金色の鯉が棲んでいて、昔から因幡家を守っているという言い伝えがある。
気晴らしに遠乗りする時には、沼の周りを一周するのが決まりになっていた。
吉祥丸が十歳の時、親子がいつものように馬に乗り、散策していると、沼の畔の草むらから赤子の鳴き声が聞こえた。
父親が草むらを分け入ってみると、藁で編まれたチグラの中で弱々しく泣いている赤子が見つかった。
「父上、赤ん坊ですか?」
「どうやら捨て子のようじゃ」
「さぞや飢えておりましょう。屋敷に連れ帰りましょう」
吉祥丸の瞳が輝いた。
百ヶ沼の畔で拾われたおなごの赤ん坊は、「百姫」と名づけられ、因幡家で吉祥丸の妹として育てられることになった。
吉祥丸は生まれた時に母親を亡くし、兄弟がいなかったので妹ができてたいそう喜んだ。何の因果か、百姫は生まれつき目が不自由だったが、父親と兄の愛情を一身に受けてすくすくと育った。
時は室町の世である。
百姫が拾われた因幡家は、将軍が任じた守護大名家であった。
百姫が三歳になり、しばらくして嫡男の吉祥丸は元服を終え、名を景遠と改めた。
守護大名家の嫡男として、若輩ながら威風堂々とした若武者ぶりに、元服に出席した姻戚(いんせき)関係の者や家人たちは、魅了されてため息をつき、父親も満足げに見やった。
同時に、因幡家当主が都詰めとなる間の守護代である桐生氏(きりゅうし)の娘、お杣(そま)との縁組が決まった。
第二章 笛吹き女(ふえふきめ)
ある日、座敷で侍女と遊んでいた百姫は、美しい音色がどこからか聞こえてくることに気がついた。
小さなお道具での雛遊びの手を止め、
「あの音は?」
「篠笛の音色でございますね。どなたが吹いておられるのでしょうね」
「なんてきれいな音かしら」
そこへ、乳母が部屋へやってきた。
「あれは、身分のいやしき笛吹き女の笛の音です。門番が何度、追いはらってもやってくるそうですよ」
「でも、夢のようなきれいな音だわ」
姫はうっとりして言った。
「乳母や、お願い。その笛吹き女をこちらに呼んでちょうだい」
「姫さま、とんでもございません。どこの誰とも分からぬ者でございますよ」
「お願いじゃ。笛をもっと近くで聞いてみたい」
笛吹き女は、大道芸人のように奇抜な髪型に結っていた。着物はまるで唐土(もろこし)の民族衣装のようなので、乳母や侍女が透垣(すいがき)(生垣)越しに恐る恐る話しかけると、にっこり笑って庭先まで入ってきた。
「姫さまのご所望とあらば、喜んで吹かせていただきます」
どういう身分の者かは判らないが、明瞭な大和言葉で、気品ある言葉遣いと顔立ちである。乳母は心を許して百姫が座る簀の子に呼び寄せた。
笛吹き女は、手にしていた笛を口元に構えた。みるみる美しい調べが奏でられる。
「乳母や。気持ちのよい音色じゃのう」
百姫はすっかり笛の虜(とりこ)になってしまった。
乳母は因幡家当主の許可を得て、笛吹き女を、しばらく屋敷に逗留(とうりゅう)(滞在)させることにした。
ほどなく百姫は、自分でも笛を吹きたいと言い出した。笛吹き女は快く引き受けて、幼い姫に笛の持ち方の前に座り方を教えた。
「笛をしっかり持つためには、しっかりした座り方をせねばなりませぬ」
座敷で笛吹き女と百姫は、向かい合って立った。
「背すじを直ぐにお立ちくださいませ。次に床に膝を着かれて。お着物はお尻の下に敷きながら、かかとの上に座ります」
小さな膝を折って、百姫は一生懸命に座った。
「おじょうずにお座りになれましたね、姫さま。この座り方が、正座と申します。しっかりお座りできれば、笛もぐらぐらと動いたりしませぬから。……次に笛の持ち方をお教えしましょう」
笛吹き女は、幼い姫に丁寧に笛の指導をした。
父親や兄の景遠ばかりでなく、家来や下仕えの女まで、繊細で流麗(りゅうれい)な音色に心を癒された。
笛吹き女に指導を受ける百姫の姿を、庭の透垣越しに景遠は、そっと窺いに来たほどだ。
「習い事には、まだまだ早いお齢(とし)でおられるのに、怜悧(れいり)な姫さまじゃこと」
「かな文字のお稽古も始められたとか」
侍女たちは、感心する日々を送った。
庭に面した座敷で、凜とした正座をして篠笛を吹く姿は、生まれついての武家の娘であるかのように毅然としていた。
しかし、身体の弱い娘で、幼い頃から熱を出して寝こむことが多い。
景遠は、屋敷の外には一歩も出さず、夏の暑さや冬の厳しい寒さからも、季節の変わり目の体調を崩しやすい時も、姫のための環境に抜かりのないよう側仕えの者に言いつけた。
(こわれものを扱うようとは、このことを言うのですね)
(ほんに、殿様は、百姫さまをお目に入れても痛くないような可愛がりようで……)
侍女たちは噂した。
笛吹き女は、しばらく滞在してから、礼を言って去って行った。
第三章 お杣(そま)の方
やがて――。
百姫は十六歳になり、武家の子女の慣わしである「鬢(びん)削ぎの儀式」が六月十六日に執り行われた。
義兄の景遠が鬢の髪にかみそりを当て、毛先を削いだ。
平安時代に行われた慣例では恵方(えほう)を向いて置かれた碁盤の上に立って行われるのだが、百姫の希望で碁盤の上に正座して愛用の篠笛を持って行われた。
狭い碁盤の上でも、正確に正座の所作をして座り、笛を手にした百姫の姿は神々しくさえあった。
鬢を削ぎ終えた百姫は、白い頬にかかる削いだ黒髪が一段と大人びて見えた。
「これはこれは。近寄りがたくなったかのう」
景遠が、からかうように言った。
「自分では髪の削ぎ方が見えぬゆえ、歯がゆい思いです」
決して恨み事ではなく照れて言った言葉なのだが、景遠は、不憫に思うのだった。
やがて、約定通り、桐生氏から一の姫である杣姫が景遠の元へ輿入れしてきた。
つづら折れの山道を雅やかな花嫁行列が連なり、たくさんの花嫁道具が因幡家の屋敷に運びこまれた。
百姫が侍女から聞いた話では、新郎の景遠は白い狩衣、花嫁の杣姫も純白の打ち掛け姿で、恭しく夫婦の儀が執り行われた。
華やかな宴が三日三晩続けられた。
百姫の住まう奥の館にも、風に乗って賑やかな舞の気配や鼓(つづみ)の音、婚礼を祝う人々の笑いさざめく声が聞こえてきた。
「兄上さまの元に、美しい花嫁が来られたとか。どのようなお人でありましょう」
「寂しゅう思われることはございませぬ。殿は、姫さまが一番大切なのですから」
乳母は胸を張って言った。
「……そのようなことは心配していないわ。義姉になる方と仲良うやっていきたいだけ」
百姫は、ぼんやりと宴の聞こえる方角に顔を向けていた。
やがて、お杣の方に姫が生まれたが、景遠の百姫への手厚い配慮は変わりなく続けられた。
お杣の方は、産屋(うぶや)にいる時も奥屋敷に戻ってからも、生まれた姫と侍女たちだけで過ごすことが多かった。
「殿は、どちらにおいでか」
尋ねる度に、侍女の答えはいつも同じであった。
「百姫さまの元へお越しでございます」
「お目のご不自由な妹さまのことを、よほど心配しておられると見える」
お杣の方が、機嫌を損ねていたのも無理からぬことだったが、気位が高く、侍女にはおおらかな様子しか見せなかった。
それでも、すやすやと眠る赤子の邑姫(ゆうひめ)を見やり、ため息をついてもらす。
「殿も、たまには邑姫のお顔を見に来てくださらぬかのう」
そんなことと気づいていない百姫は、邑姫が三歳くらいになると、正座を教えたいと言い出した。
その旨、侍女からお杣の方付きの侍女へ伝えると、
「ありがとうございます。近くにお伺いします」
快い返事が来た。
当日、百姫はわくわくして邑姫を待っていた。
赤子の時に初対面の挨拶に伺い、邑姫のむずかる声を少し聞いただけでそれきり会っていない。
(どのような子にお育ちなのであろう)
お杣の方と共にやってきた小さな邑姫は黒々と艶のある振り分け髪が可愛らしく、百姫の前に座り、
「よろしゅうお願い申します。百姫さま」
あどけない声ながら、しっかり挨拶した。
「こちらこそよろしゅうお願いいたします、邑姫さま」
両手を受けるように差し出すと、小さな手のひらが重ねられた。百姫は微笑んで稽古を始めた。
所作は、百姫が幼い時に訪れた笛吹き女から教わったものである。
「邑姫さま、背すじを真っ直ぐに立ちます。できましたか。次は床に膝を着いて。お召し物はお尻の下に敷いて、かかとの上にゆっくり座ります。できましたか?」
侍女が代わりに見届けて「おできになりました」と答えると、百姫は、にっこり微笑んで褒めた。
「ようおできになられました。お忘れになられませぬよう」
「はい。百姫さま」
愛らしい返事が返ってくる。
「母上さまもお稽古いたしましょうよ」
邑姫のおねだりで、お杣の方も立ち上がった。
「これは、義姉上さま。よろしゅうお願いいたします」
所作の指導をすると、お杣の方は打掛を優雅に裾さばきして鮮やかな所作をこなし、正座した。
「さすがのご所作、さすがの背すじの伸び方でございますな」
百姫が褒めた。
「まるでお目が見えるようじゃのう、百姫さま」
「お打掛の衣ずれの音でお察しできます」
百姫は難なくお見通しのようだった。
邑姫は優しい百姫になつき、それから時々は楽しいひと時を共に過ごした。
第四章 悲しみ
因幡家当主の父親がにわか病(やまい)を得て亡くなり、景遠が家督を相続した。
亡くなる直前に父親は、枕元に景遠と近侍(きんじ)(側で仕える者)を呼び寄せた。苦しい息の下から、父親はすがるように息子の手を握りしめ、
「景遠、そちは太平の世に生まれにて、戦を知らぬ」
「父上、しっかりなさってくださいませ」
「よいか、近き周りの者にこそ油断するでないぞ。気を許してはならぬぞ。……とりわけ、そちは穏やかな性格じゃ。人を信じすぎるきらいがあるからのう」
かたわらから、代々仕えている守護職補佐役の老人が、
「殿。わしら古参の者が、きっと若様をお守りいたしますぞ」
父親は小刻みにうなずいた。
「頼むぞ、景遠を……」
景遠がつかんでいた手から、父親の腕が力なく落ちた。
ひと通りの法要がすむと、景遠は都へ上洛し、将軍から改めて守護職に任じられた。
因幡家で祝いの宴が催され、百姫が篠笛を吹くことになった。ちょうど桜が満開になった春の日である。
笛を奏でている最中に――。
百姫は突如、気を失い、そのまま呆気なくみまかった。(=亡くなった)愛用の篠笛が庭の毛氈の上に転がったままになった。
百姫の乳母は、一気に歳をとったように白髪が増え、毎日、侍女たちと共に泣き暮らした。
「百姫さまに、なんとかこの美しい山々や、青い空や、百ヶ沼の青みどりの輝く水面を見ていただきとうございました」
景遠は、年老いた乳母の肩に手を置き、共に嘆いた。
「乳母。そなたは、お百をよう世話してやってくれた。礼を申すぞ」
「もったいのうございます。殿さま」
百姫の過ごした離れの床の間には、笛が遺されていた。空でさえ輝きを失くしたように暗く重い日々が続いた。
景遠は、朝な夕なに沼の畔へ出かけ、亡き妹の面影を追った。
夕暮れ時、鳥の群れが森の中へ帰っていくのを仰ぎ見ていると、今にも百姫の声が聞こえてきそうに思える。
そのうち、百姫を思う気持ちは妹へのそれではなく、ひとりの女人を思う気持ちであったと気づいたのだった。
(お百、この兄は、いや景遠はそなたひとりを生涯の連れ合いとして添いたかったぞ……)
奥方のお杣の方は、夫の気持ちをとっくに察していた。
百姫の愛用の篠笛の音が聞こえてくる。景遠が吹いているのだ。
(百姫、亡くなられてなお、わらわを苦しめられるのか――)
お杣の方の胸の奥は嫉妬の炎で満ちていた。
そんなある日、お杣の方の父親である桐生氏が訪ねてきた。
景遠に拝謁し、先代当主の位牌に線香を手向けた後、娘の住まう奥座敷にやってきた。
すでに夜になっていた。紙燭(ししょく)の炎が薄暗く燃える。
「お杣、達者かな。孫姫のお邑も」
隣室で幼い邑姫は、大人たちの思いも知らず、すやすやと眠っていた。
「実は、そなたに頼みがあってな。この薬を――」
ふところから白い紙に包んだ薬を取り出した。
「少しずつ、ご膳の料理に入れてはくれまいか」
「父上、それは何の……」
桐生氏の白髪の混じった眉が厳めしく寄せられた。が、すぐに眉を開き、
「いや、なに、大陸伝来の滋養強壮薬じゃ。因幡の殿にはご健勝でおいでいただかなくてはのう」
桐生氏は言い足したが、お杣には父親の思惑が、直ぐに感じられた。
「父上、まさか、まさか、それは――」
桐生氏が、密かに守護職の座を狙っていることをお杣は知っている。
(いかがわしい薬を景遠の膳に入れることなど――)
「いやでございます。わらわは、そんなつもりなど毛頭ございませぬ」
お杣はきっぱり言った。
「お杣。わしの耳にも入っておるぞ。そなたは、さんざん屈辱を受けてきたではないか。正室を差し置いて、妹の部屋にばかり通っていた夫が憎くはないのか?」
邑姫が布団の中で寝返りをうった。
お杣の方は、邑姫の枕元へ寄ろうと立ち上がりながら、もう一度拒絶した。
「父上。夜が更けてございます。お引き取りくださいませ」
「ふむ。まあよい」
口元に薄笑いを浮かべて、桐生氏は部屋を後にした。
何日かしてから、お杣の方は景遠から呼び出された。
景遠は言い出しにくそうにしていたが、やがて決心したようで、口を開いた。
「お杣、桐生の家へ帰ってはもらえぬか」
「殿!」
裏山の林に冷たい風が吹き抜けた。お杣の心は凍りついた。
「真実愛していたのは、お百ひとりだとようやく分かったのだ」
景遠の声には、愛情のひとかけらも感じられなかった。
(離縁を言い渡されるとは――)
その場にいたたまれず、お杣は立ち上がって濡れ縁に出て、うずくまった。艶やかな袖が、ぽとりぽとりと落ちる涙に濡れた。
(よくも長年にわたり、わらわをないがしろに――)
(百姫が亡くなった今になっても、こんな屈辱を受けねばならぬとは!)
怒りが稲妻のように全身を貫いた。
第五章 薬湯
邑姫が高熱を発して床についた。
薬師を呼んで診させたが原因が判らず、一向に薬も効かない。
景遠は国じゅうの薬師を呼び寄せ、お杣の方も心配して祈祷師に拝ませたりしたが、回復のきざしが見えない。小さな身体で高熱に苦しみながら伏せっている姿は、痛々しすぎる。
お杣の方の離縁の話は、何も進まないままに放置されていた。
夏の夕方。
遠くで鳴っていた雷が近づきつつあり、空は薄暗くなってきた。その日も景遠は、悠姫の枕元で水桶に浸した手ぬぐいを絞って姫の額に当てるなど看病をしていた。
お杣の方が薬湯(やくとう)を持って入ってきた。
邑姫の寝床のかたわらに静かに座る。邑姫や百姫と共に稽古した正座の所作で座った。いつの間にか身に沁みこんでいたようだ。
看病疲れから脇息にもたれて、うたた寝をしていた景遠が目を覚ませた。
「ああ、いつの間にか寝てしもうていたようじゃ」
重そうな頭を振る。
「さぞやお疲れでございましょう。薬湯をお持ちしました。どうぞ召し上がれ」
いつになく優しいお杣の方から薬湯の入った湯呑みを受け取った。
それを口元へ持っていく――。
雷が真上まで接近して、部屋に稲光が閃いた。
「なりませぬ!」
激しい口調に、思わず景遠が顔を上げると、褥(しとね)(=布団)の上に邑姫が立ち上がっているではないか。
「邑姫?」
「その薬湯をお飲みになってはなりませぬ! その湯呑みには、毒が……」
稲光が邑姫の顔を浮かび上がらせた。その面差しは、邑姫ではなく、百姫そのものだ。景遠は思わず薬湯の湯呑みを床に落としてしまった。畳から「ジュッ」という音がして、煙が立ちあがった。
「義姉上さま……」
声もまた、百姫の声だ。
「わらわだけでなく、兄上さまのお命まで奪おうと……。許せませぬ!」
見開いた瞳は、深い青色ではないか。水の世界に棲むものの色である。
耳をつんざく雷が鳴りひびき、篠突くような雨が降り出した。
お杣の方は恐ろしさのあまり、ひれ伏した。
「ひぃっ、お許し……お許しくださいませ」
身体をがたがた震わせている。
景遠が近づいてお杣の方の肩を抱き寄せた。
「百姫、もうよかろう。お家同士の決めた相手ではあるが、お杣は余のたったひとりの妻じゃ。どうか許してやってほしい」
「兄上さま……」
「余が頭を下げる。お杣は心を入れ替えるであろう」
百姫は青い瞳を閉じて黙りこむ。その瞬間、気配がかき消えた。
景遠が急いで障子を開け、雨の中へ飛び出していった。
「百姫! いずこへ行く!」
お杣の方は、打ちひしがれて邑姫の小さな身体を抱きしめた。
第六章 別れ
景遠は馬にまたがり、百ヶ沼へと急いだ。
そぼつく雨の中、沼の周りには一面の葦(あし)が生えている。沼の畔に立つ人影を見つけ、景遠は馬を下りた。
「お百!」
振り向いたのは、生前そのままの美しい百姫であった。しかもつぶらな瞳を開けて微笑んでいる。
「そなた、目が見えるのか」
百姫は悲しそうに首を横に振った。
景遠は百姫を抱きしめた。強く強く、どこへも行かないよう、しかし力を入れては消えてしまいそうなので、そっと腕を緩める。
「赤ん坊の頃から慈しんで育てていただき……できることなら、ずっと兄上の側にいたかった……」
「お百……」
「しかし、もう時刻(とき)が来たようです」
「時刻とは?」
沼の中央から、一艘の小舟が近づいてきた。ひとりの女が乗っている。静かに船着き場に小舟を寄せた。小舟を漕いできたのは、かつて幼かった百姫に笛と正座を教えた奇妙な身なりの笛吹き女ではないか。被っていた市女笠(いちめがさ)をひょいと傾けて顔を見せた。
「姫さま、お迎えに参りました」
女の言葉にうなずき、百姫は景遠の腕をすり抜けて小舟に乗る。
「お百、行ってしまうのか」
「はい。行かねばなりませぬ。……我が役目を果たさねばなりませぬ」
帯にはさんでいた篠笛を抜き取ると、小舟の上にかつて習った所作の正座で座った。笛を構えて口まで持っていく。
雨が小降りになり、沼の上を、か細い笛の音がただよう。なんと物悲しく流麗な調べであろう。
「お百―――!」
小舟は岸を離れ漕ぎ出されていく。やがて舟の影は、濃い霧の中へ没して見えなくなった。
第七章 謀反の果て
翌年、守護代を務めていた桐生氏が謀反を起こした。
宵の刻、奥屋敷で読み物をしていた景遠は、物々しい気配に立ち上がった。
同時に側近の者が廊下を駆けてきて、ひざまずいた。
「謀反でございます!」
「だ、誰じゃ」
「桐生氏でございます。山の麓(ふもと)に夥しい兵馬が押し寄せております!」
「桐生氏だとっ? ま、まさか」
景遠は蒼白になった。
「わが因幡守護大名の代理を務める桐生氏が――!」
景遠の元へ古参の家人が血相を変えて集まってきた。
「迎え討て! 急ぎ、兵を集めよ!」
家来に甲冑をつけさせるのももどかしく、景遠は叫んだ。
父親が身まかる際の言葉が思い出された。
『近き周りの者にこそ、油断するでない』
景遠は大変な苦戦を強いられた。
桐生氏が謀反の旗揚げをしたのは、病で倒れたとの知らせが入り、お杣の方と邑姫の迎えの駕籠がやってきて、館に運ばれていった直後のことである。
娘と孫娘を因幡家が人質にできないよう、先に手を打ったのだ。
「謀ったな……」
景遠の拳が握りしめられ震えた。
また、桐生氏は、実の娘と孫娘といえど、戦に勝つためなら命を奪いかねない冷酷な男であった。
桐生勢は、因幡の城を取り巻いた。火矢が雨のように打ち込まれ、城の一部に燃え移った。軍勢の声や甲冑(かっちゅう)の触れ合う音、馬のいななき、馬蹄音に包まれた。
「桐生氏……。ネズミ一匹逃さぬ構えだな」
戦のない世が続き、油断していたことを景遠は思い知った。幾日もしないうちに、城は占領された。
桐生氏の前に、後ろ手で縛られた景遠が引き立てられてきた。兜を脱がされ、黒髪は肩にざんばらに広がり鎧(よろい)のあちこちは裂けて顔面は血がにじんでいる。
景遠は、桐生氏を睨みつけた。
「桐生どの……。謀反人となって主君の城を奪った人間に、守護職が認められると思われるのか」
「ふふふ……」
ふてぶてしく、黄色い歯を見せて桐生氏は笑った。
「将軍家に余を推挙するよう、他の三家の守護大名にも申し合わせておる」
「なんと。そこまで手を回して……」
景遠の唇が、噛みしめられた。
桐生氏のことゆえ、手抜かりなく他の三家の弱みを握り、脅す手段にでも出たのかもしれない。
「お頭(つむり)の回る方が勝利するのじゃ。念のため、将軍家とも数年前に姻戚関係を結んでおる」
「……」
「景遠どの、その御首(みしるし)、頂戴つかまつる」
家来に指図が下された、その時――。
どこからか、か細い笛の音が流れてきた。
「おや?」
「因幡景遠は?」
家来が笛の音に気を取られたほんの一瞬の間に、景遠の姿は消えていた。いくら捜索しても行方は知れなかった。
第八章 真の別れ
桐生氏の戦勝の宴が因幡の城で開かれた。
庭には巨大な篝火がいくつも焚かれ、兵どもは酒宴を楽しんだ。
「我が桐生の完全な勝利じゃ。皆の者、存分に飲むがよい!」
家来や猿楽芸人が勝利の舞を謳歌している時――。
またもや、どこからか寥々(りょうりょう=むなしい)とした笛の音が聞こえてきた。
篠笛を吹きながら森の中から、中紅(なかくれない)のあでやかな小袖姿に黒髪の若い娘が、酒宴の場に近づいてくる。
「お武家さま方、ついて来られませ」
涼やかな声で誘われ、泥酔した兵士どもは、娘の後を追って歩き始めた。
(なんと美しいおなごじゃ)
(なんと心地好き笛の調べであろう)
呪術にかけられたように沼にいざなわれていき――、多くの兵士や大将の桐生氏までが、沼の中へ自ら踏み入り、没していったという。
皆が沈んでいった水面に金色の鯉が、ぱしゃりと跳ねたそうな。
景遠は、笛の音に気を取られた敵の油断をついて、家来に助けられて城の外へ脱出していた。
百が沼の畔に立ち、報告を受けた景遠の胸にひらめいたのは、金色の鯉と重なる百姫の面影であった。
ふと気配がして顔を上げると、いつぞや小舟に乗る百姫を見送った通りの姿があった。
「お百――」
百姫は濃いまつ毛を伏せたまま、
「景遠兄上さま、どうかお願いでございます。お杣姉上さまと邑姫さまをお迎えに行ってくだされませ。きっとお二方ともお待ちでありましょう」
「……分かった。きっとそういたそう。……お百、お前はいずこへ?」
「人々が穏やかでいるために、沼の鯉の魂に戻りましても旅をして、正座で笛を吹き続けます。――今度こそ真のお別れにございます。どうぞ、息災で因幡家の大将としてお暮しくださいませ」
あの時のように、市女笠の女が小舟の上に座して待っている。百姫は音もたてず小舟に乗った。
(お百――。余の命と因幡家を救うために戻ってくれたのか――。感謝するぞ――)
景遠は離れていく小舟に向かって畔に正座し、合掌して見送った。