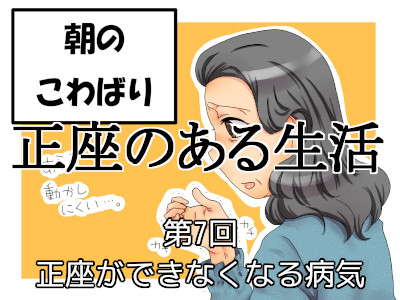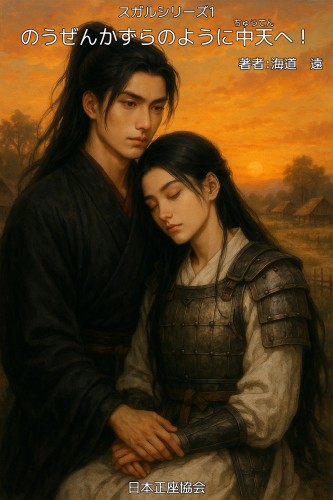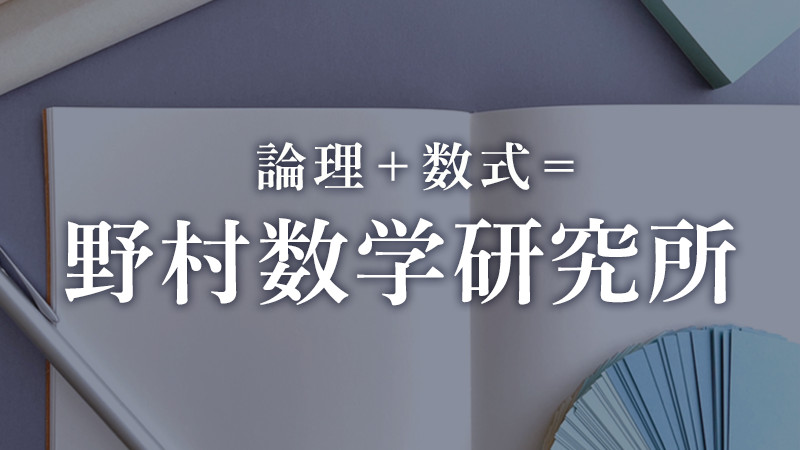[350]お江戸正座24
タイトル:お江戸正座24
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:24
掲載日:2025/04/17
著者:虹海 美野
あらすじ:
おはるは商家のお内儀さんで手習いに通う子がいる。
ある日、昔お武家様で行儀見習いのご奉公を一緒にしていたおようと再会する。
おようは戯作者の諏訪理田と夫婦になり、家で行儀見習いの教室を開いているが、臨月であった。
お教室をできるだけ休まず続けると言うおように、昔の恩もありおはるは教室の手伝いを申し出た。
正座の仕方や襖の開け閉めなどの稽古をするおはるだが、ふとした発言が生徒たちには引っかかってしまい……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
おはるがおように再会したのは、水菓子屋(果物屋)であった。
夏の厳しい盛りで、どちらもすいかを買い求めていた。身重らしく、おなかが大きいのが先に目に入った。自身の経験からみて、もうすぐ臨月かしら、と思った。その人がすいかを買い求める声に、ふと覚えがあった。整った横顔を見つめ、おようちゃん……、と心の中で呟いた。
「もしかして、おようちゃん?」と、娘時代のように声をかけると、その上品でほっそりとした面(おもて)を上げたのは、やはりおようであった。
「おはるちゃん」と、おようも同様に、娘時代と同じ様子でおはるを呼んだ。
二人は近くの茶店で、買ったすいかを脇に置き、麦湯を頼んだ。
「本当に久しぶりね」
声を弾ませるおはるに、おようも頷く。
「おはるちゃん、今は?」
「息子と娘のどちらも手習いに行って、最近、こうして昼間は好きに過ごしているの」
「まあ」とおようは驚き、「早いものね。私は、この子が初めてなのよ」と、おなかを撫でた。
「そうなの」
おはるは喜びと驚きでおようを見た。
二人の出会いは、お武家様への行儀見習いを兼ねたご奉公であった。
おはるとおようは同じ時期にお武家様にご奉公し、年も同じであった。お武家様でのご奉公中、見るもの、聞くもの、初めてのものも多かった。お武家様にご奉公するのは、大概裕福な家の娘である。この先の縁談を考え、少しでも条件のよいところへ嫁げるようにという親心からだ。だから、江戸でのおしゃれやおいしいものを、おはるは結構知っていたし、ほかのご奉公する娘も同様であった。それでも、お武家様ならではの習慣なんかもあって、学ぶことは多かった。おはるにとって特に印象に残っているのは、美しい雛人形であった。なんと美しく、精巧なのだろうと思った。そうして、いつか、自分に娘が生まれたら、こんな雛人形を用意してやりたい、と夢見たのだった。
そんなふうに、やや浮足立つおはると違い、おようは大層勤勉にご奉公に励んだ。お武家様でご奉公する娘を指導するお方の中には、厳しい方や時には気性の激しい方もおられたが、おようは全く動じず、粛々と勤めに励んだ。
ある時、おはるが、『おようちゃんはどうしてそんなに忍耐強いの?』と尋ねると、『ここでのお勤めを終えたら、守りたいお人がいるの』と答えた。女忍にでもなるつもりか? と冗談半分に思ったが、おようはお勤めを終えると、諏訪理田という、当時殆ど江戸で知られていない戯作者と一緒になった。そうして、行儀見習いのお教室を開いた。
一方のおはるは、親の勧めで大きな商家に嫁いだ。
食べるのに困らず、炊事、洗濯もしなくてよい。
だが、やはり大きな家というのは、それだけ財を成し、守るための工夫、心がけがあって、若いご新造のおはるがあれがほしい、これがほしいと、好きにできるわけではなかった。取り立てて、贅沢をするつもりはないが、息子が生まれた際には端午の節句に盛大に祝ってもらい、祝いの品も届いたが、娘の桃の節句にひな人形は用意されなかった。娘が生まれた時にあのお武家様で見たような雛人形を買ってやりたいと思ったが、それは叶わなかった。持参金を充ててもよかったが、それも角が立つ。この家に入ったのだから、それに倣うべきで、まあ、どうにもならない無理難題というほどでもないので、それは心の内に収めた。
今では夫は若旦那から旦那になり、義理の両親は隠居生活に入り、息子、娘ともに手習いに通い、弁当も持参するので、朝から夕刻までは手が空くようになった。
だから、たまにこうして買い物がてらのんびりできるようになった。
その出先での、かつてのご奉公仲間との再会であった。
「おようちゃんは、お武家様で学んだことで、しっかり旦那さまを支えてきたのね。すごいわ。私は家でたまに娘に礼儀作法を教えるくらいで、全然……」
そう話ながら、おはるは娘のことを思い出す。
まだまだ幼いが、おはるが、正座をする時には着物をお尻の下に敷き、背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、手はは太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うようにし、足の親指同士が離れぬように、と教えると、はい、と居住まいを正す。息子もそれを見て、きちんと正座する。それは、おはるにとって、小さな幸せの時である。
「おはるちゃんがきちんとした娘さんだったからこそ、ご縁があって、今娘さんにもそれを伝えられているんだから、素晴らしいことよ」
そうきっぱりと言うおようは、相変わらず、如才なく、けれど温かい。
「ありがとう。そんなふうに言ってくれて……。おようちゃんはお教室を開いて生徒さんがいるのに」
そこまで話し、「そういえば、おようちゃん、赤さんが生まれたら、お教室はどうなさるの」と尋ねた。
おようは「ああ」とため息をつき、「生まれた日は、お教室は申し訳ないけどお休みしようと思うけど、その後は出来る限り生徒さんに迷惑をかけないように、これまで通りやっていきたいと思っているの。母には『それは無理だ』って。『ひと月は安静にしていないといけないから、その間は手伝いに行く』って言われてて、その時になってみないとなんとも」
「そう……」
おはるもそこでしんみりと頷く。
確かに子が生まれてすぐに動けるわけではない。
人によって違うだろうが、やはりゆっくり休めればその方がよいだろうし、子も暫くはいつおなかを空かせて泣くか、定まらぬ。
おはるの場合は女中さんもいたし、義理の母もずいぶんと面倒を見てくれた。だから、本当に上げ膳据え膳でゆっくりと休めた。だが、おようは旦那さんと二人暮らしのようだ。実のお母さんが手伝いに来てくれると言うのだから、洗濯や食事はまあ、大丈夫であろう。
だが、行儀見習いのお教室は……。
「ねえ、おようちゃん、差し出がましいけれど、もし、もしも、助けが必要なら言ってね。例えば、お教室の時に赤さんが泣いたら、その間の生徒さんの対応くらいなら、私でもできると思うの。この通り、私、今は昼間なら時間の自由も利くし、嫁いでから家のことをお義母さんに教わって、今ではもう任せてもらえているから、お店の内側のことさえしっかりやっていれば、出かけても大丈夫なのよ」
言いながら、おはるは、お武家様にご奉公をしている時、何度もおように助けられ、事なきを得たことを思い出していた。どうお礼をしようか、ご奉公が終わったら、お父ちゃん、お母ちゃんに訳を話して、何か少し値の張る贈り物でもしようか、と幾度も思った。だが、おようはご奉公が終わると、すぐに戯作者諏訪理田の元へ嫁いでしまった。人づてに聞いたが、おようは小さな家で夫と二人暮らし、行儀見習いの教室を開いていて、あれやこれやと着飾るものも求めてはいないようだ、ということだった。そうすると、どうしたものか、おはるにとっては嬉しい華やかな簪や、鮮やかな紅もあまり喜ばれぬかも知れぬし、着物も娘時代とは違ったものを好むようになったかも知れぬ、菓子とて、教室を開く師になったのだから、欲しければ自分で買えそうである。わざわざお礼だと持って行くのも気が引けた。結婚のお祝いに、と高価な食器を贈ることも考えたが、そうすると、おようのことだ、おはるが結婚した際にも同額、もしかしたらそれ以上の何かを贈るのは明らかだった。それでは、意味がないし、と悩みに悩み、何も返せず仕舞いになった。
そうして、その後おはるも縁談が決まり、それからは目まぐるしく忙しい日々で、それきりになっていた。
「おはるちゃん……、すごく嬉しいけれど、そんなこと、頼めないわ」
厳しい顔で首を横に振るおようの手を、おはるは取った。
「おようちゃん、じゃあ、私からのお願い。ぜひ、やらせてちょうだい。私、おようちゃんほど優秀じゃなかったけど、一応お武家様でご奉公したし、嫁ぎ先でもお商売を支える家のことは仕込まれたから、少しは役に立てると思うの。それを少しだけ、外の世界でも役立たせてもらえないかしら」
おようは驚いた顔をして、おはるを見た。
おはるは目を逸らさず、おようを見て頷いて見せた。
「本当に、いいの? もし、ご都合がつかなくなったり、疲れたりしたら、すぐに言ってくれると約束してくれる?」
やった、とおはるは心の内で叫び、大きく頷いた。
「もちろんよ。お武家様で、何度もおようちゃんに助けてもらったじゃない。私が助けを求めるのが得意なのは、おようちゃんもわかっているでしょう?」
「本当に、おはるちゃんは優しい。変わらないわ」
おようはそう言い、目尻を指先で拭いた。
そうして、そこからおようの『お願い』をおはるは具体的に聞き、了承した。
まず、お教室はおようが産気づいてから子が生まれた直後のお教室をおはる一人で、そこから三月ほどおようが子のために席を外している間を頼みたいということ。そうして、おはる一人にお願いする間は、お教室の生徒さんからの月謝の全額、おようが席を外している間を頼む期間は六割をおはるに渡したい、ということだった。月謝に関しては、おはるは頑なに断ったが、月謝を受け取ってもらえないと、こちらも頼みづらい、とおようは譲らなかった。それで、おはるがもしお教室の手伝いに行けなかった日は、その分を引いてもらう、という条件で、三月の間、お教室の手伝いに行くことが決まった。
2
さて、こうしておはるが行儀見習いの教室に師として、否、その手助けとして、とにかく勤めに行く日がやって来た。
子どもたちが帰って来るまでにお教室は終わっているが、一応、今日はお母ちゃんはお教室に行っていますからね、と伝えた。
場所はおはるの住む店が軒を連ねる辺りから、少し歩いた静かな場所にある。菓子屋の前を通ると、もう本当に畑と家が点在するようなところだ。その中に、おようの家はあった。
きっちり手入れがされているわけではないが、家の周囲が掃き清められ、引き戸の前には行儀見習いの看板が出ている。
つい、おようちゃん、と言いそうになったが、友達とはいえ、今日からおはるは雇われる身である。ここは、きちんとけじめをつけて、と思っていると、にゃーん、と呑気な鳴き声が聞こえた。
足元を見ると、猫が尻尾を立て、ゆっくりとおはるに近づいて来るではないか。猫は好きだが、こんなふうに人懐こい猫に会うのは珍しく、つい、「あらあら、かわいらしい」、と声を漏らした。
すると、「ほら、こっちだよ」と、男の人の声がする。
今のを聞かれたか、と我に返ると、着物をだらしなく着崩した、痩せた男の人が、煮干しを手に、猫に手招きしている。
猫はにゃーん、と鳴いて、男の人の方へすり寄った。
撫でられて、ごろごろと猫は心地よさげに喉を鳴らす。
この家の奉公人か?
そうだ、おようちゃんの旦那さんは戯作者だ。
そうした人を雇っていたとて、不思議ではない。
商家にお商売のための奉公人がいるように、余裕のある家では家のことを任せる奉公人を雇うことが多くあるではないか。
あの、お内儀さまは……、と言いかけた時、「あなた、今日は版元の方とお約束があると言っていたでしょう。間に合わなくなりますよ。早く着替えてくださいな」と、聞き覚えのある声がした。
「あら、おはるちゃん」
ぱっと、また娘時代に戻った呼び方で、おようがおはるを呼んだ。
「今日から、お世話になります。精いっぱい努めますので、ご指南のほど、よろしくお願いします」
おはるがはっとして、頭を下げると、おようも「こちらこそ。来ていただき、本当に助かりました。何かありましたら、遠慮なくおっしゃってください」と頭を下げる。
そうして、おようは顔を上げると、「あなた、こちらお話していたおはるちゃん。以前一緒にご奉公していたことがあるの。これからの産前産後、三月ほどお教室を手伝っていただくことになったの」と、おはるを紹介した。
おようは今、『あなた』と言った。
奉公人ではなかった。
おようちゃんの夫であり、戯作者の諏訪理田とは、この人であったか……。
正直、おようちゃんほどの人が、なぜお武家様にご奉公までした後にこのお人と一緒になったのか、おはる首を傾げたくなった。自慢ではないが、おはるが一緒になった旦那さまは、りりしく、お商売にも真面目で、大きな商家の跡取りの度量があり、新調する着物はどれも大層映える。
一方のこの諏訪理田という、おようちゃんの夫。
優しげではあるが、痩せていて、何やらだらしのない恰好で、昼間っからやっていることは猫の相手である。
おようちゃんのご両親は、この人とおようちゃんが一緒になるのを喜んだのかしら……。
失礼を承知ながらもそう思っていると、「これはこれは、おようがお世話になっております。今日もお忙しい中、こうしてうちのおようのために来てくださって。大変ではありませんでしたか」と、柔らかく諏訪理田がおはるを慮る。
おはるは、ふっと、この諏訪理田の人柄を感じた。
決して、決してこの諏訪理田と一緒になりたいなどとは思わぬが、このちょっとしたやり取りで、人と成りというものが伝わる。
男の人の、威厳などではなく、優しさでその強さを感じたのは、これが初めてのことだった。
3
さて、いつまでも猫と遊んでいる諏訪理田を、おようは『いい加減に支度してくださいな』と急かし、よそ行きの着物に替え、財布だの手拭だのと持ち物を確認して送り出した。
まるで手習いに行く子を送り出すようだ、と内心おはるは思った。
そうして、行儀見習いの時間になった。
現在、稽古はおおよそ、三日から四日に一度の間隔で、午前に半刻(約一時間)ほど行われており、始まる時間も昼前ということで、おはるにとっては、朝の店のことや子どもたちのことを終えた頃におようの教室に行き、子どもたちが帰ってくるよりもずっと早く自宅に戻れるとあって、願ったりかなったりの好条件であった。
この日の生徒さんは五名ほどで、皆、年の頃は十三から十四。簪や着物などの身なりから、余裕のある家の娘であることが覗えた。あと数年もすればうちの娘もこんなふうに装うのかしら、と思うとおはるの心は弾む。
生徒さんたちは、もう何度もお教室に通っているので、所作が美しい。
座る際に袖や裾を気遣うのはもちろん、正座も背筋を伸ばし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃え、足袋を履いた足の親指同士が離れぬようにしている。
「だいぶ暑くなってきましたが、みなさん、お変わりありませんでしたか? ご家族も息災でしょうか」
そんなふうにおようは、娘たちに話しかける。
何気ない会話のようだが、ここから、娘たちの様子を先に見ておくのがおようのやり方だと理解した。本人の体調が優れなければ、それを考慮する必要があるし、家で誰かの加減が優れなければ、医者を呼んだり、薬を買いに行ったり、看病や、家事をやる必要も出てくる。それに、行儀見習いに通う娘の多くは、ほかの習い事も並行して行っている。この後、昼餉を終えたら、次の稽古があり、夜はその復習、というのも、この年ごろの娘なら珍しくはない。おはるもそうであった。
娘たちがそれぞれに、変わりないことを伝えると、「それでは、前回の復習から入りましょう」と言った。
そうして、「その前に」と言い、「こちらはおはるさん。昔同じお武家様の元で行儀見習いをしておりました。今は、商家のお内儀さまです。私が臨月なのを慮って、いつもはこうして一緒に、そうして、私がお産の時とその後、暫く、代わりをしていただくことになりました。おはるさんのことは、先生と呼んでくださいね」と、おはるを娘たちに紹介した。
のんびりと娘たちとおようを眺めていたおはるは、はっとし、「こんにちは」とあいさつした。
娘たちも礼儀正しく、それを返す。
そうして、この日はおようの稽古をおはるは隣で見て、要領を覚えた。
なんとかなりそうだ、と心が軽くなった。
そのなんとか、がやって来たのは、次の稽古であった。
おようがおなかの張りが強くなり、床に臥せった。
まあ、この時のために自分がいるのだから、とわかっていたが、おはるはやや戸惑った。
前回は、おようが師として娘たちの前におり、その師の友達であり、代理の師として構えていたが、今回は、その娘たちの稽古をつけなければならぬ。
見ている分には、気安かったが、考えてみれば、十三、四の娘というのは、なかなかに手ごわいものである。その年の頃、おはる自身はのんびりとしていたが、周囲の娘の中には、鋭い言葉や考えの者もいた。
なんとなく、お互いが緊迫した中で、稽古が行われた。
どうしよう、と動揺したおはるは、「今日は、私がお稽古を担当します。私には、息子と娘がいて、なんだかみなさんも、子どものような感じで……、どうか力を抜いてくださいね」と笑顔を作った。
だが、この時、娘たちの表情が僅かの間止まった。
その後、娘たちが視線を伏せながらも、目配せし合っている。
何がいけなかったのか……。
娘たちは表向きといったふうに、「はい」と返事をし、稽古も従順に聞いている。
前回のおようの様子を見ていたので、稽古の進め方は滞りなかった。
だが、どこか、よそよそしい……。
これまでの師であったおようが今日おらず、代わりのおはるが教えたのだから、まあ、仕方がないといえば、それまでだ。
もし仮に、手習いの師が急に代わったら、やはり子どもの頃のおはるも何かしら思うところがあるだろう。
そう考えながら、お教室の生徒を送り出し、今日の稽古は終わった。
おようの様子を見に行くと、目を薄く閉じて、じっとしていた。
「おようちゃん、具合はどう?」
「ありがとう。だいぶ楽になってきた」
枕元には盆に載せた水が置いてある。心配したおようの夫が用意したのだろう。そのくらいのことはできると知って、失礼ながら安堵した。
おようの横におはるは正座した。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向かい合うようにし、足の親指同士が離れぬようにする。夏の時分に足袋を履いたのは久方ぶりであった。
「本当に助かったわ。自分だけでなんとかできると思っていたけれど、考えが甘かったわね」
「そんな……。甘いなんてことないわ。今はとにかく無理はいけないわ」
「ありがとう」と、おようは言った。
「ひとりで大丈夫?」
「ええ、もうじきあの人も帰って来るから」
「そう。何かあったら、遠慮せずに言ってちょうだいね」
「もう、十分遠慮しないで甘えてるわ」
「……まだまだ大丈夫よ。頼ってもらった方が嬉しいの」
「ありがとう」
そんなふうに話し、おはるはおようの家を出た。
そうして、帰りに店の並んだ通りに出て、何か子どもに土産でも、と軒先を歩いていると、賑やかな話し声がした。呼び合う名前や声に聞き覚えがある。
つと、斜め後ろを見ると、茶屋で娘たちが床几に座り、話に夢中の様子だ。日よけの御簾が下りているので、通行人は見えぬようである。
「ねえ、あの先生、どう思う?」
「先生って言うだけ優しいわ。私は先生とは思わない。おはるさんて呼ぼうかしら」
「気持ちはわかるわ」
「やっぱり思った?」
「当然じゃない」
どういうこと?
おはるは軒先の商品を見る振りをしながら、話の続きを待った。
「『息子と娘がいる』って、私たちは行儀見習いに通っているのに、母親みたいな言い方をされても困るわよ。だったら、うちでお母ちゃんの言うことを聞いていればいい話で、わざわざお教室に通わないわ」
「そうよ。およう先生は絶対にそんなことないわ。きちんと生徒として、見てくださっているもの」
「そうよ。先生、昔、店を暖簾分けしてもらう前の板前さんの稽古もしたことがあるそうなの。なんでも、気の短い方だったらしいけど、先生は全く動じずに、稽古されたって話よ」
「そんな話どこで聞いたの?」
「うちの近所の質屋の大旦那。うちが行儀見習いはどこがいいかって話したら、それならって、今の先生のところを教えてくださったの。なんでも、その板前さんを先生のところに紹介したのも質屋の大旦那だったんですって。『この人なら大丈夫』だと思ったそうよ。つまり、質屋の大旦那が太鼓判を押した先生ということね」
「まあ! うちはたまたま近所だったからだけど、およう先生で本当によかったと思うの。へんに気取ったところがないけど、きちんとされていて、決して慣れ合いのような、今日の先生のような言い方はなさらないわ」
ここまで聞いて、おはるはその場を離れた。
何かを買って帰ろうという意欲も消えていた。
……そんなつもりはなかった。
ただ、生徒である娘さんたちとの距離を縮めたかった。
そんなにいけないことを言ったのだろうか。
そんなにも気に障ったのだろうか。
……もし、自分がおようちゃんのお教室をお預かりしている間に門下生が次々離れてしまったら、どうしよう。
おはるは大層暗い面持ちになった。
4
子どもに土産を買う気分もそがれ、そのまま帰宅し、しょんぼりしているおはるに、遅い昼餉を摂りに来た夫が「どうした」と声をかけた。
「甘かったようです」とおはるは小さく言った。
「なんだなんだ、張り切って、友達を助けるとか、外で稼ぐとか威勢のいいこと言ってたってのに」
ははは、と笑う夫に、今は何も返せない。
その様子に、「まあ、初日なんだからさあ、そんなに肩に力入れなさんな」と夫は言った。
「初日だからというか、おようちゃんは生徒さんたちに毅然と接して、尊敬されているけど、私がうっかり気安くして、生徒さんたちの気分を悪くさせて、このままじゃあ、おようちゃんのお教室を助けるどころか、迷惑をかけることになるのよ……」
不甲斐ないながら、ほかに言う相手もおらず、おはるは小さく言った。
「まあ、それがおはるなんだから、いいじゃあないか」と、夫はおはるの頭に手を置いた。
何もよくない、とおはるは内心思う。
「誰だって、初めての場所や、初めて会った人に慣れるのは時間がかかるさ。その生徒さんだって、まだ十をちょっと過ぎたくらいだろう? 向こうに完全を求めるのも酷ってもんさ」
そこまで言うと、夫はお女中に声をかけ、おはるの膳を持って来るように言った。
「まあ、飯でも食って、元気出しな」
おはるは小さく頷いた。
そういえば、この家に嫁いで来て、まだわからぬことばかりだった時、お商売で忙しい夫が、昼餉を摂る短い時間に、今のように頭に手を置き、一緒に昼餉を摂った。親が決めて一緒になった人だったけれど、その時、とても安心したのを思い出した。年甲斐もない、と思うが、それでも、初めて何かをやって、うまくいかぬと感じれば、心は萎れる。それをまた、どうにか立て直してゆく。
おはるは、はあっと息をつき、背筋を伸ばして、正座した。
着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬように。そうして、持って来てもらった膳を前に箸を取る。
そういえば、お武家様で初めて見た膳は、おはるの生まれ育った商家とは違った。何もかも、珍しかった……。
5
おはるは、部屋の隅に置いてあった行李を出した。
中には、お武家様で行儀見習いを終えた後、お武家様で見た食器や装飾品を、あまり上手とはいえぬが、おはるが描き残した、らくがきのような紙が何枚か入っていた。実家に戻って来て、安心したとともに、興奮冷めやらぬ思いで、心のままに書きつけたものだっただろう。
懐かしい思いに浸っていると、ばたばたと騒がしい足音がして、子どもたちが帰って来た。
「ああ、おかえり」と振り返ると。
二人して、おはるの膝に飛び込んで来た。
「ああ、よかった。お母ちゃん、帰って来てた」
「今日はご用があるって言ってたから、まだおうちにいないかと思った」
いつもなら、もう重いから、というところだが、おはるは子二人の重さにえも言われぬ安心感を抱いたのだった。
6
おようが産気づいたのは、それから間もなくのことであった。
お教室の終わった日の夕刻に産気づき、翌日の朝に生まれたと聞いた。安産だと言う。知らせてくれたのは、なんとおようの夫の諏訪理田で、なんでも実家が茶葉を扱う商いをしているとかで、大層良い茶まで携え、やって来たのだった。次の稽古からお願いするようになるとのおようの伝言とともに、『お世話になります』という丁寧な言葉も添えられていた。
お教室のある日ではなかったが、おはるが見舞いに訪れると、おようの母がいて、おようは子を抱いていた。
「ああ、おようちゃん、おめでとう」と、おはるは涙ぐみ、おようの傍に膝を揃え、そっとおようの子を見たのだった。
「まあ、かわいらしい……。おようちゃん、体調はどう?」
「ありがとう。産婆さんと母の話では、安産で、安静にしていれば大丈夫だろうって」
「ああ、よかった。本当によかった……」
「おはるちゃん、申し訳ないのだけれど、次のお教室を一度、任せてもいいかしら」
おはるは膝を進め、おようの目を見て頷いた。
「当たり前じゃない。一度なんて今から決めてしまうと、自分を追い込んでしまうわ。もう、それこそ一年くらい休むくらいのつもりでいてちょうだい。そのために、私が来ているんだから」
そこへ、洗濯物を取り込みに庭へ出たおようの母が入って来た。
「ありがとうございます。およう。おはるさんの言う通りよ。力を抜いて、ゆっくり休んだ方が、自然と回復も早くなるというもの。何もかも、根詰めて考えなくともいいのよ」
おようの母は、その場で膝を揃え、背筋を伸ばし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、手をついて頭を下げた。
礼儀作法でも教える座礼であるが、こんな時でも、大層落ち着いた、美しい所作で、さすがおようちゃんのお母さんだと、おはるは思った。
「お礼が遅れましたが、本当にありがとうございます」
「いえ、とんでもないです。気になさらないでください。おようちゃんからは、しっかりお稽古のお月謝のことまで決めてもらっていますから」
笑って、おはるはおようの母の気持ちを軽くする。
「それなら、私も覚えておきますね。この子がうっかり忘れた、なんて言わないように」
そんなふうにおようの母は受け流してくれた。
「あの、おようちゃんが回復するまで、こちらに?」
気にかかっていたことをおはるは訊ねた。
おようのところは父もおり、家をずっと離れるのは、いささか大変であろう。
「ええ、まあ、追い追い様子を見て。あちらの家も帰らずじまいというわけにはいきませんから、時々は戻りますけど。まあ、そう遠くもありませんし」
そうは言っても、おようの母の年で、二軒分の炊事に洗濯は大変だろう。
おはるはこの時は何も言わなかったが、翌日も見舞いがてらおようを訪ね、家事を申し出るつもりでいた。
7
翌日、野菜を入れた粥でもおように作ろうと、何種類かの野菜を買い、昼前におようの家に行くと、すでに先客がいた。
まだ若い娘だが、髪の結い方で人の妻とわかる。
「初めまして。きぬと申します」と、この娘は、背筋を伸ばし、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬようにして、きれいな所作であいさつする。
「こちらこそ初めまして。おようちゃんの昔の友達で、はると申します」
「おはるさん、来てくださったのですか」と、奥からおようの夫の顔を出す。その腕には子が抱かれていて、すやすやと眠っている。
そうして、どうぞ、どうぞと奥へ通してもらうと、そこにはきれいに詰められた弁当がふたつあった。
卵焼きや魚の切り身、野菜をふんだんに使った、上品なお菜が揃っている。
「夫が、以前先生にお世話になったことがありまして、今は炊事もままならぬだろうし、身体によいもので滋養をつけた方がいいだろうと申しまして」
「まあ……」
おきぬは、「また、持って参りますので、どうぞお大事に」と言い、腰を浮かせる。
「あの、私のことならお気遣いなく」とおはるは言ったが、「いえ、これからお店の方に戻りますので」と、控えめな笑顔で答え、おきぬはその場を辞した。
野菜は涼しい土間に置き、それでは、とおはるはこの日、教室で使う座布団を日に当て、その間に水汲みと掃除をし、おようの夫が座布団を取り込んでおくと言ってくれたので、その言葉に甘え、家に戻った。
8
そうして翌日、お教室が始まる少し前に行くと、また、知らぬ女性がいた。名はおふみと言い、おはるやおようと同世代のようであった。聞けば、おふみはおようと昔近所同士で、おまけにおようの夫、諏訪理田の兄と一緒になったのだと言う。つまり、おようとおふみは義理の姉妹ということだ。おふみは、おようの出産で、おようの母がおようのところへ行くことを実家に顔を出した折に聞き、今日は見舞いがてら、私が行きますから休んでいて、と、おようの母の代わりを買って出たのだと言う。おふみにも手習いに通う子がおり、今年から一人で出歩ける時間ができたと言うことだった。
そうして、昨日おはるが買って来た野菜を使い、粥を作っていた。
なんとまあ、おようは人望のあるひとだ、とおはるは今更ながらに思った。
昨日までお母さんが来てくれていた安心感か、豪華な差し入れの弁当のおかげか、とにかく、おようの産後の体調は良さそうであった。
今は、子どもが眠っているので、おようもすうすうと眠っている。
おふみさんが、おようが寝ている間に夕餉の支度をしておくし、子が起きて、おようを起こすようならば、それもこちらでやりますと言ってくれたので、おはるはありがたく、お教室の方だけを任せてもらうことにした。
お教室は、もう春から通われている生徒さんばかりなので、最初の礼から、座礼、襖の開け閉め、歩く時の姿勢、物の受け取り方などの所作を一通り行う。
その中で、おはるはお武家様でご奉公した後に、家で描きつけた、いわば落書きを、少し躊躇いというか、恥じらいがあったが、生徒さんたちに見せた。お武家様での行儀見習いを終えて、ほっとして家に戻って、印象に残っているものを描いたものなんです、と紙を広げてみせた。
この日、この試みを最初にしたのは、以前、お教室の後におはるのことを批判していた娘たちだったので、やや不安はあったが、子が生まれた直後までお教室のことを心配し、おはるに詫びるおようを思えば、何も恐るに足りない、と思えた。
あの人望のあるおように、偶然とはいえ、お教室を任されたのだ。
それなりの自負を持たなくては、おように失礼というものだ。
お教室は無事に終わった。
最後に、もし、何か意見があれば申してください、と言おうかと迷ったが、それはやめておいた。
教室で行ったことが、おはるにとっての全てで、それをどう受け取るかは生徒さんであると、思えた。
9
翌日おようの家には、おつたという女性がいた。
なんでも札差のご新造さんで、昨日来たおきぬさんが以前お付の女中をしていたと言う。そうして、おようの昔の教え子なのだと自身を紹介した。
「先生のおかげで、不慣れな札差のおうちに嫁いでも、なんとかやってこられました」と、屈託ない笑顔で言う。
そうして、この日は、澄まし汁や、刺身の膳が用意してあった。
おつたさんのご実家が料亭で、おつたさんがご実家に連絡し、料理を届けるように頼んだのだと言う。
いやはや、おはるの家もそれなりに余裕があったが、大きな料亭のお嬢さんで、札差のご新造さんというのは、こういったはからいも華やかである。
おようのお母さんは、洗濯物を持ち帰り、家で洗って、明日にでも持って来ると言う。
その翌日にも、おようの元生徒だというお嬢さんがやって来ていたし、その翌日には、おきぬさんがまた弁当を届けにやって来た。ほかにも、夫の母がお付の女中とともにやって来て炊事をしたり、夫の兄たちや妻がそれぞれの商いであるという米や、産後の身体によいという生薬や茶、少し気が早いが子の使う食器なんかを携えては訪れ、むずがる子をあやしたり、家のことを手伝って帰っているそうだ。新しい筆と子のための産着は、諏訪理田の師匠夫婦からだと言う。
おはるはそれほどやることもなく、この日は今夜の夕餉と明日の朝の分のごはんを炊き、皿を洗って帰った。
毎日のように誰かしらがやって来るのは、やはりおようの人望であろう。そうして、毎日誰かがやって来るというのは、ひとつ間違えは、余計疲れてしまうものであろうが、そこは、互いの信頼関係というか、そこもおようの人と成りの現れであろうか、来る側はおようが休めるよう皆心得ているし、おようもそうした心遣いを無碍にせず、養生に徹している。訪れる人々の厚意と努力の賜物か、おようの体調は順調に戻ってゆき、数日で、いつも通りの装いに髪を結っていた。
「おようちゃん、調子はどう?」
いつものようにお教室の時間より早く訪ねたおはるに、「おはるちゃんのおかげで、本当にゆっくり養生できたわ。ただ、まだお稽古の方はもう暫くお願いして大丈夫かしら? あと少しすれば、生徒さんの前にも出られると思うの」と、おようはおはるに感謝し、この先のことを伝えた。
「もちろんよ」とおはるは頷き、「私は自信を持ってお教室を預からせてもらっているけど……、生徒さんたちはどうかしら」と、首を傾げた。
産後間もないおように、お教室を預かると言っている傍からこんなことを、と、我ながら呆れるが、つい、心に溜まっていた不安を吐露してしまった。
「とても喜んでいるわ」と、おようは答えた。
優しいおようのこと、そう言ってくれるのだろう、とおはるは内心思う。
だが、おようは続ける。
「ほら、最初におはるちゃんを紹介した生徒さんたち。昨日の午後、お見舞いに来てくれてね、そこで、おはる先生が、お武家様にご奉公されたことを教えてくださって、面白かったって。またそういう話を聞きたいそうよ」
「え」と、おはるは目を見開く。
おはるに好意的とは思えなかった、あの娘さんたちが、そんなふうにおように言ってくれるとは思いもしなかった。
「ねえ、今日はお母ちゃんが昼と夜のお菜を用意して、もう帰ったところで、誰も来ないから、少しゆっくりしない? 昨日お見舞いに来てくれた生徒さんたちが持って来てくれたお菓子もあるの」
おようの提案に、「じゃあ、お茶を淹れさせて」と、おはるが申し出る。
「やだ、いいわよ」と言うおようを留める。
「私、毎日おようちゃんちの家事をお手伝いするつもりだったけど、ほとんど何もしていないの。お茶くらい、淹れさせてちょうだいな」と言い、おようを座らせた。
おようは盆の横にあった菓子器を引き寄せた。
おはるが茶を淹れ、二人は向き合う。
横では、おようの子が機嫌よく、手足を動かしている。
「さっきの話だけどね」とおようが切り出す。
「うん」とおはるは頷いた。
「私たちもそうだけど、大人になるまでは、本当にいろいろと遠回りをするものだと思うの。お武家様ですら、幼い頃は、儘ならない様子を見てきたわよね。初めての場所で、初めての人に会う時の反応も、その後の接し方も、それぞれ違うもの。最初は驚いても、後で考えれば、いい人、ということもあるわ」
「本当ね」とおはるは頷いた。
商家に嫁ぎ、ずいぶんと忙しい時を過ごした。
そうして、それはほぼ家の中でのことであった。
誰かと新たな出会いから、関係を構築していくことから、離れていた時期でもあった。その期間、おはるにはおはるの、大切なことがあったということであるが、こうして、久方ぶりに外に触れる、というのは、予想しないことも含まれていたわけである。驚いたことも、嬉しいことも……。
まあ、あの娘さんたちの言っていたことは、どちらも本当なのだろう。
嘘をつかぬ、そういう年ごろ、ということか。
そんなことを思いながら、出してもらった菓子を食べ、おはるは妙に達観した思いに包まれた。
10
稽古の後、おはるはおようが生徒さんから見舞いにもらった菓子を売っている店を訪ね、土産に同じものを買って帰った。
この後、おようは順調に回復し、約束の三月後におはるは、行儀見習いの代理を終える。
ほかの人が色々と差し入れ、家事を手伝い、見舞っている中、私だけ謝礼は受け取れない、とおはるは言ったが、ほかの方へはそれ相応のお礼をさせていただいて、きちんと受け取ってもらっているから安心して、とおようは譲らなかった。
そうして、受け取った謝礼で、おはるは雛人形を買うことにした。
息子には立派な兜があったので、ちゃんばらの玩具を買おう。
春は、もうすぐそこである。

![[327]お江戸正座17](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)