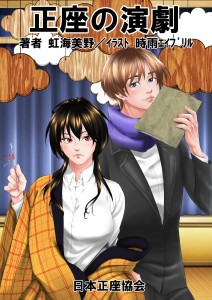[213]正座修行の百世(ももせ)と流転(るてん)

タイトル:正座修行の百世(ももせ)と流転(るてん)
発行日:2021/12/01
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:48
販売価格:200円
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
神様のおわす仙界。百世(ももせ)はお転婆な女の子、流転(るてん)はおとなしい男の子。ふたりとも魂売り屋から正座の大師匠、万古老のところへ売られてきた。以来、育てられながら正座の稽古に励んでいる。共に三百歳を超えているが、見かけは十一歳くらいの子どもだ。
万古老から昇格試験の課題が言い渡された。孔雀明王さまに正座の稽古をつけることだ。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/3472510
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止します。
序 章
「お~~い、流転、何をしている、もう帰らないと万古お師匠様が心配するぞ~~!」
百世の甲高い声が夕日の射す森の中に響いた。森の鹿やリスや野ウサギたちは耳を立てて立ち止まった。
「百世、ちょっと待ってくれぇ」
頭のてっぺんで黒髪を結んだ男の子が答える。
ふたりともラクダ色の一枚の布を頭からかぶり、腰に荒縄だけを巻いた格好をしている。
「今、孔雀のピーちゃんの話を聞いてるとこなんだ」
流転の前に長い首を地面につけて、一羽の孔雀が足を折って座りこんでいた。ピーちゃんは流転の仲良しなのだ。彼の言うには、
「実は孔雀明王さま―――まゆらちゃんが、果実の食べ過ぎで身体が重くなられて、背中にお乗せする役目に疲れてきたのだ」
ピーちゃんはここのところやせ細って、瑠璃色の羽根の艶も悪くなっている。
「まゆらちゃん?」
「孔雀明王さまをサンスクリットで呼ぶと、マーユーラなので、まゆらちゃんと呼んでいるのです」
「そのまゆらちゃんが重くなってるの?」
流転と百世は顔を見合わせるばかりだ。
日陰のやぶの中、下を向いてクロユリが咲いている。
「あっ、珍しい。クロユリだ! 万古老さまに持って帰ってあげよう!」
百世はクロユリをプチンと摘み取った。
第 一 章 百世と流転
神々のおわす仙界――。
百世と流転は、山奥の秘境で正座の万古大師匠の元で育てられた。
まだ「魂」のカタチの頃、「魂集め屋」に集められ、「魂売り屋」に売られて来たのだ。師匠の万古老がその魂を買った。
百世は茂みの中を走ったり木登りしたりが大好きな女の子で、顔は泥だらけ、せっかくのきれいな銀髪が台無しだ。
流転は百世とは正反対で、地面に木切れで文字を書いたり小川に葉っぱを浮かべたり、リスや小鳥と遊ぶのが好きな男の子だ。
それでも正座のお稽古だけは、毎夜厳しく万古老からつけられていた。
正座の昇格試験が近いことも知らされている。それに合格すれば何かのご褒美が待っている。
ある日、流転は一羽の孔雀と仲良くなった。孔雀明王さまを上に乗せている孔雀だ。
孔雀明王のことは「まゆらちゃん」。孔雀は「ピーちゃん」と呼び合いっこする仲良しだ。ずっと一心同体なんだから。
ピーちゃんから「孔雀明王さまが最近、重くて疲れる」悩みを打ち明けられても、ふたりは戸惑うばかりだった。
万古大師匠がふたりを呼び出し、正座させた。白いあごヒゲを撫でながらふたりを睨みつける。百世は手に持っていたクロユリの花を腰の荒縄にはさんだ。
「正座の所作は覚えているじゃろうな」
「はい!」
ふたりは緊張して返事し、正座の所作をしてみせる。
背筋をまっすぐ伸ばして立ち、身体の芯もまっすぐ整える。床に膝をつき、着物の裾は膝の内側にはさみ、かかとの上に静かに座る。両手は膝の上に。ふたりとも順番を間違えずにできた。
「よろしい」
万古老の「合格」を聞いて、ふたりは胸を撫でおろした。
「気を抜くのはまだ早い。昇格の課題はこれから言い渡す」
「え?」
「よいか、申すぞ。お前たちの昇格試験は、【孔雀明王に美しい正座をしていただくこと】じゃ」
「孔雀明王?」
「どこかで聞いたような……」
百世が首をかしげる。
「あ、あれだよ、百世! ピーちゃんが悩んでいるまゆらちゃんのことだ」
「ああ、ピーちゃんがずっと背中に乗せてるっていう明王さまのことか。え? 明王さまに美しい正座をしていただくって?」
「それが俺たちの昇格試験?」
百世と流転は顔を見合わせてから、万古老に向き直った。
「その通りじゃ。孔雀明王は四人の明王の中でひとりだけ、穏やかなお顔をしておられる女神さまじゃ。ずっと孔雀の背中であぐらを組んでおられる。しかし、あぐらばかりではお疲れであろう。わしが一石を投じ、正座の良さも知っていただければ一石二鳥! ということでな、わしが考えた課題じゃ」
万古老は得意げにヒゲをねじった。
「万古老さま。孔雀明王さまと乗せている孔雀で二鳥、そして一石を投じるという意味で『一石二鳥』ですか? きゃははは、万古老さまのダジャレ、面白い!」
百世がひとりで笑い転げたが流転は咳ばらいをした。
「こら、百世。孔雀は毒蛇やサソリを食べる攻撃的な鳥じゃ。そんなことを言ってるとついばまれるぞ。では課題はわかったな」
万古老は洞窟の奥に消えた。
「孔雀明王さまに正座してもらう、だって~~?」
「俺らみたいな、子どもが明王さまにお稽古つけるのか?」
ふたりはたまげてしまった。
「万古老さまこそ大きなお腹をして、いつもあぐらをかいているじゃないか、なあ?」
百世がくちびるを尖らせた。
第 二 章 作戦
「まずは相手を知らないと口説き落とせないぞ。孔雀明王さまについて調べるんだ」
その夜、ふたりはせんべい布団の上に座って会議を始めた。
「孔雀明王さまのことなら、ピーちゃんからいつも聞いてるから、だいたいのことは分かるけど?」
「お~~~! さすがは流転くん! 恩に着るぜ!」
百世は流転の頭の小さなチョンマゲを指でピンとはじいて、ほっぺにチューした。
「やめろよ、百世!」
流転はチョンマゲを結い直した。
「孔雀明王のまゆらちゃんは女神さまだ。夏の一夜に年に一度だけ咲く月下美人さんが大好きなんだって。歌も上手で……」
「月下美人て、あの白い花? 花が好きなのか?」
「仙界のトウゲンキョウ繁華街に『ムーンライト』っていうクラブがある。そこの花形歌手のことだよ。俺たちみたいな妖しの者さ」
流転の言葉に、百世は目を飛び出させた。
「トウゲンキョウ繁華街なんて出入りしてるのか、流転!」
「し、してないよ、話に聞いただけだよ」
「月下美人は歌手やってるのか?」
「そうなんだって。咲くのは一年に一度だけど、毎晩歌っていて最近ファンクラブまでできて、すごい人気なんだって」
「へええええええ」
(あたいが山や谷を駆け回ってすりキズこさえてる間に、流転はこんな情報を仕入れてるのか)
百世は驚くばかりだ。
「でも、孔雀明王さまのまゆらちゃんは、内気でファンクラブに入ってないし、サインももらったことがないんだって」
「内気でというより、プライドが高いから他の有名な女のサインをもらえないくらい屈折してるのかもしれないよ」
「ははは。とにかく孔雀明王さまは、月下美人のサインが欲しくてたまらないんだってさ」
「そいじゃサインもらって、孔雀明王さまにプレゼントして正座の稽古をしてもらおうよ!」
ふたりの会議はまとまった。
翌日の夜、さっそくトウゲンキョウの繁華街に行ってみる。ネオンとやらが色とりどりにチカチカして、山育ちのふたりはおどおどしてしまった。
「月下美人が歌ってるクラブってのは、どの辺だ?」
流転が書いた地図を広げてみるが、暗闇にネオンがチカチカしていては見辛いったらありゃしない。
「そこの小路を入った突きあたりじゃないかな? ピーちゃんに聞いて書いた地図だから、俺の想像半分で分かりにくいなあ」
「あった! 『クラブ・ムーンライト』だろ?」
百世が駆けだした先に、『ムーンライト』の看板が光っている。
他の妖しのおじさんや、この世のものでなさそうな異形の者が、どやどやと入っていく入口にふたりは突進した。
――が、すぐに蝶ネクタイした一つ目小僧につまみ出された。
「ここは子どもが入るところじゃないの。さっさと帰りな」
「子どもに見えても、俺たちは三百歳……」
「ふん、まだ三百歳か。ここにはいるには千年早いよ!」
「ちょっとくらい、いいじゃないか! 月下美人さ~~ん、いるんでしょ! ちょっとだけ会いたいんですけど~~!」
百世と流転は抵抗したが、一つ目小僧のボーイに何回も追い出された。そうこうしているうちに、
「誰か、私の名前呼んだ~~~?」
色っぽい声が聞こえてきて、純白の白いスパンコールがいっぱい付いたマーメイドドレスを着た女が現れた。顔は大きなつぼみのカタチで葉っぱの髪の毛は長く垂れ、腕も長い葉だ。植木鉢をボーイ三人に持たせてそこに植わっている。
第 三 章 月下美人のサイン
「この辺でいいわ。下ろして」
月下美人はボーイ達に女王様然と命令して、自分の植わっている植木鉢を地面に下ろさせた。
(うわ、手ごわそう!)
百世と流転は同時に思った。大きな植木鉢から見下ろす月下美人は長身美女で真っ白い花弁のデザインのティアラまでかぶっている。唇には純白のリップ。アイシャドウも純白だ。
「あのう、あたいたち、いえ私たち百世と流転と言います。正座修行をしています。実は月下美人さんのサインをいただきたくて参りました」
「ええ? 子どもじゃないの。あんたたちみたいな子どもに私の歌の良さが分かるの?」
流転が変わって、
「実はサインを欲しいのは、孔雀明王さま。月下美人さんの熱烈なファンなんです」
「孔雀明王が私のファン? ふん、珍しい話じゃないわね。四人の明王のうち三人も私のファンだし、如来さまや菩薩さまも、ほとんどファンクラブに入ってるわよ」
月下美人は頭をそびやかして答えた。
「サインくらい、ファンクラブに入れば送ってあげるわよ。それよりファンならさっさと『ムーンライト』に歌を聴きに来なさいよ! って孔雀明王に伝えてちょうだい!」
「それが……孔雀明王さまは、その勇気がないとかで……」
「イラつくわね! 私は行くわよ。さ、お店の中へ運んで」
三人のボーイに命令して中へ入ろうとする。
「お待ちください、月下美人さん!」
流転が叫んだ。丁寧な口調を心がけて、
「サインをしてくださったら、あなたのあこがれの君、月読の君の頭上で咲くことができますよ。それでもお断りになりますか?」
「……」
月下美人が葉っぱの手で合図して、ボーイを止めた。
「月読の君の頭の上で、三十日間咲かせてさしあげます。いかがですか?」
「……月読の君ですって……?」
月下美人が白い頬を真っ赤に染めた。
月読の君は月の精だ。
人間界の光源氏の君も真っ青になりそうな、美しい青年の姿をしている。
「おい、流転、いつの間に月下美人の好みまで調べてたのさ」
「攻める相手のことは充分に調べてから取りかかる。これ、鉄則じゃないか」
「お前、意外と策士(策略をたてることが巧みな人)だな、流転!」
「お前が単純すぎるんだよ」
流転のおかげで、月下美人に「月読の君の頭上で花を咲かせてあげる」という話が効き目あり、月下美人はなよなよした葉っぱの腕に花の蜜の墨をつけて、ウキウキして半紙の上にサインした。
「やったあ!」
百世と流転は踊り上がって喜んだ。これで孔雀明王さまに正座の稽古をしてもらえば昇格試験に合格する。
第 四 章 月読を説得
「でも、月読の君は月下美人を頭の上で咲かせるっていうの、許してくれるかな?」
百世は立ち止まった。
「月読の君に、しっかりお願いしに行かなくちゃ」
「ま、またかよ、流転。ツメが甘いじゃねえか。月読の君は偉大なるお月様だぞ。孔雀明王さまのようにオタクな趣味があったとしても、そんなことで落とせるとは思えないぞ」
「今回は当たってくだけろ、だ」
百世と流転は月の登ってくる方角を調べて、できるだけ近い峰まで登って待っていた。
薄紫の夕闇が濃くなっていき、峰のてっぺんで待っていると、白い半月が昇ってきた。その神々しいこと。
ふたりが魅入っていると、静かな足音が聞こえた。日本の直衣すがたの美しい貴公子が立っていた。月読が地上に降り立ったのだ。
「そこのわらべふたりよ。麿に何か用か?」
声まで黄金の鈴を鳴らしたように麗しい。
「俺らは流転と百世と申す者です」
ふたりはその場に正座して頭を下げた。
「地上で歌手をしている月下美人さんは月読さまを、とてもお慕いしています。一度だけ頭の上で咲かせることをお許しいただきたいのです」
「何とな――?」
「肩の上に座らせてさしあげればお顔の花が御頭上にて開きます」
月読の君は口元に扇を持っていった。目元がしかめられ、扇がぶるぶる震えだした。
「月下美人は月の下で咲くから美しいのじゃ。それを月の上で咲かせよとは無礼千万! 麿の存在をなんと心得る!」
扇の上からのぞく月読の眼はひどくとんがっている。
「ほら見ろ、百世。お前がちゃんとリサーチしないから怒らせたじゃないか」
「無礼にもホドがある!」
月読がお上品に声を荒げた。
「そんな勝手な願いを言うなら、麿は満月ストライキをしようぞ」
「満月ストライキ?」
もし、満月ストライキなど起こされれば、海は満潮にならなくなり珊瑚は産卵しなくなり、タヌキたちは宴会しなくなり、狼男は変身できなくなる!
――珊瑚たちだけではない。あらゆる生き物が命を授からなくなる。この世の生態系が狂ってしまう。
「ひえ~~~~! どえりゃ~~ことになっちまうよ、流転! どうする?」
流転は奥の手とばかりに、すかさず言う。
「今まで通り、満月にしてくださったら桜の香の真珠を献上します! お得になりますよ」
「桜の香の真珠って何だよ」
百世が月読に聞こえないようにモショモショ尋ねると、流転は、
「海神が何千年も磯貝の宝箱の中にしまっていた真珠。育ったのはウミガメの卵くらいの大きさだ。万古老が何故かひとつ持っている」
月読は疑り深い眼でふたりを睨みながら、
「桜の香の真珠を持ったら、どんな得をするのじゃ?」
流転は、
「真珠を口に含んで正座すれば足がしびれなくなります」
「正座がしびれなくなるとな?」
「月読さま、正座をご存じですか?」
「うむ。下界を見下ろしていると、大和の国できっちりした座り方をよく目にする。一度やってみたかった」
「そ、そうです!」
「あれは足がしびれるであろうの。――よかろう。真珠を受け取る代わりに、麿の頭上で月下美人に顔の花を咲かせることを一夜だけ許そうぞ」
それを聞いた月下美人は、不満をもらした。
「三十日間咲く約束だったのに一晩だけなの~~?」
第 五 章 孔雀明王さまに会う
突然、百世と流転の心の奥に、万古老の声が響いた。
『百世、流転。いずこまで行っておる~~~!』
「やべえ、万古老だ~~!」
「早く洞窟へ帰ろう!」
慌てて走り出したとたんに、百世がいつぞや摘み取ったクロユリがポトンと地面に落ちた。あれからずいぶん経つのでしなびている。
「あ、この前のクロユリ。こんなにしなびてしまったんじゃ、もういいや」
百世はクロユリをそのままにして、急いで万古老の居所の洞窟へ戻った。
「課題は孔雀明王を正座させることなのに、芋づる式に、ずいぶん遠回りしておるのではないか?」
万古老の黄色い眼がじろりとふたりを睨んだ。
「まったく、目を離すとすぐこれだ。GPSが手放せぬわ」
「万古老さま、いつの間にスマホなんぞという人間界の近代機器をお持ちになったんですか?」
「スマ……なんぞ知らぬ! わしの脳内には古来よりのGPSが搭載されておるのじゃ」
「へえええ」
万古老はふたりに、基本に返って孔雀明王さまに正座の稽古をしてもらうように命令する。
「そうだった! 俺たちの課題は、まゆらちゃんに正座の稽古をしてもらうことだった!」
銀髪をくしゃくしゃにして百世が慌てる。
「孔雀明王さまに、孔雀から降りて正座のお稽古をしてもらうように正々堂々とお願いしようか」
流転が提案する。
ふたりは孔雀明王さまの山寺へ会いに行った。
ひゅん!
いきなり目の前を弓矢と槍が飛んできて、足元の地面に突き刺さる。
(孔雀明王さまって、優しいのじゃなかったのか?)
流転と百世は抱き合って震える。朱塗りのお堂の奥から四本の腕を持つ孔雀明王が、ピーちゃんの背中に乗って出てきた。手には槍と弓矢を構えている。それと何やら果物も。
(我は元々、毒蛇やサソリをやっつける明王である。向かってくる者には容赦せぬ)
再び武器を構えようとするところへ、孔雀のピーちゃんが引き止めた。
「まゆらちゃん、待って!」
「どうしたんだ、ピーちゃん」
「この子たちはボクの身体を気遣って、まゆらちゃんに正座のお稽古をさせようとしているんだよ」
「正座? それは何だ?」
「日本という国の座り方で、あぐらよりお行儀がいいんだって。ボクはずっと、まゆらちゃんを乗せているだろ。正直に言うと重くて重くて耐えられないんだよ。その正座をお風呂でするとダイエットになるらしいし……」
「ピーちゃん! 私のことが重かったの? 辛かったの?」
「ここのところ、まゆらちゃんは吉祥果っていう桃と倶縁果っていうレモンのスイーツばっかりたくさん食べてたでしょう?」
孔雀明王はドッキリする。最近、衣を着替える時に頭がなかなか出なくて、冠の飾りに引っかかってビリっと破れるし、何重もつけている腕輪がきつくなってきたと感じていたのだ。
「ああ、ピーちゃん、悪かったわ。つい両手に持ってるもんだから食べ始めると止まらないのよ。知らなかったわ、ピーちゃんをそんなに苦しめていたなんて」
「まゆらちゃん、ボクも正座っていうのを習ってみようと思うんだ。そしたらもっと安定して君を乗せられるようになるからさ」
ピーちゃんは涙ながらに言った。
「ピーちゃん、そこまで考えていてくれたの?」
孔雀明王は嬉し泣きして急に態度を変えた。
「そこのわらべふたり。正座というもののお稽古をしてあげてもよくてよ」
流転と百世は、そろって「バンザイ」した。
第 六 章 満月の夜が闇に
ついに孔雀明王さまが百世と流転の手ほどきを受けて正座のお稽古をする日がやってきた。
ふたりはこの前よりマシな着物を着替えて、夕暮れに孔雀明王さまのお寺へ向かった。今夜は満月だ。
「月下美人さんが、孔雀明王さまの正座するところを見たいんだって。今頃、あのクラブのボーイさんたちに植木鉢を運ばせてこっちへ向かってると思うよ」
百世が言った。
「ええ? じゃあ、孔雀明王さまは大喜びだな。大ファンの月下美人さんにお稽古の様子を見物してもらえるなんて」
「できるかな? カチンコチンにキンチョーしてるだろうな」
「そっか。その心配もあるな」
「まだ月下美人さんのサインを渡せていなかったから、持ってきたんだ」
ふたりはお寺の山門に到着した。
「月下美人さん、遅いな。この時刻にって約束したんだけど」
「そのうち来るだろうよ。先にお堂に入って孔雀明王さまのところへ行こう。百世」
孔雀明王さまはピーちゃんの背中の上で待っていた。この前よりお化粧が濃い。孔雀緑色の衣装とアイシャドー。クジャク緑の上に金色が照り映え、輝くばかりの美しさだ。
「明王さま、これ」
流転が半紙に書かれたサインを差し出した。
「お稽古を受けて下さるお礼に、月下美人さんのサインです」
「まあっ!」
孔雀明王はピーちゃんの背中から飛び降りた。震える手でサインを受け取り、
「月下美人さんのサイン……。純白の清々しいあの方の……」
サインに頬ずりした。
「月下美人さんが言ってましたよ。孔雀明王さまも一度、『クラブ・ムーンライト』においでくださいって」
「まあ、そんな光栄なことを言ってくださったの?」
「はい! もうすぐ明王さまの正座のお稽古を見学にいらっしゃいます」
孔雀明王は、嬉しさのあまり真後ろにぶっ倒れた。
明王が意識を取り戻した時には、外はすっかり日が暮れていた。
ピーちゃんと百世と流転が明王さまの額に氷を乗せたり、孔雀のうちわで風を送ったりしていた。
「大丈夫? まゆらちゃん。正座のお稽古できる?」
「あ、ありがとう、あなたたち。もう大丈夫よ……」
お堂の床に起き上がった。その時、
「遅くなってごめんなさいねえ」
お堂の入口から、月下美人が植木鉢をボーイたちに担がれてやってきた。
「これは月下美人さま! わ……わざわざおいでくださいまして。サインまでいただき……ありがとうございました」
孔雀明王さまはしどろもどろながら、ぴーちゃんに支えられて、どうにか出迎えた。
「私がこんな山奥のお寺まで来てあげたんだから、お稽古、頑張ってちょうだいよ」
あいかわらず、ツンツンしている。
「じゃあ、正座のお稽古を始めます」
百世が言い、孔雀明王さまとピーちゃんはお堂の床に敷かれた緑色の毛氈の上に立った。
開け放たれた扉からは月の光が射しこんできた。百世が流転の耳元で、
「おい、流転。月読の君さまへ桜の香の真珠はちゃんと届けてあるんだろうな?」
「はいな。月読の君さまは喜んでお礼の返事をくださったよ」
「よく、万古老さまのところから盗み出せたな」
「盗み出すなんて人聞きの悪いこと言うなよ。ちょっと借りただけだい」
さて、クジャク緑の毛氈の上に、孔雀明王さまとピーちゃんは並んで立った。
「はい、おふたりとも背すじを真っすぐに。そうそう、そして毛氈の上に膝をつき、明王さまは美しいお衣装の裾を膝の内側にはさみ、かかとの上に静かに座ってください。ピーちゃんは長い足を折って座ってね」
孔雀明王さまとピーちゃんは、順序を間違えずに見事に正座した。
「あぐらも良いけど、正座もしゃっきりして良いものねえ」
その頃、峰の上で酒を楽しんでいた月読の君は、侍女の持つ盆の上に盃を置いた、
「そろそろ桜の香の真珠の効き目を試してみようか」
あぐらから正座に座り直した。それから、ゆっくりとふところから半紙に挟んだ真珠を取り出した。海ガメの卵くらいの大きさの立派すぎる真珠だ。
「さて、本当に正座してもしびれないのかな?」
口を開けて真珠を含んだ。
空では月の表面を細い雲が流れていく。
「今宵は格別に美しいのう……。う、ぐぐっ」
だしぬけに月読は顔色を変えて首元を押さえた。激しく咳きこむ。
「うぐ、ゴホゴホ……」
「月読さま!」
侍女たちがおろおろして水を用意したり、背中をさすったり。
ようやく何かのカタマリを吐き出した。それはバラバラに別れて岩の上に散った。
侍女たちが悲鳴をあげた。
「きゃあ~~~! サ、サソリの子!」
たちまち満月は真っ黒い雲に覆われ、地上も闇に覆われた。
第 七 章 白も黒も美しい
「キィ~~~!」
ピーちゃんが鳴き、翼をバタつかせた。お堂を飛び出し真っ暗な空めがけて飛び立った。
「ピーちゃん、どこへ行くの~~~!」
孔雀明王さまと百世は呆気にとられた。流転がひとり呟く。
「あの方角は、月読さまの宮のある方角だ」
「流転、よく見えるな」
「体内GPSだよ。俺たちも行こう! 何か大変なことが起こったみたいだ」
その頃、月読は侍女たちに守られて、サソリの子の群れから逃げていた。
「確かに真珠を口に含んだはずなのに……」
月読は青ざめて口元に絹の布をあてているが、サソリの子の感触が消えないようだ。
そのカタチの良い唇が不意にふさがれた。
「う?」
しっとりと重い黒髪の女が、薄闇の中で月読の頭を抱き寄せ、接吻したのだ。
「お前は?」
「嫌われ者のクロユリでございます、月読さま」
黒っぽい十二単をまとっていて間近に迫る金色の瞳は不吉な光を発している。
同時に闇がのっぺりと重く重く月読の宮を覆っている。
「お怨み申し上げますぞ、月読さま。永い間、お慕いしておりますのに、私には恩情たまわらず、月下美人をその尊き頭上で咲くことをお許しになるとは……」
「真珠をサソリのカタマリとすり替えたのは、お前の仕業か」
「そうでございますとも。あなたさまはサソリの毒を少々含んでしまわれたので、満月にする力を失われた。これでこの世は永遠に闇に覆われます。ふっふっふ、よい気味だ……。黒いというだけで私をないがしろにした罰です」
月読はクロユリの手を振りはらおうとするが、力が出ない。再びサソリの子の群れが、足元からカサカサと登ってこようとしている。
「ううっ」
おぞましさに月読はうめいた。
そこへ!
「キイ~~~!」
羽ばたきの音がして、月読の身体をかばって空から降りてきたもの――孔雀のピーちゃんだった。
岩にざわざわと群れるサソリの子を、片っぱしからついばんでいく。
「月読さま、大丈夫でございますか?」
「お前は?」
「孔雀明王さまに仕える者でございます」
山肌の濃い闇の中にポツンと白い輝きが見え、どんどん近づいてくる。
百世と流転が月下美人の植木鉢を担いで峰を登ってきたのだ。黒い雲に覆われた月から微かな光を受けて、月下美人の白いドレスがキラキラと輝いている。
「月読さま~~! 大丈夫ですかっ」
「おお、いつぞやのわらべふたりか」
「早く月下美人さんを、頭の上へ!」
百世と流転が、植木鉢から月下美人をそっと抜き、月読に横抱きにさせた。彼女は彼の頭を抱きかかえ、冠に添えるように大輪の花を開かせた。眩しい輝きだ。
暗闇が花からの光で静かに後退し始める。
やがて黒雲が去り、地上は元の満月の明るさに戻った。
百世と流転はほっとして地面に座りこんでいた。
「おのれ……、おのれ……。黒い花はどうしても愛されぬのか」
クロユリがしおれて地面に伏していた。悔しさのあまり、歯ぎしりしている。
月読の君が、ゆっくり月下美人を地面に下ろし、クロユリに歩み寄った。
「クロユリよ。そなたの花言葉は『呪い』であったな。呪いや憎しみからは何も生まれぬ。いくら怨んでも幸せはつかめぬ。お前がもし、不運を感じているのなら、それはお前の心が呼び寄せたこと。呪う心こそが醜い思いこみじゃ。――白い月下美人も、漆黒のそなたも同じく美しいぞ」
「え……」
クロユリがひん死の姿で顔を上げると、月読が傍らに正座して手を差しのべた。
「さあ、森でいきいきと咲くがよい。漆黒の美しさを愛でる者も多かろう」
「月読さま……。お命を狙った私めに、救いのお手を差しのべて下さるとは」
クロユリもその場に正座して深々と頭を下げた。
「月読さま、正座の所作をご存じだったんですか」
「ははは、いつも下界を見下ろしていると申したであろう。そなたたちの稽古もいつも見ているぞ。昇格試験がうまくいくと良いな」
百世と流転はドキンとした。
月下美人さんはピーちゃんの背中に乗って峰を降り始める。
花が閉じようとしていた。
「ありがとう、子どもたち。来年の花が咲くまでトウゲンキョウ通りの『ムーンライト』で歌ってるわ」
百世と流転はピーちゃんを孔雀明王さまの元へ送り届けた。
「明王さま、ぴーちゃん、ありがとうございました。正座のお稽古、頑張ってくださいね」
「ピーちゃんとふたりで正座とダイエット頑張るわ」
明王さまとピーちゃんも笑顔で見送り、百世と流転は万古老の待つ洞窟へ帰っていった。
万古老はアゴヒゲを撫でながら、ふたりを待っていた。
「どうにか合格じゃのう」
「ありがとうございます。で、ご褒美は?」
百世と流転はワクワクして返事を待った。
「褒美? そうじゃのう、わしの大切な真珠を盗んだことを見逃してやることかのう」
「そ、そんな~~」
「流転、やっぱりバレていたじゃないか!」
「だって、百世……」
夜明けの暁色が辺りを包んでいた。