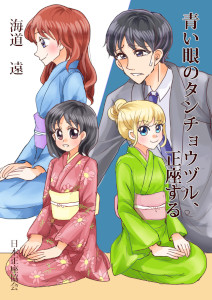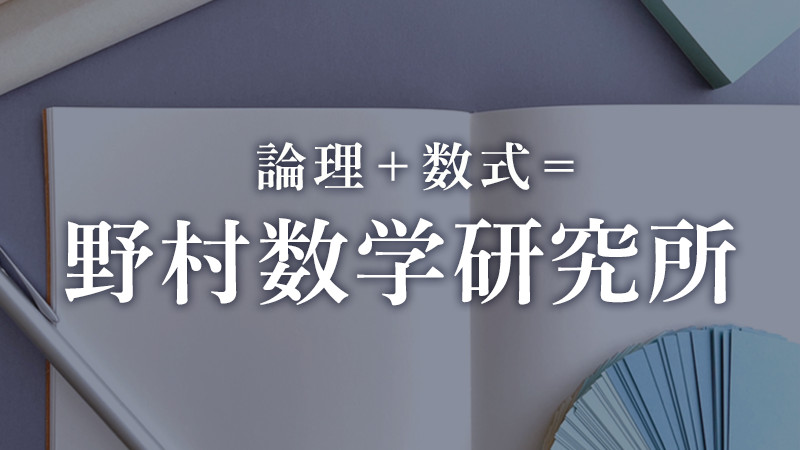[370]お江戸正座29
タイトル:お江戸正座29
掲載日:2025/07/30
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:29
著者:虹海 美野
あらすじ:
久三は郷から江戸へ出て来る途中、口入屋の翁と出会い、口入屋の世話になりながら江戸での生活を始める。
久三の大らかな人柄と本人が無自覚な頭のよさが評判を呼び、途切れず仕事が入り、久三は江戸で順調な生活を送る。
ある日、翁と友達のご隠居の提案で、賞金つきの利き饅頭大会を開くことが決まる。
その大会に参加したいとやって来たのは干物屋の長女、おはなであったが、当日、おはなの両親がおはなの参加を止めようとし……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
久三(ひさぞう)の実家は、江戸からほど近い村の農家である。比較的土地が広く、豊作に恵まれたので、贅沢を言わなければ、食べるのに困らなかった。長男の久一が家を継ぎ、次男の久二が同じ村の一人娘の家へ婿入りした。
そうして久三は江戸に出ることにした。
江戸で何をするかは決めていなかった。
ただ、継ぐ家がないのなら、江戸に出てみようという思いがあった。
そう長くはない江戸までの道中で、久三は花見帰りに足を傷めた翁に会った。久三は翁を背負い、家まで送った。この年になると、仰々しい花見とは別に、ふらりとひとりで気の向くままに出かけたくてね、供も断ったらこんなことになり、面目ない、と翁は久三の背で詫びた。行く先は同じなんだから、こっちとしては心強い道案内ができて感謝してるよ、と久三が返すと、なんとまあ、特殊な若者だ、と翁は呟いた。この翁が江戸で口入屋(仕事を紹介する店)を商っていた。
「それじゃあ」と去ろうとする久三に、「あんた、今日の宿のあてはあるのか?」と翁が訊ねた。
「ないけど、なんとかなるよ。こちとら、江戸の町人みたいにきれいな屋敷でないと寝られないってことはないからね」
そう言って颯爽と歩き出そうとする久三を、翁は「これこれ」と再度呼び止めた。
「大したお構いはできぬが、そちらさんさえよければ、いくら居ても構わぬ」
久三が振り返ると、翁は「あんたは信用できる人だ。今回の礼と言ってはなんだが、飯もお出ししよう。それで、あんたさえよければ、仕事も紹介しよう。何せ、うちはそれが商売だ」と言った。
こんなに上手い話があるのだろうか、と久三は思った。
だが、多くの人を見てきた翁は、この若いのは、辛抱強く、しかもそれを顔に出さぬ、そうして、どういう育ち方をしたのかはわからぬが、食や金銭に卑しさもない、と肚の中で思った。
この若い男をこのままどこかに行かせてしまうのは惜しい、と商売人の勘も働いた。
それで翌朝、ぐっすり眠っていたこの久三が起きると、炊き立ての飯に汁物、焼き豆腐に香のものをつけた膳を出した。
久三は布団をきっちりと畳み、膳を前に正座した。
背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、足の親指同士が離れぬようにしている。
気さくな印象だったが、箸の上げ下ろしもきれいである。
己の勘は当たっていた、と翁は思った。
顔見知りのご隠居が、碁の相手を求めてやって来た折、手持無沙汰で庭掃除や戸の修理に勤しむ久三を目ざとく見つけ、「あの若いのは?」と尋ねる。一部始終を話すと、このご隠居が身を乗り出し、自分もぜひ花見の供をと所望した。
長年のお付も年で、弁当だの敷物だのを持たせるのには忍びない。それに、どこかの酔客に絡まれたりした時や、疲れた時にも心もとない。行楽を邪魔せず、けれど頼りになる者がいい、と言う。
久三にその場で訊いてみると、「花見ができるんなら、金銭はいらない」と言う。
首を傾げ、ごくごく当然といった口ぶりだ。
滅多にいない逸材だと翁は思って家に泊めたが、これは、こちらの利だけでなく、この久三にとっても、運のよい出会いであったと、思った。こんなに人が好くては、腹黒い連中にいいように利用されていたかも知れぬ。
「いやいや、こちらさんはね、金銭を払うという条件で頼んでいる。つまりは、無銭で頼むのじゃあ、具合の悪いこともある。これを持ってくれだの、助けてくれだの、そういうのを心置きなく頼める人でないと嫌な場合もある」
そう説明すると、「荷は力のある者が持てばいいし、何かあれば助けるのが道理だ」と、やや納得いかぬ表情でいたが、兎に角、翁はこの仕事を久三に任せた。
後日、このご隠居とともに、キツネにつままれたような面持ちで出かけて行った久三だったが、矢張り、ご隠居は久三に対し、大層な喜びようであった。そうして、約束の額より多くを払い、「これで久三に何か旨いものでも」と言う。もちろん、この翁はその分を店の勘定には入れない。
この久三の話が、話好きのご隠居から広まり、盆栽の名手だが腰を少々痛めたという老人に代わり、老人の腰が回復するまでそれを売りに行く仕事をした。そこでの久三の評判もよかった。客への感じは極めてよいが、決して値切る客には応じぬ。そうして毎日、『大事にしてくださるというお客の元へ無事売りましたよ』と空になった大八車を押しながら帰って来ては、お代を渡す。
久三への依頼は途切れることなく、新たに久三の噂を聞きつけてやって来た客に、翁は「申し訳ございません。ご指名の久三ですが、仕事が幾つも入って、暫くは無理なんですわ」と詫びるほどであった。
依頼先での仕事ぶりはもちろん、その人柄から、「うちに娘がいれば、婿に来てほしいんだけどねえ」と付け加えられたりもした。
久三は翁に預かってもらっている給金もそろそろ貯まってきたことだし、いろいろな仕事を請けたおかげで江戸の様子もわかってきた頃だから、住まいを決め、ずっと続ける仕事をしようと考え始めていた。
この日は朝からしとしとと雨が降っていた。
いつも何かしら仕事の入っていた久三であったが、翁があまりに久三が働きづめなのもよろしくない、と休みにしてくれた。仕事の依頼は来ているが、それを敢えて詰め込まずに休みを入れてくれる翁の気遣いに久三は感謝した。
午前中、碁を打ちに来ていたご隠居も帰り、昼餉を挟んで今は久三が翁の相手をしている。
「ううん」と翁が膝に頬杖をつき、眉をしかめる。
その向かいで、久三は正座し、碁盤を見つめていた。
久三は背筋を伸ばし、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、着物を尻の下に敷き、足の親指同士が離れぬようにし、脇は締めるか軽く開く程度、手は太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃えている。
「本当にお前さん、碁は始めたばかりかい?」
「はあ、ここに来て、碁をやっているのをなんとなく見ておりましたが……」
「いやあ、大したものだ。お前さん、盆栽を売る際にも、向こうでは一切書付をしないで、戻ってから、どれがどの値で売れたか空で言えたと聞いていたがね。幼いうちに奉公にでも出ていれば、もう今頃は店を任されるくらいに出世したんじゃないか?」
「褒めすぎですよ、旦那。私は手習いに行かせてもらいましたから、そりゃあ、勘定はできますし、碁も人がやっているのを見れば、自然と覚えられるものでしょう」
教えてもらったからって皆が皆、修得できるでなし、見たからって、碁でこんなに難しい一手を思いつくでもなし……、と翁は思うのだった。
2
翌日、いつものご隠居からの依頼で、久三は山菜採りの供にでかけた。
口入屋の翁としては、もっとよそからの依頼を久三にあてがいたかったが、ここは先に約束を取り付けた自分だと、ご隠居も譲らなかった。
ご隠居の採った山菜を自分のと一緒に籠に入れる久三に、「この先はどうするつもりだい?」とご隠居が訊く。
「……はい。私も考えてはいるんですが。居職かなんかの仕事を紹介してもらって、ゆくゆくは長屋で暮らしたいと……」
「口入屋の旦那はそのへんのことを考えてくれているのかね」
「いやあ、そこまで頼るのはさすがに。これまで通り、紹介してもらった仕事をしながら、探していこうとは思っていますが」
「そうか……。まあ、あの人もね、お前さんを高く買っているし、大事にしているが、商売人でもある。自分の損になる人をいつまでも世話したりはしないでしょう。つまりは、ただの優しさでお前さんを家に置いているわけじゃあないんだ。感謝は大事だが、相手にも利があるってところもね、肝に銘じておきなさいな。ところで、お前さんは、勘定も正確だし、客の相手もうまくやれるってんなら、商いはどうだい?」
「商い、ですか」
「気が向かないかい?」
「いえ、雇ってくれるところがあればいいんですが、それもあれでしょう。幼い頃から奉公をしているとか、どこかの手代だったとかっていうのがないと難しいでしょう」
「一層、どこかに婿入りするというのはどうかねえ」
婿入り?
そこでご隠居が「おや、これは食べられるものだったか?」と尋ねる。
山育ちの久三は、すぐにご隠居の手元を見遣り、「はい」と頷いた。
3
春の長雨が始まった頃、久三は提灯作りの居職にありついていた。口入屋に依頼のあった仕事のひとつを翁が久三に融通してくれたのである。恐らくは、久三の話を聞いたご隠居が、翁にうまく言ってくれたのだろう。ご隠居に久三は礼を言ったが、「さあて、何のことやら」と、ご隠居はとぼけ、「それよりお前さん、碁の方もいけるそうじゃあないか。今度私とも手合わせしておくれ」と朗らかに言うのだった。
提灯作りはコツを掴めば、後はしめたものである。
せっかくご隠居の口添えもあって得た仕事、続けられるよう精進するのみだ。
この仕事を続けられる目処が立てば、翁の口入屋から出ようと考えていた。
今日もご隠居がやって来て、翁と囲碁に興じている。
「最近、この陽気もあって、ご近所で集まって何かしようという輩が多いらしいなあ」と翁が言う。
「ほう。どんな?」
「狂歌だとか、長唄だとかを人を集めてやるそうだ」
「そうかい。こちとら、なるべくのんびり、少ない気ごころ知れた人と過ごしたいもんだがな」
ご隠居の答えに、「そうして変化を嫌うのもよくない、と思うんだが。どうだね」と翁が言う。
「どう、とは?」
「私もあなたも、顔は広い。そこそこの生活も送れている。せっかくなんだから、こう、若い人なんかも呼んで、何かするのはどうだろう」
「まあ、悪い話じゃあないですな」
「そうでしょう。そうでしょう」と翁が頷く。
「じゃあ、何をいたしましょう」
「通り一遍の集まりじゃあつまらない。こう、面白いものがよろしい。『へえ、あそこはそんな面白いことを』と言われるようなね」
「ううむ」と言いながら、ご隠居が茶とともに出された饅頭を食べる。
「例えば、饅頭を当てるなんてのは、どうですかい?」
「饅頭? 利き酒じゃなしに、饅頭?」
「面白いものがよろしいと言ったのはそっちでしょう。利き酒は、まあ、割とやる人が多い。だが、これで集まるのはそこそこに年かさのいった男ばかりになりかねないし、集まった後に酔った者が大勢出ては面倒でしょう」
「確かにねえ。で、饅頭の場合はどうするんで?」
「特別な銘柄は必要ないでしょう。この近所の饅頭を五つくらい用意するんです。大きさや色艶なんかでわかるんじゃあ面白くないから、目隠しでもしてね」
「いやはや。暇だと、本当に役に立たぬことを思いつくもんだ」
「それはお互いさまでしょう」
二人の年寄りの雑談だ、と久三は思っていた。
こんなばかばかしいことをやるはずがない、と。
4
だが、久三の思いとは異なり、このご隠居と翁は大真面目であった。
まさか、と久三が思っているうちに、饅頭屋を五つ挙げ、更には一番多く正解した者には賞金も出すときた。
ご隠居の店と翁の口入屋に参加する者を募る紙も貼り出した。
わらわらと紙の前に人が集まる。
提灯作りの合間に店の前を掃いていた久三に、「あの」と娘が声をかけた。
「はい、なんでしょう」と久三が振り返る。
口数は少なそうだが、華やかな印象の娘であった。
江戸へ来て、若い着飾った娘を見る機会が増えると思っていたが、江戸に着いてすぐ出会ったのが、ここの翁、そうしてそこから来る仕事は全て年寄りが関係していたから、却って村にいた時の方が娘に会う機会は多かった。
「この利き饅頭は、女子(おなご)も参加できますか?」
「……ちょいとお待ちを」と、久三は中へ入った。
そうして、強い日差しに気づき、「中でお待ちください」と娘を振り返り、「旦那、旦那」と呼ぶ。
「おう、どうした?」
庭で盆栽の手入れをしている翁に、「あの、利き饅頭は女子も出られるのかって、今訊かれやして」と伝える。
「おう。構わん。寧ろその方がいい。年寄りばっかりが集まるんじゃあ、知った者同士だけになるかも知れないからな。それじゃあ意味がない」
「はあ。あの、参加するなら、名前なんかを訊いた方がいいですかね」
「そうだな。一応は参加する人数の上限を設けないとな」
「わかりました」
「頼んだ」
久三は急いで店の入り口へ戻った。
ひんやりした上がり框手前に、すっと背筋を伸ばした後ろ姿が見える。
艶やかな黒髪に華奢な首や、娘らしい淡い水色の着物が久三には大層麗しく見えた。
「あの、よいそうです。寧ろその方がいい、とのことで」
そう伝えると、「え、本当ですか?」と、自分から訊いておきながら、まさか、といったような顔をしている。
その驚いて見開かれた目がきれいで、かわいらしいと久三は思った。
「それで、一応お名前を聞いておくようにとのことなんですが」
ああ、と娘が頷く。
「はな、と申します。この先の干物屋の娘とお伝えいただければ、すぐにおわかりになるかと」
「おはな、さんですね。わかりました。伝えておきます」
大きく頷いた久三は、顔がほころぶのに気づかなかった。
5
利き饅頭の日には、五軒の菓子屋から饅頭を取り寄せた。
参加するのは二十五名であるから、結構な数である。
最初に目隠しをして二軒の店の饅頭を食べ比べる。
この界隈では高い店の饅頭と、人気のある店の饅頭を食べ、どの店かを当てる。店に関しては、この界隈、とだけ伝え、具体的な名は伏せている。これに正解できた者が、次の三つの利き饅頭に進める。そこで全て正解した者が賞金をもらえる、ということらしい。饅頭を三つ当てるだけなのだから、何人も全て正解の者が出るのではないか、と久三は翁に尋ねたが、なあに、二人、三人なら同じ額の賞金を出せばよし、もっと多いなら、賞金を分ければよろしい、という返事であった。懐温かく、心にゆとりのある人というのは違うものだ、と久三は思った。
参加したのは、近所の長屋の大家だとか、茶道の師であるとか、七十を過ぎた婆さん、茶屋の店主、大食い大会で優勝したことのある大工、とさまざまである。他にも、十二、三の男の子も何人かいた。自薦も他薦もあったらしいが、ご近所さんに「ぜひ勝っておくれね」と期待を受け、参加する者が半数であった。
続々と集まる人の中で、久三はおはなの姿を探していた。
参加者は来た順に久三が店の奥にある座敷に案内する。結構な人が集まるので、二間続きの部屋の襖を取り払って、会場にした。
座敷には饅頭の入った箱に目隠し用の布、湯呑にさゆが用意されている。饅頭の味をより正確に確認するのには、茶よりさゆがよかろうと言ったのは、ご隠居であった。
私はね、この大会のために朝から何も食べてやしませんよ、という婆さんもいれば、しっかりと腹を満たして味に集中すると豪語する大工、今朝も茶を嗜み、心を落ち着かせて来ましたという茶道の師なんかが、雑談を始めているが、それぞれに決して負けぬという意地のようなものが見え隠れしていた。
そんな中、入り口から「後生だから考え直しておくれ」という悲痛な声がした。それに続いて「そうだ、利き饅頭なんかに出たとわかったら、近所の笑い者だ」という声。四十代くらいの夫婦が誰かを止めているようすだ。
「お母ちゃん、ここまで来て何言ってるのよ」と、娘の声がする。
「おえんは黙っていなさい」
「お姉ちゃんが出るのが駄目だって言うのなら、私が出る。饅頭の味なら自信があるんだから」
「おすえまで何を言い出す!」
「もう、とにかく私は出るんだから! 名前も伝えてあるんだよ。これで急に出ないってなれば失礼だし、お父ちゃんが言うように出て笑い者になるなら、それでいいよ」
「おはな!」
入り口では、先日利き饅頭に参加したいとやって来たおはな、そうしてそのおはなに似た、おはなの妹と思われる娘が二人。それに話の様子から両親とわかる男女がもめていた。
「あの、おはなさん、どうぞ、中へ」と久三は声をかけた。
「……ありがとうございます」
これまでのやり取りを聞かれていたことに気づいたらしいおはなは、やや気まずそうな面持ちで俯き、店に上がる。
「おはな!」と、おはなのお父ちゃんがまだおはなを呼んでいる。
「あの、よろしければ、見て行かれますか」と久三はおはなの家族に訊いた。
「いいの?」
ぱっと、末の妹らしい娘が顔を上げる。
「おすえちゃん、中に入れたって、お饅頭を好きなだけ食べられるわけじゃあないのよ」と、おはなが姉の顔で言う。
ふいに久三は、実家を思い出した。
もう長兄は家を継ぎ、次兄は婿入りしたが、幼い頃が甦る。
久三、久三、と二人とも久三を気にかけ、幾つになっても末子は末子の扱いであった。
江戸へ来て、初めて会った人の家の世話になり、運よく仕事にありつき、飄々とやっていると思っていたが、その実、結構気を張り、忙しかったのかも知れぬ。
目の前にいるこの家族は、そう遠くはない郷を久三に思い出させた。
兄ちゃんたち、元気にしているかな、とふいに心に浮かぶのは、今の兄たちではなく、もっと幼い頃の兄たちであった。
村では、菓子にありつけることは滅多になく、蜜柑や野菜の甘みが子どもの久三にとって嬉しいものだった。
そう考えると、贅沢というか、もう育つ環境が違うと感じるはずのこの家族なのだが、不思議と久三の心をせつなく、そうして温かくする。
翁とご隠居が様子を見にやって来た。
「これはこれは。どうぞどうぞ。もう始まりますぞ。ささ、おはなちゃんは参加者だ。おえんちゃん、おすえちゃんが居ればおはなちゃんも心強いだろう」
そんなふうに言って、翁とご隠居はおはなの一家を促した。
6
そうして、利き饅頭が始まった。
座布団に大きく足を崩して座る者もあれば、きちんと座る者もある。
おはなは端の席で背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬようにし、太もものつけ根と膝の間で指先同士が向き合うように揃え、正座している。
それぞれが目隠しをし、饅頭を食べる。
食べた後にそれをどの店か黙って書きつける。
ここで三分の一ほどが脱落した。
おはなは正解し、残った。
脱落した者は、残念そうにしていたが、一口、二口と食べた後の残りの饅頭を食べ、後ろに下がった。
おはなの残した饅頭は、目ざとく妹のおすえが持って行き、頬張っている。
残った者はさゆを口に含み、再び目隠しをする。
ひとつは口入屋の並びにある饅頭屋のもの、ひとつは翁の行きつけの店のもの、そうして最後のひとつは祭りの日なんかに出店で売り出すものだそうだ。
どの参加者も一つ目、二つ目で頷き、三つ目で首を傾げる。
久三はおはなを見守っていた。
どうか、当るように、と心の内で強く思った。
おはなは三つ目の出店の饅頭は当てたが、一つ目と二つ目との店の名が入れ違い、利き饅頭の勝者になれなかった。
全て当てたのは、長屋の大家と七十を過ぎた婆さんの二人であった。
顔の広さに年の功が勝敗を分けたといったところか。
それでも皆は、出店の饅頭を当てたおはなを讃えていた。
太っ腹のご隠居と翁は、この後仕出し料理を頼み、宴会を始めた。
皆が寛いで楽しんでいる中、おはなの一家は隅の方で皆、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は締めるか軽く開く程度、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらいで正座し、本当に形ばかり料理に手をつけ、すぐに暇を告げる。
久三はおはなの一家を見送った。
その時、余った饅頭の入った箱をこっそり持ち出し、おはなの家族が先に外へ出たのを見計らって、それを渡した。
「利き饅頭では食べた気がしなかったのではないですか。皆さんは向こうで好きなように食べたり飲んだりしていますから、帰ってゆっくりしてください」
おはなは驚いたように目を見開き、久三を見上げた。
「おはなさんが勝てれば、私としては嬉しかったのですが、なかなかそうもいかないものですね。ですが、まだお若いのに難しい出店の饅頭を当てたのだから、私からすると、おはなさんの勝ちでしたよ」
おはなはまじまじと久三を見つめ、それからさっと俯いた。
「出店の饅頭は、昔から、特別なことがあると買ってもらっていたから、よく味を覚えているんです」
「そうでしたか……」
「……では、今日はありがとうございました」
おはなは丁寧に会釈し、店を後にしたのだった。
そんなおはなをずっと見送った久三が店に戻ると、奥の座敷から、「おや、残りの饅頭はどうしたんだい? 私はまだ食べるつもりだったんだけどね」という婆さんの声が聞こえてきた。
7
利き饅頭から、ご縁が生まれた、という話はあっと言う間に広まった。
利き饅頭の後、おはなの家族は口入屋の前を通るたびに久三と言葉を交わすようになり、おはなと久三も自然と距離が縮まった。
久三は、そろそろ翁の家を出て、どこか住まいを探すことを考えていた。当初の予定より、随分と長いこと翁のところで世話になってしまったが、翁は、寧ろ久三が居てくれる方がお商売がやりやすかったと言ってくれ、お前さんさえよければ、うちに間借りのかたちでずっと住んでいてくれて構わないとまで言ってくれたのだった。
だが、さすがにそれは、と久三は長屋の空きを探し始めた。
そんな折、おはなの父が久三を少し借りたいと口入屋に来た。
おはなの父は出店の饅頭を買い、床机に促した。
この日は初夏の祭りがあった。
「うちのおはなは、生まれた時、それはそれはかわいらしくて、花のようで、おはなと付けました。うちは小さな干物屋で、大層な家ではありませんが、妻とともに頑張ってやってきました」
「はい」と久三は頷いた。
おはなの両親や、きちんとしていて、物をはっきり言えるあの家の娘三人を見れば、わかることである。
「こんなことを言うのはどうかと思いますが、うちのおはなと一緒になって、店を継ぐ気はありませんか。あなたのようなできたお人なら、婿養子にと言う家も多いでしょう。それは承知の上ですが、できれば私は本人の希望を叶えてやりたい。もし、嫌でなければ……」
そこまで言ったおはなの父の手を、久三は取った。
「嫌なわけがありません」
おはなの家に行ったことも、もちろん店の様子を見たこともなかった。
けれど、久三に迷いはなかった。
迷えば、必ず後悔するとわかっていた。
8
こうして、久三は干物屋に婿入りした。
仕入れに行くのも、店でのお商売も、すぐに馴染んだ。
家では店のすぐ奥の間をおはなの両親が使い、二階の一間をおはなと、おえん、おすえが使っていた。
だが、久三がおはなと一緒になると、おえん、おすえは二階から、一階の階段下の土間の隣の板の間で寝起きするようになった。
それは申し訳ない。
この家のお嬢さんたちに部屋を譲ってもらうわけにはいかない、と久三は固辞したが、そんなのおはな姉ちゃんが承知するわけないじゃない、とおえんもおすえも口を揃え、おはなは決まり悪そうに俯いていた。
久三は、居住まいを正し、背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらい、脇は締めるか軽く開く程度、足の親指同士が離れぬようにし、正座した。
そうして手をつき、座礼した。
はっとしたようにおはなたちも皆、正座し、座礼したのだった。
9
久三とおはなは、密かに思い合っていたものの、これまで立ち話を軽くする程度の間柄で一緒になった。
まあ、世間ではちらりとお互いの姿だけを確認し、もう祝言という夫婦もあるのだから、そう考えればそこそこに近づいての結婚ではある。
久三はおはながずっと気にかかっていたし、おはなの方でも同じだとわかって嬉しかったが、さあ、いざ一緒に暮らして、三度の飯もほぼ同時となればどうだろうか、と口入屋を出る前夜に思った。
「お前さん、知り合ったばかりの私の家では、存分にくつろいで、飯も食っていたではないか」と翁は言うが、いやいや、ここの翁と飯を食うのと、おはなとでは違うではないか……。まあ、それは黙って、「そうですね」と言っておいた。
しかし、実際におはなと一緒になってみると、不思議なほど、その仲はうまくいく。
三男で末っ子だった久三は、兄二人がよくあやしてくれた記憶からか、おはながなんとなく機嫌が悪かったり、疲れていたりすると、それとなく、言葉をかけたり、店番を代わったりし、それでおはなも落ち着くようで、後でありがとう、と言う。
そうして、おはなは三姉妹の長女だからか、家、店の様子をよく見ていた。久三がなんとはなしに人恋しくなるような時には、背を撫でてくれ、膳に好きなものがあればおはなが自分の分もそっと久三の皿に移してくれる。
互いのそうした些細な気遣いが、大層居心地よく、また代えがたいものになるのにそう時間はかからなかった。
男兄弟だけで育った久三にとっておはなは、妻であり、そうして姉であり妹でもあった。三姉妹のおはなにとっても久三は夫であり、兄であり、弟でもあった。
夏、秋と季節が過ぎ、冬の近づいた家では、火鉢を出し、暖を取る。
階下からは、おはなと義妹たちの楽しそうなおしゃべりが聞こえてくる。
久三は布団の中で早くもうとうとする。階段を上がって来るおはなの足音がし、「あ、もう寝てる」と呟くのがうっすらと聞こえた。
そうして、おはなが久三の布団をかけ直し、顔のすぐ下まで温かくしてくれる。
隣の布団におはなが入る気配が、久三を深い安堵へと導く。お父ちゃん、お母ちゃん、兄ちゃんたちでもない人が隣にいることが、こんなにも安心できるとは、これまで久三は知らなかった。
あの日江戸に出なければ、口入屋の翁に出会わなければ、否、利き饅頭なんて案がなければ……。
あの日、おはなが久三の名を訊ねようとし、声をかけたはいいが勇気が出ず、つい利き饅頭に女子も参加できるのか、と思いつきで言ったことを、久三はまだ知らない。

![[323]お江戸正座15](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)